29 / 55
人喰いつづら(四)
しおりを挟む
大角屋の店主はよほど葛籠に執着しているのか、あるいはお松に未練があるのか、その後も幾度か屋敷を訪れては葛籠の消息を知りたがった。そして仙一郎の返答を聞く度、哀れなほどに肩を落として屋敷を辞し、鳥総松に悲しげな目を注ぎながら去っていく。お凛にはそれがどうにも胸に痛く感じられてならなかった。
「大角屋の旦那様、お気の毒ですよねぇ……」
「お嬢さんに頼まれた手前仕方がない。それに、あんな危ない葛籠は手元にない方がいいに決まってる。私だって胸が痛むんだ。ああ切ない」
毛ほども胸が痛んでいる風もなく、煙管を咥えていた仙一郎がぷかりと煙を吐く。ただ葛籠を返したくないだけなのであろう、とお凛は主を横目で睨んだ。
睦月の半ばを過ぎる頃には、大角屋文斉の様子がおかしい、という噂が耳に届くようになっていた。
ひどく憔悴して夜も眠れず、食事も喉を通らず、頭を抱えているかと思えば表に飛び出し、一人であてどもなく他所をさ迷っているのだという。そのため、大角屋の主は気の病にでも罹ったのか、それとも店に何か深刻な問題が生じたのを隠しているのではあるまいか、などという憶測が飛び交っているらしかった。
「この分だと、文斉さんは本当に病みついちまうかもしれないねぇ」
熱々の汁粉にふうふう息を吹きかけながら、炬燵に入った仙一郎が神妙な顔で言う。お凛は何だか、お松にも、おつたにも、仙一郎にも、無性に腹が立ってきた。
「こんなのはあんまりじゃありませんか。大角屋さんもそのお松とかいう人に情けなんてかけないで、ご番所に訴えてやればいいのに……!」
「私に当たらないでおくれ。そう簡単に割り切れたら苦労しないんだよ、男女の仲ってのは。子供にはわからないだろうねぇ」
憐れみの眼差しを送ってくる青年を取って食いそうな目で睨むと、でもさ、と慌てて仙一郎は話題を変えた。
「葛籠を盗んだそのお松はどう思っているのかねぇ。自分のせいでご店主がすっかり弱っちまってるって聞いたら、気になって仕方がないんじゃないか?」
「さぁ、どうでしょうねぇ。元々手癖が悪いそうですし、お店への忠義なんて持ち合わせていなさそうですし、何とも思わないんじゃありませんか?とっくに江戸から消えているかもしれませんよ」
「おお、怖。本当なら打ち首になる盗みを見逃してくれた恩人を見捨てるってのかい。女は怖いねぇ」
「そうなんですよ。だから旦那様もお気をつけ下さいね。怖ぁい女中が料理に何を入れるか分かったもんじゃありませんからね」
途端に餅を噛んでいた仙一郎が、ぐふっ、と喉を鳴らし、半纏の上から胸を叩いて身悶えする。
「──正月早々死ぬかと思った……」涙目を見開いてぜぇぜぇ喘ぐと、仙一郎はぐいと童顔をしかめて言った。
「わかった、わかった。このまま文斉さんを放っておくのも後生が悪い。ひとつ、そのお松もお前のように非情な女中なのかどうか、賭けをしてみようじゃないか」
「え?」
訝しげに首を傾げるお凛に、主は妙に楽しげな笑みを浮かべて見せた。
「そろそろ頃合いだろう。そのお松って女中に、会いに行ってみるとしようか」
***
江戸の水運物流の中心地である日本橋小網町一帯は、廻船問屋を始め多くの問屋が軒を連ね、日本橋川沿いの小網河岸には白壁の土蔵がずらりと立ち並んでいる。睦月の澄み渡った薄青い空の下、「小網町河岸三十六蔵」と呼ばれるその土蔵を背景に、大小様々な船がひしめきながら川面を行き交う様は壮観だ。小網河岸に沿って広がる小網町二丁目の表通りは、醤油樽を積み上げた大八や大きな荷を背中に負った商人や棒手振りの姿で活気にあふれ、耳朶が切れそうに冴えた朝の空気まで熱を帯びて感じられる。その通りの半ばに位置する大角屋には、矩に大の字を染め抜いた屋号も鮮やかな暖簾が軒下に翻り、堂々たる店構えがひときわ目を引いた。
「……お店に伺うんじゃないんですか?」
賑わう大通りを挟んだ反対側に立ち、大角屋の店先を眺めて一向に動こうとしない仙一郎にお凛は尋ねた。
「お前ねぇ、お松が臆面もなく、のこのこ店に現れると思うのかい?」
小馬鹿にしたように青年が見下ろすので、脛を蹴ってやろうかしらと思いながら唇をへの字にした。
「じゃあ、どうしてこんなところにいるんですか?お店には来ないんでしょう?」
「ここに来るとは言っていない。ま、何日かここに通うつもりでいないといけないかもわからないが」
謎かけのようなことを言って、縮緬の胴着に結城紬の長着、真綿を入れた古渡唐桟の羽織という鯔背な風采の青年は、「おお寒」と白い息を吐きながら往来に目を凝らしている。
一体どういうことなのだ。お凛はわけがわからぬまま、仕方なく仙一郎の真似をして埃っぽい通りを見回した。
「──お、あれかな?」
仙一郎の声に、お凛は慌てて主の視線を辿った。大角屋の暖簾をくぐり、表に出てきた女の姿があった。
「……あれは、おつた様じゃありませんか」
渋い鮫小紋に若々しい弁慶格子の帯という出で立ちで、大角屋の長女のおつたが雑踏に紛れて歩いていくのが見える。女中も連れず、一人であるらしい。
「一人ってのが、怪しい」
舌なめずりしながらそうごちると、仙一郎は「行くぞ」とお凛を促して歩き出した。
え、え、と戸惑うお凛にお構いなしに、するすると人波を縫っていく。おつたの後をつけてどうするというんだろうか。
仙一郎の背中を追う内に、通りを北上し、思案橋の袂に出た。橋を渡るのかと思いきやおつたは右に折れ、かつお河岸を左手に見ながら少し歩いてまた小網町へ戻り、稲荷堀と呼ばれる幅八間ほどの入堀に沿って進む。この細い堀の右岸には酒井雅楽頭の中屋敷の白壁が伸びている。左岸にはいくつかの商家が軒を連ねているが、残りは武家屋敷ばかりで人通りは嘘のように疎らになった。
ゆらゆらと淀んだ水が揺れる堀の側を、脇目も振らずに進んでいたおつたは、やがて磐城平藩安藤家中屋敷の北端に位置する小網稲荷の雑木林にさしかかった。床机をひとつだけ置いて、手持ち無沙汰な風に老人が煙管を咥えている水茶屋が、鳥居の脇にぽつんと立つ。その小さな稲荷の前でおつたは一瞬足を止め、素早く左右を見回した。途端、仙一郎がお凛の襟首を掴むなり、側の店の暖簾の陰にひょいと隠れた。おつたに見つかりはしなかっただろうか。どきどきしながら息を潜めていると、やがて仙一郎が暖簾の陰から出て行った。
続いてみれば、おつたの姿は通りになかった。稲荷に入っていったらしい。
行くぞ、と目で促す主と共に燻んだような杉の緑に被われた境内に足を踏み入れると、森閑とした参道の石畳を踏みながら、足早に歩いていくおつたの後ろ姿が目に入った。
おつたが石畳を逸れて、本殿の横手の木立へと分け入っていく。そうっと近づいていくと、おつたの前に、もう一人、女が立っているのが見えた。
吹き流しにした手ぬぐいで頭を被っているが、遠目からもはっと目を引くような美貌が見て取れた。
……まさか。
思わず仙一郎を見上げると、青年は無邪気に目を光らせ、興味津々の顔で二人の女を凝視している。
二人は少しの間何事かを熱心に話し込んでいたが、やがておつたはもう一人の女の腕をやさしく叩くと、くるりと踵を返してこちらへ戻ってきた。お凛と仙一郎は慌てて木陰に身を潜め、娘が通り過ぎていくのを息を殺して見送った。
砂利を踏む小さな足音が遠ざかり、さわさわと木枯らしに枝を揺らす木々の音だけが耳を撫でる。
と、仙一郎がすうっと動いた。
木立の奥に佇んでいる女の前にゆらりと立つと、はっと硬直する女に向かってにこりと笑う。
「こいつはどうも。お松さんですか。ここまで来るなんて、やっぱり主思いなんですねぇ。見ろお凛、お松さんはお前みたいに血も涙もない女中じゃないぞ」
得意気に胸を張る主と呆気に取られているお凛を、女はぽかんとして見比べていた。
「お松さんが世にも珍しい葛籠を盗んだと聞いたもんで、そんな女傑にぜひお目にかかりたいもんだと、実はずうっとうずうずしていたんですよ」
「──何をおっしゃってるのか、さっぱり。あんた十手持ちか何か?葛籠なんぞ知りませんよ」
鋭く両目を光らせて警戒するお松に、仙一郎は軽薄な笑顔を浮かべて見せる。
「いやだなぁ、賢くて美人で手癖も口も悪い女中って、あなたなんでしょう? 見りゃわかりますって」
「何言いやがるんだ、このすっとこどっこい!ふざけたことを抜かすと舌を引っこ抜くよ、この青瓢箪!」
気色ばんで女が罵った途端、仙一郎が褒め言葉を浴びせられた犬のように目に喜色を浮かべた。
「うわぁ、いいですねぇ。癖になりそう。あ、もしやご店主もこれが癖になったとか?もっと罵ってくれませんか?ほらほら」
うっ、と女が言葉に詰まり、こいつ何なの、とお凛に苛立たしげな視線を振ってくる。お察しします、と目で頷き、「旦那様、気色悪いこと言っていないで下さいよ」とお凛が白い目で睨むと、仙一郎は我に返って咳払いした。
「で……先ほどは、どうして大角屋さんのお嬢さんと立ち話なんぞしてたんです?随分親しげでしたねぇ。ご店主が憔悴しきっていらっしゃると聞いて、ご様子を伺いにきたんですか。でも変ですね、ご店主を裏切ったはずのあなたが、どうしてそんなことを気にかけるんです?」
女の瞳がすっと固くなる。黙り込んだお松に、仙一郎が無邪気に畳み掛けた。
「……あっ!もしや、今度のことはおつたさんと仲良く共謀して仕組んだ狂言だとか?」
えっ、とお凛が息を飲むと、お松が鋭く視線を上げた。束の間の沈黙を、杉の梢を掠める風のひゅうひゅうという侘しい音が埋める。
「……そんなことあるはずないでしょう、阿呆らしい。あたしは手癖の悪い女なんですよ。あんた一体……」
「金目のもの目当てなら、もう少し高価なものを盗めばよかったのに。わざわざあんな葛籠を盗んだのには、何か理由があるんじゃありませんか?」
「理由なんざありゃしませんてば。金目のものが入っているもんだと思ったんですよ」
「でもあの葛籠、空っぽでしたよ?」
一瞬の間を置いて、お松が何かを覚ったように血相を変え、表情を凍らせた。「……あんた……」
「あ、申し遅れました。私、木場の通称「あやかし屋敷」の主、仙一郎と申します。あなたが妙円寺に預けた葛籠ね、今私が預かっているんですよ。葛籠がやたらと餌をねだるので面倒見きれんと、和尚さんがすっかり困じ果ててしまいましてねぇ」
唇をふるわせて女が絶句する。面が割れ落ちたかのように、頑なだったお松の双眸に様々な感情が渦を巻く。木枯らしが手ぬぐいをはたはた揺らし、鬢のほつれ髪が白い頬に乱れる様は、胸が衝かれるように美しかった。
「文斉さんはねぇ、そりゃあ意気消沈なすってましたよ。もう見ちゃいられないくらいで。葛籠が盗まれたせいなんですかね。それとも……あなたが姿を消したせいなんでしょうかね?」
杉林がざわざわと鳴る。まるで胸騒ぎのように、その音は高くなったり低くなったりしながら、いつまでもお松の周囲を駆け巡っているようだった。
「大角屋の旦那様、お気の毒ですよねぇ……」
「お嬢さんに頼まれた手前仕方がない。それに、あんな危ない葛籠は手元にない方がいいに決まってる。私だって胸が痛むんだ。ああ切ない」
毛ほども胸が痛んでいる風もなく、煙管を咥えていた仙一郎がぷかりと煙を吐く。ただ葛籠を返したくないだけなのであろう、とお凛は主を横目で睨んだ。
睦月の半ばを過ぎる頃には、大角屋文斉の様子がおかしい、という噂が耳に届くようになっていた。
ひどく憔悴して夜も眠れず、食事も喉を通らず、頭を抱えているかと思えば表に飛び出し、一人であてどもなく他所をさ迷っているのだという。そのため、大角屋の主は気の病にでも罹ったのか、それとも店に何か深刻な問題が生じたのを隠しているのではあるまいか、などという憶測が飛び交っているらしかった。
「この分だと、文斉さんは本当に病みついちまうかもしれないねぇ」
熱々の汁粉にふうふう息を吹きかけながら、炬燵に入った仙一郎が神妙な顔で言う。お凛は何だか、お松にも、おつたにも、仙一郎にも、無性に腹が立ってきた。
「こんなのはあんまりじゃありませんか。大角屋さんもそのお松とかいう人に情けなんてかけないで、ご番所に訴えてやればいいのに……!」
「私に当たらないでおくれ。そう簡単に割り切れたら苦労しないんだよ、男女の仲ってのは。子供にはわからないだろうねぇ」
憐れみの眼差しを送ってくる青年を取って食いそうな目で睨むと、でもさ、と慌てて仙一郎は話題を変えた。
「葛籠を盗んだそのお松はどう思っているのかねぇ。自分のせいでご店主がすっかり弱っちまってるって聞いたら、気になって仕方がないんじゃないか?」
「さぁ、どうでしょうねぇ。元々手癖が悪いそうですし、お店への忠義なんて持ち合わせていなさそうですし、何とも思わないんじゃありませんか?とっくに江戸から消えているかもしれませんよ」
「おお、怖。本当なら打ち首になる盗みを見逃してくれた恩人を見捨てるってのかい。女は怖いねぇ」
「そうなんですよ。だから旦那様もお気をつけ下さいね。怖ぁい女中が料理に何を入れるか分かったもんじゃありませんからね」
途端に餅を噛んでいた仙一郎が、ぐふっ、と喉を鳴らし、半纏の上から胸を叩いて身悶えする。
「──正月早々死ぬかと思った……」涙目を見開いてぜぇぜぇ喘ぐと、仙一郎はぐいと童顔をしかめて言った。
「わかった、わかった。このまま文斉さんを放っておくのも後生が悪い。ひとつ、そのお松もお前のように非情な女中なのかどうか、賭けをしてみようじゃないか」
「え?」
訝しげに首を傾げるお凛に、主は妙に楽しげな笑みを浮かべて見せた。
「そろそろ頃合いだろう。そのお松って女中に、会いに行ってみるとしようか」
***
江戸の水運物流の中心地である日本橋小網町一帯は、廻船問屋を始め多くの問屋が軒を連ね、日本橋川沿いの小網河岸には白壁の土蔵がずらりと立ち並んでいる。睦月の澄み渡った薄青い空の下、「小網町河岸三十六蔵」と呼ばれるその土蔵を背景に、大小様々な船がひしめきながら川面を行き交う様は壮観だ。小網河岸に沿って広がる小網町二丁目の表通りは、醤油樽を積み上げた大八や大きな荷を背中に負った商人や棒手振りの姿で活気にあふれ、耳朶が切れそうに冴えた朝の空気まで熱を帯びて感じられる。その通りの半ばに位置する大角屋には、矩に大の字を染め抜いた屋号も鮮やかな暖簾が軒下に翻り、堂々たる店構えがひときわ目を引いた。
「……お店に伺うんじゃないんですか?」
賑わう大通りを挟んだ反対側に立ち、大角屋の店先を眺めて一向に動こうとしない仙一郎にお凛は尋ねた。
「お前ねぇ、お松が臆面もなく、のこのこ店に現れると思うのかい?」
小馬鹿にしたように青年が見下ろすので、脛を蹴ってやろうかしらと思いながら唇をへの字にした。
「じゃあ、どうしてこんなところにいるんですか?お店には来ないんでしょう?」
「ここに来るとは言っていない。ま、何日かここに通うつもりでいないといけないかもわからないが」
謎かけのようなことを言って、縮緬の胴着に結城紬の長着、真綿を入れた古渡唐桟の羽織という鯔背な風采の青年は、「おお寒」と白い息を吐きながら往来に目を凝らしている。
一体どういうことなのだ。お凛はわけがわからぬまま、仕方なく仙一郎の真似をして埃っぽい通りを見回した。
「──お、あれかな?」
仙一郎の声に、お凛は慌てて主の視線を辿った。大角屋の暖簾をくぐり、表に出てきた女の姿があった。
「……あれは、おつた様じゃありませんか」
渋い鮫小紋に若々しい弁慶格子の帯という出で立ちで、大角屋の長女のおつたが雑踏に紛れて歩いていくのが見える。女中も連れず、一人であるらしい。
「一人ってのが、怪しい」
舌なめずりしながらそうごちると、仙一郎は「行くぞ」とお凛を促して歩き出した。
え、え、と戸惑うお凛にお構いなしに、するすると人波を縫っていく。おつたの後をつけてどうするというんだろうか。
仙一郎の背中を追う内に、通りを北上し、思案橋の袂に出た。橋を渡るのかと思いきやおつたは右に折れ、かつお河岸を左手に見ながら少し歩いてまた小網町へ戻り、稲荷堀と呼ばれる幅八間ほどの入堀に沿って進む。この細い堀の右岸には酒井雅楽頭の中屋敷の白壁が伸びている。左岸にはいくつかの商家が軒を連ねているが、残りは武家屋敷ばかりで人通りは嘘のように疎らになった。
ゆらゆらと淀んだ水が揺れる堀の側を、脇目も振らずに進んでいたおつたは、やがて磐城平藩安藤家中屋敷の北端に位置する小網稲荷の雑木林にさしかかった。床机をひとつだけ置いて、手持ち無沙汰な風に老人が煙管を咥えている水茶屋が、鳥居の脇にぽつんと立つ。その小さな稲荷の前でおつたは一瞬足を止め、素早く左右を見回した。途端、仙一郎がお凛の襟首を掴むなり、側の店の暖簾の陰にひょいと隠れた。おつたに見つかりはしなかっただろうか。どきどきしながら息を潜めていると、やがて仙一郎が暖簾の陰から出て行った。
続いてみれば、おつたの姿は通りになかった。稲荷に入っていったらしい。
行くぞ、と目で促す主と共に燻んだような杉の緑に被われた境内に足を踏み入れると、森閑とした参道の石畳を踏みながら、足早に歩いていくおつたの後ろ姿が目に入った。
おつたが石畳を逸れて、本殿の横手の木立へと分け入っていく。そうっと近づいていくと、おつたの前に、もう一人、女が立っているのが見えた。
吹き流しにした手ぬぐいで頭を被っているが、遠目からもはっと目を引くような美貌が見て取れた。
……まさか。
思わず仙一郎を見上げると、青年は無邪気に目を光らせ、興味津々の顔で二人の女を凝視している。
二人は少しの間何事かを熱心に話し込んでいたが、やがておつたはもう一人の女の腕をやさしく叩くと、くるりと踵を返してこちらへ戻ってきた。お凛と仙一郎は慌てて木陰に身を潜め、娘が通り過ぎていくのを息を殺して見送った。
砂利を踏む小さな足音が遠ざかり、さわさわと木枯らしに枝を揺らす木々の音だけが耳を撫でる。
と、仙一郎がすうっと動いた。
木立の奥に佇んでいる女の前にゆらりと立つと、はっと硬直する女に向かってにこりと笑う。
「こいつはどうも。お松さんですか。ここまで来るなんて、やっぱり主思いなんですねぇ。見ろお凛、お松さんはお前みたいに血も涙もない女中じゃないぞ」
得意気に胸を張る主と呆気に取られているお凛を、女はぽかんとして見比べていた。
「お松さんが世にも珍しい葛籠を盗んだと聞いたもんで、そんな女傑にぜひお目にかかりたいもんだと、実はずうっとうずうずしていたんですよ」
「──何をおっしゃってるのか、さっぱり。あんた十手持ちか何か?葛籠なんぞ知りませんよ」
鋭く両目を光らせて警戒するお松に、仙一郎は軽薄な笑顔を浮かべて見せる。
「いやだなぁ、賢くて美人で手癖も口も悪い女中って、あなたなんでしょう? 見りゃわかりますって」
「何言いやがるんだ、このすっとこどっこい!ふざけたことを抜かすと舌を引っこ抜くよ、この青瓢箪!」
気色ばんで女が罵った途端、仙一郎が褒め言葉を浴びせられた犬のように目に喜色を浮かべた。
「うわぁ、いいですねぇ。癖になりそう。あ、もしやご店主もこれが癖になったとか?もっと罵ってくれませんか?ほらほら」
うっ、と女が言葉に詰まり、こいつ何なの、とお凛に苛立たしげな視線を振ってくる。お察しします、と目で頷き、「旦那様、気色悪いこと言っていないで下さいよ」とお凛が白い目で睨むと、仙一郎は我に返って咳払いした。
「で……先ほどは、どうして大角屋さんのお嬢さんと立ち話なんぞしてたんです?随分親しげでしたねぇ。ご店主が憔悴しきっていらっしゃると聞いて、ご様子を伺いにきたんですか。でも変ですね、ご店主を裏切ったはずのあなたが、どうしてそんなことを気にかけるんです?」
女の瞳がすっと固くなる。黙り込んだお松に、仙一郎が無邪気に畳み掛けた。
「……あっ!もしや、今度のことはおつたさんと仲良く共謀して仕組んだ狂言だとか?」
えっ、とお凛が息を飲むと、お松が鋭く視線を上げた。束の間の沈黙を、杉の梢を掠める風のひゅうひゅうという侘しい音が埋める。
「……そんなことあるはずないでしょう、阿呆らしい。あたしは手癖の悪い女なんですよ。あんた一体……」
「金目のもの目当てなら、もう少し高価なものを盗めばよかったのに。わざわざあんな葛籠を盗んだのには、何か理由があるんじゃありませんか?」
「理由なんざありゃしませんてば。金目のものが入っているもんだと思ったんですよ」
「でもあの葛籠、空っぽでしたよ?」
一瞬の間を置いて、お松が何かを覚ったように血相を変え、表情を凍らせた。「……あんた……」
「あ、申し遅れました。私、木場の通称「あやかし屋敷」の主、仙一郎と申します。あなたが妙円寺に預けた葛籠ね、今私が預かっているんですよ。葛籠がやたらと餌をねだるので面倒見きれんと、和尚さんがすっかり困じ果ててしまいましてねぇ」
唇をふるわせて女が絶句する。面が割れ落ちたかのように、頑なだったお松の双眸に様々な感情が渦を巻く。木枯らしが手ぬぐいをはたはた揺らし、鬢のほつれ髪が白い頬に乱れる様は、胸が衝かれるように美しかった。
「文斉さんはねぇ、そりゃあ意気消沈なすってましたよ。もう見ちゃいられないくらいで。葛籠が盗まれたせいなんですかね。それとも……あなたが姿を消したせいなんでしょうかね?」
杉林がざわざわと鳴る。まるで胸騒ぎのように、その音は高くなったり低くなったりしながら、いつまでもお松の周囲を駆け巡っているようだった。
1
お気に入りに追加
88
あなたにおすすめの小説

夜珠あやかし手帖 ろくろくび
井田いづ
歴史・時代
あなたのことを、首を長くしてお待ちしておりましたのに──。
+++
今も昔も世間には妖怪譚がありふれているように、この辻にもまた不思議な噂が立っていた。曰く、そこには辻斬りの妖がいるのだと──。
団子屋の娘たまはうっかり辻斬り現場を見てしまった晩から、おかしな事件に巻き込まれていく。
町娘たまと妖斬り夜四郎の妖退治譚、ここに開幕!
(二作目→ https://www.alphapolis.co.jp/novel/284186508/398634218)

抜け忍料理屋ねこまんま
JUN
歴史・時代
里を抜けた忍者は、抜け忍として追われる事になる。久磨川衆から逃げ出した忍者、疾風、八雲、狭霧。彼らは遠く離れた地で新しい生活を始めるが、周囲では色々と問題が持ち上がる。目立ってはいけないと、影から解決を図って平穏な毎日を送る兄弟だが、このまま無事に暮らしていけるのだろうか……?

葉桜よ、もう一度 【完結】
五月雨輝
歴史・時代
【第9回歴史・時代小説大賞特別賞受賞作】北の小藩の青年藩士、黒須新九郎は、女中のりよに密かに心を惹かれながら、真面目に職務をこなす日々を送っていた。だが、ある日突然、新九郎は藩の産物を横領して抜け売りしたとの無実の嫌疑をかけられ、切腹寸前にまで追い込まれてしまう。新九郎は自らの嫌疑を晴らすべく奔走するが、それは藩を大きく揺るがす巨大な陰謀と哀しい恋の始まりであった。
謀略と裏切り、友情と恋情が交錯し、武士の道と人の想いの狭間で新九郎は疾走する。

裏長屋の若殿、限られた自由を満喫する
克全
歴史・時代
貧乏人が肩を寄せ合って暮らす聖天長屋に徳田新之丞と名乗る人品卑しからぬ若侍がいた。月のうち数日しか長屋にいないのだが、いる時には自ら竈で米を炊き七輪で魚を焼く小まめな男だった。

西涼女侠伝
水城洋臣
歴史・時代
無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超
舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。
役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。
家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。
ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。
荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。
主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。
三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)
涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

忍者同心 服部文蔵
大澤伝兵衛
歴史・時代
八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。
服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。
忍者同心の誕生である。
だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。
それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
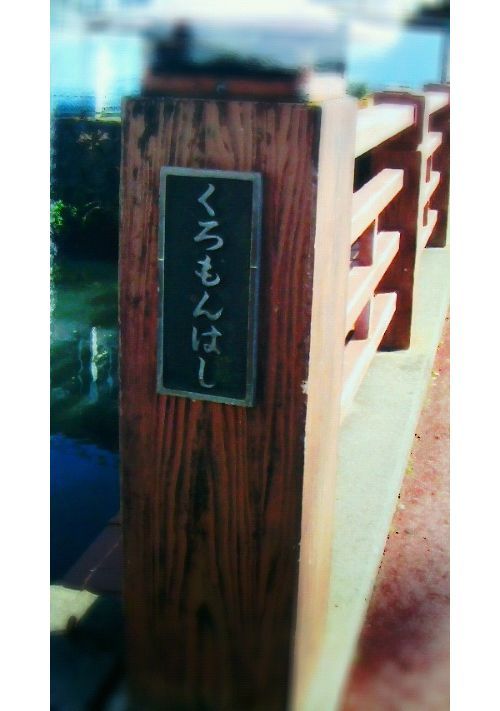
肥後の春を待ち望む
尾方佐羽
歴史・時代
秀吉の天下統一が目前になった天正の頃、肥後(熊本)の国主になった佐々成政に対して国人たちが次から次へと反旗を翻した。それを先導した国人の筆頭格が隈部親永(くまべちかなが)である。彼はなぜ、島津も退くほどの強大な敵に立ち向かったのか。国人たちはどのように戦ったのか。そして、九州人ながら秀吉に従い国人衆とあいまみえることになった若き立花統虎(宗茂)の胸中は……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















