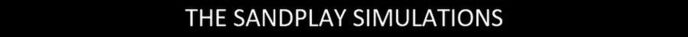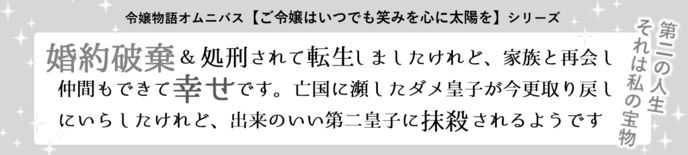25 / 35
Simulation Main thread
八、心配事
しおりを挟む「もうだめだな……」
ぼうっとする頭の先で、藤村と金森、そしてアリマが話すのが聞こえた。
「お許しください」
「なんだ、アリマ」
「ゼロ様からユタになにか言伝はございませんか?」
「ない。今日ユタの容体をお伝えしてみるが、ここしばらくすっかりお心が離れたご様子。期待するだけ無駄であろう」
「しかし……」
「病を他の者にうつしてはならぬ。速やかに部屋を移せ」
北の隅の薄暗い部屋にひとり移された。
(僕、どうなるの……?)
コミカとタシホは早く元気になれと言ってくれたが、すぐに部屋を去っていった。自分の身は自分で守るのが御用郎の鉄則なのだ。ここでは怪我をしても病になっても、めったに医者に診てもらえない。弱いものは種を残す価値がなく、代わりはいくらでもいるからだ。
(そういえば……、ヒノリ様が寝込んでいるという話だったけれど、どうなったんだろう……)
同じ立場になってふいに思い出された。御寵郎ではあるが、だがゼロに見放されたらユタにはなんの後ろ盾もない。ヒノリは高官相手の上級の御用郎。全ての女たちから見放されるという事はまずあるまい。同じ病人でも、こうなってみるといかに自分の立場が危ういかがわかる。
(例え、病が治ったとしても、ゼロ様はもう僕を御呼びになってはくださらないんだ……)
そう思うと、ひたすら胸が切なく、涙が止まらなかった。
下級官吏が薬と水と粥を持って来てくれたが、ただ置いていくだけで、世話をしてくれるという事はなかった。宿にいたときならば、マナホがユタの世話を焼き、マナホが病気や怪我をしたときはユタがその世話を焼いた。それが思い出されてますます心細さが胸に突いた。
(マナホ……)
泣きながらその姿に心の内で呼びかけ続けている間に、ユタは眠っていた。熱っぽい頭の中で、マナホの夢を見た。
「ユタ、起きろ、ユタ」
はっ、と目を覚ますと、ユタを見下ろす神々しい顔があった。
(ゼロ様……)
「呆れたやつだ。薬も飲んでいないではないか。生きるつもりもないのか、お前は」
「……ゼロ様、どうして……」
見ると、ゼロの後ろにはなにやら薬箱を抱えた技官を筆頭に、藤村、金森、会原などの官吏たちがぞろりと控えていた。
「医者を連れてきた。ちゃんと休めばすぐ良くなる」
医者らしき官吏がユタに薬の入った椀を差し出した。椀を受け取り飲み干すのを見届けた後、ゼロが静かな目でユタの顔色を見つめた。
「うわさは聞いているぞ。食べていないそうだな」
(そんなことより、ゼロ様が……ゼロ様が会いに来てくださった……)
自然と涙でにじむ目をこすった。
「なにを泣いている。これほど手間のかかるお前に関わったのは、わたしの間違いだったな」
涙目でゼロを見上げると、凪いだ瞳がまっすぐに返ってきた。その視線を受けるだけで、ユタの心は満たされるようだった。
「……もうお会いになってはくれないのかと……」
「ああ、もう会うつもりはなかった」
「え……」
やはりアリマの言う通りなのか。ユタの心は激しく揺れた。
「ぼ、僕、なにがいけなかったんでしょうか……?」
じっと黙って見ていたかと思うと、突然ゼロが人払いをさせた。ふたりきりになったところで、ゼロは改めてため息をついた。
「お前ほど愚かな者を、宮に上げようなどと、マナホはよくも考えたものだ」
「マナホ……?」
「お前、歴史を学びたいんじゃなかったのか?」
「え……」
「いろはを覚えて、文を寄こして来たまではいい。それ以降、ちっとも進まず、指南役が匙を投げたというではないか。三日と開けずに送ってくる文にも、その成果は一向に見られない。ただ会いたい、会いたいと、そればかり。なんのためにお前はここに残ったのだ。恋文を習うためか。あほらしい」
改めて自分のしたことを聞いたからには、それはもう、ユタからはぐうの音も出なかった。
「つまらぬ者と関わってしまったものだ。わたしもそれほど暇ではない。病が治ったら宿に帰れ」
「……そんな、嫌です……!」
「ここに残ってもいいが、お前の行く先など知れている。戻ったほうがましだぞ」
「ぼ、僕はゼロ様のお側にいたいんです……っ」
「用のない者をそばに置いておく気はない」
「僕、ちゃんとやります! ちゃんと学びますから!」
子どもがすがるような目のユタに、ゼロは静かに言った。
「わたしはお前が歴史を知りたいと言ったとき、珍しいことがあるものだと思った。この国の仕組みにただ埋もれるのは簡単だ。お前が歴史を知り、なにを感じなにを考えるのか、わたしは少しばかりそれに興味を引かれただけだ。だが、お前も他の男たちと同じであったな。強い女の庇護が欲しいだけのつまらぬ者だ」
(つまらない……)
ユタは次第に冷静さを取り戻し始めていた。
ゼロの温情をマナホのそれに重ね合わせすぎていたのかもしれない。ユタが信愛を寄せるのと同じように、ゼロも自分にそうした気持ちを寄せてくれるのではないかと。そんなことはあるはずない。わかっていたはずなのに。どうしてこんな大それたことを思ってしまったんだろう。ユタにもようやくそれがわかった。
(好きなんだ……、ゼロ様が好きだ……)
宿にいたときユタはマナホを愛していた。その体を許しあいたいと思うほどに。今は、ゼロに近づきたいと感じている。自分から決して触れることは許されないとわかっていても、心と体がゼロと触れ合いたいと叫んでいる。
わかっている。ゼロは少しもそんなことを思ってもいない。ただ、たまたま関わってしまった哀れな滓に少しばかりの情をかけてやっただけなのだ。わずかな興味と、息抜きと、たまたま乗り掛かってしまった偶然によって。
それを認めると、ユタの心は急に苦しかった。
「……ゼロ様、僕がちゃんと学んだら、お側においてくれますか……?」
「人のために歴史を学ぶのか? よりよく生きるためにお前は歴史を学ぶのではなかったのか」
ゼロの言うとおりだった。ゼロは初めから、そのつもりでユタに居場所を与えてくれたのだ。それを勝手に高望みしてしまったのは、自分なのだ。歴史のことを忘れたわけではなかったが、ユタの中でゼロの存在がそれ以上に大きくなっていた。
それゆえに、食い違う互いの想いの向きを思い、縮まることのない距離を思うと、涙が堪えることができなかった。
「……でも、好きな人のお側にいたいと思うのはいけないことですか……?」
「……」
ゼロがふうと息をついた。そのため息にすら淡い色がついているのではないかと思えて、ユタはすがりつきたくなった。
「お前は本当に愚かだな」
軟弱なこの青年に関わってしまったばかりに、ゼロは些末だが余計な心配事を増やしてしまっていた。であれば、最初からユタが犯されるのを黙って見過ごしておけばよかったのだが、それはあの時できなかった。
(わたしも、ばかなことをしてしまった……)
一度でも目にかけてしまうと、途中で放っておくことができないのがゼロの性格だった。
送られてくるあの拙い文見て、こいつはだめだと見限りをつけたつもりだった。それなのに、物も食べずに病で寝込んだらしいと聞かされ、自分の不行き届きで宮へ連れて来てしまったという責任感がうずいた。こうなることは予想に容易かったはずだ。右も左もわからぬ宮暮らし、頼りにできる者は多くなく、足場はいつでも軟弱で、止めに、この滓児の若者は心の支えを失ったばかり。もはや泥船の世話を焼かねば、自分の気が治まらない。沈むのを見たくないのだ。この犬のような哀れな目が、愚かしいまでの純朴さが、母性なのか庇護欲なのかをくすぐったのだろうか。
「好きだからという理由だけで、好きな者のそばにいられるところでない」
(そして、哀れだからという理由だけで、手を差し伸べていいところでもないのだ……)
「どうしたらゼロ様のお側にいられますか? 僕、ゼロ様がお喜びになるように頑張りますから……」
「いや、もういい」
はっとした。決別を突きつけられるのだと思うと、ユタは胸がつぶれそうだった。しかし、思いもよらず優しい手がユタの頬をぬぐった。
「わたしがここにいる限り、お前の面倒は見る。だから、よく学べ」
「えっ……」
「わたしの側にいるために学ぶんじゃない。自分のために学ぶんだ。そういう者でなければ、わたしは目にかけたくない。わかったか?」
「ゼロ様」
「わたしは永遠にここにいるわけではない。わたしがいなくても、歴史を知り、より良く生きることを学ばなければ、お前は生きていけない。言っていることがわかるか?」
ユタはこくこくと頭を振ってうなづいた。
「……その様子、わかってないな。もう一度言うぞ?」
「学び続ければ、ゼロ様のお側にいていいということですね?」
ゼロは口を開きかけたが、これ以上言っても無駄かもしれない、と思いいたって口を閉じた。
(なにをどう言っても、わたしはこれの面倒を見るしかないのだ……、自分で蒔いた種だな……)
「ともかく、早く体を治せ。ちゃんと食べて、良く学べ。そうしたら、また呼んでやる」
「はいっ!」
はきはきと返事をすると、ユタは膳から冷めた粥の器を取って、急ぐように口に入れた。
「そう急くな。今温め直させるから……」
「大丈夫です、急にお腹がすいてきました!」
思わず小さく吹き出してしまった。本当にまるで子どものようだ。
よく考えてみれば、滓児だからこそユタのような性格が育ったのかもしれない。包児なら五歳で一度住み慣れた宮を追われ、不自由な暮らしとその落差に激しい動揺や衝撃を禁じ得ない。そこでは少なからず親しみを寄せていた養育者と引き離されるという苦しみがある。ユタにはそれがなかった。生まれてすぐ宿に捨てられ、マナホという保護者の元で、それが当たり前として育ってきた。血のつながりはなくとも、そのような安定した親子関係を経験したものは、男児の中では極めて少ないはずだ。あるいは、マナホの性格も影響しているのかもしれない。
「げんきんな奴だな」
「はいっ、僕すぐ元気になります!」
「はは……」
声を上げて笑った。耳を立てる犬のようにぴくんとゼロを見た。ユタの口から出たのは直球の言葉だった。
「僕、ゼロ様が好きです」
唐突な告白にゼロは目を見開いた。
「ゼロ様が大好きです」
(そうか……)
ゼロにもわかる気がした。まっすぐに相手の目を見て、心のうちをさらけ出せるその誠、強さ、まっすぐさ。
「マナホはいい親だったんだな……」
「マナホはとてもよくしてくれました。今は、ゼロ様のことが一番大好きです」
「ああ、わかったよ」
思わず、ユタの頭をなでた。愛されて育ったのだ。そうでなければ、こんなふうには育たない。ユタは嬉しそうにゼロの手のぬくもりを味わった。本当は、ゼロの胸に抱きついて、頭をなでてほしい。口にすることはできなかったが、それはゼロにも伝わっている気がした。
こちらもぜひお楽しみください
0
あなたにおすすめの小説

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。


どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる