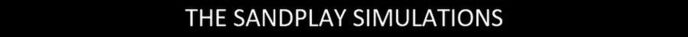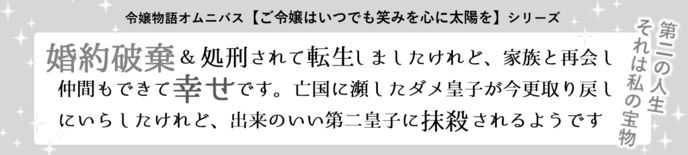22 / 35
Simulation Main thread
五、優しきもの
しおりを挟む部屋に入ると、ゼロはまた書簡を読んでいた。書簡から顔を上げたゼロの顔を見ると、どこかすがりたくなるような気がした。あの夢のせいだろうか。
「うまくいってないらしいな、ユタ」
「……は、はい」
「女が怖いか?」
「……はい……」
「どうする、歴史はもう諦めるか?」
「……あ、あれが人のれきしなのだとしたら、僕はどうしたらいいか……。花も虫も、自然の中にある雌と雄は調和しているように見えるのに、どうして人だけが乱暴なんでしょうか……。それとも、花も虫もそうとは見えないだけで、痛かったり苦しかったりするのでしょうか……」
「ふうむ……」
ゼロは少し考えていたかと思うと、さっと立ち上がった。
「出かけるぞ、ユタ」
厩にやってきた。
鞍にひょいとまたがると、ゼロがユタに手を差し伸べた。
「ほら、乗れ」
「で、でも、あの……」
「遠慮するな」
尻のたくましい立派な栗毛に、国司長官とともに平凡な少年が乗っているさまは、見る者をもれなく驚かせた。当然山室らは激しく反対したが、聞くようなゼロではなかった。
「寄り掛かっていいぞ。離れているより、くっついているほうが馬も楽なんだ。もっとくっつけ。そうだ、よし。では行くぞ」
ゼロがぽんと馬の脇腹を蹴った。
「今日は息抜きだ」
「は、はい……」
初めは緊張したが、言われたように寄り掛かっていたほうが楽だと分かった。なるがままに体を預けた。ゼロの両腕とかすかな香りがユタを包み、背中にはその体温とやわらかな感触を感じる。
(あの膨れた胸だ……)
ユタの脳裏に描かれたのは村木の胸だったが、背中に感じる感触は少しも嫌な気はしなかった。
「見てみろ、ここからだと宮のすべてが見渡せる」
小高い丘から国を見渡した。もちろん、ユタが国土を俯瞰するのは初めてのことだった。
(す、すごい……)
「あれが頂の宮。裾の宮はあれだ。わかるか?」
「は、はい……」
「あの門の向こうが、お前たちの住んでいた宿だ。ここからだとあまり見えないがな」
「はい……」
キュリリリという鳴き声とともに、空を二つの影が走った。
「見ろ、オナガだ」
「あっ……」
「つがいのようだな。今ちょうど繁殖期だ」
「今の鳥、オナガ、と言うんですか? 尾が長いから……?」
「そうらしい」
「へえ……! 見たことはあったけど、初めて名前を知りました」
振り返ったユタの目がきらきらと輝いた。男に生まれた者は、そうしたささいな動植物の名も知らずに死んでいくのだ。
「尾が長いからオナガか……へえ……」
「お前の宿まで行ってみようか」
「え……!」
(うそ、ほんとうに……?)
「どうした、行きたくないのか?」
「い、行きたいです!」
馬は宮を迂回して宿に向かって歩みだした。
一定の振動に体が慣れたころ、ユタはふと感じ続けていた疑問を口にした。
「あの……、ゼロ様はどうして、僕に良くしてくださるのですか?」
「うん? うん――……」
「……」
「乗り掛かった舟だ」
「……どういう意味でしょうか?」
「あと、ちょっとした興味だ」
「きょうみと……、舟……?」
「この国の長に赴任して、図らずもお前に会い、わずかながら心が動かされたということだ。そうしているうちに、どうやら小舟に乗りかかってしまったらしいことに気付いた。引き返してもいいが、せっかくだから行きつく先を見て見ようかとな」
「……」
「言っている意味がわかったか?」
「ところどころわからないところもありますけど、大体は……」
「まあ、あと息抜きだ」
「……ひとつの事柄に、三つも理由があるのですね。すごいです……」
「なにをありがたがってるんだ。わたしの気はいつ変わるかもしれないぞ」
「えと……、つまり、どういうことですか?」
「この国の歴史が知りたいんじゃなかったのか? 少しは字の勉強は進んでいるのか」
「あ、はい! いろはにへとほ、を習いました!」
「ほへと、だろ」
「ほへ……と、へほ、あれ……?」
「……まあいい、よく学べ」
「はっ、はいっ」
馬は止まることなく歩みを続け、方羽区にやってきた。何事かと慌てた役人たちが駆け寄ってくるたび、ゼロはただの散歩だといって追い返した。男たちは驚いたようにユタを見つめ、ゼロにはただただひれ伏した。
「宿はあれか?」
「はい、そうです! 降りてもいいですか?」
「ああいいよ。行っておいで」
いうが否や、ユタは馬を滑り降り、宿に向かって駆け出した。
ぽくぽくとのんびり馬がゼロを宿に運んだころ、宿の中からは、つんざくようなわめき声が聞こえた。
馬から降りずに待っていると、宿の長たちが三人そろって出てきた。馬の脚元に三人が正座し、地に額をつけた。
「なにかあったのか?」
「……」
「応えよ」
「……」
「申してみよ」
「……方羽宿一の長ケムタと申します……。ユタの保護者であったマナホは先日召されました……」
「……そうか……」
うわああ、と悲痛な叫びが外に響いて来る。
「穴の場所はどこだ」
「……」
「応えよ」
「……」
「申せ」
「ご案内いたします……」
「ユタにそこで待つと言ってくれ。正午までに来なければ戻らぬものとする」
「承知いたしました」
マナホの葬られた滓穴で待った。影が真下に落ちてきた。帰ろうと馬の鼻を向けると、その先にユタが立っていた。
「帰るか?」
「はい……」
「そうか、では乗れ」
ユタは真赤に染まった目と鼻を隠しもせず、馬によじ登った。背を丸め、行きのようにゼロに寄り掛かることはしない。精神的な憔悴は見るも明らかだった。
「ユタ、こっちを向いて、わたしにしがみついていろ。そのままでは落馬する」
「……」
しばらくじっとしていたかと思うと、ユタは馬上で向き直り、泣きぬれた顔をゼロに向けた。ユタの手をとると、ゼロは自分の腰にまわした。
「いくぞ」
馬は大門を通り、宮に向かう。
頬に柔らかなふくらみとなにやら甘いような香りが感じられる。男の平たい胸とは違う。春の中にいるような優しく包まれる感触。自然と緩む涙腺に、こらえきれず嗚咽した。
ユタの背中に温い手が添えられ、いたわるようにゆっくり上下した。
「う、うわあ……っ」
たまらず声を上げた。ゼロの細い体に縋りつき、胸に顔を押し当てた。ユタの頭を優しい手がなでた。
(このお方は、なぜこんなに優しいんだろう……なぜこんなに温かいんだろう……)
泣きながら、心地よい安らぎの場に身を浸し、その思いにふけった。
裾の宮につくころ、心はすっかり解き放たれ、ユタは泣きつかれてうとうととさえしていた。
「ユタ、ついたぞ」
見上げると、目の前にゼロの細くて白い首筋があった。
(ゼロ様……)
「ユタの同室の者はいるか、呼んでまいれ」
裾の宮は騒然とした。ゼロが宮を訪ねてきたこと自体が初めてだが、御用郎を共に馬に乗せ、しかもその胸に抱いてかかえるなど、かつて誰も目にしたことがなかった。コミカとタシホが動揺と興奮にせっつかれながら足早にやってきた。
「お前たちがコミカとタシホか? 許す、応えよ」
「は、はい……!」
「ユタを頼む。ゆっくり風呂に入れていたわってやってくれ。しばらくお前たちの任を解く。そばにいてやれ」
「は……はい……!」
「ではまたな、ユタ、元気を出せよ」
ふたりにユタを預け、馬上からゼロが静かな目で見つめていた。
(ゼロ様……)
去っていく背を見ると、体に風が通り抜けていくような気がした。届かないとわかっているのに、その手を伸ばして引き留めたくなる。
(行かないでください)
その思いを声にすることが許されないことは分かっていた。
この出来事は、扇動的な話題として裾の宮を席巻した。御寵郎への目に余る溺愛ぶりは官吏たちのうわさにもなって、こぞってユタをのぞき見しに来るほどだった。とはいえ、そこまで寵愛されるだけの積極的な理由を見出すことはほとんどできなかった。
この数日、館でのんびりとしている三人はユタたっての願いで字の手習いをしていた。
「ユタ。ちと、さが、逆になっているよ」
「あれ、また……」
筆をおき、和紙を変えた。
「まったく、見た目だけで言ったら俺の方が三倍はいい男なんだけどな」
「それをいうなら僕は四倍。女性を喜ばせる技なら多分五倍は上だよ」
「いったい全体、ゼロ様はユタのどこをそんなにお気に召してるんだろうな」
「正直僕にもよくわからない……。舟と、興味と、息抜きって……。でも、気が変わるかもしれないとも言われたよ」
「なあ、ユタ……」
タシホが、じりっと身を寄せた。
「ここだけの話、ゼロ様はどんなことをお求めになるんだ?」
「ああ、ここだけの話」
コミカもずいと身を詰めた。
「ぼ、僕なにも言えないよ。アリマ様になにも言うなって言われているんだ……」
「だから、ここだけの話、俺達だけだって」
「そうだ、そんなに愛されてるなら、僕達にも少し分けてくれ」
その瞬間、ユタの顔がゆでだこのように真赤に染まった。
(あ、愛されて……!)
この数日、ユタは何度も同じような反応を繰り返している。
ゼロのことを考えると、他のことがなにも考えられなくなる。体がかっかとして、胸がざわめき、抱かれたときの柔らかさやぬくもりやにおいがまだここにあるように思えてくる。
マナホを失った悲しさはあるものの、思い浮かべる時間はゼロのそれと比べるとはるかに短くなっていた。
「あーあ、まったくユタはいいな、相思相愛で」
「そうし……?」
「そうだろ? お前はゼロ様をお慕いしてるし、ゼロ様もお前を大切にしてくださる」
「でも、まだ御呼びがかからない……」
「様子を見ているんじゃないのかな。君から文でも書いてみたら?」
「ふみ……」
「せっかく字を覚えたんだから。僕のいい紙を分けてあげるよ」
「なんて書けばいいの……?」
「先日のお礼を申し上げたいって書いたらどう?」
「う、うん……! 書いてみる」
ユタが手紙を送った翌日、ユタに御呼びがかかった。
「ようやく、いろはを覚えたようだな」
「は、はい……」
「どうした、顔が赤いが、熱でもあるんじゃないのか?」
「そ、そんなことありません、大丈夫です!」
ゼロの姿かたち、匂い、声、全てが輝いて感じられた。目の前にするだけで、胸がほわほわと温かく、視線が合う度にうっとりと引き込まれる。自分でも自分がどうしてこんなふうになるのかわからない。そうかと思うと、体の奥が鞠のように弾んで、胸がどきどきと高まって静まらない。なにやら胸の中に小鳥と鞠と猫を合わせて飼っている気分だ。
「せ、先日は……、本当にありがとうございました」
「もう心の整理がついたのか?」
「はい、僕、ここで頑張ります……!」
「そうか」
「はい」
「では、性交指南を再開するか?」
「えっ……」
ユタは目を見開いた。慌てて首を左右に振った。
「お前が望んだことだぞ」
「も、もう、交ぐわいの御指南はいいです……!」
「やはり、懲りたのか」
「僕、もうわかったんです……」
「なにが?」
「女も男も、優しいということがです」
「ほう?」
「ゼロ様は、優しくて、美しい……。マナホも優しかったけれど、ゼロ様は僕にとってはもっと優しくて、とてもきれいで、この世で一番お美しい方です」
次に目を見開いたのはゼロの方だった。ははっ、と、はじかれたように笑った。
「女は怖いものではないと分かったんだな」
「はい」
「そういうことなら、藤村には指南はもういらぬと言っておこう」
(ゼロ様が笑った……! あんなふうにお笑いになるんだ……)
初めて見る笑顔に、心が近づいた気がしてうれしかった。気持ちが高まっていたがゆえに、次の言葉がユタに与えた動揺は大きかった。
「今日はもう帰っていいぞ」
「えっ……?」
「まだなにか用があるのか?」
そう聞かれると、ユタはなにも言えなかった。
(もう? まだお側にいたいのに……)
山室たちの案内で裾の宮に戻る間、ユタはなんども後ろを振り返る。遠ざかっていく頂の宮がはるか遠く感じられた。
(またお会いできる。そんなに先のことじゃない……)
そう言い聞かせながら、心はふわふわとゼロのそばに飛んでいくのであった。
こちらもぜひお楽しみください
0
あなたにおすすめの小説

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。


どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる