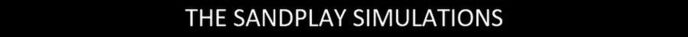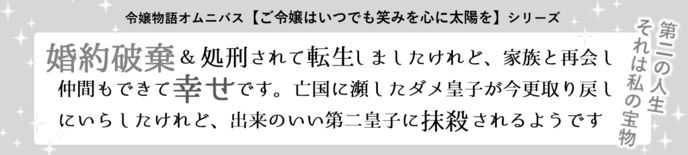7 / 35
Simulation Introduction
六、メイオウ領(6)
しおりを挟むこの世のすべての大地とすべての海をいだく強大なる「居神国」。
居神国はさる惑星における人類の平行世界。
最も近しい例を上げれば、日本国における弥生時代にも似た原始国家である。
大きく違うのは、徹底した女系王が管理する女性優位の社会であること。
政治的権力と社会的優位性を持つこと、また継承できるのは女のみ。
男は子種をもたらすだけの家畜である。……
居神国に属するメイオウ領。
ここに生きるリェンという男がこの物語の主人公である。
「ど、どうして、そうなるのか……。ギョ、ギョク兄さまぁ……」
「本当に覚えが悪いな、ジンは……。またここ、ぬが、めになっているよ。ここはのが、るになっているし」
「ジン、いいかげんにしろっ! お前のせいでちっとも前にすすまないじゃないかよっ!」
ギョクに頼み込んで字を習い始めたリェンとジンであったが、もともとの素質の差なのか、ジンは苦戦しいてた。
一方のリェンは飲み込みが良く、あっという間にひらがなを覚え、今はいくつかの漢字も習い始めていた。
その差が開くほどにジンはいじいじとし、リェンは苛立ちを募らせた。
「どうしてそうなるのだと考える前に覚えてしまったほうが楽だよ。さあ、もう一度写し直してごらん」
「はい……」
始めこそ渋っていたギョクではあったものの、年上のこうということもあって案外と面倒見がいい。
そうなると当然出来の悪いジンの方に手を取られてしまうのであった。
「もういいっ! おれはゲツ兄さまにならう!」
短気なリェンは早々に見切りをつけた。
手習いのための道具を一式包むと、さっさと炊事場を出ていった。
その脇でガイが呆れたように野菜を剥いている。
「リェンも出ていったことだし、ギョク兄さまもジンもそろそろ終わりにしてくれませんかね?」
「ああ、そうだね」
「ま、まってください。あともう少しだけ……。それより、ガイ兄さまもいっしょに習いませんか?
リェン兄さまとやるよりずっとたのしいと思うんです」
「おれはいいよ。字なんてにてもやいても食えないものに時間をついやす気はないね」
同じ"宿"から直接引き上げられたガイではあるが、現実的な性格であるせいか、あるいは料理の仕事のほうが自分に向いていると感じるのか、字を習うことに全く興味が起こらないらしい。
同じく"宿"出身のキョウもあまり字には興味がない。
「それより、ギョクのその硯は高そうだなあ。米俵何俵?」
「さあ……。ミライ様にそんなこと聞かなかったからわかりませんよ」
「ふうん、そうかい」
キョウはいつでも物の出入りや、誰がなにをミライ様にもらったかに目を配っていて、いつもそれは米何俵分だといって価値を計ろうとする。
物の価値というものに強く興味を持っているのがキョウだった。
結局ジンも荷物を引き上げて、自室で練習をすることになった。
リェンはというと、その足でゲツの部屋を訪ねていた。
「ほう、それは殊勝な心掛けだね。いいだろう、教えてあげるよ」
「ありがとうございます!」
ゲツはリェンの書いた手習いを見ると、むふむふとうなづいた。
「いいだろう。そうしたら、お前には音読を薦めよう」
「おんどく……?」
「ああ、文字は自分でももう練習できるだろう。これから漢字を読めるようになるためには、書くより読んで聞くほうがたくさんの文字を早く覚えられるのだ」
「なるほど、そうしたらおれもてがみが書けるようになりますか?」
「ここまで書ければ簡単な手紙はすぐに書けるよ。
だが、読むのと書くのとは少し手合いが違って、漢字の読み方や意味が分からなければ、複雑なことは読み解けないし、伝えたいことのすべてを書き記すこともできないのだよ」
「わかりました。なにから始めたらいいのでしょうか?」
「そうだね……。まずは手紙や歌なんかがいいけれど、わたし個人のものを読ませるわけにはいかないな。
これなんかがいいだろう。これは国史記という書物だ」
「こく、しき……」
「国の、歴史を、記した本という意味だよ」
「くにのれきし……?」
リェンが歴史という言葉を初めて聞いたのも無理はない。
"宿"にいる男たちは、字を持たないのと同時に、伝えるべく歴史も持たないのである。
この居神国で歴史を学び伝えることのできるのは、女たちだけであった。
"種"として奥宮に入った男たちは、そのものの才覚に応じて、字だけでなく歌や歴史、あるいは舞や音楽などを学ぶことが許された。
とはいっても、相応の努力と、それを教えてやろうという奇特な女とのめぐりあわせという運が必要であった。
"種"として優等を誇っていたゲツはミライに引き上げられる前から手紙や歌に励み、引き上げられてからはミライに本をもらっては自分で歴史を学んできているのであった。
「その、れきし、というのはなんでしょうか?」
「それはこの本を知ればわかるよ。わたしが読んであげるから、ここへ来て字を追いながら聞くとといい」
ゲツが寝台に腰掛けると、となりに座るように促したので、リェンはその隣へ腰かけた。
ゲツのそばから高い香が匂う。
自分が使っているものとは違っていた。
ときどきこの匂いをさせているミライが部屋に来ることがある。
少しばかり嫉妬を感じながら、リェンは開かれた本を眺めた。
ゲツが声に出しながら、字を指で追う。
「二神あり。地司るは豊春古米女神なり。天司る天津常照男神あり。
人の世を共に開けんと手を携えん。
神とは、人の世を開いた尊いお方のことだ。め、は女、お、は男のことだ。この国の祖はこの二柱の神様にあるのだ」
「はい……」
「ち、とは大地のこと、てん、とは空のことだ。豊春古米女神は大地を統べる役割を持ち、天津常照男神は空を統べる役割を持っているのだ」
「はい……」
「その別々の役割を持った女神と男神が、互いの手を取って、人の世を開いた、とそう書いてあるのだ。わかるか?」
「はい……」
リェンはこくりとうなづいたが、内心驚いていた。
神という尊い存在がいるということだが、リェンは見たこともなければ聞いたこともない。
いるなら、一体どこにいるのだろうか?
それに、空を持統べる男神とはいかなる存在だろうか?
女が力を持ち強くあるというのは納得ができる。
でも、男にも同じような力があるとは到底信じられない。
実際、現実の男たちは無力で哀れな子種を宿すだけしかできない存在だからだ。
「ア……、アマツトコテルオガミには、そのような力がほんとうにあったのですか?」
「そうだよ。国史記にはっきり書いてある。これは、過去にあった本当のできごとを記録した大切な書物なのだよ」
「す……、すごいですね……」
「続きを読もう」
「はい」
ゲツはゆっくりと国史記を読み砕いてリェンに聞かせた。
リェンは初めて知る歴史という世界に、驚き、また疑い、また感動をした。
文字という記録の中に、過去の真実が込められているというともまた深遠な思いがした。
「トヨハルコツクメガミさまと、アマツトコテルオガミさまのおかげさまで田畑にはコメが、山や海のさちがとれ、国ができていったのですね……?」
「そうだよ。では、今読んだところまでを、今度はお前が読んでご覧。そのあとに紙に書き写してみよう」
「えっ、こ、こんなにたくさんの漢字がありますが……」
「読んで書くを繰り返す事が大事なのだよ。書くときも口に出しながら書き写してみてごらん。
この本がすっかり書き写せたら、きっとそのころには手紙など楽々書けるようになっているだろうし、そればかりか目を閉じていても国史記を諳んじることだってできるようになるだろう」
「……!」
ゲツの言葉にリェンは未来の成長した自分を見て、がぜんやる気を出した。
とはいえ、やる気とは裏腹に、見覚えのない漢字になるといちいち止まってしまうし、しかもそれを細かな線でちまちまと書かねばならないいうのはなかなか根気と集中力のいる作業だった。
ゲツの読んでくれたところまではと思っていたが、耳慣れない言葉や、漢字の複雑な形、あるいは書き順を覚えるのもなかなか難しい。
しかも、筆の扱いも未熟で、とてもではないがうまく写せたというものではなかった。
「ど、どうしてもこんなに小さく書けません……」
「はじめのうちは誰でもそうだよ。でも心配いらない。わたしが最初に習ったときよりうまいくらいだ」
「ほ、ほんとうですか?」
「リェンはきっとすぐに上達する」
「が、がんばりますっ!」
ゲツのいった通り、リェンはめきめきと力をつけていった。
三月後には、ひとりでも国史記を読み進められるまでになり、知らない漢字や意味をゲツに聞けば、自ら進んでその先を写しとれるまでになっていた。
「国の歴史とは、本当に面白いものですね、ゲツ兄さま」
「そうかい? わたしは歴史より歌のほうが好きだけれど、お前は賢いからきっと面白く感じるのだろう」
「賢いだなんて。でもゲツ兄様にそういってもらえるのは嬉しいです。歴史を学んだあと、俺にも歌を教えてくれますか?」
「これ。俺ではなく、わたしといいなさいと教えただろう? 文字を習うということは、同時に礼節を学ぶということなのだよ」
「そ、そうでした……。わたしにも歌を教えてくださるでしょうか?」
「ああ、いいよ。それじゃあ今日はひとつ歌を教えてあげよう」
ところが、リェンには歌の趣というものがさっぱり理解できなかった。
「日差しが温かいので、もうすぐ春だなぁとしみじみ感じいっていることを歌っているのだよ」
「……そんな当たり前なことをなぜわざわざ言葉にして、驚いたようなふりをしているんです?」
「……。リェンは歌には向かないようだね……」
以来ゲツはリェンに歌を教えてくれなくなった。
実際、リェンは心の機微や自然の動きを言葉で現わすよりも、国史記のなかで語られる人類の戦いの歴史のほうがおもしろかった。
現実の男たちは、"宿"に押し込められ無為に過ごしているにもかかわらず、歴史上の男たちは大きな獣を追い、船を作って鯨を取り、荒れた田畑を切り開いて広い田畑を作る。
そして他国の者が攻め入ってくれば、進んで前に出て戦った。
リェンには今の抑圧された男たちの姿よりも、歴史上の男たちの姿のほうが理に適っているように感じられた。
それはさまに、男の本能を刺激されたのであった。
あるとき、ミライのお渡りがあったときに歴史の話を口にしてみた。
「今、ゲツ兄様に国史記を習っております」
「そういえばそんなことをいっていたな。どうだ、面白いか?」
「はい、とても。でも、わたしにはいつも不思議に思うことがあるのです」
「なんだ?」
リェンは目を輝かせた。
「歴史上の男たちはみな血気が盛んでたくましく、国の発展や家族や仲間を守るために進んで血を流して戦います。
察するに、今のように女の兵士ばかりではなく、男の兵士もいたようです。それもたくさん。
現在においてもそのように力の強い者や恐れ知らずの勇気ある男には、兵士として役割を与えてくだされば、きっと、昔と同じように良い働きをするのではないかと思いました。
そうでなくとも"宿"暮らしの男たちは日がなやることもなく、ただ漫然と暮らしております。
兵士として国のために役立てるとあれば、男たちはみな一生懸命になって働くのではないでしょうか?」
手を枕に黙って聞いていたミライがすうっと目を細めた。
にわかに冷たい雰囲気を発せらたのを、リェンはすぐさま感じ取った。
「国史記を学ぶのは良いが、政を考えるのはお前ではない」
「……は……、で、出過ぎたことを、も、申しました……」
ミライは機嫌悪そうにキセルを取って、リェンに火をつけさせた。
キセルといっているが、ここでミライが使っているものはその原型ようなものであり、使い方はほとんど変わらないまでも、形はかなり素朴なものであった。
リェンはひりひりとした空気にあてられて、背筋が冷たくなった。
ミライが少しも目をあわせてくれない。
もはや、自分の人生はこれまでなのではと頭の隅に恐怖が住み着く。
空気をくゆらせ、無言の時間が続く。
ここまでミライが寝台の上で黙っていたことは今まで一度もなかった。
もはや死を申し渡されるまでの猶予に思え、リェンは初めて胃の腑のあたりがきりきりとした。
ミライがようやくキセルを寝台の脇台に戻して、口を開いた。
「お前がそう思うのは、国史記をすべて学んでいないからだろう」
「……え……」
確かにリェンはまだ書の半分も進んではいなかった。
しかも、リェンが好んで読むのは戦いの場面であり、それ以外の部分はさらっただけで詳しい内容を理解しているとはいえなかった。
ミライがリェンをじっと見据える。
美しいミライに見つめられると、リェンはうれしいような恐ろしいようないいようのない高まりを感じる。
「物事の一部だけを見てわかった気になることは、愚かなることこの上ない。
物事の大きな流れを俯瞰的に見てこそ、初めてそれを理解できるのだ。
お前にはまだ国史記はまだ早かったかもな」
「……は、はい……」
「もっと簡単な歌詠みなどを習ったらどうだ」
「そ、そういたします……」
その次の晩、ミライはリェンのところへは渡らず、ジンの元へ渡った。
しかも、ジンはギョクに習いたての歌を詠んで、大いにミライを楽しませたという。
その翌朝から炊事場で大声で騒いでいるのがリェンの耳に触った。
「ミライ様がぼくの歌をほめてくださいました。もっとがんばれとおっしゃってくださったんですよ」
珍しくゲツまで炊事場に来ていた。
「それはよかったね、ジン。その褒められたという歌がこれかい? 春から夏のうつろいが良く描けていて、いい歌だね。ギョクもなかなか教えがいのある弟子ができて楽しいだろう」
「ありがとうございます、ゲツ兄様」
「はい。もう少しジンがうまく歌を作れるようになったら、三人で歌合わせなどしませんか、ゲツ兄様」
「それはいい考えだ」
「なんだか楽しそうですね……。僕にも歌というのを教えていただけるのでしょうか?」
「ああ、いいよ、シュンも一緒に学ぶといい」
「仲間がふえるのはたのしいな。シュン、一緒にがんばろう。キョウ兄様とガイ兄様も一緒にいかがですか?」
「だからおれはいいって。それよりジンは朝餉の皿を用意してくれよ。シュンはリェンを呼びに行ってくれ」
「おれも。字を習うより、布や米俵を数えていたほうが楽しいから」
シュンが出てきたところへリェンも顔を出した。
なにごともないように席についたが、ジンの得意げな顔がたまらなく腹が立つ。
話題は引き続き歌のことだった。
リェンはミライの不興を買ったことは口にせず、話の流れに合わせて口を開いた。
「わたしも一度国史記の勉強は中断して、歌を習いたく思います。ミライ様にお前は国史記より歌のほうが向いてるといわれたのです」
すると、なにも知らないキョウとガイ、ジンとシュンはふうんという顔をしたが、リェンがそんなことを言い出した理由をそれとなく察したゲツとギョクはにわかに目を合わせた。
「……いいでしょうか、ゲツ兄様?」
「もちろん構わないよ。だが、歌ならわたしよりギョクのほうが教えることに長けているようだ。
お前もジンと一緒にギョクに習うといいよ」
「えっ……!?」
まさか、ジンとまた一緒にやることになるとは思っても見なかったリェンは明らさまに顔をしかめた。
「……は、はい……」
「リェン兄様は怒りっぽいからな。シュン、ぼくらは穏やかにいこうな」
「は、はあ……」
シュンが気ぜわしくリェンとジンの顔を交互に目を走らせた。
その日の午後からギョクによる歌の勉強会が始まった。
ところが、やはりリェンにはさっぱり歌の良さがわからない。
「秋の水が冷たくなってきた、もうすぐ冬だなぁと歌っているんだよ。わかったかい?」
「はい、ギョク兄様。しっとりとしたいい歌ですね」
「それならぼくも経験があります。ぼくの暮らしていた"宿"は堀の近くにあって、冬になるにつれて堀から冷たい風が吹くんです」
「……」
リェンにわからないことが、ジンだけでなく今日初めて歌を学ぶシュンにもわかるらしい。
(わからん……。なぜそんな当たり前なことをわざわざいう必要があるんだ?
そんなことをいうほうも聞かされる方も、退屈なだけではないか……)
わかったふりをして歌を書き写してみるが、いざ自分で作ってみろといわれると、少しもそれらしいものが思い浮かんでこない。
「ギョク兄様、できました。木がらしの、あいだを吹きぬく、冷たさよ。わたしの心も、氷のようだ」
「冬の厳しさを感じる句だね。紙に清書してごらん」
「あの、ぼ、ぼくもできました。まだ字は書けませんが……」
「いってごらん。わたしが書き留めてあげるから」
「はるの日に、どこからかおる、よいかおり。心がはやる、よいきぶん」
「なかなか可愛らしい歌ができたね。初めてにしては上出来だよ」
ジンもシュンもギョクに褒められて満面の笑みを浮かべている。
リェンはさっきから筆を持ったまま、紙の上を行ったり来たりするが、一文字もかけないでいた。
「リェンはなかなか浮かばないようだね? 好きな季節や、植物や虫のこと、風や星のことでもどんなことでもいいのだよ」
「は、はい……。い、いろいろとありすぎて、どれにしようかと迷っているのです……」
強がりをいってみたものの、結局リェンはなにひとつかけずに終わってしまった。
そればかりか、毎日歌の勉強会に席を並べても、リェンはジンやシュンがやるようにはまったくいかず、いい加減ごまかしさえも効かなくなってきた。
「リェン、本当に何でもいいんだよ? うまく作ろうとせず、思ったままをそのまま歌にしてみればいいんだ」
「くすっ……、リェン兄様は歌が苦手のようですね。シュンにさえ及ばないのでは?」
「リ、リェン兄さま、ぼくなんてまだ字もうまくかけませんし、決してそんなことは……」
シュンにまで気を使われて、リェンは腹の奥がぐっと熱くなった。
なにより、ジンの勝ち誇ったような顔が本当に腹が立つ。
「今日は気分が優れません。ギョク兄様、しばらく休ませていただきます!」
耐えかねたリェンは荷物をまとめると自室に閉じこもってしまった。
(おれがジンより劣っているなんて……っ!)
くやしくてたまらない。
しかも、ミライはジンの歌を見に、このところ毎晩お渡りになっている。
リェンのところへはあの夜以来一日も渡ってこない。
歌ができなければだめだ。
リェンはそう思った。
国史記などを学ぶより、歌のほうがミライ心をつなぎとめられる。
それなのに、その歌が自分には全く理解ができない。
字のうまさも、読める漢字の数も、リェンのほうがはるかに上だった。
それなのに、歌だけがまるで風のようにリェンの体をすり抜けていく。
勝気で向上心には自信をもっていたリェンだったが、珍しく次第に気弱になっていった。
(……ああ、今夜もミライ様はお渡りにならなかった……。
おれはついに見限られたのかもしれない……)
その日は一睡も出なかった。
翌朝、くまのできたどんよりとした顔を引っ提げて、リェンはゲツの元を訪ねた。
「どうしたんだい、リェン。ひどい顔だ」
「ゲツ兄様、おれはばかなんですか……?」
「え?」
「歌がどうしてもわかりません。ゲツ兄様はおれのことを賢いといってくれたけど、本当に、歌のこととなるとさっぱりわからないんです」
リェンがあまりに思いつめた顔をしているので、ゲツは寝台に座らせ、自分もその横に座ったた。
「そう気を落とさなくてもいい。奥宮でも歌が苦手な"種"はいくらでももいたよ」
「そ、そうなんですか……?」
「ああ。リェンは歌よりも、国史記のような史実に基づいた読み物のほうが肌に合うんだろう」
「肌に合う……?」
「そうだよ。向き不向きというものがあるのだ」
「向き不向き……。で、でも、ミライ様は歌を読むジンのほうにばかり……。おれのところにはちっともお見えになりません」
「それでそんな不安そうな顔をしているのだね。そうだな、つまりこういうことだよ、リェン。
お前は男にしては頭が良すぎるのだ」
「へ?……」
リェンは意外なことを言われ、目を丸くした。
ゲツは慎重な目線でリェンを見る。
「国史記には過去男たちが社会の中でどういった役割を担ってきて、どういった過ち犯したのかということが書かれている。
お前はまだその一部しか読んではいないだろうが、その一部を読んだお前は、自分だったらこうするのに、と思ったのではないか?」
「そ……、そうです……」
まるで見透かされたような言葉にリェンは素直にうなづいた。
「普通の男はそういうことは考えないものだ。というより、考えるということ自体、ミライ様や女たちには嫌がられるのだ」
「確かに、ミライ様のご不興を買ってしまいました……」
「考える男は、余計な波風を立てると思われているのだ。
だから、お前のように賢い者は、考えてもいいが、決してそれを口には出さない方がいい。
ご不興を買うだけでなく、いつか命を危険にさらすことになるぞ」
「……は、はい……」
ミライの反応からしてもそれはなんとなく感じていたが、改めてゲツの口から聞かされると、自分がどんなに軽率なことを口にしてしまったのかがわかった。
しかも、歌に関して肌には合わないといわれてしまえば、どうにもしようがなかった。
このままジンのいいようになるのかと思うと悔しくてたまらない。
「……結局、おれに歌は無理だということなんですね……」
「リェン、折角教えてあげたのに"宿"の言葉に戻ってしまっているよ」
「すみ……、申し訳ありません……」
自室に戻った後も、リェンは書き写した歌を何度も声に出して読んでみたり、書き写してみたりしたがやはり何が面白いのかわからなかった。
(このままミライ様のお渡りがなくなってしまったらどうしよう……)
そう思うと、ひたすらうすら寒く、恐怖を背に乗せているような気がして身震いがした。
リェンは自分にはそれなりの才覚となににも負けない気力があると信じていた。
努力すれば、どんなことでもできると信じていた。
だが、今度の歌だけはだめかもしれない。
しかも、自分だけができないのだ。
いっそキョウやガイのように初めから手を付けなかった方が、粗がばれなくて逆に良かったのだろう。
(もうお前には用はない……、そういわれたらどうしよう。ミライ様……)
リェンは世闇の中でひとりでいると、ますます孤独にさいなまれ、珍しくめそめそと涙が出てくるのであった。
「リェン、入るぞ」
はっとして戸口を見た。
戸口の外に明かりがともり、ドアが開くと、ミライが立っていた。
「ミ、ミライ様……!?」
「どうした、幽霊でも見たような顔をして」
「ど、どうして、あの……」
「なんだ? 俺が俺の男に会いに来て何かおかしいか?」
「い、いえ……!」
ミライがゆったりと寝台の奥に座った。
「ほら、ここへ来い。久しぶりにお前の可愛い顔を見に来たのだ」
「はいっ」
リェンはすぐさま着物を脱ぎ払った。
リェンがミライの足元に伏せ、そっとその着物を広げようとすると、それをミライの手が止めた。
「ミライ様……」
「いいから、俺の前に来い。背を向けて。俺に抱かせろ」
「は……」
言われたとおりに、ミライに後ろから抱かれる形でそこへ座った。
同時に、ミライの柔らかな手がするっとリェンの内ももに這った。
リェンははっと息を吸い、急激に神経が震えるのを感じた。
久しぶりのミライの愛撫に、体がどれほど飢えていたがわかった。
「ほら、顔はこっちを向け。脚はもっと広げろ」
「ミ、ミライ様……」
ミライの手がするすると敏感な肌の上をすべる。
局部に向かう様にやってきたと思えば、焦らすようにぴたりと止まる。
何度も繰り返されると、それだけでリェンの竿はぐんぐんと持ち上がった。
背中にはミライの柔らかな乳の感触。
淡く心地いい香り。
ミライの白く滑らかな手が、リェンの乳首をいじる。
「んっ、あ……」
「もうこりこりしているな。お前はここをこうされるのが好きだろう?」
くいっと強く摘ままれた。
「あい……っ、はあ、ああ……」
すぐそばのミライの顔がふふと笑った。
なんとも芳しい香りと、柔らかな空気に触れ、リェンは心解かれた。
少し強引に乳首を責められるのがリェンは好きだ。
ミライの指がきつく摘まんだり、引っ張ったりしてリェンをもてあそぶ。
「はあん……、ミライ様、ミライ、さま……」
「大分焦がれておったようだな。いつもより感じやすいぞ」
「ミライ様のお渡りを……心待ちにしておりました……。もはや、見限られたかと思って、不安で……」
口にしたら、にわかに涙がにじんできた。
「リェンの涙とは。珍しいものが見れた。こっちを向け」
ぐいっと顎を掴まれた。
ミライの唇がリェンの唇を捕らえた。
まるで、果実をはむような優しくも甘い口付け。
リェンは一瞬で頭の中が白く溶けた。
ねだるようにもっともっとと口を広げていけば、ミライがくつくつと笑った。
「いい顔だ、リェン。そんなにわたしが恋しかったか?」
「はい、ミライ様、永久に離れたくありません……」
「案ずるな。今夜はお前を離しはしない」
一晩かけてリェンはたっぶりとミライの愛をうけた。
ひさしぶりのミライの温かな肌に触れて、リェンは何度も何度も放った。
その度に、リェンは生きていることを実感し、ミライへのとめどない愛情を感じた。
後から抱かれたまま、リェンはしばらく動けないほどに果てていた。
ミライが耳元で囁く。
「ゲツからお前がずいぶん気落ちをしていると聞いて、今夜はお前の所へ来た。
気分は晴れたか?」
「……はい。でも、その、ゲツ兄様が……?」
「ああ、心配していたぞ。それにこれだ」
ミライが手を伸ばしいつのまにやら置いてあった本を手に取り、リェンの前に広げた。
国史記だ。
「お前は歌がさっぱりだそうだな」
「……は、はあ……」
「国史記の続きを俺が読んでやろう」
「えっ……?」
ミライの心地よい声が、すぐそばでリェンのためだけに朗読を始めた。
「第三の大戦が終わった後、ここからだ。
国は疲弊し、多くの民が死す。二神人の世を平らかにせんとして新しき神を産む。
豊春古米女神より女子と男子産まれん」
国史記をかいつまむとこうなる。
昔双子が生まれること自体珍しいことだったが、ひとりを育てるのも大変なことであるのに、ふたりを同時に育てるのはとても難しいことであった。
このとき、豊春古米女神の体を慮った天津常照男神は考えた。
ふたりの子を育てるのは難しい。
であれば、荒れた世を平らかに導くことができるのは男子である。男子を残すべきだと。
その続きには、女子は人柱として祀り、大地に返したとある。
すなわち、女子は平和のための生贄として、地に葬られたのであった。
「えっ、お、女を、ですか……?」
「そうだ。これが天津常照男神の犯した大きな間違いだった。続きを読むぞ。
豊春古米女神嘆くこと荒れ狂う海の如く。男子の成人を見届けてお隠れになる。
隠れるとは、死んでしまったという意味だ」
「えっ!? 豊春古米女神様が……!?」
「そうだ。少し省略するが、この後この男子は御幸日子神王と名乗り国をまとめる」
「こ、この国の長が、男だったのですか……?」
「そうだ、この時代はな。だが問題はここからだ。
御幸日子神王世継ぎを求め妻を迎えん。月日経てども子に恵まれず」
「子ができなかったのですか……?」
「そうだ。神の子である御幸日子神王に子ができぬ。これは国の一大事だ。
この後、御幸日子は妻の石御玉姫にどうしたらいいかと尋ねる。
答えて曰く、御幸日子神王毎夜姿を消して、代わり現れたるは忌夜良比売神王なり」
「キ、キヨラヒメノシンノウ……?」
「生贄に葬られた双子の片割れだ」
「えっ!?」
「御幸日子神王がこの世で国の長になったように、忌夜良比売神王は死の国の長になっていたのだ」
「死の、国……」
「石御玉姫が言うには、日が落ち、御幸日子が眠ると姿形体そのものがすっかり忌夜良比売と入れ替わるという」
「入れ替わる……?」
「どのように解釈するかは諸説あるが、ともかく女である石御玉姫と忌夜良比売では子が生まれないのだ」
「ど、どうしてそのような……」
「とにかく、続きはこうある。
忌夜良比売、御幸日子を呪わんとして、国土に毒を撒く。
毒瞬く間に広まりて、民にも子ひとりも産まれず」
「ひ、ひとりも?」
「そうだ。少し先をざっくりいうと、亡国の危機を案じた御幸日子が、忌夜良比売神王を奉って、どうか心を静めてこの国に新しい命を宿してほしいと願う。
すると現れたのは忌夜良比売ではなく豊春古米女神だった」
リェンはミライの語りに魅入られたように耳を傾けた。
まさに、秘された真実が今ここで開かれようという瞬間に感じられた。
「豊春古米女神は、女たちが命を懸けて生み出した新しい命を、男たちは戦でみな端から殺してしまうので、見ているのが大変辛いと嘆いた。
豊春古米女神が双子を生んだのは、二神の力があってこそ人の世を平らかにするからだったのだ。
それなのに、天津常照男神は戦のために御幸日子神王を生かし、命を貴ぶ忌夜良比売神王を殺してしまった。
もはや母である豊春古米女神にも、死の国の長である忌夜良比売神王の心を静めることはできなかったのだ」
「そ、そんな……」
「御幸日子が死んだ母に尋ねた。どうしたら忌夜良比売の心を静められるのかと。
豊春古米女神は一度死の国に戻って、忌夜良比売に聞いてみようと答える。
ここで何度かやり取りがあるが、最終的には……」
ミライが一度言葉を区切った。
リェンが続きを促すように振り向く。
ミライの指が国史記の一部分を指さした。
「忌夜良比売親王、御幸日子親王に伝えて曰く、すべては愚なる男のなせるわざ。
永遠に罪を贖い続けよ」
ぞわっとリェンの背筋に悪寒が走った。
「ここから女中心の国づくりが始まっていくのだ。
男が必要最低限の"種"に選別されて"滓穴"に葬られるのは、今もお怒りであらせられる忌夜良比売神王のお心を鎮めるためなのだ」
知れず手が寝台の敷布を強く握りしめていた。
「はあっ、はあっ……ミライ様……っ」
「どうした?」
冷たくなった手で、ミライの温かな乳に触れた。
恐ろしさに身がすくむ。
もはや、このぬくもりがなければ生きていけないような気がする。
「ミライ様……、忌夜良比売神王は、いつか、いつかは男たちをお許しになるでしょうか……?」
「それは俺にはわからない。ただ、お前がここでこうして生きていられることは、幸せなことだと俺は思うぞ」
「そ、そう思います……」
子どものようにリェンはミライに縋ったまま、震えていた。
頭の中はぐるぐると幼いままに埋められた忌夜良比売神王の怨霊が蠢く。
リェンは"宿"の暮らしをこの世の地獄だと思っていたが、それはかつての男たちの贖罪のためであったのだとはっきり理解した。
「ミライ様、ミライ様……」
「そう怯えなくていい。ここにいる限り、お前は忌夜良比売神王の生贄にはならずに済む」
「ここにいさせてください、ずっと、ずっと。わたしは、ミライ様のためなら、なんでもしますから……」
「リェン無理をするな。怯えた男を抱いてもつまらん。今夜は帰る」
「ミ、ミライ様……っ! お願いです、ここにいてください! こっ、今夜は離さないとおっしゃったではありませんか……っ」
ミライが、はっと笑った。
「そうであったな。しかたない、今夜はこれで休むとするか。だがお前の体が冷たすぎる。
シュンにいって、なにか温かい飲み物を持ってこさせよ」
「は、はい」
リェンは着物を体に巻き付けると、そそくさとシュンに言伝てし、再び駆け戻るとミライの腕の中に丸まった。
ダンゴムシのように固まったリェンを退屈そうに抱きながら待っていると、シュンがお茶を運んできた。
「シュン、お前も来い。一緒にリェンを温めてくれ」
「は、はい……?」
茶を飲んだ後、リェンはミライとシュンに挟まれたまま朝を迎えた。
リェンはほとんど眠れなかった。
朝日が指してようやく、背中に張り付いていた忌夜良比売神王の亡霊が消え去った気がした。
「さて、俺は戻るが、シュンしばらくリェンの様子をみてやってくれ。
あまり無理させないようにな」
「わかりました」
「ミ、ミライ様、今度はいつ来てくださいますか? 明日ですか? 明後日ですか?」
「お前のそのような健気な態度を見るのも悪くないが、元気を出せ。いつものお前のほうが俺は好きだ」
「は、はい……」
すると、ミライはぐっとリェンの顎を拾い、たっぷりとねっとりとした口づけをくれていった。
リェンが瞬く間にとろっと緩んだのがはたから見ていたシュンにもわかった。
「はあ……ミライ……様……」
「いいか、次会うときは、俺をすっかり楽しませなくてはいけないぞ」
「はい……」
ぽうっとしたリェンを置いて、ミライは帰っていった。
その晩、ミライはリェンの元に渡ってきた。
リェンはすっかり準備を整えていて、シュンも側に呼んでいた。
「ミライ様、今夜は二晩分楽しんでいただきたく存じます」
「ほう……。それは楽しみだな」
奉仕のかいあって、ミライはしばらくの間リェンのもとに通い続けるようになった。
新しい歌に精を出していたジンは、歌だけではミライの心をつなぎ留められないことを理解する。
ジンは隣の部屋で楽しむ声を聞きながら歯噛みするのであった。
リェンは歌も国史記の勉強もやめた。
ただただ、ミライに奉仕するための性技を極めることにしたのである。
紆余曲折あったが、今回の軍配はリェン。
ミライと七人の男たち。
積もる話は山あれど、語る機会はまたいずれ……。
丹斗大巴(プロフィールリンク)で公開中!
こちらもぜひお楽しみください!
0
あなたにおすすめの小説

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。


どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる