4 / 9
第3章 冬
「オリオンを見上げて」 1話
しおりを挟む
「ありがとうございました!またのお越しをお待ちしております!」
俺の言葉に若い男性客は満足そうな笑顔を浮かべると店の扉を開けた。そして、コートの襟を立てながら深々と降る雪の中へと繰り出して行った。
鎌倉の夜は早いが、大晦日の今日も例外ではない。夜が更けるにつれ初詣の客は増える。にも関わらず、ここ鎌倉で一番有名な小町通りはひっそりとしている。鶴岡八幡宮を始め、各神社や寺では臨時で屋台を出し、甘酒やおでんなどの温かいものを振舞っている。うちの店も大晦日の夜遅くまで営業をしている。20時を過ぎる頃には客足がまばらになることが多く、経営面では決して潤っているとはいえなかった。だが、遅くまで営業を続けることはこの店ができた頃からの晴海のこだわりだ。
「どんなに苦しくても必要としてくれる人達のために続ける」
それが彼女の口癖だった。
俺と晴海は幼稚園の頃からの幼馴染。高校までを同じ学校で過ごしたが、3年生の夏に彼女はこの地を去った。それ以来、会うことはないと思っていた。だが、それから10年後、俺達は奇跡的に再会。恋に落ちるまでに時間はかからなかった。その僅か1年後に俺達は結婚した。俺は晴海の夢を応援するため、勤めていた会社をきっぱりと辞めた。上司はもちろん同僚や後輩にとても驚かれたが、皆最後は口を揃えてこう言った。
「一途なお前らしいな!」
そして新しい人生のスタートを笑顔で送り出してくれたのだ。
俺がこの店を初めて訪れた時はホール担当の女性店員がいた。だが、彼女は大学生のアルバイトで、就職が決まると同時に店を辞めた。以降は晴海が一人で店を切り盛りしていた。
「ホール担当のバイト入れないのか?」
「……店の経営がちょっと厳しくて。でも大丈夫。私が一人でやるから」
肩をすくめながらも晴海は笑ってこう答えた。だが、一人で店を切り盛りするのは厳しい。ホールをやりながら料理を作らなければならないのだ。案の定、彼女は体調を崩して倒れてしまった。そこで俺は結婚と同時に仕事を辞め、自らがホール担当となることで彼女の力になろうと思ったのだ。接客業は全くの未経験だったから、覚えるまではとても大変だった。客に怒られたり、晴海に注意を受けたりしながらも俺は何とかホールの仕事をこなせるようになった。
あれから20年という長い年月が流れた。再会したあの頃、まだ若いといえた俺達ももうすっかり中年の仲間入りを果たした。健康に気を遣って適度に運動やウォーキングをしているためか、大きな体型の崩れはないものの俺は自分の腹の肉付きが少し気になっている。一方、晴海は趣味でヨガを習っているためか20年前と殆ど変わらなかった。変わったことと言えば、髪の毛に少し白いものが混じり、目尻に皺が増えたことぐらいだろうか。
残念ながら子供は授からなかったが、俺はそれでも構わなかった。ただ、愛する晴海とずっと二人でこうして店を続けていけるならそれでいいと思っている。
「優志くん。表の看板、クローズにしてくれた?」
「ああ、もちろん。外、かなり雪積もってきたぞ」
店の扉を急いで閉め、両手で自身の体を思い切り抱えながら言うと、カウンター越しに晴海が楽しそうに笑った。
「大晦日に雪が積もるなんて久々だね。あの時以来かな?」
「そうだな……ってなんでそんなに楽しそうなんだ?」
すると、晴海は更にクスクスと笑いながら言った。
「だって、あの時のこと思い出すと笑っちゃうんだもん」
「……ったく。晴海はいつもそうやって俺をからかって……いいから早く厨房の片付けするぞ!」
膨れながらそう言うと晴海は依然として楽しそうに笑いながら頷いた。俺はカウンター脇の扉から厨房に入り、洗いかけの皿や鍋に手を付けた。
晴海が思い出し笑いをしていた理由。それは俺がこの店で働いて初めて迎えた大晦日の夜に起こった些細な出来事だ。その日、鎌倉には大雪が降った。俺は客足が途絶える度に外に出て、店の前に積もった大雪を必死にかき出した。もうすぐ閉店時間という頃になって、晴海が俺の様子を見に来た。その時、俺はちょうど雪かきに集中しており、晴海の存在に気づかなかった。
「……優志くん、優志くんってば!」
ふと呼ばれている事に気づいた俺は咄嗟に振り返った。だが、その時、雪かきをした後の地面が凍ってることに気づかなかった俺は思い切り足を滑らせて尻餅をついてしまったのだ。
「痛ってええ!」
「ちょっと優志くん、大丈夫?!」
晴海は驚いて飛んで来てくれたが、笑いを隠し切れていなかった。
「晴海、俺のこと笑ってるだろ」
「えっ?わ、笑ってない!笑ってないよ!」
必死に取り繕うも口元は思い切り笑っている。俺は何だかおかしくなって噴き出してしまい、晴海もそれにつられて笑い出した。粉雪舞う寒空の下に俺と晴海の笑い声が響き渡った。それ以来、雪が降ると晴海は決まって当時のことを思い出し笑うのだ。とても恥ずかしい。だが、正直なところ悪い気はしない。晴海が笑ってくれるならそれでいいと俺は思っている。
二人がかりで厨房の後片付けを終わらせ、売上の計上をしていた俺はふと時計を見てギョッとした。新年まであと15分と迫っていた。この後、鶴岡八幡宮に初詣に行く予定なのだ。
「うわっもうこんな時間かよ?!」
「優志くん!急いで着替えて!早く店を出よう!」
「待て!まだ売上金の計算が出来てない!」
「大丈夫だよ!とりあえず金庫に入れておいてまた後でやろう!」
「えっ?!わ、わかった!」
俺は晴海の指示に従い、急いで売上金を束ね袋に詰めると金庫に突っ込んでしっかりと鍵をかけた。そして、ロッカーに行き、制服から私服に着替えた。制服は黒いシャツに濃いブルーのエプロンのみとシンプルで素早く着脱ができる仕様。俺は分厚いコートの上に濃いブルーのマフラーをぐるぐると巻きつけた。エプロンと同じ色のこのマフラーは今年のクリスマスに晴海がプレゼントしてくれた手編みのものだ。
「えっ?今どき手編みのマフラーなんて欲しいの?」
俺と晴海はいつもクリスマスプレゼントの交換をするのだが、何が欲しいかリクエストをする決まりになっている。だから俺は手編みのマフラーが欲しいと言ったのだ。明確な理由は特にない。何となく手作りのものが欲しかったのだ。すると晴海は怪訝そうな顔でそう言った。
「もしかして引いてる?」
「……ちょっとね。だってもう良い歳だし。まぁでも優志くんの頼みなら仕方ないかなぁ」
苦笑いをした後に晴海はそう言った。そして思い直したように笑ったのだ。晴海は編み物をしたことがなく、最初は四苦八苦していた。だが、器用な為かすぐにコツを掴んで短期間でスラスラと編み上げた。
「すげー嬉しい。ありがとう!でも何で濃いブルーなんだ?」
「転校する直前に優志くんと雨の中を歩いたでしょ?あの時、優志くんのすぐ近くに咲いてた紫陽花の色。あれ以来、優志くんを思い出す度に紫陽花の色も一緒に思い出したんだ。だから私の中であなたのイメージカラーは濃いブルーなの」
晴海は懐かしそうに微笑みながら言った。俺はそこでふと気づいた。
「……もしかして、制服のエプロンの色が濃いブルーなのも、カフェの名前が紫陽花なのも……?」
「優志くんってば今更気づいたの?!もうとっくに気づいてると思ってた!」
晴海は恥ずかしさで顔を真っ赤にしながら、俺の肩をバンバン叩いたのだった。
店の電気を消してしっかり戸締りをする。雪はいつの間にかすっかりやんでおり、澄んだ空にはオリオン座が美しく瞬いていた。
「オリオン座ってどにいてもすぐ分かるし、凄くキレイよね」
「ああ、冬は空気が澄んでるから尚更だ」
晴海の首元にはオリオンのネックレスが静かに揺れている。これは俺が贈ったクリスマスプレゼントだ。晴海からのリクエストは「オリオン座がモチーフの物」というかなり難易度の高いものだった。センスが問われる。俺はアクセサリーショップや雑貨屋を散々探し回った。それで、ようやく見つけたのがこのオリオンのネックレスだったのだ。晴海はオリオン座が好きだった。星に興味がある訳ではない。きちんとした理由がある。
「オリオンって不思議よね。どこにいてもすぐに分かる。まるで私達のことを見守ってくれてるみたい。だから私、オリオンが好きなの。夏の紫陽花と同じくらい好き。私の店もお客さんにとってそう在りたいって強く思うの」
俺が贈ったオリオンのネックレスに感激した後、晴海は力強くそう語ったのだ。
―2話へ続く―
俺の言葉に若い男性客は満足そうな笑顔を浮かべると店の扉を開けた。そして、コートの襟を立てながら深々と降る雪の中へと繰り出して行った。
鎌倉の夜は早いが、大晦日の今日も例外ではない。夜が更けるにつれ初詣の客は増える。にも関わらず、ここ鎌倉で一番有名な小町通りはひっそりとしている。鶴岡八幡宮を始め、各神社や寺では臨時で屋台を出し、甘酒やおでんなどの温かいものを振舞っている。うちの店も大晦日の夜遅くまで営業をしている。20時を過ぎる頃には客足がまばらになることが多く、経営面では決して潤っているとはいえなかった。だが、遅くまで営業を続けることはこの店ができた頃からの晴海のこだわりだ。
「どんなに苦しくても必要としてくれる人達のために続ける」
それが彼女の口癖だった。
俺と晴海は幼稚園の頃からの幼馴染。高校までを同じ学校で過ごしたが、3年生の夏に彼女はこの地を去った。それ以来、会うことはないと思っていた。だが、それから10年後、俺達は奇跡的に再会。恋に落ちるまでに時間はかからなかった。その僅か1年後に俺達は結婚した。俺は晴海の夢を応援するため、勤めていた会社をきっぱりと辞めた。上司はもちろん同僚や後輩にとても驚かれたが、皆最後は口を揃えてこう言った。
「一途なお前らしいな!」
そして新しい人生のスタートを笑顔で送り出してくれたのだ。
俺がこの店を初めて訪れた時はホール担当の女性店員がいた。だが、彼女は大学生のアルバイトで、就職が決まると同時に店を辞めた。以降は晴海が一人で店を切り盛りしていた。
「ホール担当のバイト入れないのか?」
「……店の経営がちょっと厳しくて。でも大丈夫。私が一人でやるから」
肩をすくめながらも晴海は笑ってこう答えた。だが、一人で店を切り盛りするのは厳しい。ホールをやりながら料理を作らなければならないのだ。案の定、彼女は体調を崩して倒れてしまった。そこで俺は結婚と同時に仕事を辞め、自らがホール担当となることで彼女の力になろうと思ったのだ。接客業は全くの未経験だったから、覚えるまではとても大変だった。客に怒られたり、晴海に注意を受けたりしながらも俺は何とかホールの仕事をこなせるようになった。
あれから20年という長い年月が流れた。再会したあの頃、まだ若いといえた俺達ももうすっかり中年の仲間入りを果たした。健康に気を遣って適度に運動やウォーキングをしているためか、大きな体型の崩れはないものの俺は自分の腹の肉付きが少し気になっている。一方、晴海は趣味でヨガを習っているためか20年前と殆ど変わらなかった。変わったことと言えば、髪の毛に少し白いものが混じり、目尻に皺が増えたことぐらいだろうか。
残念ながら子供は授からなかったが、俺はそれでも構わなかった。ただ、愛する晴海とずっと二人でこうして店を続けていけるならそれでいいと思っている。
「優志くん。表の看板、クローズにしてくれた?」
「ああ、もちろん。外、かなり雪積もってきたぞ」
店の扉を急いで閉め、両手で自身の体を思い切り抱えながら言うと、カウンター越しに晴海が楽しそうに笑った。
「大晦日に雪が積もるなんて久々だね。あの時以来かな?」
「そうだな……ってなんでそんなに楽しそうなんだ?」
すると、晴海は更にクスクスと笑いながら言った。
「だって、あの時のこと思い出すと笑っちゃうんだもん」
「……ったく。晴海はいつもそうやって俺をからかって……いいから早く厨房の片付けするぞ!」
膨れながらそう言うと晴海は依然として楽しそうに笑いながら頷いた。俺はカウンター脇の扉から厨房に入り、洗いかけの皿や鍋に手を付けた。
晴海が思い出し笑いをしていた理由。それは俺がこの店で働いて初めて迎えた大晦日の夜に起こった些細な出来事だ。その日、鎌倉には大雪が降った。俺は客足が途絶える度に外に出て、店の前に積もった大雪を必死にかき出した。もうすぐ閉店時間という頃になって、晴海が俺の様子を見に来た。その時、俺はちょうど雪かきに集中しており、晴海の存在に気づかなかった。
「……優志くん、優志くんってば!」
ふと呼ばれている事に気づいた俺は咄嗟に振り返った。だが、その時、雪かきをした後の地面が凍ってることに気づかなかった俺は思い切り足を滑らせて尻餅をついてしまったのだ。
「痛ってええ!」
「ちょっと優志くん、大丈夫?!」
晴海は驚いて飛んで来てくれたが、笑いを隠し切れていなかった。
「晴海、俺のこと笑ってるだろ」
「えっ?わ、笑ってない!笑ってないよ!」
必死に取り繕うも口元は思い切り笑っている。俺は何だかおかしくなって噴き出してしまい、晴海もそれにつられて笑い出した。粉雪舞う寒空の下に俺と晴海の笑い声が響き渡った。それ以来、雪が降ると晴海は決まって当時のことを思い出し笑うのだ。とても恥ずかしい。だが、正直なところ悪い気はしない。晴海が笑ってくれるならそれでいいと俺は思っている。
二人がかりで厨房の後片付けを終わらせ、売上の計上をしていた俺はふと時計を見てギョッとした。新年まであと15分と迫っていた。この後、鶴岡八幡宮に初詣に行く予定なのだ。
「うわっもうこんな時間かよ?!」
「優志くん!急いで着替えて!早く店を出よう!」
「待て!まだ売上金の計算が出来てない!」
「大丈夫だよ!とりあえず金庫に入れておいてまた後でやろう!」
「えっ?!わ、わかった!」
俺は晴海の指示に従い、急いで売上金を束ね袋に詰めると金庫に突っ込んでしっかりと鍵をかけた。そして、ロッカーに行き、制服から私服に着替えた。制服は黒いシャツに濃いブルーのエプロンのみとシンプルで素早く着脱ができる仕様。俺は分厚いコートの上に濃いブルーのマフラーをぐるぐると巻きつけた。エプロンと同じ色のこのマフラーは今年のクリスマスに晴海がプレゼントしてくれた手編みのものだ。
「えっ?今どき手編みのマフラーなんて欲しいの?」
俺と晴海はいつもクリスマスプレゼントの交換をするのだが、何が欲しいかリクエストをする決まりになっている。だから俺は手編みのマフラーが欲しいと言ったのだ。明確な理由は特にない。何となく手作りのものが欲しかったのだ。すると晴海は怪訝そうな顔でそう言った。
「もしかして引いてる?」
「……ちょっとね。だってもう良い歳だし。まぁでも優志くんの頼みなら仕方ないかなぁ」
苦笑いをした後に晴海はそう言った。そして思い直したように笑ったのだ。晴海は編み物をしたことがなく、最初は四苦八苦していた。だが、器用な為かすぐにコツを掴んで短期間でスラスラと編み上げた。
「すげー嬉しい。ありがとう!でも何で濃いブルーなんだ?」
「転校する直前に優志くんと雨の中を歩いたでしょ?あの時、優志くんのすぐ近くに咲いてた紫陽花の色。あれ以来、優志くんを思い出す度に紫陽花の色も一緒に思い出したんだ。だから私の中であなたのイメージカラーは濃いブルーなの」
晴海は懐かしそうに微笑みながら言った。俺はそこでふと気づいた。
「……もしかして、制服のエプロンの色が濃いブルーなのも、カフェの名前が紫陽花なのも……?」
「優志くんってば今更気づいたの?!もうとっくに気づいてると思ってた!」
晴海は恥ずかしさで顔を真っ赤にしながら、俺の肩をバンバン叩いたのだった。
店の電気を消してしっかり戸締りをする。雪はいつの間にかすっかりやんでおり、澄んだ空にはオリオン座が美しく瞬いていた。
「オリオン座ってどにいてもすぐ分かるし、凄くキレイよね」
「ああ、冬は空気が澄んでるから尚更だ」
晴海の首元にはオリオンのネックレスが静かに揺れている。これは俺が贈ったクリスマスプレゼントだ。晴海からのリクエストは「オリオン座がモチーフの物」というかなり難易度の高いものだった。センスが問われる。俺はアクセサリーショップや雑貨屋を散々探し回った。それで、ようやく見つけたのがこのオリオンのネックレスだったのだ。晴海はオリオン座が好きだった。星に興味がある訳ではない。きちんとした理由がある。
「オリオンって不思議よね。どこにいてもすぐに分かる。まるで私達のことを見守ってくれてるみたい。だから私、オリオンが好きなの。夏の紫陽花と同じくらい好き。私の店もお客さんにとってそう在りたいって強く思うの」
俺が贈ったオリオンのネックレスに感激した後、晴海は力強くそう語ったのだ。
―2話へ続く―
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
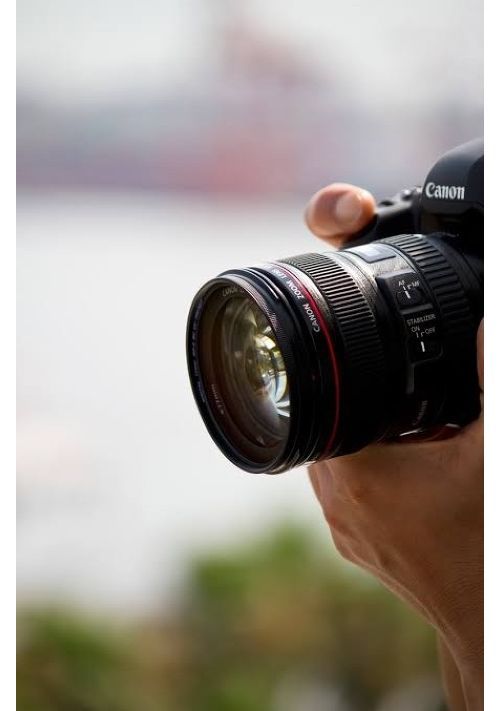
友愛ポートレート
たあこ
青春
気づけば俺の世界は、彼を中心に回っていた。
撮りたいと、初めてそう思えた人。
前の席の久瀬は、いつも一人で本を読んでいる。俺はその様子になんだか親近感を覚えて、仲良くなろうとするもきっかけを作れないでいた。
そんなある日の放課後、転機が訪れる。
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
高校デビューの理想と現実のギャップに悩む主人公の二宮雄大と一匹狼の久瀬翔太のお話です。

ハッピークリスマス ! 非公開にしていましたが再upしました。 2024.12.1
設樂理沙
青春
中学生の頃からずっと一緒だったよね。大切に思っていた人との楽しい日々が
この先もずっと続いていけぱいいのに……。
―――――――――――――――――――――――
|松村絢《まつむらあや》 ---大企業勤務 25歳
|堂本海(どうもとかい) ---商社勤務 25歳 (留年してしまい就職は一年遅れ)
中学の同級生
|渡部佳代子《わたなべかよこ》----絢と海との共通の友達 25歳
|石橋祐二《いしばしゆうじ》---絢の会社での先輩 30歳
|大隈可南子《おおくまかなこ》----海の同期 24歳 海LOVE?
――― 2024.12.1 再々公開 ――――
💍 イラストはOBAKERON様 有償画像

全てが思い出
第三者
青春
今年閉校する田舎の中学校の3年生5人、
元気ななっちゃん、大人なタク、モデル志望のみさ、コミュ障のとっきー、地元好きなそーちゃんの、卒業式までの3ヶ月間の友情・恋・家族・将来についての葛藤と幸福を綴った短編集。

別世界の君の瞳に映るのは
響ぴあの
青春
君の瞳は病になって、それから私との距離はだんだん遠くなっていった。
ちょっと雰囲気が変わった君は空色の髪の毛に染めた。
まさか、そのあと、別な病になっているなんて私は知らなかったんだ。
私の瞳にはずっと君が映っているのに、君の瞳に私は映らない。
別世界の人間になってしまったんだと勝手に思っていた。
からっぽに支配された青い髪の君。
青い空を見たら君を必ず思い出すよ。

愛するものと出会えたなら
白い恋人
青春
昔、ある事件により、人を信じる・愛することをやめてしまった主人公、白恋 優一(はくれん ゆういち)。
そんなある日、転校してきた天真爛漫な少女、双葉 ひかり(ふたば ひかり)と出会う。そんなグイグイ迫ってくるひかりを拒絶するつもりの優一だったが………。
優一はこれから人と深く関わり合えるのか、ひかりにいったいどんな過去があったのか、これからどうなってしまうのか………。

疾風バタフライ
霜月かずひこ
青春
中学での挫折から卓球を諦めた少年、越谷廉太郎。
高校では充実した毎日を送ろうと普通の進学校を選んだ。
はずだったのだが、
「越谷くん、卓球しよ?」
彼の前に現れたのは卓球の神様に愛された天才少女・朝倉寧々。
輝かしい経歴を持つ彼女はなぜか廉太郎のことを気にかけていて?
卓球にすべてをかける少年少女たちの熱い青春物語が始まる!
*
真夏の冬将軍という名義で活動していた時のものを微修正した作品となります。
以前はカクヨム等に投稿していました。(現在は削除済み)
現在は小説家になろうとアルファポリスで連載中です。

鷹鷲高校執事科
三石成
青春
経済社会が崩壊した後に、貴族制度が生まれた近未来。
東京都内に広大な敷地を持つ全寮制の鷹鷲高校には、貴族の子息が所属する帝王科と、そんな貴族に仕える、優秀な執事を育成するための執事科が設立されている。
物語の中心となるのは、鷹鷲高校男子部の三年生。
各々に悩みや望みを抱えた彼らは、高校三年生という貴重な一年間で、学校の行事や事件を通して、生涯の主人と執事を見つけていく。
表紙イラスト:燈実 黙(@off_the_lamp)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















