お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説



人喰奇談 ―ホラー短編小説集
Kfumi
ホラー
ホラー・オカルト・非日常を綴るオムニバスの短編集。
美女はある理由から男と出会い子供を欲した。
そして美しく恐ろしい狂気が目覚める。
。
※多少グロテスクな表現があります。苦手な方はご注意ください。

茨城の首切場(くびきりば)
転生新語
ホラー
へー、ご当地の怪談を取材してるの? なら、この家の近くで、そういう話があったよ。
ファミレスとかの飲食店が、必ず潰れる場所があってね。そこは首切場(くびきりば)があったんだ……
カクヨム、小説家になろうに投稿しています。
カクヨム→https://kakuyomu.jp/works/16817330662331165883
小説家になろう→https://ncode.syosetu.com/n5202ij/

功名の証(こうみょうのあかし)
北之 元
ホラー
☆あらすじ
近郊の寺から盗まれ、その後見つかって返還された戦国時代の甲冑。オカルト趣味で親交のあるA夫、B輔、C子の三人は、それが盗難直後に出品されていたオークション会場で発生した、大量猟奇殺人事件と何らかの関わりがあるらしいことをつきとめ、「呪いの甲冑」の現物を一目見ようと寺の収蔵庫に忍び込む。彼らは数百年の時代を経たのみならず、一度火災に遭っているはずの甲冑が新品同様に無傷なことをいぶかしがるが、C子がたわむれにその甲冑を身につけたとたん、身の毛もよだつ怖ろしいことが起こる。――しかし、それはその後展開する前代未聞の怪異で凄惨なできごとの序章にすぎなかった。
☆作品について
前作「転生の剣」と同じく、自作の模型から着想を得ました。私は基本がモデラーなので、創作に当たってはまず具象物を拵えることでその“依代(よりしろ)”を確保し、次いでそこから生じるイメージを文章化するという手順になるようです。 自分の力量不足を承知で今回はホラー小説に挑戦してみたのですが、本当に怖いと思える話を書くことの難しさをしみじみ実感させられました。及ばずながら自分なりにいろいろ工夫してはおりますが、はたして文字でどこまでリアルな恐怖感を表現できたのか甚だ不安です。
もとより文学とは縁遠い小生ゆえ、お目汚しの駄作レベルとは存じますが、あえて読者諸兄のご高覧に供しますので、率直なご意見を賜ることができましたら幸甚です。
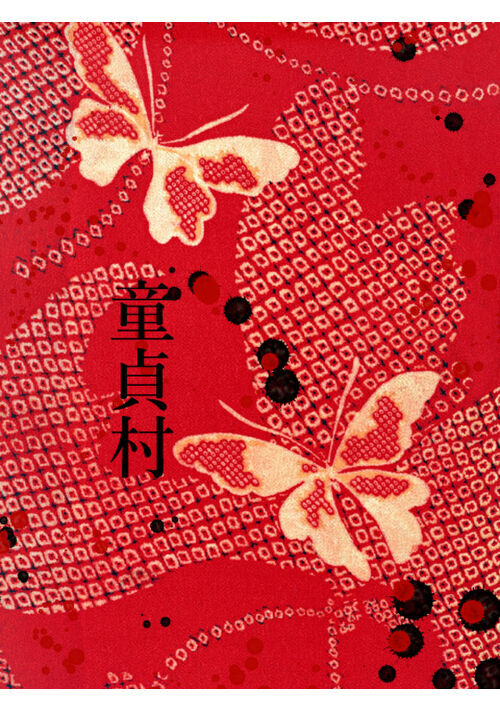
童貞村
雷尾
ホラー
動画サイトで配信活動をしている男の元に、ファンやリスナーから阿嘉黒町の奥地にある廃村の探索をしてほしいと要望が届いた。名前すらもわからないその村では、廃村のはずなのに今でも人が暮らしているだとか、過去に殺人事件があっただとか、その土地を知る者の間では禁足地扱いされているといった不穏な噂がまことしやかに囁かれていた。※BL要素ありです※
作中にでてくるユーチューバー氏は進行役件観測者なので、彼はBLしません。
※ユーチューバー氏はこちら
https://www.alphapolis.co.jp/manga/980286919/965721001

デス・アイランド
汐川ヒロマサ
ホラー
死んだはずのクラスメイトに『コカ島』に集まるように言われ高校三年生の男女六人は船で向かった。島に着き、長い山道を登ると山小屋があり、中で見つけた紙には『お前たちを許さない』と書かあり裏には『六人で殺し合え』と書いてあった。本気にしてなかった六人だったが、その夜一人目の犠牲者が出た。いったい誰が……。果たして彼らは生きて島を出られるのか――。

古への守(もり)
弐式
ホラー
夏休みに一週間ほど田舎町の広大な森の近くに住む宮瀬家で過ごすことになった小学5年生の芦谷奈津。
お世話になることになった屋敷には、絶対に入ってはいけないという部屋があった。
その夜、入ってはいけないといわれた部屋から音が聞こえ、奈津は中に入ってしまう。
そのことをきっかけに、奈津は森と宮瀬家の歪な関係と、部屋の主の話に関わることになっていく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















