お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説

病気になって芸能界から消えたアイドル。退院し、復学先の高校には昔の仕事仲間が居たけれど、彼女は俺だと気付かない
月島日向
ライト文芸
俺、日生遼、本名、竹中祐は2年前に病に倒れた。
人気絶頂だった『Cherry’s』のリーダーをやめた。
2年間の闘病生活に一区切りし、久しぶりに高校に通うことになった。けど、誰も俺の事を元アイドルだとは思わない。薬で細くなった手足。そんな細身の体にアンバランスなムーンフェイス(薬の副作用で顔だけが大きくなる事)
。
誰も俺に気付いてはくれない。そう。
2年間、連絡をくれ続け、俺が無視してきた彼女さえも。
もう、全部どうでもよく感じた。

いっぱい命じて〜無自覚SubはヤンキーDomに甘えたい〜
きよひ
BL
無愛想な高一Domヤンキー×Subの自覚がない高三サッカー部員
Normalの諏訪大輝は近頃、謎の体調不良に悩まされていた。
そんな折に出会った金髪の一年生、甘井呂翔。
初めて会った瞬間から甘井呂に惹かれるものがあった諏訪は、Domである彼がPlayする様子を覗き見てしまう。
甘井呂に優しく支配されるSubに自分を重ねて胸を熱くしたことに戸惑う諏訪だが……。
第二性に振り回されながらも、互いだけを求め合うようになる青春の物語。
※現代ベースのDom/Subユニバースの世界観(独自解釈・オリジナル要素あり)
※不良の喧嘩描写、イジメ描写有り
初日は5話更新、翌日からは2話ずつ更新の予定です。

社畜だけど異世界では推し騎士の伴侶になってます⁈
めがねあざらし
BL
気がつくと、そこはゲーム『クレセント・ナイツ』の世界だった。
しかも俺は、推しキャラ・レイ=エヴァンスの“伴侶”になっていて……⁈
記憶喪失の俺に課されたのは、彼と共に“世界を救う鍵”として戦う使命。
しかし、レイとの誓いに隠された真実や、迫りくる敵の陰謀が俺たちを追い詰める――。
異世界で見つけた愛〜推し騎士との奇跡の絆!
推しとの距離が近すぎる、命懸けの異世界ラブファンタジー、ここに開幕!

家事代行サービスにdomの溺愛は必要ありません!
灯璃
BL
家事代行サービスで働く鏑木(かぶらぎ) 慧(けい)はある日、高級マンションの一室に仕事に向かった。だが、住人の男性は入る事すら拒否し、何故かなかなか中に入れてくれない。
何度かの押し問答の後、なんとか慧は中に入れてもらえる事になった。だが、男性からは冷たくオレの部屋には入るなと言われてしまう。
仕方ないと気にせず仕事をし、気が重いまま次の日も訪れると、昨日とは打って変わって男性、秋水(しゅうすい) 龍士郎(りゅうしろう)は慧の料理を褒めた。
思ったより悪い人ではないのかもと慧が思った時、彼がdom、支配する側の人間だという事に気づいてしまう。subである慧は彼と一定の距離を置こうとするがーー。
みたいな、ゆるいdom/subユニバース。ふんわり過ぎてdom/subユニバースにする必要あったのかとか疑問に思ってはいけない。
※完結しました!ありがとうございました!

人気アイドルグループのリーダーは、気苦労が絶えない
タタミ
BL
大人気5人組アイドルグループ・JETのリーダーである矢代頼は、気苦労が絶えない。
対メンバー、対事務所、対仕事の全てにおいて潤滑剤役を果たす日々を送る最中、矢代は人気2トップの御厨と立花が『仲が良い』では片付けられない距離感になっていることが気にかかり──

転生悪役令息、雌落ち回避で溺愛地獄!?義兄がラスボスです!
めがねあざらし
BL
人気BLゲーム『ノエル』の悪役令息リアムに転生した俺。
ゲームの中では「雌落ちエンド」しか用意されていない絶望的な未来が待っている。
兄の過剰な溺愛をかわしながらフラグを回避しようと奮闘する俺だが、いつしか兄の目に奇妙な影が──。
義兄の溺愛が執着へと変わり、ついには「ラスボス化」!?
このままじゃゲームオーバー確定!?俺は義兄を救い、ハッピーエンドを迎えられるのか……。
※タイトル変更(2024/11/27)
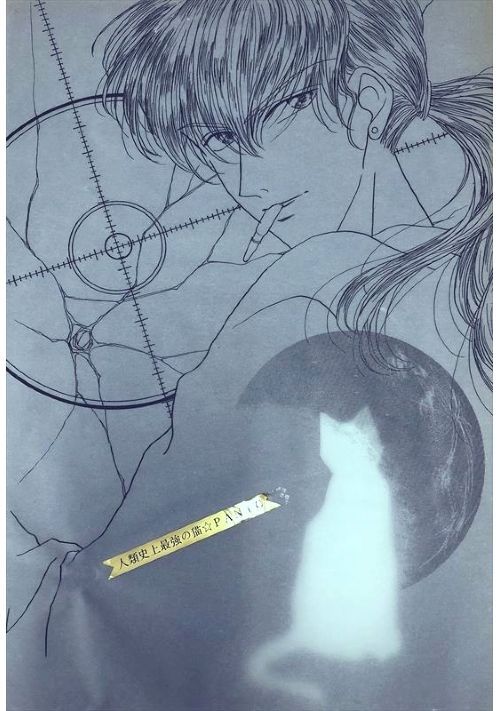
【完結】帝王様は、表でも裏でも有名な飼い猫を溺愛する
綾雅(要らない悪役令嬢1/7発売)
BL
離地暦201年――人類は地球を離れ、宇宙で新たな生活を始め200年近くが経過した。貧困の差が広がる地球を捨て、裕福な人々は宇宙へ進出していく。
狙撃手として裏で名を馳せたルーイは、地球での狙撃の帰りに公安に拘束された。逃走経路を疎かにした結果だ。表では一流モデルとして有名な青年が裏路地で保護される、滅多にない事態に公安は彼を疑うが……。
表も裏もひっくるめてルーイの『飼い主』である権力者リューアは公安からの問い合わせに対し、彼の保護と称した強制連行を指示する。
権力者一族の争いに巻き込まれるルーイと、ひたすらに彼に甘いリューアの愛の行方は?
【重複投稿】エブリスタ、アルファポリス、小説家になろう
【注意】※印は性的表現有ります

はじまりの恋
葉月めいこ
BL
生徒×教師/僕らの出逢いはきっと必然だった。
あの日くれた好きという言葉
それがすべてのはじまりだった
好きになるのに理由も時間もいらない
僕たちのはじまりとそれから
高校教師の西岡佐樹は
生徒の藤堂優哉に告白をされる。
突然のことに驚き戸惑う佐樹だが
藤堂の真っ直ぐな想いに
少しずつ心を動かされていく。
どうしてこんなに
彼のことが気になるのだろう。
いままでになかった想いが胸に広がる。
これは二人の出会いと日常
それからを描く純愛ストーリー
優しさばかりではない、切なく苦しい困難がたくさん待ち受けています。
二人は二人の選んだ道を信じて前に進んでいく。
※作中にて視点変更されるシーンが多々あります。
※素敵な表紙、挿絵イラストは朔羽ゆきさんに描いていただきました。
※挿絵「想い03」「邂逅10」「邂逅12」「夏日13」「夏日48」「別離01」「別離34」「始まり06」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















