7 / 45
自転
6
しおりを挟む
「無理することもないよ。俺はそういう医者だから」
さっぱりと言った先生は、そうやって手を引いては私を組敷くのだけど。
少し見つめて私が目を閉じれば、髪を撫でてお皿を片しに行ってしまうような、そんな人。
私はこんなとき、いっそどうして女だったのだろうと胸で考える。
私は先生が好きだけど、先生はそれだけの人で、考えは胸に突き刺さるナイフと痙攣して血を流すような、そんな現象と言うだけで。
愛するには遠い、離れるには近い。
起き上がることなく手首を見つめてみれば「陽、」と、リビングの流しの先生なのか、それとも胸から流れた鮮血なのか、触れられた耳の奥から頭に響いて痙攣してしまうようで。
一生このまま苦しいのかな。
泣きたくなる手前で目を閉じてみる。夢の近くにある何かに引っ張られてしまいたい。また、眩暈のような甘い吐き気のような、暗闇が訪れようとしている。
眠いのかもしれない。
私は何を持っているんだろう、この、傷だらけの──
泣いている気がした。
慣れた、ことだった。
これを潮汐破壊と言うのだろうかと目を開けた先、リビングのLEDライトが直に頭痛に繋がった。
この状況に頭に来るが、まだ耳鳴りがする、前頭葉辺りにヒステリックな痛みを伴うのだが破壊的な衝動で起き上がれば「ハル?」と間抜けな甘ったるい声がしたことに反吐が出そうだった。
ゆっくりと血液が止まるような、そんな感じで。
「てめぇ何しやがった照井、」
ドスの利いた声とは俺のこの掠れた喋りにくい喉詰まりの事か。
ゲロ吐きそうな無性な頭痛に顔をしかめたところで物質強度を無視する俺は臨界の衛生軌道半径を越えていないと起き上がる。
流しから見下ろすようにこちらを見ている間抜け面の精神科医を睨めば「悠、」と漸く俺に気付いたようだった。
「…久しぶりに会えたと思ったのにな」
「殺されてぇかクソ野郎」
「そんな元気ないくせに」
「一日近くは寝たからな、てめぇの予想以上には体力あるんだよ、この変態野郎」
「…やれやれ」
変態野郎、主治医の照井永一はどーしょも無さそうに流しの音を止め、リビングに戻って来て俺に手を差しのべるが、俺はその手を引っ張り体制を崩した野郎に「強姦でサツ呼ぶぞこの発情期野郎が」と言い捨てた。
照井は反射的に右手をつくが、付き方は悪そうだ、少し捻ったようで「痛っ、」と呟いた。
「…あぶなっ、」
「…てめ、ハルに何したって、聞いてんだよおい、」
その体制のまま照井の股間を膝でぐりぐりとやれば「やめろっつーの、違うから、」と情けない声をあげた。
「この状況で説得力皆無だろこのロリコンが、」
「落ち着けってば、」
「落ち付けじゃねぇんだよ、現にハルは引っ込んじまっただろうがよ、あぁ!?」
最早股間を蹴り上げる勢いでいけば「痛い痛い痛い痛い!」と、漸く俺から離れた照井は泣きそうだった。
「過保護だな全く…マジで違うからね、なんなのホント、」
「だぁからっ、」
「押し倒したのは認める、君がこんなんだから何も出来やしないでしょうが!」
「あたりめぇだろぶっ殺すぞてめぇ」
「あ~…も~…。
まぁいいや落ち着いて。ちゃんとお薬もあげるしハルとはなんもなかった!
ちょっと水取って来てあげるから。君にも聞きたいこと山程あるからな今日は」
「はぁ?」
まぁ大方わかってる。
今朝、突然人格が交代しちまった事だろうとは思う。
これは不安定で、じんわりと血液が巡るような、そんな昼夜逆転のような生理現象でしかないんだよ。
照井は一旦俺から離れ、冷蔵庫から水を取ってきて、テキトーにポケットから処方薬を出した。
確かに、まずはこの興奮状態で血管が逝っちまいそうな状況を打破しよう。腹立ちすぎて微妙に息が上がってるし。
水だけ奪い取ってガバ飲みしたが、思った以上に喉は動かなかった。わりと首筋を伝ってニットの襟を濡らした俺に「あーあーあー、」と、照井は保護者のように、だがオーバーなリアクションを取った。
「…行儀悪い子」
「…るっ、さいんだよっ、」
「はいはい…」
照井はソファの側にあった自分の鞄から薬を取り出し、水と共に口に含んだ。
後頭部はわりと荒く掴まれた。だがゆっくり静かに薬と水を口移しされるが、それも腹立たしいので薬を乗せたその舌は噛んでやる。わりとすぐに引っ込めては「いはっ、」と後頭部を掴んでいた手も離された。
「調子こいて舌入れてくるバカいるか、おい」
「どうせ慣れてんじゃん…」
「うるせぇな、マジで。お前これハルにやってたら」
「はいはーい。俺は何回殺人予告を受けるんですか。いい加減にして」
ふざけた調子で降参のポーズをした照井に「ったく、」とこちらが一歩引く。
わかっている。こいつには甲斐性がない。
慣れたことだった。
さっぱりと言った先生は、そうやって手を引いては私を組敷くのだけど。
少し見つめて私が目を閉じれば、髪を撫でてお皿を片しに行ってしまうような、そんな人。
私はこんなとき、いっそどうして女だったのだろうと胸で考える。
私は先生が好きだけど、先生はそれだけの人で、考えは胸に突き刺さるナイフと痙攣して血を流すような、そんな現象と言うだけで。
愛するには遠い、離れるには近い。
起き上がることなく手首を見つめてみれば「陽、」と、リビングの流しの先生なのか、それとも胸から流れた鮮血なのか、触れられた耳の奥から頭に響いて痙攣してしまうようで。
一生このまま苦しいのかな。
泣きたくなる手前で目を閉じてみる。夢の近くにある何かに引っ張られてしまいたい。また、眩暈のような甘い吐き気のような、暗闇が訪れようとしている。
眠いのかもしれない。
私は何を持っているんだろう、この、傷だらけの──
泣いている気がした。
慣れた、ことだった。
これを潮汐破壊と言うのだろうかと目を開けた先、リビングのLEDライトが直に頭痛に繋がった。
この状況に頭に来るが、まだ耳鳴りがする、前頭葉辺りにヒステリックな痛みを伴うのだが破壊的な衝動で起き上がれば「ハル?」と間抜けな甘ったるい声がしたことに反吐が出そうだった。
ゆっくりと血液が止まるような、そんな感じで。
「てめぇ何しやがった照井、」
ドスの利いた声とは俺のこの掠れた喋りにくい喉詰まりの事か。
ゲロ吐きそうな無性な頭痛に顔をしかめたところで物質強度を無視する俺は臨界の衛生軌道半径を越えていないと起き上がる。
流しから見下ろすようにこちらを見ている間抜け面の精神科医を睨めば「悠、」と漸く俺に気付いたようだった。
「…久しぶりに会えたと思ったのにな」
「殺されてぇかクソ野郎」
「そんな元気ないくせに」
「一日近くは寝たからな、てめぇの予想以上には体力あるんだよ、この変態野郎」
「…やれやれ」
変態野郎、主治医の照井永一はどーしょも無さそうに流しの音を止め、リビングに戻って来て俺に手を差しのべるが、俺はその手を引っ張り体制を崩した野郎に「強姦でサツ呼ぶぞこの発情期野郎が」と言い捨てた。
照井は反射的に右手をつくが、付き方は悪そうだ、少し捻ったようで「痛っ、」と呟いた。
「…あぶなっ、」
「…てめ、ハルに何したって、聞いてんだよおい、」
その体制のまま照井の股間を膝でぐりぐりとやれば「やめろっつーの、違うから、」と情けない声をあげた。
「この状況で説得力皆無だろこのロリコンが、」
「落ち着けってば、」
「落ち付けじゃねぇんだよ、現にハルは引っ込んじまっただろうがよ、あぁ!?」
最早股間を蹴り上げる勢いでいけば「痛い痛い痛い痛い!」と、漸く俺から離れた照井は泣きそうだった。
「過保護だな全く…マジで違うからね、なんなのホント、」
「だぁからっ、」
「押し倒したのは認める、君がこんなんだから何も出来やしないでしょうが!」
「あたりめぇだろぶっ殺すぞてめぇ」
「あ~…も~…。
まぁいいや落ち着いて。ちゃんとお薬もあげるしハルとはなんもなかった!
ちょっと水取って来てあげるから。君にも聞きたいこと山程あるからな今日は」
「はぁ?」
まぁ大方わかってる。
今朝、突然人格が交代しちまった事だろうとは思う。
これは不安定で、じんわりと血液が巡るような、そんな昼夜逆転のような生理現象でしかないんだよ。
照井は一旦俺から離れ、冷蔵庫から水を取ってきて、テキトーにポケットから処方薬を出した。
確かに、まずはこの興奮状態で血管が逝っちまいそうな状況を打破しよう。腹立ちすぎて微妙に息が上がってるし。
水だけ奪い取ってガバ飲みしたが、思った以上に喉は動かなかった。わりと首筋を伝ってニットの襟を濡らした俺に「あーあーあー、」と、照井は保護者のように、だがオーバーなリアクションを取った。
「…行儀悪い子」
「…るっ、さいんだよっ、」
「はいはい…」
照井はソファの側にあった自分の鞄から薬を取り出し、水と共に口に含んだ。
後頭部はわりと荒く掴まれた。だがゆっくり静かに薬と水を口移しされるが、それも腹立たしいので薬を乗せたその舌は噛んでやる。わりとすぐに引っ込めては「いはっ、」と後頭部を掴んでいた手も離された。
「調子こいて舌入れてくるバカいるか、おい」
「どうせ慣れてんじゃん…」
「うるせぇな、マジで。お前これハルにやってたら」
「はいはーい。俺は何回殺人予告を受けるんですか。いい加減にして」
ふざけた調子で降参のポーズをした照井に「ったく、」とこちらが一歩引く。
わかっている。こいつには甲斐性がない。
慣れたことだった。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説
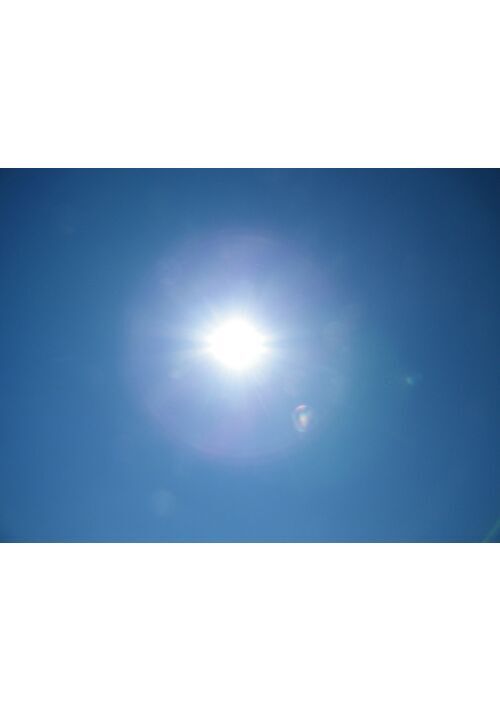
天穹は青く
梅林 冬実
現代文学
母親の無理解と叔父の存在に翻弄され、ある日とうとう限界を迎えてしまう。
気付けば傍に幼い男の子がいて、その子は尋ねる。「どうしたの?」と。
普通に生きたい。それだけだった。頼れる人なんて、誰もいなくて。
不意に訪れた現実に戸惑いつつも、自分を見つめ返す。その先に見えるものとは。

あなたがわたしを本気で愛せない理由は知っていましたが、まさかここまでとは思っていませんでした。
ふまさ
恋愛
「……き、きみのこと、嫌いになったわけじゃないんだ」
オーブリーが申し訳なさそうに切り出すと、待ってましたと言わんばかりに、マルヴィナが言葉を繋ぎはじめた。
「オーブリー様は、決してミラベル様を嫌っているわけではありません。それだけは、誤解なきよう」
ミラベルが、当然のように頭に大量の疑問符を浮かべる。けれど、ミラベルが待ったをかける暇を与えず、オーブリーが勢いのまま、続ける。
「そう、そうなんだ。だから、きみとの婚約を解消する気はないし、結婚する意思は変わらない。ただ、その……」
「……婚約を解消? なにを言っているの?」
「いや、だから。婚約を解消する気はなくて……っ」
オーブリーは一呼吸置いてから、意を決したように、マルヴィナの肩を抱き寄せた。
「子爵令嬢のマルヴィナ嬢を、あ、愛人としてぼくの傍に置くことを許してほしい」
ミラベルが愕然としたように、目を見開く。なんの冗談。口にしたいのに、声が出なかった。

扉の先のブックカフェ
ミドリ
現代文学
社会人四年目の月島マリは、お喋りが止まない同期の梨花の存在に悩まされていた。家族のいないマリにとっての癒やしスポット・ブックカフェ『ピート』の年上マスターと、偶然本屋で出会った同い年の大川健斗と過ごす憩いの時間に、やがて少しずつ変化が起きて――。
なろうでも掲載してます。

妻と愛人と家族
春秋花壇
現代文学
4 愛は辛抱強く,親切です。愛は嫉妬しません。愛は自慢せず,思い上がらず, 5 下品な振る舞いをせず,自分のことばかり考えず,いら立ちません。愛は傷つけられても根に持ちません。 6 愛は不正を喜ばないで,真実を喜びます。 7 愛は全てのことに耐え,全てのことを信じ,全てのことを希望し,全てのことを忍耐します。
8 愛は決して絶えません。
コリント第一13章4~8節

副社長氏の一途な恋~執心が結んだ授かり婚~
真木
恋愛
相原麻衣子は、冷たく見えて情に厚い。彼女がいつも衝突ばかりしている、同期の「副社長氏」反田晃を想っているのは秘密だ。麻衣子はある日、晃と一夜を過ごした後、姿をくらます。数年後、晃はミス・アイハラという女性が小さな男の子の手を引いて暮らしているのを知って……。



スルドの声(交響) primeira desejo
桜のはなびら
現代文学
小柄な体型に地味な見た目。趣味もない。そんな目立たない少女は、心に少しだけ鬱屈した思いを抱えて生きてきた。
高校生になっても始めたのはバイトだけで、それ以外は変わり映えのない日々。
ある日の出会いが、彼女のそんな生活を一変させた。
出会ったのは、スルド。
サンバのパレードで打楽器隊が使用する打楽器の中でも特に大きな音を轟かせる大太鼓。
姉のこと。
両親のこと。
自分の名前。
生まれた時から自分と共にあったそれらへの想いを、少女はスルドの音に乗せて解き放つ。
※表紙はaiで作成しました。イメージです。実際のスルドはもっと高さのある大太鼓です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















