16 / 32
三
2
しおりを挟む
疲れが取れたかどうかは、わからない。
引き締める、というわけではないけれど、そんなことはシャワーを浴びれば意図せずとも頭の隅の角に追いやられる。
いつからか、そういう頭の構造になっていた。
桜木から一本「どれくらいで来れる?」とメールが返ってきていた。
時刻も目に付く、自分は遅れ気味なようだ。仕事の内容を見た時点で少し力が抜けたせいもあるだろう。
部屋を出るタイミングがお姉さんと重なった。彼女とは家の前で別れる。
軽バンは少しわかりにくい、隅の方に停まっていた。
「ごめん、ちょっと遅くなった」
「うっす、はよ。まあ“足舐め社長”だろ?」
「うん」
足舐め社長こと笹塚耕三さんは、アカリの太客だ。
指名の曜日は特に決まっていない。昼間が大半。しかし、土曜日だなんて珍しい。
こちらとしては昨日、出しすぎてしまったので有り難いには、有り難いけれど。
「土曜日は珍しいよな」
「俺も思ってたところ。家族サービスとか大切にするタイプだと思ってた」
「土曜に稼働してる会社も珍しくねーけど、まぁ関係ねぇよな」
桜木は運転をしながらちらっとこちらを見、赤信号で太股に触れてきた。
多分、からかっているのだ。
「何」
「別に」
一撫でしてくる桜木に何かを言ってはやりたいが、一度黙る。感情が纏まらない。
「…そういえば前沢さんに電話したって、」
「は?」
確かに。
取り繕って当たり前なことを言ってしまった。桜木は多分、意味不明に受け取っただろう。
少し身体が沸騰しそうだ。これは間違いなく、メンタル的な問題で。
あまりに意味不明だったのかもしれない、急に桜木は眉を顰め「なんかあったか」と、怪訝そうに聞いてきた。
「…いや、朝嬉しそうに言われたってだけ。別に電話しなくても、気付かなそうだったよ、あの人」
「…どーゆーこと?」
「デリヘルだかなんだかとお楽しみだったから」
「…は?何それ………笑えるな」
取って付けたような桜木の語尾は、言葉とはまるっきり反対の感情に聞こえた。
多分、察したのだ。自分の使った金は泡になったのだと。
「そんな暇あるならもう少し働いて欲しいよな。電話番なんて社長じゃなくても出来るし。なんで経営者ってそうなんだろうな」
意外だった。
「…珍しいね、オーナーの悪口なんて」
「別に。お前がいらんこと言うからだよ。まぁ良いけどね、諭吉がどこに派遣されようが」
「…はは、」
「なんだよ」
「かの福沢諭吉様をデリヘル扱いするなんて」
ははは、と灯が笑っていると、彼は居心地が悪そうに「そんなんじゃないわ」と呟く。
遅れ気味に出たのだけれど、時間通りに到着した。
灯が持ち物を確認していると、桜木は「120分だよな」と、わかっているだろう内容を確認をしてきた。
「うん、そう」
「じゃーえっと……足舐め社長は会社、午後スタートなのかな。微妙な時間だな」
「合わせたのかもね。まぁ関係ないでしょ」
「昼飯くらい買っとくか?」
「そのあと入らなければ」
最終確認を終え、「いってらっしゃい」と見送られた。桜木はいつも、そういうところはきちんとしているのだ。
高級ホテルの七階だった。
いつもより人通りがある空気感。
それでもやはり、社長が泊まるような場所なのだ、どこか厳然で非日常の空気。
こんこん、と扉を叩けばすぐに「いらっしゃい」と、初老で清潔な、柔らかい空気のおじさんが現れる。
考慮し、玄関に入ってから「アカリです」と名乗った。
彼はニコニコしながら「土曜日にご苦労様」と上品に労ってくれる。
微かに薫る、柑橘系の湿った匂い。
パリッとした白いシャツ。
「どうぞ」と促してくれる笹塚のどこか丁寧な所作に、毎回少し気後れしそうになる、それだけ高貴な雰囲気の人。
「お邪魔します、よろしくお願いします」
拝むように手を合わせ、挨拶をした。
彼がまさか“足舐め社長”と呼ばれているだなんて、知り合いはもちろん、すれ違った誰しもが想像をしないだろう。
その性癖の中で一ヶ所、高貴というよりも神経質な面がある。それは、通されたそのテーブルにトンと置いてある筒状の「除菌シート」だ。
まぁまぁと、彼はまず、いつも最初に聞く、「何か飲むかい?」と。そして受話器の前に行くのだ。
「じゃあ…ホットの紅茶を」とアカリが答えるとその場でオーダーし、そして自分は自前のミールをくるくるまわしコーヒーを作る。
ぶわっと、コーヒーの薫りがまわりを包んだ。
本当は自分に振る舞いたいのだろう、笹塚はそういう人だ。
しかし、初めて出会った頃にルールは説明した。飲食物はホテル等のオーダー品のみ。自身で持ち込んだ物をボーイに与えてはいけない、ということを。
アカリは紅茶が来るまでの間、それを眺め「いつか飲んでみたいです」と笹塚に言っておいた。
それは、本心だ。
「…そうだねぇ、是非飲ませてあげたいよ」
「本当にすみません」
「いやまぁ、当然だよね。それが良いんだよ。君は特にね。自衛は備えあって憂いなしだから」
例えば。
彼が一日、自分を貸し切ってくれたとしよう。どんな一日を過ごしてくれるのだろうか。
正直この人のそれは気になっていたりする。これはお金の問題ではなく。
「コーヒーの匂いって、落ち着きますよね」
「そうだね、いまはそれを楽しんでくれたら幸いだよ」
引き締める、というわけではないけれど、そんなことはシャワーを浴びれば意図せずとも頭の隅の角に追いやられる。
いつからか、そういう頭の構造になっていた。
桜木から一本「どれくらいで来れる?」とメールが返ってきていた。
時刻も目に付く、自分は遅れ気味なようだ。仕事の内容を見た時点で少し力が抜けたせいもあるだろう。
部屋を出るタイミングがお姉さんと重なった。彼女とは家の前で別れる。
軽バンは少しわかりにくい、隅の方に停まっていた。
「ごめん、ちょっと遅くなった」
「うっす、はよ。まあ“足舐め社長”だろ?」
「うん」
足舐め社長こと笹塚耕三さんは、アカリの太客だ。
指名の曜日は特に決まっていない。昼間が大半。しかし、土曜日だなんて珍しい。
こちらとしては昨日、出しすぎてしまったので有り難いには、有り難いけれど。
「土曜日は珍しいよな」
「俺も思ってたところ。家族サービスとか大切にするタイプだと思ってた」
「土曜に稼働してる会社も珍しくねーけど、まぁ関係ねぇよな」
桜木は運転をしながらちらっとこちらを見、赤信号で太股に触れてきた。
多分、からかっているのだ。
「何」
「別に」
一撫でしてくる桜木に何かを言ってはやりたいが、一度黙る。感情が纏まらない。
「…そういえば前沢さんに電話したって、」
「は?」
確かに。
取り繕って当たり前なことを言ってしまった。桜木は多分、意味不明に受け取っただろう。
少し身体が沸騰しそうだ。これは間違いなく、メンタル的な問題で。
あまりに意味不明だったのかもしれない、急に桜木は眉を顰め「なんかあったか」と、怪訝そうに聞いてきた。
「…いや、朝嬉しそうに言われたってだけ。別に電話しなくても、気付かなそうだったよ、あの人」
「…どーゆーこと?」
「デリヘルだかなんだかとお楽しみだったから」
「…は?何それ………笑えるな」
取って付けたような桜木の語尾は、言葉とはまるっきり反対の感情に聞こえた。
多分、察したのだ。自分の使った金は泡になったのだと。
「そんな暇あるならもう少し働いて欲しいよな。電話番なんて社長じゃなくても出来るし。なんで経営者ってそうなんだろうな」
意外だった。
「…珍しいね、オーナーの悪口なんて」
「別に。お前がいらんこと言うからだよ。まぁ良いけどね、諭吉がどこに派遣されようが」
「…はは、」
「なんだよ」
「かの福沢諭吉様をデリヘル扱いするなんて」
ははは、と灯が笑っていると、彼は居心地が悪そうに「そんなんじゃないわ」と呟く。
遅れ気味に出たのだけれど、時間通りに到着した。
灯が持ち物を確認していると、桜木は「120分だよな」と、わかっているだろう内容を確認をしてきた。
「うん、そう」
「じゃーえっと……足舐め社長は会社、午後スタートなのかな。微妙な時間だな」
「合わせたのかもね。まぁ関係ないでしょ」
「昼飯くらい買っとくか?」
「そのあと入らなければ」
最終確認を終え、「いってらっしゃい」と見送られた。桜木はいつも、そういうところはきちんとしているのだ。
高級ホテルの七階だった。
いつもより人通りがある空気感。
それでもやはり、社長が泊まるような場所なのだ、どこか厳然で非日常の空気。
こんこん、と扉を叩けばすぐに「いらっしゃい」と、初老で清潔な、柔らかい空気のおじさんが現れる。
考慮し、玄関に入ってから「アカリです」と名乗った。
彼はニコニコしながら「土曜日にご苦労様」と上品に労ってくれる。
微かに薫る、柑橘系の湿った匂い。
パリッとした白いシャツ。
「どうぞ」と促してくれる笹塚のどこか丁寧な所作に、毎回少し気後れしそうになる、それだけ高貴な雰囲気の人。
「お邪魔します、よろしくお願いします」
拝むように手を合わせ、挨拶をした。
彼がまさか“足舐め社長”と呼ばれているだなんて、知り合いはもちろん、すれ違った誰しもが想像をしないだろう。
その性癖の中で一ヶ所、高貴というよりも神経質な面がある。それは、通されたそのテーブルにトンと置いてある筒状の「除菌シート」だ。
まぁまぁと、彼はまず、いつも最初に聞く、「何か飲むかい?」と。そして受話器の前に行くのだ。
「じゃあ…ホットの紅茶を」とアカリが答えるとその場でオーダーし、そして自分は自前のミールをくるくるまわしコーヒーを作る。
ぶわっと、コーヒーの薫りがまわりを包んだ。
本当は自分に振る舞いたいのだろう、笹塚はそういう人だ。
しかし、初めて出会った頃にルールは説明した。飲食物はホテル等のオーダー品のみ。自身で持ち込んだ物をボーイに与えてはいけない、ということを。
アカリは紅茶が来るまでの間、それを眺め「いつか飲んでみたいです」と笹塚に言っておいた。
それは、本心だ。
「…そうだねぇ、是非飲ませてあげたいよ」
「本当にすみません」
「いやまぁ、当然だよね。それが良いんだよ。君は特にね。自衛は備えあって憂いなしだから」
例えば。
彼が一日、自分を貸し切ってくれたとしよう。どんな一日を過ごしてくれるのだろうか。
正直この人のそれは気になっていたりする。これはお金の問題ではなく。
「コーヒーの匂いって、落ち着きますよね」
「そうだね、いまはそれを楽しんでくれたら幸いだよ」
0
お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説


百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。


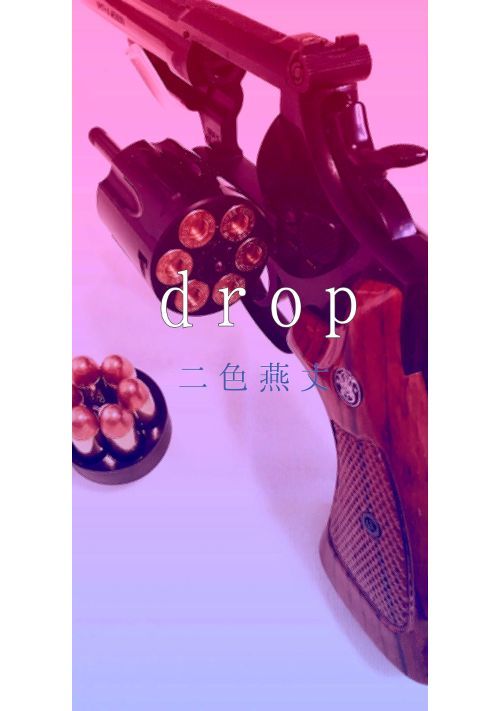

ハルとアキ
花町 シュガー
BL
『嗚呼、秘密よ。どうかもう少しだけ一緒に居させて……』
双子の兄、ハルの婚約者がどんな奴かを探るため、ハルのふりをして学園に入学するアキ。
しかし、その婚約者はとんでもない奴だった!?
「あんたにならハルをまかせてもいいかなって、そう思えたんだ。
だから、さよならが来るその時までは……偽りでいい。
〝俺〟を愛してーー
どうか気づいて。お願い、気づかないで」
----------------------------------------
【目次】
・本編(アキ編)〈俺様 × 訳あり〉
・各キャラクターの今後について
・中編(イロハ編)〈包容力 × 元気〉
・リクエスト編
・番外編
・中編(ハル編)〈ヤンデレ × ツンデレ〉
・番外編
----------------------------------------
*表紙絵:たまみたま様(@l0x0lm69) *
※ 笑いあり友情あり甘々ありの、切なめです。
※心理描写を大切に書いてます。
※イラスト・コメントお気軽にどうぞ♪
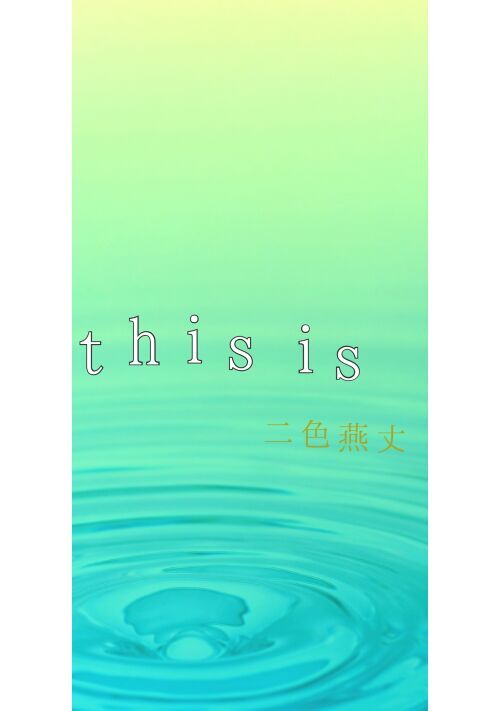
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















