48 / 64
懐古
2
しおりを挟む
甚だ生きた心地がしない。
懐古のその人が目の前に座って日本酒を飲んでいる。記憶にありふれたはずの光景だった。さして感情もなくただただ徳利から猪口へ液体を移し、口に運んでまた移し。それが一つの風景で、家庭の情緒に近いもので。
着流し、これもシックなグレーだが友禅だとわかるようなもの。昔の彼もそう、着物に執着があったように、蛍はそう思う。
薄い色に見えた髪は、10年近い年月を得て少し白髪混じりで、着流しの袖から覗く筋の浮いた、しかし細すぎない腕やきっちりしていない懐からの鎖骨、首筋に年月というよりは年齢を感じた。
あの頃母親は30代後半だった。10も歳の離れていたこの男は恐らく40代後半だったはずだ。いまはもう、50も半ばだろうか。
実のところ蛍は、この男のそういった詳しい物差しを知らない。父親であるかと問われれば、そうらしいがそれも母や祖父の口伝てのような気がしてしまっている。
何故ならば当の父親裕次郎が、自分を実子だと認めないからである。ここの詳細すら母には聞けない。
母が死に祖父と二人で暮らした短い間に、一度書類を見せられたような気がしなくはないが、なんせ蛍もその歳にはもう、受け入れる受け入れないの判断は正直許容になかった。なので曖昧なのである。
幼い頃からの積み重ねた知識には、母にとって今自分の目の前にふらっと、まるで猫のように姿を現したこの男は母の『恋人』であり、蛍の遺伝子上の『父親』とある。
しかしこの男、裕次郎から見れば蛍はなんなのか、正直よくわからないのだ。
ただ、事実としては、息子として受け入られなかった、母親もまた然り、妻として迎え入れられなかった、それだけのことで。
蛍と命名したのはどうやら別の人物、つまりは別の男だとか、そんな譫言も聞いた。実際どうなのか、自分がどこの何者なのかは今になってはもう、わからないのだ。
蛍は思う。
恐らくはどこかこの男の虚言じみた、ある意味、事実かもしれないと。この男は元来の作家だけあり、今回顧すれば虚言癖、妄想癖があったように思えてならない。ならばもしかすると自分にも、思い当たる節がある。
自分もある意味二重人格のような錯覚に陥る。所謂、涛川蛍か上柴楓かの違いなのだが。彼はそう、それをまだまだ受け入れないのではないか、そんな気がしてならない。
だが、何はともあれ。
結論として今目の前に対峙しているようだ。
膝を抱えて男を前にして浮かんでくるものは、蛍には案外何もなく。ただ理性とか、感情とかそんなものすら今は消し飛んでしまったような虚無、虚空を見ている。
この男の喉仏が優雅に上下する仕組みすら意識を滑り落ち、ただ、
あぁ流れ落ちるようだ。
そんな垂れ流すような思考回路は巡回をしない。延々とぶち当たる場所もなくどこかへ行って浮遊し、煙のように消えてしまう。
浮遊した蜉蝣のような、そんな意識。あれは一体どこを目指すのか誰も知らない。夕陽、だと言うのは人間の勝手な情緒だ。
ふと懐から煙管を出した父の姿を見て、蛍は歯を食い縛るような寒気を覚えた。
あの、寂れた狭い空間に染み付いた窓硝子とそれに浮かんだ水滴と気配の消え失せた母親、と、コンビニの安い焼酎のカップに伸びた手首と紺色の着物の袖。
今や煙管はその腕が、いつ持ったか解らないがそれを貪った後の一言、猛禽類、よりははっきりとした輪郭のその瞳で射ぬかれて薄唇が云うのは。
「君のせいで俺はこんな道を選んでしまったんだよ」
「…っ、」
無意識のとめどない妄想に近い回想から突如、引き戻された現実。
自分は今、幽体離脱のような呼吸をしていた。薬物過剰摂取や大量飲酒に近い、現実寄りの瞑想。思わず蛍は膝に顔を埋めて過呼吸を繰り返す。どっと冷や汗が全身を駆け巡る。生理的に手足が、痺れるような、痙攣のような震えをきたした。
「蛍、おい、落ち着け」
治まらない。
恐らく友人が隣で肩を抱いて背を擦ってくれている。しかしそんなもので懐古を解雇出来るならば、こんな呼吸気管は、心理は、前頭葉は悲鳴という概念を知らないで育つはずだ。
悲鳴?
あぁそうかこれは。
生きていることの、悲鳴なのか。
「どうした蛍。俺の顔を見てくれないかい?なぜ背ける」
「うるせぇ、てめぇ本気で、殺すぞ」
友人の低い一言に蛍ははっとした。
循環は瞬間にして止まってしまった。比喩なく心臓に、冷たい何か、鋭利な何かが突き立てられたような気がした。
底冷えする、腹の奥底からの歪な、しかし曖昧な塊になってしまったどろどろとした悲鳴に似ているそれは確実なる、殺意。
そう確信した瞬間に立ち上がった空太の腕を、思わず蛍は引き止めた。
空太のその腕は自分の痙攣とはまた違った震えをなしている。
「空太、だめ、」
「蛍、」
一瞬だけ蛍を見下ろした空太の眼の鋭さに、怯えた。確実なる男への憎悪。
しかしそれが一瞬だ。
蛍を見て困惑の色を見せてからまたしゃがみ、「蛍、」と、目元を拭ってくれた空太の指が震えている。
これも悲鳴だ。優しさも憎悪もすべて、感情とは、そうやって出来ている。
いまの自分は何故こうして友人を悲しませるのだろうかと蛍は模索する。それが目的ではないのに。
自意識過剰過ぎるのか。
溜め息は殺せる、感情も押し止められる。
ただ頭が悪い、自分を何度も殺せないで同じ事を何度こうして、
また一つはっと蛍は気が付いた。
これはそう、循環。同じ言葉で、同じ景色で、違う状況で、今ここに浮遊したこれは、巡回、迷回。
まだ立ち止まり、また立ち往生して飛散して廻って繰り返している、あの日から、ずっと。苛みは再燃して一酸化炭素が酸素を奪って脳の回転を沈静化させてしまっている。
諸悪の根元、然れど自分に。
懐古のその人が目の前に座って日本酒を飲んでいる。記憶にありふれたはずの光景だった。さして感情もなくただただ徳利から猪口へ液体を移し、口に運んでまた移し。それが一つの風景で、家庭の情緒に近いもので。
着流し、これもシックなグレーだが友禅だとわかるようなもの。昔の彼もそう、着物に執着があったように、蛍はそう思う。
薄い色に見えた髪は、10年近い年月を得て少し白髪混じりで、着流しの袖から覗く筋の浮いた、しかし細すぎない腕やきっちりしていない懐からの鎖骨、首筋に年月というよりは年齢を感じた。
あの頃母親は30代後半だった。10も歳の離れていたこの男は恐らく40代後半だったはずだ。いまはもう、50も半ばだろうか。
実のところ蛍は、この男のそういった詳しい物差しを知らない。父親であるかと問われれば、そうらしいがそれも母や祖父の口伝てのような気がしてしまっている。
何故ならば当の父親裕次郎が、自分を実子だと認めないからである。ここの詳細すら母には聞けない。
母が死に祖父と二人で暮らした短い間に、一度書類を見せられたような気がしなくはないが、なんせ蛍もその歳にはもう、受け入れる受け入れないの判断は正直許容になかった。なので曖昧なのである。
幼い頃からの積み重ねた知識には、母にとって今自分の目の前にふらっと、まるで猫のように姿を現したこの男は母の『恋人』であり、蛍の遺伝子上の『父親』とある。
しかしこの男、裕次郎から見れば蛍はなんなのか、正直よくわからないのだ。
ただ、事実としては、息子として受け入られなかった、母親もまた然り、妻として迎え入れられなかった、それだけのことで。
蛍と命名したのはどうやら別の人物、つまりは別の男だとか、そんな譫言も聞いた。実際どうなのか、自分がどこの何者なのかは今になってはもう、わからないのだ。
蛍は思う。
恐らくはどこかこの男の虚言じみた、ある意味、事実かもしれないと。この男は元来の作家だけあり、今回顧すれば虚言癖、妄想癖があったように思えてならない。ならばもしかすると自分にも、思い当たる節がある。
自分もある意味二重人格のような錯覚に陥る。所謂、涛川蛍か上柴楓かの違いなのだが。彼はそう、それをまだまだ受け入れないのではないか、そんな気がしてならない。
だが、何はともあれ。
結論として今目の前に対峙しているようだ。
膝を抱えて男を前にして浮かんでくるものは、蛍には案外何もなく。ただ理性とか、感情とかそんなものすら今は消し飛んでしまったような虚無、虚空を見ている。
この男の喉仏が優雅に上下する仕組みすら意識を滑り落ち、ただ、
あぁ流れ落ちるようだ。
そんな垂れ流すような思考回路は巡回をしない。延々とぶち当たる場所もなくどこかへ行って浮遊し、煙のように消えてしまう。
浮遊した蜉蝣のような、そんな意識。あれは一体どこを目指すのか誰も知らない。夕陽、だと言うのは人間の勝手な情緒だ。
ふと懐から煙管を出した父の姿を見て、蛍は歯を食い縛るような寒気を覚えた。
あの、寂れた狭い空間に染み付いた窓硝子とそれに浮かんだ水滴と気配の消え失せた母親、と、コンビニの安い焼酎のカップに伸びた手首と紺色の着物の袖。
今や煙管はその腕が、いつ持ったか解らないがそれを貪った後の一言、猛禽類、よりははっきりとした輪郭のその瞳で射ぬかれて薄唇が云うのは。
「君のせいで俺はこんな道を選んでしまったんだよ」
「…っ、」
無意識のとめどない妄想に近い回想から突如、引き戻された現実。
自分は今、幽体離脱のような呼吸をしていた。薬物過剰摂取や大量飲酒に近い、現実寄りの瞑想。思わず蛍は膝に顔を埋めて過呼吸を繰り返す。どっと冷や汗が全身を駆け巡る。生理的に手足が、痺れるような、痙攣のような震えをきたした。
「蛍、おい、落ち着け」
治まらない。
恐らく友人が隣で肩を抱いて背を擦ってくれている。しかしそんなもので懐古を解雇出来るならば、こんな呼吸気管は、心理は、前頭葉は悲鳴という概念を知らないで育つはずだ。
悲鳴?
あぁそうかこれは。
生きていることの、悲鳴なのか。
「どうした蛍。俺の顔を見てくれないかい?なぜ背ける」
「うるせぇ、てめぇ本気で、殺すぞ」
友人の低い一言に蛍ははっとした。
循環は瞬間にして止まってしまった。比喩なく心臓に、冷たい何か、鋭利な何かが突き立てられたような気がした。
底冷えする、腹の奥底からの歪な、しかし曖昧な塊になってしまったどろどろとした悲鳴に似ているそれは確実なる、殺意。
そう確信した瞬間に立ち上がった空太の腕を、思わず蛍は引き止めた。
空太のその腕は自分の痙攣とはまた違った震えをなしている。
「空太、だめ、」
「蛍、」
一瞬だけ蛍を見下ろした空太の眼の鋭さに、怯えた。確実なる男への憎悪。
しかしそれが一瞬だ。
蛍を見て困惑の色を見せてからまたしゃがみ、「蛍、」と、目元を拭ってくれた空太の指が震えている。
これも悲鳴だ。優しさも憎悪もすべて、感情とは、そうやって出来ている。
いまの自分は何故こうして友人を悲しませるのだろうかと蛍は模索する。それが目的ではないのに。
自意識過剰過ぎるのか。
溜め息は殺せる、感情も押し止められる。
ただ頭が悪い、自分を何度も殺せないで同じ事を何度こうして、
また一つはっと蛍は気が付いた。
これはそう、循環。同じ言葉で、同じ景色で、違う状況で、今ここに浮遊したこれは、巡回、迷回。
まだ立ち止まり、また立ち往生して飛散して廻って繰り返している、あの日から、ずっと。苛みは再燃して一酸化炭素が酸素を奪って脳の回転を沈静化させてしまっている。
諸悪の根元、然れど自分に。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説
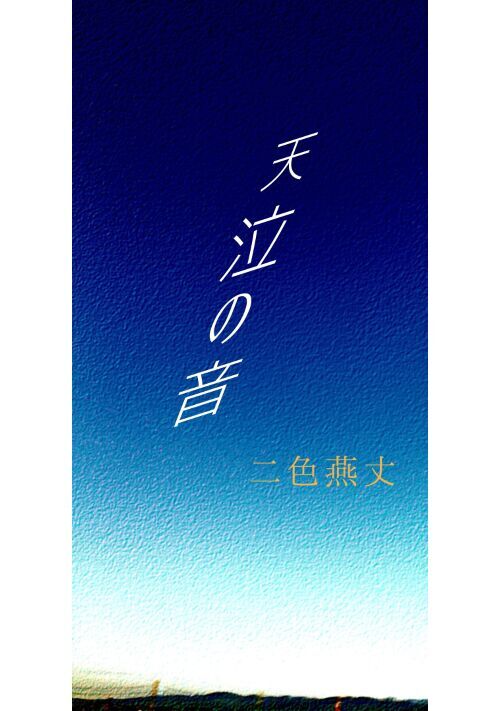

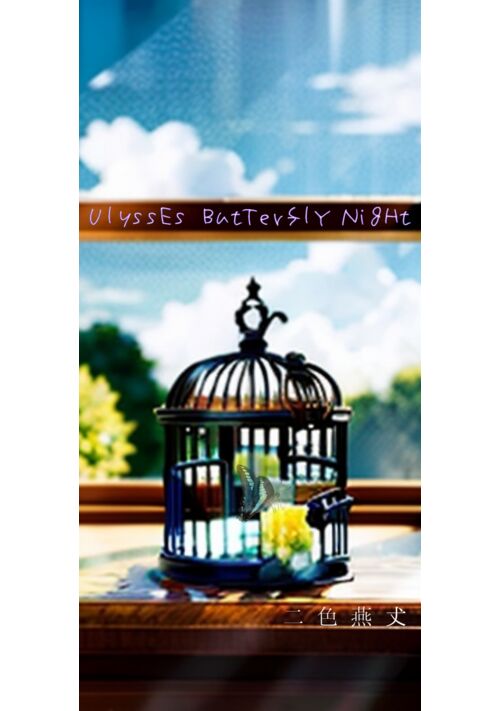
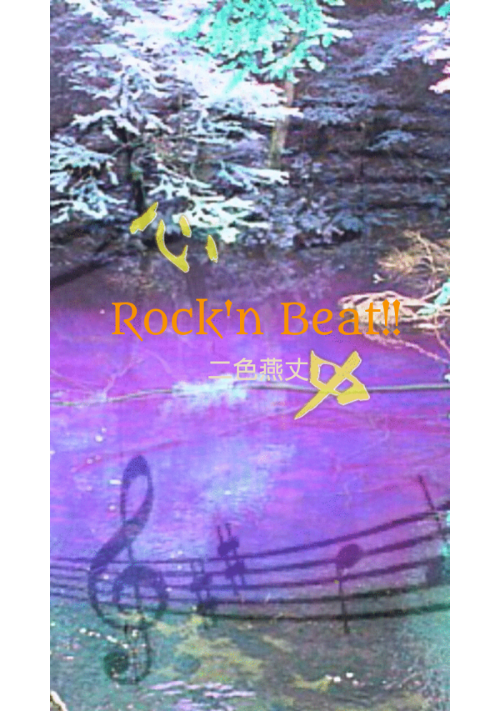



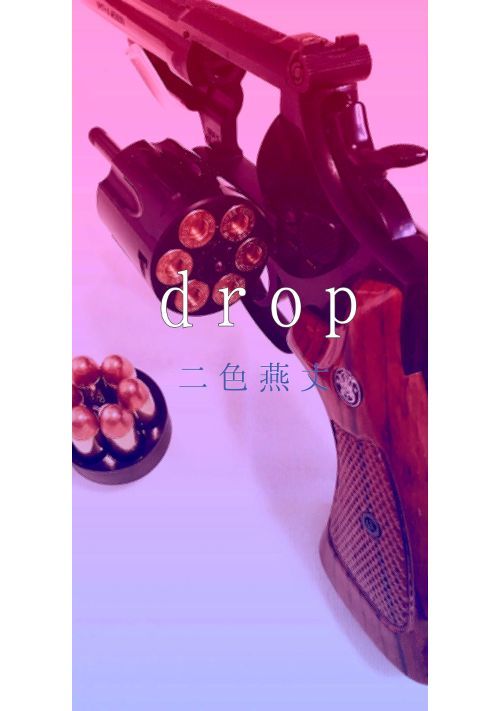
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















