4 / 64
月夜
4
しおりを挟む
たまたま前回の“月夜”で、直木賞候補になってしまうという、作家デビューから5年目にしてよくわからない奇跡が起きてしまったため、所謂“雰囲気小説”を書けとの要請が出版社から来てしまったのだ。
はぁ、雰囲気小説ねぇ。わりかし自分は雰囲気小説家ですよ。中身はすかすかで構いませんかと蛍、もとい上柴楓が開き直った結果、構いませんと言われてしまい、1話の締め切りまであと半月にして15枚しか進んでいないのである。これは流石によくない。
少し前にタイトルも“雰囲気”で出したら流石にそれは一蹴されてしまった。そりゃ、そうである。
最早いっそのこと好きな小説を書いた方が血肉になるのではないか、大体雰囲気小説とはどういうことなのかと悶々としてしまう。
あ、この際だからアイコスクソアパレル野郎と言う単語、頂こうかな。かなり痛烈だ。
それにはまず吸ってみないことにはわかんないよなぁ、こういうのって。何がクソなんだろうか。アパレルは関係あるのだろうか。何がふざけてるのだろうか。聞いておけばよかったと悔やまれる。
****
ハイライトの煙は、上に綺麗に真っ直ぐ登る。そんな拙いきっかけでタバコを始めた。けして、死んだ母親がハイライトを吸っていたからではない。
ただ、見ていると思い出す。夜のネオンと白い煙。池の橋に凭れかかった彼の言葉は、今でも胸に染み付いて離れない。
****
あ、いいんじゃないの。
しかしなんだかなぁ、入っていけないなぁイマイチ。文章的には間違いなく後のやつなのだがどうもはっきりと輪郭が浮かばない。それとも雰囲気さえ良ければいいの?雰囲気さえ良ければ。
書いていて思わず溜め息が漏れた。
その聴覚に忍び込んだ、パシャっと言う聞き慣れた人工的なポラロイドの音。
目の前を見ればいつの間にか、空太が帰ってきていた。蛍は露骨に嫌そうに、眉根を寄せる。
かぐやが、蛍の手元からするりと去っていく。いつの間に側にいたのか。
空太が苦笑いしながら、ポラロイドカメラから出てきた写真を取り出し、蛍の目の前で振っている。
「やめろと何回言ったら」
「悪ぃ悪ぃ。かぐやとのベストショットだなぁと思ってついな。ほら」
「いらん」
へらへらしながら渡してくる空太の写真を、受け取りつつも言葉では一蹴してみせる。
確かに良い出来かもしれない。
この男は本当に昔からなんなんだと、蛍の中にある不機嫌さに似たものが問う。どうも空気というものを持っていくし持ってくる。
「…夕飯は、」
「あぁ、さつきちゃんがな、肉くれたよ。なんか地鶏だって」
「あぁ、茄子取れたし、うーん炒めようか」
「茄子?」
「秋茄子」
空太とどうも会話が噛み合っていない気がするがまぁ、いい。
蛍が筆を置いて立ち上がると、空太が代わりに向かい側へ座り、書きかけの原稿を手に取り、読み始めた。
「上柴先生、どうですか」
「どうもこうもない。全然だよ」
「こっちはボツ?」
「基本的に今回はみんなボツ。全然浮かばないんだ。
大体なんだと思う?雰囲気小説って」
「うーん…なんだろう。
でもそれってさ、捉え方じゃねぇの?野山さんもさ、“上柴楓”の雰囲気を求めてるんじゃねぇの?」
「…つまり?」
「だから、お前が書きたいようなのでいっぺんだしてみたら?」
「…うーん…」
わからない。
ちなみに野山さんとは、上柴楓、つまりは涛川蛍の書籍編集担当だ。
今日、空太がここに来ているのも、きっと野山さんに一言添えられているからに違いない。でなければ出版社の営業だなんて、しかもその出版社直々の本屋になんて来る用事がないはずだ。
あと考えられるとすれば…。
「まだ、表紙にはちょっと…」
「ん?うん。まぁ月刊の短編連作だし気長にいくよ」
その蛍の予想も外れたようだ。
空太も実は、これまた売れない画家である。幸か不幸かこの男は、デビュー当時から蛍の単行本、文庫本の表紙を担当しているのである。
はぁ、雰囲気小説ねぇ。わりかし自分は雰囲気小説家ですよ。中身はすかすかで構いませんかと蛍、もとい上柴楓が開き直った結果、構いませんと言われてしまい、1話の締め切りまであと半月にして15枚しか進んでいないのである。これは流石によくない。
少し前にタイトルも“雰囲気”で出したら流石にそれは一蹴されてしまった。そりゃ、そうである。
最早いっそのこと好きな小説を書いた方が血肉になるのではないか、大体雰囲気小説とはどういうことなのかと悶々としてしまう。
あ、この際だからアイコスクソアパレル野郎と言う単語、頂こうかな。かなり痛烈だ。
それにはまず吸ってみないことにはわかんないよなぁ、こういうのって。何がクソなんだろうか。アパレルは関係あるのだろうか。何がふざけてるのだろうか。聞いておけばよかったと悔やまれる。
****
ハイライトの煙は、上に綺麗に真っ直ぐ登る。そんな拙いきっかけでタバコを始めた。けして、死んだ母親がハイライトを吸っていたからではない。
ただ、見ていると思い出す。夜のネオンと白い煙。池の橋に凭れかかった彼の言葉は、今でも胸に染み付いて離れない。
****
あ、いいんじゃないの。
しかしなんだかなぁ、入っていけないなぁイマイチ。文章的には間違いなく後のやつなのだがどうもはっきりと輪郭が浮かばない。それとも雰囲気さえ良ければいいの?雰囲気さえ良ければ。
書いていて思わず溜め息が漏れた。
その聴覚に忍び込んだ、パシャっと言う聞き慣れた人工的なポラロイドの音。
目の前を見ればいつの間にか、空太が帰ってきていた。蛍は露骨に嫌そうに、眉根を寄せる。
かぐやが、蛍の手元からするりと去っていく。いつの間に側にいたのか。
空太が苦笑いしながら、ポラロイドカメラから出てきた写真を取り出し、蛍の目の前で振っている。
「やめろと何回言ったら」
「悪ぃ悪ぃ。かぐやとのベストショットだなぁと思ってついな。ほら」
「いらん」
へらへらしながら渡してくる空太の写真を、受け取りつつも言葉では一蹴してみせる。
確かに良い出来かもしれない。
この男は本当に昔からなんなんだと、蛍の中にある不機嫌さに似たものが問う。どうも空気というものを持っていくし持ってくる。
「…夕飯は、」
「あぁ、さつきちゃんがな、肉くれたよ。なんか地鶏だって」
「あぁ、茄子取れたし、うーん炒めようか」
「茄子?」
「秋茄子」
空太とどうも会話が噛み合っていない気がするがまぁ、いい。
蛍が筆を置いて立ち上がると、空太が代わりに向かい側へ座り、書きかけの原稿を手に取り、読み始めた。
「上柴先生、どうですか」
「どうもこうもない。全然だよ」
「こっちはボツ?」
「基本的に今回はみんなボツ。全然浮かばないんだ。
大体なんだと思う?雰囲気小説って」
「うーん…なんだろう。
でもそれってさ、捉え方じゃねぇの?野山さんもさ、“上柴楓”の雰囲気を求めてるんじゃねぇの?」
「…つまり?」
「だから、お前が書きたいようなのでいっぺんだしてみたら?」
「…うーん…」
わからない。
ちなみに野山さんとは、上柴楓、つまりは涛川蛍の書籍編集担当だ。
今日、空太がここに来ているのも、きっと野山さんに一言添えられているからに違いない。でなければ出版社の営業だなんて、しかもその出版社直々の本屋になんて来る用事がないはずだ。
あと考えられるとすれば…。
「まだ、表紙にはちょっと…」
「ん?うん。まぁ月刊の短編連作だし気長にいくよ」
その蛍の予想も外れたようだ。
空太も実は、これまた売れない画家である。幸か不幸かこの男は、デビュー当時から蛍の単行本、文庫本の表紙を担当しているのである。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説
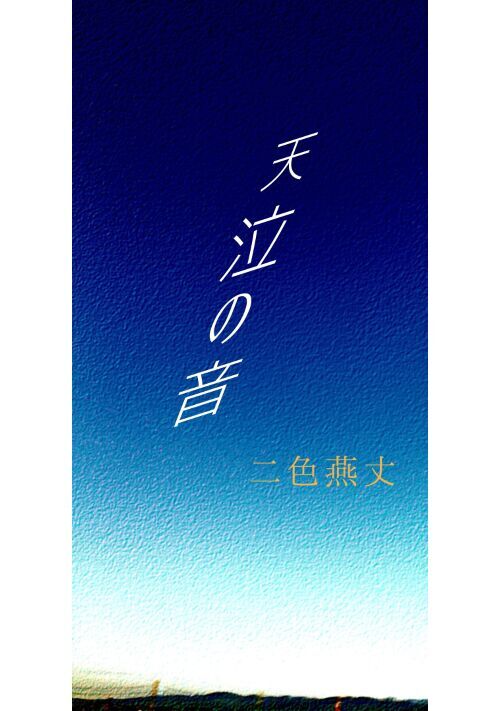

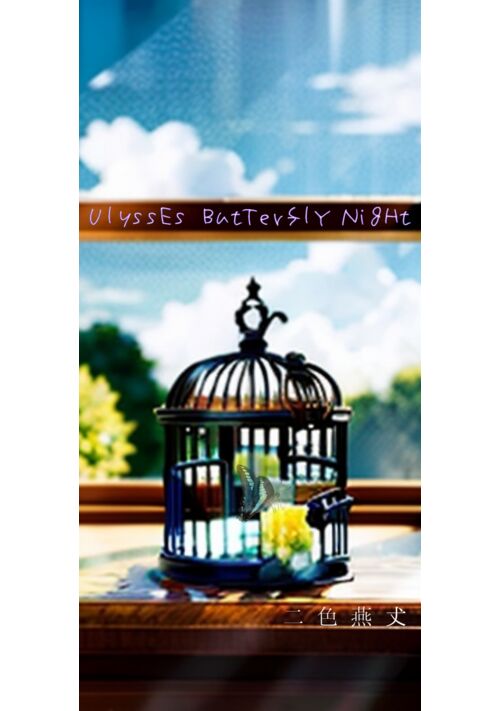
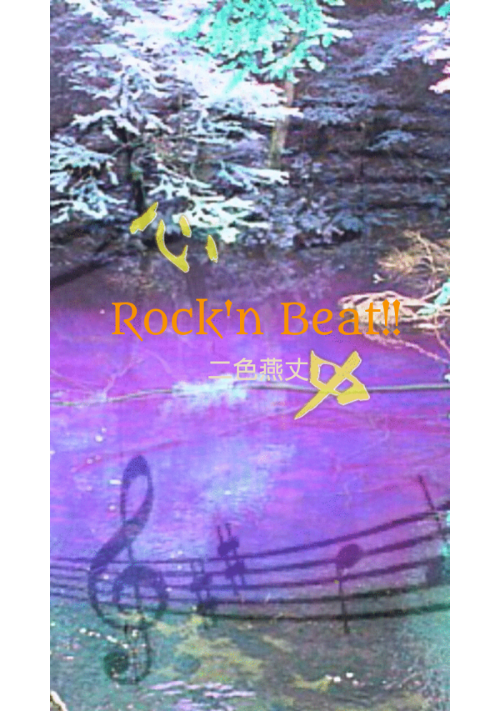



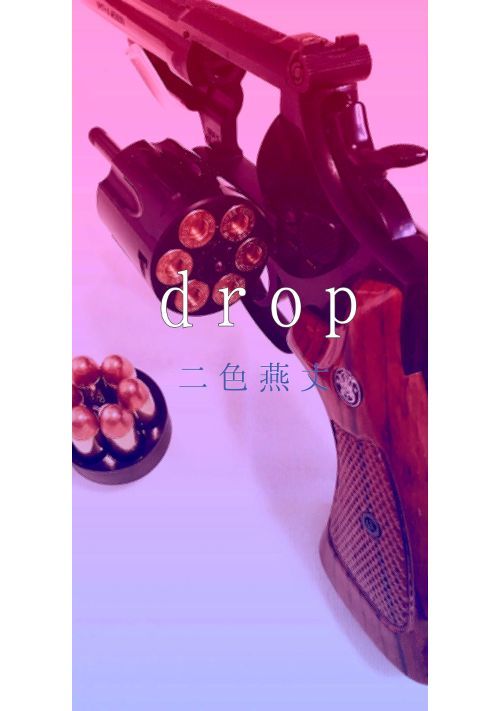
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















