114 / 129
Get So Hell?
前編5
しおりを挟む
…右耳に触れていることに気付く。
寒くて感覚が麻痺している。
船の影響か山の影響か。痛いのかなんなのかわからない。
手で温もってきた、うぉお、じんじんする。熱い時は耳に触れるものだがなるほど、耳はそもそも一番冷たいんだっけか、雪に馴染んだ感触を思い出す。
北海道での初日、その地を焼け跡だと思った。京の大火事のような見栄えだったからだ。
…去ったからか、わりと疲れていたんだなと気付く余裕が出来たかもしれない。
京を去ってからの日々…思い出せることもあるが、嫌な事が圧倒的に多い……のかもしれない、それすらイマイチわからない。
茶坊主はすぐに綿入れと新しい作務衣を持ってくる。
…多分、遠回しに警戒している。拳銃のせいもあるだろう。
寺側は役人の持ち物を預かる訳にもいかないし、だからといって、これは武器だ。言うことも躊躇われるのだろうし。
ちらちら眺める茶坊主を前に、気に止めない態度を試みあっさりと綿入れを借りる。
外套よりも軽いし、やはり馴染みがある。
「……洋装ってぇ、こりゃぁ、どやって洗うんです?そんの薄い肌着?は洗えそうですが…」
「あ、あー…羊毛ってもんらしいが」
獣の毛らしい、等と言ってはいけないような気がする。
「まぁ…川は近くにあったよね」
「え、え!そげなこと、お役人様にさせられま」
「あ、こう見えて昔は坊主をやってたから」
坊主時代もあんまり坊主と思われてなかったけどね。
「え、そーなんですかぁ?」
「そーなんです。
まぁ、気にしないで欲しい。自分の物だから自分でやるよ」
「しっかしぃ、この辺の川ばシバれますよ」
うーん、と首を傾げながら、茶坊主は「まずぁ、朝餉の用意しますねぇ」と下がった。
…まぁ、どこも「来るもの拒まず去るもの追わず」だったなと、少し懐かしさも感じるのだが。
朝飯を済ませ川へ行くと、小姓たちはちらほらと、洗濯の準備をしている。
坊主時代、それこそ下っ端で洗濯なんかをしていた頃。ついでに魚を手掴みしこっそり台所を使っていた。
それがそうだ…あの従者が兎を捌いて持ち込んだ時、自分はそれを叱る立場にいたな。
川でよく、水浴びもしていたよなぁ、あいつ。
懐かしい。
「………」
桶に水を組もうとしたが、しゃがんだだけで水の冷たさがわかる。
側で泳ぐ魚が鮮明に見える。とても綺麗な川だ。
意識せず自然と木の枝を探している自分に気付く。あぁそうか、暫く野宿もあったから、当たり前に魚を狩るという感覚が身に付いてしまっている。
京も冬は寒いが、流石にここまでではなかった。雪だって、これ程重く残らない。
それを何年も見ることになったのだが、舞う姿は綺麗なのもので、空気も澄む。しかし積もると面倒臭い。
「………」
桶に水を入れる。ここに手を突っ込むのは確かに躊躇われるなと、やり場なく魚を枝に刺してみる。
はぁーと息を吐く。まだ白いんだなと、思い付きよりも、反射的に。桶の水を頭から被ってみた。どうしてそういう衝動に駆られたかは不明である。
少しスッキリ…いや、寒いなこれは。寒いというか痛いな…。
思った瞬間には「お役人様っ!」と、小姓が寄ってきてしまった。
多分、気がどうかしていると思われた。いけないいけない。
小姓は、濡れた朱鷺貴と側にある魚や洗濯物を眺め「まずぁ…」と俯く。
「朝餉の薪、まだぁ、ありますんで…湯、沸かしますね…」
少し不躾だったなと、「さっき漁師に貰った。夕飯に魚でも食ってくれ…」と魚を渡し、それから有難く湯浴みをした。
昔は早湯だったもんだが、寒い地に滞在していたせいか、最近はめっきり長湯になった。
丁度良い頃合かなと、思ったより早く冷めてきた湯を桶に汲み、川へは戻らず洗濯を始めた。
一人が始めれば、他の者も使いやすいだろう。現に、湯を使う者も現れた。
久しぶりだったからだろうか、洗っているうちに下地の襟の折り返しが消えた。
「…うーん」
まぁ、別にいいか。折り曲げて干すんだろうか…。
袖元の釦が消えている。まぁ、これは別にいい。
というか正直邪魔だったから丁度いい。全部取りたいくらいだ。
始めは遠慮がちだった小姓たちが、「手際ぁいーんですね…」と、気付けば皆集まっている。
「お役人さんば、元はどん辺のお寺にいたんですか?」
「………今は無いけど、ここから遠いよ。西の方」
「へぇ、」
「雪もこれほど降らなかった。結構、綺麗だよな」
「私んらには、やんなるほどですよ。そんじゃぁ、蝦夷なんてぇ、苦労しましたねぇ」
「確かに驚いた。雪がな、灰だか…桜かもわからなかったんだよ」
そうですかぁ。と会話は終わる。
雪掻きを手伝い、一宿一飯の礼とし核心は互いに触れないまま、寺を去ることにする。
「貴殿の旅路に幸あらんことを」
お守りを貰った、懐かしいものだ。
多分、これくらいの距離感がいいのだと感じる。
やはり政府とその他での乖離があるようだが、多分この地はまだマシな方だろう。
寺院は、財政案により少し逼迫し始めている。
東京府まではまだ遠く。
その地がまだ「武蔵」と呼ばれていた頃。半年程は滞在していた。
あの頃、世話になった寺と同じ名前の寺が燃える事件があった。
そんな日常に身を置きその殺伐を感じながらも、どこか遠くのことのように感じていた当時。
その、燃えた方の寺は当時外交に使われていた。
今は再建されまた外交に使われていると聞く。
寒くて感覚が麻痺している。
船の影響か山の影響か。痛いのかなんなのかわからない。
手で温もってきた、うぉお、じんじんする。熱い時は耳に触れるものだがなるほど、耳はそもそも一番冷たいんだっけか、雪に馴染んだ感触を思い出す。
北海道での初日、その地を焼け跡だと思った。京の大火事のような見栄えだったからだ。
…去ったからか、わりと疲れていたんだなと気付く余裕が出来たかもしれない。
京を去ってからの日々…思い出せることもあるが、嫌な事が圧倒的に多い……のかもしれない、それすらイマイチわからない。
茶坊主はすぐに綿入れと新しい作務衣を持ってくる。
…多分、遠回しに警戒している。拳銃のせいもあるだろう。
寺側は役人の持ち物を預かる訳にもいかないし、だからといって、これは武器だ。言うことも躊躇われるのだろうし。
ちらちら眺める茶坊主を前に、気に止めない態度を試みあっさりと綿入れを借りる。
外套よりも軽いし、やはり馴染みがある。
「……洋装ってぇ、こりゃぁ、どやって洗うんです?そんの薄い肌着?は洗えそうですが…」
「あ、あー…羊毛ってもんらしいが」
獣の毛らしい、等と言ってはいけないような気がする。
「まぁ…川は近くにあったよね」
「え、え!そげなこと、お役人様にさせられま」
「あ、こう見えて昔は坊主をやってたから」
坊主時代もあんまり坊主と思われてなかったけどね。
「え、そーなんですかぁ?」
「そーなんです。
まぁ、気にしないで欲しい。自分の物だから自分でやるよ」
「しっかしぃ、この辺の川ばシバれますよ」
うーん、と首を傾げながら、茶坊主は「まずぁ、朝餉の用意しますねぇ」と下がった。
…まぁ、どこも「来るもの拒まず去るもの追わず」だったなと、少し懐かしさも感じるのだが。
朝飯を済ませ川へ行くと、小姓たちはちらほらと、洗濯の準備をしている。
坊主時代、それこそ下っ端で洗濯なんかをしていた頃。ついでに魚を手掴みしこっそり台所を使っていた。
それがそうだ…あの従者が兎を捌いて持ち込んだ時、自分はそれを叱る立場にいたな。
川でよく、水浴びもしていたよなぁ、あいつ。
懐かしい。
「………」
桶に水を組もうとしたが、しゃがんだだけで水の冷たさがわかる。
側で泳ぐ魚が鮮明に見える。とても綺麗な川だ。
意識せず自然と木の枝を探している自分に気付く。あぁそうか、暫く野宿もあったから、当たり前に魚を狩るという感覚が身に付いてしまっている。
京も冬は寒いが、流石にここまでではなかった。雪だって、これ程重く残らない。
それを何年も見ることになったのだが、舞う姿は綺麗なのもので、空気も澄む。しかし積もると面倒臭い。
「………」
桶に水を入れる。ここに手を突っ込むのは確かに躊躇われるなと、やり場なく魚を枝に刺してみる。
はぁーと息を吐く。まだ白いんだなと、思い付きよりも、反射的に。桶の水を頭から被ってみた。どうしてそういう衝動に駆られたかは不明である。
少しスッキリ…いや、寒いなこれは。寒いというか痛いな…。
思った瞬間には「お役人様っ!」と、小姓が寄ってきてしまった。
多分、気がどうかしていると思われた。いけないいけない。
小姓は、濡れた朱鷺貴と側にある魚や洗濯物を眺め「まずぁ…」と俯く。
「朝餉の薪、まだぁ、ありますんで…湯、沸かしますね…」
少し不躾だったなと、「さっき漁師に貰った。夕飯に魚でも食ってくれ…」と魚を渡し、それから有難く湯浴みをした。
昔は早湯だったもんだが、寒い地に滞在していたせいか、最近はめっきり長湯になった。
丁度良い頃合かなと、思ったより早く冷めてきた湯を桶に汲み、川へは戻らず洗濯を始めた。
一人が始めれば、他の者も使いやすいだろう。現に、湯を使う者も現れた。
久しぶりだったからだろうか、洗っているうちに下地の襟の折り返しが消えた。
「…うーん」
まぁ、別にいいか。折り曲げて干すんだろうか…。
袖元の釦が消えている。まぁ、これは別にいい。
というか正直邪魔だったから丁度いい。全部取りたいくらいだ。
始めは遠慮がちだった小姓たちが、「手際ぁいーんですね…」と、気付けば皆集まっている。
「お役人さんば、元はどん辺のお寺にいたんですか?」
「………今は無いけど、ここから遠いよ。西の方」
「へぇ、」
「雪もこれほど降らなかった。結構、綺麗だよな」
「私んらには、やんなるほどですよ。そんじゃぁ、蝦夷なんてぇ、苦労しましたねぇ」
「確かに驚いた。雪がな、灰だか…桜かもわからなかったんだよ」
そうですかぁ。と会話は終わる。
雪掻きを手伝い、一宿一飯の礼とし核心は互いに触れないまま、寺を去ることにする。
「貴殿の旅路に幸あらんことを」
お守りを貰った、懐かしいものだ。
多分、これくらいの距離感がいいのだと感じる。
やはり政府とその他での乖離があるようだが、多分この地はまだマシな方だろう。
寺院は、財政案により少し逼迫し始めている。
東京府まではまだ遠く。
その地がまだ「武蔵」と呼ばれていた頃。半年程は滞在していた。
あの頃、世話になった寺と同じ名前の寺が燃える事件があった。
そんな日常に身を置きその殺伐を感じながらも、どこか遠くのことのように感じていた当時。
その、燃えた方の寺は当時外交に使われていた。
今は再建されまた外交に使われていると聞く。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説


Get So Hell? 2nd!
二色燕𠀋
歴史・時代
なんちゃって幕末。
For full sound hope,Oh so sad sound.
※前編 Get So Hell?
※過去編 月影之鳥


大日本帝国領ハワイから始まる太平洋戦争〜真珠湾攻撃?そんなの知りません!〜
雨宮 徹
歴史・時代
1898年アメリカはスペインと戦争に敗れる。本来、アメリカが支配下に置くはずだったハワイを、大日本帝国は手中に収めることに成功する。
そして、時は1941年。太平洋戦争が始まると、大日本帝国はハワイを起点に太平洋全域への攻撃を開始する。
これは、史実とは異なる太平洋戦争の物語。
主要登場人物……山本五十六、南雲忠一、井上成美
※歴史考証は皆無です。中には現実性のない作戦もあります。ぶっ飛んだ物語をお楽しみください。
※根本から史実と異なるため、艦隊の動き、編成などは史実と大きく異なります。
※歴史初心者にも分かりやすいように、言葉などを現代風にしています。

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――
黒鯛の刺身♪
歴史・時代
戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。
一般には武田勝頼と記されることが多い。
……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。
信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。
つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。
一介の後見人の立場でしかない。
織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。
……これは、そんな悲運の名将のお話である。
【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵
【注意】……武田贔屓のお話です。
所説あります。
あくまでも一つのお話としてお楽しみください。

独裁者・武田信玄
いずもカリーシ
歴史・時代
歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!
平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。
『事実は小説よりも奇なり』
この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……
歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。
過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。
【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い
【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形
【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人
【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある
【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である
この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。
(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
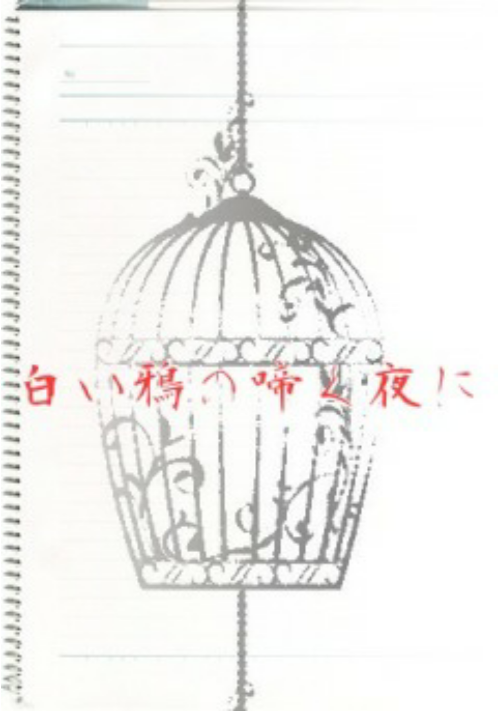
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















