お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

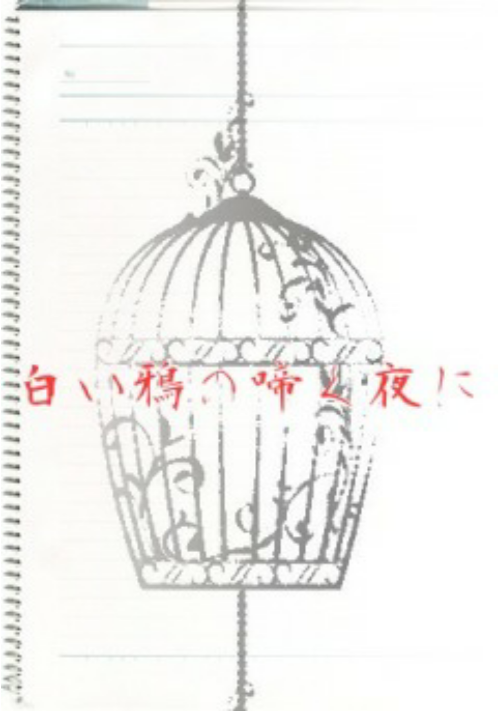

枢軸国
よもぎもちぱん
歴史・時代
時は1919年
第一次世界大戦の敗戦によりドイツ帝国は滅亡した。皇帝陛下 ヴィルヘルム二世の退位により、ドイツは共和制へと移行する。ヴェルサイユ条約により1320億金マルク 日本円で200兆円もの賠償金を課される。これに激怒したのは偉大なる我らが総統閣下"アドルフ ヒトラー"である。結果的に敗戦こそしたものの彼の及ぼした影響は非常に大きかった。
主人公はソフィア シュナイダー
彼女もまた、ドイツに転生してきた人物である。前世である2010年頃の記憶を全て保持しており、映像を写真として記憶することが出来る。
生き残る為に、彼女は持てる知識を総動員して戦う
偉大なる第三帝国に栄光あれ!
Sieg Heil(勝利万歳!)

Get So Hell? 2nd!
二色燕𠀋
歴史・時代
なんちゃって幕末。
For full sound hope,Oh so sad sound.
※前編 Get So Hell?
※過去編 月影之鳥


ノスタルジック・エゴイスト
二色燕𠀋
現代文学
生きることは辛くはない
世界はただ、丸く回転している
生ゴミみたいなノスタルジック
「メクる」「小説家になろう」掲載。
イラスト:Odd tail 様
※ごく一部レーティングページ、※←あり

鬼面の忍者 R15版
九情承太郎
歴史・時代
陽花「ヤングでムッツリな服部半蔵が主人公の戦国コメディ。始まるざますよ!」
更紗「読むでがんす!」
夏美「ふんがー!」
月乃「まともに始めなさいよ!」
服部半蔵&四人の忍者嫁部隊が、徳川軍団の快進撃に貢献するチープでファンキーな歴史ライトノベルだぜ、ベイベー!
※本作品は、2016年3月10日に公開された「鬼面の忍者」を再編集し、お色気シーンを強化したイヤんバカン版です。
※カクヨムでの重複投稿をしています。
表紙は、画像生成AIで出力したイラストです。

獅子の末裔
卯花月影
歴史・時代
未だ戦乱続く近江の国に生まれた蒲生氏郷。主家・六角氏を揺るがした六角家騒動がようやく落ち着いてきたころ、目の前に現れたのは天下を狙う織田信長だった。
和歌をこよなく愛する温厚で無力な少年は、信長にその非凡な才を見いだされ、戦国武将として成長し、開花していく。
前作「滝川家の人びと」の続編です。途中、エピソードの被りがありますが、蒲生氏郷視点で描かれます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















