あなたにおすすめの小説

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ
朽縄咲良
歴史・時代
【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】
戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。
永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。
信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。
この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。
*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

織田信長 -尾州払暁-
藪から犬
歴史・時代
織田信長は、戦国の世における天下統一の先駆者として一般に強くイメージされますが、当然ながら、生まれついてそうであるわけはありません。
守護代・織田大和守家の家来(傍流)である弾正忠家の家督を継承してから、およそ14年間を尾張(現・愛知県西部)の平定に費やしています。そして、そのほとんどが一族間での骨肉の争いであり、一歩踏み外せば死に直結するような、四面楚歌の道のりでした。
織田信長という人間を考えるとき、この彼の青春時代というのは非常に色濃く映ります。
そこで、本作では、天文16年(1547年)~永禄3年(1560年)までの13年間の織田信長の足跡を小説としてじっくりとなぞってみようと思いたった次第です。
毎週の月曜日00:00に次話公開を目指しています。
スローペースの拙稿ではありますが、お付き合いいただければ嬉しいです。
(2022.04.04)
※信長公記を下地としていますが諸出来事の年次比定を含め随所に著者の創作および定説ではない解釈等がありますのでご承知置きください。
※アルファポリスの仕様上、「HOTランキング用ジャンル選択」欄を「男性向け」に設定していますが、区別する意図はとくにありません。

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
勝利のために走るのではない。
生きるために走る者は、
傷を負いながらも、歩みを止めない。
戦国という時代の只中で、
彼らは何を失い、
走り続けたのか。
滝川一益と、その郎党。
これは、勝者の物語ではない。
生き延びた者たちの記録である。
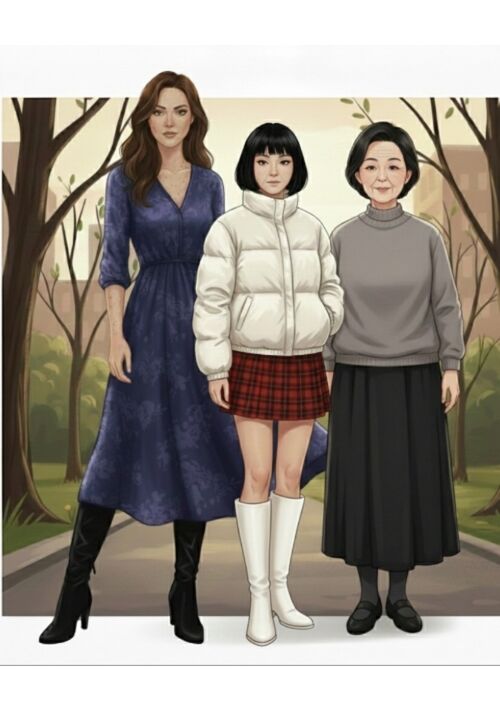
熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
恋愛
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

別れし夫婦の御定書(おさだめがき)
佐倉 蘭
歴史・時代
★第11回歴史・時代小説大賞 奨励賞受賞★
嫡男を産めぬがゆえに、姑の策略で南町奉行所の例繰方与力・進藤 又十蔵と離縁させられた与岐(よき)。
離縁後、生家の父の猛反対を押し切って生まれ育った八丁堀の組屋敷を出ると、小伝馬町の仕舞屋に居を定めて一人暮らしを始めた。
月日は流れ、姑の思惑どおり後妻が嫡男を産み、婚家に置いてきた娘は二人とも無事与力の御家に嫁いだ。
おのれに起こったことは綺麗さっぱり水に流した与岐は、今では女だてらに離縁を望む町家の女房たちの代わりに亭主どもから去り状(三行半)をもぎ取るなどをする「公事師(くじし)」の生業(なりわい)をして生計を立てていた。
されどもある日突然、与岐の仕舞屋にとっくの昔に離縁したはずの元夫・又十蔵が転がり込んできて——
※「今宵は遣らずの雨」「大江戸ロミオ&ジュリエット」「大江戸シンデレラ」「大江戸の番人 〜吉原髪切り捕物帖〜」にうっすらと関連したお話ですが単独でお読みいただけます。

裏長屋の若殿、限られた自由を満喫する
克全
歴史・時代
貧乏人が肩を寄せ合って暮らす聖天長屋に徳田新之丞と名乗る人品卑しからぬ若侍がいた。月のうち数日しか長屋にいないのだが、いる時には自ら竈で米を炊き七輪で魚を焼く小まめな男だった。

改造空母機動艦隊
蒼 飛雲
歴史・時代
兵棋演習の結果、洋上航空戦における空母の大量損耗は避け得ないと悟った帝国海軍は高価な正規空母の新造をあきらめ、旧式戦艦や特務艦を改造することで数を揃える方向に舵を切る。
そして、昭和一六年一二月。
日本の前途に暗雲が立ち込める中、祖国防衛のために改造空母艦隊は出撃する。
「瑞鳳」「祥鳳」「龍鳳」が、さらに「千歳」「千代田」「瑞穂」がその数を頼みに太平洋艦隊を迎え撃つ。

日本の運命を変えた天才少年-日本が世界一の帝国になる日-
ましゅまろ
歴史・時代
――もしも、日本の運命を変える“少年”が現れたなら。
1941年、戦争の影が世界を覆うなか、日本に突如として現れた一人の少年――蒼月レイ。
わずか13歳の彼は、天才的な頭脳で、戦争そのものを再設計し、歴史を変え、英米独ソをも巻き込みながら、日本を敗戦の未来から救い出す。
だがその歩みは、同時に多くの敵を生み、命を狙われることも――。
これは、一人の少年の手で、世界一の帝国へと昇りつめた日本の物語。
希望と混乱の20世紀を超え、未来に語り継がれる“蒼き伝説”が、いま始まる。
※アルファポリス限定投稿
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















