111 / 111
第九章 蒲生氏郷編 小牧・長久手の戦い
第111話 ツキに見放された名将
しおりを挟む犬山城の広間には秀吉方の諸将が集まっていた。
尾張・美濃の各地を攻める為の軍議が開かれている。上座に座るのはもちろん総大将の羽柴秀吉だ。
秀吉の後方、床の間に当たる場所には馬蘭の後立が付いた兜が安置されている。有名な一の谷馬蘭後立付兜だ。
兜の中央に向かって幾筋もの馬蘭が集まる様は、まるで後光が差しているかのような錯覚を覚える。
賦秀もその派手さには舌を巻いていた。
もっとも、周囲の者から見れば賦秀の漆黒の具足も派手さでは負けていない。
燕尾型の兜を付けた漆黒の塊が疾走する姿は、ある種の異様さを諸人に抱かせるに充分なものだ。だが、当の賦秀には自分が派手だとの自覚は無い。
『目立ちはしても渋い黒なのだから、派手と言うには当たらんだろう』
そう言って周囲を呆れさせていた。
「皆の衆、此度はよう集まってもらった。早速だが、これより我らは尾張の西、加賀野井・奥・竹ヶ鼻の諸城を攻める」
秀吉が高らかに宣言する。
既に諸将はそのことを察しており、秀吉の宣言にも黙って頷くだけだ。
「加賀野井城攻めの先陣は蒲生飛騨守に申しつける」
「ハッ!」
秀吉の指名を受けて賦秀が頭を下げた。
言うまでもなく先陣は名誉なことであり、先陣の働き如何によっては合戦そのものの趨勢すらも決まる。
六角家中にあって長く蒲生が先陣を勤めて来たのは、ひとえにその武に対する信頼の証だ。
そして、今秀吉はその信頼の証を蒲生賦秀に与えた。賦秀としてもそれが嬉しくないわけでは無い。
だが、一点だけ心に引っかかる物があった。
――叔父御は退いてくれるだろうか
加賀野井城は大垣から尾張に至る西尾張の交通の要衝に当たり、信雄側としても重要な拠点だ。
しかも、今回は秀吉の鮮やかな勝利を喧伝するために一気に攻め寄せねばならない。城攻めは苛烈なものとなり、城に籠る将兵は城を枕に討死を覚悟せねばならないだろう。
加賀野井城には、蒲生に敗れて尾張に退いた北伊勢の在地領主たちが籠っている。その中で主に軍勢を指揮しているのは峰、楠、千種、阿下喜の四将だ。
四将の一人である千種三郎左衛門は六角旧臣の後藤賢豊の実弟で、六角義賢の命によって千種氏の養子となった人物だ。そして、賦秀の母は後藤賢豊の妹だ。
つまり、加賀野井城に籠る千種三郎左衛門は蒲生賦秀の叔父に当たる。
昨年まで味方同士だった羽柴秀吉と織田信雄が敵対した以上、こうした事態は決して珍しい物では無い。それどころか、乱世にあってはたとえ親子兄弟と言えども敵味方に分かれて戦うこともあった。
だが、肉親の情としては忍びない物がある。
まして後藤家を継いだ後藤高治は本能寺の変に際して明智光秀に与したために領地を追われ、今では行方も分からなくなっている。
実家を継いだ甥に加えて実弟まで喪えば、母はさぞや悲しむだろう。
賦秀としても、これ以上母方の血筋を喪うのは本意では無かった。
※ ※ ※
「飛騨守殿」
軍議が終わり、犬山城を引き上げて自陣に戻ろうとする賦秀を呼ぶ声がした。
賦秀が振り返ると、黒田官兵衛が片足を引きずりながらにこやかな顔で近づいてきている。賦秀も官兵衛を認めて頭を下げた。
「これは官兵衛殿、此度は急遽大坂から参られたとか。ご苦労に存ずる」
「いや、なに。飛騨守殿こそ、戸木城を放っての参陣、気が気ではありますまい」
官兵衛はそう言ってねぎらってくれるが、目の前の敵を放り出して犬山城に参陣したのは賦秀だけではない。黒田官兵衛も開戦当初は大坂城の留守居役を務めていたが、長久手の敗戦の穴を埋めるために急遽秀吉に参陣を命じられた一人だ。
「軍議の場では何やら浮かぬ顔をしておられたが、何か心配ごとがおありかな?」
「恐れ入ります。加賀野井城に籠る千種三郎左衛門は我が叔父でござれば……」
「うむ。此度の加賀野井攻めは苛烈な物になりましょう。ご心配はごもっとも。なれど、我らが此度の戦に敗れても同じことが言えますかな?」
賦秀は官兵衛の言葉に思わず顔を上げた。
雑賀衆は四国の長曾我部元親とも連携を取って大坂城を脅かさんとしており、優勢な伊勢と違って河内は防衛戦となっている。黒田官兵衛こそ気が気ではないだろう。今大坂城を攻め落とされれば、秀吉の勢力は大きく後退せざるを得なくなるのだ。
だが、官兵衛は内心の焦りを押し隠して賦秀の様子を心配までしてくれている。
――儂は何を甘えたことを
考えてみれば、ここまでしてこの戦に勝とうとしているのは一人秀吉の為ではない。
元々は幼い三法師から織田の家督を奪い取ろうとする織田信雄に対抗してのものだ。今ここで肉親の情に流され、秀吉が敗れるようなことになれば、それこそ亡き信長に顔向けできなくなる。
「ご助言忝い。おかげで迷いが晴れ申した」
「お手前は今や筑前守様の片腕と申すべき勇将。存分にお働きを」
そう言って官兵衛がニッコリと笑う。
官兵衛の言ったことは決して大げさではない。小牧・長久手の戦いにおける秀吉軍の総数は十万にも上ると言われるが、それは各地の秀吉方の軍勢の総数であって、尾張で直接的に小牧山の家康軍と相対しているのは僅か二万六千ほどに過ぎない。
その中で二千の兵を擁する蒲生勢は、立派に秀吉軍の主力の一角と言える。蒲生勢が先陣を申しつけられるのも、それだけの存在感を持っているからこそだ。
いまさら迷っている場合では無かった。
翌日より蒲生勢は加賀野井城に攻めかかった。
賦秀は一縷の望みをかけて加賀野井城の千種三郎左衛門に夜討ちを掛けるから城を逃げろと通達していたが、千種勢は退かず、結局賦秀は千種勢もろとも加賀野井城の将兵を殲滅した。
蒲生の戦ぶりは苛烈を極め、抵抗する者は容赦なく斬り捨てる非情さを見せた。
続く奥城も一日で落城し、秀吉の武威は西尾張に響き渡った。
そして秀吉は竹ヶ鼻城を水攻めにし、家康の後詰を誘った。竹ヶ鼻城主の不破広綱は家康に救援要請を行ったが、結局家康は後詰を出さず、六月に入って竹ヶ鼻城は降伏した。
家康としても下手に誘いに乗って自軍が敗北してしまえば、長久手の戦勝が一気に吹き飛ぶ恐れがある。そのため、不破広綱に対して降伏するよう勧めるのみであった。
家康は打って出る気が無いと判断した秀吉は、六月十日に竹ヶ鼻城の開城を見届けると一旦大坂城に戻ることにした。
もはやこの戦は直接対決では無く外交戦の様相を呈して来ている。秀吉としても、前線に張り付いている意味は薄かった。
※ ※ ※
「何!? 猿は既に大坂へ戻っただと!?」
滝川一益は蟹江城の物見櫓で呆気に取られていた。
眼下には織田信雄と徳川家康の連合軍が集合し、今にも蟹江城に攻めかかろうとしている。
一益は怒りのあまり、拳を握って櫓の壁を思い切り殴りつけた。
「一体奴は何を考えている! 味方を見殺しにするつもりか!」
剃り上げた頭が湯気をあげんばかりに真っ赤に染まる。滝川一益はそれほど怒りに燃えていた。
蟹江城は長島城と清州城の中間に位置する尾張南部の城だ。九鬼嘉隆の安宅船を用いて伊勢松ヶ島を出航した滝川勢は、海上からの強襲によって蟹江城を奪取していた。
勢いに乗った滝川勢は大野城の攻略にかかったが、ここはいち早く信雄の援軍が到着したために一益は大野城攻略を諦めて蟹江城に引き返した。
信雄・家康連合軍にすれば、突如として後方から敵勢が湧いて出たことになる。竹ヶ鼻城については涙を呑んで後詰を諦めた家康だが、蟹江城の滝川一益を放置しておくことは出来なかった。
馬鹿を見たのは一益の方だ。
当然ながら、一益は独断で蟹江城を攻略したわけでは無い。秀吉の指示があったからこそだ。
しかし、当の秀吉はまさか一益が海上からの強襲揚陸によってここまでの戦果を上げるとは思っていなかった。精々尾張の南の海上を牽制し、小牧山の家康を焦らせれば上出来だと思っていた。
つまり、一益の手際は鮮やか過ぎた。
秀吉としても、この機を捉えて犬山城の軍勢を清州に攻めかからせれば一息に家康の首すら取れたかもしれない。それほどに蟹江城を攻略した意義は大きい。
だが、一益が蟹江城を攻略したのは六月十六日のことであり、この時には既に秀吉は近江佐和山まで引き上げている。
秀吉は滝川一益の力量を見誤っていた。
「どうする? 城を捨てるか?」
傍らの九鬼嘉隆が一益の顔色を窺う。
海戦においては無類の強さを発揮する海賊大名も、こと陸戦となれば一益を頼らざるを得ない。このまま籠城するか、それとも蟹江城を放棄して脱出するか。
一益は厳しい選択を迫られていた。
「……今少し、粘る。前田城を見殺しには出来ん」
前田城を守る前田長定は、今回一益の調略に応じて秀吉方に寝返っている。
今一益が蟹江城を逃げ出せば、前田長定はかけた梯子を外されることになる。それは、今まさに一益が秀吉に受けた仕打ちと全く同じことだ。
自分が受けた仕打ちを前田長定に返すということは、一益の矜持が許さなかった。
「よし」
九鬼嘉隆も覚悟を決めて各所に防衛の指示を出しに行く。
一方の一益は、この籠城の先に暗い予感しかなかった。
この一益の予感は現実のものとなる。
佐和山城で一益の奮戦を知った羽柴秀吉は、慌てて北伊勢に軍勢を回した。一益を援護し、合わせて尾張を信雄・家康連合軍から奪取するためだ。
だが、時すでに遅く前田城は落城し、その上信雄・家康連合軍によって尾張の海上は封鎖されていた。
滝川一益は自身も手傷を負いながら必死の抵抗を見せたが、秀吉が援軍を用意していることなど知る由も無い。
秀吉から見捨てられたと思った一益は、七月二日に蟹江城を明け渡して伊勢に退去した。
一時的な和睦中にも関わらず織田信雄は逃げる滝川勢に背後から襲い掛かり、調略に応じた前田長定は信雄軍に討たれ、一益自身もほうほうの体で逃げざるを得なかった。
一益は何とか伊勢に逃れたが、逃げた先で秀吉が七月十五日を期して尾張に総攻撃を掛ける手配をしていたことを知った。
全ては秀吉の失策という他なかった。
だが、秀吉がこの失敗を糊塗するために取った手段はさらに卑劣な物だった。
敗戦の責任は一益の嫡男滝川一忠にあるとして一忠を追放し、自身の援軍が間に合わなかったのではなく、一忠が早々に籠城を諦めたから負けたのだとした。
責任を一忠に負わせたのは、一忠がしきりに秀吉の援軍が間に合わなかったと周囲に喧伝していた為だ。
さすがに不味いと思ったのか、秀吉は従来約束していた通り滝川一益に三千石を与えると共に、本来一忠に与えられるはずだった一万二千石を一益の次男の一時に与えることで滝川家からの抗議を封じ込めた。
結果的に、この蟹江城合戦は秀吉が家康に直接対決で勝つ最後の機会だった。
この機を逃した秀吉は、当初の予定通り家康と睨み合いを続ける一方で各地の反秀吉方を切り崩すべく大坂城に帰還する。
名将滝川一益は、本能寺の変以降は徹頭徹尾ツキに見放されていた。
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
勝利のために走るのではない。
生きるために走る者は、
傷を負いながらも、歩みを止めない。
戦国という時代の只中で、
彼らは何を失い、
走り続けたのか。
滝川一益と、その郎党。
これは、勝者の物語ではない。
生き延びた者たちの記録である。

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ
朽縄咲良
歴史・時代
【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】
戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。
永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。
信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。
この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。
*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

四代目 豊臣秀勝
克全
歴史・時代
アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。
読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。
史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。
秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。
小牧長久手で秀吉は勝てるのか?
朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?
朝鮮征伐は行われるのか?
秀頼は生まれるのか。
秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

織田信長 -尾州払暁-
藪から犬
歴史・時代
織田信長は、戦国の世における天下統一の先駆者として一般に強くイメージされますが、当然ながら、生まれついてそうであるわけはありません。
守護代・織田大和守家の家来(傍流)である弾正忠家の家督を継承してから、およそ14年間を尾張(現・愛知県西部)の平定に費やしています。そして、そのほとんどが一族間での骨肉の争いであり、一歩踏み外せば死に直結するような、四面楚歌の道のりでした。
織田信長という人間を考えるとき、この彼の青春時代というのは非常に色濃く映ります。
そこで、本作では、天文16年(1547年)~永禄3年(1560年)までの13年間の織田信長の足跡を小説としてじっくりとなぞってみようと思いたった次第です。
毎週の月曜日00:00に次話公開を目指しています。
スローペースの拙稿ではありますが、お付き合いいただければ嬉しいです。
(2022.04.04)
※信長公記を下地としていますが諸出来事の年次比定を含め随所に著者の創作および定説ではない解釈等がありますのでご承知置きください。
※アルファポリスの仕様上、「HOTランキング用ジャンル選択」欄を「男性向け」に設定していますが、区別する意図はとくにありません。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

影武者の天下盗り
井上シオ
歴史・時代
「影武者が、本物を超えてしまった——」
百姓の男が“信長”を演じ続けた。
やがて彼は、歴史さえ書き換える“もう一人の信長”になる。
貧しい百姓・十兵衛は、織田信長の影武者として拾われた。
戦場で命を賭け、演じ続けた先に待っていたのは――本能寺の変。
炎の中、信長は死に、十兵衛だけが生き残った。
家臣たちは彼を“信長”と信じ、十兵衛もまた“信長として生きる”ことを選ぶ。
偽物だった男が、やがて本物を凌ぐ采配で天下を動かしていく。
「俺が、信長だ」
虚構と真実が交差するとき、“天下を盗る”のは誰か。
時は戦国。
貧しい百姓の青年・十兵衛は、戦火に焼かれた村で家も家族も失い、彷徨っていた。
そんな彼を拾ったのは、天下人・織田信長の家臣団だった。
その驚くべき理由は——「あまりにも、信長様に似ている」から。
歴史そのものを塗り替える——“影武者が本物を超える”成り上がり戦国譚。
(このドラマは史実を基にしたフィクションです)

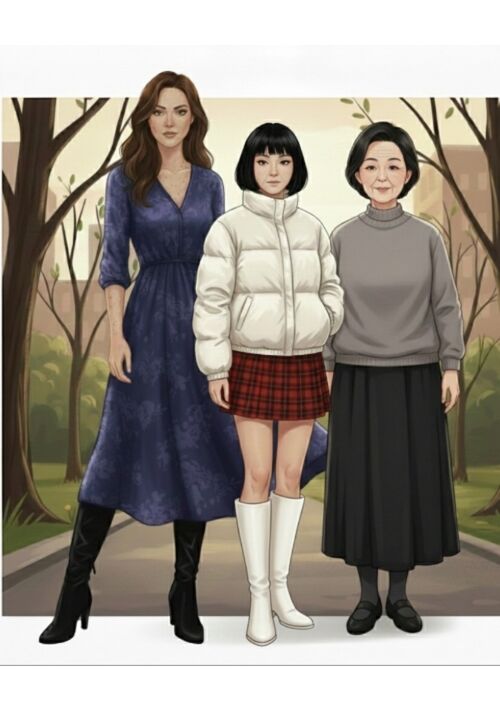
熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
恋愛
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















