94 / 111
第七章 蒲生賢秀編 本能寺の変
第94話 佐助の意地
しおりを挟む天正九年(1581年)四月
信長は総勢十万近くの軍勢を持って伊賀国に進軍した。『天正伊賀の乱』と呼ばれる伊賀忍び衆掃討作戦だが、実を言うと織田軍が伊賀国を攻めるのはこれが初めてでは無かった。
遡ること三年前の天正六年
伊勢北畠家の家督を継いで伊勢国を掌握した織田信雄は、次に伊賀を平定するべく丸山城の修築を命じた。これを脅威に感じた伊賀国人衆は、丸山城の城普請が完成する前に攻め落とすべく夜襲を仕掛け、織田勢を撃退していた。
これに怒った信雄は、翌天正七年に父である信長に何の相談もせずに伊勢から八千の軍勢を率いて伊賀国への侵攻を開始する。しかし、この時も伊賀国人衆による奇襲の前に為すすべなく敗走した。
信長は勝手に伊賀へ侵攻した信雄に激怒したが、同時に八千の軍勢をわずかな手勢で敗走させた伊賀国人衆の武力にも警戒心を抱いた。しかし、摂津周辺では有岡城に荒木村重を包囲し、さらに本願寺や三木城も包囲している最中にあってとても伊賀に振り向ける戦力は無かった。
だが今や有岡城は陥落し、三木城も落城。さらには本願寺も降伏して畿内には織田家に対抗する勢力が存在しなくなったことで、満を持して全兵力を伊賀制圧に投入することが出来た。
そして、甲賀から伊賀に向けて進軍する織田軍の中には蒲生勢を率いる忠三郎賦秀の姿があった。
行軍中の馬上にあって賦秀は常の彼には似合わない憂鬱な顔をしていた。
隣を進む町野繁仍もそんな賦秀に不審な顔を向ける。燕が尾を広げたような独特の兜をかぶった賦秀は、その傾いた出で立ちとは裏腹にため息を吐くばかりだ。
「若、いかがなさいましたか?」
「……いや、このことをお祖父様が知れば、いかほどに悲しむかと思ってな」
「……」
町野もその一言で賦秀の憂鬱の原因を理解した。
これから侵攻する伊賀には、蒲生家の旧主である六角義賢が潜伏しているとの情報もある。義賢自身は南近江を失いながらも、織田包囲網の要として武田勝頼と上杉謙信の和議をまとめ、さらには本願寺や毛利とも連携して信長に抵抗を続けていた。だが、上杉謙信は上洛を目前にして卒中に倒れ、本願寺も既に無く、毛利は西国から出て来る気配が無い。
さらには、長年拠点としていた甲賀は既に織田家の支配下に収まっており、今回伊賀が織田軍に制圧されれば今度こそ義賢は逃げ場を失う可能性もある。
「やむを得ぬことでございます。ご隠居様の尽力によって上様も六角様親子の助命を承知されました。それでもなお上様に抵抗を続けたのは承禎様の自儘にございましょう」
「分かっている。父上ならば、まずは上様に忠義であることこそ蒲生家の生き方であると申されるだろう」
「その通りにございます。若殿がそのようなお顔をされては、兵達の士気にも関わりますぞ」
「……」
―――せめて、お祖父様がこのことを知らずに逝けたことを幸いと思おう
賦秀はそう思って無理やり自分を納得させた。
長く六角家の柱石として働いた蒲生定秀は、二年前の天正七年三月にこの世を去っていた。享年七十二歳。人間五十年と言われた当時としては長命であると言える。
織田信長に六角親子の助命を飲ませた定秀は、当の六角親子からは最期まで裏切り者と罵られたままで終わった。
※ ※ ※
四月から始まった伊賀制圧戦は、既に夏を過ぎ秋になろうとしていた。
伊賀国人衆の奇襲を警戒する信長は、伊勢口、柘植口、玉滝口、笠間口、多羅尾口などあらゆる方面から伊賀国全体を重層的に包囲していた。
いかに伊賀国人衆が奇襲や攪乱を得意としていると言っても、これだけ重厚な包囲網でじっくりと攻められれば数の違いが如実に表れて来る。
九月になる頃には、伊賀衆の拠点は比自山城と平楽寺の二か所を残すのみとなっていた。
玉滝口から伊賀上野に侵入した蒲生勢は、服部川の河原で野営に入った。
伊賀上野の平野は狭く、その狭い平地にひしめき合うように織田軍の諸部隊が陣を張っている。必然、蒲生勢の陣地は川に近い場所に取らざるを得なかった。
暦は秋になったとはいえ、未だ暑い日も続いている。
河原に陣を張る蒲生勢には涼を求めて川沿いで眠る者が多かった。
深夜
賦秀はこの日も昼間の暑さに多少の疲労を覚え、夜の川の涼風に当てられてぐっすりと眠っていた。そんな賦秀の陣小屋に町野繁仍が駆け込んでくる。
「若! 一大事です!」
「将監か……どうした?」
未だ半分寝ぼけていたが、町野の悲鳴にも似た叫び声に叩き起こされて周囲を見回す。
視界に入った景色は相変わらずの小屋の壁だったが、その中に炎の明かりが混じっていた。
「火の色……?」
「夜襲にございます!」
「!!」
今度こそ賦秀は目覚めて寝藁から跳ね起きた。
周囲ではあちこちで戦う兵の微かな声が響いている。賦秀も慌てて兜をかぶると、槍を片手に陣小屋を飛び出した。
「慌てるな! かがり火を増やせ! 同士討ちをすることになるぞ!」
陣中を走り回りながら賦秀が様々に指示を飛ばす。途中何人かの伊賀衆と行き会い、槍先で突き、あるいは薙ぎ払って吹き飛ばしながら進んだ。
黒い頭巾を被って目だけを出した伊賀衆は、声も必要最小限しか出していない。明らかに闇に紛れて同士討ちを誘っている。
「敵は闇に紛れているぞ!かがり火を絶やすな!」
「若殿!ここは危のうございます!」
後ろから追いかけて来た町野が賦秀を強引に後方へ連れ出した。
伊賀衆は河原周辺に広く展開しており、寝込みを襲われた蒲生勢は既に充分すぎるほど浮足立っている。もはやここから立て直すことは不可能だ。
「一旦退きましょう! 全軍に後退の合図を!」
「将監! しかし……」
「ぐずぐずしていると若殿ご自身がここで討ち死に為されることになりますぞ!」
町野の一喝で賦秀も渋々兵を河原から下げた。
伊賀衆は服部川に沿って各地の陣に夜襲を仕掛けており、川から離れれば深追いはしてこない。深追いすれば敵中で孤立するのは伊賀衆の方になるからだ。
蒲生陣の隣に陣を張る筒井順慶の部隊からもかがり火を灯せいう怒鳴り声が響いてくる。
結局夜が明けた後、蒲生勢には三百人を超える被害が出ていた。
―――儂のせいだ
六角義賢のことを気に病み、戦に前向きになれなかった自分の心の隙を突かれたのだと思った。
言われるまでも無くここは戦場であり、伊賀衆にとって蒲生賦秀は倒すべき敵なのだ。油断などとんでもないし、敵の事実上の指揮官の安否を気遣っている余裕などあって良いはずが無かったのだ。
例え圧倒的な勝ち戦の中であっても、追い詰められた敵は窮余の策を打って来る。それを分かったつもりでいながら、心の底で理解できていなかったと思い知った。
※ ※ ※
滝川一益は隣に立つ益氏と共に遠くに見える平楽寺に視線を向けていた。平楽寺にはまさに今蒲生勢が攻めかかっている最中だが、伊賀衆の抵抗が激しく戦況ははかばかしくない。
「やれやれ、やはり親父殿に比べて息子は今一つだな」
一益がため息を吐く。
遠目から見ても、お世辞にも蒲生が押しているとは言い難い。圧倒的な兵力差があるからこそ逆襲を受けずに済んでいるだけだ。これが蒲生勢のみで進軍していたら、あっという間に逆襲を受けて敗走しているだろう。
「そこで鉄砲を撃ちかけんか。ええい、じれったいな」
「殿も少し落ち着きなされ。さほどに熱くなられてはいざと言う時の判断に乱れが生じますぞ」
益氏に指摘されて一益はバツが悪そうに頭を掻く。
益氏の言う通り、一益は今回甲賀方面からの軍勢の指揮を任されている。蒲生勢は滝川勢の寄騎のような立場になっているわけだが、その蒲生勢が苦戦しているとなれば滝川勢から援軍を出さねばならない。
蒲生ならば援軍など必要ないと高を括っていたが、賦秀の将としての器量は今一つというのが一益が下した判断だった。
「……ふむ。儀太夫、蒲生の後詰に向かってくれるか」
「承知しました」
そう言って益氏が踵を返して軍勢に向かっている。やがて一千ほどの兵が抜き出されると、足早に前線へと向かった。
―――やれやれ、まったく世話の焼ける……
再び一益はため息を吐く。
一益の見立て通り、平楽寺の守りにてこずっていた蒲生勢は益氏の援軍を得て一気に攻勢を強め、平楽寺はその日の昼過ぎには落城した。
平楽寺を失った伊賀衆は比自山城に籠ってなおも抵抗を続けたが、衆寡敵せず織田軍の総攻撃の前日には比自山城から逃走する。
結局そのまま伊賀衆は国外へ逃亡し、伊賀一国は織田家の制圧するところとなった。
※ ※ ※
甲斐の甲府では六角義定を前に三雲賢春が膝を着いていた。賢春の着衣はドロドロに汚れ、あちこちに焼け焦げたような跡が残っている。
賢春から受け取った文に目を通した義定は、そのまま深く息を吐いた。
「父上は何とか伊賀から逃れることが出来たか」
「ハッ!今は和泉に逃れ、キリシタンの寺にて匿われております」
「キリシタンの寺か」
「かの者らは逃げて来た者に寛容です。ご隠居様も今は動きを控えて世の動向を見守ると申されておりました」
「わかった。こちらもいよいよ覚悟を決めねばならんかもしれんな」
ほっと胸を撫でおろしていた義定は、再び厳しい顔つきに戻っている。
武田勝頼の元に身を寄せていた六角義賢の次男六角義定は、武田家の命運が尽きかけていることを敏感に察していた。
長篠の敗戦以来も幾度となく徳川と遠江高天神城を巡って争っていた勝頼だったが、天正九年の三月にはついに徳川家康によって高天神城を落とされている。
この落城前後、勝頼は織田信長との和睦を模索しており、信長を刺激することを恐れた勝頼は高天神城に後詰を送らなかったが、このことに武田旗下の国人衆は大いに動揺した。
高天神城を見捨てた勝頼の武名は地に落ち、天下最強と謳われた武田家も家臣から次々に離反者が出ている。そこを狙って織田と徳川から様々に調略の手が伸びており、今の武田は既に戦える状態では無くなっていた。
「こんなはずでは……ご隠居様や御屋形様が上杉・武田・北条の和睦を整えられ、東国が団結して織田に当たるはずでありましたのに……」
賢春の顔が悔しそうに歪み、涙が一筋零れ落ちる。
「言うな、佐助。上杉殿が倒れさえしなければ、今度こそ織田は終わりとなるはずであった。織田信長という男は天をも斬り従えるほどの天運を持っておるのやもしれん」
賢春とは対照的に、義定の方は半ば諦めのような雰囲気が漂っている。
思えば、六角家は永禄の上洛戦以後様々に信長と敵対してきた。
朝倉の裏切り後に野洲河原にて蜂起したが、柴田勝家を始めとした織田方の諸将に敗れた。その後、朝倉・浅井と武田の間を仲介し、比叡山とも連携して志賀の陣で信長を追い詰めた。だが、朝倉・浅井と織田との和議が成立すると、その隙に信長は各地の反乱勢力を鎮圧しつつ浅井を追い詰めていった。
浅井が自ら小谷城に引きこもったことも浅井が敗れた原因ではあるが、それにしても信長にしてやられたという印象が強い。
その後は武田信玄の西上作戦に合わせて畿内の勢力を糾合し、足利義昭を信長から切り離すことに成功した。
だが、武運拙く信玄は上洛を前にして病没し、足利義昭は信長に追放されて鞆に逃れた。
そして今度は東国を糾合して織田に挑戦したが、主力足り得る上杉は謙信の急死とその後の上杉家の後継者争いで織田と戦どころでは無くなってしまった。
北条は再び徳川と同盟して武田と敵対し、肝心の武田も信長との和議を望みながら信長に相手にされていないのが現状だ。
そして畿内からは本願寺の勢力も駆逐され、今また六角義賢の潜伏する伊賀も織田家に制圧された。
これ以上織田と戦う術はない。今の織田家は既に六角家が抗しえる相手では無くなった。
「武田の命運もいつ尽きるとも知れぬ。かくなる上は、我らも織田に降伏するしかあるまい」
「某は織田に降伏など出来ませぬ。我らが降れば、今まで死んだ者が浮かばれませぬ」
「佐助……もはやこれは抗いきれぬ。世の流れと申すべきものだ」
「いいえ。某は諦めません。いつの日か必ず、織田家を倒してご覧に入れまする!」
「待て!佐助!」
義定の制止も聞かず、賢春は六角屋敷を飛び出した。
もはや義定は織田に降伏の意思を固めた。であるならば、義賢や義治との取次ぎももはや不要であろう。
行く当てなどなかったが、それでも賢春はどうしても信長に降る気になれなかった。
―――主家すらも失って……
今や三雲家の領地と呼べる物など残っていない。そして義定の元を飛び出したことで仕えるべき主も失った。
これ以上生きていてどうなると言うのか。
それでも『生きよ』と言う蒲生賢秀の言葉だけが未だ心の中に響いていた。
蒲生を頼れば、恐らく賢秀は笑顔で迎えてくれるだろう。だがそれだけは死んでも出来ない相談だ。何故と言われれば明確に言葉には出来ないが、敢えて言えば男の意地とでもいうべきものだ。
蒲生を頼って織田に降るならばとうの昔にそうしている。万策尽き果てたからと言って今更おめおめと賢秀に頭を下げることなど出来なかった。
0
あなたにおすすめの小説
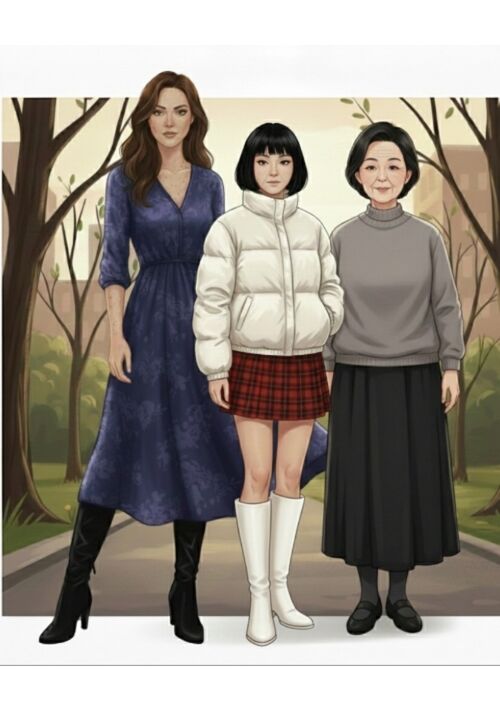
熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
現代文学
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ
朽縄咲良
歴史・時代
【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】
戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。
永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。
信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。
この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。
*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

織田信長 -尾州払暁-
藪から犬
歴史・時代
織田信長は、戦国の世における天下統一の先駆者として一般に強くイメージされますが、当然ながら、生まれついてそうであるわけはありません。
守護代・織田大和守家の家来(傍流)である弾正忠家の家督を継承してから、およそ14年間を尾張(現・愛知県西部)の平定に費やしています。そして、そのほとんどが一族間での骨肉の争いであり、一歩踏み外せば死に直結するような、四面楚歌の道のりでした。
織田信長という人間を考えるとき、この彼の青春時代というのは非常に色濃く映ります。
そこで、本作では、天文16年(1547年)~永禄3年(1560年)までの13年間の織田信長の足跡を小説としてじっくりとなぞってみようと思いたった次第です。
毎週の月曜日00:00に次話公開を目指しています。
スローペースの拙稿ではありますが、お付き合いいただければ嬉しいです。
(2022.04.04)
※信長公記を下地としていますが諸出来事の年次比定を含め随所に著者の創作および定説ではない解釈等がありますのでご承知置きください。
※アルファポリスの仕様上、「HOTランキング用ジャンル選択」欄を「男性向け」に設定していますが、区別する意図はとくにありません。

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
勝利のために走るのではない。
生きるために走る者は、
傷を負いながらも、歩みを止めない。
戦国という時代の只中で、
彼らは何を失い、
走り続けたのか。
滝川一益と、その郎党。
これは、勝者の物語ではない。
生き延びた者たちの記録である。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

影武者の天下盗り
井上シオ
歴史・時代
「影武者が、本物を超えてしまった——」
百姓の男が“信長”を演じ続けた。
やがて彼は、歴史さえ書き換える“もう一人の信長”になる。
貧しい百姓・十兵衛は、織田信長の影武者として拾われた。
戦場で命を賭け、演じ続けた先に待っていたのは――本能寺の変。
炎の中、信長は死に、十兵衛だけが生き残った。
家臣たちは彼を“信長”と信じ、十兵衛もまた“信長として生きる”ことを選ぶ。
偽物だった男が、やがて本物を凌ぐ采配で天下を動かしていく。
「俺が、信長だ」
虚構と真実が交差するとき、“天下を盗る”のは誰か。
時は戦国。
貧しい百姓の青年・十兵衛は、戦火に焼かれた村で家も家族も失い、彷徨っていた。
そんな彼を拾ったのは、天下人・織田信長の家臣団だった。
その驚くべき理由は——「あまりにも、信長様に似ている」から。
歴史そのものを塗り替える——“影武者が本物を超える”成り上がり戦国譚。
(このドラマは史実を基にしたフィクションです)

屈辱と愛情
守 秀斗
恋愛
最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















