83 / 111
第六章 蒲生賢秀編 元亀争乱
第83話 信長包囲網
しおりを挟む
主要登場人物別名
弾正忠… 織田信長 織田家当主
光源院… 足利義輝 先々代足利将軍 足利義昭の実兄
――――――――
元亀四年(1573年)一月
正月の松も取れぬ内から京の二条御所で将軍足利義昭を中心に御前会議が開かれていた。
「三河から火急の報せが参りました。先月のうちに三方ヶ原に置いて武田と徳川が戦に及び、武田が圧勝したとのことにございます。かくなる上は松永弾正の申す通り、これ以上織田と運命を共にすべきではありますまい」
「兄上、お待ちください。今の公方様があるは織田殿の力に依る所が大きい。今一時不利になったからと織田と袂を分かつのは早計に過ぎましょう」
幕臣の中でも重臣に位置する三淵藤英が反信長派に投じることを強く主張していた。対して引き続き信長と歩みを共にすべきと主張しているのは細川藤孝だ。
この二人は実の兄弟であり、共に足利義昭を支える重臣として活動していた。
「馬鹿者。お主は織田に騙されておるのだ。公方様が各地へ御内書を出されるのはいわば将軍として当然のこと。それを織田弾正忠は明智を通じて御内書を勝手に出すことはまかりならぬと言って参った。
僭越の沙汰であると明智を叱りつけた所、あまつさえ明智は幕臣を離れて織田に尻尾を振る有様。これ以上将軍家の権威を損なって如何する」
「それはあまりにも一方的に過ぎましょう。織田殿はあくまでも御内書を出す前には一言相談が欲しいと申されたに過ぎませぬ。天下の差配は織田殿に任せると公方様も仰せになった以上、織田殿の申されることは真っ当にございましょう」
先ほどから議論は延々と繰り返しになっている。上座に座る義昭も腹を決めかねている様子だった。
元々は明智光秀を通じて信長が義昭に申し入れた五か条の要求書が根本にあった。
信長は確かに五か条の要求書を出して義昭の行動を制限しようとしたが、それも義昭が信長の同意なしに各地に御内書をバラ撒くことを止めさせることが主な目的だ。
そのため、信長は要求書を世間には一切公表せず、全て内々のこととして処理していた。義昭の面目を潰すような真似は一切していない。そして義昭も信長の意を受けて独自の行動を控えようという意向だった。
だが、それに待ったをかけたのが三淵藤英だ。実のところ、義昭の出した御内書の多くは藤英の主導によるところが大きい。そのため、藤英としては義昭が信長の意に沿うことはようやく手に入れた幕府重臣としての権威を失うことになる。
足利義輝に仕えていた頃は三好長慶によって随分と頭を抑えつけられていた藤英だったが、信長が畿内を抑えたことでようやく権勢を振るう機会を得た。苦労の末に勝ち取った権勢の座を今更降りるつもりは藤英には毛頭なかった。
「しかし、今更武田に与するというのもいささか……。武田は織田殿が必死になって整えた和議を平然と破り、素知らぬ顔で織田と敵対しております。武田が信用できるかどうかも考えねばなりますまい」
細川藤孝の最大の心配事がそれだった。
そもそも武田の西上作戦は、織田信長にとって武田信玄の裏切りと言える行為だ。
五年前の永禄十一年は信長が足利義昭を奉じて上洛した年だが、一方で東国では武田信玄が甲駿相三国同盟を一方的に破棄して駿河の今川を攻めた年でもある。これによって今川氏真は掛川城に逃れ、滅亡寸前にまで追いやられている。
だが、それに怒ったのが相模の北条氏康だ。氏康は武田の裏切りを糾弾して武田を駿河から追い払うべく軍を起こす。それまで武田と連携していた徳川も北条と同調して武田と敵対した。
さらには北条・徳川は越後の上杉謙信とも歩調を合わせ、武田を三方から包囲する態勢を整えた。
北条・徳川・上杉の三者が『反武田』でまとまったのには理由がある。駿河は豊かな土地であり、戦に慣れた武田家が駿河を得れば東国では武田の勢力が頭一つ抜け出ることになる。その上、武田信玄はそれまでにも数多くの裏切りを繰り返しており、武田との和議や約束が最後まで守られると信じている者は誰もいなかった。現に、今の今まで同盟していた今川家が桶狭間の敗戦で混乱していると見るや、あっさりと同盟を破棄して侵攻している。武田信玄にとっては条約破りなど日常茶飯事と言える。
東国一の大大名となった武田が、次に北条や徳川、上杉との盟約を破って攻め込まないという保証はどこにもなかった。
信玄は反武田同盟の内、北条氏康とは何とか和議を結ぶことに成功した。氏康自身の体調が急速に悪化したこともあって北条はこれ以上武田との戦線を維持できなかったためだ。
だが、徳川と上杉は武田に対して挟撃の構えを崩さなかった。武田の膨張をこれ以上見過ごせなかったのが正直な所だろう。窮した信玄は信長に助けを求めた。
それまでも武田と織田は同盟関係にあったが、信玄は信長に徳川と上杉を何とかしてくれと哀願した。信玄は『もしも信長に見捨てられれば、武田は滅ぶしか無くなる』と近臣に漏らすほど追い詰められていたという。
信長は信玄の願いを容れて武田と徳川・上杉との和睦に尽力した。
徳川は隠れも無き織田の忠実な同盟者であり、信長から矛を収めよと言えば徳川家康とて無視はできない。だが、上杉謙信に対してはその手は効かない。
そこで、信長は将軍義昭の上意という形式を取って上杉謙信に武田との和睦を要請した。足利将軍家からの要請であれば謙信も無下にすることは出来ない。こうして武田信玄は何とか窮地を脱した。
その武田信玄が、上杉謙信が越中に侵攻して手がふさがっていると見るや、たちまち軍を発して三方ヶ原で徳川を破り、信長を第六天魔王と糾弾して織田を討つと呼号している。
信長の怒りももっともだし、細川藤孝とてそんな武田信玄が本当に信用できるのかと疑問を持つのも当然だった。
「お主の言うことも分からんではない。だが、現実問題として織田が京を守れると思うか?今から織田は武田と決戦に及ばざるを得ぬ。そうなれば必然的に織田の主力は東へと向かおう。
畿内には三好や松永、本願寺が居る。それに、浅井や朝倉も武田と連携して織田を叩く構えを見せている。織田の命運も今や風前の灯とは思わぬか?」
「それは……」
三淵藤英の言葉に細川藤孝も異論を差しはさむことは出来なかった。
三方ヶ原で徳川に圧勝した武田だが、まだ織田の本軍を破った訳ではない。今後上洛する上で、どこかの時点で織田の主力と決戦に及ぶだろうというのが世間の共通認識だ。
武田の裏切りに怒った信長は、上杉とも連携して武田を叩く構えを見せている。それに対し、武田信玄も畿内各地の反信長の諸将と連携して織田を封殺しようと政略を巡らしている。
事態は未だどう転ぶか予断を許さないが、その中で一つ確実なことは決戦は尾張か美濃で行われるだろうということだ。
信長としても本拠地である尾張・美濃を蹂躙されて黙っているわけにはいかない。その過程で織田家の主力は尾張・美濃へと戻らざるを得ない。頼みの織田軍を欠いた足利義昭が、反信長の浅井・朝倉・三好・本願寺・六角らに攻められて無事に京を守り通せるとは到底思えない。
「これ以上織田と共に歩めば、光源院様の二の舞ということもあり得ます。公方様には何卒ご英断をお願い申し上げます」
藤英が上座の義昭に対して頭を下げる。もはや議論は尽くされたともいえる態度だった。今や戦国乱世は極まり、武家の棟梁たる足利将軍とて臣下に弑逆されることもあり得る。その実例が『永禄の変』であり、義昭の実兄である足利義輝である。
あくまでも織田家を頼みとして畿内各地の諸将を敵に回せば、最悪の場合義昭の命が奪われる可能性すらある。そう言われれば、藤孝も反論できない。
だが、義昭はそれでも織田と決別する決断は出来なかった。
正月早々に議論を尽くしたが、冬の間は義昭も態度を決めかねて逡巡する。その義昭が反信長派として挙兵したのは旧暦の二月十三日だが、これは現在の暦でいう三月に当たる。越前の雪が溶け、いよいよ朝倉が大挙して京へと進軍して来る、そのギリギリまで義昭は信長を見捨てる決断を出来なかった。
※ ※ ※
「父上、これより出陣します」
「気を付けてな」
「ハッ!」
具足姿の蒲生賢秀は、中野城の隠居所で父の定秀と対面していた。
足利義昭が織田と決別し、石山と今堅田に出兵して反信長の兵を挙げた。驚いた信長はすぐさま柴田勝家に命じて石山・今堅田の拠点を包囲するとともに、京に居る足利義昭に対して和睦交渉を開始する。
賢秀ら蒲生勢には柴田勝家に従って石山城の包囲に出陣するようにと指令が届いていた。
「時に、弾正忠殿は公方様と和睦なさるそうだが、その後のことは考えているのか?」
「その後……公方様と和睦し、武田の上洛を食い止める以上に何かありましょうか?」
定秀がため息を一つ吐き、庭先に視線を移すとポツリと呟く。
「……此度の武田の動き、手引きしたのはご隠居様と御屋形様であろう」
「まさか……」
定秀は今なお六角義賢をご隠居様と呼び、六角義治を御屋形様と呼んでいた。定秀にとっては六角家以外を主君と仰ぐことは考えられることでは無かった。
「朝倉が武田を信じると思うか?」
今回の信長包囲網以前に朝倉と武田の交流は無い。それに、朝倉は甲斐武田の親戚筋にあたる若狭武田を攻めている。どちらかと言えば甲斐武田とは敵対関係にあると言える。
まして、武田信玄は条約破りなど屁とも思っていない。今川の末路を見れば、昨日の味方は明日の略奪対象になるのが武田信玄という男だということは充分に察せられる。
信長包囲網に置いて朝倉の動きが鈍った最大の理由はそこにあった。信長包囲網の主力たる武田信玄を朝倉義景は信用できないでいた。
上洛して権勢を得た途端、今度は朝倉に向かって攻めかかって来るかもしれないのだ。
「公方様が説き伏せられたのでは?」
「現公方にそのような力は無い。朝倉は義昭公の上洛を支援することはついに無かったではないか。今更公方に口説かれたからと言って、朝倉が素直に軍を出すとは到底思えぬ」
「……では」
「うむ。心しておけ。公方、朝倉、武田を繋いだのは六角家だ。この戦は公方と和睦したからと言って終わるわけでは無いぞ」
老いたりとはいえ、定秀の情勢を見る目は的確だった。
今回の武田信玄上洛には背後で六角親子の暗躍があった。故六角定頼は足利義昭の父足利義晴を最後まで支援し続けたし、朝倉宗滴と六角定頼の間では『末代まで』と言われる密約が結ばれてもいる。そして、甲斐を追われた信玄の父武田信虎は、八十歳の老骨に鞭打って京と甲賀を何度も往復して信玄上洛の交渉を進めている。
足利義昭、朝倉義景、武田信玄。
この三者を仲介して間を取り持つことが出来るのは六角しかいない。その為、武田信虎は六角義賢の潜む甲賀郡に何度も足を運んだのだ。
「父上は、どうなされるおつもりですか?」
「……」
未だ庭先を見つめる定秀に、賢秀の心も不意にざわつく。今回の武田信玄上洛は信長にとって最大の危機と言っていい。今この時に近江の国人衆が信長に背けば、織田信長は京を放棄するか本拠地を放棄するかの究極の二択を迫られることになる。
仮に定秀が六角家と行動を共にすればどうなるか……。
不意に定秀が庭先に向けていた視線を賢秀に向けると、ニコリと笑った。
「お主は弾正忠殿御為に働くが良い。何が起ころうともな」
一体何が起こるというのか、この時の賢秀には想像も出来なかった。
弾正忠… 織田信長 織田家当主
光源院… 足利義輝 先々代足利将軍 足利義昭の実兄
――――――――
元亀四年(1573年)一月
正月の松も取れぬ内から京の二条御所で将軍足利義昭を中心に御前会議が開かれていた。
「三河から火急の報せが参りました。先月のうちに三方ヶ原に置いて武田と徳川が戦に及び、武田が圧勝したとのことにございます。かくなる上は松永弾正の申す通り、これ以上織田と運命を共にすべきではありますまい」
「兄上、お待ちください。今の公方様があるは織田殿の力に依る所が大きい。今一時不利になったからと織田と袂を分かつのは早計に過ぎましょう」
幕臣の中でも重臣に位置する三淵藤英が反信長派に投じることを強く主張していた。対して引き続き信長と歩みを共にすべきと主張しているのは細川藤孝だ。
この二人は実の兄弟であり、共に足利義昭を支える重臣として活動していた。
「馬鹿者。お主は織田に騙されておるのだ。公方様が各地へ御内書を出されるのはいわば将軍として当然のこと。それを織田弾正忠は明智を通じて御内書を勝手に出すことはまかりならぬと言って参った。
僭越の沙汰であると明智を叱りつけた所、あまつさえ明智は幕臣を離れて織田に尻尾を振る有様。これ以上将軍家の権威を損なって如何する」
「それはあまりにも一方的に過ぎましょう。織田殿はあくまでも御内書を出す前には一言相談が欲しいと申されたに過ぎませぬ。天下の差配は織田殿に任せると公方様も仰せになった以上、織田殿の申されることは真っ当にございましょう」
先ほどから議論は延々と繰り返しになっている。上座に座る義昭も腹を決めかねている様子だった。
元々は明智光秀を通じて信長が義昭に申し入れた五か条の要求書が根本にあった。
信長は確かに五か条の要求書を出して義昭の行動を制限しようとしたが、それも義昭が信長の同意なしに各地に御内書をバラ撒くことを止めさせることが主な目的だ。
そのため、信長は要求書を世間には一切公表せず、全て内々のこととして処理していた。義昭の面目を潰すような真似は一切していない。そして義昭も信長の意を受けて独自の行動を控えようという意向だった。
だが、それに待ったをかけたのが三淵藤英だ。実のところ、義昭の出した御内書の多くは藤英の主導によるところが大きい。そのため、藤英としては義昭が信長の意に沿うことはようやく手に入れた幕府重臣としての権威を失うことになる。
足利義輝に仕えていた頃は三好長慶によって随分と頭を抑えつけられていた藤英だったが、信長が畿内を抑えたことでようやく権勢を振るう機会を得た。苦労の末に勝ち取った権勢の座を今更降りるつもりは藤英には毛頭なかった。
「しかし、今更武田に与するというのもいささか……。武田は織田殿が必死になって整えた和議を平然と破り、素知らぬ顔で織田と敵対しております。武田が信用できるかどうかも考えねばなりますまい」
細川藤孝の最大の心配事がそれだった。
そもそも武田の西上作戦は、織田信長にとって武田信玄の裏切りと言える行為だ。
五年前の永禄十一年は信長が足利義昭を奉じて上洛した年だが、一方で東国では武田信玄が甲駿相三国同盟を一方的に破棄して駿河の今川を攻めた年でもある。これによって今川氏真は掛川城に逃れ、滅亡寸前にまで追いやられている。
だが、それに怒ったのが相模の北条氏康だ。氏康は武田の裏切りを糾弾して武田を駿河から追い払うべく軍を起こす。それまで武田と連携していた徳川も北条と同調して武田と敵対した。
さらには北条・徳川は越後の上杉謙信とも歩調を合わせ、武田を三方から包囲する態勢を整えた。
北条・徳川・上杉の三者が『反武田』でまとまったのには理由がある。駿河は豊かな土地であり、戦に慣れた武田家が駿河を得れば東国では武田の勢力が頭一つ抜け出ることになる。その上、武田信玄はそれまでにも数多くの裏切りを繰り返しており、武田との和議や約束が最後まで守られると信じている者は誰もいなかった。現に、今の今まで同盟していた今川家が桶狭間の敗戦で混乱していると見るや、あっさりと同盟を破棄して侵攻している。武田信玄にとっては条約破りなど日常茶飯事と言える。
東国一の大大名となった武田が、次に北条や徳川、上杉との盟約を破って攻め込まないという保証はどこにもなかった。
信玄は反武田同盟の内、北条氏康とは何とか和議を結ぶことに成功した。氏康自身の体調が急速に悪化したこともあって北条はこれ以上武田との戦線を維持できなかったためだ。
だが、徳川と上杉は武田に対して挟撃の構えを崩さなかった。武田の膨張をこれ以上見過ごせなかったのが正直な所だろう。窮した信玄は信長に助けを求めた。
それまでも武田と織田は同盟関係にあったが、信玄は信長に徳川と上杉を何とかしてくれと哀願した。信玄は『もしも信長に見捨てられれば、武田は滅ぶしか無くなる』と近臣に漏らすほど追い詰められていたという。
信長は信玄の願いを容れて武田と徳川・上杉との和睦に尽力した。
徳川は隠れも無き織田の忠実な同盟者であり、信長から矛を収めよと言えば徳川家康とて無視はできない。だが、上杉謙信に対してはその手は効かない。
そこで、信長は将軍義昭の上意という形式を取って上杉謙信に武田との和睦を要請した。足利将軍家からの要請であれば謙信も無下にすることは出来ない。こうして武田信玄は何とか窮地を脱した。
その武田信玄が、上杉謙信が越中に侵攻して手がふさがっていると見るや、たちまち軍を発して三方ヶ原で徳川を破り、信長を第六天魔王と糾弾して織田を討つと呼号している。
信長の怒りももっともだし、細川藤孝とてそんな武田信玄が本当に信用できるのかと疑問を持つのも当然だった。
「お主の言うことも分からんではない。だが、現実問題として織田が京を守れると思うか?今から織田は武田と決戦に及ばざるを得ぬ。そうなれば必然的に織田の主力は東へと向かおう。
畿内には三好や松永、本願寺が居る。それに、浅井や朝倉も武田と連携して織田を叩く構えを見せている。織田の命運も今や風前の灯とは思わぬか?」
「それは……」
三淵藤英の言葉に細川藤孝も異論を差しはさむことは出来なかった。
三方ヶ原で徳川に圧勝した武田だが、まだ織田の本軍を破った訳ではない。今後上洛する上で、どこかの時点で織田の主力と決戦に及ぶだろうというのが世間の共通認識だ。
武田の裏切りに怒った信長は、上杉とも連携して武田を叩く構えを見せている。それに対し、武田信玄も畿内各地の反信長の諸将と連携して織田を封殺しようと政略を巡らしている。
事態は未だどう転ぶか予断を許さないが、その中で一つ確実なことは決戦は尾張か美濃で行われるだろうということだ。
信長としても本拠地である尾張・美濃を蹂躙されて黙っているわけにはいかない。その過程で織田家の主力は尾張・美濃へと戻らざるを得ない。頼みの織田軍を欠いた足利義昭が、反信長の浅井・朝倉・三好・本願寺・六角らに攻められて無事に京を守り通せるとは到底思えない。
「これ以上織田と共に歩めば、光源院様の二の舞ということもあり得ます。公方様には何卒ご英断をお願い申し上げます」
藤英が上座の義昭に対して頭を下げる。もはや議論は尽くされたともいえる態度だった。今や戦国乱世は極まり、武家の棟梁たる足利将軍とて臣下に弑逆されることもあり得る。その実例が『永禄の変』であり、義昭の実兄である足利義輝である。
あくまでも織田家を頼みとして畿内各地の諸将を敵に回せば、最悪の場合義昭の命が奪われる可能性すらある。そう言われれば、藤孝も反論できない。
だが、義昭はそれでも織田と決別する決断は出来なかった。
正月早々に議論を尽くしたが、冬の間は義昭も態度を決めかねて逡巡する。その義昭が反信長派として挙兵したのは旧暦の二月十三日だが、これは現在の暦でいう三月に当たる。越前の雪が溶け、いよいよ朝倉が大挙して京へと進軍して来る、そのギリギリまで義昭は信長を見捨てる決断を出来なかった。
※ ※ ※
「父上、これより出陣します」
「気を付けてな」
「ハッ!」
具足姿の蒲生賢秀は、中野城の隠居所で父の定秀と対面していた。
足利義昭が織田と決別し、石山と今堅田に出兵して反信長の兵を挙げた。驚いた信長はすぐさま柴田勝家に命じて石山・今堅田の拠点を包囲するとともに、京に居る足利義昭に対して和睦交渉を開始する。
賢秀ら蒲生勢には柴田勝家に従って石山城の包囲に出陣するようにと指令が届いていた。
「時に、弾正忠殿は公方様と和睦なさるそうだが、その後のことは考えているのか?」
「その後……公方様と和睦し、武田の上洛を食い止める以上に何かありましょうか?」
定秀がため息を一つ吐き、庭先に視線を移すとポツリと呟く。
「……此度の武田の動き、手引きしたのはご隠居様と御屋形様であろう」
「まさか……」
定秀は今なお六角義賢をご隠居様と呼び、六角義治を御屋形様と呼んでいた。定秀にとっては六角家以外を主君と仰ぐことは考えられることでは無かった。
「朝倉が武田を信じると思うか?」
今回の信長包囲網以前に朝倉と武田の交流は無い。それに、朝倉は甲斐武田の親戚筋にあたる若狭武田を攻めている。どちらかと言えば甲斐武田とは敵対関係にあると言える。
まして、武田信玄は条約破りなど屁とも思っていない。今川の末路を見れば、昨日の味方は明日の略奪対象になるのが武田信玄という男だということは充分に察せられる。
信長包囲網に置いて朝倉の動きが鈍った最大の理由はそこにあった。信長包囲網の主力たる武田信玄を朝倉義景は信用できないでいた。
上洛して権勢を得た途端、今度は朝倉に向かって攻めかかって来るかもしれないのだ。
「公方様が説き伏せられたのでは?」
「現公方にそのような力は無い。朝倉は義昭公の上洛を支援することはついに無かったではないか。今更公方に口説かれたからと言って、朝倉が素直に軍を出すとは到底思えぬ」
「……では」
「うむ。心しておけ。公方、朝倉、武田を繋いだのは六角家だ。この戦は公方と和睦したからと言って終わるわけでは無いぞ」
老いたりとはいえ、定秀の情勢を見る目は的確だった。
今回の武田信玄上洛には背後で六角親子の暗躍があった。故六角定頼は足利義昭の父足利義晴を最後まで支援し続けたし、朝倉宗滴と六角定頼の間では『末代まで』と言われる密約が結ばれてもいる。そして、甲斐を追われた信玄の父武田信虎は、八十歳の老骨に鞭打って京と甲賀を何度も往復して信玄上洛の交渉を進めている。
足利義昭、朝倉義景、武田信玄。
この三者を仲介して間を取り持つことが出来るのは六角しかいない。その為、武田信虎は六角義賢の潜む甲賀郡に何度も足を運んだのだ。
「父上は、どうなされるおつもりですか?」
「……」
未だ庭先を見つめる定秀に、賢秀の心も不意にざわつく。今回の武田信玄上洛は信長にとって最大の危機と言っていい。今この時に近江の国人衆が信長に背けば、織田信長は京を放棄するか本拠地を放棄するかの究極の二択を迫られることになる。
仮に定秀が六角家と行動を共にすればどうなるか……。
不意に定秀が庭先に向けていた視線を賢秀に向けると、ニコリと笑った。
「お主は弾正忠殿御為に働くが良い。何が起ころうともな」
一体何が起こるというのか、この時の賢秀には想像も出来なかった。
0
あなたにおすすめの小説
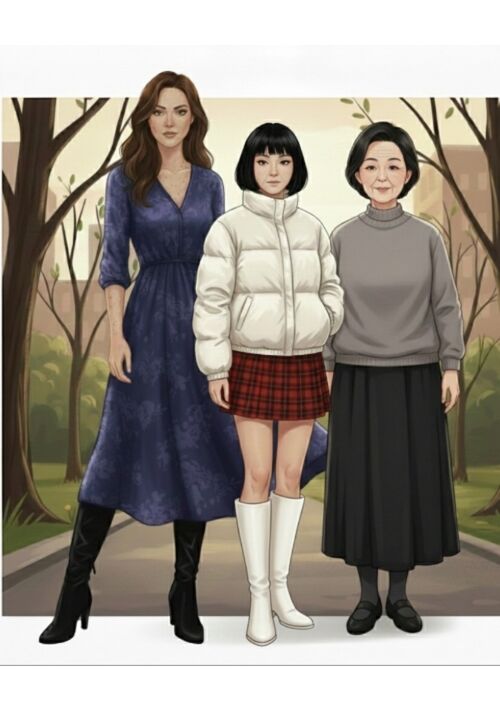
熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
現代文学
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ
朽縄咲良
歴史・時代
【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】
戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。
永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。
信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。
この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。
*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

織田信長 -尾州払暁-
藪から犬
歴史・時代
織田信長は、戦国の世における天下統一の先駆者として一般に強くイメージされますが、当然ながら、生まれついてそうであるわけはありません。
守護代・織田大和守家の家来(傍流)である弾正忠家の家督を継承してから、およそ14年間を尾張(現・愛知県西部)の平定に費やしています。そして、そのほとんどが一族間での骨肉の争いであり、一歩踏み外せば死に直結するような、四面楚歌の道のりでした。
織田信長という人間を考えるとき、この彼の青春時代というのは非常に色濃く映ります。
そこで、本作では、天文16年(1547年)~永禄3年(1560年)までの13年間の織田信長の足跡を小説としてじっくりとなぞってみようと思いたった次第です。
毎週の月曜日00:00に次話公開を目指しています。
スローペースの拙稿ではありますが、お付き合いいただければ嬉しいです。
(2022.04.04)
※信長公記を下地としていますが諸出来事の年次比定を含め随所に著者の創作および定説ではない解釈等がありますのでご承知置きください。
※アルファポリスの仕様上、「HOTランキング用ジャンル選択」欄を「男性向け」に設定していますが、区別する意図はとくにありません。

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
勝利のために走るのではない。
生きるために走る者は、
傷を負いながらも、歩みを止めない。
戦国という時代の只中で、
彼らは何を失い、
走り続けたのか。
滝川一益と、その郎党。
これは、勝者の物語ではない。
生き延びた者たちの記録である。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

影武者の天下盗り
井上シオ
歴史・時代
「影武者が、本物を超えてしまった——」
百姓の男が“信長”を演じ続けた。
やがて彼は、歴史さえ書き換える“もう一人の信長”になる。
貧しい百姓・十兵衛は、織田信長の影武者として拾われた。
戦場で命を賭け、演じ続けた先に待っていたのは――本能寺の変。
炎の中、信長は死に、十兵衛だけが生き残った。
家臣たちは彼を“信長”と信じ、十兵衛もまた“信長として生きる”ことを選ぶ。
偽物だった男が、やがて本物を凌ぐ采配で天下を動かしていく。
「俺が、信長だ」
虚構と真実が交差するとき、“天下を盗る”のは誰か。
時は戦国。
貧しい百姓の青年・十兵衛は、戦火に焼かれた村で家も家族も失い、彷徨っていた。
そんな彼を拾ったのは、天下人・織田信長の家臣団だった。
その驚くべき理由は——「あまりにも、信長様に似ている」から。
歴史そのものを塗り替える——“影武者が本物を超える”成り上がり戦国譚。
(このドラマは史実を基にしたフィクションです)

屈辱と愛情
守 秀斗
恋愛
最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















