27 / 36
Lesson 26 ぜんぶわかってるよ
しおりを挟む
学校へ行く足が重たかったけれど何事もないような顔をして学校へ行った。
迎えに来る松永の手を取り、他愛のない話をする。
だけど聞いているはずの話は耳からすべて抜けていってしまって、結局どんな話をしたのか、後になってみるとなにひとつ覚えていなかった。
重症。
これじゃダメだってわかってるのに頭と心が一緒になってくれない。
授業中、ぼんやりと眺めてしまう教科書。
そこに刻まれた葵の字が、私の目にはまるで3Dのように浮き彫りになって見える。
「……しも! 大霜陽菜子!」
突然、フルネームで名前を呼ばれて顔を上げる。
教壇に立つ担任が私を呆れたように見つめていた。
「は……はい」
「考え事か?」
「えっと……」
答える言葉が見つからずにうつむく私。
それを見つめるクラスメートの間から、くすくすと小さな笑いが漏れる。
「恋愛にうつつを抜かすのもいいが、しっかり勉強しないとな」
「……はい」
そう言って担任がちらりと松永を見る。
松永が両眉を真ん中に寄せていた。
その顔がなんとなく悲しげに見えて、私はすぐに目を逸らした。
見ないでほしい。
今の私を見ないでほしい。
見透かされる心の中に住むのがあなたじゃないと、そうはっきりわかっていても伝えたくないと意固地になる私を心底見ないで欲しかった。
ゆっくりと腰を下ろす。
担任は文化祭についての話を始めた。
来週の金曜から3日間、学校はお祭りだ。
文化祭が楽しみだったはずなのに、今回はそんな気分にならない。
いっそ休んでしまおうか。
そんな私の耳に松永の勢いのいい声が飛び込んできた。
「俺と大霜が出ます!」
ハッと顔を上げる私に、クラスメートの視線が一気に集まった。
なにを言った?
そう思って松永を見てから担任を見ると、担任は腕組みしながら大きくうなずいた。
「ほかに立候補はいないか?」
担任の言葉には誰ひとり反応しない。
「じゃあ、うちのクラスからは松永と大霜。おまえたちが代表だ」
パチパチと拍手が上がる。
いったい、なんのことやらわからず、ひとりぼんやりする私に担任が笑う。
「ベストカップル賞。きちっと取ってくれよ」
その言葉に私は松永を見た。
ニッコリ。
満面の笑みを湛えて、彼はこちらを見ていた。
反論する間もなく私は文化祭のメインイベントとなるクラス対抗『ベストカップルグランプリ』に、松永とクラスの代表として出ることになってしまった。
そんな気分じゃない。
松永と付き合い始めたけど『ベストカップル』という言葉には抵抗がある。
HRが終わりると、部活へと行こうとする松永を引きとめた。
「なに?」
松永はいつもの甘く爽やかな笑みを私に向けた。
「なんで立候補なんてするの!」
そう言う私を松永は一瞬淋しげに見つめた。
その視線が胸に突き刺さる。
けれど、すぐに元のやんわりとした笑顔を作り。
「自信になるじゃん」
と松永は答えた。
「陽菜子と俺がベストカップルに選ばれたら、俺たちの自信になるじゃん。
『周りが羨ましく思う』くらい、『お似合い』ってことだろ?」
私の胸にあえて響かせるような言葉を選んで言ってるんじゃないか。
そんな気さえする松永の言葉に、私は掴んでいた腕を離してしまった。
「後悔はさせねーって言ったじゃん、俺」
笑みがなくなる松永に胸がギュッと押しつぶされそうになった。
松永の思いがなにも語らない瞳から溢れだしてくる。
それを素直に受けとめられなくて、私は一歩後ずさってしまった。
「全部わかってるよ、俺」
そう言って、松永が私にもう一度ほほ笑みかける。
「わかってても、それでもいいって選んだのは『陽菜子』じゃないから。俺の選んだことだから」
どうしてそんなふうに笑えるの?
葵が好きで好きでたまらないのに、松永から目が離せなくなるのはどうして?
「松永……!」
私に背を向けて、教室を出て行こうとする松永のその背中に向かって呼びかけた。
松永は足をとめて。
「なあ」
と言った。
「ベストカップルになれたら忘れろよ」
トクン、トクンと小さな悲鳴を上げる胸に拳を添えた。
「今すぐには無理でも……俺だけを見てくれよ」
にっこりと松永は笑った。
「私……」
答えが見つからない。
忘れることはできない。
松永だけを見ることに対して、はっきりとした返事をしてあげられない。
「一週間じゃ難しいわな」
コリコリと頭を掻くと松永は笑顔だけを残し行ってしまった。
揺れる瞳に、切なさで溢れる瞳に罪悪感と言う名のシミが心の中に広がっていく。
松永の言うようにすっぱりあきらめてしまえばいい。
だって葵にとって私は『仕方ない』くらいの価値しかない人間なんだから。
「どうすんの?」
松永が出て行った教室の扉とは反対側に千波が立っていた。
「立ち聞きする気はなかったんだけどね。聞こえちゃったもんだから」
そう言いながら、千波は近寄って来た。
「カテキョに言いたいこと、言えなかったんでしょ?」
「千波はなんでもお見通しだね」
「バカね、陽菜子がわかりやすいのよ」
近づいてくる千波に小さく笑みを返した。
「私、カテキョが好きみたい」
「だと思った」
千波の笑顔に、締めつけられていた胸が緩くほどける。
「でもね、松永も嫌いじゃないの」
松永も嫌いじゃない。
でも葵への想いとは遠くかけ離れている。
それがわかって、苦しくて、つらくて。
わかりきっていたのに、松永に甘える自分の中途半端加減にイラついた。
「そりゃ、嫌いだったら手なんて繋げないわよ」
千波が苦笑する。
そして、私の背中をポンっと押す。
「いいじゃない、松永は好きでやってんだもん。そういうの、利用するのは『女の特権』よ」
なんだか、すごく大人びた千波の発言に私は眉尻を下げた。
「ねぇ、何歳?」
「あら、一緒よ。17歳」
「どうしたらそんなこと言えるの?」
私の質問に千波はクスッと小悪魔な笑みを浮かべる。
「さあ? 知識って大事よねぇ」
将来、どんな悪女になるのか……そう思ったら可笑しくなった。
「ベストカップルグランプリはさあ、頑張んなさいよ」
「なんで?」
「きっと……面白いことになると思うから」
何かを企むような千波の笑みに、私は何か嫌な予感がした。
けれど、千波はそんな私の予感など無視するようにフフフッと含んだ笑みを浮かべて見せた。
『面白いこと』?
聞こうとしたけれど、千波はもうその話を遮断するように「帰ろう」と私を促した。
文化祭まで一週間。
もう悩んだって仕方ない。
葵が好き。
この事実はもう曲がらない。
松永と一緒にいると楽。
この事実も同じ、私の中では曲がらない。
それでもいいと言った松永を利用するなんてことは私にはできないから、せめてこの一週間は松永だけを見よう。
どうしても追ってしまうけど。
……葵の影を追ってしまうけど。
文化祭をキリにしよう。
その日までは葵のことは封印してまっすぐに向き合いたい。
きっと最後は『ごめん』と言ってしまうことになるとは思うけど――
片思いでもいいから、葵のことを考えていたいと思う気持ちで心が満たされてしまったから。
たとえ葵にとって私が取るに足らない存在でも、それでも葵がいい。
はっきりした気持ちに全部、全部、決着をつけよう。
ごめん。
もう少しだけ甘えてさせて、松永。
千波と一緒に歩く道に、秋風が吹く。
赤色に姿を変えた葉を乗せて、風が吹き抜けて行く。
見上げた空へと向かう木の葉には手が届かなくて、私はギュッと拳を作った。
風に乗って舞う木の葉に自分自身を重ねながら、それでもやっと答えを見つけた私の顔はさっきよりもほんのすこしだけ晴れやかなものになっていたんじゃないかって思う。
迎えに来る松永の手を取り、他愛のない話をする。
だけど聞いているはずの話は耳からすべて抜けていってしまって、結局どんな話をしたのか、後になってみるとなにひとつ覚えていなかった。
重症。
これじゃダメだってわかってるのに頭と心が一緒になってくれない。
授業中、ぼんやりと眺めてしまう教科書。
そこに刻まれた葵の字が、私の目にはまるで3Dのように浮き彫りになって見える。
「……しも! 大霜陽菜子!」
突然、フルネームで名前を呼ばれて顔を上げる。
教壇に立つ担任が私を呆れたように見つめていた。
「は……はい」
「考え事か?」
「えっと……」
答える言葉が見つからずにうつむく私。
それを見つめるクラスメートの間から、くすくすと小さな笑いが漏れる。
「恋愛にうつつを抜かすのもいいが、しっかり勉強しないとな」
「……はい」
そう言って担任がちらりと松永を見る。
松永が両眉を真ん中に寄せていた。
その顔がなんとなく悲しげに見えて、私はすぐに目を逸らした。
見ないでほしい。
今の私を見ないでほしい。
見透かされる心の中に住むのがあなたじゃないと、そうはっきりわかっていても伝えたくないと意固地になる私を心底見ないで欲しかった。
ゆっくりと腰を下ろす。
担任は文化祭についての話を始めた。
来週の金曜から3日間、学校はお祭りだ。
文化祭が楽しみだったはずなのに、今回はそんな気分にならない。
いっそ休んでしまおうか。
そんな私の耳に松永の勢いのいい声が飛び込んできた。
「俺と大霜が出ます!」
ハッと顔を上げる私に、クラスメートの視線が一気に集まった。
なにを言った?
そう思って松永を見てから担任を見ると、担任は腕組みしながら大きくうなずいた。
「ほかに立候補はいないか?」
担任の言葉には誰ひとり反応しない。
「じゃあ、うちのクラスからは松永と大霜。おまえたちが代表だ」
パチパチと拍手が上がる。
いったい、なんのことやらわからず、ひとりぼんやりする私に担任が笑う。
「ベストカップル賞。きちっと取ってくれよ」
その言葉に私は松永を見た。
ニッコリ。
満面の笑みを湛えて、彼はこちらを見ていた。
反論する間もなく私は文化祭のメインイベントとなるクラス対抗『ベストカップルグランプリ』に、松永とクラスの代表として出ることになってしまった。
そんな気分じゃない。
松永と付き合い始めたけど『ベストカップル』という言葉には抵抗がある。
HRが終わりると、部活へと行こうとする松永を引きとめた。
「なに?」
松永はいつもの甘く爽やかな笑みを私に向けた。
「なんで立候補なんてするの!」
そう言う私を松永は一瞬淋しげに見つめた。
その視線が胸に突き刺さる。
けれど、すぐに元のやんわりとした笑顔を作り。
「自信になるじゃん」
と松永は答えた。
「陽菜子と俺がベストカップルに選ばれたら、俺たちの自信になるじゃん。
『周りが羨ましく思う』くらい、『お似合い』ってことだろ?」
私の胸にあえて響かせるような言葉を選んで言ってるんじゃないか。
そんな気さえする松永の言葉に、私は掴んでいた腕を離してしまった。
「後悔はさせねーって言ったじゃん、俺」
笑みがなくなる松永に胸がギュッと押しつぶされそうになった。
松永の思いがなにも語らない瞳から溢れだしてくる。
それを素直に受けとめられなくて、私は一歩後ずさってしまった。
「全部わかってるよ、俺」
そう言って、松永が私にもう一度ほほ笑みかける。
「わかってても、それでもいいって選んだのは『陽菜子』じゃないから。俺の選んだことだから」
どうしてそんなふうに笑えるの?
葵が好きで好きでたまらないのに、松永から目が離せなくなるのはどうして?
「松永……!」
私に背を向けて、教室を出て行こうとする松永のその背中に向かって呼びかけた。
松永は足をとめて。
「なあ」
と言った。
「ベストカップルになれたら忘れろよ」
トクン、トクンと小さな悲鳴を上げる胸に拳を添えた。
「今すぐには無理でも……俺だけを見てくれよ」
にっこりと松永は笑った。
「私……」
答えが見つからない。
忘れることはできない。
松永だけを見ることに対して、はっきりとした返事をしてあげられない。
「一週間じゃ難しいわな」
コリコリと頭を掻くと松永は笑顔だけを残し行ってしまった。
揺れる瞳に、切なさで溢れる瞳に罪悪感と言う名のシミが心の中に広がっていく。
松永の言うようにすっぱりあきらめてしまえばいい。
だって葵にとって私は『仕方ない』くらいの価値しかない人間なんだから。
「どうすんの?」
松永が出て行った教室の扉とは反対側に千波が立っていた。
「立ち聞きする気はなかったんだけどね。聞こえちゃったもんだから」
そう言いながら、千波は近寄って来た。
「カテキョに言いたいこと、言えなかったんでしょ?」
「千波はなんでもお見通しだね」
「バカね、陽菜子がわかりやすいのよ」
近づいてくる千波に小さく笑みを返した。
「私、カテキョが好きみたい」
「だと思った」
千波の笑顔に、締めつけられていた胸が緩くほどける。
「でもね、松永も嫌いじゃないの」
松永も嫌いじゃない。
でも葵への想いとは遠くかけ離れている。
それがわかって、苦しくて、つらくて。
わかりきっていたのに、松永に甘える自分の中途半端加減にイラついた。
「そりゃ、嫌いだったら手なんて繋げないわよ」
千波が苦笑する。
そして、私の背中をポンっと押す。
「いいじゃない、松永は好きでやってんだもん。そういうの、利用するのは『女の特権』よ」
なんだか、すごく大人びた千波の発言に私は眉尻を下げた。
「ねぇ、何歳?」
「あら、一緒よ。17歳」
「どうしたらそんなこと言えるの?」
私の質問に千波はクスッと小悪魔な笑みを浮かべる。
「さあ? 知識って大事よねぇ」
将来、どんな悪女になるのか……そう思ったら可笑しくなった。
「ベストカップルグランプリはさあ、頑張んなさいよ」
「なんで?」
「きっと……面白いことになると思うから」
何かを企むような千波の笑みに、私は何か嫌な予感がした。
けれど、千波はそんな私の予感など無視するようにフフフッと含んだ笑みを浮かべて見せた。
『面白いこと』?
聞こうとしたけれど、千波はもうその話を遮断するように「帰ろう」と私を促した。
文化祭まで一週間。
もう悩んだって仕方ない。
葵が好き。
この事実はもう曲がらない。
松永と一緒にいると楽。
この事実も同じ、私の中では曲がらない。
それでもいいと言った松永を利用するなんてことは私にはできないから、せめてこの一週間は松永だけを見よう。
どうしても追ってしまうけど。
……葵の影を追ってしまうけど。
文化祭をキリにしよう。
その日までは葵のことは封印してまっすぐに向き合いたい。
きっと最後は『ごめん』と言ってしまうことになるとは思うけど――
片思いでもいいから、葵のことを考えていたいと思う気持ちで心が満たされてしまったから。
たとえ葵にとって私が取るに足らない存在でも、それでも葵がいい。
はっきりした気持ちに全部、全部、決着をつけよう。
ごめん。
もう少しだけ甘えてさせて、松永。
千波と一緒に歩く道に、秋風が吹く。
赤色に姿を変えた葉を乗せて、風が吹き抜けて行く。
見上げた空へと向かう木の葉には手が届かなくて、私はギュッと拳を作った。
風に乗って舞う木の葉に自分自身を重ねながら、それでもやっと答えを見つけた私の顔はさっきよりもほんのすこしだけ晴れやかなものになっていたんじゃないかって思う。
0
お気に入りに追加
52
あなたにおすすめの小説

異世界召喚されたけどヤバい国だったので逃げ出したら、イケメン騎士様に溺愛されました
平山和人
恋愛
平凡なOLの清水恭子は異世界に集団召喚されたが、見るからに怪しい匂いがプンプンしていた。
騎士団長のカイトの出引きで国を脱出することになったが、追っ手に追われる逃亡生活が始まった。
そうした生活を続けていくうちに二人は相思相愛の関係となり、やがて結婚を誓い合うのであった。
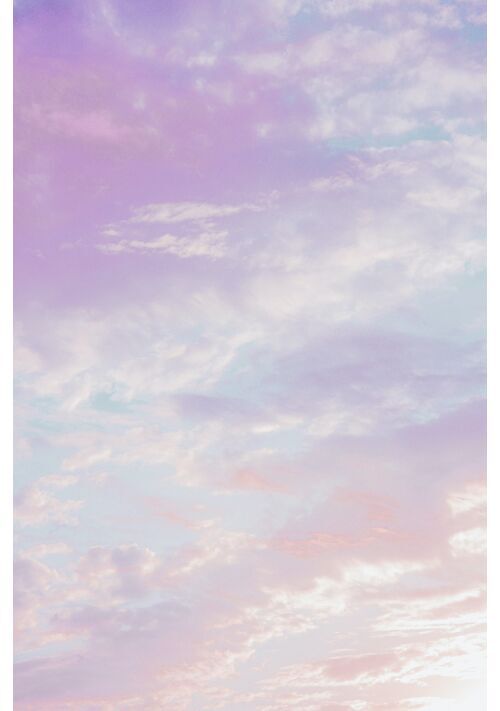
極道に大切に飼われた、お姫様
真木
恋愛
珈涼は父の組のため、生粋の極道、月岡に大切に飼われるようにして暮らすことになる。憧れていた月岡に甲斐甲斐しく世話を焼かれるのも、教え込まれるように夜ごと結ばれるのも、珈涼はただ恐ろしくて殻にこもっていく。繊細で怖がりな少女と、愛情の伝え方が下手な極道の、すれ違いラブストーリー。

わたしのことはお気になさらず、どうぞ、元の恋人とよりを戻してください。
ふまさ
恋愛
「あたし、気付いたの。やっぱりリッキーしかいないって。リッキーだけを愛しているって」
人気のない校舎裏。熱っぽい双眸で訴えかけたのは、子爵令嬢のパティだ。正面には、伯爵令息のリッキーがいる。
「学園に通いはじめてすぐに他の令息に熱をあげて、ぼくを捨てたのは、きみじゃないか」
「捨てたなんて……だって、子爵令嬢のあたしが、侯爵令息様に逆らえるはずないじゃない……だから、あたし」
一歩近付くパティに、リッキーが一歩、後退る。明らかな動揺が見えた。
「そ、そんな顔しても無駄だよ。きみから侯爵令息に言い寄っていたことも、その侯爵令息に最近婚約者ができたことも、ぼくだってちゃんと知ってるんだからな。あてがはずれて、仕方なくぼくのところに戻って来たんだろ?!」
「……そんな、ひどい」
しくしくと、パティは泣き出した。リッキーが、うっと怯む。
「ど、どちらにせよ、もう遅いよ。ぼくには婚約者がいる。きみだって知ってるだろ?」
「あたしが好きなら、そんなもの、解消すればいいじゃない!」
パティが叫ぶ。無茶苦茶だわ、と胸中で呟いたのは、二人からは死角になるところで聞き耳を立てていた伯爵令嬢のシャノン──リッキーの婚約者だった。
昔からパティが大好きだったリッキーもさすがに呆れているのでは、と考えていたシャノンだったが──。
「……そんなにぼくのこと、好きなの?」
予想もしないリッキーの質問に、シャノンは目を丸くした。対してパティは、目を輝かせた。
「好き! 大好き!」
リッキーは「そ、そっか……」と、満更でもない様子だ。それは、パティも感じたのだろう。
「リッキー。ねえ、どうなの? 返事は?」
パティが詰め寄る。悩んだすえのリッキーの答えは、
「……少し、考える時間がほしい」
だった。

セカンドラブ ー30歳目前に初めての彼が7年ぶりに現れてあの時よりちゃんと抱いてやるって⁉ 【完結】
remo
恋愛
橘 あおい、30歳目前。
干からびた生活が長すぎて、化石になりそう。このまま一生1人で生きていくのかな。
と思っていたら、
初めての相手に再会した。
柚木 紘弥。
忘れられない、初めての1度だけの彼。
【完結】ありがとうございました‼

五歳の時から、側にいた
田尾風香
恋愛
五歳。グレースは初めて国王の長男のグリフィンと出会った。
それからというもの、お互いにいがみ合いながらもグレースはグリフィンの側にいた。十六歳に婚約し、十九歳で結婚した。
グリフィンは、初めてグレースと会ってからずっとその姿を追い続けた。十九歳で結婚し、三十二歳で亡くして初めて、グリフィンはグレースへの想いに気付く。
前編グレース視点、後編グリフィン視点です。全二話。後編は来週木曜31日に投稿します。

サラシがちぎれた男装騎士の私、初恋の陛下に【女体化の呪い】だと勘違いされました。
ゆちば
恋愛
ビリビリッ!
「む……、胸がぁぁぁッ!!」
「陛下、声がでかいです!」
◆
フェルナン陛下に密かに想いを寄せる私こと、護衛騎士アルヴァロ。
私は女嫌いの陛下のお傍にいるため、男のフリをしていた。
だがある日、黒魔術師の呪いを防いだ際にサラシがちぎれてしまう。
たわわなたわわの存在が顕になり、絶対絶命の私に陛下がかけた言葉は……。
「【女体化の呪い】だ!」
勘違いした陛下と、今度は男→女になったと偽る私の恋の行き着く先は――?!
勢い強めの3万字ラブコメです。
全18話、5/5の昼には完結します。
他のサイトでも公開しています。

【完結】その男『D』につき~初恋男は独占欲を拗らせる~
蓮美ちま
恋愛
最低最悪な初対面だった。
職場の同僚だろうと人妻ナースだろうと、誘われればおいしく頂いてきた来る者拒まずでお馴染みのチャラ男。
私はこんな人と絶対に関わりたくない!
独占欲が人一倍強く、それで何度も過去に恋を失ってきた私が今必死に探し求めているもの。
それは……『Dの男』
あの男と真逆の、未経験の人。
少しでも私を好きなら、もう私に構わないで。
私が探しているのはあなたじゃない。
私は誰かの『唯一』になりたいの……。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















