7 / 9
リンク
しおりを挟む
おばあさんの写真が届いた日、桜子は再び祭りの夢を見ていた。
それはいつもと少しだけ違う夢で、いつもの桜子よりもずいぶんと視界が低かった。
歩くとコンクリートに履物が当ってカランコロンと涼しげな音を立てるし、着ているものはお腹のあたりが窮屈だ。
祭りの中にいるというのに恐怖心はなく、出店をひとつひとつ覗いてみては歓声をあげる。
今日が祭りであることが当たり前のように感じ、いつしか桜子は右手に綿飴、左手には水風船を持っていた。
遠くから聞こえてくる笛や太鼓の音も心地よく響いて聞こえ、ダンジリの明かりを目指して歩き出す。
「わぁ……!」
光に反射して輝く林檎飴がすごく綺麗で、桜子は子供のような声を上げ、目を輝かせた。
「林檎飴、1つちょうだい」
手持ちも確認せずにそう言うと、おじさんに大きな林檎飴を受け取ってから、お金が足りない事に気がついた。
「いいよいいよ。今日は祭りなんだから楽しんでおいで」
焦って巾着の中を必死で探す桜子に、おじさんは笑顔を向けた。
「ありがとう、おじさん!」
キラキラ光る林檎飴を食べながら、再び桜子は歩き出す。
甘い飴が口いっぱいに広がって、幸せな気分になってくる。
ついつい頬が緩み、1人でクスクスと笑い始めた。
楽しい。
お祭りって楽しいし、林檎飴ってとてもおいしい。
どうしてこれが戦争なのだろう。
どうしてこれが恐怖なのだろう。
祭りの中にいると、祭り戦争のことなんて忘れてしまいそうになる。
「ダンジリ!」
大人の男たちが肩へ担いでいる大きなダンジリが、すぐ横を通り過ぎた。
ダンジリには色とりどりのチョウチンがぶら下がっていて、屋根には大きな作り物の金魚が乗っかっている。
林檎飴を食べながらその金魚を見送っていると、その眼がギロリとこちらへ動いた。
「金魚がこっち見た!」
それでも怖くはない、ただただ楽しかった。
こんなお祭りがいつまでも続くと思っていた。
毎年毎年、必ず繰り返されると思っていた。
人の関係がどんどん軽薄になり、伝統行事が失われていく時代になっても、それは変わらないと思っていた。
よく晴れた夏の日に昼間から浴衣を着て待っていた時、《雨天中止》の知らせが来ても。
ずっとずっと、待っていた――。
『祭りは死んだ』
林檎飴をくれた店のおじさんが、灰色の濁った目をして呟いた。
祭りは死んだ――。
その言葉の意味はよくわからなかったけれど、桜子は胸に大きな穴が開き、悲しさに包まれたのだった。
☆☆☆
「どうした? 平気か?」
そう言いながら揺さぶり起こしてくれたのはおじいさんだった。
目を開けると、視界がぼんやりと滲んでいる。
「なんだか、とても悲しい夢を見た気がする……」
「だから泣いてたんだな」
言われて初めて自分が泣いていることに気がつく。
頬の涙をぬぐうと、おじいさんが手の甲をさすってくれる。
そうされていると落ち着くようだった。
「おばあさんも、眠れない夜にこうして手の甲をさすると落ち着いて眠れるようになったんだよ」
「私、おばあさんにすごくよく似てるのね」
「あぁ、そうだよ」
今度は悲しい夢を見ませんように。
そう呟きながら、桜子は再び眠りについたのだった。
☆☆☆
祭り戦争が4日後に近づいていた。
テレビでは祭り戦争の時に必要な事、やってはいけないことなどを毎日のように繰り返し放送されている。
桜子は地下のシューターから戻ってきて「修理が終わったみたいよ」と、修哉に伝えた。
シューターのどこかが壊れていたというワケではないが、念には念を入れて新しいものに交換してもらったのだ。
「そうか、よかった。これで桜子も安心できるな」
「えぇ」
祭り戦争を一番怖がっているのが自分だとわかっているから、桜子は頬を少し赤らめて頷いた。
「戦争は簡単に家の中にまで入ってきて荒らしていく。今日は仕事が休みだから、必要なものシューターに運ぼうと思うんだ」
手伝ってくれるよね?
修哉の言葉に、桜子はもちろん。と、返事をした。
荷物を運ぶのは単調で、しかし大変な作業だった。
必要なものはすべてロボットやコンピューター内に納められているため、それごと運ばなければならないのだ。
昔みたいに置き場に困るということはなくなったが、いざ移動しようという時には困ってしまう。
どんどんコンパクトなロボットが出ているようだけれど、この家を建てるために買うのを我慢していたので家には古くて大きなものしかない。
「この中のものはメモリーカードに移し変えよう。テレビの中のデータはそのまま地下へ転送して、それから――」
そんな事をしているとあっという間に一日が過ぎていく。
2人で作業を続けている間、修哉は新しく入った女子社員のことばかりを話していた。
とにかくすごくよく働いて、気がきいて、今時いないような女の子なんだとか。
桜子はその話しを聞きながらも、頭の中にはキラキラと輝く林檎飴が存在した。
あれはいったいどんな味なんだろう?
夢の中で食べた時は、甘くて、ほっぺがジンジンした。
きっと、実際に食べればもっともっとおいしいハズだ。
「桜子、聞いてる?」
「えぇ、聞いてるわよ。いい子ね、その子」
嫌味ではなく素直にそう言ったのに、修哉はニヤリと笑って「もしかして焼きもちかい?」と言ってきた。
そんな事ないわ。
と言いかけたが言葉を飲み込み、「そうね」と、微笑んだ。
修哉は、いつだって自分を一番に考えていてほしいと思っている人なんだ。
桜子が焼きもちをやくと、修哉は嬉しがる。
「心配するなよ。俺は桜子が一番だからさ」
林檎飴って、たとえばこんなキスよりも甘いんだろうか……。
☆☆☆
「私、昨日夢の中で小さな女の子になってたの」
修哉のキスを合図に作業を止めた2人は、今ベッドの中にいる。
「うん……」
半分夢の中にいる修哉が、返事をしてくれる。
「それは、今まで私が夢の中で客観的に見てた女の子なの。綿菓子とヨーヨーを持ってた」
「うん……」
「その夢の中に、私の姿はなかったの」
これって、一体どういうことなんだろう?
今まで見ていた夢とは全然違う。
楽しい祭りがなくなってしまうという悲しい夢。
夢の中の彼女と私がリンクしているような、そんな不思議な夢。
「ねぇ、修哉私怖いの」
次眠ると、一体どんな夢を見るのか、怖いの――。
それはいつもと少しだけ違う夢で、いつもの桜子よりもずいぶんと視界が低かった。
歩くとコンクリートに履物が当ってカランコロンと涼しげな音を立てるし、着ているものはお腹のあたりが窮屈だ。
祭りの中にいるというのに恐怖心はなく、出店をひとつひとつ覗いてみては歓声をあげる。
今日が祭りであることが当たり前のように感じ、いつしか桜子は右手に綿飴、左手には水風船を持っていた。
遠くから聞こえてくる笛や太鼓の音も心地よく響いて聞こえ、ダンジリの明かりを目指して歩き出す。
「わぁ……!」
光に反射して輝く林檎飴がすごく綺麗で、桜子は子供のような声を上げ、目を輝かせた。
「林檎飴、1つちょうだい」
手持ちも確認せずにそう言うと、おじさんに大きな林檎飴を受け取ってから、お金が足りない事に気がついた。
「いいよいいよ。今日は祭りなんだから楽しんでおいで」
焦って巾着の中を必死で探す桜子に、おじさんは笑顔を向けた。
「ありがとう、おじさん!」
キラキラ光る林檎飴を食べながら、再び桜子は歩き出す。
甘い飴が口いっぱいに広がって、幸せな気分になってくる。
ついつい頬が緩み、1人でクスクスと笑い始めた。
楽しい。
お祭りって楽しいし、林檎飴ってとてもおいしい。
どうしてこれが戦争なのだろう。
どうしてこれが恐怖なのだろう。
祭りの中にいると、祭り戦争のことなんて忘れてしまいそうになる。
「ダンジリ!」
大人の男たちが肩へ担いでいる大きなダンジリが、すぐ横を通り過ぎた。
ダンジリには色とりどりのチョウチンがぶら下がっていて、屋根には大きな作り物の金魚が乗っかっている。
林檎飴を食べながらその金魚を見送っていると、その眼がギロリとこちらへ動いた。
「金魚がこっち見た!」
それでも怖くはない、ただただ楽しかった。
こんなお祭りがいつまでも続くと思っていた。
毎年毎年、必ず繰り返されると思っていた。
人の関係がどんどん軽薄になり、伝統行事が失われていく時代になっても、それは変わらないと思っていた。
よく晴れた夏の日に昼間から浴衣を着て待っていた時、《雨天中止》の知らせが来ても。
ずっとずっと、待っていた――。
『祭りは死んだ』
林檎飴をくれた店のおじさんが、灰色の濁った目をして呟いた。
祭りは死んだ――。
その言葉の意味はよくわからなかったけれど、桜子は胸に大きな穴が開き、悲しさに包まれたのだった。
☆☆☆
「どうした? 平気か?」
そう言いながら揺さぶり起こしてくれたのはおじいさんだった。
目を開けると、視界がぼんやりと滲んでいる。
「なんだか、とても悲しい夢を見た気がする……」
「だから泣いてたんだな」
言われて初めて自分が泣いていることに気がつく。
頬の涙をぬぐうと、おじいさんが手の甲をさすってくれる。
そうされていると落ち着くようだった。
「おばあさんも、眠れない夜にこうして手の甲をさすると落ち着いて眠れるようになったんだよ」
「私、おばあさんにすごくよく似てるのね」
「あぁ、そうだよ」
今度は悲しい夢を見ませんように。
そう呟きながら、桜子は再び眠りについたのだった。
☆☆☆
祭り戦争が4日後に近づいていた。
テレビでは祭り戦争の時に必要な事、やってはいけないことなどを毎日のように繰り返し放送されている。
桜子は地下のシューターから戻ってきて「修理が終わったみたいよ」と、修哉に伝えた。
シューターのどこかが壊れていたというワケではないが、念には念を入れて新しいものに交換してもらったのだ。
「そうか、よかった。これで桜子も安心できるな」
「えぇ」
祭り戦争を一番怖がっているのが自分だとわかっているから、桜子は頬を少し赤らめて頷いた。
「戦争は簡単に家の中にまで入ってきて荒らしていく。今日は仕事が休みだから、必要なものシューターに運ぼうと思うんだ」
手伝ってくれるよね?
修哉の言葉に、桜子はもちろん。と、返事をした。
荷物を運ぶのは単調で、しかし大変な作業だった。
必要なものはすべてロボットやコンピューター内に納められているため、それごと運ばなければならないのだ。
昔みたいに置き場に困るということはなくなったが、いざ移動しようという時には困ってしまう。
どんどんコンパクトなロボットが出ているようだけれど、この家を建てるために買うのを我慢していたので家には古くて大きなものしかない。
「この中のものはメモリーカードに移し変えよう。テレビの中のデータはそのまま地下へ転送して、それから――」
そんな事をしているとあっという間に一日が過ぎていく。
2人で作業を続けている間、修哉は新しく入った女子社員のことばかりを話していた。
とにかくすごくよく働いて、気がきいて、今時いないような女の子なんだとか。
桜子はその話しを聞きながらも、頭の中にはキラキラと輝く林檎飴が存在した。
あれはいったいどんな味なんだろう?
夢の中で食べた時は、甘くて、ほっぺがジンジンした。
きっと、実際に食べればもっともっとおいしいハズだ。
「桜子、聞いてる?」
「えぇ、聞いてるわよ。いい子ね、その子」
嫌味ではなく素直にそう言ったのに、修哉はニヤリと笑って「もしかして焼きもちかい?」と言ってきた。
そんな事ないわ。
と言いかけたが言葉を飲み込み、「そうね」と、微笑んだ。
修哉は、いつだって自分を一番に考えていてほしいと思っている人なんだ。
桜子が焼きもちをやくと、修哉は嬉しがる。
「心配するなよ。俺は桜子が一番だからさ」
林檎飴って、たとえばこんなキスよりも甘いんだろうか……。
☆☆☆
「私、昨日夢の中で小さな女の子になってたの」
修哉のキスを合図に作業を止めた2人は、今ベッドの中にいる。
「うん……」
半分夢の中にいる修哉が、返事をしてくれる。
「それは、今まで私が夢の中で客観的に見てた女の子なの。綿菓子とヨーヨーを持ってた」
「うん……」
「その夢の中に、私の姿はなかったの」
これって、一体どういうことなんだろう?
今まで見ていた夢とは全然違う。
楽しい祭りがなくなってしまうという悲しい夢。
夢の中の彼女と私がリンクしているような、そんな不思議な夢。
「ねぇ、修哉私怖いの」
次眠ると、一体どんな夢を見るのか、怖いの――。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

病気になって芸能界から消えたアイドル。退院し、復学先の高校には昔の仕事仲間が居たけれど、彼女は俺だと気付かない
月島日向
ライト文芸
俺、日生遼、本名、竹中祐は2年前に病に倒れた。
人気絶頂だった『Cherry’s』のリーダーをやめた。
2年間の闘病生活に一区切りし、久しぶりに高校に通うことになった。けど、誰も俺の事を元アイドルだとは思わない。薬で細くなった手足。そんな細身の体にアンバランスなムーンフェイス(薬の副作用で顔だけが大きくなる事)
。
誰も俺に気付いてはくれない。そう。
2年間、連絡をくれ続け、俺が無視してきた彼女さえも。
もう、全部どうでもよく感じた。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
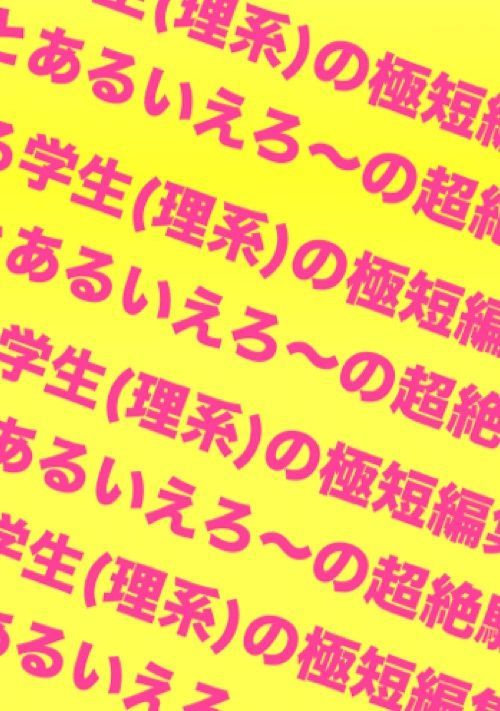
いえろ〜の極短編集
いえろ~
ライト文芸
私、いえろ~が書いた極短編集です。
☆極短編・・・造語です。一話完結かつ字数がかなり少なめ(現在目安1000字前後)の物語。ショートショートって言うのかもしれないけどそんなの知らないです(開き直り)
ー ストーブ ー
ストーブを消した五分後、いつもつけ直してしまう女の子のお話。
ー 大空 ー
色々思い悩んでいる学生は、大空を見てこう思ったのだそうだ。
ー ルーズリーフ ー
私が弟を泣かせてしまった次の日、弟はこれを差し出してきた。
ー Ideal - Idea ー
僕は、理想の自分になるために、とにかく走った。
ー 限られた時間の中で ー
私は、声を大にして言いたい。
ー 僕を見て ー
とにかく、目の前にいる、僕だけを見てよ。
ー この世も悲観したものじゃない ー
ただ殻に閉じこもってた、僕に訪れた幸運のお話。

いっぱい命じて〜無自覚SubはヤンキーDomに甘えたい〜
きよひ
BL
無愛想な高一Domヤンキー×Subの自覚がない高三サッカー部員
Normalの諏訪大輝は近頃、謎の体調不良に悩まされていた。
そんな折に出会った金髪の一年生、甘井呂翔。
初めて会った瞬間から甘井呂に惹かれるものがあった諏訪は、Domである彼がPlayする様子を覗き見てしまう。
甘井呂に優しく支配されるSubに自分を重ねて胸を熱くしたことに戸惑う諏訪だが……。
第二性に振り回されながらも、互いだけを求め合うようになる青春の物語。
※現代ベースのDom/Subユニバースの世界観(独自解釈・オリジナル要素あり)
※不良の喧嘩描写、イジメ描写有り
初日は5話更新、翌日からは2話ずつ更新の予定です。

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















