88 / 255
第9章
第88話 分類
しおりを挟む
クラスメートと教室に二人きりでも、特に何の変化も生じなかった。もちろん、心的変化は多少生じる。それはたぶん人間の動物としての機能だ。同類、もしくは非同類が自分の周囲にどれだけ存在するのか、常に把握しようとする。
月夜は構わず本を読み続ける。
学校の授業は、面白いといえば面白かった。一年生の内はまだ理系、文系という括りはなく、芸術科目以外は皆一律に同じ教科を履修する。英語も数学も国語も、どれもそれぞれの特色があり、また逆にそれぞれに関連する部分も見られ、中学の頃よりも教科の内外問わず内容が一層緻密になった感じだ。
けれど、中学の頃と変わらないという見方もできそうだった。何をもって違う、同じという判断をするのかは不明だが、どちらともとれるように月夜には思えた。外見からすると同じ、内に入って見渡せば違うという感じだろうか。
自分のように、学校の授業についてそうした分析を行っている者が、ほかにどれくらいいるのか、月夜は知りたかった。別に自分をとりたてて示したいのではない。純粋な疑問として興味があるのだ。あるいは、自分の同類を見極めたいという、これまた動物的な視座の表れかもしれない。
皆、与えられた課題に一生懸命取り組んでいるように見える。それは大変素晴らしいことで、学生としての本分を充分に発揮しているといえる。しかしながら、ときにはそうした内の視点からではなく、外の視点からも物事を見つめる必要があるのではないか。自分を自分として見るのではなく、集団の内の一部として見るということだ。
英語、数学、国語と、科目はいくつかに分けられているが、どうして分かれているのだろう?
小学校に入学したときから、科目は分けられて提示されてきたから、それは最早当たり前のこととして認識されている。けれど、考えてみれば奇妙な話だ。たとえば、英語と国語は、ともに言語という括りで一つにまとめることができる。さらにいえば、それは「まとめられる」可能性を秘めているのではない。もともとは一つだった。それを人間の恣意的な判断によって分けたのだ。すなわち、英語と国語というのは、人間の文化の一部を切り取った部分、ということになる。
文系と理系の区別というのは、まさにそうした行為の結果の表れであり、本当は、そんなふうに明確に分けられるものではない。理系だからといって、英語や国語ができなくて良いというわけにはいかない。文字が読めなければ、如何なる教科の参考書も読むことができない。
月夜は構わず本を読み続ける。
学校の授業は、面白いといえば面白かった。一年生の内はまだ理系、文系という括りはなく、芸術科目以外は皆一律に同じ教科を履修する。英語も数学も国語も、どれもそれぞれの特色があり、また逆にそれぞれに関連する部分も見られ、中学の頃よりも教科の内外問わず内容が一層緻密になった感じだ。
けれど、中学の頃と変わらないという見方もできそうだった。何をもって違う、同じという判断をするのかは不明だが、どちらともとれるように月夜には思えた。外見からすると同じ、内に入って見渡せば違うという感じだろうか。
自分のように、学校の授業についてそうした分析を行っている者が、ほかにどれくらいいるのか、月夜は知りたかった。別に自分をとりたてて示したいのではない。純粋な疑問として興味があるのだ。あるいは、自分の同類を見極めたいという、これまた動物的な視座の表れかもしれない。
皆、与えられた課題に一生懸命取り組んでいるように見える。それは大変素晴らしいことで、学生としての本分を充分に発揮しているといえる。しかしながら、ときにはそうした内の視点からではなく、外の視点からも物事を見つめる必要があるのではないか。自分を自分として見るのではなく、集団の内の一部として見るということだ。
英語、数学、国語と、科目はいくつかに分けられているが、どうして分かれているのだろう?
小学校に入学したときから、科目は分けられて提示されてきたから、それは最早当たり前のこととして認識されている。けれど、考えてみれば奇妙な話だ。たとえば、英語と国語は、ともに言語という括りで一つにまとめることができる。さらにいえば、それは「まとめられる」可能性を秘めているのではない。もともとは一つだった。それを人間の恣意的な判断によって分けたのだ。すなわち、英語と国語というのは、人間の文化の一部を切り取った部分、ということになる。
文系と理系の区別というのは、まさにそうした行為の結果の表れであり、本当は、そんなふうに明確に分けられるものではない。理系だからといって、英語や国語ができなくて良いというわけにはいかない。文字が読めなければ、如何なる教科の参考書も読むことができない。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
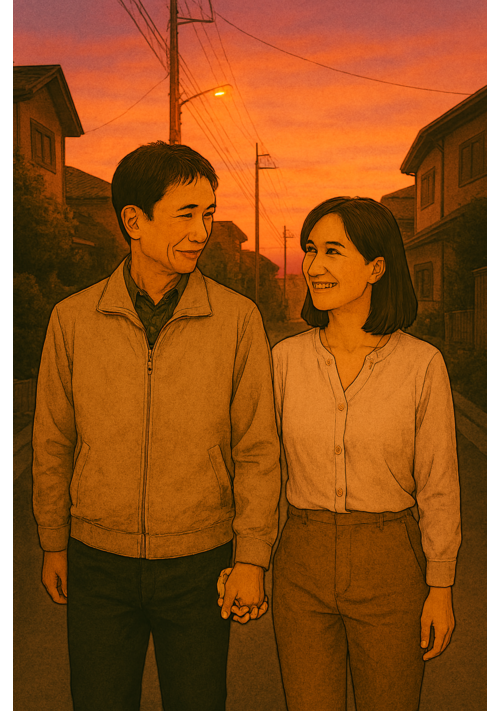
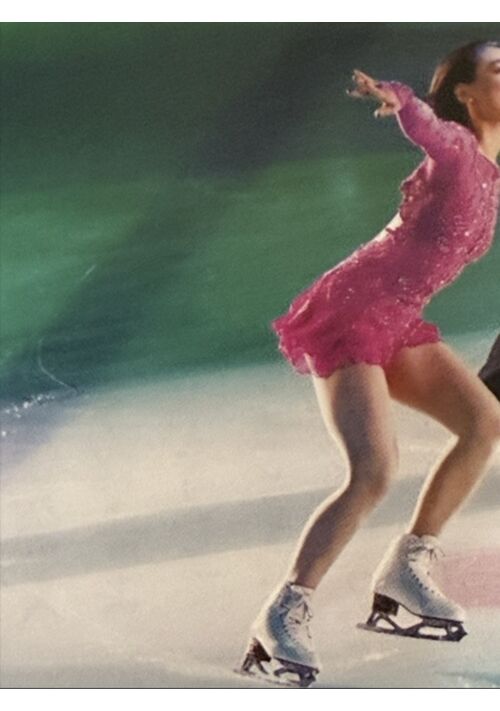
あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。



上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















