11 / 255
第2章
第11話 破壊、静寂の朝
しおりを挟む
ベッドの中で目を覚ました。時刻は午前五時。若干曇った眼を擦りながら身体を起こし、月夜は床に足をつく。隣ではフィルが小さく丸まっている。彼に毛布をかけ直し、クローゼットの前まで移動して、彼女は衣服を取り出して着替えた。
昨日は遅くまで起きていたから、三時間くらいしか眠っていない。けれど、彼女にはそれで充分だった。特に身体に不具合はない。今までずっとそうしてきたし、それが自分に合った生活の仕方なのだろう、ということで彼女は理解している。
月夜は、ご飯も食べないし、あまり眠らない。これだけ聞くと、どこか人間離れした印象を受ける。そして、事実として、彼女は自分が人間に属する存在なのか、未だに判断しかねていた。たぶん、現代に生きる多くの者が、自分は人間だと信じて生きているだろうが、そう述べられるはっきりとした根拠がないことに、果たしてどれだけの者が気がついているだろうか。たしかに、染色体の数を計測すれば、それで人間か否かを判断することはできる。しかし、染色体の数が人間らしさの根源だとはいえない。
自分は、何者か?
幼稚だが、しかし、よく心に浮かぶ問でもある。
いつも通り勉強机に座って、月夜は本を読み始めた。昨日読んでいたものとは違って、今度は数学に関する本だった。彼女は別段数学が得意でもないし、苦手でもない。世間では、こういう状態を普通と呼ぶらしい。普通とは一体何だろうか。意味としては、変わらない、ということを述べているように思えるが、万物流転という言葉があることとどう折り目をつけるのだろう。
机の上に置いてある目覚まし時計が、今さらになって鳴り出した。月夜は一瞬それに目を向け、次の瞬間には手を伸ばして、その煩いマシーンの頭を軽く押した。喧しいベルの音はすぐに止み、また静かな朝の時間が訪れる。
けれど、布団の中でごそごそと音がして、途端に生活感が生じるようになった。
振り向かなくても分かった。
フィルが目を覚まして、彼女の傍に寄ってきた。
「目覚ましをかけたのは、フィル?」月夜は珍しく自分から声をかけた。
「ああ、そうだ」フィルは月夜の膝に乗って、彼女を見上げる。「なかなか素晴らしい案だろう?」
「あん? あんって、何?」
「パンの中に入っているやつ」
「え?」
「今日は、ちょっと寒いな」
「フィルが?」
「え?」
沈黙が訪れる。
昨日は遅くまで起きていたから、三時間くらいしか眠っていない。けれど、彼女にはそれで充分だった。特に身体に不具合はない。今までずっとそうしてきたし、それが自分に合った生活の仕方なのだろう、ということで彼女は理解している。
月夜は、ご飯も食べないし、あまり眠らない。これだけ聞くと、どこか人間離れした印象を受ける。そして、事実として、彼女は自分が人間に属する存在なのか、未だに判断しかねていた。たぶん、現代に生きる多くの者が、自分は人間だと信じて生きているだろうが、そう述べられるはっきりとした根拠がないことに、果たしてどれだけの者が気がついているだろうか。たしかに、染色体の数を計測すれば、それで人間か否かを判断することはできる。しかし、染色体の数が人間らしさの根源だとはいえない。
自分は、何者か?
幼稚だが、しかし、よく心に浮かぶ問でもある。
いつも通り勉強机に座って、月夜は本を読み始めた。昨日読んでいたものとは違って、今度は数学に関する本だった。彼女は別段数学が得意でもないし、苦手でもない。世間では、こういう状態を普通と呼ぶらしい。普通とは一体何だろうか。意味としては、変わらない、ということを述べているように思えるが、万物流転という言葉があることとどう折り目をつけるのだろう。
机の上に置いてある目覚まし時計が、今さらになって鳴り出した。月夜は一瞬それに目を向け、次の瞬間には手を伸ばして、その煩いマシーンの頭を軽く押した。喧しいベルの音はすぐに止み、また静かな朝の時間が訪れる。
けれど、布団の中でごそごそと音がして、途端に生活感が生じるようになった。
振り向かなくても分かった。
フィルが目を覚まして、彼女の傍に寄ってきた。
「目覚ましをかけたのは、フィル?」月夜は珍しく自分から声をかけた。
「ああ、そうだ」フィルは月夜の膝に乗って、彼女を見上げる。「なかなか素晴らしい案だろう?」
「あん? あんって、何?」
「パンの中に入っているやつ」
「え?」
「今日は、ちょっと寒いな」
「フィルが?」
「え?」
沈黙が訪れる。
0
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。


敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
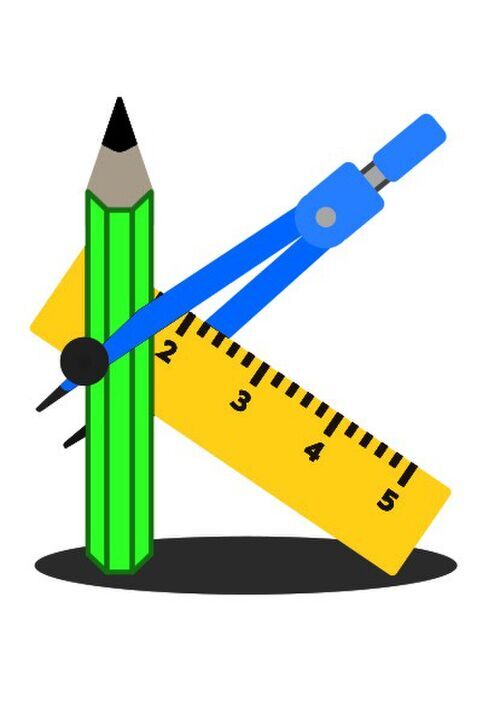
Dream Per Second
羽上帆樽
ライト文芸
古文書の解析をすることになった二人。しかし、作業は思わぬ怪異に見舞われることになる。近所のスーパーマーケット。三角形の大地。山の上の時計台。彼らはどこにいて、どこに向かうおうとしているのか?

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















