9 / 10
第9章 不道徳
しおりを挟む
週が明けて、また学校が始まった。多くの生徒が、もう冬休み気分を抜けて、通常の生活に馴染んでいるようだ。そうやって、勉強するのが自分の役目なのだと生徒が錯覚することで、学校という小さな社会は成り立っている。
その日の朝、例の図書委員の女子生徒が、登校するなり、事件が解決したことを告げた。いや、解決という言い方はおかしいかもしれない。彼女の話によると、犯人が捕まったわけではないが、盗まれた本が、すべて返却ボックスに戻っているのが見つかった、とのことだった。無断で持ち出されていたのは、小説と、図鑑だが、どちらも同じタイミングで返されていたのを見ると、犯人は同一人物だったらしい、ということを、彼女は今さらながら指摘した。複数犯ではないか、という意見も、図書委員の中では出ていたようだ。
忘れ去られる前に、事件が解決するのは、学校では比較的珍しいことだ。だから、彼女の報告を聞いたクラスメートは、何ともいえない顔をしていた。刺激的な出来事が起きたのに、それが解決してしまったとなれば、もう何も面白いことはない。もちろん、皆、本が返ってきたこと自体は、喜ばしいと考えているだろう。けれど、陳腐な日常を彩るコンテンツが、一瞬の内に姿を消してしまった。これには落胆している生徒が多かった。
そして、彼らがどれだけ喚いたとしても、日常はいつも通りやって来る。担任の教師が教室に入ってきて、ホームルームが始まった。今日も授業が始まる。
授業中、月夜は、ぼうっと窓の外を眺めていた。
教師の話は耳に入っていたが、脳できちんと処理されている割合は、いつもの六十パーセント程度にすぎなかった。残りの四十パーセントは、何の処理も成されることなく、音として反対側の耳から出ていく(そんなことは、物理的にありえないが)。
今日は雪が降っていた。ぱらぱらとした粉雪で、地面に積もったのを踏めば、良い感触を味わえそうだ。
そろそろ、試験の準備をしなくてはならない、と月夜は考える。
とはいっても、彼女は毎日予習と復習を行っているから、試験のための勉強は必要なかった。普段と同じように勉強して、前日に少しだけ体調に気を遣えば良い。もっとも、どれほど気を遣っても、体調を悪くすることはある。だから、完全に体調を管理することはできない。しかし、百パーセント体調を崩さない方法も、ないとはいえない。自ら命を断てば、もう二度と体調を崩すことはない。
右斜め前方に目を向ける。
囀は、授業中だというのに、机に突っ伏して眠っていた。
教師は何も言わない。
その背中が、妙に寂しそうに見えた。
今すぐ立ち上がって、後ろから抱き締めたくなった。
でも、今は授業中だから、それはできない。
では、授業が終わったら、それはできるのか?
月夜には、その自信はなかった。
手を繋ぐことはできるのに、どうして、抱き締めることはできないのか?
どちらも、自分と相手の接触という、酷く根本的なコミュニケーションにすぎないのに……。
数学の授業中、月夜はシャープペンシルを何度か回した。特に回したかったわけではない。ただ、そんなふうに指を動かしていないと、なんだか落ち着かなかった。
そして、そんなことをしても、全然落ち着かなかった。
昼休みになって、月夜は自分から囀の傍に行った。
後ろの席のクラスメートと話していた彼女は、顔を上げて月夜を見る。
「どうしたの? 何か用事?」囀は笑顔で尋ねた。
月夜は首を振る。
「用事はないけど、少し、話したい、と思って」
囀はクラスメートとの会話を中断し、月夜に付き合う姿勢を確立した。話し相手のクラスメートは、そんな囀の対応を、快く受け入れてくれた。人の優しさとは、本来こういうものだ、と月夜は思う。その点、自分は、あまり、彼女に優しくできていないかもしれない、とも思った。
「何?」
廊下に出て、窓の外を向いていた月夜に、囀が質問した。
月夜は彼女を見る。
「ごめん」月夜は謝った。「何か、傷つけてしまったかもしれない、と思って」
「何を?」囀は笑った。「えっと、どういう意味?」
「うーんと……」
月夜は必死に考える。けれど、何を伝えたいのか、自分でも分からなくなってしまった。いや、本当は具体的に伝えいたことがないのに、何かを伝えたいと、形だけを想定していたことを、今になって気づいたのだ。
そのまま、月夜は沈黙する。
囀は、表情を変えて、月夜の肩に触れた。
「……どうしたの? なんか、様子が変だけど……」
月夜は自分でもそう思った。
「ごめんね」月夜は言った。「自分でも、何を言いたいのか、分からない」
囀は月夜を見つめ、目を細めて上品に笑う。
「うん、いいよ。そんなの、よくあることだし」
「そうかな」
「うん、そうそう。僕なんて、しょっちゅうそんな感じだよ」
室内と外気の温度差で、廊下の窓硝子は濡れている。二人の吐息に含まれる体温が、空気中の水蒸気を水滴に変化させる。
「本当は、囀に、あんなことは言いたくなかった」月夜は説明した。「私が指図をするようなことじゃなかった。でも……。なぜか、そうしようと、思ってしまった。だから、それを謝りたいんだと思う」
囀は話さない。
月夜と一緒に、窓の外に目を向けていた。
「私は、いつも、自分の衝動に突き動かされて、行動してしまう」
囀は少し笑った。
「月夜が?」
「そう、思わない?」
「うーん、どうかな……。そう言われてみれば、そんな感じもするけど、月夜に対する印象は、少し違う気がするよ」
「じゃあ、どんな感じ?」
囀は暫くの間黙る。
それから、愛らしい口もとを動かして言った。
「真摯、かな」
月夜は首を傾げる。
「真摯?」
「うん、そう」
「どういうところが、真摯?」
「僕の意見を聞きたがるのも、珍しいね」
「そう?」
「いや、ほかの人からは、あまり求められたことがない、と思ってね」
「私は、もう少し、周りの人を頼った方がいい、と言われたことがある」月夜は話す。「だから、囀に、訊いてみようかな、と思った」
囀は終始笑顔だ。
「月夜は、自分にも、他人にも、真摯だよ」囀は説明した。「どちらかに傾いているわけじゃない。自分の衝動に突き動かされて、行動してしまうって、さっき言っていたけど、その目的は、自分の願望を叶えるためだけじゃないでしょう? 他人のことを思って、そうしたい、と感じるんだから、自分がよければいい、という感情ではないと思うよ」
「でも、そうやって、他人を助けた結果、自分は、気持ちの良い思いをするわけだから、結局は、自分のことばかり、考えていることになるんじゃないのかな?」
「今日は雄弁だね、月夜」
それは月夜も感じていることだった。自分は、今、囀とコミュニケーションをとることを望んでいる、と思う。
「私は、今日は、雄弁みたい」
特に間違えた指摘だとは思えなかったから、月夜は肯定した。
「そういうところが、真摯だって思うんだよ」
月夜は首を傾げる。
「あまり、自分のことを意識しすぎない方がいいよ」囀は話した。「不安になるだけだから……。……僕も、月夜に出会って、少し変わったんだ。自然と、君のことを考えるようになった。月夜にどう思われたいか、ということばかり考えていたけど、そんなことは、どうでもいいって、思えるようになったんだよ。もっと、月夜と一緒にいる時間を、大切にしようと思ったんだ。うーん、ちょっと、上手く説明できている気がしないけど……。とにかく、不安は少ない方がいい。僕が言えるのは、それだけかな」
言葉の一つ一つの意味を考え、次にそれらが合わさって作られる文の意味を考えて、月夜は囀が言ったことを適切に理解しようとする。
なんとなく、分かったような気がした。
だから、彼女は、頷いた。
「大丈夫?」
囀が尋ねる。
大丈夫だとは思えなかったから、月夜は首を振った。
「まあ、いいよ。もう、終わったことだしさ」囀は話す。「月夜が、まだ、考え続けると言うのなら、僕は止めないよ」
「うん……」
予鈴が鳴り、二人は教室に戻った。次の授業は現代文だから、部屋を移動する必要はなかった。
授業を受けながらも、月夜は、先ほど囀が言ったことを、何度も頭の中で繰り返していた。話の意味は分かったが、彼女がそう説明するに至った経緯を考え出すと、不可解な点がいくつも見つかった。だから、今度はそれを一つずつ検証していく。
でも……。
自分と、一緒にいる時間を、大切にする?
その言葉が妙に引っかかった。
月夜は、いつも、周りの存在と、そうしてこなかった気がする。
それが、少しいけない気がした。
その言葉が印象に残ったのは、それが自分に足りていないからだ。
囀の席を見る。
彼女は、今は顔を上げて、教師の板書をノートに写している。真剣な眼差しではなかったが、集中して内容を理解しようとしているように見えた。
自分は、囀という一人の人間を、しっかり見ようとしていただろうか?
彼女を、何か一つの概念のように捉えていたのではないか?
そう……。
だから、モラルに反した彼女を、非難したのだ。
でも……。
本当は、そうするべきではなかったのではないか?
概念のように抽象化することで、囀が抱える悲しみを、考慮の枠内から自然に排除していた。
それが、いけなかった。
それが、間違えていた。
囀を囀として、自分と対等な存在だと認識することを、どこかで怠っていたのではないか?
たぶん、怖かったのだ。
彼女を自分と同じように扱うのが、怖かった。
では、その恐怖は何に起因するのか?
答えは一つしかない。
それは、自分を信じていなかったことだ。
それしかない。
だから、自分を反映する鏡のような囀を、直視することができなかった。
なんて根本的なミスだろう……。
その時点で、すべてがずれていたのだ。
すべての授業が終わり、放課後になった。月夜は、また今日も図書室に向かった。
暫くの間、彼女は図書室の入り口付近にいた。そこに立っているだけでは怪しまれるから、傍に展覧された本を手に取って読んだ。背後にはカウンターがあり、そこに返却ボックスが置かれている。
囀がここに立っている状況を想像した。
一時的に彼女の視点まで自己を昇華させ、辺りを見渡す。
本を予約するには、司書に頼んで、シートにクラスと名前を記入しなくてはならない。そこにそれらの情報を記すことで、初めて予約が成立する。
今回の事件で被害者として扱われたのは、一人の女子生徒だが、彼女もその手続きを済ませたはずだ。つまり、シートを確認すれば、そこに彼女の名前を見つけることができる。そして、本を予約するということは、彼女は図書室の常連である可能性が高い。図書室を普段から利用しない者は、本を予約しようという発想に至らない。予約した場合、本が返却され次第、図書室までその本を取りに行くことになるが、常連なら、図書室に向かうのが毎日の行動の中で習慣化されているから、それを面倒だとは感じない。しかし、常連ではない場合、本がなかったら、普通それで諦める。わざわざ借りに来て、さらに返しに来るようなことをしたくないからだ。
では、囀はどうだっただろう?
月夜が知っている限りでは、囀も定期的に図書室に通っていた。常連というレッテルが、どの程度の頻度を重ねた者に貼られるのか分からないが、とにかく、本を読みたいという動機があって、囀が定期的にここへ顔を出していたのは確かだ。
例の女子生徒と、囀が、互いに知り合いだった場合、どうなるだろう?
いや、知り合いというのは、少々関係が強すぎる。顔を知っている、くらいで良いはずだ。囀が転校してきてから、まだ数週間しか経っていないが、人の顔は、少なければ一回、多くても三回も目にすれば、確実に覚えられる。
月夜は、囀がとったであろう行動を、より鮮明に頭に思い描く。
本は最大で二週間借りられる。囀は、本を読む速度が、速い方か、遅い方か、月夜には分からない。読んでいる本がころころ変わっていた気もするが、それは、一冊を読み終えて次の本に移ったのではなく、何冊もの本を並行していた読んでいたのかもしれない。もちろん、どちらともいえないが、これはあまり重要ではない。
月夜は後ろを振り返り、司書に頼んで、本を予約したいと伝えた。今見ていた展覧場所に、ブックスタンドだけ立っている箇所があったから、そこにある本を借りたいと伝えた。司書は笑顔で対応し、月夜に予約した者の情報を記すシートを手渡した。
そこには、紐で括られた紙が何枚も重なっている。
過去の分まで纏められているようだ。
司書は手もとのパソコンに目を移し、彼女が書き終わるまで事務作業をしている。
月夜は、ページを捲って、過去に遡った。
可能性は、高いとも低いともいえないが、彼女が考えていることが成り立っていた場合、事実は自然と分かるようになる。
二回ページを捲ったところで、それを見つけた。
囀の名前だった。
さらに、もう一枚捲る。
もう一つ、囀の名前があった。
一つ目と二つ目の囀の名前が記された状況を分析する。彼女の名前の後ろには、どちらの場合にも、連続して同一人物の名前が記されていた。学年も一年生になっている。
なるほど、と月夜は思った。
彼女の仮説は立証された。
月夜はシートを司書に渡して、その場を去った。
部屋を奥へと進み、個人用のブースに着く。
リュックから勉強道具を取り出し、すぐに数学の問題を解き始めた。
もう、これ以上、確認する必要はなかった。
今分かったことから、事実がどのようなものだったか大体分かったが、それ以上真偽を突き詰めても意味はない。
ただ、自分と、囀が過ごす時間は、少しだけ華やかなものになるだろう、と思えた。
背後に気配を感じて、月夜は振り返る。
囀が立っていた。
「どうしたの?」月夜は質問する。
「僕も、勉強するよ」そう言って、囀は笑いかける。「夜になったら、教室に行こう」
月夜は頷いた。
囀は月夜の隣を通り過ぎ、向こう側の席に周ろうとする。
月夜は彼女を呼び止めた。
訊く必要はなかったが、訊いても良いかと思った。
「ねえ、囀」
囀は足を止めて、月夜を振り返る。
「何?」
「囀は、いつも、本をどこに仕舞っているの?」
「本? 本って?」
「自分で買った本でも、図書室で借りた本でも」
「仕舞っているって、どういうこと?」囀は笑う。「家だったら、当然、書棚の中だけど」
「借りた本は?」
「えっと……、ここで借りた本は、まず、ロッカーに仕舞うかな」囀は言った。「鞄は大抵いっぱいだから、帰りに教科書と交換するね」
月夜は頷いた。
「分かった。ありがとう」
「それでおしまい?」
「うん、そう」
「妙なことを訊くね」
「そう?」
「うん、まあ……」囀は言った。「僕は、何も訊かれなかったことにしよう」
そう言い残して、囀は月夜の対面に座る。
ペンを持ち直して、月夜は計算を始めた。
囀にも、自分の言いたいことは伝わっただろう、と思った。
*
夜になった。
月夜はすでに教室に移動して、眠っていた。夜の教室で眠るのは初めてだった。今まで何度もこの時間帯まで教室に残ったが、眠ろうと思ったことはなかった。
疲れているわけでもないのに、なんとなく、眠りたいと思って、机の上に両腕を載せて、その中に顔を埋めた。すると、たちまち意識がぼんやりとして、いつの間にか眠ってしまった。
目を覚ます。
顔を上げると、目の前に巨大な黒板があった。
時計は午後十一時を示している。
教室前方の扉が開いて、囀が入ってきた。
「やあ」囀は言った。「もしかして、寝ていたの?」
「どうして分かるの?」月夜は尋ねる。
「額が、赤くなっているから」
月夜は自分の額に触れる。たしかに、少し熱を帯びていた。感覚もいつもと違う。
囀は窓の傍に近づいて、それを勢い良く開いた。
冷たい外気が流れ込んでくる。
「今日は月が綺麗だよ」囀は言った。「あ、今の、告白のつもりなんだけど、分かる?」
立ち上がって、月夜は囀の傍に行く。空を見上げると、左側が欠けた半月が浮かんでいた。
「源氏物語は、もう読んだ?」
外を向いたまま、月夜は囀に質問する。
「ああ、あれね、まだ、読んでいない」囀は答える。「やっぱり、読むなら最初から読まないと、感動が薄れる気がしてさ」
「最終巻だけ読むのも、良いと思うよ」
「でも、それだと、物足りない」
「そう?」
「うん……。クライマックスだけ体験しても、そこに至るまでの過程がないと、駄目だね」
囀は上着のポケットからルービックキューブを取り出した。
彼はそれを軽く投げ上げる。
「これ、知っている?」
「ルービックキューブ?」
「うん、そうそう。面白いよね、たまには」
「たまに、面白いの?」
「いや、たまにやると、面白いんだ」
「やってみて」
「僕が?」囀は得意気な顔をする。「よし、いいだろう」
縦横に三分割された正方形の板を、囀は手際よく回転させる。しかし、手際が良いだけで、全然色は揃わなかった。どうやら、初心者らしい。色が揃わなくて、やり方も分からないのに面白く感じるのは、どういうことだろう、と月夜は不思議に思う。単純に、機構が面白いという意味かもしれない。これを作った人は、いったい何から発想を得たのだろうか。
囀からそれを受け取り、月夜も少し挑戦してみる。開始から五分程度で、彼女は青い色を一面に揃えることができた。
「へえ、凄いじゃん」囀は感想を述べる。
完全にまぐれなので、月夜は凄いとは思わなかった。
青を維持したままほかの色を揃えることはできないので、一度崩して、すべての色を揃える道程を考える。しかし、これはどうやら無理そうだった。論理的に一つずつ考えていけば、必ず揃えることができるはずだが、順序の候補が多すぎて、すべてを試す気にはなれなかった。やり方が明らかでも、それをやりたいと思わなければ、達成はできない。
「それが、どうかしたの?」
一通り遊び終えてから、月夜は囀に質問した。
「これ?」囀はルービックキューブを投げる。「いや、どうもしないけど……」
「たしかに、面白かった」
「でしょう?」
「細胞分裂みたいで、面白い」
「細胞分裂?」
囀は、今度はハーモニカを取り出して、それを吹き始める。
しかし、こちらも初心者のようで、メロディーになっていなかった。
途中から明らかな不協和音になったので、月夜は囀にやめるように諭した。
「え、何でよ」囀は不満そうな顔をする。
「ちょっと、耳に悪い、と思ったから」
「練習なんだから、できなくて当然でしょう?」囀は笑った。「それとも、月夜、できるの?」
ハーモニカを受け取って、月夜はそれを軽く吹いてみる。しかし、できるわけがなかった。
「できない」月夜は報告する。
「そうそう。だから、練習するんだよ」
「そうだけど……。……うん、分かった。じゃあ、どうぞ」
「嘘。煩いんだよね。やめます」
それ以上、囀のポケットからは何も出てこなかった。
「ねえ、月夜」沈黙していた囀が、月夜に話しかけた。「僕ね、もうそろそろ、行かなくちゃいけないんだ」
月夜は彼を見る。
「どこへ?」
「ここではない、どこかに」
「どうして?」
「存在しないからだよ」
月夜は答えない。
「存在しないから、存在しない者が存在する所に、行かなくちゃいけないんだ」
「存在しないのに、存在するとは、どういう意味?」
「そのままの意味だよ。理解はできるでしょう?」
月夜は考え、そして頷く。
「だから、月夜と一緒にいるのも、あと少し」
「私が、君と一緒に行きたいって言ったら?」
「そんなこと、君は言わないと思うよ」
「もし、そう言ったら、という話」
「拒否はしない」囀は言った。「でも、月夜のためにはならないとは伝える。……もう、伝えちゃったけどね」
月夜には、囀に同行する意思はなかった。それが最善だと判断したからだ。
「まあ、とにかく、お礼は言っておくよ。楽しかった。どうもありがとう」
「うん……」
「どうしたの? 寂しいの?」
「少し」
「元気出してよ。そんなに重い話じゃないよ」
「でも……」
「でも?」
「好きなものを失うのは、辛い」
囀は月夜の肩に触れる。
「いつか、また会えるよ」
「そう?」
「うん、きっと」
教室で二時間くらい過ごし、二人で裏門から外に出た。駅がある方に向かって歩く。
踏み切りの前を通過した。
真っ直ぐ進み、階段を上る。
その間、二人とも何も話さなかった。
改札を抜けて、ホームに立ち、電車が来るのを待つ。
空いている電車に乗り込み、二人並んで席に着いた。
「なんか、あっという間だったね」囀が言った。
月夜は頷く。
「会ったときのこと、覚えている?」
月夜はもう一度頷く。
「あれって、本当に運命だったんじゃないかって、僕は思っているんだ」囀は話した。「こんなに数ある電車の座席で、たまたま月夜がいる位置に乗車するなんて、そうとしか思えない」
「乗る、または降りるときに使う階段の位置と、人の行動を考慮に入れれば、ある程度は、絞り込むことができる」
「じゃあ、月夜が狙ったのかな?」
「いや、違う」
「そういうのを、運命っていうんだよ」
「いわない気がするけど……」
「いうんだって」囀は楽しそうだ。
月夜は小さく頷いた。
「……分かった」
囀の最寄り駅に到着する。
彼は、何も言わずに、月夜に手を振って、電車を降りていった。
扉が閉まる。
月夜は後ろを振り返った。
彼の姿は、すでにそこになかった。
明日になれば、もう、囀はいない。
彼は学校に来ない。
寂しかったが、それで良いと思った。
家に着く頃には、午前二時近くになっていた。玄関の鍵を開けて中に入ると、フィルがそこに座って待っていた。
「どうしたの?」後ろ手に玄関のドアを閉めて、月夜は尋ねた。
「終わったのか?」フィルは訊き返す。
月夜は小さく頷いた。
リビングにリュックを置き、そのまますぐに風呂に入った。今日はフィルも一緒だった。彼の身体を先に洗い、湯船の中にそっと入れる。水に浮かぶ彼は、見ていていつも愉快だ。可愛いというよりは、可笑しいといった方が近い。
自分も一通り洗い終えて、月夜もお湯に浸かった。
フィルを抱きかかえる。
「思った以上に元気そうだな、月夜」フィルが話す。
「そう?」
「ああ」
「思った以上にって、何を思ったの?」
「事態が起きて、それにどれくらい影響を受けたか、と想像した、ということだ」
「分かっている」
「じゃあ、訊くなよ」フィルは笑った。「分かっていることは、訊いてはいけない」
「フィルと、話したかっただけだよ」
「ほかにいくらでも話題はある」
「じゃあ、フィルの好きな色は?」
「そんなこと、訊いてどうなるんだ?」
「訊きたかっただけ」
「俺が好きなのは空色だ。ちなみに、空色と、水色の違いは、分かるか?」
「分からない」
「空色は、何でもありなんだ」彼は言った。「お前みたいに、真っ黒でも、空色は空色なのさ」
その日の朝、例の図書委員の女子生徒が、登校するなり、事件が解決したことを告げた。いや、解決という言い方はおかしいかもしれない。彼女の話によると、犯人が捕まったわけではないが、盗まれた本が、すべて返却ボックスに戻っているのが見つかった、とのことだった。無断で持ち出されていたのは、小説と、図鑑だが、どちらも同じタイミングで返されていたのを見ると、犯人は同一人物だったらしい、ということを、彼女は今さらながら指摘した。複数犯ではないか、という意見も、図書委員の中では出ていたようだ。
忘れ去られる前に、事件が解決するのは、学校では比較的珍しいことだ。だから、彼女の報告を聞いたクラスメートは、何ともいえない顔をしていた。刺激的な出来事が起きたのに、それが解決してしまったとなれば、もう何も面白いことはない。もちろん、皆、本が返ってきたこと自体は、喜ばしいと考えているだろう。けれど、陳腐な日常を彩るコンテンツが、一瞬の内に姿を消してしまった。これには落胆している生徒が多かった。
そして、彼らがどれだけ喚いたとしても、日常はいつも通りやって来る。担任の教師が教室に入ってきて、ホームルームが始まった。今日も授業が始まる。
授業中、月夜は、ぼうっと窓の外を眺めていた。
教師の話は耳に入っていたが、脳できちんと処理されている割合は、いつもの六十パーセント程度にすぎなかった。残りの四十パーセントは、何の処理も成されることなく、音として反対側の耳から出ていく(そんなことは、物理的にありえないが)。
今日は雪が降っていた。ぱらぱらとした粉雪で、地面に積もったのを踏めば、良い感触を味わえそうだ。
そろそろ、試験の準備をしなくてはならない、と月夜は考える。
とはいっても、彼女は毎日予習と復習を行っているから、試験のための勉強は必要なかった。普段と同じように勉強して、前日に少しだけ体調に気を遣えば良い。もっとも、どれほど気を遣っても、体調を悪くすることはある。だから、完全に体調を管理することはできない。しかし、百パーセント体調を崩さない方法も、ないとはいえない。自ら命を断てば、もう二度と体調を崩すことはない。
右斜め前方に目を向ける。
囀は、授業中だというのに、机に突っ伏して眠っていた。
教師は何も言わない。
その背中が、妙に寂しそうに見えた。
今すぐ立ち上がって、後ろから抱き締めたくなった。
でも、今は授業中だから、それはできない。
では、授業が終わったら、それはできるのか?
月夜には、その自信はなかった。
手を繋ぐことはできるのに、どうして、抱き締めることはできないのか?
どちらも、自分と相手の接触という、酷く根本的なコミュニケーションにすぎないのに……。
数学の授業中、月夜はシャープペンシルを何度か回した。特に回したかったわけではない。ただ、そんなふうに指を動かしていないと、なんだか落ち着かなかった。
そして、そんなことをしても、全然落ち着かなかった。
昼休みになって、月夜は自分から囀の傍に行った。
後ろの席のクラスメートと話していた彼女は、顔を上げて月夜を見る。
「どうしたの? 何か用事?」囀は笑顔で尋ねた。
月夜は首を振る。
「用事はないけど、少し、話したい、と思って」
囀はクラスメートとの会話を中断し、月夜に付き合う姿勢を確立した。話し相手のクラスメートは、そんな囀の対応を、快く受け入れてくれた。人の優しさとは、本来こういうものだ、と月夜は思う。その点、自分は、あまり、彼女に優しくできていないかもしれない、とも思った。
「何?」
廊下に出て、窓の外を向いていた月夜に、囀が質問した。
月夜は彼女を見る。
「ごめん」月夜は謝った。「何か、傷つけてしまったかもしれない、と思って」
「何を?」囀は笑った。「えっと、どういう意味?」
「うーんと……」
月夜は必死に考える。けれど、何を伝えたいのか、自分でも分からなくなってしまった。いや、本当は具体的に伝えいたことがないのに、何かを伝えたいと、形だけを想定していたことを、今になって気づいたのだ。
そのまま、月夜は沈黙する。
囀は、表情を変えて、月夜の肩に触れた。
「……どうしたの? なんか、様子が変だけど……」
月夜は自分でもそう思った。
「ごめんね」月夜は言った。「自分でも、何を言いたいのか、分からない」
囀は月夜を見つめ、目を細めて上品に笑う。
「うん、いいよ。そんなの、よくあることだし」
「そうかな」
「うん、そうそう。僕なんて、しょっちゅうそんな感じだよ」
室内と外気の温度差で、廊下の窓硝子は濡れている。二人の吐息に含まれる体温が、空気中の水蒸気を水滴に変化させる。
「本当は、囀に、あんなことは言いたくなかった」月夜は説明した。「私が指図をするようなことじゃなかった。でも……。なぜか、そうしようと、思ってしまった。だから、それを謝りたいんだと思う」
囀は話さない。
月夜と一緒に、窓の外に目を向けていた。
「私は、いつも、自分の衝動に突き動かされて、行動してしまう」
囀は少し笑った。
「月夜が?」
「そう、思わない?」
「うーん、どうかな……。そう言われてみれば、そんな感じもするけど、月夜に対する印象は、少し違う気がするよ」
「じゃあ、どんな感じ?」
囀は暫くの間黙る。
それから、愛らしい口もとを動かして言った。
「真摯、かな」
月夜は首を傾げる。
「真摯?」
「うん、そう」
「どういうところが、真摯?」
「僕の意見を聞きたがるのも、珍しいね」
「そう?」
「いや、ほかの人からは、あまり求められたことがない、と思ってね」
「私は、もう少し、周りの人を頼った方がいい、と言われたことがある」月夜は話す。「だから、囀に、訊いてみようかな、と思った」
囀は終始笑顔だ。
「月夜は、自分にも、他人にも、真摯だよ」囀は説明した。「どちらかに傾いているわけじゃない。自分の衝動に突き動かされて、行動してしまうって、さっき言っていたけど、その目的は、自分の願望を叶えるためだけじゃないでしょう? 他人のことを思って、そうしたい、と感じるんだから、自分がよければいい、という感情ではないと思うよ」
「でも、そうやって、他人を助けた結果、自分は、気持ちの良い思いをするわけだから、結局は、自分のことばかり、考えていることになるんじゃないのかな?」
「今日は雄弁だね、月夜」
それは月夜も感じていることだった。自分は、今、囀とコミュニケーションをとることを望んでいる、と思う。
「私は、今日は、雄弁みたい」
特に間違えた指摘だとは思えなかったから、月夜は肯定した。
「そういうところが、真摯だって思うんだよ」
月夜は首を傾げる。
「あまり、自分のことを意識しすぎない方がいいよ」囀は話した。「不安になるだけだから……。……僕も、月夜に出会って、少し変わったんだ。自然と、君のことを考えるようになった。月夜にどう思われたいか、ということばかり考えていたけど、そんなことは、どうでもいいって、思えるようになったんだよ。もっと、月夜と一緒にいる時間を、大切にしようと思ったんだ。うーん、ちょっと、上手く説明できている気がしないけど……。とにかく、不安は少ない方がいい。僕が言えるのは、それだけかな」
言葉の一つ一つの意味を考え、次にそれらが合わさって作られる文の意味を考えて、月夜は囀が言ったことを適切に理解しようとする。
なんとなく、分かったような気がした。
だから、彼女は、頷いた。
「大丈夫?」
囀が尋ねる。
大丈夫だとは思えなかったから、月夜は首を振った。
「まあ、いいよ。もう、終わったことだしさ」囀は話す。「月夜が、まだ、考え続けると言うのなら、僕は止めないよ」
「うん……」
予鈴が鳴り、二人は教室に戻った。次の授業は現代文だから、部屋を移動する必要はなかった。
授業を受けながらも、月夜は、先ほど囀が言ったことを、何度も頭の中で繰り返していた。話の意味は分かったが、彼女がそう説明するに至った経緯を考え出すと、不可解な点がいくつも見つかった。だから、今度はそれを一つずつ検証していく。
でも……。
自分と、一緒にいる時間を、大切にする?
その言葉が妙に引っかかった。
月夜は、いつも、周りの存在と、そうしてこなかった気がする。
それが、少しいけない気がした。
その言葉が印象に残ったのは、それが自分に足りていないからだ。
囀の席を見る。
彼女は、今は顔を上げて、教師の板書をノートに写している。真剣な眼差しではなかったが、集中して内容を理解しようとしているように見えた。
自分は、囀という一人の人間を、しっかり見ようとしていただろうか?
彼女を、何か一つの概念のように捉えていたのではないか?
そう……。
だから、モラルに反した彼女を、非難したのだ。
でも……。
本当は、そうするべきではなかったのではないか?
概念のように抽象化することで、囀が抱える悲しみを、考慮の枠内から自然に排除していた。
それが、いけなかった。
それが、間違えていた。
囀を囀として、自分と対等な存在だと認識することを、どこかで怠っていたのではないか?
たぶん、怖かったのだ。
彼女を自分と同じように扱うのが、怖かった。
では、その恐怖は何に起因するのか?
答えは一つしかない。
それは、自分を信じていなかったことだ。
それしかない。
だから、自分を反映する鏡のような囀を、直視することができなかった。
なんて根本的なミスだろう……。
その時点で、すべてがずれていたのだ。
すべての授業が終わり、放課後になった。月夜は、また今日も図書室に向かった。
暫くの間、彼女は図書室の入り口付近にいた。そこに立っているだけでは怪しまれるから、傍に展覧された本を手に取って読んだ。背後にはカウンターがあり、そこに返却ボックスが置かれている。
囀がここに立っている状況を想像した。
一時的に彼女の視点まで自己を昇華させ、辺りを見渡す。
本を予約するには、司書に頼んで、シートにクラスと名前を記入しなくてはならない。そこにそれらの情報を記すことで、初めて予約が成立する。
今回の事件で被害者として扱われたのは、一人の女子生徒だが、彼女もその手続きを済ませたはずだ。つまり、シートを確認すれば、そこに彼女の名前を見つけることができる。そして、本を予約するということは、彼女は図書室の常連である可能性が高い。図書室を普段から利用しない者は、本を予約しようという発想に至らない。予約した場合、本が返却され次第、図書室までその本を取りに行くことになるが、常連なら、図書室に向かうのが毎日の行動の中で習慣化されているから、それを面倒だとは感じない。しかし、常連ではない場合、本がなかったら、普通それで諦める。わざわざ借りに来て、さらに返しに来るようなことをしたくないからだ。
では、囀はどうだっただろう?
月夜が知っている限りでは、囀も定期的に図書室に通っていた。常連というレッテルが、どの程度の頻度を重ねた者に貼られるのか分からないが、とにかく、本を読みたいという動機があって、囀が定期的にここへ顔を出していたのは確かだ。
例の女子生徒と、囀が、互いに知り合いだった場合、どうなるだろう?
いや、知り合いというのは、少々関係が強すぎる。顔を知っている、くらいで良いはずだ。囀が転校してきてから、まだ数週間しか経っていないが、人の顔は、少なければ一回、多くても三回も目にすれば、確実に覚えられる。
月夜は、囀がとったであろう行動を、より鮮明に頭に思い描く。
本は最大で二週間借りられる。囀は、本を読む速度が、速い方か、遅い方か、月夜には分からない。読んでいる本がころころ変わっていた気もするが、それは、一冊を読み終えて次の本に移ったのではなく、何冊もの本を並行していた読んでいたのかもしれない。もちろん、どちらともいえないが、これはあまり重要ではない。
月夜は後ろを振り返り、司書に頼んで、本を予約したいと伝えた。今見ていた展覧場所に、ブックスタンドだけ立っている箇所があったから、そこにある本を借りたいと伝えた。司書は笑顔で対応し、月夜に予約した者の情報を記すシートを手渡した。
そこには、紐で括られた紙が何枚も重なっている。
過去の分まで纏められているようだ。
司書は手もとのパソコンに目を移し、彼女が書き終わるまで事務作業をしている。
月夜は、ページを捲って、過去に遡った。
可能性は、高いとも低いともいえないが、彼女が考えていることが成り立っていた場合、事実は自然と分かるようになる。
二回ページを捲ったところで、それを見つけた。
囀の名前だった。
さらに、もう一枚捲る。
もう一つ、囀の名前があった。
一つ目と二つ目の囀の名前が記された状況を分析する。彼女の名前の後ろには、どちらの場合にも、連続して同一人物の名前が記されていた。学年も一年生になっている。
なるほど、と月夜は思った。
彼女の仮説は立証された。
月夜はシートを司書に渡して、その場を去った。
部屋を奥へと進み、個人用のブースに着く。
リュックから勉強道具を取り出し、すぐに数学の問題を解き始めた。
もう、これ以上、確認する必要はなかった。
今分かったことから、事実がどのようなものだったか大体分かったが、それ以上真偽を突き詰めても意味はない。
ただ、自分と、囀が過ごす時間は、少しだけ華やかなものになるだろう、と思えた。
背後に気配を感じて、月夜は振り返る。
囀が立っていた。
「どうしたの?」月夜は質問する。
「僕も、勉強するよ」そう言って、囀は笑いかける。「夜になったら、教室に行こう」
月夜は頷いた。
囀は月夜の隣を通り過ぎ、向こう側の席に周ろうとする。
月夜は彼女を呼び止めた。
訊く必要はなかったが、訊いても良いかと思った。
「ねえ、囀」
囀は足を止めて、月夜を振り返る。
「何?」
「囀は、いつも、本をどこに仕舞っているの?」
「本? 本って?」
「自分で買った本でも、図書室で借りた本でも」
「仕舞っているって、どういうこと?」囀は笑う。「家だったら、当然、書棚の中だけど」
「借りた本は?」
「えっと……、ここで借りた本は、まず、ロッカーに仕舞うかな」囀は言った。「鞄は大抵いっぱいだから、帰りに教科書と交換するね」
月夜は頷いた。
「分かった。ありがとう」
「それでおしまい?」
「うん、そう」
「妙なことを訊くね」
「そう?」
「うん、まあ……」囀は言った。「僕は、何も訊かれなかったことにしよう」
そう言い残して、囀は月夜の対面に座る。
ペンを持ち直して、月夜は計算を始めた。
囀にも、自分の言いたいことは伝わっただろう、と思った。
*
夜になった。
月夜はすでに教室に移動して、眠っていた。夜の教室で眠るのは初めてだった。今まで何度もこの時間帯まで教室に残ったが、眠ろうと思ったことはなかった。
疲れているわけでもないのに、なんとなく、眠りたいと思って、机の上に両腕を載せて、その中に顔を埋めた。すると、たちまち意識がぼんやりとして、いつの間にか眠ってしまった。
目を覚ます。
顔を上げると、目の前に巨大な黒板があった。
時計は午後十一時を示している。
教室前方の扉が開いて、囀が入ってきた。
「やあ」囀は言った。「もしかして、寝ていたの?」
「どうして分かるの?」月夜は尋ねる。
「額が、赤くなっているから」
月夜は自分の額に触れる。たしかに、少し熱を帯びていた。感覚もいつもと違う。
囀は窓の傍に近づいて、それを勢い良く開いた。
冷たい外気が流れ込んでくる。
「今日は月が綺麗だよ」囀は言った。「あ、今の、告白のつもりなんだけど、分かる?」
立ち上がって、月夜は囀の傍に行く。空を見上げると、左側が欠けた半月が浮かんでいた。
「源氏物語は、もう読んだ?」
外を向いたまま、月夜は囀に質問する。
「ああ、あれね、まだ、読んでいない」囀は答える。「やっぱり、読むなら最初から読まないと、感動が薄れる気がしてさ」
「最終巻だけ読むのも、良いと思うよ」
「でも、それだと、物足りない」
「そう?」
「うん……。クライマックスだけ体験しても、そこに至るまでの過程がないと、駄目だね」
囀は上着のポケットからルービックキューブを取り出した。
彼はそれを軽く投げ上げる。
「これ、知っている?」
「ルービックキューブ?」
「うん、そうそう。面白いよね、たまには」
「たまに、面白いの?」
「いや、たまにやると、面白いんだ」
「やってみて」
「僕が?」囀は得意気な顔をする。「よし、いいだろう」
縦横に三分割された正方形の板を、囀は手際よく回転させる。しかし、手際が良いだけで、全然色は揃わなかった。どうやら、初心者らしい。色が揃わなくて、やり方も分からないのに面白く感じるのは、どういうことだろう、と月夜は不思議に思う。単純に、機構が面白いという意味かもしれない。これを作った人は、いったい何から発想を得たのだろうか。
囀からそれを受け取り、月夜も少し挑戦してみる。開始から五分程度で、彼女は青い色を一面に揃えることができた。
「へえ、凄いじゃん」囀は感想を述べる。
完全にまぐれなので、月夜は凄いとは思わなかった。
青を維持したままほかの色を揃えることはできないので、一度崩して、すべての色を揃える道程を考える。しかし、これはどうやら無理そうだった。論理的に一つずつ考えていけば、必ず揃えることができるはずだが、順序の候補が多すぎて、すべてを試す気にはなれなかった。やり方が明らかでも、それをやりたいと思わなければ、達成はできない。
「それが、どうかしたの?」
一通り遊び終えてから、月夜は囀に質問した。
「これ?」囀はルービックキューブを投げる。「いや、どうもしないけど……」
「たしかに、面白かった」
「でしょう?」
「細胞分裂みたいで、面白い」
「細胞分裂?」
囀は、今度はハーモニカを取り出して、それを吹き始める。
しかし、こちらも初心者のようで、メロディーになっていなかった。
途中から明らかな不協和音になったので、月夜は囀にやめるように諭した。
「え、何でよ」囀は不満そうな顔をする。
「ちょっと、耳に悪い、と思ったから」
「練習なんだから、できなくて当然でしょう?」囀は笑った。「それとも、月夜、できるの?」
ハーモニカを受け取って、月夜はそれを軽く吹いてみる。しかし、できるわけがなかった。
「できない」月夜は報告する。
「そうそう。だから、練習するんだよ」
「そうだけど……。……うん、分かった。じゃあ、どうぞ」
「嘘。煩いんだよね。やめます」
それ以上、囀のポケットからは何も出てこなかった。
「ねえ、月夜」沈黙していた囀が、月夜に話しかけた。「僕ね、もうそろそろ、行かなくちゃいけないんだ」
月夜は彼を見る。
「どこへ?」
「ここではない、どこかに」
「どうして?」
「存在しないからだよ」
月夜は答えない。
「存在しないから、存在しない者が存在する所に、行かなくちゃいけないんだ」
「存在しないのに、存在するとは、どういう意味?」
「そのままの意味だよ。理解はできるでしょう?」
月夜は考え、そして頷く。
「だから、月夜と一緒にいるのも、あと少し」
「私が、君と一緒に行きたいって言ったら?」
「そんなこと、君は言わないと思うよ」
「もし、そう言ったら、という話」
「拒否はしない」囀は言った。「でも、月夜のためにはならないとは伝える。……もう、伝えちゃったけどね」
月夜には、囀に同行する意思はなかった。それが最善だと判断したからだ。
「まあ、とにかく、お礼は言っておくよ。楽しかった。どうもありがとう」
「うん……」
「どうしたの? 寂しいの?」
「少し」
「元気出してよ。そんなに重い話じゃないよ」
「でも……」
「でも?」
「好きなものを失うのは、辛い」
囀は月夜の肩に触れる。
「いつか、また会えるよ」
「そう?」
「うん、きっと」
教室で二時間くらい過ごし、二人で裏門から外に出た。駅がある方に向かって歩く。
踏み切りの前を通過した。
真っ直ぐ進み、階段を上る。
その間、二人とも何も話さなかった。
改札を抜けて、ホームに立ち、電車が来るのを待つ。
空いている電車に乗り込み、二人並んで席に着いた。
「なんか、あっという間だったね」囀が言った。
月夜は頷く。
「会ったときのこと、覚えている?」
月夜はもう一度頷く。
「あれって、本当に運命だったんじゃないかって、僕は思っているんだ」囀は話した。「こんなに数ある電車の座席で、たまたま月夜がいる位置に乗車するなんて、そうとしか思えない」
「乗る、または降りるときに使う階段の位置と、人の行動を考慮に入れれば、ある程度は、絞り込むことができる」
「じゃあ、月夜が狙ったのかな?」
「いや、違う」
「そういうのを、運命っていうんだよ」
「いわない気がするけど……」
「いうんだって」囀は楽しそうだ。
月夜は小さく頷いた。
「……分かった」
囀の最寄り駅に到着する。
彼は、何も言わずに、月夜に手を振って、電車を降りていった。
扉が閉まる。
月夜は後ろを振り返った。
彼の姿は、すでにそこになかった。
明日になれば、もう、囀はいない。
彼は学校に来ない。
寂しかったが、それで良いと思った。
家に着く頃には、午前二時近くになっていた。玄関の鍵を開けて中に入ると、フィルがそこに座って待っていた。
「どうしたの?」後ろ手に玄関のドアを閉めて、月夜は尋ねた。
「終わったのか?」フィルは訊き返す。
月夜は小さく頷いた。
リビングにリュックを置き、そのまますぐに風呂に入った。今日はフィルも一緒だった。彼の身体を先に洗い、湯船の中にそっと入れる。水に浮かぶ彼は、見ていていつも愉快だ。可愛いというよりは、可笑しいといった方が近い。
自分も一通り洗い終えて、月夜もお湯に浸かった。
フィルを抱きかかえる。
「思った以上に元気そうだな、月夜」フィルが話す。
「そう?」
「ああ」
「思った以上にって、何を思ったの?」
「事態が起きて、それにどれくらい影響を受けたか、と想像した、ということだ」
「分かっている」
「じゃあ、訊くなよ」フィルは笑った。「分かっていることは、訊いてはいけない」
「フィルと、話したかっただけだよ」
「ほかにいくらでも話題はある」
「じゃあ、フィルの好きな色は?」
「そんなこと、訊いてどうなるんだ?」
「訊きたかっただけ」
「俺が好きなのは空色だ。ちなみに、空色と、水色の違いは、分かるか?」
「分からない」
「空色は、何でもありなんだ」彼は言った。「お前みたいに、真っ黒でも、空色は空色なのさ」
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説
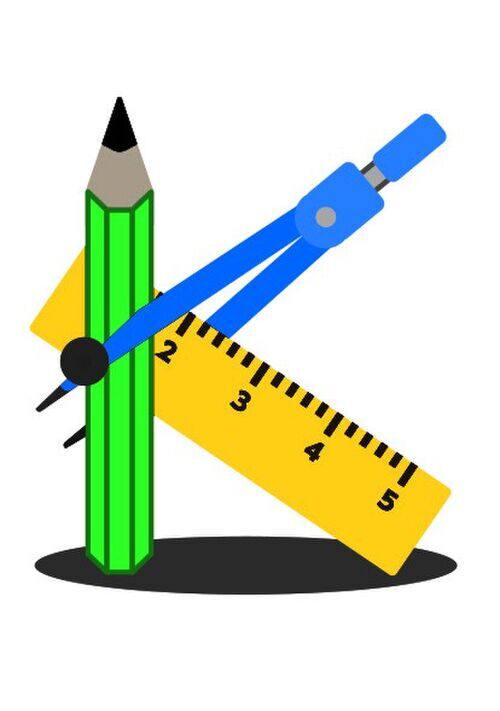
皿かナイフか
羽上帆樽
ライト文芸
深夜の喫茶店で、少女は一人の少年と出会った。そして事件は起こる。皿の粉砕。音を奏でるピアノは、どのようにして使われるのが適切か? 自分が存在することを証明するためには、どうしたって他者の存在が必要になる(自分が他者になることができれば、この手続きは必要ない)。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。



『 ゆりかご 』 ◉諸事情で非公開予定ですが読んでくださる方がいらっしゃるのでもう少しこのままにしておきます。
設樂理沙
ライト文芸
皆さま、ご訪問いただきありがとうございます。
最初2/10に非公開の予告文を書いていたのですが読んで
くださる方が増えましたので2/20頃に変更しました。
古い作品ですが、有難いことです。😇
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
" 揺り篭 " 不倫の後で 2016.02.26 連載開始
の加筆修正有版になります。
2022.7.30 再掲載
・・・・・・・・・・・
夫の不倫で、信頼もプライドも根こそぎ奪われてしまった・・
その後で私に残されたものは・・。
・・・・・・・・・・
💛イラストはAI生成画像自作

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















