3 / 5
第3部 空が逃げる時
しおりを挟む
「どうして、生きているんだと思う?」とその人が言った。彼女はもう咥え煙草はやめていた。その代わりに、購買で買ってきたオレンジジュースを飲んでいる。
「どうして、というのは、どういう意味?」僕は尋ね返した。
「別に」彼女は前を向いたまま話す。「どんな回答も、想定していないけど」
「理由なんてないと思う」僕は答えた。「自分の意志で生まれてきたわけじゃない。気づいたら、生まれてしまっていた。だから理由はない」
僕がそう答えると、その人はペットボトルを咥えたまま、こちらを見た。もう空は大分陰っていて、でも、その陰るというのは、時間の経過で太陽の高度が下がってきたことによるものではなく、もっと本質的に陰湿で、言うなれば、そう、彼女がその気候を誘き寄せたように僕には思えた。つまり、その気候さえ彼女の一部だということだ。
「私も、そう思う」ペットボトルを口から離して、その人は言った。「そっか」
「何が、そっか?」
「君も、私と同じなんだな、と」
「何が?」
「色々」
そう言って、彼女はまた正面を向く。ここにカメラマンがいて、僕たちのやり取りの一部始終を撮影していたら、その映像には特筆すべき変化はないだろう。サインカーブとでも言った感じか。ある一定の傾向が、一定の周期で訪れるようなもの。彼女の顔が、前を向いたり僕の方を向いたり、を繰り返す映像。愉快といえば愉快ではないか。
「君は、秀才、あるいは、天才だから、僕とは違うと思うよ」と、僕は言ってみた。
彼女はまたこちらを向くと、僕を少々睨みつける。でも、それは自然と滲み出た表情ではなくて、明らかにわざと作られた表情だった。
「そういうこと言う人、嫌い」
「あそう」僕は頷く。「僕も、いい表現ではないと思うけど」
「でも、たぶん、私って、天才だから」彼女は言った。「何でも、すぐに分かってしまうんだ」
「大変だね」
「何が?」
「色々」
空に色はもうない。たとえ虹がかかっても、それはモノクロで、大枠としては二色しかないと見なされるに違いない。雲は分厚くて、けれど密度は小さそうだった。中身が空洞なのかもしれない。雷でも降ってきそうだった。飛び降りて死ぬよりは、雷に打たれて死んだ方が、鮮やかというか、エクセレントだろうか。
「天才って、天賦の才能という意味で、つまりは、持って生まれてしまった才能のことだと思う」その人が話す。僕には歌声に聞こえた。つまり、そこには学術的論理的化学的経済的具体的意味はない可能性が高い。「私、何でも分かっちゃうんだ。教科書を開いた瞬間に、書かれていることがすべて分かってしまう。だから、もう開かない。学校に来ないのも同じ」
「そんな話は、聞いたことがあるよ」僕は言った。「どこから出てきた噂かは、分からないけど」
「だから、死のうと思って」
「それで、どうして死が出てくるの?」
僕の質問に、その人はすぐには答えない。頭を大きく上に向けて、一升瓶で酒を飲むようにオレンジジュースを喉に流し込んだ。お腹の中が大変なことになってしまうのではないかと、少し心配になる。
「ペットボトルの蓋を開けた瞬間に、オレンジジュースの味が分かるんじゃないの?」僕は尋ねる。
「そうだよ」彼女は答えた。「でも、これは、飲まないと駄目だから」
「意味が分からない」
「死ぬための準備なの」彼女は言った。「ここから飛び降りたときに、周囲に飛び散る水分の量が多い方が、芸術的かなと思って」
「芸術のために死ぬの?」
「違うよ」
「じゃあ、どうして死ぬの?」
「さっき言わなかったっけ?」
「死ぬことだけは、まだ試していないから、ということ?」
「そんな感じ」その人は頷く。「分かっているじゃないか」
僕は溜め息を吐いた。この人と話していると、妙に疲れてくる、と感じていた。なるほど、だから彼女の周囲には誰もいないのだな、とも考えた。
たぶん、彼女は、こちらが考えていることを、こちらがそれを口にする前に分かっている。それでも、まだ分かっていないという体を装って会話をしてくれているのだ。普通に考えれば、それは優しさの類だろう。けれど、僕にはその、体、が妙に引っかかった。彼女が自分と僕が同じだと言ったのは、こういう意味かもしれない。要するに、僕には彼女の、体、を分かることができるのだ。
不意に、圧力。
考え事をしていたから、気づかなかった。
それとも、本当に彼女が世界そのものだからか。
すべてが彼女の思い通りになるからか。
左側から抱き締められる。
「君も、一緒に飛ぶ?」
すぐ傍に、彼女の笑った顔があった。
「どうして、というのは、どういう意味?」僕は尋ね返した。
「別に」彼女は前を向いたまま話す。「どんな回答も、想定していないけど」
「理由なんてないと思う」僕は答えた。「自分の意志で生まれてきたわけじゃない。気づいたら、生まれてしまっていた。だから理由はない」
僕がそう答えると、その人はペットボトルを咥えたまま、こちらを見た。もう空は大分陰っていて、でも、その陰るというのは、時間の経過で太陽の高度が下がってきたことによるものではなく、もっと本質的に陰湿で、言うなれば、そう、彼女がその気候を誘き寄せたように僕には思えた。つまり、その気候さえ彼女の一部だということだ。
「私も、そう思う」ペットボトルを口から離して、その人は言った。「そっか」
「何が、そっか?」
「君も、私と同じなんだな、と」
「何が?」
「色々」
そう言って、彼女はまた正面を向く。ここにカメラマンがいて、僕たちのやり取りの一部始終を撮影していたら、その映像には特筆すべき変化はないだろう。サインカーブとでも言った感じか。ある一定の傾向が、一定の周期で訪れるようなもの。彼女の顔が、前を向いたり僕の方を向いたり、を繰り返す映像。愉快といえば愉快ではないか。
「君は、秀才、あるいは、天才だから、僕とは違うと思うよ」と、僕は言ってみた。
彼女はまたこちらを向くと、僕を少々睨みつける。でも、それは自然と滲み出た表情ではなくて、明らかにわざと作られた表情だった。
「そういうこと言う人、嫌い」
「あそう」僕は頷く。「僕も、いい表現ではないと思うけど」
「でも、たぶん、私って、天才だから」彼女は言った。「何でも、すぐに分かってしまうんだ」
「大変だね」
「何が?」
「色々」
空に色はもうない。たとえ虹がかかっても、それはモノクロで、大枠としては二色しかないと見なされるに違いない。雲は分厚くて、けれど密度は小さそうだった。中身が空洞なのかもしれない。雷でも降ってきそうだった。飛び降りて死ぬよりは、雷に打たれて死んだ方が、鮮やかというか、エクセレントだろうか。
「天才って、天賦の才能という意味で、つまりは、持って生まれてしまった才能のことだと思う」その人が話す。僕には歌声に聞こえた。つまり、そこには学術的論理的化学的経済的具体的意味はない可能性が高い。「私、何でも分かっちゃうんだ。教科書を開いた瞬間に、書かれていることがすべて分かってしまう。だから、もう開かない。学校に来ないのも同じ」
「そんな話は、聞いたことがあるよ」僕は言った。「どこから出てきた噂かは、分からないけど」
「だから、死のうと思って」
「それで、どうして死が出てくるの?」
僕の質問に、その人はすぐには答えない。頭を大きく上に向けて、一升瓶で酒を飲むようにオレンジジュースを喉に流し込んだ。お腹の中が大変なことになってしまうのではないかと、少し心配になる。
「ペットボトルの蓋を開けた瞬間に、オレンジジュースの味が分かるんじゃないの?」僕は尋ねる。
「そうだよ」彼女は答えた。「でも、これは、飲まないと駄目だから」
「意味が分からない」
「死ぬための準備なの」彼女は言った。「ここから飛び降りたときに、周囲に飛び散る水分の量が多い方が、芸術的かなと思って」
「芸術のために死ぬの?」
「違うよ」
「じゃあ、どうして死ぬの?」
「さっき言わなかったっけ?」
「死ぬことだけは、まだ試していないから、ということ?」
「そんな感じ」その人は頷く。「分かっているじゃないか」
僕は溜め息を吐いた。この人と話していると、妙に疲れてくる、と感じていた。なるほど、だから彼女の周囲には誰もいないのだな、とも考えた。
たぶん、彼女は、こちらが考えていることを、こちらがそれを口にする前に分かっている。それでも、まだ分かっていないという体を装って会話をしてくれているのだ。普通に考えれば、それは優しさの類だろう。けれど、僕にはその、体、が妙に引っかかった。彼女が自分と僕が同じだと言ったのは、こういう意味かもしれない。要するに、僕には彼女の、体、を分かることができるのだ。
不意に、圧力。
考え事をしていたから、気づかなかった。
それとも、本当に彼女が世界そのものだからか。
すべてが彼女の思い通りになるからか。
左側から抱き締められる。
「君も、一緒に飛ぶ?」
すぐ傍に、彼女の笑った顔があった。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

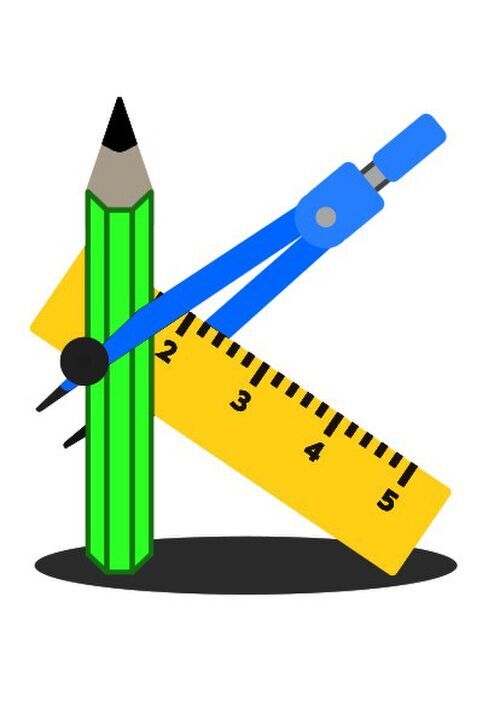
蜜柑製の死
羽上帆樽
現代文学
毎日500文字ずつ更新する詞です。その日の自分の状態が現れるだろうと予想します。上手くいく日もあれば、そうでない日もあるでしょう。どこから読んでも関係ありません。いつから知り合いになっても関係がないのと同じように。いつまで続くか未定です。続くまで続きます。


百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

零空(レイクウ) Empty Sky イノセント・スカイ
M921
SF
戦争はどこで起きても不思議ではない。
何が火種で起きるかわからない
一体何が正義で何が悪なのかそれさえもわからない。
傭兵…金で買われ戦場へ行き任務を遂行する
まるでロボットのように。
そこに私情はない。
命はチェスの駒と一緒…
金で作られた翼でこの空を舞い叩き落とすだけ
私たちは傭兵。そこに命はない……
あらすじ
ある日東京上空に国籍不明の戦闘機が出現
自衛隊も出撃するが手も足も出ず地上も占領されてしまう。
そこで日本政府より傭兵部隊であるフェニックス隊、リュコス隊へ国籍不明部隊を東京から追い出してほしいとの依頼が入る
一体どこの国なのか、目的はなんなのか。
そして、命とはなんなのか。
何を思い空を飛ぶ?金のためか?己の思想か?
愛するもののためか?
鋼の翼で不死鳥が空を舞う
「フェニックス隊!エンゲージ!!」
《ウィルコ!》
世界観は地球をもう一回り大きくして実際ある国と架空の国を織り交ぜている感じです。
パラレルワールドとして見てください。
※本作はフィクションです。実際にある団体、組織とは何も関係ありません。ご了承の方のみ閲覧ください。

とある高校の淫らで背徳的な日常
神谷 愛
恋愛
とある高校に在籍する少女の話。
クラスメイトに手を出し、教師に手を出し、あちこちで好き放題している彼女の日常。
後輩も先輩も、教師も彼女の前では一匹の雌に過ぎなかった。
ノクターンとかにもある
お気に入りをしてくれると喜ぶ。
感想を貰ったら踊り狂って喜ぶ。
してくれたら次の投稿が早くなるかも、しれない。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















