7 / 10
第7章 神々
しおりを挟む
「月夜、クッキーは持ったか?」
「クッキーって、何?」
クリスマスになった。イヴではない。正真正銘の当日だ。月夜の家には、サンタクロースはやって来なかった。当たり前だ。よく、父親がサンタクロースだから、サンタクロースは存在しない、といった主張を耳にするが、それは論理的に間違えている。父親がサンタクロースだったからといって、世界のどこにも、サンタクロースは存在しない、というわけではない。あなたの家では、サンタクロースの役を父親がやっていた、というだけであって、サンタクロースは、世界のどこかにはいるかもしれない。反対に、いないことを証明するのは、ほとんど不可能だといって良い。悪魔の証明、というやつだ。
「クッキーとは何か、だって?」歩きながら、フィルが言った。「小麦粉を使った、焼き菓子のことに決まっているじゃないか」
「今、手には持っていない」
「じゃあ、その、手提げ鞄の中に入っているんだな。分かった」
「うん、入っているよ」
「いちいち、面倒臭い手順を踏まないと、話が通じないようだ」
「どうして、話が通じないの?」
「まあ、主体が見ているものと、客体が見ているものでは、まったく違う、ということだろう」
「どう違うの?」
「つまり、視点が違う。見えるものと、見えないものが、それぞれある。鏡を通して自分を見ることはできても、その行為をしている自分を、背後から見ることはできないだろう?」
「できない」
「そういうことさ」
「どういうこと?」
月夜は、帽子を被ってこなかった。紗矢は、サンタクロースの帽子を被ってきてほしい、と言っていたが、そんなものは持っていないので、被ることはできない。それでは、別の帽子を被っていこうか、という議論をフィルとしたが、そんな必要はないと判断して、結局、何も被っていかないことになった。
便箋と、封筒は、紗矢に言われた通り持ってきた。筆記用具も持っている。けれど、今日はクリスマス当日だから、今からサンタクロースに手紙を書いても、もう意味がないだろう。月夜は、それを分かっていて、昨日は紗矢の所に行かなかった。どうしてそんな選択をしたかというと、これが特に理由はない。たまたま、事の成り行きで、そうなっただけだ。事の成り行きとはおそろしいものだ、と月夜はまるで他人事のように考える。事実、その通り、彼女にとっては他人事だ。まさか、紗矢も、サンタクロースに手紙を送ったら、本当にプレゼントが貰えるとは考えていないだろう。
ビンゴについても、そんなものは持っていないから、今日はやるつもりはなかった。近所の店を探しても、見つからなかった。
時刻は午後六時だ。もう空は暗い。完全に夜といって良い。パーティーをするのだから、やはり、夜だろう、というフィルの意見を採用して、月夜はこの時間帯に紗矢の所に行くことにした。
「それじゃあ、今日のイベントは、サンタクロース宛に、手紙を書く、ということだけか?」草原に立ち入ったとき、フィルが尋ねた。
「うん」
「なんとも、寂しいクリスマスだな」
「そうかな?」
「しかも、届かない手紙を、二人で書くのか」
「そうなるね」
「なかなかシュールだな」
「そうかな……」
「月夜は、そういう意味のないことが好きなのか?」
「特に、好きだと感じるものは、ない」
「何も?」
「好きと、嫌いの、境界がはっきりしていないから、何も言えない」
「相変わらずだな」
「フィルは、意味のないことが好き?」
「意味がある方が、好きだな」
「自分みたいに?」
「それ、どういう意味だ?」
「ごめんなさい、適当に言いました」
「どうして、突然敬語になる?」
「敬いたかったから」
石造りの階段を上る。山の中が暗いのは分かっていたから、月夜は懐中電灯を持ってきていた。それで足もとを照らしながら、二人は先へと進む。フィルは、今は月夜の手提げ鞄の中だった。
山道は若干湿っていた。朝の霧がまだ残っているのかもしれない。草の香りと、土の香りが混ざって、自然をすぐ傍に感じた。自然とは何か、と訊かれても、たぶん誰も答えられないだろう。もちろん、答えることに価値があるとはいえない。答えない、というのが、最も懸命な対応かもしれない。
静かだった。
今日は、鳥の鳴き声は聞こえない。
やがて、道が開けて、神社がある広場に到着した。
紗矢は、石段の上に座っていた。
「月夜」二人に気づいて、紗矢が声を出しながら立ち上がった。「ちょっと、月夜……」
「何?」
「もう……」
「どうしたの?」
「どうしたの、じゃないじゃん」紗矢は月夜の袖を引いて、自分の隣に座らせる。「もう、どうして、昨日の内に来てくれなかったの?」
「どうして、と訊かれても、答えられない」
「ずるい」
「何が?」
「まったく、酷いなあ……」
たしかに、酷いかもしれないな、と月夜は思った。その通り、彼女は酷いことをした。もう、サンタクロースは、自分の国に帰ってしまったに違いない。
「メリークリスマス」月夜は言った。
「もう、遅いよう」紗矢が口を尖らせる。「プレゼント、もう、もらえないよ……」
「ごめんね」
「それ、本気で謝っている?」笑いながら、紗矢は月夜の顔を覗き込む。「でも、まあ、いいよ。なんか、月夜って発想が飛躍しているよね」
「そう?」
「うん……。あと、危機感がない、という感じもする」
「どうして、危機感が必要なの?」
「だって、その方が安全じゃない?」
「そうかもしれないけど、危機感は、ない方が、いいと思うよ」
「まあね」
「便箋と、封筒を持ってきたけど、書く?」
「今から?」紗矢は笑った。「今から書いても、もう、誰にも届かないじゃん」
「来年の分のお願いを、今年の内にしておく」
「ああ、なるほど……」
「書く?」
「うーん、どうしようかなあ……」紗矢は自身の顎に人差し指を当てて、考える。「……うん、でも、せっかくだから、書こう」
「紗矢は、何が欲しいの?」
「プレゼント?」
「うん」
「内緒」
「内緒が、欲しいの?」
「違うよ」
持ってきたクッキーと、麦茶を口に含みながら、二人はサンタクロースに向けて手紙を書いた。もちろん、飲食をするのは月夜だけだ。この表現は、貴重といえば貴重だろう。普段飲食をしない彼女が、だけ、と限定を伴って、飲食をすると描写されている。なかなかお目にかかれる表現ではない。
月夜は、サンタクロースへの手紙に、時間を下さい、と書いた。ほかに何も思いつかなかったからだ。彼女には、基本的に、欲しいものがない。何も欲しくないわけではないが、特別これが欲しい、と感じたことはなかった。だから、普通なら手に入らない最も有益なものとして、時間を選んだ。理由はそれだけだ。大した理由ではない。
紗矢は、幸せが欲しい、と書いていた。彼女らしいといえば彼女らしい。何が彼女を彼女たらしめるのか、それは分からない。けれど、その文面を見たとき、月夜はなぜかそう感じた。紗矢が、死ぬ前に、幸せを掴めたのか、掴めなかったのか、月夜には分からない。この場合は、どちらでも良い、とは言い切れない。それは、自分が彼女の友達だからかもしれない、と月夜はふと思う。そんなことを思うのは、しかし本当に珍しかった。自分ではない誰かを、自分と深い関係があると感じるのは、月夜にはあまりないことだ。
二人は、書き終えた便箋を丁寧に畳んで、封筒の中に仕舞った。月夜は、紗矢が書いたものを預かることにした。ここに置いておくわけにはいかない、と紗矢が自分からそうするように頼んだからだ。月夜は、特に断る理由がなかったから、紗矢のお願いを受け入れた。
「ああ、クリスマスか……。今頃、皆、恋人同士で、何か楽しいことでもやっているんだろうな……」紗矢が呟く。
「何か、楽しいこと、とは?」
「一緒にソファに座りながら、映画を観たりとか、食事をしながら愛を語り合ったりとか、あとは、プレゼントの交換会を開いたりとか、じゃないの?」
「紗矢は、そういうことがしたいの?」
「うーん、どうかなあ……。したいような、しなくてもいいような……」
「俺とやるのは、嫌らしいからな」月夜の膝の上にいるフィルが、低い声で話す。
「別に、嫌じゃないけどさあ……。今ひとつ、ぱっとしない感じだよね」
「失礼だな」
月夜はフィルの頭を撫でる。彼は、今は大人しくしている。もっとも、彼は普段から大人しい。
「月夜は、こんな所にいていいの?」
「ん? こんな所って?」
「私なんかと、こんな場所で、貴重な時間を消費していていいのか、という質問だよ」
「そうしてほしいって、紗矢が言ったんだよ」
「あ、そうか……。……もしかして、無理させちゃったかな? ……ごめんね」
「どうして、謝るの?」
「なんか、悪いことしたかな、と思って」
「よく、分からないけど……」
「ほかに、用事とかなかった?」
「用事は、ない」月夜は話す。「紗矢と、一緒にいるのは、楽しいよ」
「本当に?」紗矢は表情を明るくする。
「うん」
「よかったあ……。なんか、嫌われちゃうかもしれないって、心配していたんだ、私……」
「どうして、私が、紗矢を嫌うの?」
「うん、なんとなく……」
「なんとなくで、誰かを嫌う人がいるの?」
「いるかもね、どこかには」
「月夜は、ほかのやつとは、感覚がずれているからな」フィルが言った。「本人は、自覚していないみたいだが」
「自覚?」月夜は首を傾げる。
「ほらな」
「ほらな?」
「なんだ? 何か気に障ったのか?」
「フィルって、月夜と一緒のときも、いつもこんな感じなの?」紗矢が尋ねる。
「うん、そうだよ」
「いや、違うね」フィルが断言する。「お前と一緒にいるときだけだ、俺が、こんな無愛想なのは」
「やっぱり……」紗矢が呟いた。
「そうなの?」月夜は首の角度を大きくする。
「ああ、そうだ」フィルは薄く笑い、軽くウインクした。「俺は、いい子だからな」
いい子とは、私のことかな、と月夜は思った。
「ねえ、紗矢」月夜は言った。「一つ訊いてもいい?」
「何?」
「どうして、私にフィルを拾わせたの?」
月夜がそう尋ねると、紗矢は少しだけ驚いたような顔をした。少しだけ驚いた、のではない。少しだけ、驚いたような顔をしたのだ。それほど重要なことではないが、紗矢は、あまり、声を上げて驚くようなタイプではない。
「……フィルが、そう言ったの?」
「そうだよ」
紗矢はフィルを見る。彼は顔を横に向けて、小さく欠伸をした。どうやら、二人の話に付き合う気はないらしい。
「そっか……」
紗矢は、何も否定しなかった。
夜の冷たい空気が流れる。木々が音を立てて揺れ、草原がある方から、吹き込むように風が入り込んできた。寒い。月夜は今日もコートを着ていない。紗矢に関しては、今も半袖のままだった。きっと、もう温度を感じないのだろう。それはそれで、とても良いかもしれない、と月夜は思う。フィルの暖かさを傍で感じられないのは、少しだけ寂しいが……。
「あのね、月夜」
「何?」
「私は、特別君を選ぼうと思ったわけじゃないんだ」
「うん」
「ただ、君のことが見えて、君も私たちが見えるみたいだったから、君を選んだ、というだけ」紗矢は話す。「あとは、君の風貌が気に入ったから、かな……。うん、理由なんて、その程度のものだよ。何か、特別な理由があったわけじゃない。少なくとも、私は、そう考えている」
「あの時間に、あの場所に、フィルを置いて、私を誘ったの?」
「そうだよ」
「どうして、紗矢が、直接、私の所に来なかったの?」
「私は、ここから出られないから」
「どうして?」
「気になるの?」
「気には、ならないけど、訊いておいた方がいいかな、と思った」
「フィルは、移動できる。けれど、私はできない。どうしてか分かる?」
「分からないよ。どうして?」
「フィルは、空間だからだよ」
「空間?」月夜は首を傾げる。
「そう、空間……」紗矢は言った。「空間は、自由に移動できる。そう、移動……。つまりは、物質の位置が変わる、ということだよね。私は、あまり、そういう学問に詳しくないから、よくは分からないけど……」
「それが、どうかしたの?」
「それが、彼が移動できる理由だよ」
「どういうこと?」
「どういうことだと思う?」
月夜は、一度黙って考える。
紗矢の説明は、少々おかしいところがある、と彼女は思った。まず、空間は、自由に移動できる、というのは、「空間」が主語なのではない。空間の中を、「私」あるいは「誰か」が、自由に移動できる、という意味だ。だから、普通、空間が、主体的に、移動できる、という捉え方はしない。しかし、紗矢はそれを混同している。いや、意図的にそうしている、と考えた方が良いかもしれない。これは、一種の言葉遊びだ。そんなふうに、言い包めようと思えば、どんなことでも、適当に言い包められるのだ。人間が持ち合わせる論理とは、そういうものだ。
「月夜は、フィルと一緒にいてくれる? それとも、もう一緒にいてくれない?」
「私は、いいよ。でも、紗矢は、それでいいの?」
紗矢は月夜を見る。
月夜も紗矢を見た。
数秒間、視線が交錯する。
「私は、それでいい」やがて、月夜から目を逸らして、紗矢は言った。「それでいいよ」
月夜は、前を向いたまま答える。
「分かった」
「何が?」
「紗矢の考えを、承認した、という意味」
「うん……。月夜なら、そう言うと思ったよ」
「予想していたの?」
「予想、というほどではないけど、なんとなく、そんな気がしていた」
「紗矢、笑わないの?」
「どういう意味?」
「嬉しくないの?」
「どういう意味?」
沈黙。
フィルは退屈そうだ。その通り、退屈なのだろう。人間の少女らが、何やら真剣そうなやり取りをしている、くらいに考えているに違いない。彼は、どんなことでも他人事だ。自分が関与していないと思っている。しかし、月夜は、彼のそんな態度が好きだった。自分もそんなふうに生きられたら良い、と素直に思う。思いは、常に素直だ、と考えたことがある。けれど、素直は、常に思いではない。どうして、そんなことを考えるのか? 考える必要がないのに、それでも考えてしまうのは、どうしてだろう?
紗矢は、身を乗り出して、月夜を軽く抱きしめた。
「何?」
月夜は尋ねる。
「ごめんね……」
「何が?」
「ううん、なんでもない」
「うん……」
「月夜、温かいね」
「そう?」
「うん。私なんかよりずっと」
「私は、よく、冷たい、と言われる」
「たぶん、私が体温を持たないから、今は月夜の方が温かいんだよ」
「なるほど」
「何が、なるほどなの?」
「特に、意味のない、相槌」
「月夜は、素直だね」
「そうかな」
「そうだよ。……私も、もっと素直になりたかった」
「誰に対して?」
「自分に対して」
「それは、難しいよ」
「難しかったら、できなくても、いいかな?」
「いい、と、思う」
「ありがとう」
「なぜ、感謝するの?」
「なぜだと思う?」
月夜には、分からなかった。
空から雪が降ってくる。雪を見てから、雪だ、と月夜は思った。季節外れではないが、予想外ではある。彼女は、あまりテレビを見ないから、天気予報は確認していない。空はたしかに曇っていた。暗いから、気づかなかった。これが、ホワイトクリスマス、というものらしい。
人は、なぜ、勉強するのだろう? 一度勉強したからといって、それですべてが身につくわけではない。必ず、失われる部分が存在する。決して完全にはならない。それなのに、何度も同じことを繰り返して、内容を記憶して、少しでも自分の能力が上がれば、と期待する。いずれ死んでしまうのに、どうしてそんなことをするのか、月夜は不思議に感じる。
彼女は、言うなれば、学校の成績のために勉強している。自分の能力を上げる、ということを、勉強の目的にしていない。それは、つまり、やらされている、ということでもある。学校に通って、与えられた課題をこなして、次に進む。それらはすべて計画されている。けれど、習得の精度には個人差があるから、すべての生徒が、計画された通りに目標を達成できる、というわけではない。人間は、生まれながらにして不平等なのだから、すべての生徒の勉強の量や質が同じでも、結局のところ差に変化は生じない。だから、能力のない生徒は、能力がある生徒以上に勉強しなくてはならなくなる。どうして、そんな不合理なことを求めるのか。能力がないのなら、もう、それで良いではないか。どうして、それ以上鍛錬しなくてはならないのか。しても、仕方がない。だって、いつか死んでしまうのだから……。
自分が発見した成果が、自分が死んだあとで、ほかの人に受け継がれる。それが楽しいから、学問を極めるのだ、と言う人もいる。けれど、いつまで、そんなことを続けるつもりだろう? 終わりがないのに、いったい何を目標にしているのか。それが、月夜には分からない。生命は、そういったサイクルに縛られている。それを断ち切ることはできない。断ち切ろうとすれば、たちまち環境というシステムに阻害される。人間にそのサイクルを断ち切らせないために、世界には、予め、安全装置が組み込まれているのだ。では、それは何のためだろう? そう考えても、結局何の答えも出ない。それは、目標や、目的を掲げるのが、人間に特有な行為だからかもしれない。では、人間が、目標や、目的を掲げるのは、どうしてだろう?
そう……。目標や、目的なんて、本当は存在しない。
人間が、存在すると錯覚しているだけだ。
それらがあれば、素晴らしいと感じるし、それらがなければ、価値はないと感じる。
だから、皆、将来の夢を掲げて、それを頼りに生きている。それがなければ、まともに生きることすらできない。生物として、ここまで脆弱な種はほかにない。人間は、弱い生き物だ。生物という集合の中で、最も生きる能力を持っていないのではないか。
横を向いて、月夜は紗矢を見る。
紗矢は、死んだのに、まだ、こうして、この世界に留まっている。それは、彼女が人間だったからかもしれない。やはり、目標や、目的がないと、死後の世界でも生きていけないのだ。だから、ここに座って、自分と会話をする、そのために生きている、と思い込んでいる。あるいは、ほかにも、目標や目的が存在するのかもしれない。
ほかの、目標や、目的。
では、それらがすべて達成されれば、紗矢は消えてしまうのか?
消えるために、目標や、目的を掲げている?
なんて、馬鹿げているのだろう……。
そして、なんて、寂しい存在なのだろう……。
「月夜、何、考えているの?」
紗矢が訊いた。
「少し、わけの分からないこと」
「へえ、どんな?」紗矢はにこにこ笑って話す。「聞かせてよ。そういう話、大好きだよ」
「紗矢は、何のために、ここにいるの?」
「私?」紗矢は少し不思議そうな顔をした。「うーん、なんとなく、かな……。……月夜は、どうして、生きているの?」
「どうしてだろう……」
「それを、考えていたの?」
「うん、まあ、そう」
「そういうときって、あるよね」
「そう?」
「うん……。私も、よく考えたよ。死んでしまいたい、とも思った。結果的に、その願いは叶ったけど、でも、死んでも、何も変わらないんだよね。いっそのこと、死ぬことを目標に、それだけを楽しみに生きられたら、どれほど素晴らしかっただろう、と、今になって思うよ。彼と、毎日、それだけを頼りに生きる。どう? 素晴らしいって思わない?」
「少し、思う」
「まだまだ、楽しいことは、あったかもしれないね。今さら、もう遅いけど……。月夜は、そうならないように、祈っているよ。なるべくなら、死ぬのは早くない方がいい。まあ、こんなこと、いちいち言わなくても分かると思うけど……」
「自分から、死ぬのは、いけないこと?」
「いいこと、ではないよ」紗矢は笑った。「いけない、とは言えないけどね」
「私が、死にたいって言ったら、どうする?」
「私は、止めるかもしれない」
「うん……。それは、正しい、かな」
「……どうだろう。正しいことなんて、何もないのかもしれない」
ペットボトルの中身を飲みながら、月夜はお茶について考えた。
彼女は、どちらかというと、お茶が好きだ。どれくらい好きかというと、少なくとも、牛乳以上には好きだといえる。牛乳は、動物から齎される液体だから、彼女はあまり好きではない。その点、お茶は植物から齎される液体だから、彼女は、好ましい、と感じる。
月夜は、基本的に、動物の肉や、動物の油が嫌いだ。その第一の理由は、それらが、自分と同じ「動物」というカテゴリーに属する生き物の、殺された成れの果てのものだからだ。しかし、この理屈がおかしいことはすぐに分かる。なぜなら、植物にも、命があることに変わりはないからだ。動物を殺すと嫌悪感を抱くのに、植物を殺しても特に何も感じない、というのは、明らかに人間のエゴだ。あるいは、もう少し規模を大きくして、動物のエゴだともいえる。動物は、無意味にほかの動物を殺さない。しかし、動物は、意味がなくても、様々な植物を殺す。これは、動物と、植物の間に、何らかの差があらからだと考えられる。ほとんどの人間は、その差を無意識の内に認識している。言葉で詳細に説明できない、というだけで、その差が存在すること自体は、ほとんどの人間は分かっているのだ。
いっそのこと、植物になりたい、と月夜は思う。
植物は、痛みを感じるのか? たとえ痛みを感じても、表現する手段がなければ、それは誰にも伝わらない。動物は、痛みを感じると、それを身体を使って表現する。だから、同じ「動物」というカテゴリーに属する人間には、それが分かる。けれど、植物の場合は分からない。ここには、言語的な相違がある、とも考えられる。植物が使う言語を、人間が理解できれば、あるいは、彼らと意思の疎通を図ることができるかもしれない。
そうした結果、もし、植物が、痛みを感じていると分かったら、もっといえば、もし、植物にも、動物と同じように、感情と呼べるものがあると分かったら、人間はどうするだろう? それでも、自分勝手なエゴで、彼らを殺すだろうか?
植物も、人間と同じように、色々なことを考えているかもしれない。人間は考える葦である、と言った科学者がいたが、本当は、葦は考える人間であるのかもしれない。本当にそうだとしたら、人間はどうしたら良いだろう? そう考えたとき、月夜は、どうしても、皆消えてしまえば良いのではないか、という結論に至ってしまう。彼女には、それ以外の解決策は考えられなかった。本当は、それは、解決策、とは呼べない。人間が救われなければ、解決策ではない。人間が関わらない解決策というものは、この世界には存在しない。
世界とは何か?
世界と、人間の社会は、同義か?
……分からない。
そう、分からないことだらけ。
これだけ多くの動物を殺して、これだけ多くの植物を殺して、多種多様な手段でエネルギーを消費して、様々に思考した結果人間が導き出した答えが、分からない、という酷く空疎なものだったら、神様はどう思うだろう?
人間なんて、生み出さなければ良かった、と後悔するだろうか?
どうだろう?
「月夜、今夜は、ここに泊まっていけば?」紗矢が言った。
「家に帰って、フィルとお風呂に入らないと」
「フィルと、私と、どっちが大切?」紗矢は笑いながら尋ねる。
月夜は暫く考える。
やがて、彼女は、最も合理的な結論に至った。
「お風呂が、一番大切」
紗矢は、沈黙して、応えなかった。
「クッキーって、何?」
クリスマスになった。イヴではない。正真正銘の当日だ。月夜の家には、サンタクロースはやって来なかった。当たり前だ。よく、父親がサンタクロースだから、サンタクロースは存在しない、といった主張を耳にするが、それは論理的に間違えている。父親がサンタクロースだったからといって、世界のどこにも、サンタクロースは存在しない、というわけではない。あなたの家では、サンタクロースの役を父親がやっていた、というだけであって、サンタクロースは、世界のどこかにはいるかもしれない。反対に、いないことを証明するのは、ほとんど不可能だといって良い。悪魔の証明、というやつだ。
「クッキーとは何か、だって?」歩きながら、フィルが言った。「小麦粉を使った、焼き菓子のことに決まっているじゃないか」
「今、手には持っていない」
「じゃあ、その、手提げ鞄の中に入っているんだな。分かった」
「うん、入っているよ」
「いちいち、面倒臭い手順を踏まないと、話が通じないようだ」
「どうして、話が通じないの?」
「まあ、主体が見ているものと、客体が見ているものでは、まったく違う、ということだろう」
「どう違うの?」
「つまり、視点が違う。見えるものと、見えないものが、それぞれある。鏡を通して自分を見ることはできても、その行為をしている自分を、背後から見ることはできないだろう?」
「できない」
「そういうことさ」
「どういうこと?」
月夜は、帽子を被ってこなかった。紗矢は、サンタクロースの帽子を被ってきてほしい、と言っていたが、そんなものは持っていないので、被ることはできない。それでは、別の帽子を被っていこうか、という議論をフィルとしたが、そんな必要はないと判断して、結局、何も被っていかないことになった。
便箋と、封筒は、紗矢に言われた通り持ってきた。筆記用具も持っている。けれど、今日はクリスマス当日だから、今からサンタクロースに手紙を書いても、もう意味がないだろう。月夜は、それを分かっていて、昨日は紗矢の所に行かなかった。どうしてそんな選択をしたかというと、これが特に理由はない。たまたま、事の成り行きで、そうなっただけだ。事の成り行きとはおそろしいものだ、と月夜はまるで他人事のように考える。事実、その通り、彼女にとっては他人事だ。まさか、紗矢も、サンタクロースに手紙を送ったら、本当にプレゼントが貰えるとは考えていないだろう。
ビンゴについても、そんなものは持っていないから、今日はやるつもりはなかった。近所の店を探しても、見つからなかった。
時刻は午後六時だ。もう空は暗い。完全に夜といって良い。パーティーをするのだから、やはり、夜だろう、というフィルの意見を採用して、月夜はこの時間帯に紗矢の所に行くことにした。
「それじゃあ、今日のイベントは、サンタクロース宛に、手紙を書く、ということだけか?」草原に立ち入ったとき、フィルが尋ねた。
「うん」
「なんとも、寂しいクリスマスだな」
「そうかな?」
「しかも、届かない手紙を、二人で書くのか」
「そうなるね」
「なかなかシュールだな」
「そうかな……」
「月夜は、そういう意味のないことが好きなのか?」
「特に、好きだと感じるものは、ない」
「何も?」
「好きと、嫌いの、境界がはっきりしていないから、何も言えない」
「相変わらずだな」
「フィルは、意味のないことが好き?」
「意味がある方が、好きだな」
「自分みたいに?」
「それ、どういう意味だ?」
「ごめんなさい、適当に言いました」
「どうして、突然敬語になる?」
「敬いたかったから」
石造りの階段を上る。山の中が暗いのは分かっていたから、月夜は懐中電灯を持ってきていた。それで足もとを照らしながら、二人は先へと進む。フィルは、今は月夜の手提げ鞄の中だった。
山道は若干湿っていた。朝の霧がまだ残っているのかもしれない。草の香りと、土の香りが混ざって、自然をすぐ傍に感じた。自然とは何か、と訊かれても、たぶん誰も答えられないだろう。もちろん、答えることに価値があるとはいえない。答えない、というのが、最も懸命な対応かもしれない。
静かだった。
今日は、鳥の鳴き声は聞こえない。
やがて、道が開けて、神社がある広場に到着した。
紗矢は、石段の上に座っていた。
「月夜」二人に気づいて、紗矢が声を出しながら立ち上がった。「ちょっと、月夜……」
「何?」
「もう……」
「どうしたの?」
「どうしたの、じゃないじゃん」紗矢は月夜の袖を引いて、自分の隣に座らせる。「もう、どうして、昨日の内に来てくれなかったの?」
「どうして、と訊かれても、答えられない」
「ずるい」
「何が?」
「まったく、酷いなあ……」
たしかに、酷いかもしれないな、と月夜は思った。その通り、彼女は酷いことをした。もう、サンタクロースは、自分の国に帰ってしまったに違いない。
「メリークリスマス」月夜は言った。
「もう、遅いよう」紗矢が口を尖らせる。「プレゼント、もう、もらえないよ……」
「ごめんね」
「それ、本気で謝っている?」笑いながら、紗矢は月夜の顔を覗き込む。「でも、まあ、いいよ。なんか、月夜って発想が飛躍しているよね」
「そう?」
「うん……。あと、危機感がない、という感じもする」
「どうして、危機感が必要なの?」
「だって、その方が安全じゃない?」
「そうかもしれないけど、危機感は、ない方が、いいと思うよ」
「まあね」
「便箋と、封筒を持ってきたけど、書く?」
「今から?」紗矢は笑った。「今から書いても、もう、誰にも届かないじゃん」
「来年の分のお願いを、今年の内にしておく」
「ああ、なるほど……」
「書く?」
「うーん、どうしようかなあ……」紗矢は自身の顎に人差し指を当てて、考える。「……うん、でも、せっかくだから、書こう」
「紗矢は、何が欲しいの?」
「プレゼント?」
「うん」
「内緒」
「内緒が、欲しいの?」
「違うよ」
持ってきたクッキーと、麦茶を口に含みながら、二人はサンタクロースに向けて手紙を書いた。もちろん、飲食をするのは月夜だけだ。この表現は、貴重といえば貴重だろう。普段飲食をしない彼女が、だけ、と限定を伴って、飲食をすると描写されている。なかなかお目にかかれる表現ではない。
月夜は、サンタクロースへの手紙に、時間を下さい、と書いた。ほかに何も思いつかなかったからだ。彼女には、基本的に、欲しいものがない。何も欲しくないわけではないが、特別これが欲しい、と感じたことはなかった。だから、普通なら手に入らない最も有益なものとして、時間を選んだ。理由はそれだけだ。大した理由ではない。
紗矢は、幸せが欲しい、と書いていた。彼女らしいといえば彼女らしい。何が彼女を彼女たらしめるのか、それは分からない。けれど、その文面を見たとき、月夜はなぜかそう感じた。紗矢が、死ぬ前に、幸せを掴めたのか、掴めなかったのか、月夜には分からない。この場合は、どちらでも良い、とは言い切れない。それは、自分が彼女の友達だからかもしれない、と月夜はふと思う。そんなことを思うのは、しかし本当に珍しかった。自分ではない誰かを、自分と深い関係があると感じるのは、月夜にはあまりないことだ。
二人は、書き終えた便箋を丁寧に畳んで、封筒の中に仕舞った。月夜は、紗矢が書いたものを預かることにした。ここに置いておくわけにはいかない、と紗矢が自分からそうするように頼んだからだ。月夜は、特に断る理由がなかったから、紗矢のお願いを受け入れた。
「ああ、クリスマスか……。今頃、皆、恋人同士で、何か楽しいことでもやっているんだろうな……」紗矢が呟く。
「何か、楽しいこと、とは?」
「一緒にソファに座りながら、映画を観たりとか、食事をしながら愛を語り合ったりとか、あとは、プレゼントの交換会を開いたりとか、じゃないの?」
「紗矢は、そういうことがしたいの?」
「うーん、どうかなあ……。したいような、しなくてもいいような……」
「俺とやるのは、嫌らしいからな」月夜の膝の上にいるフィルが、低い声で話す。
「別に、嫌じゃないけどさあ……。今ひとつ、ぱっとしない感じだよね」
「失礼だな」
月夜はフィルの頭を撫でる。彼は、今は大人しくしている。もっとも、彼は普段から大人しい。
「月夜は、こんな所にいていいの?」
「ん? こんな所って?」
「私なんかと、こんな場所で、貴重な時間を消費していていいのか、という質問だよ」
「そうしてほしいって、紗矢が言ったんだよ」
「あ、そうか……。……もしかして、無理させちゃったかな? ……ごめんね」
「どうして、謝るの?」
「なんか、悪いことしたかな、と思って」
「よく、分からないけど……」
「ほかに、用事とかなかった?」
「用事は、ない」月夜は話す。「紗矢と、一緒にいるのは、楽しいよ」
「本当に?」紗矢は表情を明るくする。
「うん」
「よかったあ……。なんか、嫌われちゃうかもしれないって、心配していたんだ、私……」
「どうして、私が、紗矢を嫌うの?」
「うん、なんとなく……」
「なんとなくで、誰かを嫌う人がいるの?」
「いるかもね、どこかには」
「月夜は、ほかのやつとは、感覚がずれているからな」フィルが言った。「本人は、自覚していないみたいだが」
「自覚?」月夜は首を傾げる。
「ほらな」
「ほらな?」
「なんだ? 何か気に障ったのか?」
「フィルって、月夜と一緒のときも、いつもこんな感じなの?」紗矢が尋ねる。
「うん、そうだよ」
「いや、違うね」フィルが断言する。「お前と一緒にいるときだけだ、俺が、こんな無愛想なのは」
「やっぱり……」紗矢が呟いた。
「そうなの?」月夜は首の角度を大きくする。
「ああ、そうだ」フィルは薄く笑い、軽くウインクした。「俺は、いい子だからな」
いい子とは、私のことかな、と月夜は思った。
「ねえ、紗矢」月夜は言った。「一つ訊いてもいい?」
「何?」
「どうして、私にフィルを拾わせたの?」
月夜がそう尋ねると、紗矢は少しだけ驚いたような顔をした。少しだけ驚いた、のではない。少しだけ、驚いたような顔をしたのだ。それほど重要なことではないが、紗矢は、あまり、声を上げて驚くようなタイプではない。
「……フィルが、そう言ったの?」
「そうだよ」
紗矢はフィルを見る。彼は顔を横に向けて、小さく欠伸をした。どうやら、二人の話に付き合う気はないらしい。
「そっか……」
紗矢は、何も否定しなかった。
夜の冷たい空気が流れる。木々が音を立てて揺れ、草原がある方から、吹き込むように風が入り込んできた。寒い。月夜は今日もコートを着ていない。紗矢に関しては、今も半袖のままだった。きっと、もう温度を感じないのだろう。それはそれで、とても良いかもしれない、と月夜は思う。フィルの暖かさを傍で感じられないのは、少しだけ寂しいが……。
「あのね、月夜」
「何?」
「私は、特別君を選ぼうと思ったわけじゃないんだ」
「うん」
「ただ、君のことが見えて、君も私たちが見えるみたいだったから、君を選んだ、というだけ」紗矢は話す。「あとは、君の風貌が気に入ったから、かな……。うん、理由なんて、その程度のものだよ。何か、特別な理由があったわけじゃない。少なくとも、私は、そう考えている」
「あの時間に、あの場所に、フィルを置いて、私を誘ったの?」
「そうだよ」
「どうして、紗矢が、直接、私の所に来なかったの?」
「私は、ここから出られないから」
「どうして?」
「気になるの?」
「気には、ならないけど、訊いておいた方がいいかな、と思った」
「フィルは、移動できる。けれど、私はできない。どうしてか分かる?」
「分からないよ。どうして?」
「フィルは、空間だからだよ」
「空間?」月夜は首を傾げる。
「そう、空間……」紗矢は言った。「空間は、自由に移動できる。そう、移動……。つまりは、物質の位置が変わる、ということだよね。私は、あまり、そういう学問に詳しくないから、よくは分からないけど……」
「それが、どうかしたの?」
「それが、彼が移動できる理由だよ」
「どういうこと?」
「どういうことだと思う?」
月夜は、一度黙って考える。
紗矢の説明は、少々おかしいところがある、と彼女は思った。まず、空間は、自由に移動できる、というのは、「空間」が主語なのではない。空間の中を、「私」あるいは「誰か」が、自由に移動できる、という意味だ。だから、普通、空間が、主体的に、移動できる、という捉え方はしない。しかし、紗矢はそれを混同している。いや、意図的にそうしている、と考えた方が良いかもしれない。これは、一種の言葉遊びだ。そんなふうに、言い包めようと思えば、どんなことでも、適当に言い包められるのだ。人間が持ち合わせる論理とは、そういうものだ。
「月夜は、フィルと一緒にいてくれる? それとも、もう一緒にいてくれない?」
「私は、いいよ。でも、紗矢は、それでいいの?」
紗矢は月夜を見る。
月夜も紗矢を見た。
数秒間、視線が交錯する。
「私は、それでいい」やがて、月夜から目を逸らして、紗矢は言った。「それでいいよ」
月夜は、前を向いたまま答える。
「分かった」
「何が?」
「紗矢の考えを、承認した、という意味」
「うん……。月夜なら、そう言うと思ったよ」
「予想していたの?」
「予想、というほどではないけど、なんとなく、そんな気がしていた」
「紗矢、笑わないの?」
「どういう意味?」
「嬉しくないの?」
「どういう意味?」
沈黙。
フィルは退屈そうだ。その通り、退屈なのだろう。人間の少女らが、何やら真剣そうなやり取りをしている、くらいに考えているに違いない。彼は、どんなことでも他人事だ。自分が関与していないと思っている。しかし、月夜は、彼のそんな態度が好きだった。自分もそんなふうに生きられたら良い、と素直に思う。思いは、常に素直だ、と考えたことがある。けれど、素直は、常に思いではない。どうして、そんなことを考えるのか? 考える必要がないのに、それでも考えてしまうのは、どうしてだろう?
紗矢は、身を乗り出して、月夜を軽く抱きしめた。
「何?」
月夜は尋ねる。
「ごめんね……」
「何が?」
「ううん、なんでもない」
「うん……」
「月夜、温かいね」
「そう?」
「うん。私なんかよりずっと」
「私は、よく、冷たい、と言われる」
「たぶん、私が体温を持たないから、今は月夜の方が温かいんだよ」
「なるほど」
「何が、なるほどなの?」
「特に、意味のない、相槌」
「月夜は、素直だね」
「そうかな」
「そうだよ。……私も、もっと素直になりたかった」
「誰に対して?」
「自分に対して」
「それは、難しいよ」
「難しかったら、できなくても、いいかな?」
「いい、と、思う」
「ありがとう」
「なぜ、感謝するの?」
「なぜだと思う?」
月夜には、分からなかった。
空から雪が降ってくる。雪を見てから、雪だ、と月夜は思った。季節外れではないが、予想外ではある。彼女は、あまりテレビを見ないから、天気予報は確認していない。空はたしかに曇っていた。暗いから、気づかなかった。これが、ホワイトクリスマス、というものらしい。
人は、なぜ、勉強するのだろう? 一度勉強したからといって、それですべてが身につくわけではない。必ず、失われる部分が存在する。決して完全にはならない。それなのに、何度も同じことを繰り返して、内容を記憶して、少しでも自分の能力が上がれば、と期待する。いずれ死んでしまうのに、どうしてそんなことをするのか、月夜は不思議に感じる。
彼女は、言うなれば、学校の成績のために勉強している。自分の能力を上げる、ということを、勉強の目的にしていない。それは、つまり、やらされている、ということでもある。学校に通って、与えられた課題をこなして、次に進む。それらはすべて計画されている。けれど、習得の精度には個人差があるから、すべての生徒が、計画された通りに目標を達成できる、というわけではない。人間は、生まれながらにして不平等なのだから、すべての生徒の勉強の量や質が同じでも、結局のところ差に変化は生じない。だから、能力のない生徒は、能力がある生徒以上に勉強しなくてはならなくなる。どうして、そんな不合理なことを求めるのか。能力がないのなら、もう、それで良いではないか。どうして、それ以上鍛錬しなくてはならないのか。しても、仕方がない。だって、いつか死んでしまうのだから……。
自分が発見した成果が、自分が死んだあとで、ほかの人に受け継がれる。それが楽しいから、学問を極めるのだ、と言う人もいる。けれど、いつまで、そんなことを続けるつもりだろう? 終わりがないのに、いったい何を目標にしているのか。それが、月夜には分からない。生命は、そういったサイクルに縛られている。それを断ち切ることはできない。断ち切ろうとすれば、たちまち環境というシステムに阻害される。人間にそのサイクルを断ち切らせないために、世界には、予め、安全装置が組み込まれているのだ。では、それは何のためだろう? そう考えても、結局何の答えも出ない。それは、目標や、目的を掲げるのが、人間に特有な行為だからかもしれない。では、人間が、目標や、目的を掲げるのは、どうしてだろう?
そう……。目標や、目的なんて、本当は存在しない。
人間が、存在すると錯覚しているだけだ。
それらがあれば、素晴らしいと感じるし、それらがなければ、価値はないと感じる。
だから、皆、将来の夢を掲げて、それを頼りに生きている。それがなければ、まともに生きることすらできない。生物として、ここまで脆弱な種はほかにない。人間は、弱い生き物だ。生物という集合の中で、最も生きる能力を持っていないのではないか。
横を向いて、月夜は紗矢を見る。
紗矢は、死んだのに、まだ、こうして、この世界に留まっている。それは、彼女が人間だったからかもしれない。やはり、目標や、目的がないと、死後の世界でも生きていけないのだ。だから、ここに座って、自分と会話をする、そのために生きている、と思い込んでいる。あるいは、ほかにも、目標や目的が存在するのかもしれない。
ほかの、目標や、目的。
では、それらがすべて達成されれば、紗矢は消えてしまうのか?
消えるために、目標や、目的を掲げている?
なんて、馬鹿げているのだろう……。
そして、なんて、寂しい存在なのだろう……。
「月夜、何、考えているの?」
紗矢が訊いた。
「少し、わけの分からないこと」
「へえ、どんな?」紗矢はにこにこ笑って話す。「聞かせてよ。そういう話、大好きだよ」
「紗矢は、何のために、ここにいるの?」
「私?」紗矢は少し不思議そうな顔をした。「うーん、なんとなく、かな……。……月夜は、どうして、生きているの?」
「どうしてだろう……」
「それを、考えていたの?」
「うん、まあ、そう」
「そういうときって、あるよね」
「そう?」
「うん……。私も、よく考えたよ。死んでしまいたい、とも思った。結果的に、その願いは叶ったけど、でも、死んでも、何も変わらないんだよね。いっそのこと、死ぬことを目標に、それだけを楽しみに生きられたら、どれほど素晴らしかっただろう、と、今になって思うよ。彼と、毎日、それだけを頼りに生きる。どう? 素晴らしいって思わない?」
「少し、思う」
「まだまだ、楽しいことは、あったかもしれないね。今さら、もう遅いけど……。月夜は、そうならないように、祈っているよ。なるべくなら、死ぬのは早くない方がいい。まあ、こんなこと、いちいち言わなくても分かると思うけど……」
「自分から、死ぬのは、いけないこと?」
「いいこと、ではないよ」紗矢は笑った。「いけない、とは言えないけどね」
「私が、死にたいって言ったら、どうする?」
「私は、止めるかもしれない」
「うん……。それは、正しい、かな」
「……どうだろう。正しいことなんて、何もないのかもしれない」
ペットボトルの中身を飲みながら、月夜はお茶について考えた。
彼女は、どちらかというと、お茶が好きだ。どれくらい好きかというと、少なくとも、牛乳以上には好きだといえる。牛乳は、動物から齎される液体だから、彼女はあまり好きではない。その点、お茶は植物から齎される液体だから、彼女は、好ましい、と感じる。
月夜は、基本的に、動物の肉や、動物の油が嫌いだ。その第一の理由は、それらが、自分と同じ「動物」というカテゴリーに属する生き物の、殺された成れの果てのものだからだ。しかし、この理屈がおかしいことはすぐに分かる。なぜなら、植物にも、命があることに変わりはないからだ。動物を殺すと嫌悪感を抱くのに、植物を殺しても特に何も感じない、というのは、明らかに人間のエゴだ。あるいは、もう少し規模を大きくして、動物のエゴだともいえる。動物は、無意味にほかの動物を殺さない。しかし、動物は、意味がなくても、様々な植物を殺す。これは、動物と、植物の間に、何らかの差があらからだと考えられる。ほとんどの人間は、その差を無意識の内に認識している。言葉で詳細に説明できない、というだけで、その差が存在すること自体は、ほとんどの人間は分かっているのだ。
いっそのこと、植物になりたい、と月夜は思う。
植物は、痛みを感じるのか? たとえ痛みを感じても、表現する手段がなければ、それは誰にも伝わらない。動物は、痛みを感じると、それを身体を使って表現する。だから、同じ「動物」というカテゴリーに属する人間には、それが分かる。けれど、植物の場合は分からない。ここには、言語的な相違がある、とも考えられる。植物が使う言語を、人間が理解できれば、あるいは、彼らと意思の疎通を図ることができるかもしれない。
そうした結果、もし、植物が、痛みを感じていると分かったら、もっといえば、もし、植物にも、動物と同じように、感情と呼べるものがあると分かったら、人間はどうするだろう? それでも、自分勝手なエゴで、彼らを殺すだろうか?
植物も、人間と同じように、色々なことを考えているかもしれない。人間は考える葦である、と言った科学者がいたが、本当は、葦は考える人間であるのかもしれない。本当にそうだとしたら、人間はどうしたら良いだろう? そう考えたとき、月夜は、どうしても、皆消えてしまえば良いのではないか、という結論に至ってしまう。彼女には、それ以外の解決策は考えられなかった。本当は、それは、解決策、とは呼べない。人間が救われなければ、解決策ではない。人間が関わらない解決策というものは、この世界には存在しない。
世界とは何か?
世界と、人間の社会は、同義か?
……分からない。
そう、分からないことだらけ。
これだけ多くの動物を殺して、これだけ多くの植物を殺して、多種多様な手段でエネルギーを消費して、様々に思考した結果人間が導き出した答えが、分からない、という酷く空疎なものだったら、神様はどう思うだろう?
人間なんて、生み出さなければ良かった、と後悔するだろうか?
どうだろう?
「月夜、今夜は、ここに泊まっていけば?」紗矢が言った。
「家に帰って、フィルとお風呂に入らないと」
「フィルと、私と、どっちが大切?」紗矢は笑いながら尋ねる。
月夜は暫く考える。
やがて、彼女は、最も合理的な結論に至った。
「お風呂が、一番大切」
紗矢は、沈黙して、応えなかった。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説
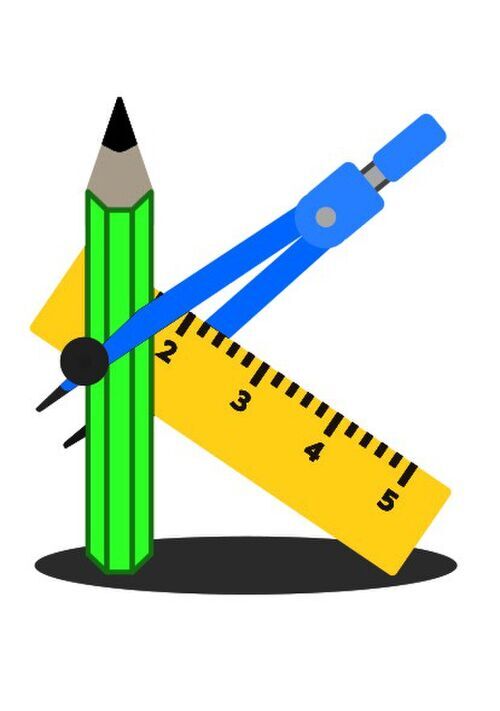
舞台装置は闇の中
羽上帆樽
ライト文芸
夜。少年と少女は出会い、言葉を交わして、再び別れていく。意味も意義も意図も持たない彼らの言動には、いったいどのような価値あるのだろう? 意味や価値を創造するのが人間なら、無意味や無価値を創造するのもまた人間。そんな物語を作るために、彼らは存在するのかもしれない(しかし、それもまた目的という人間の創造物であることを忘れてはならない)。

5年も苦しんだのだから、もうスッキリ幸せになってもいいですよね?
gacchi
恋愛
13歳の学園入学時から5年、第一王子と婚約しているミレーヌは王子妃教育に疲れていた。好きでもない王子のために苦労する意味ってあるんでしょうか。
そんなミレーヌに王子は新しい恋人を連れて
「婚約解消してくれる?優しいミレーヌなら許してくれるよね?」
もう私、こんな婚約者忘れてスッキリ幸せになってもいいですよね?
3/5 1章完結しました。おまけの後、2章になります。
4/4 完結しました。奨励賞受賞ありがとうございました。
1章が書籍になりました。

古屋さんバイト辞めるって
四宮 あか
ライト文芸
ライト文芸大賞で奨励賞いただきました~。
読んでくださりありがとうございました。
「古屋さんバイト辞めるって」
おしゃれで、明るくて、話しも面白くて、仕事もすぐに覚えた。これからバイトの中心人物にだんだんなっていくのかな? と思った古屋さんはバイトをやめるらしい。
学部は違うけれど同じ大学に通っているからって理由で、石井ミクは古屋さんにバイトを辞めないように説得してと店長に頼まれてしまった。
バイト先でちょろっとしか話したことがないのに、辞めないように説得を頼まれたことで困ってしまった私は……
こういう嫌なタイプが貴方の職場にもいることがあるのではないでしょうか?
表紙の画像はフリー素材サイトの
https://activephotostyle.biz/さまからお借りしました。

愛する貴方の心から消えた私は…
矢野りと
恋愛
愛する夫が事故に巻き込まれ隣国で行方不明となったのは一年以上前のこと。
周りが諦めの言葉を口にしても、私は決して諦めなかった。
…彼は絶対に生きている。
そう信じて待ち続けていると、願いが天に通じたのか奇跡的に彼は戻って来た。
だが彼は妻である私のことを忘れてしまっていた。
「すまない、君を愛せない」
そう言った彼の目からは私に対する愛情はなくなっていて…。
*設定はゆるいです。


【完結】忘れてください
仲 奈華 (nakanaka)
恋愛
愛していた。
貴方はそうでないと知りながら、私は貴方だけを愛していた。
夫の恋人に子供ができたと教えられても、私は貴方との未来を信じていたのに。
貴方から離婚届を渡されて、私の心は粉々に砕け散った。
もういいの。
私は貴方を解放する覚悟を決めた。
貴方が気づいていない小さな鼓動を守りながら、ここを離れます。
私の事は忘れてください。
※6月26日初回完結
7月12日2回目完結しました。
お読みいただきありがとうございます。

人生を共にしてほしい、そう言った最愛の人は不倫をしました。
松茸
恋愛
どうか僕と人生を共にしてほしい。
そう言われてのぼせ上った私は、侯爵令息の彼との結婚に踏み切る。
しかし結婚して一年、彼は私を愛さず、別の女性と不倫をした。

よくできた"妻"でして
真鳥カノ
ライト文芸
ある日突然、妻が亡くなった。
単身赴任先で妻の訃報を聞いた主人公は、帰り着いた我が家で、妻の重大な秘密と遭遇する。
久しぶりに我が家に戻った主人公を待ち受けていたものとは……!?
※こちらの作品はエブリスタにも掲載しております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















