8 / 10
第8章 閃
しおりを挟む
午前六時に目を覚まして、月夜はいつも通り勉強した。学校を休むから、その分、家で勉強しなくてはならない。学校の授業と、家庭での個人的な勉強では、内容がまったくといって良いほど違うが、だからといって、方法まで異なるわけではない。勉強は、もうやり方が決まっている。人間が使う言語の論理体系を変えない限り、その方法が変わることはないだろう。
数学と、世界史を進めて、気がつくと、八時になっていた。
今日は、真昼との約束がある。彼に呼び出されて、学校を休むことになった。最初は、無断で欠席しても良いかな、と思っていたが、さすがにそれはまずいと思い直して、月夜は学校に電話を入れた。担任に繋がって、要件を伝えても、彼はまったく驚かなかった。月夜も、真昼も、教師や友人からあまり見られていない。もちろん、物質としては認識されているだろうが、月夜と真昼という個々の存在には、彼らはまったく目を向けようとしない。月夜にはそれが分かっていた。電話を切って、平日の朝なのに、私服に着替える。なぜだか分からないが、洋服を選ぶのに多少時間がかかった。真昼のことを意識しているせいかもしれない。別に、一方的に好意を寄せているわけではないし、もう、充分気に入られているのだから、今さらそんな気遣いをしても、と思う。それなのに、ちょっと気合いを入れて、「自分」という存在を加工しようとしていることに気づいて、月夜は、もう少しで笑ってしまいそうになった。でも、彼女は笑わない。どうしてなのか、自分でも分からなかったが、一人で笑うことに抵抗があった。
濃い色をしたジーンズと、少し大きめのシャツを着て、玄関を出る前にその上から黒いジャケットを羽織った。帽子を被っても良かったが、それでは、かなり怪しく見えてしまいそうだから、今日は控えておいた。
待ち合わせは十時だから、まだ一時間近くある。それでも、電車が遅れないとは限らないし、待っている時間に本を読んでいれば良い話だから、月夜は余裕を持って家を出た。駅で本を読んでも、家で本を読んでも、やっていることに変わりはない。彼女は、周囲の環境から多大な影響を受ける方ではないから、多少騒がしくても、いつもと同じように本の内容に集中できた。
真昼が言っていた駅というのは、二人が、毎日、学校に行く際に降りる駅のことではない。待ち合わせをする駅というのが、二人の間で予め定められていて、そこまで行くのに、学校の最寄り駅を通過する必要がある。平日だが、通学や通勤の時間帯とは多少ずれているから、車内は混んでいない。駅でも同じ学校の生徒に遭遇することはなかった。
いつもより少しだけ長い間電車に乗って、真昼と待ち合わせをしている駅に到着する。電車を降り、改札を抜けると、月夜は構内の隅で本を読み始めた。
月夜は、駅という場所が好きだった。彼女は、好き、嫌い、という判断を、真昼に思われているほどしない。それは、言葉の問題で、本当は、その二項だけで表せる感情ではない。しかし、どういうわけか、駅の構造に関しては、彼女を強く引き寄せるものがあった。
たとえば、月夜は、駅の地下構内を支える巨大な柱が好きだ。微妙な曲率というか、円形だから正面がなくても、ある一定の方向から眺めたときに、見えない部分があるのが良い。これは、このサイズの円柱でないと実感できない。真昼という人間も、少し会話をするだけでは普通に見えるが、もう少し深入りすると、まったく見えない部分があるから、そういった点では、彼に対する好意と似通っているかもしれない。
そんなことを考えながら、彼女は本を読む。
本に書かれている内容は、間違いなく彼女の頭に入っているが、それ以外の情報も同時に認識されている。本を読むのも、周囲の状況を把握するのも、どちらもインプットだから、処理として大きな差はない。違うのは、本の場合、ただ読むだけではなく、読むのと同時に個人的な思索を行っている、ということだ。これは、人の話を聞きながら、同時にその内容を吟味している、ということと似ている。人間の頭はそういうふうにできているらしい。だからといって、それが特別だとか、そういう話ではない。もっと良い処理の仕方があるかもしれないし、実際に、コンピューターは、人間とは違う方法で情報の処理を行っている。
真昼はなかなか現れない。
それもそのはずで、まだ、約束の時間まで三十分以上ある。
真昼は、多くの場合、時間にルーズだ。ルーズというのは、約束の時間を破るという意味ではなく、守るのも、破るのも、気にしない、ということを示す。そもそも、時間というものは、ある単位を基本として人間が定めたものだから、それに従わない、という選択をすることもできる。もしかすると、真昼には彼に固有な独立した単位が存在するのかもしれない。そう考えると、なんだかわくわくして、月夜の本を読む速度は速くなった。
時間が過ぎる。そもそも、過ぎない時間はない。
改札の向こうから真昼が現れた。
驚くことではないが、彼は制服を着ていた。
ほとんどの場合、真昼は制服を着て生活している。私服を持っていないわけではないらしいが、いまいち自信がない、とのことらしい。学校をずる休みしているのに、堂々と制服を着てくる神経が、月夜には理解できない。けれど、理解できなくても面白いとは感じたから、彼の服装について彼女は特に指摘しなかった。
「やあ、待った?」近くまで来て、真昼が言った。
「待った」
「え、本当に? どれくらい?」
「たぶん、二十分くらい」
「それは、君が早く来すぎなんじゃないかな」
「うん、そうだよ」
「じゃあ、僕のせいじゃないね。よかったよ」
「よかった」
月夜が先ほど乗ってきたのとは別の路線に切り替えて、二人は再び電車に乗った。席は沢山空いているから、自由に選んで座れる。しかし、どこに座っても大して変わりはないので、二人は、適当に、座席の中央に腰かけた。こういう座り方をする人間は珍しい。普通、電車の座席の場合、端の方から座っていく。最初に端が埋まり、次に、それらから一つ飛ばして、奇数個目の席が埋まる。それを繰り返し、混雑してくると、ついに隣同士の席に座る人が出てくる。月夜と真昼は知り合いだから、初めから隣り合って座った。反対に、そうしなければ、人間の距離感として大分おかしい。二人の場合、これでもまだ遠いくらいだった。
月夜は、真昼に、今日の目的について尋ねるのは控えた。その内彼の方から話してくるだろう、と予想したからだ。彼は自由人だから、自分が決めたタイミングで物事を進めるのを好む。月夜が彼の行動に干渉することはないが、ときどき、タイミングを見誤って、真昼の機嫌を損ねることがあった。機嫌を損ねるといっても、彼は露骨に不満を零すような人間ではないから、その変化を読み取るのは難しい。経験がものを言う、といって良い。どちらかというと、真昼は不機嫌でも笑顔だ。というよりも、彼は常に笑顔だから、より一層彼の感情を推し量るのは難しくなる。しかし、それは月夜もお互い様だったから、彼女にとって一方的に不利な状況ではなかった。
「今日の朝、起きたら、いつの間にか宿題が終わっていたんだ」対面にある窓の向こうを見ながら、真昼が言った。辺りに人はいないから、他人に会話が聞かれる心配はない。「どうしてか分からないけど、与えられた課題が、すべて終わっていた。きっと、自分でも知らない内に、問題を解いていたんだろうね。いつだろう……。寝る前にそんなことはしないし、だからといって、家に帰ってすぐ勉強する、ということもないから、それこそ、本当に、眠っている間に布団から這い上がって、無意識の内に解いたのかもしれない。そうでなければ、幽体離脱した、とかね」
真昼は楽しそうだ。楽しそうだから、月夜も楽しくなった。
「君が眠っている間に、私が、君の部屋に忍び込んで、解いたかもしれない」
「それ、本当?」真昼は笑う。「そうだったらいいなあ……。でも、窓は鍵をかけておいたから、ちょっとありえないよ。魔法を使ったというなら、話は別だけど……」
「ごめんなさい。よく考えないで、話した」
「謝らなくていいよ」
「でも、その宿題は、今日提出するものだったんじゃないの?」
「うん、そうなんだ。だから、はっきりいって、終わらせた意味がない。提出期限を破ってしまったら、もう、価値はないんだ。ああいうのは、時間を守って終わらせないと、駄目だよね。ときどき、一週間前の宿題を出している人がいるけど、そんなことするくらいなら、僕なら、たぶん、二度とやらないだろうな。……君なら、どうする?」
「どう、というのは、何を訊いているの?」
「もし、一週間前に提出すべき宿題を、やっていないことに気づいたら、やって出すか、それとも出さないか、ということ」
「出す」
「へえ……。それは、どうして?」
「出した、という事実が、残るから」
「でも、遅れた、という事実が、それより先に存在するよ」
「そっか」
「うん、そうだ」
「それなら、出さない、かもしれない」
「出すかもしれないし、出さないかもしれないから、断定的な答えじゃないと、駄目だよ」
「じゃあ、出さない」
「本当に?」
「うん」
「どうして?」
「遅れた、という事実が、先にある、という君の意見を聞いて、なるほど、と、思ったから」
「思ったの?」
「思ったよ」
「思う、というのは、意識的か、それとも、無意識か、どっちだと思う?」
「どっちだと思う、という質問の、思うは、意識的か、無意識か、どっちだと、思う?」
真昼は月夜を見る。
「それ、おかしなことになるよ」
「うん。仕方がない、と思う」
「その、思うというのは……」
「うん」
「いや」
「何?」
「なんでもないよ」
「分かった」
二十分ほど電車に乗り続けて、二人はホームに降り立った。そのとき、真昼になんの躊躇いもなく手を握られて、月夜はびっくりした。けれど、それが表情として顔に出ることはない。彼女の感情や感覚は、すべて一律で無表情で処理される。もちろん、その許容範囲を越えれば、感情が顔に出ることもある。それにしても、自分は、今までの人生で、心の底から笑ったことも、泣いたことも、怒ったこともないのではないか、と月夜は思った。そう思いたいだけかもしれない。いずれにせよ、彼女が感情を表に出すのに消極的なことに変わりはない。それでも、真昼に笑ってほしいと言われれば、躊躇せずに笑うことくらいはできた。
改札を出ると都市が広がっていて、二人が住んでいる地域に比べれば、恒常的に活気があるように見える。日中でも街を人が歩いていて、自動車が走る音もあちこちから聞こえてきた。ただし、動物の鳴き声は聞こえない。人間も動物だが、そこに人間は含まれない。それは、どうしてだろう? 多くの場合、人間は、自分たちとほかの動物を区別したがる。そうしないと生きていけないのかもしれない。月夜は、あまり食事をしないが、それには、ほかの動物を食べなくてはならない、ということも関係していた。できるなら、彼女は動物の肉を食べたくない。そこに合理的な理由があるわけではないが、だからといって、ただの「嫌だ」という感情に起因して、そのように考えているわけでもない。そう、「考えている」のだから、少なくともそれは意識的だ。その点については、月夜はまだ自分のことを理解できていない、といえる。残された人生は、限りあるものだが、それまでに、少しずつでも、自分に関することが明らかになれば良いな、と彼女は考えていた。
都市の裏通りに、小さな公園があった。
真昼は、その中へ、迷わず足を踏み入れていく。
月夜は黙って彼のあとをついていった。
背の高いビルが周囲に建っているが、この公園は、そんな環境から孤立しているように感じられた。ブランコの塗装は剥げかけ、至る所から雑草が顔を出している。そして、何より、誰も遊んでいなかった。時間帯も関係しているかもしれないが、もし、普段から利用者がいるのなら、こんな閑散とした雰囲気にはならない。それに、地面から雑草が生えているということは、長い間、その地面が誰にも踏まれていない、ということを示している。
真昼がベンチに座ったから、月夜も彼の隣に腰かけた。というよりも、手を繋いでいるから、そうするしかない。
とても静かだ。
音は聞こえるのに、静かだ、と感じる。
「少し、休憩しよう」真昼が言った。「慣れない旅だから、もしかすると、これから、もっとエネルギーを消費するかもしれない。君は、不必要にエネルギーを消費するのは嫌いだろう?」
月夜は頷く。
「うん」
「お腹、空いた?」
「いや、空いてない」
「そう……。……風が心地いいね」
「風は、今は吹いていない」
月夜に言われて、真昼は初めてそれに気がついた。彼は苦い表情をして、月夜の瞳を見つめる。
いつも通り、そこには、彼女に特有な冷徹さがあった。
「うん、そうか……。僕は、今、ちょっと、頭が回っていないみたいだ」
「ちょっと、というのは、どれくらいのことを、言っているの?」
「君は回っているみたいだね」
「歩くのをやめても、地球は回っている」
「それは、生きている間に、できる限り活動した方がいい、ということ?」
「うーん……。活動しなくても、幸せは、掴めるかもしれない」
「やけに面白いことを言うね」
「そうかな」
「うん、そんな感じがするよ」
「ここに、私を連れてきたのは、どうして?」
月夜はいきなり質問した。
如何なる前兆も示さずに、突然質問することで、自分の本気度を伝えられる、と月夜は考えている。相手のことを気遣って前振りを設けるのも良いが、比較的親しい間柄では、それは却って逆効果になる可能性が高い。
「今、それを訊くんだね」案の定、真昼にそう言われた。
「タイミング、間違えた?」
「いや、僕も、君なら、そろそろ訊いてくるかな、と思っていたんだ」真昼は薄く笑う。「今まで訊かないでくれて、ありがとう」
月夜は首を傾げてそれに応じる。
真昼は、愛おしそうに彼女の顔を見つめた。
「僕が今から話すことを、信じなくても、いい、とだけ伝えておくよ」真昼は話す。「でも、君なら、きっと信じてくれるんだろうな……。……君は、疑う必要がなければ、疑わない。そして、僕は、君に疑われるような人間ではない、と自負している」
「うん。そうだよ」
「僕は、もう、あの学校には行かない」
風が吹いて、ブランコがきいきいと音を立てた。
「どうして?」
「どうしてだと思う?」
真昼に尋ねられたから、月夜は黙って考える。訊かれた質問には、きちんと考えてから答えなくてはならない。それが、月夜が掲げるポリシーだった。しかし、彼女は自分ではそのポリシーを認識していない。処世術みたいなもので、後天的に会得されたものだった。
「どこかに、引っ越す、ということ?」
やがて、月夜は、導出された最も合理的な考えを口にする。
「うん、そう」真昼は頷いた。「その通り、正解だよ」
「本当に?」
「うん、本当」
「そっか」
「もしかして、予想していた?」
「予想は、していなかった」月夜は話す。「でも、それなら、また会えるんだね」
月夜がそう言った瞬間、真昼は、身を乗り出して、彼女の手を握ったまま、月夜を抱きしめた。
時間が停止する。
呼吸と、拍動。
その二つしか、この空間に存在していない。
「……何?」
「なんでもない。少し、いいかな?」
「……うん……」
髪の香り。
身体の温かみ。
それらは、物質が存在することで生じる幻想だ。
でも、二人とも、その幻想を、綺麗だ、と思った。
綺麗だから、それで良い。
それ以上である必要はない。
ただただ、綺麗。
何もかも、綺麗。
綺麗、綺麗、綺麗。
言葉を発さず、抱きしめるだけで良いから、無駄なエネルギーを消費しなくて、綺麗だった。
「どうして、私を、ここに連れてきたの?」
抱きしめられたまま、月夜はニュアンスを変えて質問した。
真昼は月夜を離し、ベンチから立ち上がる。
「ここが、僕が次に住む街だからだよ」真昼は辺りを見渡した。「けっこう都会だけど、まあ、悪くはないね。田舎も、都会も、それぞれいいところがあるから、どっちがいいか、なんて決められないよ」
「じゃあ、本当に、そんなに離れるわけではないから、よかった」
「うん、まあね」
「それで、どうして、私をここに連れてきたの?」
「どう、というのは、どういう意味?」
「口頭で伝えるだけじゃ駄目だったの?」
「うーん、そうだけど、なんていうのか、ほら、やっぱり、現物を見てもらった方がいいかな、と思って……」
「いい、というのは?」
「その方が、臨場感があるだろう?」
「ごめん、よく分からない」
「分かる必要はないよ。とにかく、それで僕は満足したから、よかったね、と思ってくれればいいよ」
「分かった。よかったね」
「うん、よかった」
暫くその公園に滞在した。
真昼の話によると、彼は、もう、引っ越し先で、どの学校に通うか決まっているみたいだった。高等学校だから、どのような手続きを踏めば入学できるのか、月夜は知らなかったが、その点については真昼も説明しなかった。とりあえず、入学できるのだから、それで良い、と月夜は思う。高校は義務教育ではないが、はっきりいって中学校とあまり変わらない。やっていることもほとんど同じだし、むしろ、違うところを述べよ、と言われた方が困る。そうすると、やはり、義務教育か否か、あるいは、高等か中等か、というのが答えになるが、それでは名称が違うだけで、答えになっていないに等しい。やっていることが変わらないのだから、やはり何も変わらない。
「さて……。じゃあ、僕の要件は終えたから、少し、辺りを散策しよう」
月夜は真昼を見る。
「散策、というのは、具体的に、どういう行為なの?」
「え? うーん、なんだろう……。特に目的を持っているわけではないけど、何かしら面白いものを見つけたい、という意思を念頭に、気の赴くまま歩くこと、じゃないかな」
「散歩、との違いは?」
「散歩は、歩くことがメインだけど、散策は、歩くことではなく、新しい発見をすることがメインじゃないかな、と僕は思うよ」
「君以外には、思えないよ」
「それ、どういう意味?」
「意味は、ない」
「歩ける?」
「うん」月夜は立ち上がる。「でも、疲れる」
「それはそうだよ。生きているんだから」
「君は、疲れても、平気?」
「平気じゃないけど、ある程度なら耐えられるよ。君は、疲れるのは、嫌いなの?」
「嫌いだよ」
「随分とストレートな答えだね」
「ストレートではない答え、とは?」
「婉曲表現を使う、とかじゃないかな」
「具体的には?」
「歩きながら話すよ」
真昼が歩き始めたから、月夜も彼に続いた。もう一度、手を繋ぐ。熱の変換が行われた。
「たとえば、考えておこう、というのが、代表的な婉曲表現だね」真昼は言った。「考えておこう、というのは、言葉としては、まだ結論が出ていないから、後々答える、という意味だけど、個人的には、そんなことって、ほとんどないと思うんだ。何かを尋ねられたら、もう、その瞬間に、だいたいの答えは決まっている。だから、考えておこう、と答えるのは、答えが出ているけど、それを今は口にしたくない、という意思の表れなんだ。問題を今解決しないで、先延ばしにしている。それが、いいことなのか、よくないことなのかは、僕には分からない。ときどき、先延ばしにしたくなることもあるから、それなら、それでも、いいと思う。でも、中には、そういうことを認めてくれない人もいるから、困ったものだよね」
「困るの?」
「困る」
「どう困るの?」
「うーん、あまり困らないけど」
「困るんじゃないの?」
「うん、困る」
「困るの?」
「困らない」
これ以上は無駄なやり取りになると判断して、月夜は口を閉じた。
裏通りから大通りに出ると、大勢の車と人に遭遇する。ビルも高層のものが多くて、二人が通っている学校がある辺りとは、様子がまるで違っていた。でも、空気が汚いとは思わない。空気が汚いというのは、人間にとって必要のない物質が多く含まれている、ということだが、それでは、そもそも、空気には窒素が最も多く含まれているのだから、どこに行っても汚いじゃないか、ともいえる。当然、これは、言葉遊びだ。あまり面白くないかもしれない。
駅前の広場に戻って、近くにあった移動式のクレープ屋で、クレープを買った。しかし、買ったのは真昼一人だけだ。月夜は、やはり、必要以上に食事をしない。飲み物も飲まないから、燃費が非常に良い。それでいて、学校の勉強はよくできるし、瞬時に合理的な判断をすることもできるから、いったい、そんなことを可能にする燃焼機関と演算装置が、本当に存在するのか、と真昼はいつも不思議に思う。彼は、バナナとカスタードクリームが入ったクレープを買った。生地も含めて、すべて炭水化物、つまり糖類だから、これ以上ないくらいエネルギーで溢れている。
花壇の淵に座って、真昼は糖分を補給する。月夜もその隣に座った。
「ときどき、遊びに来てよ。僕も、暇があれば行くから」真昼が話す。
「うん」月夜は頷いた。
「ときどきとは、どれくらいか、と訊かないの?」
「今は、訊かないことにした」
「どうして?」
「君が、クレープを食べているから」
「食べていると、どうして、訊かないの?」
「話すのが大変で、食べる速度が落ちるから、かな」
「なるほど。でもね、僕は、ものを食べながら、話ができるんだ」
「どうやって?」
「それに答えるには、人の会話とは、どこまでを会話と呼ぶのか、を定義する必要があるね」
「必要は、ない、と思う」
「そう? まあ、そうかな……」
「クレープ、美味しい?」
「美味しいよ。一口食べる?」
「いらない」
「そう言うと思ったよ」
「じゃあ、どうして尋ねたの?」
「その方が、いいかな、と思って」真昼は呟く。「キスもできるし」
「キスが、したいの?」
「いや、あまり」
「そう」
「それは、落ち込んでいるのかな?」
「どうして、落ち込む必要があるの?」
「必要は、ないかもしれないね」
「うん。ないと思う」
「空が綺麗だ」
「空は、どんなときも、綺麗だよ」
「曇っていても?」
「太陽光線を、地球に必要な分だけ届けてくれるから、無駄がなくて、綺麗」
「その、綺麗、の定義だけど、いい加減、やめた方がいいんじゃない?」
「どうして?」
「いや、僕は大変気に入っているんだけど、ほかの人に言うと、あまりよく思われないんじゃないかな、と思ってさ」
「ほかの人に、よく思われる必要は、ある?」
「きっと、ある」
「いつ?」
「いつでも」
「どうして?」
「理由はない」
「そっか」
「でも、関係は、悪いよりは、いい方がいいだろう?」
「そんな、気が、するだけ」
「そうかな……」
「関係に、いいも、悪いも、ないよ」
「そう?」
「うん……」
「僕と、君の関係は?」
「良好」
「なんだ。じゃあ、いいんじゃないか」
「そんな気がするだけ」
「悲観的だね、君って」
「君は、楽観的?」
「比較的、そうだと思うよ。ああ、比較的、というのは、君に比べたら、という意味だけど」
「たしかに、そうかも」
「でも、悲観的でも、楽観的でも、事実は変わらないね」
二人がどのように捉えても、暫くの間、互いに会いにくくなることに変わりはない。
月夜は真昼の肩に自分の頭を預けた。
そのまま、魂も預けて良い気がする。
いや、良いだろう。
彼になら、殺されても良い。
まだ昼を迎えたばかりだった。
一日がまだ半分も残っている。
「何をしたい?」真昼が質問する。
「何も、したくないことを、したい」月夜は答えた。「ずっと、このまま」
真昼は答えない。
それは、声に出す必要がないから、綺麗だった。
数学と、世界史を進めて、気がつくと、八時になっていた。
今日は、真昼との約束がある。彼に呼び出されて、学校を休むことになった。最初は、無断で欠席しても良いかな、と思っていたが、さすがにそれはまずいと思い直して、月夜は学校に電話を入れた。担任に繋がって、要件を伝えても、彼はまったく驚かなかった。月夜も、真昼も、教師や友人からあまり見られていない。もちろん、物質としては認識されているだろうが、月夜と真昼という個々の存在には、彼らはまったく目を向けようとしない。月夜にはそれが分かっていた。電話を切って、平日の朝なのに、私服に着替える。なぜだか分からないが、洋服を選ぶのに多少時間がかかった。真昼のことを意識しているせいかもしれない。別に、一方的に好意を寄せているわけではないし、もう、充分気に入られているのだから、今さらそんな気遣いをしても、と思う。それなのに、ちょっと気合いを入れて、「自分」という存在を加工しようとしていることに気づいて、月夜は、もう少しで笑ってしまいそうになった。でも、彼女は笑わない。どうしてなのか、自分でも分からなかったが、一人で笑うことに抵抗があった。
濃い色をしたジーンズと、少し大きめのシャツを着て、玄関を出る前にその上から黒いジャケットを羽織った。帽子を被っても良かったが、それでは、かなり怪しく見えてしまいそうだから、今日は控えておいた。
待ち合わせは十時だから、まだ一時間近くある。それでも、電車が遅れないとは限らないし、待っている時間に本を読んでいれば良い話だから、月夜は余裕を持って家を出た。駅で本を読んでも、家で本を読んでも、やっていることに変わりはない。彼女は、周囲の環境から多大な影響を受ける方ではないから、多少騒がしくても、いつもと同じように本の内容に集中できた。
真昼が言っていた駅というのは、二人が、毎日、学校に行く際に降りる駅のことではない。待ち合わせをする駅というのが、二人の間で予め定められていて、そこまで行くのに、学校の最寄り駅を通過する必要がある。平日だが、通学や通勤の時間帯とは多少ずれているから、車内は混んでいない。駅でも同じ学校の生徒に遭遇することはなかった。
いつもより少しだけ長い間電車に乗って、真昼と待ち合わせをしている駅に到着する。電車を降り、改札を抜けると、月夜は構内の隅で本を読み始めた。
月夜は、駅という場所が好きだった。彼女は、好き、嫌い、という判断を、真昼に思われているほどしない。それは、言葉の問題で、本当は、その二項だけで表せる感情ではない。しかし、どういうわけか、駅の構造に関しては、彼女を強く引き寄せるものがあった。
たとえば、月夜は、駅の地下構内を支える巨大な柱が好きだ。微妙な曲率というか、円形だから正面がなくても、ある一定の方向から眺めたときに、見えない部分があるのが良い。これは、このサイズの円柱でないと実感できない。真昼という人間も、少し会話をするだけでは普通に見えるが、もう少し深入りすると、まったく見えない部分があるから、そういった点では、彼に対する好意と似通っているかもしれない。
そんなことを考えながら、彼女は本を読む。
本に書かれている内容は、間違いなく彼女の頭に入っているが、それ以外の情報も同時に認識されている。本を読むのも、周囲の状況を把握するのも、どちらもインプットだから、処理として大きな差はない。違うのは、本の場合、ただ読むだけではなく、読むのと同時に個人的な思索を行っている、ということだ。これは、人の話を聞きながら、同時にその内容を吟味している、ということと似ている。人間の頭はそういうふうにできているらしい。だからといって、それが特別だとか、そういう話ではない。もっと良い処理の仕方があるかもしれないし、実際に、コンピューターは、人間とは違う方法で情報の処理を行っている。
真昼はなかなか現れない。
それもそのはずで、まだ、約束の時間まで三十分以上ある。
真昼は、多くの場合、時間にルーズだ。ルーズというのは、約束の時間を破るという意味ではなく、守るのも、破るのも、気にしない、ということを示す。そもそも、時間というものは、ある単位を基本として人間が定めたものだから、それに従わない、という選択をすることもできる。もしかすると、真昼には彼に固有な独立した単位が存在するのかもしれない。そう考えると、なんだかわくわくして、月夜の本を読む速度は速くなった。
時間が過ぎる。そもそも、過ぎない時間はない。
改札の向こうから真昼が現れた。
驚くことではないが、彼は制服を着ていた。
ほとんどの場合、真昼は制服を着て生活している。私服を持っていないわけではないらしいが、いまいち自信がない、とのことらしい。学校をずる休みしているのに、堂々と制服を着てくる神経が、月夜には理解できない。けれど、理解できなくても面白いとは感じたから、彼の服装について彼女は特に指摘しなかった。
「やあ、待った?」近くまで来て、真昼が言った。
「待った」
「え、本当に? どれくらい?」
「たぶん、二十分くらい」
「それは、君が早く来すぎなんじゃないかな」
「うん、そうだよ」
「じゃあ、僕のせいじゃないね。よかったよ」
「よかった」
月夜が先ほど乗ってきたのとは別の路線に切り替えて、二人は再び電車に乗った。席は沢山空いているから、自由に選んで座れる。しかし、どこに座っても大して変わりはないので、二人は、適当に、座席の中央に腰かけた。こういう座り方をする人間は珍しい。普通、電車の座席の場合、端の方から座っていく。最初に端が埋まり、次に、それらから一つ飛ばして、奇数個目の席が埋まる。それを繰り返し、混雑してくると、ついに隣同士の席に座る人が出てくる。月夜と真昼は知り合いだから、初めから隣り合って座った。反対に、そうしなければ、人間の距離感として大分おかしい。二人の場合、これでもまだ遠いくらいだった。
月夜は、真昼に、今日の目的について尋ねるのは控えた。その内彼の方から話してくるだろう、と予想したからだ。彼は自由人だから、自分が決めたタイミングで物事を進めるのを好む。月夜が彼の行動に干渉することはないが、ときどき、タイミングを見誤って、真昼の機嫌を損ねることがあった。機嫌を損ねるといっても、彼は露骨に不満を零すような人間ではないから、その変化を読み取るのは難しい。経験がものを言う、といって良い。どちらかというと、真昼は不機嫌でも笑顔だ。というよりも、彼は常に笑顔だから、より一層彼の感情を推し量るのは難しくなる。しかし、それは月夜もお互い様だったから、彼女にとって一方的に不利な状況ではなかった。
「今日の朝、起きたら、いつの間にか宿題が終わっていたんだ」対面にある窓の向こうを見ながら、真昼が言った。辺りに人はいないから、他人に会話が聞かれる心配はない。「どうしてか分からないけど、与えられた課題が、すべて終わっていた。きっと、自分でも知らない内に、問題を解いていたんだろうね。いつだろう……。寝る前にそんなことはしないし、だからといって、家に帰ってすぐ勉強する、ということもないから、それこそ、本当に、眠っている間に布団から這い上がって、無意識の内に解いたのかもしれない。そうでなければ、幽体離脱した、とかね」
真昼は楽しそうだ。楽しそうだから、月夜も楽しくなった。
「君が眠っている間に、私が、君の部屋に忍び込んで、解いたかもしれない」
「それ、本当?」真昼は笑う。「そうだったらいいなあ……。でも、窓は鍵をかけておいたから、ちょっとありえないよ。魔法を使ったというなら、話は別だけど……」
「ごめんなさい。よく考えないで、話した」
「謝らなくていいよ」
「でも、その宿題は、今日提出するものだったんじゃないの?」
「うん、そうなんだ。だから、はっきりいって、終わらせた意味がない。提出期限を破ってしまったら、もう、価値はないんだ。ああいうのは、時間を守って終わらせないと、駄目だよね。ときどき、一週間前の宿題を出している人がいるけど、そんなことするくらいなら、僕なら、たぶん、二度とやらないだろうな。……君なら、どうする?」
「どう、というのは、何を訊いているの?」
「もし、一週間前に提出すべき宿題を、やっていないことに気づいたら、やって出すか、それとも出さないか、ということ」
「出す」
「へえ……。それは、どうして?」
「出した、という事実が、残るから」
「でも、遅れた、という事実が、それより先に存在するよ」
「そっか」
「うん、そうだ」
「それなら、出さない、かもしれない」
「出すかもしれないし、出さないかもしれないから、断定的な答えじゃないと、駄目だよ」
「じゃあ、出さない」
「本当に?」
「うん」
「どうして?」
「遅れた、という事実が、先にある、という君の意見を聞いて、なるほど、と、思ったから」
「思ったの?」
「思ったよ」
「思う、というのは、意識的か、それとも、無意識か、どっちだと思う?」
「どっちだと思う、という質問の、思うは、意識的か、無意識か、どっちだと、思う?」
真昼は月夜を見る。
「それ、おかしなことになるよ」
「うん。仕方がない、と思う」
「その、思うというのは……」
「うん」
「いや」
「何?」
「なんでもないよ」
「分かった」
二十分ほど電車に乗り続けて、二人はホームに降り立った。そのとき、真昼になんの躊躇いもなく手を握られて、月夜はびっくりした。けれど、それが表情として顔に出ることはない。彼女の感情や感覚は、すべて一律で無表情で処理される。もちろん、その許容範囲を越えれば、感情が顔に出ることもある。それにしても、自分は、今までの人生で、心の底から笑ったことも、泣いたことも、怒ったこともないのではないか、と月夜は思った。そう思いたいだけかもしれない。いずれにせよ、彼女が感情を表に出すのに消極的なことに変わりはない。それでも、真昼に笑ってほしいと言われれば、躊躇せずに笑うことくらいはできた。
改札を出ると都市が広がっていて、二人が住んでいる地域に比べれば、恒常的に活気があるように見える。日中でも街を人が歩いていて、自動車が走る音もあちこちから聞こえてきた。ただし、動物の鳴き声は聞こえない。人間も動物だが、そこに人間は含まれない。それは、どうしてだろう? 多くの場合、人間は、自分たちとほかの動物を区別したがる。そうしないと生きていけないのかもしれない。月夜は、あまり食事をしないが、それには、ほかの動物を食べなくてはならない、ということも関係していた。できるなら、彼女は動物の肉を食べたくない。そこに合理的な理由があるわけではないが、だからといって、ただの「嫌だ」という感情に起因して、そのように考えているわけでもない。そう、「考えている」のだから、少なくともそれは意識的だ。その点については、月夜はまだ自分のことを理解できていない、といえる。残された人生は、限りあるものだが、それまでに、少しずつでも、自分に関することが明らかになれば良いな、と彼女は考えていた。
都市の裏通りに、小さな公園があった。
真昼は、その中へ、迷わず足を踏み入れていく。
月夜は黙って彼のあとをついていった。
背の高いビルが周囲に建っているが、この公園は、そんな環境から孤立しているように感じられた。ブランコの塗装は剥げかけ、至る所から雑草が顔を出している。そして、何より、誰も遊んでいなかった。時間帯も関係しているかもしれないが、もし、普段から利用者がいるのなら、こんな閑散とした雰囲気にはならない。それに、地面から雑草が生えているということは、長い間、その地面が誰にも踏まれていない、ということを示している。
真昼がベンチに座ったから、月夜も彼の隣に腰かけた。というよりも、手を繋いでいるから、そうするしかない。
とても静かだ。
音は聞こえるのに、静かだ、と感じる。
「少し、休憩しよう」真昼が言った。「慣れない旅だから、もしかすると、これから、もっとエネルギーを消費するかもしれない。君は、不必要にエネルギーを消費するのは嫌いだろう?」
月夜は頷く。
「うん」
「お腹、空いた?」
「いや、空いてない」
「そう……。……風が心地いいね」
「風は、今は吹いていない」
月夜に言われて、真昼は初めてそれに気がついた。彼は苦い表情をして、月夜の瞳を見つめる。
いつも通り、そこには、彼女に特有な冷徹さがあった。
「うん、そうか……。僕は、今、ちょっと、頭が回っていないみたいだ」
「ちょっと、というのは、どれくらいのことを、言っているの?」
「君は回っているみたいだね」
「歩くのをやめても、地球は回っている」
「それは、生きている間に、できる限り活動した方がいい、ということ?」
「うーん……。活動しなくても、幸せは、掴めるかもしれない」
「やけに面白いことを言うね」
「そうかな」
「うん、そんな感じがするよ」
「ここに、私を連れてきたのは、どうして?」
月夜はいきなり質問した。
如何なる前兆も示さずに、突然質問することで、自分の本気度を伝えられる、と月夜は考えている。相手のことを気遣って前振りを設けるのも良いが、比較的親しい間柄では、それは却って逆効果になる可能性が高い。
「今、それを訊くんだね」案の定、真昼にそう言われた。
「タイミング、間違えた?」
「いや、僕も、君なら、そろそろ訊いてくるかな、と思っていたんだ」真昼は薄く笑う。「今まで訊かないでくれて、ありがとう」
月夜は首を傾げてそれに応じる。
真昼は、愛おしそうに彼女の顔を見つめた。
「僕が今から話すことを、信じなくても、いい、とだけ伝えておくよ」真昼は話す。「でも、君なら、きっと信じてくれるんだろうな……。……君は、疑う必要がなければ、疑わない。そして、僕は、君に疑われるような人間ではない、と自負している」
「うん。そうだよ」
「僕は、もう、あの学校には行かない」
風が吹いて、ブランコがきいきいと音を立てた。
「どうして?」
「どうしてだと思う?」
真昼に尋ねられたから、月夜は黙って考える。訊かれた質問には、きちんと考えてから答えなくてはならない。それが、月夜が掲げるポリシーだった。しかし、彼女は自分ではそのポリシーを認識していない。処世術みたいなもので、後天的に会得されたものだった。
「どこかに、引っ越す、ということ?」
やがて、月夜は、導出された最も合理的な考えを口にする。
「うん、そう」真昼は頷いた。「その通り、正解だよ」
「本当に?」
「うん、本当」
「そっか」
「もしかして、予想していた?」
「予想は、していなかった」月夜は話す。「でも、それなら、また会えるんだね」
月夜がそう言った瞬間、真昼は、身を乗り出して、彼女の手を握ったまま、月夜を抱きしめた。
時間が停止する。
呼吸と、拍動。
その二つしか、この空間に存在していない。
「……何?」
「なんでもない。少し、いいかな?」
「……うん……」
髪の香り。
身体の温かみ。
それらは、物質が存在することで生じる幻想だ。
でも、二人とも、その幻想を、綺麗だ、と思った。
綺麗だから、それで良い。
それ以上である必要はない。
ただただ、綺麗。
何もかも、綺麗。
綺麗、綺麗、綺麗。
言葉を発さず、抱きしめるだけで良いから、無駄なエネルギーを消費しなくて、綺麗だった。
「どうして、私を、ここに連れてきたの?」
抱きしめられたまま、月夜はニュアンスを変えて質問した。
真昼は月夜を離し、ベンチから立ち上がる。
「ここが、僕が次に住む街だからだよ」真昼は辺りを見渡した。「けっこう都会だけど、まあ、悪くはないね。田舎も、都会も、それぞれいいところがあるから、どっちがいいか、なんて決められないよ」
「じゃあ、本当に、そんなに離れるわけではないから、よかった」
「うん、まあね」
「それで、どうして、私をここに連れてきたの?」
「どう、というのは、どういう意味?」
「口頭で伝えるだけじゃ駄目だったの?」
「うーん、そうだけど、なんていうのか、ほら、やっぱり、現物を見てもらった方がいいかな、と思って……」
「いい、というのは?」
「その方が、臨場感があるだろう?」
「ごめん、よく分からない」
「分かる必要はないよ。とにかく、それで僕は満足したから、よかったね、と思ってくれればいいよ」
「分かった。よかったね」
「うん、よかった」
暫くその公園に滞在した。
真昼の話によると、彼は、もう、引っ越し先で、どの学校に通うか決まっているみたいだった。高等学校だから、どのような手続きを踏めば入学できるのか、月夜は知らなかったが、その点については真昼も説明しなかった。とりあえず、入学できるのだから、それで良い、と月夜は思う。高校は義務教育ではないが、はっきりいって中学校とあまり変わらない。やっていることもほとんど同じだし、むしろ、違うところを述べよ、と言われた方が困る。そうすると、やはり、義務教育か否か、あるいは、高等か中等か、というのが答えになるが、それでは名称が違うだけで、答えになっていないに等しい。やっていることが変わらないのだから、やはり何も変わらない。
「さて……。じゃあ、僕の要件は終えたから、少し、辺りを散策しよう」
月夜は真昼を見る。
「散策、というのは、具体的に、どういう行為なの?」
「え? うーん、なんだろう……。特に目的を持っているわけではないけど、何かしら面白いものを見つけたい、という意思を念頭に、気の赴くまま歩くこと、じゃないかな」
「散歩、との違いは?」
「散歩は、歩くことがメインだけど、散策は、歩くことではなく、新しい発見をすることがメインじゃないかな、と僕は思うよ」
「君以外には、思えないよ」
「それ、どういう意味?」
「意味は、ない」
「歩ける?」
「うん」月夜は立ち上がる。「でも、疲れる」
「それはそうだよ。生きているんだから」
「君は、疲れても、平気?」
「平気じゃないけど、ある程度なら耐えられるよ。君は、疲れるのは、嫌いなの?」
「嫌いだよ」
「随分とストレートな答えだね」
「ストレートではない答え、とは?」
「婉曲表現を使う、とかじゃないかな」
「具体的には?」
「歩きながら話すよ」
真昼が歩き始めたから、月夜も彼に続いた。もう一度、手を繋ぐ。熱の変換が行われた。
「たとえば、考えておこう、というのが、代表的な婉曲表現だね」真昼は言った。「考えておこう、というのは、言葉としては、まだ結論が出ていないから、後々答える、という意味だけど、個人的には、そんなことって、ほとんどないと思うんだ。何かを尋ねられたら、もう、その瞬間に、だいたいの答えは決まっている。だから、考えておこう、と答えるのは、答えが出ているけど、それを今は口にしたくない、という意思の表れなんだ。問題を今解決しないで、先延ばしにしている。それが、いいことなのか、よくないことなのかは、僕には分からない。ときどき、先延ばしにしたくなることもあるから、それなら、それでも、いいと思う。でも、中には、そういうことを認めてくれない人もいるから、困ったものだよね」
「困るの?」
「困る」
「どう困るの?」
「うーん、あまり困らないけど」
「困るんじゃないの?」
「うん、困る」
「困るの?」
「困らない」
これ以上は無駄なやり取りになると判断して、月夜は口を閉じた。
裏通りから大通りに出ると、大勢の車と人に遭遇する。ビルも高層のものが多くて、二人が通っている学校がある辺りとは、様子がまるで違っていた。でも、空気が汚いとは思わない。空気が汚いというのは、人間にとって必要のない物質が多く含まれている、ということだが、それでは、そもそも、空気には窒素が最も多く含まれているのだから、どこに行っても汚いじゃないか、ともいえる。当然、これは、言葉遊びだ。あまり面白くないかもしれない。
駅前の広場に戻って、近くにあった移動式のクレープ屋で、クレープを買った。しかし、買ったのは真昼一人だけだ。月夜は、やはり、必要以上に食事をしない。飲み物も飲まないから、燃費が非常に良い。それでいて、学校の勉強はよくできるし、瞬時に合理的な判断をすることもできるから、いったい、そんなことを可能にする燃焼機関と演算装置が、本当に存在するのか、と真昼はいつも不思議に思う。彼は、バナナとカスタードクリームが入ったクレープを買った。生地も含めて、すべて炭水化物、つまり糖類だから、これ以上ないくらいエネルギーで溢れている。
花壇の淵に座って、真昼は糖分を補給する。月夜もその隣に座った。
「ときどき、遊びに来てよ。僕も、暇があれば行くから」真昼が話す。
「うん」月夜は頷いた。
「ときどきとは、どれくらいか、と訊かないの?」
「今は、訊かないことにした」
「どうして?」
「君が、クレープを食べているから」
「食べていると、どうして、訊かないの?」
「話すのが大変で、食べる速度が落ちるから、かな」
「なるほど。でもね、僕は、ものを食べながら、話ができるんだ」
「どうやって?」
「それに答えるには、人の会話とは、どこまでを会話と呼ぶのか、を定義する必要があるね」
「必要は、ない、と思う」
「そう? まあ、そうかな……」
「クレープ、美味しい?」
「美味しいよ。一口食べる?」
「いらない」
「そう言うと思ったよ」
「じゃあ、どうして尋ねたの?」
「その方が、いいかな、と思って」真昼は呟く。「キスもできるし」
「キスが、したいの?」
「いや、あまり」
「そう」
「それは、落ち込んでいるのかな?」
「どうして、落ち込む必要があるの?」
「必要は、ないかもしれないね」
「うん。ないと思う」
「空が綺麗だ」
「空は、どんなときも、綺麗だよ」
「曇っていても?」
「太陽光線を、地球に必要な分だけ届けてくれるから、無駄がなくて、綺麗」
「その、綺麗、の定義だけど、いい加減、やめた方がいいんじゃない?」
「どうして?」
「いや、僕は大変気に入っているんだけど、ほかの人に言うと、あまりよく思われないんじゃないかな、と思ってさ」
「ほかの人に、よく思われる必要は、ある?」
「きっと、ある」
「いつ?」
「いつでも」
「どうして?」
「理由はない」
「そっか」
「でも、関係は、悪いよりは、いい方がいいだろう?」
「そんな、気が、するだけ」
「そうかな……」
「関係に、いいも、悪いも、ないよ」
「そう?」
「うん……」
「僕と、君の関係は?」
「良好」
「なんだ。じゃあ、いいんじゃないか」
「そんな気がするだけ」
「悲観的だね、君って」
「君は、楽観的?」
「比較的、そうだと思うよ。ああ、比較的、というのは、君に比べたら、という意味だけど」
「たしかに、そうかも」
「でも、悲観的でも、楽観的でも、事実は変わらないね」
二人がどのように捉えても、暫くの間、互いに会いにくくなることに変わりはない。
月夜は真昼の肩に自分の頭を預けた。
そのまま、魂も預けて良い気がする。
いや、良いだろう。
彼になら、殺されても良い。
まだ昼を迎えたばかりだった。
一日がまだ半分も残っている。
「何をしたい?」真昼が質問する。
「何も、したくないことを、したい」月夜は答えた。「ずっと、このまま」
真昼は答えない。
それは、声に出す必要がないから、綺麗だった。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

独身寮のふるさとごはん まかないさんの美味しい献立
水縞しま
ライト文芸
旧題:独身寮のまかないさん ~おいしい故郷の味こしらえます~
第7回ライト文芸大賞【料理・グルメ賞】作品です。
◇◇◇◇
飛騨高山に本社を置く株式会社ワカミヤの独身寮『杉野館』。まかない担当として働く有村千影(ありむらちかげ)は、決まった予算の中で献立を考え、食材を調達し、調理してと日々奮闘していた。そんなある日、社員のひとりが失恋して落ち込んでしまう。食欲もないらしい。千影は彼の出身地、富山の郷土料理「ほたるいかの酢味噌和え」をこしらえて励まそうとする。
仕事に追われる社員には、熱々がおいしい「味噌煮込みうどん(愛知)」。
退職しようか思い悩む社員には、じんわりと出汁が沁みる「聖護院かぶと鯛の煮物(京都)」。
他にも飛騨高山の「赤かぶ漬け」「みだらしだんご」、大阪の「モダン焼き」など、故郷の味が盛りだくさん。
おいしい故郷の味に励まされたり、癒されたり、背中を押されたりするお話です。

群青のアトリエ
如月芳美
ライト文芸
注意欠陥・多動性障害(ADHD)に悩む瑠璃(るり)は、中学二年で不登校になってから約二年の間、近くの図書館で絵を描いて過ごしていた。
そこで出会った一人の男性。
今まで会った事の無いタイプの彼に彼女は強く惹かれ、彼のアトリエに出入りするようになるが、そこにはもう一人出入りする同い年の男の子がいた。
素敵な大人の男性と、憎たらしいけど少し気になる男の子。
ADHDの彼女をきちんと受け止めてくれた二人との関係は――。
※作品内に出てくるコンテスト、美術館等は全て架空のものです。
※ADHDのキャラが出てきますが、ADHDの方が全てこういう特性というわけではありません。『ADHDの中の一つの型』をピックアップしています。
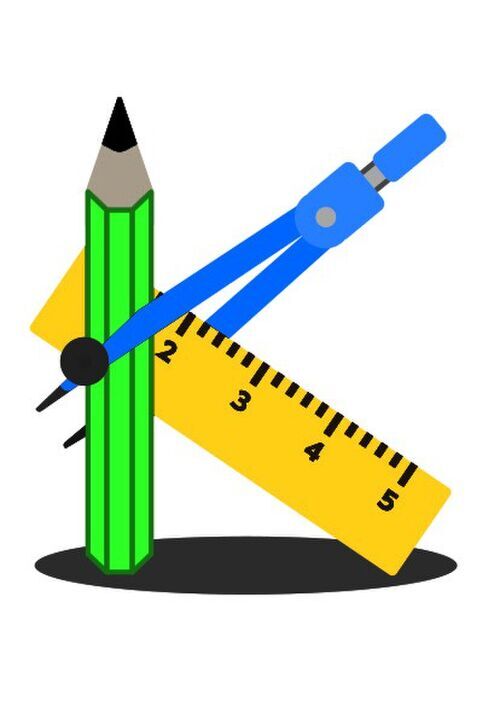
舞台装置は闇の中
羽上帆樽
ライト文芸
暗闇月夜は高校生になった。ここから彼女の物語は始まる。
行く先は不明。ただし、時間は常に人間の隣にあるが故に、進行を妨げることはできない。
毎日1000文字ずつ更新します。いつまで続くか分かりません。
終わりが不明瞭であるため、どこから入ってもらっても構いません。

会社の上司の妻との禁断の関係に溺れた男の物語
六角
恋愛
日本の大都市で働くサラリーマンが、偶然出会った上司の妻に一目惚れしてしまう。彼女に強く引き寄せられるように、彼女との禁断の関係に溺れていく。しかし、会社に知られてしまい、別れを余儀なくされる。彼女との別れに苦しみ、彼女を忘れることができずにいる。彼女との関係は、運命的なものであり、彼女との愛は一生忘れることができない。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















