1 / 10
第1章 光
しおりを挟む
暗闇月夜は、その日家に帰らなかった。
閑散とした学校の教室で、彼女は自分の席に座り、黙って本を読んでいる。黒板が生み出す暗黒が室内に充満し、窓の外から差し込む月明かりはスポットライト、規則正しく整列した机は生物を形作る細胞を連想させ、この空間を独立した場所として際立たせている。音がなければ空気もない。いや、もちろん空気は存在するが、彼女が呼吸をしても、取り込まれる酸素と、吐き出される二酸化炭素の量が均一である限り、存在しないのと同じことになる。とにかく、広がりゆく暗黒の世界で、彼女は長い間一人だった。
彼女が家に帰らない理由は特にない。家に帰っても誰もいないから、このまま学校に残っていよう、といった至極簡単な決定を行ったにすぎない。そんな簡単な決定をするのにも、しかし、やはり、最初の内はそれなりの度胸を必要とする。彼女が家に帰らないのは初めてではなかったが、それでも、こんな時間に学校に一人でいる、といった状況は、想像以上にスリリング、そして、想像していた通りにエキサイティングだった。
窓は開いている。できた隙間から夜の冷たい風が室内に吹き込んで、押さえている本のページをぱらぱらと靡かせた。本を読むとき、彼女は栞を使わない。たとえどこまで読んだか忘れてしまっても、それなら、過去に読んだ部分を、一度も読んだことがないと思い込んで、もう一度読み返すだけだ。こういうことができる人間は、しかし以外と少ないらしい。そういった意味では、彼女は特異な存在だったし、言い方を変えれば、通常ではないという意味で異常だった。
読んでいた本を閉じ、彼女は軽く伸びをする。澄んだ瞳は月明かりを反射し、今は半透明に輝いていた。青白い光を宿すその瞳は、見るものに冷徹な印象を植えつける。その内側に微かながら確かな暖かさを見出だせる者は、今のところ、彼女以外には一人しかいなかった。
その一人が、教室の扉を明けて、彼女のもとへやって来る。
月夜は顔をそちらに向けて、彼と同じタイミングで挨拶をした。
「やあ」
「うん」
挨拶というものは、しなくても良いと言えば、たしかにする必要はない。してもしなくても意思の疎通はできる。そもそも、何が挨拶か、というのは人によって違っている。片手を上げたり、ちょっとした声を発したり、頷いたり、そうした行為が挨拶として通る人間も存在する。彼女の場合、それは「うん」という簡単な言葉で、これ以上ないくらい簡略化された情報発信だった。
月夜のもとにやって来た少年は、彼女の隣の席に腰を下ろす。
「今日も一人?」彼が尋ねた。
「うん」月夜はそれに応じる。顔は彼の方を向いて、冷徹さを帯びた瞳が彼の目を射抜いた。
「君は、一人が好き? それとも、誰かといる方が良い?」
「どちらかというと、一人」月夜は説明する。「でも、一緒にいるのが君なら、いい」
少年は彼女が読んでいた本を手に取り、表紙を眺める。本は新品同様に綺麗で、事実その通り新品だった。けれど、彼女が本を購入した時点で、それは新品ではなくなる。この理屈は、ほかの事象にも通ることが多い。境界線ははっきりとは存在しない。数学の授業で境界条件の示し方を習ったから、月夜は、数学と、ありとあらゆる事象が、根本的な部分で繋がっていることを理解した。
「へえ、古典か」少年が呟く。「君は、古典、という柄には見えないけど」
「そう?」
「うん、そう。どちらかというと、ミステリー、あるいは、SFという感じだね、僕の中では」
「ミステリーは、筆者本人が楽しめる作品で、SFは、誰もが楽しめる作品だと思う」
「どういう意味?」
「そのままの意味」
「じゃあ、古典は?」
「古典は、時代を超えて楽しめる作品」
「まあ、そうだね」少年は何かを思いついたような顔をし、人差し指を立てる。「あ、じゃあ、君は、もし過去に戻れるとしたら、どの時代に戻りたい?」
「どうして、そんなことを訊くの?」
「なんとなく、思いついたからだよ」
「私は、小学生の頃に戻りたい」
「それは、時代とは言わない気がするけど」
「うん……。……時代なら、奈良時代、かな」
「どうして、その時代がいいの?」
「ごめんなさい、適当に言った」月夜は本当に申し訳なさそうな顔をする。「もう少し、考えてから答えればよかった」
「いや、もとの質問が適当だったから、適当に答えるのは、適当だよ」
「そうかな?」
「うん、そう」少年は笑う。「君さ、今の冗談、通じてる?」
「うん」
「面白かった?」
「うん、面白かったよ」
「じゃあ、少しは笑ったら?」
「……私、今、笑っていなかった?」
「笑っていない」少年は言った。「でも、それでいいよ」
月夜は、余程のことがない限り笑わない。面白いことがあっても、楽しいことがあっても、すべて一律で無表情で処理される。だから、彼女の冷徹さはより一層引き立てられることになる。その中に暖かさを見つけるには、それ相応の技術が必要になる。技術も、技能も、練習すればすべて身につく。問題は、練習する覚悟が自分にあるか、ということだ。
学校という場所は、夜になると化物の巣窟になる。そんな怪談話を聞いて、友達と一緒に夜の学校に忍び込んだことがあったな、と月夜は昔のことを思い出した。確か小学生のときのことだった。彼女の方から言い出したのではない。多くの場合、月夜は自ら提案をしない。そのときも友達に誘われて、断る理由がなかったから付き合った、というだけだった。無責任といえばそうかもしれないが、彼女が友達についていっても、それで迷惑を被る人間は誰もいない。そのときから彼女は一人だったし、両親の代わりになる人間は誰もいなかったから、もしかすると、そんな寂しさを紛らわすために、友達の誘いに乗ったのかもしれない。
「とても静かだ」
少年は椅子から立ち上がり、教室の中を歩き回る。自主的な行動が少ない月夜とは対象的に、彼は割とひっきりなしに動く。それが自分の使命だとでもいうように活動するから、月夜は彼が不思議だった。そんな彼の行動を見ても、彼女がそれを止めようと思うことはない。そもそも、止める必要がない。余程危ないことをしない限りは、自分が彼に干渉する必要はない、というのが彼女の基本的なスタンスだった。
「君は、明日はどうするつもり?」窓の傍に置いてある花瓶を手に取って、少年が質問した。
「どうって、どういう意味?」
「今日は家に帰らないで、明日はどうやって、学校で生活をするの?」
「まだ、零時を迎えていないから、なんとかなると思うよ」
「じゃあ、やっぱり一度家に帰るの?」
「うん」
「そう……。それなら、どうやって校門の外に出るか、考えておかないとね」
「たしか、裏口が開いているから、大丈夫」
「裏口? どうして、開いているの? もともと、鍵がかかっていない、とか?」
「分からないけど、いつも開いている」
「心当たりは?」
「心当たりは、ない」月夜は答える。「何か分かったら、君に教えるね」
「いや、いいよ、別に」
「……どうして?」
「気になるわけではないんだ。ちょっと、話がそういう流れだったから、訊いてみようかな、と思っただけで」
「そういう流れって、どういう流れ?」
「君に尋ねた方がいいかなと思った、ということ」
「うん」
「それでよかった?」
「うーん、分からない」
「分かる必要はないよ」
「うん」
「君は、花は好き?」少年は花瓶から水仙を一本引き抜く。
「どちらかといえば、好きだと思う」
「具体的に、どんなところが?」
「花は、どれも綺麗だから、綺麗なものは、好き」
「君の、綺麗、の基準は?」
「基準って?」
「どういう条件が揃ったら、綺麗と感じるか、というデータ」
「それは、考えたことがないから、分からない」
「じゃあ、ちょっと考えてみてよ」
「どうして?」
「気になるから」
少年がそう言うと、月夜は冷徹な視線を彼に向けて、一度頷いた。
「分かった」
彼は満足そうに笑い、窓の外に顔を向ける。
当然、今、この学校には彼らしかいない。反対にいえば、二人がいるだけで充分だった。この世界に存在するものは、過密にも、過疎にも、そのどちらの状態にもならない。自然と淘汰され、必然的な量としてそこに存在する。だから、彼も、彼女も、今この場所に存在するべく存在する、と考えることもできる。ただし、どのように考えても、それで事実が変わるわけではない、ということを留意しておく必要がある。考えるのは人間の特権だが、どのように考えても、世界そのものが変わることはない。
窓の外に街の明かりは見えなかった。近くに人が住んでいないからだ。ここから歩いて帰るとなれば、多少なりとも時間がかかる。月夜は、毎日電車に乗ってここに来ていた。けれど、歩いて帰ることもできなくはない。少年は、いつも月夜を送ったあと、そのままどこかへと消えていく。だから、もしかすると、彼はどこにも住んでいないのかもしれない。宇宙は広いから、彼が地球に住んでいる確証はない。そんなふうに考えられるのも、このファンタジックな空気感があってこそだ、と月夜は考える。
「うん、分かった」
暫くして、月夜は彼の質問に対する答えが出たから、呟いた。
「私に利益を与える可能性があるものは、すべて、綺麗だと感じる」
少年は彼女を見る。
「じゃあ、君にとってプラスになるものは、全部綺麗なんだね?」
「うん、そう」
「僕は、綺麗?」
「うん、綺麗だよ」
「君にとって、利益になる?」
「うん、なる」
「どんな?」
「一緒にいると、楽しい」
「本当に?」
「本当」
「どれくらい楽しいの?」
「どれくらいというのは、どんな単位を使って表現したらいい?」
「うーん、色々あるけど、ノット、が一番適切かな」
「一ノットは、どれくらい?」
「さあね、僕には分からない」
「それじゃあ、上手く説明できないよ」
「うん、それでも、やってみるから、面白くなるんじゃないか」
「君は面白いの?」
「面白いね、とても。君は?」
「面白いよ。そして、楽しい」
「で、僕の価値は何ノットくらい?」
「たぶん、五・二ノットくらいだと思う」
「へえ、どうして?」
「なんとなく、そう思った」
「なるほど」
「面白かった?」
「うん、まあ」
「まあというのは、どれくらい?」
「三ノットくらいかな」
「そう、分かった」
「分からないよ、全然」
二人が口を閉じると、途端に静寂が辺りを支配するようになる。静寂とは、何も聞こえないという意味ではない。音は確かに存在する。それらの音は確固とした意味を持たないから、意味を認識する人間にとっては、何も聞こえないのと同等になる。
月夜は再び本を手に取り、ページを捲って読書を再開した。自分がどこまで読んだのか覚えていなくても、物語はどこを読んでも面白い。自分ではない誰かの人生を謎る行為は、時空を超えるみたいで、自分がどこにいるのかさえ分からなくなる。もしかすると、自分はどこにもいないのかもしれない。それでも、少年が彼女を認識してくれるから、そうやって他人から把握されて、初めて自分が存在するのが分かる。人間は一人では生きていけないというのは、おそらくはそういう意味だろう。人間は、自分一人しか存在しないのなら、自分を把握することすらできない脆弱な思考力しか持っていない。
「もう少し、君のことが知りたいな」教室の後方に移動していた少年が、沈黙を破って彼女に質問した。
月夜は本を持ったまま、顔だけを後ろに向けて、彼の姿を捉える。
「私?」
「うん、そう」
「具体的に、どんなことが知りたいの? それと、もう少し、というのはどれくらい?」
「最初に具体的な内容を決めないで、ランダムに物事を知りたいんだ。それから、もう少しというのは謙遜だから、あまり気にしなくていいよ」
「あまり、というのは、どれくらい?」
「それも気にしなくていい」少年は笑う。「僕が量的な言葉を使っても、君が気にする必要はない、と伝えておくよ」
「分かった」
「じゃあ、まずは……。君は、どんなタイプの人が好みなの?」
月夜は読んでいた本をまた閉じて、それを机の上に置く。
「それは、どういう意味?」
「うん、つまりね」少年は手近な席に座った。「君の恋愛感覚について尋ねているんだ」
「恋愛と、親交は、何が違うの?」
「恋愛は、生物学的にいえば、よりよい個体を残せそうだ、と遺伝子が判断した者に向けられる感情と、それに基づく関係。そして、親交は、自分に楽しみを与えてくれる者に対して向けられる感情と、その関係のこと」
「じゃあ、恋愛も、親交も、綺麗?」
「たしかに、そうかもしれない」
「君はどんな人が好きなの?」
「僕? 実は、僕は、なかなか他人を好きになれないんだ」
「どうして?」
「自分が嫌いだから」
「自分が嫌いだと、どうして他人を好きになれないの?」
「物事は、すべて、まず自分に起こり、次に他人へと向かうからだよ」少年は言った。「たとえば、自分でルールを守れなければ、他人にそれを強要することはできない。それと同じ。まずは自分を攻略し、次に他人の攻略に挑戦する。自分を攻略できなければ、他人に挑戦することはできない。だから、自分を好きになれない僕は、そこで足止めを食らって、次の段階に進めないんだ」
「それは、理屈? それとも、言い訳?」
「なかなか鋭い質問だね」
「どっち?」
「うん、たぶん、言い訳」
「うん、私もそう思う」
「君ってさ、裏表がないよね」
「裏と、表?」
「そう……。つまり、人を選ばない、ということ。それはいいことかもしれないけど、自分を危険に晒すこともあるから、気をつけた方がいいよ」
「うん」
「で、君は、どんなタイプの人が好きなの?」
「私は、とりあえず、君が好き」
「とりあえず、というのは?」予想外の答えで、少年は思わず笑ってしまった。
「君がしてくれた説明と照らし合わせて、自分にとって相応しい回答を考えたら、そうなった」
「今のところ、僕は好きだ、ということ?」
「そう」
「それは、なんていうのか、まあ、嬉しいよ」
「誰が?」
「僕が」
「私も、嬉しい」
「へえ、どうして?」
「君が、嬉しいから」
「その感情は、綺麗?」
「結果的に私も嬉しくなって、それは私の利益になるから、綺麗」
「その台詞、ほかの人には言わない方がいいよ」
「……どうして?」
「僕以外の人間には、通用しないと思うから」
「それは、何を根拠に言っているの?」
「根拠はない。けれど、なんとなくそんな気がする。僕は、心が狭いから、すぐに諦める癖がある。君がそういう性格をしていても、ふーん、と思うだけで終わってしまう。気に食わなかったり、気に入らなかったりしても、なんとなく受け流せる、ということ」
「うん」
「だから、君のその言葉にも、ちゃんと好意が含まれているんだな、と勝手に解釈した」
「そう……」
「……もしかして、傷つけてしまった?」
「え、なんで?」
「いや、寂しそうな顔をしているな、と思ってさ」
「そう?」月夜は自分の頬に触れる。
「いや、それは違うか」彼は言った。「君は、いつもそんな顔だったね」
天井のどこかで回る換気扇が、この部屋の空気を撹拌している。プロペラが回転する度に過去が消去されて、数秒先の未来が作り出される。そんな奇妙な連想をしている間にも、時間は確実に過ぎ去り、気づいたときには自分はすでにそこにいない。月夜は、そんな訳の分からない連想をすることがあった。自分で考えたいと思っているわけではなくても、自然とそういったことを考えてしまう。だから、無意識の内に、彼女の中の誰かが、そんな思考を望んでいるのかもしれない。
それでは、その発想は何のためにするのだろう?
彼女には分からなかった。
月夜は椅子から立ち上がり、背凭れにかけてあったリュックを背負う。
「もう、帰るの?」彼女の様子を見て、少年が質問した。
「うん、帰る」
「じゃあ、送っていくよ」
「うん」
「忘れ物はない?」
「たぶん、忘れて困るようなものは、ない」
少年は笑った。
教室の扉を開けて、リノリウムの廊下を歩く。細かい穴がいくつも開いた天井がずっと向こうまで続いていて、非常灯が二人をその先へと誘った。消火栓の赤いランプと、水道から漏れ出る水の音を頼りに、二人は昇降口へと向かっていく。廊下にある窓はすべて鍵がかかっていたが、その向こう側に広がる空は、すぐにそこにあるように感じられた。
昇降口で外靴に履き替えて、裏口を目指す。ビオトープに棲む蛙が、何かを呼ぶように鳴いていた。
月夜が言った通り、裏口に鍵はかかっていない。監視カメラもないから、誰も二人の姿を捕捉することはできない。
それでも、木菟だけは、きっと彼らを捉えている。
街灯もない夜道を、二人は並んで歩いた。
「君は、どうして学校に来ているの?」
歩き始めて数分してから、少年が月夜に尋ねた。
「学校で勉強するのは、権利だから」彼女は話す。「権利は、正しく使う必要がある、と聞いたことがある」
「うん、それはそうだね」
「君は、どうして?」
「え?」
「どうして、学校に来ているの?」
「さあ、どうしてかな」
「理由もないのに、来ているの?」
「そうかもしれない」
「学校は楽しい?」
「うん、まあね」
「どこが、一番楽しい?」
「それは、場所を訊いているの? それとも、何が楽しいか、という質問?」
「どっちも」
「場所は教室で、楽しいのは、下校しているときかな」
「下校は、今してるよ」
「そう。君と帰るのは、それなりに面白いんだ」彼は言った。「でも、それは、日中に学校に通っているからだよ。もし下校だけ独立して取り出すことができても、きっとそこに面白さはない。過程が大事だということだね。何事もそうかもしれない。人生だって、ただ死ぬだけではつまらない。ずっと生きてきたから、死ぬときにそれなりに納得することができるんだ」
「君は、いつかは死にたい?」
「うん、いつかはね」
「どんなふうに死にたい?」
「君は?」
「私は、一人で死にたい」
少年は黙った。
自動車が通らないから、二人が黙れば辺りは静かになる。
月が二人を見下ろしていた。
「……どうして、一人で死にたいの?」彼は尋ねる。
「一人の方が、寂しくないから、だと思う」
「どういう意味?」
「周りに誰かがいたら、その人が、悲しい思いをするかもしれない、と気を遣わなくてはならなくなる、という意味」
「それが、寂しいの?」
「うん、寂しい」
「人が寂しさを感じるのは、どうしてだろう?」
月夜は黙って考える。
涼しい風が二人の間を通り抜けた。
「自分にとって損失になるから、感覚的に辛い思いをすることで、死を未然に防ぐためだと思う」彼女は言った。「自分にとって不利益だから、綺麗じゃない、ということ」
「でも、寂しいのは、綺麗だよ」
「そう?」
「そうさ」
「君は、寂しいは、綺麗、と感じるの?」
「うん、感じるよ」
「そっか」
「君は感じないの?」
「うん、感じる」
「それじゃあ、君が言った『綺麗』の定義は、もう一度考え直さないといけないね」
「そうかも」
「がっかりした?」
「何が?」
「自分の定義が、批判されて」
「いや、あまり」
「じゃあ、少しはしたんだね」
「がっかりはしてないけど、不利益でもないから、それでよかった」
「それって、どれのこと?」
「うーん、分からない。もう、眠くて、あまり頭が回らない」
「そう。じゃあ、すぐに寝るといいよ。歩きながらでも、眠れないことはないから」
「君は、歩きながら眠れるの?」
「眠ろうと思えば、いつでも眠れる」
「私は、眠ろうと思ったことがないよ」
「いつも、自然と眠ってしまう、ということ?」
「そんな感じ」
「いいね。眠る努力をしないでも眠れるのは、エネルギーの消費が最小限で、綺麗だ」
「綺麗?」
「うん」
「私と、睡眠は、どっちが綺麗?」
「どっちも」
「どちらかだったら、どっち?」
「睡眠」
いつも電車で帰る道を歩いて通るから、普段とは違う発見がある。けれど、それほど長い旅程というわけでもないから、家にはすぐに到着する。電車を使った方が便利だというだけで、決して歩けない距離ではなかった。それに、新しい発見があるといっても、電車で移動するときと視点が違うだけで、歩いて帰ったことも何度かあるから、完全に新鮮な気持ちにはなれない。今日みたいに夜に下校することもあったから、どちらかというと、久し振り、といった方が正しかった。
少年が歩く速度も、月夜が歩く速度も、もともと大して変わらない。だから、お互いに余計な労力をかけなくて済む。愛情は、自分を殺して相手に尽くすことで生まれるが、できるなら、自分を殺す度合いが小さくて、相手に尽くす度合いが大きい方が良い。マイナスが少なくて、プラスが多いなら、それ以上のものはない。しかしながら、実際にはそう上手くいくことは少ない。適度にバランスをとろうとしても、必ず多少はどちらかに傾く。二人の場合、少年はどちらかというと自分勝手で、月夜は彼に対して従順だったから、少年から見ればプラス、月夜から見ればマイナスだった。
その差は、大々的に示すべきものではない。誤差の範囲内として処理できる。月夜も、彼も、自分のことが大切だったが、それと同じくらい相手のことも大切だった。少年は、自分で自分を好きになれないと言ったが、それは彼の理想が高すぎるせいかもしれない。月夜にはそれが分かっていたから、彼の説明を黙って受け入れることにした。
左右には住宅街が広がっている。街灯はすべて消えていて、不審者がいても気づかない可能性が高い。照明が機能を果たしていないのは、そういった人物が少ないからかもしれないが、それ以上に、エネルギーの消費を押さえたい、といった誰かの意思がはたらいていると考えた方が自然だ。光があれば、自然と人が集まってくる。だから、光を消せば、人はあまり集まらない。輝いているスターがいれば、誰だってその人のもとに集まりたくなるし、コンサート会場の照明が消えれば、人々は自然と駅の方へと流れる。人も、結局のところ蛾と変わらない。それが悪いという話ではなく、むしろ月夜はそんな哀れさが好きだった。
結果的に、家に着くまで一時間ほど歩き続けた。
少し疲れて、息が上がってしまった。
玄関の前で月夜が振り返り、少年に小さく挨拶をする。
「さようなら」
少年は軽く手を上げ、それに応じた。
「うん、またね」
彼が暗闇の中に消えるまで、月夜はその背中を見続ける。少年は途中で振り返り、彼女だけに聞こえる声で言った。
「そういえば、僕には名前がないから、君につけてもらおう、と思ったんだけど」
「名前?」月夜は首を傾げる。「私は、名前をつけたことがないから、ほかの人に頼んだ方がいいと思う」
「でも、君につけてもらいたいんだ」
少年の要望を聞いて、月夜は頷いた。
「分かった」
「すぐに考えられそう?」
「すぐというのは、どれくらいの時間?」
「寒いから、五分くらいでお願いできる?」
「うん、できる」
「じゃあ、少し待つよ」
「うん……」
あと五時間もすれば、二人とも再び学校に向かう。すぐに再会できるから、それまでに考えるという方法もあったが、月夜は、彼に頼まれたことは基本的に断らなかった。
二分と三十秒が経過して、月夜は答えを出すに至った。
「できた」
少年は顔を上げる。
「どんな名前になった?」
「私が月夜だから、君は真昼」
彼女の返答を聞いて、少年は笑った。
「随分と単純な名前だね」
「そう?」
「うん、そうだよ」
「じゃあ、変える?」
「いや、いいよ、そのままで」少年は頷く。「僕は、これから、真昼、でいくよ」
「変な名前で、ごめんなさい」
「大丈夫だよ、これで」
「うん」
「じゃあ、またね、月夜」
「おやすみなさい」
前を向いて、真昼は夜の街へと消えていく。
月夜は玄関を開けて、家の中に入った。
ドアが閉まる。
日の光が、地平線の下で待っていても、彼女の夜は終わらない。
閑散とした学校の教室で、彼女は自分の席に座り、黙って本を読んでいる。黒板が生み出す暗黒が室内に充満し、窓の外から差し込む月明かりはスポットライト、規則正しく整列した机は生物を形作る細胞を連想させ、この空間を独立した場所として際立たせている。音がなければ空気もない。いや、もちろん空気は存在するが、彼女が呼吸をしても、取り込まれる酸素と、吐き出される二酸化炭素の量が均一である限り、存在しないのと同じことになる。とにかく、広がりゆく暗黒の世界で、彼女は長い間一人だった。
彼女が家に帰らない理由は特にない。家に帰っても誰もいないから、このまま学校に残っていよう、といった至極簡単な決定を行ったにすぎない。そんな簡単な決定をするのにも、しかし、やはり、最初の内はそれなりの度胸を必要とする。彼女が家に帰らないのは初めてではなかったが、それでも、こんな時間に学校に一人でいる、といった状況は、想像以上にスリリング、そして、想像していた通りにエキサイティングだった。
窓は開いている。できた隙間から夜の冷たい風が室内に吹き込んで、押さえている本のページをぱらぱらと靡かせた。本を読むとき、彼女は栞を使わない。たとえどこまで読んだか忘れてしまっても、それなら、過去に読んだ部分を、一度も読んだことがないと思い込んで、もう一度読み返すだけだ。こういうことができる人間は、しかし以外と少ないらしい。そういった意味では、彼女は特異な存在だったし、言い方を変えれば、通常ではないという意味で異常だった。
読んでいた本を閉じ、彼女は軽く伸びをする。澄んだ瞳は月明かりを反射し、今は半透明に輝いていた。青白い光を宿すその瞳は、見るものに冷徹な印象を植えつける。その内側に微かながら確かな暖かさを見出だせる者は、今のところ、彼女以外には一人しかいなかった。
その一人が、教室の扉を明けて、彼女のもとへやって来る。
月夜は顔をそちらに向けて、彼と同じタイミングで挨拶をした。
「やあ」
「うん」
挨拶というものは、しなくても良いと言えば、たしかにする必要はない。してもしなくても意思の疎通はできる。そもそも、何が挨拶か、というのは人によって違っている。片手を上げたり、ちょっとした声を発したり、頷いたり、そうした行為が挨拶として通る人間も存在する。彼女の場合、それは「うん」という簡単な言葉で、これ以上ないくらい簡略化された情報発信だった。
月夜のもとにやって来た少年は、彼女の隣の席に腰を下ろす。
「今日も一人?」彼が尋ねた。
「うん」月夜はそれに応じる。顔は彼の方を向いて、冷徹さを帯びた瞳が彼の目を射抜いた。
「君は、一人が好き? それとも、誰かといる方が良い?」
「どちらかというと、一人」月夜は説明する。「でも、一緒にいるのが君なら、いい」
少年は彼女が読んでいた本を手に取り、表紙を眺める。本は新品同様に綺麗で、事実その通り新品だった。けれど、彼女が本を購入した時点で、それは新品ではなくなる。この理屈は、ほかの事象にも通ることが多い。境界線ははっきりとは存在しない。数学の授業で境界条件の示し方を習ったから、月夜は、数学と、ありとあらゆる事象が、根本的な部分で繋がっていることを理解した。
「へえ、古典か」少年が呟く。「君は、古典、という柄には見えないけど」
「そう?」
「うん、そう。どちらかというと、ミステリー、あるいは、SFという感じだね、僕の中では」
「ミステリーは、筆者本人が楽しめる作品で、SFは、誰もが楽しめる作品だと思う」
「どういう意味?」
「そのままの意味」
「じゃあ、古典は?」
「古典は、時代を超えて楽しめる作品」
「まあ、そうだね」少年は何かを思いついたような顔をし、人差し指を立てる。「あ、じゃあ、君は、もし過去に戻れるとしたら、どの時代に戻りたい?」
「どうして、そんなことを訊くの?」
「なんとなく、思いついたからだよ」
「私は、小学生の頃に戻りたい」
「それは、時代とは言わない気がするけど」
「うん……。……時代なら、奈良時代、かな」
「どうして、その時代がいいの?」
「ごめんなさい、適当に言った」月夜は本当に申し訳なさそうな顔をする。「もう少し、考えてから答えればよかった」
「いや、もとの質問が適当だったから、適当に答えるのは、適当だよ」
「そうかな?」
「うん、そう」少年は笑う。「君さ、今の冗談、通じてる?」
「うん」
「面白かった?」
「うん、面白かったよ」
「じゃあ、少しは笑ったら?」
「……私、今、笑っていなかった?」
「笑っていない」少年は言った。「でも、それでいいよ」
月夜は、余程のことがない限り笑わない。面白いことがあっても、楽しいことがあっても、すべて一律で無表情で処理される。だから、彼女の冷徹さはより一層引き立てられることになる。その中に暖かさを見つけるには、それ相応の技術が必要になる。技術も、技能も、練習すればすべて身につく。問題は、練習する覚悟が自分にあるか、ということだ。
学校という場所は、夜になると化物の巣窟になる。そんな怪談話を聞いて、友達と一緒に夜の学校に忍び込んだことがあったな、と月夜は昔のことを思い出した。確か小学生のときのことだった。彼女の方から言い出したのではない。多くの場合、月夜は自ら提案をしない。そのときも友達に誘われて、断る理由がなかったから付き合った、というだけだった。無責任といえばそうかもしれないが、彼女が友達についていっても、それで迷惑を被る人間は誰もいない。そのときから彼女は一人だったし、両親の代わりになる人間は誰もいなかったから、もしかすると、そんな寂しさを紛らわすために、友達の誘いに乗ったのかもしれない。
「とても静かだ」
少年は椅子から立ち上がり、教室の中を歩き回る。自主的な行動が少ない月夜とは対象的に、彼は割とひっきりなしに動く。それが自分の使命だとでもいうように活動するから、月夜は彼が不思議だった。そんな彼の行動を見ても、彼女がそれを止めようと思うことはない。そもそも、止める必要がない。余程危ないことをしない限りは、自分が彼に干渉する必要はない、というのが彼女の基本的なスタンスだった。
「君は、明日はどうするつもり?」窓の傍に置いてある花瓶を手に取って、少年が質問した。
「どうって、どういう意味?」
「今日は家に帰らないで、明日はどうやって、学校で生活をするの?」
「まだ、零時を迎えていないから、なんとかなると思うよ」
「じゃあ、やっぱり一度家に帰るの?」
「うん」
「そう……。それなら、どうやって校門の外に出るか、考えておかないとね」
「たしか、裏口が開いているから、大丈夫」
「裏口? どうして、開いているの? もともと、鍵がかかっていない、とか?」
「分からないけど、いつも開いている」
「心当たりは?」
「心当たりは、ない」月夜は答える。「何か分かったら、君に教えるね」
「いや、いいよ、別に」
「……どうして?」
「気になるわけではないんだ。ちょっと、話がそういう流れだったから、訊いてみようかな、と思っただけで」
「そういう流れって、どういう流れ?」
「君に尋ねた方がいいかなと思った、ということ」
「うん」
「それでよかった?」
「うーん、分からない」
「分かる必要はないよ」
「うん」
「君は、花は好き?」少年は花瓶から水仙を一本引き抜く。
「どちらかといえば、好きだと思う」
「具体的に、どんなところが?」
「花は、どれも綺麗だから、綺麗なものは、好き」
「君の、綺麗、の基準は?」
「基準って?」
「どういう条件が揃ったら、綺麗と感じるか、というデータ」
「それは、考えたことがないから、分からない」
「じゃあ、ちょっと考えてみてよ」
「どうして?」
「気になるから」
少年がそう言うと、月夜は冷徹な視線を彼に向けて、一度頷いた。
「分かった」
彼は満足そうに笑い、窓の外に顔を向ける。
当然、今、この学校には彼らしかいない。反対にいえば、二人がいるだけで充分だった。この世界に存在するものは、過密にも、過疎にも、そのどちらの状態にもならない。自然と淘汰され、必然的な量としてそこに存在する。だから、彼も、彼女も、今この場所に存在するべく存在する、と考えることもできる。ただし、どのように考えても、それで事実が変わるわけではない、ということを留意しておく必要がある。考えるのは人間の特権だが、どのように考えても、世界そのものが変わることはない。
窓の外に街の明かりは見えなかった。近くに人が住んでいないからだ。ここから歩いて帰るとなれば、多少なりとも時間がかかる。月夜は、毎日電車に乗ってここに来ていた。けれど、歩いて帰ることもできなくはない。少年は、いつも月夜を送ったあと、そのままどこかへと消えていく。だから、もしかすると、彼はどこにも住んでいないのかもしれない。宇宙は広いから、彼が地球に住んでいる確証はない。そんなふうに考えられるのも、このファンタジックな空気感があってこそだ、と月夜は考える。
「うん、分かった」
暫くして、月夜は彼の質問に対する答えが出たから、呟いた。
「私に利益を与える可能性があるものは、すべて、綺麗だと感じる」
少年は彼女を見る。
「じゃあ、君にとってプラスになるものは、全部綺麗なんだね?」
「うん、そう」
「僕は、綺麗?」
「うん、綺麗だよ」
「君にとって、利益になる?」
「うん、なる」
「どんな?」
「一緒にいると、楽しい」
「本当に?」
「本当」
「どれくらい楽しいの?」
「どれくらいというのは、どんな単位を使って表現したらいい?」
「うーん、色々あるけど、ノット、が一番適切かな」
「一ノットは、どれくらい?」
「さあね、僕には分からない」
「それじゃあ、上手く説明できないよ」
「うん、それでも、やってみるから、面白くなるんじゃないか」
「君は面白いの?」
「面白いね、とても。君は?」
「面白いよ。そして、楽しい」
「で、僕の価値は何ノットくらい?」
「たぶん、五・二ノットくらいだと思う」
「へえ、どうして?」
「なんとなく、そう思った」
「なるほど」
「面白かった?」
「うん、まあ」
「まあというのは、どれくらい?」
「三ノットくらいかな」
「そう、分かった」
「分からないよ、全然」
二人が口を閉じると、途端に静寂が辺りを支配するようになる。静寂とは、何も聞こえないという意味ではない。音は確かに存在する。それらの音は確固とした意味を持たないから、意味を認識する人間にとっては、何も聞こえないのと同等になる。
月夜は再び本を手に取り、ページを捲って読書を再開した。自分がどこまで読んだのか覚えていなくても、物語はどこを読んでも面白い。自分ではない誰かの人生を謎る行為は、時空を超えるみたいで、自分がどこにいるのかさえ分からなくなる。もしかすると、自分はどこにもいないのかもしれない。それでも、少年が彼女を認識してくれるから、そうやって他人から把握されて、初めて自分が存在するのが分かる。人間は一人では生きていけないというのは、おそらくはそういう意味だろう。人間は、自分一人しか存在しないのなら、自分を把握することすらできない脆弱な思考力しか持っていない。
「もう少し、君のことが知りたいな」教室の後方に移動していた少年が、沈黙を破って彼女に質問した。
月夜は本を持ったまま、顔だけを後ろに向けて、彼の姿を捉える。
「私?」
「うん、そう」
「具体的に、どんなことが知りたいの? それと、もう少し、というのはどれくらい?」
「最初に具体的な内容を決めないで、ランダムに物事を知りたいんだ。それから、もう少しというのは謙遜だから、あまり気にしなくていいよ」
「あまり、というのは、どれくらい?」
「それも気にしなくていい」少年は笑う。「僕が量的な言葉を使っても、君が気にする必要はない、と伝えておくよ」
「分かった」
「じゃあ、まずは……。君は、どんなタイプの人が好みなの?」
月夜は読んでいた本をまた閉じて、それを机の上に置く。
「それは、どういう意味?」
「うん、つまりね」少年は手近な席に座った。「君の恋愛感覚について尋ねているんだ」
「恋愛と、親交は、何が違うの?」
「恋愛は、生物学的にいえば、よりよい個体を残せそうだ、と遺伝子が判断した者に向けられる感情と、それに基づく関係。そして、親交は、自分に楽しみを与えてくれる者に対して向けられる感情と、その関係のこと」
「じゃあ、恋愛も、親交も、綺麗?」
「たしかに、そうかもしれない」
「君はどんな人が好きなの?」
「僕? 実は、僕は、なかなか他人を好きになれないんだ」
「どうして?」
「自分が嫌いだから」
「自分が嫌いだと、どうして他人を好きになれないの?」
「物事は、すべて、まず自分に起こり、次に他人へと向かうからだよ」少年は言った。「たとえば、自分でルールを守れなければ、他人にそれを強要することはできない。それと同じ。まずは自分を攻略し、次に他人の攻略に挑戦する。自分を攻略できなければ、他人に挑戦することはできない。だから、自分を好きになれない僕は、そこで足止めを食らって、次の段階に進めないんだ」
「それは、理屈? それとも、言い訳?」
「なかなか鋭い質問だね」
「どっち?」
「うん、たぶん、言い訳」
「うん、私もそう思う」
「君ってさ、裏表がないよね」
「裏と、表?」
「そう……。つまり、人を選ばない、ということ。それはいいことかもしれないけど、自分を危険に晒すこともあるから、気をつけた方がいいよ」
「うん」
「で、君は、どんなタイプの人が好きなの?」
「私は、とりあえず、君が好き」
「とりあえず、というのは?」予想外の答えで、少年は思わず笑ってしまった。
「君がしてくれた説明と照らし合わせて、自分にとって相応しい回答を考えたら、そうなった」
「今のところ、僕は好きだ、ということ?」
「そう」
「それは、なんていうのか、まあ、嬉しいよ」
「誰が?」
「僕が」
「私も、嬉しい」
「へえ、どうして?」
「君が、嬉しいから」
「その感情は、綺麗?」
「結果的に私も嬉しくなって、それは私の利益になるから、綺麗」
「その台詞、ほかの人には言わない方がいいよ」
「……どうして?」
「僕以外の人間には、通用しないと思うから」
「それは、何を根拠に言っているの?」
「根拠はない。けれど、なんとなくそんな気がする。僕は、心が狭いから、すぐに諦める癖がある。君がそういう性格をしていても、ふーん、と思うだけで終わってしまう。気に食わなかったり、気に入らなかったりしても、なんとなく受け流せる、ということ」
「うん」
「だから、君のその言葉にも、ちゃんと好意が含まれているんだな、と勝手に解釈した」
「そう……」
「……もしかして、傷つけてしまった?」
「え、なんで?」
「いや、寂しそうな顔をしているな、と思ってさ」
「そう?」月夜は自分の頬に触れる。
「いや、それは違うか」彼は言った。「君は、いつもそんな顔だったね」
天井のどこかで回る換気扇が、この部屋の空気を撹拌している。プロペラが回転する度に過去が消去されて、数秒先の未来が作り出される。そんな奇妙な連想をしている間にも、時間は確実に過ぎ去り、気づいたときには自分はすでにそこにいない。月夜は、そんな訳の分からない連想をすることがあった。自分で考えたいと思っているわけではなくても、自然とそういったことを考えてしまう。だから、無意識の内に、彼女の中の誰かが、そんな思考を望んでいるのかもしれない。
それでは、その発想は何のためにするのだろう?
彼女には分からなかった。
月夜は椅子から立ち上がり、背凭れにかけてあったリュックを背負う。
「もう、帰るの?」彼女の様子を見て、少年が質問した。
「うん、帰る」
「じゃあ、送っていくよ」
「うん」
「忘れ物はない?」
「たぶん、忘れて困るようなものは、ない」
少年は笑った。
教室の扉を開けて、リノリウムの廊下を歩く。細かい穴がいくつも開いた天井がずっと向こうまで続いていて、非常灯が二人をその先へと誘った。消火栓の赤いランプと、水道から漏れ出る水の音を頼りに、二人は昇降口へと向かっていく。廊下にある窓はすべて鍵がかかっていたが、その向こう側に広がる空は、すぐにそこにあるように感じられた。
昇降口で外靴に履き替えて、裏口を目指す。ビオトープに棲む蛙が、何かを呼ぶように鳴いていた。
月夜が言った通り、裏口に鍵はかかっていない。監視カメラもないから、誰も二人の姿を捕捉することはできない。
それでも、木菟だけは、きっと彼らを捉えている。
街灯もない夜道を、二人は並んで歩いた。
「君は、どうして学校に来ているの?」
歩き始めて数分してから、少年が月夜に尋ねた。
「学校で勉強するのは、権利だから」彼女は話す。「権利は、正しく使う必要がある、と聞いたことがある」
「うん、それはそうだね」
「君は、どうして?」
「え?」
「どうして、学校に来ているの?」
「さあ、どうしてかな」
「理由もないのに、来ているの?」
「そうかもしれない」
「学校は楽しい?」
「うん、まあね」
「どこが、一番楽しい?」
「それは、場所を訊いているの? それとも、何が楽しいか、という質問?」
「どっちも」
「場所は教室で、楽しいのは、下校しているときかな」
「下校は、今してるよ」
「そう。君と帰るのは、それなりに面白いんだ」彼は言った。「でも、それは、日中に学校に通っているからだよ。もし下校だけ独立して取り出すことができても、きっとそこに面白さはない。過程が大事だということだね。何事もそうかもしれない。人生だって、ただ死ぬだけではつまらない。ずっと生きてきたから、死ぬときにそれなりに納得することができるんだ」
「君は、いつかは死にたい?」
「うん、いつかはね」
「どんなふうに死にたい?」
「君は?」
「私は、一人で死にたい」
少年は黙った。
自動車が通らないから、二人が黙れば辺りは静かになる。
月が二人を見下ろしていた。
「……どうして、一人で死にたいの?」彼は尋ねる。
「一人の方が、寂しくないから、だと思う」
「どういう意味?」
「周りに誰かがいたら、その人が、悲しい思いをするかもしれない、と気を遣わなくてはならなくなる、という意味」
「それが、寂しいの?」
「うん、寂しい」
「人が寂しさを感じるのは、どうしてだろう?」
月夜は黙って考える。
涼しい風が二人の間を通り抜けた。
「自分にとって損失になるから、感覚的に辛い思いをすることで、死を未然に防ぐためだと思う」彼女は言った。「自分にとって不利益だから、綺麗じゃない、ということ」
「でも、寂しいのは、綺麗だよ」
「そう?」
「そうさ」
「君は、寂しいは、綺麗、と感じるの?」
「うん、感じるよ」
「そっか」
「君は感じないの?」
「うん、感じる」
「それじゃあ、君が言った『綺麗』の定義は、もう一度考え直さないといけないね」
「そうかも」
「がっかりした?」
「何が?」
「自分の定義が、批判されて」
「いや、あまり」
「じゃあ、少しはしたんだね」
「がっかりはしてないけど、不利益でもないから、それでよかった」
「それって、どれのこと?」
「うーん、分からない。もう、眠くて、あまり頭が回らない」
「そう。じゃあ、すぐに寝るといいよ。歩きながらでも、眠れないことはないから」
「君は、歩きながら眠れるの?」
「眠ろうと思えば、いつでも眠れる」
「私は、眠ろうと思ったことがないよ」
「いつも、自然と眠ってしまう、ということ?」
「そんな感じ」
「いいね。眠る努力をしないでも眠れるのは、エネルギーの消費が最小限で、綺麗だ」
「綺麗?」
「うん」
「私と、睡眠は、どっちが綺麗?」
「どっちも」
「どちらかだったら、どっち?」
「睡眠」
いつも電車で帰る道を歩いて通るから、普段とは違う発見がある。けれど、それほど長い旅程というわけでもないから、家にはすぐに到着する。電車を使った方が便利だというだけで、決して歩けない距離ではなかった。それに、新しい発見があるといっても、電車で移動するときと視点が違うだけで、歩いて帰ったことも何度かあるから、完全に新鮮な気持ちにはなれない。今日みたいに夜に下校することもあったから、どちらかというと、久し振り、といった方が正しかった。
少年が歩く速度も、月夜が歩く速度も、もともと大して変わらない。だから、お互いに余計な労力をかけなくて済む。愛情は、自分を殺して相手に尽くすことで生まれるが、できるなら、自分を殺す度合いが小さくて、相手に尽くす度合いが大きい方が良い。マイナスが少なくて、プラスが多いなら、それ以上のものはない。しかしながら、実際にはそう上手くいくことは少ない。適度にバランスをとろうとしても、必ず多少はどちらかに傾く。二人の場合、少年はどちらかというと自分勝手で、月夜は彼に対して従順だったから、少年から見ればプラス、月夜から見ればマイナスだった。
その差は、大々的に示すべきものではない。誤差の範囲内として処理できる。月夜も、彼も、自分のことが大切だったが、それと同じくらい相手のことも大切だった。少年は、自分で自分を好きになれないと言ったが、それは彼の理想が高すぎるせいかもしれない。月夜にはそれが分かっていたから、彼の説明を黙って受け入れることにした。
左右には住宅街が広がっている。街灯はすべて消えていて、不審者がいても気づかない可能性が高い。照明が機能を果たしていないのは、そういった人物が少ないからかもしれないが、それ以上に、エネルギーの消費を押さえたい、といった誰かの意思がはたらいていると考えた方が自然だ。光があれば、自然と人が集まってくる。だから、光を消せば、人はあまり集まらない。輝いているスターがいれば、誰だってその人のもとに集まりたくなるし、コンサート会場の照明が消えれば、人々は自然と駅の方へと流れる。人も、結局のところ蛾と変わらない。それが悪いという話ではなく、むしろ月夜はそんな哀れさが好きだった。
結果的に、家に着くまで一時間ほど歩き続けた。
少し疲れて、息が上がってしまった。
玄関の前で月夜が振り返り、少年に小さく挨拶をする。
「さようなら」
少年は軽く手を上げ、それに応じた。
「うん、またね」
彼が暗闇の中に消えるまで、月夜はその背中を見続ける。少年は途中で振り返り、彼女だけに聞こえる声で言った。
「そういえば、僕には名前がないから、君につけてもらおう、と思ったんだけど」
「名前?」月夜は首を傾げる。「私は、名前をつけたことがないから、ほかの人に頼んだ方がいいと思う」
「でも、君につけてもらいたいんだ」
少年の要望を聞いて、月夜は頷いた。
「分かった」
「すぐに考えられそう?」
「すぐというのは、どれくらいの時間?」
「寒いから、五分くらいでお願いできる?」
「うん、できる」
「じゃあ、少し待つよ」
「うん……」
あと五時間もすれば、二人とも再び学校に向かう。すぐに再会できるから、それまでに考えるという方法もあったが、月夜は、彼に頼まれたことは基本的に断らなかった。
二分と三十秒が経過して、月夜は答えを出すに至った。
「できた」
少年は顔を上げる。
「どんな名前になった?」
「私が月夜だから、君は真昼」
彼女の返答を聞いて、少年は笑った。
「随分と単純な名前だね」
「そう?」
「うん、そうだよ」
「じゃあ、変える?」
「いや、いいよ、そのままで」少年は頷く。「僕は、これから、真昼、でいくよ」
「変な名前で、ごめんなさい」
「大丈夫だよ、これで」
「うん」
「じゃあ、またね、月夜」
「おやすみなさい」
前を向いて、真昼は夜の街へと消えていく。
月夜は玄関を開けて、家の中に入った。
ドアが閉まる。
日の光が、地平線の下で待っていても、彼女の夜は終わらない。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

古屋さんバイト辞めるって
四宮 あか
ライト文芸
ライト文芸大賞で奨励賞いただきました~。
読んでくださりありがとうございました。
「古屋さんバイト辞めるって」
おしゃれで、明るくて、話しも面白くて、仕事もすぐに覚えた。これからバイトの中心人物にだんだんなっていくのかな? と思った古屋さんはバイトをやめるらしい。
学部は違うけれど同じ大学に通っているからって理由で、石井ミクは古屋さんにバイトを辞めないように説得してと店長に頼まれてしまった。
バイト先でちょろっとしか話したことがないのに、辞めないように説得を頼まれたことで困ってしまった私は……
こういう嫌なタイプが貴方の職場にもいることがあるのではないでしょうか?
表紙の画像はフリー素材サイトの
https://activephotostyle.biz/さまからお借りしました。

よくできた"妻"でして
真鳥カノ
ライト文芸
ある日突然、妻が亡くなった。
単身赴任先で妻の訃報を聞いた主人公は、帰り着いた我が家で、妻の重大な秘密と遭遇する。
久しぶりに我が家に戻った主人公を待ち受けていたものとは……!?
※こちらの作品はエブリスタにも掲載しております。

看取り人
織部
ライト文芸
宗介は、末期癌患者が最後を迎える場所、ホスピスのベッドに横たわり、いずれ訪れるであろう最後の時が来るのを待っていた。
後悔はない。そして訪れる人もいない。そんな中、彼が唯一の心残りは心の底で今も疼く若かりし頃の思い出、そして最愛の人のこと。
そんな時、彼の元に1人の少年が訪れる。
「僕は、看取り人です。貴方と最後の時を過ごすために参りました」
これは看取り人と宗介の最後の数時間の語らいの話し

もう一度『初めまして』から始めよう
シェリンカ
ライト文芸
『黄昏刻の夢うてな』ep.0 WAKANA
母の再婚を機に、長年会っていなかった父と暮らすと決めた和奏(わかな)
しかし芸術家で田舎暮らしの父は、かなり変わった人物で……
新しい生活に不安を覚えていたところ、とある『不思議な場所』の話を聞く
興味本位に向かった場所で、『椿(つばき)』という同い年の少女と出会い、ようやくその土地での暮らしに慣れ始めるが、実は彼女は……
ごく平凡を自負する少女――和奏が、自分自身と家族を見つめ直す、少し不思議な成長物語

一か月ちょっとの願い
full moon
ライト文芸
【第8位獲得】心温まる、涙の物語。
大切な人が居なくなる前に、ちゃんと愛してください。
〈あらすじ〉
今まで、かかあ天下そのものだった妻との関係がある時を境に変わった。家具や食器の場所を夫に教えて、いかにも、もう家を出ますと言わんばかり。夫を捨てて新しい良い人のもとへと行ってしまうのか。
人の温かさを感じるミステリー小説です。
これはバッドエンドか、ハッピーエンドか。皆さんはどう思いますか。
<一言>
世にも奇妙な物語の脚本を書きたい。

お茶をしましょう、若菜さん。〜強面自衛官、スイーツと君の笑顔を守ります〜
ユーリ(佐伯瑠璃)
ライト文芸
陸上自衛隊衛生科所属の安達四季陸曹長は、見た目がどうもヤのつく人ににていて怖い。
「だって顔に大きな傷があるんだもん!」
体力徽章もレンジャー徽章も持った看護官は、鬼神のように荒野を走る。
実は怖いのは顔だけで、本当はとても優しくて怒鳴ったりイライラしたりしない自衛官。
寺の住職になった方が良いのでは?そう思うくらいに懐が大きく、上官からも部下からも慕われ頼りにされている。
スイーツ大好き、奥さん大好きな安達陸曹長の若かりし日々を振り返るお話です。
※フィクションです。
※カクヨム、小説家になろうにも公開しています。
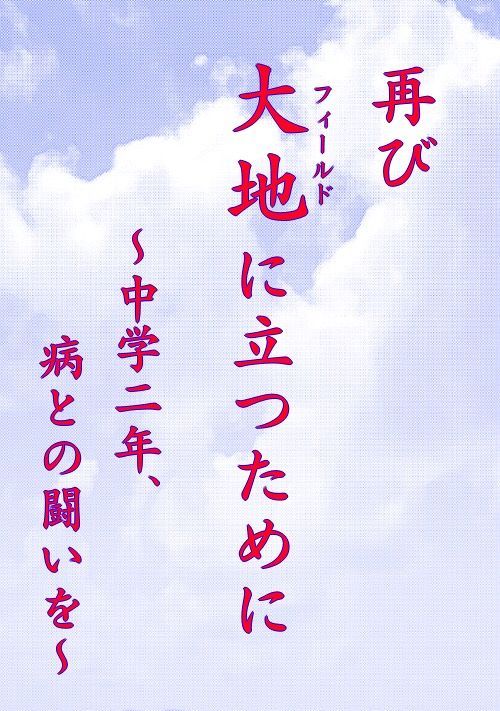
再び大地(フィールド)に立つために 〜中学二年、病との闘いを〜
長岡更紗
ライト文芸
島田颯斗はサッカー選手を目指す、普通の中学二年生。
しかし突然 病に襲われ、家族と離れて一人で入院することに。
中学二年生という多感な時期の殆どを病院で過ごした少年の、闘病の熾烈さと人との触れ合いを描いた、リアルを追求した物語です。
※闘病中の方、またその家族の方には辛い思いをさせる表現が混ざるかもしれません。了承出来ない方はブラウザバックお願いします。
※小説家になろうにて重複投稿しています。

だいたい全部、聖女のせい。
荒瀬ヤヒロ
恋愛
「どうして、こんなことに……」
異世界よりやってきた聖女と出会い、王太子は変わってしまった。
いや、王太子の側近の令息達まで、変わってしまったのだ。
すでに彼らには、婚約者である令嬢達の声も届かない。
これはとある王国に降り立った聖女との出会いで見る影もなく変わってしまった男達に苦しめられる少女達の、嘆きの物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















