3 / 10
第3章 遭遇は写実的に
しおりを挟む
午後八時を迎える前に部屋から出て、僕とリィルは広間へと向かった。ブロックを突っ切ってそのまま真っ直ぐ進むだけだ。
広間に到着すると、先ほど外で会った少女が一人でソファに座っているのを見つけた。彼女は座ったまま目を閉じている。僕はリィルに先ほど話題にした少女であることを告げ、彼女のもとに近づいていった。
僕たちがソファの前に立つと、少女は気配を察知して瞼を開けた。先ほどは黒いコートを纏っていたが、今は黒いセーター姿だった。足にはブーツを履いているが、彼女が身につけているものはすべて黒かった。
「また会いましたね」僕は声をかけた。「誰かを待っているんですか?」
「ええ、もうすぐ食事の時間ですから」
そう言って少女は僕から顔を逸し、隣に立つリィルに視線を向ける。それから二度ほど瞬きをし、再び僕の方を向いた。
「お二人とも、どんなご関係なんですか?」
少女に尋ねられて、僕は少し考える。僕の方も訊きたいことがあったが、先を越されてしまったので、自分の質問は後回しにすることにした。
「どうと訊かれても、少し困りますけど……」言葉を選びながら僕は答える。「まあ、たぶん、友人か、それ以上の関係でしょうね」
僕の返答を聞いて、リィルはあからさまに不機嫌そうな顔をしたが、僕は今は何も言わないでおいた。
「えっと……。僕の方も、一つ訊いていいですか?」
僕の問いを受け、少女は僅かに首を傾げる。
「貴女は、もしかして……。……僕たちと同じ理由でここに来た、つまり……、えっと、翻訳家の方ですか?」
僕の質問を聞いて少女は少し笑い、それから面白そうに口を開いた。
「ええ、そうです。お二人もそうだったんですね」
「ヴァイオリンを弾くために、来たんじゃないんですか?」
「ヴァイオリンは、私の趣味です。ここのオーナーに頼まれて、持ってきました」
「オーナーというのは……」
「ガザエルさんです」
なるほどと思い、僕は頷いた。
少女は自らをウルスと名乗った。彼女は正真正銘の翻訳家で、僕たち以上にその分野に精通しているらしい。見た目は僕よりも明らかに幼いが、もしかするとそれほど離れてはいないかもしれない。年齢について尋ねるのは気が引けたので、僕は実際に訊いてみることはしなかった。
暫くの間ラウンジでウルスと話をしていたが、午後八時を少し過ぎた頃ガザエルが姿を現した。
「お三方とも、お揃いですね」笑みを浮かべながらガザエルは言った。「もう一人の方は、少し遅れてくるそうで……。そういうことだから、先に始めましょう」
ガザエルに導かれて、僕とリィル、そしれウルスの三人は、正面玄関にあるカウンターの内側に入り、その先のエリアに足を踏み入れた。この辺りは地下に空間が形成されているため、建物の外から観察することはできない。
普段は美術館の職員が詰め所として使っている場所のようで、部屋は全部で二つあった。一つはカウンターから階段を下りてすぐにある部屋で、そこには事務机や書棚が並べられている。その先にドアがあり、そこを抜けると如何にも食堂という感じの部屋に辿り着いた。
ガザエルの説明によると、この部屋はもともと食堂として使うためにデザインされたのではなく、あくまで美術館のモニュメントとして設計されたものらしい。最初の段階では地下にもいくつか展示場所を作る予定だったとのだ。それが後々計画が変更され、今の三つのフロアで作品の展示を行うことになったとのことだった。
「食堂のモニュメントって、どういうことですか?」
珍しく積極的に質問をしたリィルに対して、ガザエルは答えた。
「別に、深い意味はありませんよ。ただ、何通りかあった候補の中から、たまたま食堂が選ばれただけです」
部屋の中央には巨大な長机が一つだけあり、その周囲に椅子が等間隔にいくつも並べられている。西洋的な食堂といえば誰もが想像するような、典型的な意匠が施されている。クオリティーはなかなかのものだが、どこか安っぽい感じもしなくはない。予算の都合で細かい部分がオミットされることになったのかもしれないと僕は考えた。
料理の準備があると言って、ガザエルは食堂から出ていった。もう少しで用意できるから、暫く待っていてほしいとのことだ。
上座は開けておいて、その次の席から僕たちは順に椅子に座った。入り口に近い方の席に僕が着き、その対面にリィル、そして僕の隣がウルスという配置だ。
椅子に座ると、ウルスはすぐに目を閉じてしまった。単純に眠いだけという可能性もないとはいえないが、おそらく違うだろう。椅子に座ったら必ず脚を組む人間がいるように、それが彼女の座るときの癖なのかもしれない。
テーブルの上には、ナイフとフォーク、スプーン、硝子製のグラス、それにナプキンの上に配置された皿がすでに並べられていた。当然リィルの席にも同様のものが用意されていたので、彼女の事情についてどのように説明しようかと僕は考えた。
そもそもの問題として、夕飯の時間になる前にガザエルに伝えておけば良かったのだが、読書をしている内についつい忘れてしまったのだ。僕にはよくあることだが、よくあることだからというのは理由にならない。そんなことを言っても、それで何か改善されるわけではないのだが……。
「お腹、空きましたか?」
自分のミスを意識したくなかったのか、僕はなんとなくウルスに声をかけた。
「ええ」目を閉じたまま、ウルスは軽く頷く。
「何か、好きな食べ物はありますか?」
「大抵のものは好きです」ウルスは端的に答えた。「嫌いなものはありません」
「もしよかったら、その……、彼女の分を貰ってもらえませんか?」目を閉じているウルスに対して、僕はリィルを指さして示す。
「どうしてですか?」ウルスは目を開けて、僕を見た。
「えっと、彼女、ちょっとした病気で……。……その、普通の食事ができないんです」
「普通ではない食事というものが、あるんですか?」
「ええ……。なんか、こう、彼女専用のものがあるんです。僕もよくは分からないんですけど……。それがあるから、彼女はなんとか毎日生活することができています」
ウルスは訝しげな目で僕を見たあと、そのまま視線をリィルに向けた。ウルスに見られて、リィルは澄ました顔で首を傾げる。ウルスは再び僕を見て、それから回答を示した。
「分かりました。では、頂きます」
「どうもありがとう」
ウルスは再び目を閉じたが、今度はすぐに瞼を上げて、テーブルにあるナプキンを手に取った。それを折り紙のように折り始め、ときどき角度を変えて観察したりする。
「お二人は、どこの出身ですか?」
「僕たちですか?」ウルスに問われ、僕は答える。「ここからだと、東の方になりますね」
僕は住んでいる地名をウルスに伝えたが、彼女は知らないと言った。反対に彼女が住んでいる地名を聞いても、やはり僕にも分からなかった。互いに守備範囲の外だったから、今まで名前を聞いたことがなかったのかもしれない。
「ウルスさんは、一人?」
突然リィルに問われ、ウルスは彼女に目を向ける。
「そうです。ずっと、一人です」
「ずっと?」
「生まれたときから、という意味です」
「ご両親は?」僕は尋ねる。
「私が生まれて間もない頃に、亡くなりました」ウルスは説明した。「幼い頃は叔母に育てられたみたいですが、そのときのこともあまり覚えていません。いつからか一人で暮らすようになって、今日までずっとそうしてきました」
「親戚とか、いないの?」興味を惹かれたのか、リィルは続けてウルスに質問する。
「私の知る限りでは」ウルスは答えた。「一度も会ったことはありません」
リィルがなぜそんなことを訊いたのか、僕には分からなかった。タイミングとして不適切なわけではないが、まあ、いつも通り、突飛な思考の結果だろうと思っておく。
「翻訳家になろうと思ったきっかけも、特にありません」ウルスは話した。「ヴァイオリンが趣味で、その勉強のために他言語を学ぶ必要があったが故に、いつの間にか母語以外の能力も身についていて……。……充分に生きていける仕事がほかに思いつかなかったから、この仕事を選んだだけです」
「どうして、そんなことを僕たちに話すんですか?」気になって、僕は笑いながら尋ねた。
「私のことを、知ってもらいたかったからです」ウルスは奇妙な笑みを浮かべて答える。「親交を深めておいた方が、お互いにとってプラスになるのではありませんか?」
「ええ、その通りです」僕は頷いた。「でも、僕には貴女にお話しできるほどの経歴はありません」
ガザラスが戻ってくるまで、僕たちは三人で会話を交わした。有益な情報はほとんど得られなかったが、ウルスがどのような人間なのかは、少しだけ分かったような気がした。しかし、それもあくまでそんな気がしただけだ。出会って数時間で窺えるものといえば、彼女を取り巻く雰囲気のようなものくらいでしかない。
出ていって十分くらい経った頃、ガザラスが食堂に戻ってきた。彼に伴ってコックらしき人物が数名部屋に入ってくる。ガザラスの話によると、彼らはこの美術館と提携している業者の者らしい。館内にも二階にレストランがあって、普段はそこで働いているとのことだった。
ここは山の頂上だから、食材を調達するのは簡単にはいかないとのことだ。各週の決められた日に麓から運ばれてくる以外は、自分たちで買いに行かなくてはならないとガザラスは話した。
コックが料理を用意している間に、僕はガザラスにリィルとウルスとの間で交わされた交渉について説明した。互いに交換条件を持ち出したわけではないから、交渉と呼ぶのは相応しいとはいえないが、特に詮索することなくガザラスは了承してくれた。
用意された料理は西洋的なものだった。もともとテーブルに置かれていた皿にはフライドポテトが添えられたサーロインステーキが載せられ、そのほかにも、チーズが載ったサラダや魚介類を使ったバスタなど、地域による縛りはないが、少なくともこの国のものではない料理が沢山並べられた。国産ではない本場のワインなんかも用意されていたが、僕はお酒は飲めないので、ガザエルには予め断っておいた。
一通り料理の準備ができてから、僕たちは食事を始めた。リィルは例によって椅子に座っているだけだが、周囲の人々がそれを気にする様子はなかった。
「あともう一方いらっしゃる予定ですが……」食事を進めながら、ガザエルが呟いた。彼は上座の席に座っている。「彼は、今日中には間に合わないかもしれない。どこかで道草を食っているようです」
「まだ、山の中にも入っていないんですか?」気になって僕は質問する。
「連絡によると」彼は頷いた。「今からでは、もう、立ち入ろうとは思わないでしょう」
食事の際にはあまり口を開かない僕だが、どういうわけか、今回は口の動きが途切れることはほとんどなかった。リィルはどちらかというと人見知りなので、慣れるまでは社交辞令さえ口にしないが、僕はガザエルとウルスとある程度話題を共有することができて、食事をしながら会話をするという試練を久し振りに経験した。
会話の中で、ガザエルとウルスが以前からの知り合いだということも判明した。話によると、以前にも同様の作業が行われたことがあるらしく、ウルスはそのときもここまでやって来たようだ。その際に彼女が楽器を演奏できることを知り、次回会うときに是非演奏してもらいたいとガザエルが頼んだみたいだった。
「ヴァイオリンを弾くときに、注意するべきことは何ですか?」
楽器にはあまり興味がなかったが、僕は思いついたことをそのままウルスに質問した。
「何だと思いますか?」ポテトを刺したフォークを持ち上げて、ウルスは尋ねる。
「うーん、何でしょう……。弦が切れないように、摩擦を少なくすることでしょうか」
僕の返答を訊いて、ウルスは少しだけ笑った。彼女の笑うタイミングは、予想が簡単だとはいえない。ずっと一緒にいるリィルでさえ未だに予想できないのだから、ウルスのことを知るためにはもっと時間がかかるかもしれない。
「もちろん、それも大事です。しかし、それは何をする場合でも同じでしょう」
彼女の言葉を聞いて僕は頷く。
「一番大切なのは、音を音として認識しないことです」ウルスは説明した。「厳密には、音を一つ一つ捉えようとせず、全体の流れを捉えようと努力することです」
ウルスの話を聞いて、僕はなるほどと思った。
「しかし、そうも言っていられない」ウルスが話すのをやめると、今度はガザエルが口を開いた。「歳をとると、その日を生きるので精一杯になってくる。とても、一生のことを考えて生きることなんてできませんよ」
「ガザエルさんは、まだ、それほどのお年ではないのでは?」ウルスが尋ねる。
「年齢は秘密です。教えても、全然面白くない。そういうウルスさんは、おいくつなんでしたっけ?」
「私は、十六です」ウルスは澄ました顔で答えた。「ガザエルさんは、少なくとも、私よりは上でしょう」
ウルスの年齢についてある程度は予想していたが、彼女から実際に聞いて、僕はやはり驚いた。十六となると僕よりも幼い。おそらく、彼女の翻訳家としての腕は僕よりも圧倒的に上だろう。僕が精力的に勉強することを怠ってきたというのもあるが、自分が生きてきたより少ない時間を用いてここまで上り詰めたとなると、ウルスにはそれ相応の才能があるといわざるをえない。勉強をするには時間が必要だが、彼女の場合その効率が良い、つまり技能の習得が平均よりも速いということになる。
「学校には通ったんですか?」グラタンを食べながら、僕はウルスに質問した。
「いいえ」ウルスは首を振る。「そんな時間は、私にはありませんでした。学校に通う経験も必要だったでしょうが……。……そうしたチャンスを捨てなければ、ほかの経験をすることはできませんでした」
ウルスのような人間には、それなりの確率で出会う。いわゆる秀才と呼ばれる人々だが、多くの場合、そうした人々に出会っても、その人物を秀才だと認識するまでには至らない。だから知らず知らずの内に出会って、そのまま別れてしまう。今の自分の能力を上げるには、自分より能力が上の人から影響を受ける以外にはないから、彼女に出会えて良かったと僕は思った。
ローストビーフを口に入れ、僕はそれを咀嚼する。ふと隣のリィルを見ると、彼女はテーブルに両肘をついてその上に顎を載せ、ガザエルと話すウルスをじっと見つめていた。
「どうかした?」
僕の声に反応して、リィルは勢い良く顔をこちらに向ける。
「別に」
彼女の返事を聞いて、僕は思わず笑ってしまった。
「その回答は、気にしてほしいと言っているようなものだよ」
「気にしてくれなくても、全然困らないから」
「念願の食事じゃないか。楽しまなくていいの?」
「もう、充分楽しんだ」
「あそう」僕は頷き、お酒の代わりに注いでもらったグレープジュースを飲む。「それなら、よかったよ。ブラボー」
一時間ほどで食事は終わった。準備から片付けまですべてここの職員にやってもらったから、なんとなく申し訳ないような気持ちだったが、相手が良いと言ってくれているのだから、今回は甘えておくことにしようと僕は思った(それはいつものことだが)。
自室に戻ると、リィルはそのままベッドに倒れ込んだ。滲み出ているどころか、最早放出しているといっても良いくらい不機嫌さを晒していたから、僕もさすがに放おっておくことはできず、彼女に構うことにした。
「何が、そんなに気に入らなかったの?」椅子に座り、正面に横たわる彼女を見て僕は訊いた。
リィルはなかなか返事をしない。数秒経過してから、顔を布団におしつけたくぐもった声で彼女は答えた。
「だから、何も気に入らなかったわけじゃない」
「じゃあ、おかしいよ。そうでなかったら、君がそんな態度をとるはずがない」
僕がそう言うと、リィルは勢い良く身体を起こす。
「どうして、私のことを知っているような言い方をするの?」
「え?」僕は思わず笑みを零す。
「何も分かっていないくせに」
どうやら本気で怒っているみたいだったから、僕は本当に可笑しくなってしまった。失礼極まりないが、怒っているときのリィルは非常に面白いのだ。どこがどう面白いのか説明するのは難しいが、だからこそ分析してレポートに纏める価値があるかもしれない。
「たしかに、僕は君のことをあまり理解していないよ」手を伸ばして、僕はインスタントコーヒーの瓶に触れる。「ただね、分かっていないくせにとか言われても、余計に分からなくなるだけだ。それなら、きちんと話した方が、君のためにもなるんじゃないかな」
「違う」
「何が?」
リィルは僕から顔を背ける。
例によって、数秒間の沈黙。
なんとなく、僕はその時間を空で数える。
八と六分の一秒くらい経過したとき、リィルは小さな声で呟いた。
「……自分でも、何が気に入らなかったのか、分からない」
予想していたよりも彼女の返答が的確だったから、僕は少しだけ安心した。どうやら完全に感情的になっているわけではないみたいだ。きちんと理性的な判断をしたうえで、それでも自分の感情を優先しようとしているらしい。
「君が怒っている原因は、なんとなく分かるよ」僕は話した。同時にインスタントコーヒーの粉末が入った瓶の蓋を閉め、カップにお湯を注ぐ。水はここに戻ってくる途中で注いで、すでに沸かしてあった。「でも……。きっとそれは、君の勝手な思い込みにすぎない。僕の本心を覗いたわけじゃないんだから。……いや、たとえ僕の本心を覗くことができても、君が本当にそれを理解することはできないだろうね。そういうものだよ、人との関係ってさ」
「……じゃあ、どうやって解決するの?」
「解決できるのは君だけだ。それは君の課題であって、僕の課題ではない」
「無理」
「何が?」
「自分の間違いを認めるなんて」
リィルは真剣に言っているのだろうが、僕は可笑しくて仕方がなかった。
僕が笑い声を零したのに反応して、リィルは再び僕を睨む。
「どうして、そんな簡単に笑うの?」
「ごめん、悪かったよ。僕の癖なんだ。許してほしい」
リィルはまた顔を背ける。
液体が入ったカップをスプーンでかき混ぜ、僕はそれを一口啜る。渋さは感じず、リラックスできる程度の薄味だった。
リィルに構うのはここまでにすることにして、僕は本を開く。
彼女も僕も、まだまだ幼い。身体的には成熟しているが、精神的に成熟しているかと問われたら、頷くことができる自信はない。少なくとも僕はそうだ。そうした大人になるための過程をスキップして、今日までそれっぽく生きてきてしまった。そして、スキップした過程はもう二度と取り返すことはできない。だから、今後もいわゆる「大人」を演じていくことしかできないのだ。他人が見るのは表面的な僕でしかないから、それでも特に問題はないだろう。
ただ、僕とリィルの二人の間で生じる問題には、他人は誰も介入してくれない。だから自分たちで解決するしかない。この幼稚な頭を駆使して自分たちなりの答えを見つけ出さなくてはならない。
もちろん、それは骨の折れる作業になるだろう。もしかしたら、最後まで答えなんて見つけられないかもしれない。
それでも……。
リィルとなら上手くやっていける感覚が僕にはある。
それは、彼女と出会ったときから感じていたものだ。
これは果たして運命だろうか?
……もしかするとそうかもしれない。現段階では、否定する根拠よりも、肯定する根拠の方が勢力が勝っている。たぶん、それは一般的な場合とは真逆の構図だろう。あくまで僕とリィルの関係が特殊というだけだ。
リィルはそのまま沈黙してしまった。もしかすると眠ってしまったのかもしれない。
僕は立ち上がり、リィルの身体に毛布をかける。季節に関わらず、何もかけずに寝ると風邪を引く。まるで年齢に関係なく怪獣が好きな僕みたいだ。
何の反応もしないリィルをそのままにして、立ち上がった序に僕は窓の外を見た。すでに午後九時を過ぎているから、空は真っ暗になっている。見上げると、真っ黒な天蓋に星がいくつも煌めいていた。ここからでは月は見えないが、きっとどこかに昇っているはずだ。
目の前には公園がある。僕たちが住む町にあるものとは雰囲気は異なるが、閉鎖された空間という共通点だけでも、そこは長閑な場所のように見える。
公園と夜空。
それら二つの要素が相まって、僕の頭は昔のことを思い出した。
リィルと初めて出会ったとき、僕は丘の上にある公園にいた。そしてもちろん時刻は深夜。そのときはまだ背の低かった僕には、リィルの長い手脚がとても美しく見えた。
僕と彼女の関係はその瞬間から始まったといっても良いが、傍から見たら関係の性質は大分変わったように映るに違いない。しかしながら、それは外見の変化から抱くイメージの差にすぎないだろう。実際のところは、僕とリィルの関係はそこまで変化していない。変化がない、つまりは成長がなくて困るほどではないが、その根幹にあるものは何一つとして変わっていないといって良い。
人間に似ていながらも異なる性質を帯びたリィルが、そのときの僕にはとても魅力的に見えた。自分とは程遠い存在であるようにも、それでいて手を伸ばせば届くような存在にも、そのどちらにも思えたのだ。言い換えれば、それは僕が彼女との間に差を感じていたということでもある。自分と彼女が異なるものだと思っていたのだ。
けれど、それは違った。あとになって、僕は自分も彼女と同類であることを知った。その事実が判明したときは何の驚きも抱かなかったが、時間が経つに連れて徐々に動揺するようになった。もちろん、今ではもう充分に受け留めきれていると思うが、ときどきそんな自分を不思議に感じることもある。
そして、それを不思議に感じるのには、きちんとした理由がある。
本当は不思議なのではない。
不思議という形に抽象化することで、真実を知る、もしくは再確認することを避けているのだ。
不思議という形に抽象化される前は、それは恐怖、あるいは不安、そんな形をしたものだった。
そう……。
今でも、その恐怖や不安の存在を必死に隠蔽しようとしている。
不思議だ、不思議だと繰り返すことで、本当のことを知るのを避けているのだ。
でも……。
きっとその恐怖や不安の温床には、ある一人の人物が存在している。それは理解しているし、揺らぎようのない事実だということも分かっている。
そして、僕たちの未来にはそのたった一人の人物が待っている。
真実を教えるために、いや……、真実に気がついたかどうかを確かめるために、待っているのだ。
だから……。
「ああ、もう、やめた」
背後から突然声が聞こえて、僕はゆっくりと後ろを振り返った。驚いたときに素直に驚きを表に出せないのは、僕の欠点であるのと同時に、長所ともいえる。
「一通りいじけて、気が済んだ?」僕は笑いながらリィルに尋ねる。
「何、その言い方?」
リィルは上半身だけをベッドから起こし、そのままの姿勢で僕を睨みつける。
「……なんか、ごめん」
態度はそのままだったが、リィルは謝った。
「何が?」僕は分からない振りをする。
「不機嫌で、ごめん」
「別に、いいよ。機嫌なんて、自分で制御できるものじゃないし」
リィルは顔を背け、少しだけ頰を膨らませる。
「それに……」
僕の言葉を聞いて、リィルは再び僕を見た。
「それに、何?」
「いや、うん……。……いつものことだな、と思って……」
部屋のドアがノックされ、僕とリィルの会話はそこで途切れた。僕は部屋の中を進み、鍵を解錠してドアを開く。
ドアの先にはウルスが立っていた。黒いコートに身を包み、小さな顔を上に向けて僕の顔を見ている。
「コンサートの時間です」
そう言って、ウルスは持っていた楽器ケースを軽く持ち上げた。
広間に到着すると、先ほど外で会った少女が一人でソファに座っているのを見つけた。彼女は座ったまま目を閉じている。僕はリィルに先ほど話題にした少女であることを告げ、彼女のもとに近づいていった。
僕たちがソファの前に立つと、少女は気配を察知して瞼を開けた。先ほどは黒いコートを纏っていたが、今は黒いセーター姿だった。足にはブーツを履いているが、彼女が身につけているものはすべて黒かった。
「また会いましたね」僕は声をかけた。「誰かを待っているんですか?」
「ええ、もうすぐ食事の時間ですから」
そう言って少女は僕から顔を逸し、隣に立つリィルに視線を向ける。それから二度ほど瞬きをし、再び僕の方を向いた。
「お二人とも、どんなご関係なんですか?」
少女に尋ねられて、僕は少し考える。僕の方も訊きたいことがあったが、先を越されてしまったので、自分の質問は後回しにすることにした。
「どうと訊かれても、少し困りますけど……」言葉を選びながら僕は答える。「まあ、たぶん、友人か、それ以上の関係でしょうね」
僕の返答を聞いて、リィルはあからさまに不機嫌そうな顔をしたが、僕は今は何も言わないでおいた。
「えっと……。僕の方も、一つ訊いていいですか?」
僕の問いを受け、少女は僅かに首を傾げる。
「貴女は、もしかして……。……僕たちと同じ理由でここに来た、つまり……、えっと、翻訳家の方ですか?」
僕の質問を聞いて少女は少し笑い、それから面白そうに口を開いた。
「ええ、そうです。お二人もそうだったんですね」
「ヴァイオリンを弾くために、来たんじゃないんですか?」
「ヴァイオリンは、私の趣味です。ここのオーナーに頼まれて、持ってきました」
「オーナーというのは……」
「ガザエルさんです」
なるほどと思い、僕は頷いた。
少女は自らをウルスと名乗った。彼女は正真正銘の翻訳家で、僕たち以上にその分野に精通しているらしい。見た目は僕よりも明らかに幼いが、もしかするとそれほど離れてはいないかもしれない。年齢について尋ねるのは気が引けたので、僕は実際に訊いてみることはしなかった。
暫くの間ラウンジでウルスと話をしていたが、午後八時を少し過ぎた頃ガザエルが姿を現した。
「お三方とも、お揃いですね」笑みを浮かべながらガザエルは言った。「もう一人の方は、少し遅れてくるそうで……。そういうことだから、先に始めましょう」
ガザエルに導かれて、僕とリィル、そしれウルスの三人は、正面玄関にあるカウンターの内側に入り、その先のエリアに足を踏み入れた。この辺りは地下に空間が形成されているため、建物の外から観察することはできない。
普段は美術館の職員が詰め所として使っている場所のようで、部屋は全部で二つあった。一つはカウンターから階段を下りてすぐにある部屋で、そこには事務机や書棚が並べられている。その先にドアがあり、そこを抜けると如何にも食堂という感じの部屋に辿り着いた。
ガザエルの説明によると、この部屋はもともと食堂として使うためにデザインされたのではなく、あくまで美術館のモニュメントとして設計されたものらしい。最初の段階では地下にもいくつか展示場所を作る予定だったとのだ。それが後々計画が変更され、今の三つのフロアで作品の展示を行うことになったとのことだった。
「食堂のモニュメントって、どういうことですか?」
珍しく積極的に質問をしたリィルに対して、ガザエルは答えた。
「別に、深い意味はありませんよ。ただ、何通りかあった候補の中から、たまたま食堂が選ばれただけです」
部屋の中央には巨大な長机が一つだけあり、その周囲に椅子が等間隔にいくつも並べられている。西洋的な食堂といえば誰もが想像するような、典型的な意匠が施されている。クオリティーはなかなかのものだが、どこか安っぽい感じもしなくはない。予算の都合で細かい部分がオミットされることになったのかもしれないと僕は考えた。
料理の準備があると言って、ガザエルは食堂から出ていった。もう少しで用意できるから、暫く待っていてほしいとのことだ。
上座は開けておいて、その次の席から僕たちは順に椅子に座った。入り口に近い方の席に僕が着き、その対面にリィル、そして僕の隣がウルスという配置だ。
椅子に座ると、ウルスはすぐに目を閉じてしまった。単純に眠いだけという可能性もないとはいえないが、おそらく違うだろう。椅子に座ったら必ず脚を組む人間がいるように、それが彼女の座るときの癖なのかもしれない。
テーブルの上には、ナイフとフォーク、スプーン、硝子製のグラス、それにナプキンの上に配置された皿がすでに並べられていた。当然リィルの席にも同様のものが用意されていたので、彼女の事情についてどのように説明しようかと僕は考えた。
そもそもの問題として、夕飯の時間になる前にガザエルに伝えておけば良かったのだが、読書をしている内についつい忘れてしまったのだ。僕にはよくあることだが、よくあることだからというのは理由にならない。そんなことを言っても、それで何か改善されるわけではないのだが……。
「お腹、空きましたか?」
自分のミスを意識したくなかったのか、僕はなんとなくウルスに声をかけた。
「ええ」目を閉じたまま、ウルスは軽く頷く。
「何か、好きな食べ物はありますか?」
「大抵のものは好きです」ウルスは端的に答えた。「嫌いなものはありません」
「もしよかったら、その……、彼女の分を貰ってもらえませんか?」目を閉じているウルスに対して、僕はリィルを指さして示す。
「どうしてですか?」ウルスは目を開けて、僕を見た。
「えっと、彼女、ちょっとした病気で……。……その、普通の食事ができないんです」
「普通ではない食事というものが、あるんですか?」
「ええ……。なんか、こう、彼女専用のものがあるんです。僕もよくは分からないんですけど……。それがあるから、彼女はなんとか毎日生活することができています」
ウルスは訝しげな目で僕を見たあと、そのまま視線をリィルに向けた。ウルスに見られて、リィルは澄ました顔で首を傾げる。ウルスは再び僕を見て、それから回答を示した。
「分かりました。では、頂きます」
「どうもありがとう」
ウルスは再び目を閉じたが、今度はすぐに瞼を上げて、テーブルにあるナプキンを手に取った。それを折り紙のように折り始め、ときどき角度を変えて観察したりする。
「お二人は、どこの出身ですか?」
「僕たちですか?」ウルスに問われ、僕は答える。「ここからだと、東の方になりますね」
僕は住んでいる地名をウルスに伝えたが、彼女は知らないと言った。反対に彼女が住んでいる地名を聞いても、やはり僕にも分からなかった。互いに守備範囲の外だったから、今まで名前を聞いたことがなかったのかもしれない。
「ウルスさんは、一人?」
突然リィルに問われ、ウルスは彼女に目を向ける。
「そうです。ずっと、一人です」
「ずっと?」
「生まれたときから、という意味です」
「ご両親は?」僕は尋ねる。
「私が生まれて間もない頃に、亡くなりました」ウルスは説明した。「幼い頃は叔母に育てられたみたいですが、そのときのこともあまり覚えていません。いつからか一人で暮らすようになって、今日までずっとそうしてきました」
「親戚とか、いないの?」興味を惹かれたのか、リィルは続けてウルスに質問する。
「私の知る限りでは」ウルスは答えた。「一度も会ったことはありません」
リィルがなぜそんなことを訊いたのか、僕には分からなかった。タイミングとして不適切なわけではないが、まあ、いつも通り、突飛な思考の結果だろうと思っておく。
「翻訳家になろうと思ったきっかけも、特にありません」ウルスは話した。「ヴァイオリンが趣味で、その勉強のために他言語を学ぶ必要があったが故に、いつの間にか母語以外の能力も身についていて……。……充分に生きていける仕事がほかに思いつかなかったから、この仕事を選んだだけです」
「どうして、そんなことを僕たちに話すんですか?」気になって、僕は笑いながら尋ねた。
「私のことを、知ってもらいたかったからです」ウルスは奇妙な笑みを浮かべて答える。「親交を深めておいた方が、お互いにとってプラスになるのではありませんか?」
「ええ、その通りです」僕は頷いた。「でも、僕には貴女にお話しできるほどの経歴はありません」
ガザラスが戻ってくるまで、僕たちは三人で会話を交わした。有益な情報はほとんど得られなかったが、ウルスがどのような人間なのかは、少しだけ分かったような気がした。しかし、それもあくまでそんな気がしただけだ。出会って数時間で窺えるものといえば、彼女を取り巻く雰囲気のようなものくらいでしかない。
出ていって十分くらい経った頃、ガザラスが食堂に戻ってきた。彼に伴ってコックらしき人物が数名部屋に入ってくる。ガザラスの話によると、彼らはこの美術館と提携している業者の者らしい。館内にも二階にレストランがあって、普段はそこで働いているとのことだった。
ここは山の頂上だから、食材を調達するのは簡単にはいかないとのことだ。各週の決められた日に麓から運ばれてくる以外は、自分たちで買いに行かなくてはならないとガザラスは話した。
コックが料理を用意している間に、僕はガザラスにリィルとウルスとの間で交わされた交渉について説明した。互いに交換条件を持ち出したわけではないから、交渉と呼ぶのは相応しいとはいえないが、特に詮索することなくガザラスは了承してくれた。
用意された料理は西洋的なものだった。もともとテーブルに置かれていた皿にはフライドポテトが添えられたサーロインステーキが載せられ、そのほかにも、チーズが載ったサラダや魚介類を使ったバスタなど、地域による縛りはないが、少なくともこの国のものではない料理が沢山並べられた。国産ではない本場のワインなんかも用意されていたが、僕はお酒は飲めないので、ガザエルには予め断っておいた。
一通り料理の準備ができてから、僕たちは食事を始めた。リィルは例によって椅子に座っているだけだが、周囲の人々がそれを気にする様子はなかった。
「あともう一方いらっしゃる予定ですが……」食事を進めながら、ガザエルが呟いた。彼は上座の席に座っている。「彼は、今日中には間に合わないかもしれない。どこかで道草を食っているようです」
「まだ、山の中にも入っていないんですか?」気になって僕は質問する。
「連絡によると」彼は頷いた。「今からでは、もう、立ち入ろうとは思わないでしょう」
食事の際にはあまり口を開かない僕だが、どういうわけか、今回は口の動きが途切れることはほとんどなかった。リィルはどちらかというと人見知りなので、慣れるまでは社交辞令さえ口にしないが、僕はガザエルとウルスとある程度話題を共有することができて、食事をしながら会話をするという試練を久し振りに経験した。
会話の中で、ガザエルとウルスが以前からの知り合いだということも判明した。話によると、以前にも同様の作業が行われたことがあるらしく、ウルスはそのときもここまでやって来たようだ。その際に彼女が楽器を演奏できることを知り、次回会うときに是非演奏してもらいたいとガザエルが頼んだみたいだった。
「ヴァイオリンを弾くときに、注意するべきことは何ですか?」
楽器にはあまり興味がなかったが、僕は思いついたことをそのままウルスに質問した。
「何だと思いますか?」ポテトを刺したフォークを持ち上げて、ウルスは尋ねる。
「うーん、何でしょう……。弦が切れないように、摩擦を少なくすることでしょうか」
僕の返答を訊いて、ウルスは少しだけ笑った。彼女の笑うタイミングは、予想が簡単だとはいえない。ずっと一緒にいるリィルでさえ未だに予想できないのだから、ウルスのことを知るためにはもっと時間がかかるかもしれない。
「もちろん、それも大事です。しかし、それは何をする場合でも同じでしょう」
彼女の言葉を聞いて僕は頷く。
「一番大切なのは、音を音として認識しないことです」ウルスは説明した。「厳密には、音を一つ一つ捉えようとせず、全体の流れを捉えようと努力することです」
ウルスの話を聞いて、僕はなるほどと思った。
「しかし、そうも言っていられない」ウルスが話すのをやめると、今度はガザエルが口を開いた。「歳をとると、その日を生きるので精一杯になってくる。とても、一生のことを考えて生きることなんてできませんよ」
「ガザエルさんは、まだ、それほどのお年ではないのでは?」ウルスが尋ねる。
「年齢は秘密です。教えても、全然面白くない。そういうウルスさんは、おいくつなんでしたっけ?」
「私は、十六です」ウルスは澄ました顔で答えた。「ガザエルさんは、少なくとも、私よりは上でしょう」
ウルスの年齢についてある程度は予想していたが、彼女から実際に聞いて、僕はやはり驚いた。十六となると僕よりも幼い。おそらく、彼女の翻訳家としての腕は僕よりも圧倒的に上だろう。僕が精力的に勉強することを怠ってきたというのもあるが、自分が生きてきたより少ない時間を用いてここまで上り詰めたとなると、ウルスにはそれ相応の才能があるといわざるをえない。勉強をするには時間が必要だが、彼女の場合その効率が良い、つまり技能の習得が平均よりも速いということになる。
「学校には通ったんですか?」グラタンを食べながら、僕はウルスに質問した。
「いいえ」ウルスは首を振る。「そんな時間は、私にはありませんでした。学校に通う経験も必要だったでしょうが……。……そうしたチャンスを捨てなければ、ほかの経験をすることはできませんでした」
ウルスのような人間には、それなりの確率で出会う。いわゆる秀才と呼ばれる人々だが、多くの場合、そうした人々に出会っても、その人物を秀才だと認識するまでには至らない。だから知らず知らずの内に出会って、そのまま別れてしまう。今の自分の能力を上げるには、自分より能力が上の人から影響を受ける以外にはないから、彼女に出会えて良かったと僕は思った。
ローストビーフを口に入れ、僕はそれを咀嚼する。ふと隣のリィルを見ると、彼女はテーブルに両肘をついてその上に顎を載せ、ガザエルと話すウルスをじっと見つめていた。
「どうかした?」
僕の声に反応して、リィルは勢い良く顔をこちらに向ける。
「別に」
彼女の返事を聞いて、僕は思わず笑ってしまった。
「その回答は、気にしてほしいと言っているようなものだよ」
「気にしてくれなくても、全然困らないから」
「念願の食事じゃないか。楽しまなくていいの?」
「もう、充分楽しんだ」
「あそう」僕は頷き、お酒の代わりに注いでもらったグレープジュースを飲む。「それなら、よかったよ。ブラボー」
一時間ほどで食事は終わった。準備から片付けまですべてここの職員にやってもらったから、なんとなく申し訳ないような気持ちだったが、相手が良いと言ってくれているのだから、今回は甘えておくことにしようと僕は思った(それはいつものことだが)。
自室に戻ると、リィルはそのままベッドに倒れ込んだ。滲み出ているどころか、最早放出しているといっても良いくらい不機嫌さを晒していたから、僕もさすがに放おっておくことはできず、彼女に構うことにした。
「何が、そんなに気に入らなかったの?」椅子に座り、正面に横たわる彼女を見て僕は訊いた。
リィルはなかなか返事をしない。数秒経過してから、顔を布団におしつけたくぐもった声で彼女は答えた。
「だから、何も気に入らなかったわけじゃない」
「じゃあ、おかしいよ。そうでなかったら、君がそんな態度をとるはずがない」
僕がそう言うと、リィルは勢い良く身体を起こす。
「どうして、私のことを知っているような言い方をするの?」
「え?」僕は思わず笑みを零す。
「何も分かっていないくせに」
どうやら本気で怒っているみたいだったから、僕は本当に可笑しくなってしまった。失礼極まりないが、怒っているときのリィルは非常に面白いのだ。どこがどう面白いのか説明するのは難しいが、だからこそ分析してレポートに纏める価値があるかもしれない。
「たしかに、僕は君のことをあまり理解していないよ」手を伸ばして、僕はインスタントコーヒーの瓶に触れる。「ただね、分かっていないくせにとか言われても、余計に分からなくなるだけだ。それなら、きちんと話した方が、君のためにもなるんじゃないかな」
「違う」
「何が?」
リィルは僕から顔を背ける。
例によって、数秒間の沈黙。
なんとなく、僕はその時間を空で数える。
八と六分の一秒くらい経過したとき、リィルは小さな声で呟いた。
「……自分でも、何が気に入らなかったのか、分からない」
予想していたよりも彼女の返答が的確だったから、僕は少しだけ安心した。どうやら完全に感情的になっているわけではないみたいだ。きちんと理性的な判断をしたうえで、それでも自分の感情を優先しようとしているらしい。
「君が怒っている原因は、なんとなく分かるよ」僕は話した。同時にインスタントコーヒーの粉末が入った瓶の蓋を閉め、カップにお湯を注ぐ。水はここに戻ってくる途中で注いで、すでに沸かしてあった。「でも……。きっとそれは、君の勝手な思い込みにすぎない。僕の本心を覗いたわけじゃないんだから。……いや、たとえ僕の本心を覗くことができても、君が本当にそれを理解することはできないだろうね。そういうものだよ、人との関係ってさ」
「……じゃあ、どうやって解決するの?」
「解決できるのは君だけだ。それは君の課題であって、僕の課題ではない」
「無理」
「何が?」
「自分の間違いを認めるなんて」
リィルは真剣に言っているのだろうが、僕は可笑しくて仕方がなかった。
僕が笑い声を零したのに反応して、リィルは再び僕を睨む。
「どうして、そんな簡単に笑うの?」
「ごめん、悪かったよ。僕の癖なんだ。許してほしい」
リィルはまた顔を背ける。
液体が入ったカップをスプーンでかき混ぜ、僕はそれを一口啜る。渋さは感じず、リラックスできる程度の薄味だった。
リィルに構うのはここまでにすることにして、僕は本を開く。
彼女も僕も、まだまだ幼い。身体的には成熟しているが、精神的に成熟しているかと問われたら、頷くことができる自信はない。少なくとも僕はそうだ。そうした大人になるための過程をスキップして、今日までそれっぽく生きてきてしまった。そして、スキップした過程はもう二度と取り返すことはできない。だから、今後もいわゆる「大人」を演じていくことしかできないのだ。他人が見るのは表面的な僕でしかないから、それでも特に問題はないだろう。
ただ、僕とリィルの二人の間で生じる問題には、他人は誰も介入してくれない。だから自分たちで解決するしかない。この幼稚な頭を駆使して自分たちなりの答えを見つけ出さなくてはならない。
もちろん、それは骨の折れる作業になるだろう。もしかしたら、最後まで答えなんて見つけられないかもしれない。
それでも……。
リィルとなら上手くやっていける感覚が僕にはある。
それは、彼女と出会ったときから感じていたものだ。
これは果たして運命だろうか?
……もしかするとそうかもしれない。現段階では、否定する根拠よりも、肯定する根拠の方が勢力が勝っている。たぶん、それは一般的な場合とは真逆の構図だろう。あくまで僕とリィルの関係が特殊というだけだ。
リィルはそのまま沈黙してしまった。もしかすると眠ってしまったのかもしれない。
僕は立ち上がり、リィルの身体に毛布をかける。季節に関わらず、何もかけずに寝ると風邪を引く。まるで年齢に関係なく怪獣が好きな僕みたいだ。
何の反応もしないリィルをそのままにして、立ち上がった序に僕は窓の外を見た。すでに午後九時を過ぎているから、空は真っ暗になっている。見上げると、真っ黒な天蓋に星がいくつも煌めいていた。ここからでは月は見えないが、きっとどこかに昇っているはずだ。
目の前には公園がある。僕たちが住む町にあるものとは雰囲気は異なるが、閉鎖された空間という共通点だけでも、そこは長閑な場所のように見える。
公園と夜空。
それら二つの要素が相まって、僕の頭は昔のことを思い出した。
リィルと初めて出会ったとき、僕は丘の上にある公園にいた。そしてもちろん時刻は深夜。そのときはまだ背の低かった僕には、リィルの長い手脚がとても美しく見えた。
僕と彼女の関係はその瞬間から始まったといっても良いが、傍から見たら関係の性質は大分変わったように映るに違いない。しかしながら、それは外見の変化から抱くイメージの差にすぎないだろう。実際のところは、僕とリィルの関係はそこまで変化していない。変化がない、つまりは成長がなくて困るほどではないが、その根幹にあるものは何一つとして変わっていないといって良い。
人間に似ていながらも異なる性質を帯びたリィルが、そのときの僕にはとても魅力的に見えた。自分とは程遠い存在であるようにも、それでいて手を伸ばせば届くような存在にも、そのどちらにも思えたのだ。言い換えれば、それは僕が彼女との間に差を感じていたということでもある。自分と彼女が異なるものだと思っていたのだ。
けれど、それは違った。あとになって、僕は自分も彼女と同類であることを知った。その事実が判明したときは何の驚きも抱かなかったが、時間が経つに連れて徐々に動揺するようになった。もちろん、今ではもう充分に受け留めきれていると思うが、ときどきそんな自分を不思議に感じることもある。
そして、それを不思議に感じるのには、きちんとした理由がある。
本当は不思議なのではない。
不思議という形に抽象化することで、真実を知る、もしくは再確認することを避けているのだ。
不思議という形に抽象化される前は、それは恐怖、あるいは不安、そんな形をしたものだった。
そう……。
今でも、その恐怖や不安の存在を必死に隠蔽しようとしている。
不思議だ、不思議だと繰り返すことで、本当のことを知るのを避けているのだ。
でも……。
きっとその恐怖や不安の温床には、ある一人の人物が存在している。それは理解しているし、揺らぎようのない事実だということも分かっている。
そして、僕たちの未来にはそのたった一人の人物が待っている。
真実を教えるために、いや……、真実に気がついたかどうかを確かめるために、待っているのだ。
だから……。
「ああ、もう、やめた」
背後から突然声が聞こえて、僕はゆっくりと後ろを振り返った。驚いたときに素直に驚きを表に出せないのは、僕の欠点であるのと同時に、長所ともいえる。
「一通りいじけて、気が済んだ?」僕は笑いながらリィルに尋ねる。
「何、その言い方?」
リィルは上半身だけをベッドから起こし、そのままの姿勢で僕を睨みつける。
「……なんか、ごめん」
態度はそのままだったが、リィルは謝った。
「何が?」僕は分からない振りをする。
「不機嫌で、ごめん」
「別に、いいよ。機嫌なんて、自分で制御できるものじゃないし」
リィルは顔を背け、少しだけ頰を膨らませる。
「それに……」
僕の言葉を聞いて、リィルは再び僕を見た。
「それに、何?」
「いや、うん……。……いつものことだな、と思って……」
部屋のドアがノックされ、僕とリィルの会話はそこで途切れた。僕は部屋の中を進み、鍵を解錠してドアを開く。
ドアの先にはウルスが立っていた。黒いコートに身を包み、小さな顔を上に向けて僕の顔を見ている。
「コンサートの時間です」
そう言って、ウルスは持っていた楽器ケースを軽く持ち上げた。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
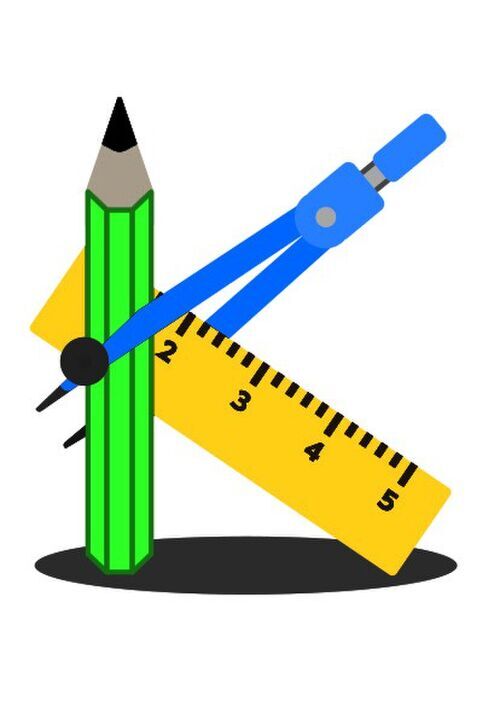
舞台装置は闇の中
羽上帆樽
ライト文芸
暗闇月夜は高校生になった。ここから彼女の物語は始まる。
行く先は不明。ただし、時間は常に人間の隣にあるが故に、進行を妨げることはできない。
毎日1000文字ずつ更新します。いつまで続くか分かりません。
終わりが不明瞭であるため、どこから入ってもらっても構いません。

45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる
よっしぃ
ファンタジー
2月26日から29日現在まで4日間、アルファポリスのファンタジー部門1位達成!感謝です!
小説家になろうでも10位獲得しました!
そして、カクヨムでもランクイン中です!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
スキルを強奪する為に異世界召喚を実行した欲望まみれの権力者から逃げるおっさん。
いつものように電車通勤をしていたわけだが、気が付けばまさかの異世界召喚に巻き込まれる。
欲望者から逃げ切って反撃をするか、隠れて地味に暮らすか・・・・
●●●●●●●●●●●●●●●
小説家になろうで執筆中の作品です。
アルファポリス、、カクヨムでも公開中です。
現在見直し作業中です。
変換ミス、打ちミス等が多い作品です。申し訳ありません。

日給二万円の週末魔法少女 ~夏木聖那と三人の少女~
海獺屋ぼの
ライト文芸
ある日、女子校に通う夏木聖那は『魔法少女募集』という奇妙な求人広告を見つけた。
そして彼女はその求人の日当二万円という金額に目がくらんで週末限定の『魔法少女』をすることを決意する。
そんな普通の女子高生が魔法少女のアルバイトを通して大人へと成長していく物語。

No One's Glory -もうひとりの物語-
はっくまん2XL
SF
異世界転生も転移もしない異世界物語……(. . `)
よろしくお願い申し上げます
男は過眠症で日々の生活に空白を持っていた。
医師の診断では、睡眠無呼吸から来る睡眠障害とのことであったが、男には疑いがあった。
男は常に、同じ世界、同じ人物の夢を見ていたのだ。それも、非常に生々しく……
手触り感すらあるその世界で、男は別人格として、「採掘師」という仕事を生業としていた。
採掘師とは、遺跡に眠るストレージから、マップや暗号鍵、設計図などの有用な情報を発掘し、マーケットに流す仕事である。
各地に点在する遺跡を巡り、時折マーケットのある都市、集落に訪れる生活の中で、時折感じる自身の中の他者の魂が幻でないと気づいた時、彼らの旅は混迷を増した……
申し訳ございませんm(_ _)m
不定期投稿になります。
本業多忙のため、しばらく連載休止します。


CREATED WORLD
猫手水晶
SF
惑星アケラは、大気汚染や森林伐採により、いずれ人類が住み続けることができなくなってしまう事がわかった。
惑星アケラに住む人類は絶滅を免れる為に、安全に生活を送れる場所を探す事が必要となった。
宇宙に人間が住める惑星を探そうという提案もあったが、惑星アケラの周りに人が住めるような環境の星はなく、見つける前に人類が絶滅してしまうだろうという理由で、現実性に欠けるものだった。
「人間が住めるような場所を自分で作ろう」という提案もあったが、資材や重力の方向の問題により、それも現実性に欠ける。
そこで科学者は「自分達で世界を構築するのなら、世界をそのまま宇宙に作るのではなく、自分達で『宇宙』にあたる空間を新たに作り出し、その空間で人間が生活できるようにすれば良いのではないか。」と。

【完結】年収三百万円台のアラサー社畜と総資産三億円以上の仮想通貨「億り人」JKが湾岸タワーマンションで同棲したら
瀬々良木 清
ライト文芸
主人公・宮本剛は、都内で働くごく普通の営業系サラリーマン。いわゆる社畜。
タワーマンションの聖地・豊洲にあるオフィスへ通勤しながらも、自分の給料では絶対に買えない高級マンションたちを見上げながら、夢のない毎日を送っていた。
しかしある日、会社の近所で苦しそうにうずくまる女子高生・常磐理瀬と出会う。理瀬は女子高生ながら仮想通貨への投資で『億り人』となった天才少女だった。
剛の何百倍もの資産を持ち、しかし心はまだ未完成な女子高生である理瀬と、日に日に心が枯れてゆくと感じるアラサー社畜剛が織りなす、ちぐはぐなラブコメディ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















