8 / 10
第8章 意気消沈
しおりを挟む
眼前には黒い水の流動。背後には新緑の大地。
約束の時間を迎えてから、すでに三十分以上が経過している。午後十一時に遊園地に向かうはずだったが、キャンプ場の前の道にぼうっと立ったまま、月夜はただ遠くの方を眺めていた。本当は、視界に映る景色など、まったく彼女の頭脳では処理されていない。それどころか、空間が存在しないことを証明するように、彼女の瞳には場所を規定する小道具の一つも映り込んでいなかった。
「いいのか、ずっとここにいて」
柵の上に座っているフィルが、月夜に向かって呟く。
月夜は目だけで彼を見る。
「よくないけど、今はいい」
「自分のためにか?」
「そう」
道を左に進めば階段があり、その先は海に繋がっている。どうして水へと至る部分に階段を作ったのか、作り手の真意は明らかではない。もともとは陸に続いていたが、時間が経つに連れて侵食されてしまったのかもしれない。
ここへ来たとき、月夜は、まず初めに、その階段を下りてみようかと考えた。なんとなく面白そうだったからだ。下まで行けば間違いなく靴やズボンが濡れるが、彼女にとってそんなことはどうでも良かった。
今日は、珍しく空に月が上っている。自分の名前と同じ状態が形成されていても、月夜は特に何の感情も抱かない。彼女は月夜という名前だが、月夜としてこの世に生まれてきたのではない。それは個人を区別するための記号にすぎず、彼女の性質を表す魔法の言葉ではない。
「俺だけでも、行こうか?」
フィルがまた尋ねる。
月夜はすぐには答えない。
波の音が、二、三度と木霊する。
「今は、傍にいてほしい」月夜は言った。「私のために、すぐ、傍に」
フィルは溜め息を吐く。
「分かったよ」
火花が待つ遊園地に向かう気になれなかったことに、深い理由はない。ただ、ここに着く前から、そこへは行きたくないと感じていた。彼女には、ときどきこういうことがある。自分でもそれが勝手な行動だと分かっているのに、どういうわけか、自制することができなくなってしまう。それくらい特定の行動をするのが嫌になる。無理をしてでもやるとか、最早そういうレベルではない。物理的に不可能、もしくはこの世の摂理に違反するというレベルで、手足が動かなくなってしまうのだ。
きっと火花は心配しているに違いない。トランシーバーは管理棟にあるから、月夜がそこに行くまで彼女と連絡をとることはできない。
フィルが提案したように、本当なら、彼だけでも火花のもとに向かわせて、事情を伝えるのが最善だった。けれど、今の月夜にはそれさえも許容できなかった。自分一人になりたくなくて、フィルについそう言ってしまった。フィルなら、遠く離れた場所にいる火花よりも、目の前にいる自分のことを優先するだろうことは、月夜には容易に想像できた。だから、彼女は確信犯といえる。結果が分かっていてわざとそういう判断をしたのだ。
顔を右に向けて、少し離れた場所にある工場を見る。
そこに行きたいと思った。
強烈に、そう感じた。
人間が常に酸素を欲しがるように、今の自分はそうすることを望んでいる。
月夜は、自分の胸の辺りが猛烈に苦しくなる感覚を覚えた。
まるで、針金で強く締めつけられるような痛みだ。
喉が閊えそうになり、締めるように自分の両手で首に触れる。
そのまましゃがみ込み、沈黙した。
「大丈夫か?」
柵の上から飛び降りて、フィルが月夜の傍に降り立つ。
月夜はどうにか頷く。
目に涙が滲み、やがて水滴となって、それは地面に染みを作る。
痛かった。
身体の内側が、圧迫されるように痛む。
苦しくて、少し声が漏れた。
フィルは月夜の脚と腹の間に潜り込み、彼女の頰に触れる。涙が彼の腕にも付着して、月光を反射してきらきらと輝いた。
「落ち着いて、深呼吸をするんだ」彼は言った。「楽になるように、想像しながら」
月夜は首を振る。
「できない」
「やってみるんだ」
月夜はもう一度首を振る。
人が抱える不安には、多くの場合原因がある。だからその原因を取り去ってしまえば、嘘のように不安な気持ちはなくなる。
しかしながら、中には理由や根拠のない不安というのもある。そのときには、原因が存在しないが故に解消する手段が見つからず、どうすることもできない。今の月夜はまさにそういう状態だった。抱いているのは不安ではないが、訳の分からない苦痛が彼女の内部に渦巻いている。
猛烈に、誰かに会いたくなった。
でも、その誰かが誰なのか、彼女には分からない。
火花?
それも、違う気がした。
誰にもどうすることもできないから、ただ時間が解決してくれるのを待つしかない。しかし、その経過する時間の内にも、彼女はずっと苦しみ続ける。
少しだけ、自殺をしたい人の気持ちが分かるような気がした。
けれど、死ぬわけにはいかない。
死んでしまえば、そんな苦しみさえも、感じることができなくなってしまう。
それでは駄目だ。
決して楽にはなれない。
そんな稚拙な考えが、どうにか彼女の意識を正常に保っている。
決して意識が朦朧としているわけではなかった。むしろ意識ははっきりしている。その分感覚も鋭敏になっているみたいで、余計に苦痛で仕方がなかった。
知らない誰かが、自分の中に潜んでいるような気がする。
苦痛はやがてそんな感覚へと昇華していき、月夜の意識を現実から乖離させようとする。
すぐ傍に誰かの足音が聞こえた。
息を吐きながら、月夜はゆっくりと顔を上げる。
細い四肢。
背の高い少女が月夜の傍で立ち止まる。
「……月夜さん?」
火花が立っていた。
「どうしたんですか?」
月夜は平静を装い、彼女の顔をじっと見つめる。瞳が涙で濡れているかもしれなかったが、そんなことを気にしていられる余裕はなかった。
「どうも、していない」月夜は呟く。「大丈夫」
火花は心配そうな目で月夜をじっと見つめる。それから片手を彼女に差し出した。
「なかなか来ないから、心配していたんです。どこか具合が悪いんですか?」
月夜は首を振る。
火花はフィルにも視線を向けたが、彼は薄く笑っただけで、何も口には出さなかった。
月夜は自身の腕を伸ばし、火花の掌に触れる。
その瞬間、今まで彼女を支配していた苦痛が霧散し、全身から溢れていた汗が嘘のように引いた。
火花に手を引かれたまま、月夜は夜の海水浴場を歩く。涼しい風が心地良い。足取りが覚束なくて、途中で何度か転びそうになったが、その度に火花が自分の重心を調節して助けてくれた。
「どうも、ありがとう」
歩きながら月夜は言った。
火花は彼女に顔を向け、いつも通りの笑顔で軽く頷いた。
遊園地の敷地内に入り、管理棟に向かった。いつもより一時間くらい遅れてしまったが、それについて火花は特に何も言わなかった。できる範囲のことをしてくれれば良いから、無理をする必要はないとだけ言われたから、月夜はとりあえず今日の分の作業を始めることにした。
火花は三角形のモニュメントへと消えていく。
残された時間はもうあまりない。
あと三日だった。
青い塔型のアトラクションがある方角へと向かい、途中で道を逸れて、その上にある緑色の直方体の橋に入った。今日はその一帯の掃除をすることになっている。そのあと、バイキングのメンテナンスをすることになっていたが、そこまでやらなくても良いと火花は言ってくれた。
橋の両側の壁は硝子張りになっていて、下や遠くの方を眺めることができる。
右手には、夜の街並みが広がっていた。海と都市が融合したような、そんな不思議な雰囲気が漂う空間だ。一方で左手には相変わらず遊園地の敷地が続いており、ここが意図的に作られた人工島であることを思い出させてくれる。
橋の上を歩きながら、箒で床を掃いていく。
「もう、大丈夫か?」月夜の肩の上で、フィルが尋ねた。
月夜は静かに頷く。
「火花が来てくれて、よかったな」
月夜はもう一度頷いた。
火花に会いたいと思ったわけではなかったが、彼女の手に触れた瞬間に、全身を支配していた緊張が離散したのは間違いなかった。それに伴って苦痛は消え去り、いたっていつも通りの自分を取り戻すことができた。
そんな経験は、彼女にとって特異ではなかった。何度も経験したことがあるわけではないが、どちらかというとその頻度は高いように思える。最近も、似たような症状がまったく見られなかったわけではない。今回ほど規模の大きいものではなかったが、よく似た症状が発現していたのは確かだった。
自分は、先ほど、何を恐れていたのだろう、と月夜は一人で考える。
今ではもう分からなくなっていた。ただ、その経験をしたことだけは覚えている。しかし、それだけでしかない。酷く抽象的な記憶で、その最中に起きた具体的なことは何一つとして彼女の記憶には残っていなかった。
「火花と、最後までいるつもりか?」
フィルに質問され、月夜は現実を再認識する。
「そう、約束したから」彼女は答える。「そのつもり」
「それでいいのか?」
月夜は視線を横に向け、フィルの姿を捉える。
「いいって、どういうこと?」
「あいつの運命を変えることは、たぶんお前にはできない」フィルは話した。「だから、あいつが最期を迎えるのを、お前は傍で見ていることになる。それで本当にいいのかと訊いているんだ」
「私に、耐えられるか、ということ?」
「そう」
月夜は再び下を向き、掃除を再開する。
「……分からない」
フィルはすぐには応えなかったが、首を傾けて、やがて自分の頰を月夜の頰に擦りつけた。
月夜もそれに応じる。
「お前がどんな判断をしても、俺はお前についていくだけだ」
月夜は頷く。
そして、少しだけ笑った。
「どうも、ありがとう」
フィルも薄く笑う。
「お前の笑顔は、自分では分かっていないかもしれないが、素敵だ」
月夜は真顔に戻る。
「そうかな?」
「ああ、そうさ」フィルは言った。「少なくとも、俺にとっては」
橋の手前側から向こう側に向かって歩く。箒と塵取りを持っていたが、それらが実際に使われることはあまりなかった。
橋には、足もとが硝子でスケルトンになっている部分がある。なぜそのようなデザインになっているのかは分からない。単純に、空中を歩いていると錯覚するための遊び心のつもりかもしれない。たしかに、透明な硝子を通して波打つ海の様子を見られるのは、不思議な感じがして面白かった。
作業は一時間ほどで終わった。バイキングの方も担当しなくてはならなかったが、今日はやめておいた。先ほどの自分の状態を鑑みて、無理をしないようにしようと思ったからだ。
管理棟まで戻ってきたが、火花はまだいなかった。トランシーバーをオンにして彼女に進捗状況を尋ねると、まだ終わりそうにないからカフェで待っていてほしいとの答えが返ってきた。それか、今彼女がいる三角形のモニュメントまで来ても良いとのことだ。どちらでも良かったが、火花の傍にいた方が良いと判断して、月夜は管理棟を出て彼女のもとへと向かった。
以前と同じように、モニュメントの入り口に立っただけで、自動的に扉が開かれた。真っ暗な階段を足もとに気をつけながら下り、火花が作業をしている空間へと辿り着く。
「お疲れ様でした」
少しだけ顔をこちらに向けて、火花が言った。
月夜は周囲にいくつかある椅子の内の一つを選んで、火花の左斜め後方に腰かける。
「順調?」
「ええ、おそらく」火花は答える。「このままのペースで進められれば、間違いなく期限内に終わらせることができます。これも月夜さんの協力のお陰です」
月夜の肩から飛び降り、フィルは部屋の中をぶらぶらし始める。精密機器が設置されているのだから、あまりうろちょろしないようにと月夜は言ったが、特に問題はないと火花に言われた。
「この遊園地のシステムが、完全に自動化されることで、どのような利益が得られるの?」
訊いても仕方がない質問だと思ったが、ほかに何も思いつかなかったので、月夜は火花に尋ねた。そんな社交辞令みたいなことを月夜が口にするのは、以前にはまったく見られなかった現象だが、最近になって彼女はそうしたことができるようになった。
「ええ、まずは、資金的な問題が改善されます」タイプを続けながら、火花は説明した。「簡単にいえば、人件費を賄う必要がなくなるということです。人間の社員を雇うのに一番資金を使いますから、それを最小限に抑えることができるようになるのは、施設としてもありがたい限りです」
「でも、それは、解雇される人がいる、ということじゃないの?」
「もちろんそうです。それは……、うーん、現代の社会ではあまり受け入れらないことかもしれませんが、私たちは、全体的な労働量を少なくすることを最大の目標としているのです。つまり……。えっと、この説明で伝わるのか分かりませんが、要するに、働かなくてもいい人の数を増やそうとしているわけです。遊ぶといったらちょっと違うかもしれませんが、まあ、労働以外のことに時間を費やせる人が増えれば、それは人類全体の利益に繋がると信じています」
「一部の人間が働けば、それでいいような未来を想定している、ということ?」
「その通りです」
火花の意見に対しては、どちらかというと、月夜は肯定的な立場だった。彼女の説明は正論で、異論の余地は認められない。ただ、それはあくまで理論であり、現実に適用できるかという問題は別にある。おそらく、火花たちはそのテストケースを実施しようとしているのだろう。大規模な社会で実施する前に、この遊園地という小規模な社会でデータをとろうとしている、とでもいえば良いだろうか。
「それ以外にも、沢山の利益が得られると考えています」火花は話す。「その一つとして、人間が管理を行う場合に比べて、ミスの発生件数が圧倒的に少なくなることが挙げられます。コンピューターですべてを制御する場合、ミスは予めミスとして発見されるので、予防線を張ることが容易になり、ミスがミスとして発生しにくくなるということです」
「人間よりも、機械の方が信用できる、と言いたいの?」
「抽象化してしまえば、そうです」
月夜は頷く。
「それは、そうかもしれない」
火花はこちらを振り返る。
しかし、彼女は少しだけ困ったような顔をした。
「……実は、その点については、私は肯定的ではないんです。……私は、どうしても人間を信じたいと思ってしまいます」
そんな火花の表情を見て、月夜は少し考える。
「個人の見解と、全体の見解では、性質が異なる、ということかな」
「ええ、そうです」火花は頷いた。「意見を述べる者の数が増えれば増えるほど、そこから出される結論は無味乾燥なものになり、人を人として扱いにくくなる傾向があります」
火花はまた正面に身体を戻す。
火花がタイプしている姿を眺めながら、月夜は今彼女が言ったことについて思考を巡らせた。
火花が言ったことは、たしかにその通りだといえる。自分と相手の二人の関係なら、一方はもう一方のことを考えるのに全力になれる。このタイプの関係は、人と人が結ぶ最も典型的かつ原始的なものだといえるだろう。友人や恋人がその代表例として挙げられるが、一方がもう一方を思うだけで良いのなら、その関係の質は必然的に高いものになる。
しかしながら、ある一人が組織全体の統括者であり、その一人が組織に属するすべての人間と関係を築くとなると、その一人と所属者一人一人の間に築かれる関係の質は、一対一の場合に比べて低くなる。さらに、それが組織と組織同士の関係へと発展すれば、もう相手を人として捉えなくなり、関係はより形式的なものになる。
報道では、まるで組織そのものが個人のように扱われることがある。本当は組織に所属する誰かが引き起こした不祥事であっても、組織という抽象的な存在が不祥事を引き起こしたかのように表現される。または、国は国として一纏まりにされ、そこに所属する個人は存在しないかのように扱われる。
国の政策、生態系の破壊、などと表現されることがあるが、国を作っているのは一人一人の人間だし、生態系を形作っているのも、また一つ一つの生物だ。後者なら、ある生態系に属する生物の何個体かが死に絶えたことを意味しているが、それを「生態系」の「破壊」という抽象度の高い言葉で表現することで、無味乾燥なものとして認識されやすくなる。
自分はどうだろう、と月夜は考える。
たしかに、そのような抽象化をしていないわけではない。ものを認識する際にグループ化して纏めようとするのは、人間の技能の一つであるといって良い。しかしながら、それをしてはならない場合もある。その場合の見極めが、自分にはいまいち上手くできていないような気がする。
自分は、本当に、人間というグループに属する一個体なのだろうか?
火花は、本当に、人間というグループに属する一個体なのだろうか?
本当は、自分は自分なのではないのか?
本当は、火花は火花なのではないのか?
火花が椅子から立ち上がり、月夜の傍まで近づいてきた。月夜は顔を上げる。
「終わりました」彼女は言った。「少し、散歩でもしませんか?」
月夜は頷いた。
一度管理棟に戻り、例によってチェックシートに今日の分の進捗状況を記しておいた。火花の作業については、このシートには記入されない。そもそも、そのような項目は存在しない。記入するのは主に月夜が担当する掃除とメンテナンスの類だけで、火花が担当しているプログラミングについては、表向きには組織全体の活動とは捉えられていないみたいだった。
遊園地の裏門に向かい、巨大な斜張橋を向こう側まで渡る。橋の上は風が強く吹きつけていて、春が近づいているものの、まだ少し肌寒く感じられた。
斜張橋の先には、今度は歩道橋のような曲がりくねった橋が存在する。その上に向かい、三人は途中で立ち止まって、そのまま遠くに見える海洋を眺めた。
酷く個人的な見解だが、月夜は、火花について、何もしていない彼女が一番綺麗だと思っていた。この場合の綺麗とは、エネルギーの消費量が少ないとか、無駄な行動が省かれているとか、そういう意味ではない。別の言葉で言い換えれば、似合っているという表現が最もよく当て嵌まる。何もしないでただ立っているだけの火花は、子どもの手に取られるのを待っている人形のように、彼女の雰囲気に非常にマッチしているように見えた。
「私……」
火花が唐突に声を出す。
しかし、それ以上の言葉はなかった。
「私、何?」
不思議に思って、月夜は尋ねる。
「いえ……。……何でもありません」
火花は黙って前方を眺め続ける。
珍しく、目の前の海を一艘の船が走るのが見えた。この時間帯は、そうした仕事に従事する者も休憩しているのか、あまり船が走っている様子を見かけることはない。
モノレールももう運行していなかった。すぐ傍に線路があるが、電車の走行音はまったく聞こえない。
「あと、二日ですね……」
火花は、先ほど口に出そうとしたのとは、明らかに違う言葉を放った。
月夜は、それを気にする素振りは見せずに、彼女の言葉に頷く。
「最後まで、自分に与えられた役割が全うできれば、これ以上ない幸せです」火花は言った。「でも……。……なんだか、欲が出てきしまったようです。……月夜さんと一緒にいられるのが、とても価値があることのように思えてきてしまって……」
月夜は、火花がそんなことを言うとは思っていなかったので、多少驚いた。彼女は、自分でそう言ったように、自分の役割を全うすることに全力をかけているように見えたからだ。自分と一緒にいるのを嬉しく思ってくれていることは、以前から分かっていたが、それが前者と対等なレベルに昇華されて捉えられることなど、あるはずがないと考えていたのだ。
「死にたく、ないの?」
月夜の言葉を聞いて、火花は笑う。
「いえ……。そんなふうに思うわけではありません。ただ、楽しいなと思っただけです」
「火花が、私とずっと一緒にいることを望むのなら、何か、考えてみるよ」
火花は月夜を見る。
「……どういう意味ですか?」
「そのままの意味」
沈黙。
「どんな方法を考えるんですか?」火花は笑いながら、月夜に質問する。
「火花が死なずに、私と一緒にいられる方法」
「どんなふうに、それを実現しますか?」
月夜は何通りか候補を思いついたが、実際に口にできたのは、一つだけだった。
「私も一緒に、火花と死ぬ」
火花は可笑しそうに笑った。
「月夜さんなら、きっとそんなことを言うと思いました」
「どうして?」
「なんとなく……」彼女は話す。「でも、それでは一緒にいることにはなりません。一緒に死んだだけです。命を失うタイミングが同じだっただけで、その状態が続くわけではありませんから……」
「火花が、一番したいことは、何?」
「私ですか?」
「うん」
「私は……」
火花はまた顔を上げ、遠くの方を眺め出す。困ったら景色に頼るというのが、彼女に見られる一つの行動パターンのように月夜には思えた。
やがて火花は首を振り、諦めたように小さな声で言った。
「やっぱり、私は自分の役割を全うしたい……。……それが、私が今まで生きてきた目的だからです」
「目的?」
「そう……。……きっと、その目的が明確だったからこそ、私は今まで生きてこられたんだと思います」
月夜は火花の言葉の意味を考える。
「……月夜さんは、何か、自分が生きる目的を決めていますか?」
火花に問われ、月夜は考える対象を変えた。しかし、何も思いつかなかった。
「何も、決めていない」
「そうですか……。でも、本当はそういうものなんだと思います。生きていく中で、自分自身で人生の意味や目的を決めていくのが正しいのでしょう。私の場合が特殊だっただけです。それは、ある意味では楽な人生だったのかもしれません」
歩道橋の先に進み、遊園地の反対側にある人工島へ渡った。こちらには住宅街が広がっているだけで、何も目立つものはない。
カーブした道をずっと無言で歩き続け、やがて遊園地の敷地の傍まで戻ってきた。
月は、もう傾きかけて、水平線の向こう側へ消えようとしている。
月夜の一歩前で立ち止まり、火花は振り返って挨拶をした。
「あと二日、よろしくお願いしますね」
返す言葉が見つからなくて、月夜はとりあえず頷く。
「そういえば、その最後の日には、花火が打ち上げられるみたいなんです」火花は笑顔で言った。「遊園地が開園している内に上がるみたいなので、それまでにすべての作業を終わらせられたら、一緒に見ませんか?」
「うん、いいよ」
「では、楽しみにしていますね」
「それが、火花が最後に望むこと?」
「ええ、そうです」彼女は笑顔で言った。「とても素敵な夜になると思いませんか?」
月夜は、もう一度頷いた。
月夜に背を向け、火花は遊園地の入り口へと向かっていく。彼女が敷地内に入ると、重たい音を立てて彼女の背後で門が自動的に閉まった。
今も、火花は、目標を定めた。そのために残りの二日を頑張ると、決心したのかもしれない。
「月夜は、彼女のために手を貸すのか?」
足もとでフィルが尋ねる。
月夜はその場にしゃがみ込み、フィルを抱き上げて言った。
「彼女のため、ではない」
約束の時間を迎えてから、すでに三十分以上が経過している。午後十一時に遊園地に向かうはずだったが、キャンプ場の前の道にぼうっと立ったまま、月夜はただ遠くの方を眺めていた。本当は、視界に映る景色など、まったく彼女の頭脳では処理されていない。それどころか、空間が存在しないことを証明するように、彼女の瞳には場所を規定する小道具の一つも映り込んでいなかった。
「いいのか、ずっとここにいて」
柵の上に座っているフィルが、月夜に向かって呟く。
月夜は目だけで彼を見る。
「よくないけど、今はいい」
「自分のためにか?」
「そう」
道を左に進めば階段があり、その先は海に繋がっている。どうして水へと至る部分に階段を作ったのか、作り手の真意は明らかではない。もともとは陸に続いていたが、時間が経つに連れて侵食されてしまったのかもしれない。
ここへ来たとき、月夜は、まず初めに、その階段を下りてみようかと考えた。なんとなく面白そうだったからだ。下まで行けば間違いなく靴やズボンが濡れるが、彼女にとってそんなことはどうでも良かった。
今日は、珍しく空に月が上っている。自分の名前と同じ状態が形成されていても、月夜は特に何の感情も抱かない。彼女は月夜という名前だが、月夜としてこの世に生まれてきたのではない。それは個人を区別するための記号にすぎず、彼女の性質を表す魔法の言葉ではない。
「俺だけでも、行こうか?」
フィルがまた尋ねる。
月夜はすぐには答えない。
波の音が、二、三度と木霊する。
「今は、傍にいてほしい」月夜は言った。「私のために、すぐ、傍に」
フィルは溜め息を吐く。
「分かったよ」
火花が待つ遊園地に向かう気になれなかったことに、深い理由はない。ただ、ここに着く前から、そこへは行きたくないと感じていた。彼女には、ときどきこういうことがある。自分でもそれが勝手な行動だと分かっているのに、どういうわけか、自制することができなくなってしまう。それくらい特定の行動をするのが嫌になる。無理をしてでもやるとか、最早そういうレベルではない。物理的に不可能、もしくはこの世の摂理に違反するというレベルで、手足が動かなくなってしまうのだ。
きっと火花は心配しているに違いない。トランシーバーは管理棟にあるから、月夜がそこに行くまで彼女と連絡をとることはできない。
フィルが提案したように、本当なら、彼だけでも火花のもとに向かわせて、事情を伝えるのが最善だった。けれど、今の月夜にはそれさえも許容できなかった。自分一人になりたくなくて、フィルについそう言ってしまった。フィルなら、遠く離れた場所にいる火花よりも、目の前にいる自分のことを優先するだろうことは、月夜には容易に想像できた。だから、彼女は確信犯といえる。結果が分かっていてわざとそういう判断をしたのだ。
顔を右に向けて、少し離れた場所にある工場を見る。
そこに行きたいと思った。
強烈に、そう感じた。
人間が常に酸素を欲しがるように、今の自分はそうすることを望んでいる。
月夜は、自分の胸の辺りが猛烈に苦しくなる感覚を覚えた。
まるで、針金で強く締めつけられるような痛みだ。
喉が閊えそうになり、締めるように自分の両手で首に触れる。
そのまましゃがみ込み、沈黙した。
「大丈夫か?」
柵の上から飛び降りて、フィルが月夜の傍に降り立つ。
月夜はどうにか頷く。
目に涙が滲み、やがて水滴となって、それは地面に染みを作る。
痛かった。
身体の内側が、圧迫されるように痛む。
苦しくて、少し声が漏れた。
フィルは月夜の脚と腹の間に潜り込み、彼女の頰に触れる。涙が彼の腕にも付着して、月光を反射してきらきらと輝いた。
「落ち着いて、深呼吸をするんだ」彼は言った。「楽になるように、想像しながら」
月夜は首を振る。
「できない」
「やってみるんだ」
月夜はもう一度首を振る。
人が抱える不安には、多くの場合原因がある。だからその原因を取り去ってしまえば、嘘のように不安な気持ちはなくなる。
しかしながら、中には理由や根拠のない不安というのもある。そのときには、原因が存在しないが故に解消する手段が見つからず、どうすることもできない。今の月夜はまさにそういう状態だった。抱いているのは不安ではないが、訳の分からない苦痛が彼女の内部に渦巻いている。
猛烈に、誰かに会いたくなった。
でも、その誰かが誰なのか、彼女には分からない。
火花?
それも、違う気がした。
誰にもどうすることもできないから、ただ時間が解決してくれるのを待つしかない。しかし、その経過する時間の内にも、彼女はずっと苦しみ続ける。
少しだけ、自殺をしたい人の気持ちが分かるような気がした。
けれど、死ぬわけにはいかない。
死んでしまえば、そんな苦しみさえも、感じることができなくなってしまう。
それでは駄目だ。
決して楽にはなれない。
そんな稚拙な考えが、どうにか彼女の意識を正常に保っている。
決して意識が朦朧としているわけではなかった。むしろ意識ははっきりしている。その分感覚も鋭敏になっているみたいで、余計に苦痛で仕方がなかった。
知らない誰かが、自分の中に潜んでいるような気がする。
苦痛はやがてそんな感覚へと昇華していき、月夜の意識を現実から乖離させようとする。
すぐ傍に誰かの足音が聞こえた。
息を吐きながら、月夜はゆっくりと顔を上げる。
細い四肢。
背の高い少女が月夜の傍で立ち止まる。
「……月夜さん?」
火花が立っていた。
「どうしたんですか?」
月夜は平静を装い、彼女の顔をじっと見つめる。瞳が涙で濡れているかもしれなかったが、そんなことを気にしていられる余裕はなかった。
「どうも、していない」月夜は呟く。「大丈夫」
火花は心配そうな目で月夜をじっと見つめる。それから片手を彼女に差し出した。
「なかなか来ないから、心配していたんです。どこか具合が悪いんですか?」
月夜は首を振る。
火花はフィルにも視線を向けたが、彼は薄く笑っただけで、何も口には出さなかった。
月夜は自身の腕を伸ばし、火花の掌に触れる。
その瞬間、今まで彼女を支配していた苦痛が霧散し、全身から溢れていた汗が嘘のように引いた。
火花に手を引かれたまま、月夜は夜の海水浴場を歩く。涼しい風が心地良い。足取りが覚束なくて、途中で何度か転びそうになったが、その度に火花が自分の重心を調節して助けてくれた。
「どうも、ありがとう」
歩きながら月夜は言った。
火花は彼女に顔を向け、いつも通りの笑顔で軽く頷いた。
遊園地の敷地内に入り、管理棟に向かった。いつもより一時間くらい遅れてしまったが、それについて火花は特に何も言わなかった。できる範囲のことをしてくれれば良いから、無理をする必要はないとだけ言われたから、月夜はとりあえず今日の分の作業を始めることにした。
火花は三角形のモニュメントへと消えていく。
残された時間はもうあまりない。
あと三日だった。
青い塔型のアトラクションがある方角へと向かい、途中で道を逸れて、その上にある緑色の直方体の橋に入った。今日はその一帯の掃除をすることになっている。そのあと、バイキングのメンテナンスをすることになっていたが、そこまでやらなくても良いと火花は言ってくれた。
橋の両側の壁は硝子張りになっていて、下や遠くの方を眺めることができる。
右手には、夜の街並みが広がっていた。海と都市が融合したような、そんな不思議な雰囲気が漂う空間だ。一方で左手には相変わらず遊園地の敷地が続いており、ここが意図的に作られた人工島であることを思い出させてくれる。
橋の上を歩きながら、箒で床を掃いていく。
「もう、大丈夫か?」月夜の肩の上で、フィルが尋ねた。
月夜は静かに頷く。
「火花が来てくれて、よかったな」
月夜はもう一度頷いた。
火花に会いたいと思ったわけではなかったが、彼女の手に触れた瞬間に、全身を支配していた緊張が離散したのは間違いなかった。それに伴って苦痛は消え去り、いたっていつも通りの自分を取り戻すことができた。
そんな経験は、彼女にとって特異ではなかった。何度も経験したことがあるわけではないが、どちらかというとその頻度は高いように思える。最近も、似たような症状がまったく見られなかったわけではない。今回ほど規模の大きいものではなかったが、よく似た症状が発現していたのは確かだった。
自分は、先ほど、何を恐れていたのだろう、と月夜は一人で考える。
今ではもう分からなくなっていた。ただ、その経験をしたことだけは覚えている。しかし、それだけでしかない。酷く抽象的な記憶で、その最中に起きた具体的なことは何一つとして彼女の記憶には残っていなかった。
「火花と、最後までいるつもりか?」
フィルに質問され、月夜は現実を再認識する。
「そう、約束したから」彼女は答える。「そのつもり」
「それでいいのか?」
月夜は視線を横に向け、フィルの姿を捉える。
「いいって、どういうこと?」
「あいつの運命を変えることは、たぶんお前にはできない」フィルは話した。「だから、あいつが最期を迎えるのを、お前は傍で見ていることになる。それで本当にいいのかと訊いているんだ」
「私に、耐えられるか、ということ?」
「そう」
月夜は再び下を向き、掃除を再開する。
「……分からない」
フィルはすぐには応えなかったが、首を傾けて、やがて自分の頰を月夜の頰に擦りつけた。
月夜もそれに応じる。
「お前がどんな判断をしても、俺はお前についていくだけだ」
月夜は頷く。
そして、少しだけ笑った。
「どうも、ありがとう」
フィルも薄く笑う。
「お前の笑顔は、自分では分かっていないかもしれないが、素敵だ」
月夜は真顔に戻る。
「そうかな?」
「ああ、そうさ」フィルは言った。「少なくとも、俺にとっては」
橋の手前側から向こう側に向かって歩く。箒と塵取りを持っていたが、それらが実際に使われることはあまりなかった。
橋には、足もとが硝子でスケルトンになっている部分がある。なぜそのようなデザインになっているのかは分からない。単純に、空中を歩いていると錯覚するための遊び心のつもりかもしれない。たしかに、透明な硝子を通して波打つ海の様子を見られるのは、不思議な感じがして面白かった。
作業は一時間ほどで終わった。バイキングの方も担当しなくてはならなかったが、今日はやめておいた。先ほどの自分の状態を鑑みて、無理をしないようにしようと思ったからだ。
管理棟まで戻ってきたが、火花はまだいなかった。トランシーバーをオンにして彼女に進捗状況を尋ねると、まだ終わりそうにないからカフェで待っていてほしいとの答えが返ってきた。それか、今彼女がいる三角形のモニュメントまで来ても良いとのことだ。どちらでも良かったが、火花の傍にいた方が良いと判断して、月夜は管理棟を出て彼女のもとへと向かった。
以前と同じように、モニュメントの入り口に立っただけで、自動的に扉が開かれた。真っ暗な階段を足もとに気をつけながら下り、火花が作業をしている空間へと辿り着く。
「お疲れ様でした」
少しだけ顔をこちらに向けて、火花が言った。
月夜は周囲にいくつかある椅子の内の一つを選んで、火花の左斜め後方に腰かける。
「順調?」
「ええ、おそらく」火花は答える。「このままのペースで進められれば、間違いなく期限内に終わらせることができます。これも月夜さんの協力のお陰です」
月夜の肩から飛び降り、フィルは部屋の中をぶらぶらし始める。精密機器が設置されているのだから、あまりうろちょろしないようにと月夜は言ったが、特に問題はないと火花に言われた。
「この遊園地のシステムが、完全に自動化されることで、どのような利益が得られるの?」
訊いても仕方がない質問だと思ったが、ほかに何も思いつかなかったので、月夜は火花に尋ねた。そんな社交辞令みたいなことを月夜が口にするのは、以前にはまったく見られなかった現象だが、最近になって彼女はそうしたことができるようになった。
「ええ、まずは、資金的な問題が改善されます」タイプを続けながら、火花は説明した。「簡単にいえば、人件費を賄う必要がなくなるということです。人間の社員を雇うのに一番資金を使いますから、それを最小限に抑えることができるようになるのは、施設としてもありがたい限りです」
「でも、それは、解雇される人がいる、ということじゃないの?」
「もちろんそうです。それは……、うーん、現代の社会ではあまり受け入れらないことかもしれませんが、私たちは、全体的な労働量を少なくすることを最大の目標としているのです。つまり……。えっと、この説明で伝わるのか分かりませんが、要するに、働かなくてもいい人の数を増やそうとしているわけです。遊ぶといったらちょっと違うかもしれませんが、まあ、労働以外のことに時間を費やせる人が増えれば、それは人類全体の利益に繋がると信じています」
「一部の人間が働けば、それでいいような未来を想定している、ということ?」
「その通りです」
火花の意見に対しては、どちらかというと、月夜は肯定的な立場だった。彼女の説明は正論で、異論の余地は認められない。ただ、それはあくまで理論であり、現実に適用できるかという問題は別にある。おそらく、火花たちはそのテストケースを実施しようとしているのだろう。大規模な社会で実施する前に、この遊園地という小規模な社会でデータをとろうとしている、とでもいえば良いだろうか。
「それ以外にも、沢山の利益が得られると考えています」火花は話す。「その一つとして、人間が管理を行う場合に比べて、ミスの発生件数が圧倒的に少なくなることが挙げられます。コンピューターですべてを制御する場合、ミスは予めミスとして発見されるので、予防線を張ることが容易になり、ミスがミスとして発生しにくくなるということです」
「人間よりも、機械の方が信用できる、と言いたいの?」
「抽象化してしまえば、そうです」
月夜は頷く。
「それは、そうかもしれない」
火花はこちらを振り返る。
しかし、彼女は少しだけ困ったような顔をした。
「……実は、その点については、私は肯定的ではないんです。……私は、どうしても人間を信じたいと思ってしまいます」
そんな火花の表情を見て、月夜は少し考える。
「個人の見解と、全体の見解では、性質が異なる、ということかな」
「ええ、そうです」火花は頷いた。「意見を述べる者の数が増えれば増えるほど、そこから出される結論は無味乾燥なものになり、人を人として扱いにくくなる傾向があります」
火花はまた正面に身体を戻す。
火花がタイプしている姿を眺めながら、月夜は今彼女が言ったことについて思考を巡らせた。
火花が言ったことは、たしかにその通りだといえる。自分と相手の二人の関係なら、一方はもう一方のことを考えるのに全力になれる。このタイプの関係は、人と人が結ぶ最も典型的かつ原始的なものだといえるだろう。友人や恋人がその代表例として挙げられるが、一方がもう一方を思うだけで良いのなら、その関係の質は必然的に高いものになる。
しかしながら、ある一人が組織全体の統括者であり、その一人が組織に属するすべての人間と関係を築くとなると、その一人と所属者一人一人の間に築かれる関係の質は、一対一の場合に比べて低くなる。さらに、それが組織と組織同士の関係へと発展すれば、もう相手を人として捉えなくなり、関係はより形式的なものになる。
報道では、まるで組織そのものが個人のように扱われることがある。本当は組織に所属する誰かが引き起こした不祥事であっても、組織という抽象的な存在が不祥事を引き起こしたかのように表現される。または、国は国として一纏まりにされ、そこに所属する個人は存在しないかのように扱われる。
国の政策、生態系の破壊、などと表現されることがあるが、国を作っているのは一人一人の人間だし、生態系を形作っているのも、また一つ一つの生物だ。後者なら、ある生態系に属する生物の何個体かが死に絶えたことを意味しているが、それを「生態系」の「破壊」という抽象度の高い言葉で表現することで、無味乾燥なものとして認識されやすくなる。
自分はどうだろう、と月夜は考える。
たしかに、そのような抽象化をしていないわけではない。ものを認識する際にグループ化して纏めようとするのは、人間の技能の一つであるといって良い。しかしながら、それをしてはならない場合もある。その場合の見極めが、自分にはいまいち上手くできていないような気がする。
自分は、本当に、人間というグループに属する一個体なのだろうか?
火花は、本当に、人間というグループに属する一個体なのだろうか?
本当は、自分は自分なのではないのか?
本当は、火花は火花なのではないのか?
火花が椅子から立ち上がり、月夜の傍まで近づいてきた。月夜は顔を上げる。
「終わりました」彼女は言った。「少し、散歩でもしませんか?」
月夜は頷いた。
一度管理棟に戻り、例によってチェックシートに今日の分の進捗状況を記しておいた。火花の作業については、このシートには記入されない。そもそも、そのような項目は存在しない。記入するのは主に月夜が担当する掃除とメンテナンスの類だけで、火花が担当しているプログラミングについては、表向きには組織全体の活動とは捉えられていないみたいだった。
遊園地の裏門に向かい、巨大な斜張橋を向こう側まで渡る。橋の上は風が強く吹きつけていて、春が近づいているものの、まだ少し肌寒く感じられた。
斜張橋の先には、今度は歩道橋のような曲がりくねった橋が存在する。その上に向かい、三人は途中で立ち止まって、そのまま遠くに見える海洋を眺めた。
酷く個人的な見解だが、月夜は、火花について、何もしていない彼女が一番綺麗だと思っていた。この場合の綺麗とは、エネルギーの消費量が少ないとか、無駄な行動が省かれているとか、そういう意味ではない。別の言葉で言い換えれば、似合っているという表現が最もよく当て嵌まる。何もしないでただ立っているだけの火花は、子どもの手に取られるのを待っている人形のように、彼女の雰囲気に非常にマッチしているように見えた。
「私……」
火花が唐突に声を出す。
しかし、それ以上の言葉はなかった。
「私、何?」
不思議に思って、月夜は尋ねる。
「いえ……。……何でもありません」
火花は黙って前方を眺め続ける。
珍しく、目の前の海を一艘の船が走るのが見えた。この時間帯は、そうした仕事に従事する者も休憩しているのか、あまり船が走っている様子を見かけることはない。
モノレールももう運行していなかった。すぐ傍に線路があるが、電車の走行音はまったく聞こえない。
「あと、二日ですね……」
火花は、先ほど口に出そうとしたのとは、明らかに違う言葉を放った。
月夜は、それを気にする素振りは見せずに、彼女の言葉に頷く。
「最後まで、自分に与えられた役割が全うできれば、これ以上ない幸せです」火花は言った。「でも……。……なんだか、欲が出てきしまったようです。……月夜さんと一緒にいられるのが、とても価値があることのように思えてきてしまって……」
月夜は、火花がそんなことを言うとは思っていなかったので、多少驚いた。彼女は、自分でそう言ったように、自分の役割を全うすることに全力をかけているように見えたからだ。自分と一緒にいるのを嬉しく思ってくれていることは、以前から分かっていたが、それが前者と対等なレベルに昇華されて捉えられることなど、あるはずがないと考えていたのだ。
「死にたく、ないの?」
月夜の言葉を聞いて、火花は笑う。
「いえ……。そんなふうに思うわけではありません。ただ、楽しいなと思っただけです」
「火花が、私とずっと一緒にいることを望むのなら、何か、考えてみるよ」
火花は月夜を見る。
「……どういう意味ですか?」
「そのままの意味」
沈黙。
「どんな方法を考えるんですか?」火花は笑いながら、月夜に質問する。
「火花が死なずに、私と一緒にいられる方法」
「どんなふうに、それを実現しますか?」
月夜は何通りか候補を思いついたが、実際に口にできたのは、一つだけだった。
「私も一緒に、火花と死ぬ」
火花は可笑しそうに笑った。
「月夜さんなら、きっとそんなことを言うと思いました」
「どうして?」
「なんとなく……」彼女は話す。「でも、それでは一緒にいることにはなりません。一緒に死んだだけです。命を失うタイミングが同じだっただけで、その状態が続くわけではありませんから……」
「火花が、一番したいことは、何?」
「私ですか?」
「うん」
「私は……」
火花はまた顔を上げ、遠くの方を眺め出す。困ったら景色に頼るというのが、彼女に見られる一つの行動パターンのように月夜には思えた。
やがて火花は首を振り、諦めたように小さな声で言った。
「やっぱり、私は自分の役割を全うしたい……。……それが、私が今まで生きてきた目的だからです」
「目的?」
「そう……。……きっと、その目的が明確だったからこそ、私は今まで生きてこられたんだと思います」
月夜は火花の言葉の意味を考える。
「……月夜さんは、何か、自分が生きる目的を決めていますか?」
火花に問われ、月夜は考える対象を変えた。しかし、何も思いつかなかった。
「何も、決めていない」
「そうですか……。でも、本当はそういうものなんだと思います。生きていく中で、自分自身で人生の意味や目的を決めていくのが正しいのでしょう。私の場合が特殊だっただけです。それは、ある意味では楽な人生だったのかもしれません」
歩道橋の先に進み、遊園地の反対側にある人工島へ渡った。こちらには住宅街が広がっているだけで、何も目立つものはない。
カーブした道をずっと無言で歩き続け、やがて遊園地の敷地の傍まで戻ってきた。
月は、もう傾きかけて、水平線の向こう側へ消えようとしている。
月夜の一歩前で立ち止まり、火花は振り返って挨拶をした。
「あと二日、よろしくお願いしますね」
返す言葉が見つからなくて、月夜はとりあえず頷く。
「そういえば、その最後の日には、花火が打ち上げられるみたいなんです」火花は笑顔で言った。「遊園地が開園している内に上がるみたいなので、それまでにすべての作業を終わらせられたら、一緒に見ませんか?」
「うん、いいよ」
「では、楽しみにしていますね」
「それが、火花が最後に望むこと?」
「ええ、そうです」彼女は笑顔で言った。「とても素敵な夜になると思いませんか?」
月夜は、もう一度頷いた。
月夜に背を向け、火花は遊園地の入り口へと向かっていく。彼女が敷地内に入ると、重たい音を立てて彼女の背後で門が自動的に閉まった。
今も、火花は、目標を定めた。そのために残りの二日を頑張ると、決心したのかもしれない。
「月夜は、彼女のために手を貸すのか?」
足もとでフィルが尋ねる。
月夜はその場にしゃがみ込み、フィルを抱き上げて言った。
「彼女のため、ではない」
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

古り行く断片は虚空に消える
羽上帆樽
ファンタジー
●何時か? 何処か? 何か?
白い断片の降る世界。少女は歩いて海に向かった。前後の要素とは関係なく、それだけで独立して存在させられる要素。降っている最中の雪も然り。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。


日給二万円の週末魔法少女 ~夏木聖那と三人の少女~
海獺屋ぼの
ライト文芸
ある日、女子校に通う夏木聖那は『魔法少女募集』という奇妙な求人広告を見つけた。
そして彼女はその求人の日当二万円という金額に目がくらんで週末限定の『魔法少女』をすることを決意する。
そんな普通の女子高生が魔法少女のアルバイトを通して大人へと成長していく物語。

【完結】年収三百万円台のアラサー社畜と総資産三億円以上の仮想通貨「億り人」JKが湾岸タワーマンションで同棲したら
瀬々良木 清
ライト文芸
主人公・宮本剛は、都内で働くごく普通の営業系サラリーマン。いわゆる社畜。
タワーマンションの聖地・豊洲にあるオフィスへ通勤しながらも、自分の給料では絶対に買えない高級マンションたちを見上げながら、夢のない毎日を送っていた。
しかしある日、会社の近所で苦しそうにうずくまる女子高生・常磐理瀬と出会う。理瀬は女子高生ながら仮想通貨への投資で『億り人』となった天才少女だった。
剛の何百倍もの資産を持ち、しかし心はまだ未完成な女子高生である理瀬と、日に日に心が枯れてゆくと感じるアラサー社畜剛が織りなす、ちぐはぐなラブコメディ。
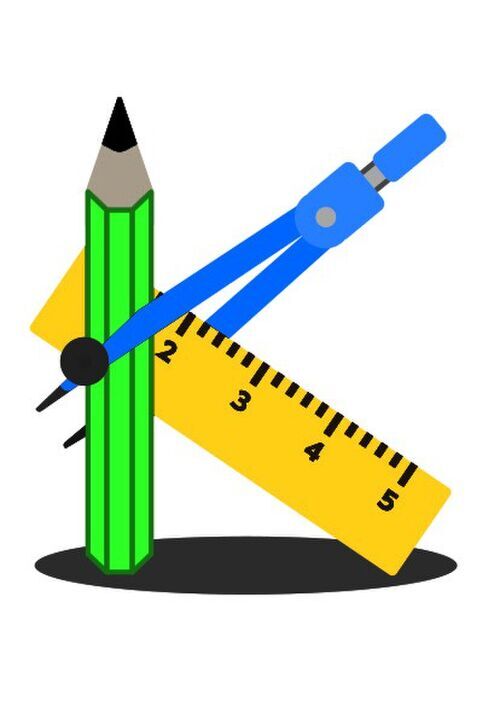
舞台装置は闇の中
羽上帆樽
ライト文芸
暗闇月夜は高校生になった。ここから彼女の物語は始まる。
行く先は不明。ただし、時間は常に人間の隣にあるが故に、進行を妨げることはできない。
毎日1000文字ずつ更新します。いつまで続くか分かりません。
終わりが不明瞭であるため、どこから入ってもらっても構いません。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















