5 / 5
第5話 解のAとB
しおりを挟む
ドアの向こう側は虚無だった。
虚像、虚栄、虚構……。これらの言葉が意味するところは、何だろう? 簡単に、「今、虚無だ」などと言ったりするが、そう言えることが、現状が虚無でないことの証明になっているのではないだろうか?
AとBは虚無の中へと入っていく。虚無に乗り出した。それで、二人の存在は消えたかのように思われたが、実際には消えていない。虚無を認識する主体が存在しなければ、虚無も存在しないからだ。したがって、ドアの向こう側を虚無だと認識するから、ドアの向こう側は虚無だということになる。
AとBは融合して、Nとなった。
「Nって、何のN?」 が尋ねる。
「さあ」 は首を捻った。「numberのNじゃないかな」
「あるいは、noun?」
「nounって、何?」 は質問する。
「knowの過去分詞形」
左右に本棚が並んでいる。そこから落ちた物か、床に本が散らばっていた。どれも古びている。表紙も中身も、すべて虫食い状態だった。
それらの中に、ただ、一つだけ、保存状態の良い本があった。
はしゃがんで、それを手に取る。表紙に被っていた埃を払った。
硬質な置き時計。その上に蛙の意匠が成されている。長針は十二を、短針は三を差していた。上方に拵えられた小窓が、蛙の口と一致している。そこが開き、中から長い舌が出されている。
は、表紙を開いて、次々にページを捲る。
一見すると、ページには何も書かれていないように見えたが、高速で開くことで、何らかの絵が浮かび上がってきた。それは、やはり、蛙の絵だった。あるいは、Nの絵?
「Nって、何?」
「何とも定められないから、Nなんだよ」 は説明する。「そうだって、数学で習ったでしょう?」
「それは、Xでは?」
「じゃあ、Nは整数かな」
「デジタルってこと?」
「数字はどこまでいってもデジタルだよ」
「デジタルすぎるってこと?」
「さあ……」 はそこで苦笑した。「デジタルすぎるって、何?」
指を鳴らせば、床に散らかった本たちは、一斉に棚の中へ収っていく。綺麗に整列するのだ。まるで細胞のように、それらは区分けされている。しかし、知識に区分けは存在しない。あらゆる要素を融合させることができる。そういう性質を持っているのだ。
それを忘れて生きている。
自分の存在も、また、区分けできない。
身に纏う空気の存在によって、常に自分は世界と繋がっている。
自分と世界の境界はない。
故に、すべて一つ。
Nの解は定数。
一だ。
「ここにあったんだ」 が言った。「やっと見つけた」
「何を?」
「すべて」
「そうか」
「そうだ」
「そうなのだ」
「そうであるのだ」
「そうであるのである」
「そうであるのであるのである」
「そうであるのであるのだ」
「そうであるのであるのなのだ」
「そうなのであるのであるのだ」
「そうか?」
「本当に、ここにすべてがある?」
「あるよ」
「ありそうな気もするし、なさそうな気もする」
「どっちでも同じだから」
背後から衝撃。
は後ろを振り返る。
古書店の小さな入り口を突き破って、船が室内に入ってきた。
「いやあ、まいりましたぜ、こりゃあ」甲板に仁王立ちした姿で、船長が言った。「どうやら、エンジン、いや、操縦系が故障してしまったみたいですぜい。勝手に動くもんで、どうしようもありません」
船が迫ってくる。
は立ち上がり、それを食べた。
古書店の外では雨が降っていた。隣にある街灯が、三人の足もとを小さく照らしている。
「お二人は、これから、どうするつもりなんです?」船長が尋ねた。
「どうも」 は答える。「帰るだけ」
「蛙だけに?」 は尋ねる。
「ひっくりかえるう」
;;;;;、と雨が降る。
:::::、と雨が降る。
雨を掻き分けて、向こうから巨大な影が。
飛び跳ね、飛び上がり、空中で一回転した。
蛙だった。
蛙は三人の前で立ち止まり、目をゆっくり上へと向ける。
挨拶のようだ。
二人は彼の上に乗る。
雨が降り注ぐ暗闇の中を、蛙はスピードを上げて駆けていく。
涼しかった。
冷たかった。
後ろを見ると、明かりの灯った古書店がみるみる離れていく。
そのとき、ドアが開いて、中から人影が。
細く尖った指が、ドアの縁を掴んでいる。
が隣を見ると、もう、そこには誰もいない。
も、船長も、いなかった。
自分も消えてしまおうか、と、 は考える。
そうだ。
初めから、何も存在していなかった。数字によって、言葉によって、存在していたかのように見えただけだ。世界はそのすべてを認識することができる。世界そのものに主体を認めることもできるだろう。
これは何だろう?
この、文字の羅列は何だろう?
うーん、何だろう?
何でも良いか。
それは、何でもあって、何でもない。
ただ、それ。
es。
何に見えるかは、分からない。
決まっていない。
そうだ、私も消えて、世界になろう。
そして、世界になったあとで、もう一度、私になろう。
それは、どちらでも、同じこと。
蛙は時を刻んでいる。
数字を刻んでいる。
でも、その鳴き声は、数字を刻んでいない。
音。
クロック・フロッグ。
声に出してみませんか?
虚像、虚栄、虚構……。これらの言葉が意味するところは、何だろう? 簡単に、「今、虚無だ」などと言ったりするが、そう言えることが、現状が虚無でないことの証明になっているのではないだろうか?
AとBは虚無の中へと入っていく。虚無に乗り出した。それで、二人の存在は消えたかのように思われたが、実際には消えていない。虚無を認識する主体が存在しなければ、虚無も存在しないからだ。したがって、ドアの向こう側を虚無だと認識するから、ドアの向こう側は虚無だということになる。
AとBは融合して、Nとなった。
「Nって、何のN?」 が尋ねる。
「さあ」 は首を捻った。「numberのNじゃないかな」
「あるいは、noun?」
「nounって、何?」 は質問する。
「knowの過去分詞形」
左右に本棚が並んでいる。そこから落ちた物か、床に本が散らばっていた。どれも古びている。表紙も中身も、すべて虫食い状態だった。
それらの中に、ただ、一つだけ、保存状態の良い本があった。
はしゃがんで、それを手に取る。表紙に被っていた埃を払った。
硬質な置き時計。その上に蛙の意匠が成されている。長針は十二を、短針は三を差していた。上方に拵えられた小窓が、蛙の口と一致している。そこが開き、中から長い舌が出されている。
は、表紙を開いて、次々にページを捲る。
一見すると、ページには何も書かれていないように見えたが、高速で開くことで、何らかの絵が浮かび上がってきた。それは、やはり、蛙の絵だった。あるいは、Nの絵?
「Nって、何?」
「何とも定められないから、Nなんだよ」 は説明する。「そうだって、数学で習ったでしょう?」
「それは、Xでは?」
「じゃあ、Nは整数かな」
「デジタルってこと?」
「数字はどこまでいってもデジタルだよ」
「デジタルすぎるってこと?」
「さあ……」 はそこで苦笑した。「デジタルすぎるって、何?」
指を鳴らせば、床に散らかった本たちは、一斉に棚の中へ収っていく。綺麗に整列するのだ。まるで細胞のように、それらは区分けされている。しかし、知識に区分けは存在しない。あらゆる要素を融合させることができる。そういう性質を持っているのだ。
それを忘れて生きている。
自分の存在も、また、区分けできない。
身に纏う空気の存在によって、常に自分は世界と繋がっている。
自分と世界の境界はない。
故に、すべて一つ。
Nの解は定数。
一だ。
「ここにあったんだ」 が言った。「やっと見つけた」
「何を?」
「すべて」
「そうか」
「そうだ」
「そうなのだ」
「そうであるのだ」
「そうであるのである」
「そうであるのであるのである」
「そうであるのであるのだ」
「そうであるのであるのなのだ」
「そうなのであるのであるのだ」
「そうか?」
「本当に、ここにすべてがある?」
「あるよ」
「ありそうな気もするし、なさそうな気もする」
「どっちでも同じだから」
背後から衝撃。
は後ろを振り返る。
古書店の小さな入り口を突き破って、船が室内に入ってきた。
「いやあ、まいりましたぜ、こりゃあ」甲板に仁王立ちした姿で、船長が言った。「どうやら、エンジン、いや、操縦系が故障してしまったみたいですぜい。勝手に動くもんで、どうしようもありません」
船が迫ってくる。
は立ち上がり、それを食べた。
古書店の外では雨が降っていた。隣にある街灯が、三人の足もとを小さく照らしている。
「お二人は、これから、どうするつもりなんです?」船長が尋ねた。
「どうも」 は答える。「帰るだけ」
「蛙だけに?」 は尋ねる。
「ひっくりかえるう」
;;;;;、と雨が降る。
:::::、と雨が降る。
雨を掻き分けて、向こうから巨大な影が。
飛び跳ね、飛び上がり、空中で一回転した。
蛙だった。
蛙は三人の前で立ち止まり、目をゆっくり上へと向ける。
挨拶のようだ。
二人は彼の上に乗る。
雨が降り注ぐ暗闇の中を、蛙はスピードを上げて駆けていく。
涼しかった。
冷たかった。
後ろを見ると、明かりの灯った古書店がみるみる離れていく。
そのとき、ドアが開いて、中から人影が。
細く尖った指が、ドアの縁を掴んでいる。
が隣を見ると、もう、そこには誰もいない。
も、船長も、いなかった。
自分も消えてしまおうか、と、 は考える。
そうだ。
初めから、何も存在していなかった。数字によって、言葉によって、存在していたかのように見えただけだ。世界はそのすべてを認識することができる。世界そのものに主体を認めることもできるだろう。
これは何だろう?
この、文字の羅列は何だろう?
うーん、何だろう?
何でも良いか。
それは、何でもあって、何でもない。
ただ、それ。
es。
何に見えるかは、分からない。
決まっていない。
そうだ、私も消えて、世界になろう。
そして、世界になったあとで、もう一度、私になろう。
それは、どちらでも、同じこと。
蛙は時を刻んでいる。
数字を刻んでいる。
でも、その鳴き声は、数字を刻んでいない。
音。
クロック・フロッグ。
声に出してみませんか?
0
お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説
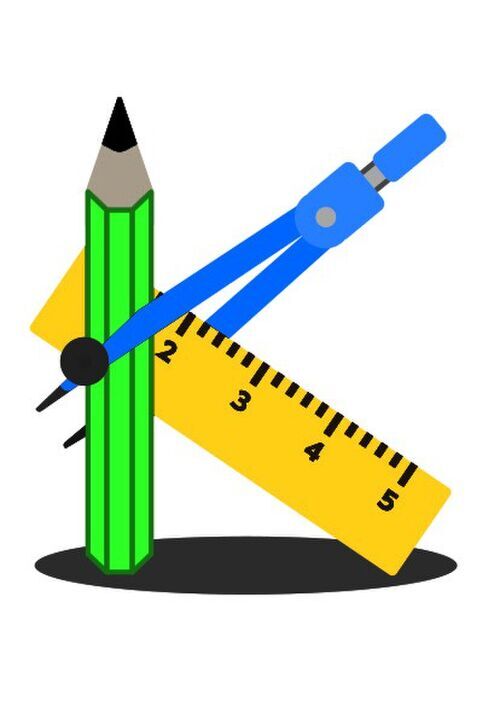
舞台装置は闇の中
羽上帆樽
ライト文芸
暗闇月夜は高校生になった。ここから彼女の物語は始まる。
行く先は不明。ただし、時間は常に人間の隣にあるが故に、進行を妨げることはできない。
毎日1000文字ずつ更新します。いつまで続くか分かりません。
終わりが不明瞭であるため、どこから入ってもらっても構いません。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。



看取り人
織部
ライト文芸
宗介は、末期癌患者が最後を迎える場所、ホスピスのベッドに横たわり、いずれ訪れるであろう最後の時が来るのを待っていた。
後悔はない。そして訪れる人もいない。そんな中、彼が唯一の心残りは心の底で今も疼く若かりし頃の思い出、そして最愛の人のこと。
そんな時、彼の元に1人の少年が訪れる。
「僕は、看取り人です。貴方と最後の時を過ごすために参りました」
これは看取り人と宗介の最後の数時間の語らいの話し

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















