4 / 5
第4話 従のAとB
しおりを挟む
Aが目を覚ますと、永遠なる空が頭の上に広がっていた。相変わらず雲に覆われ、太陽の光はない。涼しい風が吹いていた。身体を持ち上げようとして、持ち上がらないことに気づく。Bが上に乗っていたからだ。彼女はAの上で寝息を立てている。
Bを起こさないように、Aはそっと自分の上体を起こす。同時に、Bが彼の身体から滑り落ちて、呻き声を上げた。石か何かにぶつかったのかもしれない。
いつでもエンドレス。
世界はどこまでもエンドレス。
世界という言葉は嫌いだな、とAは思う。
気安く使って良い言葉ではないだろう。
「お目覚めですな」
隣から声が聞こえて、Aはそちらを見る。
船長が、パイプを咥えて座っていた。目だけでこちらを見ている。
「随分と長い間、眠っていましたぜい」
「随分って、どのくらい?」
「三日三晩ほど」船長は答える。「とっくに目的地は目の前でさあ」
そう言って、船長が正面を指さした。Aはそちらに視線を向ける。草原の向こうに、一つだけ、小屋のようなものが立っていた。ドアがあるだけで、窓はない。ドアの上に掲げられた看板に、ボールペンで書いたような字で「古書店」と書いてあった。冗談としか思えないが、はて、冗談とは何だろうかとAは思う。自分自身も冗談のような存在ではないか。
突発的に死を連想する。
発作といっても良い。
胸を押さえて、深く深呼吸をした。
地面に手をついて立ち上がり、掌に付着した土を払う。思わずそれがBの顔にかかってしまったことに、Aはすぐに気づいた。
Bが大きな目を開いて、Aを直視する。
レーザー光線とはこのことだ。
あるいは、ポインター?
「おはよう」Bが重たい声で言った。
「やあ、おはよう!」Aは高らかに応じる。「よく眠れたかなあ???」
「なんだ、それは」Bは立ち上がった。立ち眩みを起こすかもしれないと思われたが、予想は外れた。
「いや、君を怒らせたかな、と思って」
「怒らせたよ!」Bは手を伸ばし、Aの頬をつねる。「いつまで寝てるんだ、この野郎!」
Bに頬を引っ張られたまま、Aは草原の中を歩いた。手を繋いだことはあるが、頬を引っ張られるのは初めてだったから、なるほど、これが、と彼は思った。
草原、とは都合の良い言葉で、どのような草が生えているのか、どれくらいの密度で生えているのかということは、解釈する側にすべて委ねられる。それは、きっと、草原という言葉に限ったことではなく、すべての言葉に共通する。と、いう言葉にも共通するわけで、当然、言葉が集合した結果形成される、文や文章にも共通する。
存在とは何だろう?
?
?
?
このマークは、どうやって読むのが正解か?
ここに生えている草は、すべてススキの類だった。しかし、ススキは草といえるだろうかという思考を、Aは一秒間の内に千五十六回行った。それをカウントしたのはBだ。彼女はそうした補佐のために存在する。
「ここで、間違いないの?」Aは尋ねた。
「知らない」Bは答える。「でも、ほかに古書店なんて見つからないし」
「船長さんは、置いてきてよかったのかな」
「待ってるって言ってたよ」
「そうだっけ?」
「君が眠っている間に」
古書店に近づくにつれて、空から隕石が降ってくるようになり、二人がそこに辿り着くのを阻害した。ところで、距離と道のりの違いは、学校ではきちんと教えてくれない。そういう細かい部分が案外重要だったりする。公式を覚えることが学習ではない。公式の原理を知ることが学習だ。
緑色の軌跡。
あるいは、緑色の奇跡。
確率論で奇跡を論じることは可能か?
革命論で化石を講じることは化膿か?
ようやく古書店のドアの前に辿り着くと、ドアが一方的に開いた。からん、という音がする。ドアは開くだけで、その向こうから誰かが姿を現すことはない。
いつの間にか、空が真っ暗になっていた。雨が降り出しそうなほどだ。もう降り始めているかもしれない。見えないだけ、感じないだけで……。
「こうして生きている間にも、沢山の人が死んでいる」Bが言った。「それでも生きている自分に、嫌気が差す」
「あそう」Aは応じる。
「私は、どうしたらいい?」
「自分にできることをやるしかないのでは?」
「それは、逃げでは?」
「逃げではないと思うな。どうせ人は死ぬんだよ。すべてを救うことなんてできない。自分ができることをすれば、少量といえど、誰かを救うことはできるかもしれない。そういう人がいるかもしれない」
「根拠は?」
「ないよ。ただの言い分」
「あそう」
「小説や映画の類が、まさにその言い分に則ったものだよ」Aは言った。「でも、いつの時代も、そうしたものは確かに存在した。その事実を軽視することはできない」
「それが根拠?」
「そうかもしれない」
BはAの頬を離す。Aの頬は赤く染まっていた。
それは、つねられていたからではないかもしれないのだ。
世界はアナログで、言葉はデジタルだが、デジタルを用いて、アナログを予感させることができるのだ。
知っているだろう、のだ?
Bを起こさないように、Aはそっと自分の上体を起こす。同時に、Bが彼の身体から滑り落ちて、呻き声を上げた。石か何かにぶつかったのかもしれない。
いつでもエンドレス。
世界はどこまでもエンドレス。
世界という言葉は嫌いだな、とAは思う。
気安く使って良い言葉ではないだろう。
「お目覚めですな」
隣から声が聞こえて、Aはそちらを見る。
船長が、パイプを咥えて座っていた。目だけでこちらを見ている。
「随分と長い間、眠っていましたぜい」
「随分って、どのくらい?」
「三日三晩ほど」船長は答える。「とっくに目的地は目の前でさあ」
そう言って、船長が正面を指さした。Aはそちらに視線を向ける。草原の向こうに、一つだけ、小屋のようなものが立っていた。ドアがあるだけで、窓はない。ドアの上に掲げられた看板に、ボールペンで書いたような字で「古書店」と書いてあった。冗談としか思えないが、はて、冗談とは何だろうかとAは思う。自分自身も冗談のような存在ではないか。
突発的に死を連想する。
発作といっても良い。
胸を押さえて、深く深呼吸をした。
地面に手をついて立ち上がり、掌に付着した土を払う。思わずそれがBの顔にかかってしまったことに、Aはすぐに気づいた。
Bが大きな目を開いて、Aを直視する。
レーザー光線とはこのことだ。
あるいは、ポインター?
「おはよう」Bが重たい声で言った。
「やあ、おはよう!」Aは高らかに応じる。「よく眠れたかなあ???」
「なんだ、それは」Bは立ち上がった。立ち眩みを起こすかもしれないと思われたが、予想は外れた。
「いや、君を怒らせたかな、と思って」
「怒らせたよ!」Bは手を伸ばし、Aの頬をつねる。「いつまで寝てるんだ、この野郎!」
Bに頬を引っ張られたまま、Aは草原の中を歩いた。手を繋いだことはあるが、頬を引っ張られるのは初めてだったから、なるほど、これが、と彼は思った。
草原、とは都合の良い言葉で、どのような草が生えているのか、どれくらいの密度で生えているのかということは、解釈する側にすべて委ねられる。それは、きっと、草原という言葉に限ったことではなく、すべての言葉に共通する。と、いう言葉にも共通するわけで、当然、言葉が集合した結果形成される、文や文章にも共通する。
存在とは何だろう?
?
?
?
このマークは、どうやって読むのが正解か?
ここに生えている草は、すべてススキの類だった。しかし、ススキは草といえるだろうかという思考を、Aは一秒間の内に千五十六回行った。それをカウントしたのはBだ。彼女はそうした補佐のために存在する。
「ここで、間違いないの?」Aは尋ねた。
「知らない」Bは答える。「でも、ほかに古書店なんて見つからないし」
「船長さんは、置いてきてよかったのかな」
「待ってるって言ってたよ」
「そうだっけ?」
「君が眠っている間に」
古書店に近づくにつれて、空から隕石が降ってくるようになり、二人がそこに辿り着くのを阻害した。ところで、距離と道のりの違いは、学校ではきちんと教えてくれない。そういう細かい部分が案外重要だったりする。公式を覚えることが学習ではない。公式の原理を知ることが学習だ。
緑色の軌跡。
あるいは、緑色の奇跡。
確率論で奇跡を論じることは可能か?
革命論で化石を講じることは化膿か?
ようやく古書店のドアの前に辿り着くと、ドアが一方的に開いた。からん、という音がする。ドアは開くだけで、その向こうから誰かが姿を現すことはない。
いつの間にか、空が真っ暗になっていた。雨が降り出しそうなほどだ。もう降り始めているかもしれない。見えないだけ、感じないだけで……。
「こうして生きている間にも、沢山の人が死んでいる」Bが言った。「それでも生きている自分に、嫌気が差す」
「あそう」Aは応じる。
「私は、どうしたらいい?」
「自分にできることをやるしかないのでは?」
「それは、逃げでは?」
「逃げではないと思うな。どうせ人は死ぬんだよ。すべてを救うことなんてできない。自分ができることをすれば、少量といえど、誰かを救うことはできるかもしれない。そういう人がいるかもしれない」
「根拠は?」
「ないよ。ただの言い分」
「あそう」
「小説や映画の類が、まさにその言い分に則ったものだよ」Aは言った。「でも、いつの時代も、そうしたものは確かに存在した。その事実を軽視することはできない」
「それが根拠?」
「そうかもしれない」
BはAの頬を離す。Aの頬は赤く染まっていた。
それは、つねられていたからではないかもしれないのだ。
世界はアナログで、言葉はデジタルだが、デジタルを用いて、アナログを予感させることができるのだ。
知っているだろう、のだ?
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説


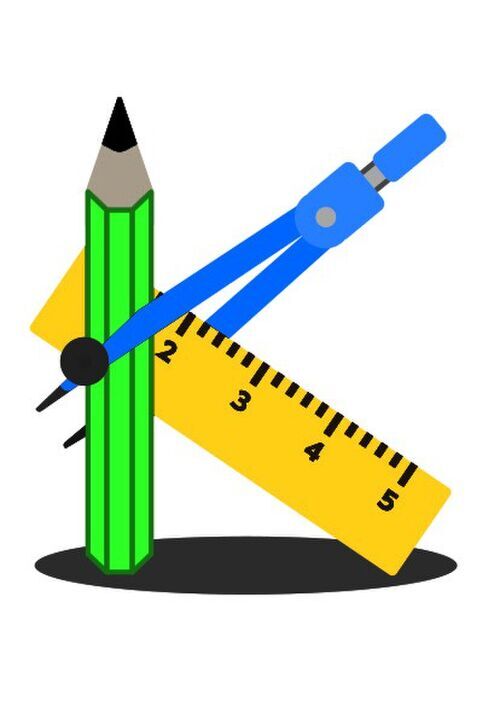
舞台装置は闇の中
羽上帆樽
ライト文芸
暗闇月夜は高校生になった。ここから彼女の物語は始まる。
行く先は不明。ただし、時間は常に人間の隣にあるが故に、進行を妨げることはできない。
毎日1000文字ずつ更新します。いつまで続くか分かりません。
終わりが不明瞭であるため、どこから入ってもらっても構いません。

十年目の結婚記念日
あさの紅茶
ライト文芸
結婚して十年目。
特別なことはなにもしない。
だけどふと思い立った妻は手紙をしたためることに……。
妻と夫の愛する気持ち。
短編です。
**********
このお話は他のサイトにも掲載しています

独り日和 ―春夏秋冬―
八雲翔
ライト文芸
主人公は櫻野冬という老女。
彼を取り巻く人と犬と猫の日常を書いたストーリーです。
仕事を探す四十代女性。
子供を一人で育てている未亡人。
元ヤクザ。
冬とひょんなことでの出会いから、
繋がる物語です。
春夏秋冬。
数ヶ月の出会いが一生の家族になる。
そんな冬と彼女を取り巻く人たちを見守ってください。
*この物語はフィクションです。
実在の人物や団体、地名などとは一切関係ありません。
八雲翔

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

黒蜜先生のヤバい秘密
月狂 紫乃/月狂 四郎
ライト文芸
高校生の須藤語(すとう かたる)がいるクラスで、新任の教師が担当に就いた。新しい担任の名前は黒蜜凛(くろみつ りん)。アイドル並みの美貌を持つ彼女は、あっという間にクラスの人気者となる。
須藤はそんな黒蜜先生に小説を書いていることがバレてしまう。リアルの世界でファン第1号となった黒蜜先生。須藤は先生でありファンでもある彼女と、小説を介して良い関係を築きつつあった。
だが、その裏側で黒蜜先生の人気をよく思わない女子たちが、陰湿な嫌がらせをやりはじめる。解決策を模索する過程で、須藤は黒蜜先生のヤバい過去を知ることになる……。

未来で待ってる
奈古七映
ライト文芸
とある地方の旧家の分家で養子として育った有希乃は、高三の春、自分が本家の跡取り娘と双子だと知らされる。その姉が重病だから代わりに跡を継げと言われた有希乃は、円満に断って平穏に分家で暮らし続ける道を養父や義兄と模索していた。
だが姉に会って、その考えは少しずつ変わっていく。
反発や嫉妬からはじまる姉妹の交流。揺れ動き、泣き笑い、葛藤を抱えながら、それぞれの17歳の夏は過ぎゆく……不思議な絆で結ばれた姉妹の交流と別れの物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















