5 / 5
第5部 描きたいと思う形
しおりを挟む
正面のドアが開いて、彼が手洗いから戻ってくる。ハンカチで濡れた手を拭きながら席についた。
「どうかした?」彼女を見て、彼は言った。「泣いている」
「え?」
彼女は自分の頬に触れる。確かに頬が濡れていた。彼女もハンカチを取り出して、その水分を拭う。
「普通に泣けるようになって、何より」彼は表情を変えないで話す。「食べたものが美味しすぎて、感動してしまった?」
「あのあと、どうしたの?」彼女は質問する。
「あのあとって?」
「私が君の身代わりになったあと」
「家に帰って、風呂に入って、眠った」彼は説明した。「それから、絵を一枚描いた。橙色で塗り潰しただけの絵。油絵の具を使って、筆で横方向に一塗りしたあと、今度はその上から縦方向に一塗りした。その工程を三度繰り返して、絵は完成した」
「一日にその工程を三度繰り返したの?」
「そうだよ」
「ただれるんじゃない?」
「たしかにぼろぼろになったけど、塗りたい気分だったから」そこで彼はコーヒーを啜る。「絵は、君が眠りに就いたあの場所に埋めておいた」
「奇麗だったね」
彼は静かに一度頷く。
絵はアナログな媒体で、一枚は一枚でしかない。それに対して、詩はどこまでで一つだろうか。詩には必ず間というものがあり、その間を補って読む。その間を媒介として、それぞれのパーツが組み合わされることで詩は形作られる。でも、その間という名の媒介に実態はないから、読む者によってパーツとパーツの組み合わせ方が異なる。絵ではありえないことだ。絵にはそもそもパーツが存在しないし、時間的な幅を伴った、そのパーツとパーツを組み合わせるという作業も行われない。
金銭を支払って、二人は喫茶店の外に出た。
外はもう暗くなっていた。
雪がちらついている。
裏通りを真っ直ぐ進んで、二人は大通りに戻ってくる。幅の広い川を横断する橋の上を歩いた。
橋を渡りきって後ろを振り返ると、もうそこに街はなかった。
今まで見ていたものは何だっただろう?
木の葉のトンネルを潜って、二人はもとの場所に戻ってくる。彼女が百年間眠っていた場所は、すでに木の葉が降り積もっていて、その跡は消えてしまっていた。
「また、眠るの?」彼が尋ねる。
「うん」
「そう」彼は言った。「じゃあ、彼によろしく」
彼女は直立の姿勢のままその場に倒れ込む。たちまち木の葉が周囲に舞い上がり、抵抗を受けて左右に揺れながら彼女の上に覆い被さった。
木々に残っていた木の葉がすべて振り落とされ、川のような流れを作った。葉の一部は彼女の身体を覆ったまま固定し、残った葉はすべて空気中に停滞した。空気中に浮かぶ葉の群れは、まず地面に対して平行に反時計回りに移動し、次に地面に対して垂直に時計回りに移動する。その工程が三度繰り返されたとき、世界は姿を変えた。いや、それは世界が姿を変えたのではない。回転する動きが世界を変えたのではなく、回転する動きを世界が生み出したのだ。
すべてを塗り替えて、
一枚の絵へ。
時間が伴ったすべてのプロセスを無視して、
一枚の絵へ。
絵を収める額縁すらも排除して、
一枚の絵へ。
空間が伴ったすべての広がりを無視して、
一枚の絵へ。
開いた目が捉えたのは、荒廃した大地にできた潤滑油の水溜まり。そして、自分の腹部に突き刺さった金属片と、涙だった。
張り付いた感触が頬にある。涙はもう乾いていた。
金属片は、実際には腹部に刺さっているのではない。刃の先はなかった。折れた断面が腹部の表面に接着しているだけだ。その先の刃は、一枚の絵を作るために使われた。そこから溢れ出した橙色の潤滑油をもって、世界は塗り替えられた。否、世界が塗り替えた。
顔を上げると、すぐ傍に彼の姿が見えた。
真っ直ぐこちらを見ている。
服も、何もかも、ぼろぼろ。
しかし、身体はなんともなさそうだった。
「大丈夫?」彼が言った。「今、外してあげよう」
彼が腕を伸ばして、彼女の腹部に引っ付いた金属片に触れる。触れただけでそれは地面に転がった。衣服は破れていたが、彼女も身体に傷はなかった。
腕が背後に回された。
沈黙。
彼女もなんとなく彼の背後へ腕を送る。
ふと視線を横にずらすと、彼の腕に巻かれた腕時計が目に入った。長針も、短針も、秒針も、すべて止まっている。
彼の頭ごしに顔を正面に向けると、灰色の大地が遙か向こうまで続いていた。
「もう、時間にも、空間にも縛られる必要はない」
彼が言った。
「ゆっくり、コーヒーを飲もう」
「私、誰?」彼女は尋ねる。
「知らないけど、誰か」
「有機? 無機?」
「どちらでも」
「そうか」
「そうだよ」
「私って、ぽんこつ?」
「全然」
「まだ、ぽんこつのまま?」
「まったく」
「生きてる?」
「生きてると、次々と変化していくんだ」
「変化していく?」
「矛盾も沢山生まれる」
「そう?」
「でもね、それは横に並べるからで、辺りに散らかせば、案外そんなこともないんだよ」
「どうかした?」彼女を見て、彼は言った。「泣いている」
「え?」
彼女は自分の頬に触れる。確かに頬が濡れていた。彼女もハンカチを取り出して、その水分を拭う。
「普通に泣けるようになって、何より」彼は表情を変えないで話す。「食べたものが美味しすぎて、感動してしまった?」
「あのあと、どうしたの?」彼女は質問する。
「あのあとって?」
「私が君の身代わりになったあと」
「家に帰って、風呂に入って、眠った」彼は説明した。「それから、絵を一枚描いた。橙色で塗り潰しただけの絵。油絵の具を使って、筆で横方向に一塗りしたあと、今度はその上から縦方向に一塗りした。その工程を三度繰り返して、絵は完成した」
「一日にその工程を三度繰り返したの?」
「そうだよ」
「ただれるんじゃない?」
「たしかにぼろぼろになったけど、塗りたい気分だったから」そこで彼はコーヒーを啜る。「絵は、君が眠りに就いたあの場所に埋めておいた」
「奇麗だったね」
彼は静かに一度頷く。
絵はアナログな媒体で、一枚は一枚でしかない。それに対して、詩はどこまでで一つだろうか。詩には必ず間というものがあり、その間を補って読む。その間を媒介として、それぞれのパーツが組み合わされることで詩は形作られる。でも、その間という名の媒介に実態はないから、読む者によってパーツとパーツの組み合わせ方が異なる。絵ではありえないことだ。絵にはそもそもパーツが存在しないし、時間的な幅を伴った、そのパーツとパーツを組み合わせるという作業も行われない。
金銭を支払って、二人は喫茶店の外に出た。
外はもう暗くなっていた。
雪がちらついている。
裏通りを真っ直ぐ進んで、二人は大通りに戻ってくる。幅の広い川を横断する橋の上を歩いた。
橋を渡りきって後ろを振り返ると、もうそこに街はなかった。
今まで見ていたものは何だっただろう?
木の葉のトンネルを潜って、二人はもとの場所に戻ってくる。彼女が百年間眠っていた場所は、すでに木の葉が降り積もっていて、その跡は消えてしまっていた。
「また、眠るの?」彼が尋ねる。
「うん」
「そう」彼は言った。「じゃあ、彼によろしく」
彼女は直立の姿勢のままその場に倒れ込む。たちまち木の葉が周囲に舞い上がり、抵抗を受けて左右に揺れながら彼女の上に覆い被さった。
木々に残っていた木の葉がすべて振り落とされ、川のような流れを作った。葉の一部は彼女の身体を覆ったまま固定し、残った葉はすべて空気中に停滞した。空気中に浮かぶ葉の群れは、まず地面に対して平行に反時計回りに移動し、次に地面に対して垂直に時計回りに移動する。その工程が三度繰り返されたとき、世界は姿を変えた。いや、それは世界が姿を変えたのではない。回転する動きが世界を変えたのではなく、回転する動きを世界が生み出したのだ。
すべてを塗り替えて、
一枚の絵へ。
時間が伴ったすべてのプロセスを無視して、
一枚の絵へ。
絵を収める額縁すらも排除して、
一枚の絵へ。
空間が伴ったすべての広がりを無視して、
一枚の絵へ。
開いた目が捉えたのは、荒廃した大地にできた潤滑油の水溜まり。そして、自分の腹部に突き刺さった金属片と、涙だった。
張り付いた感触が頬にある。涙はもう乾いていた。
金属片は、実際には腹部に刺さっているのではない。刃の先はなかった。折れた断面が腹部の表面に接着しているだけだ。その先の刃は、一枚の絵を作るために使われた。そこから溢れ出した橙色の潤滑油をもって、世界は塗り替えられた。否、世界が塗り替えた。
顔を上げると、すぐ傍に彼の姿が見えた。
真っ直ぐこちらを見ている。
服も、何もかも、ぼろぼろ。
しかし、身体はなんともなさそうだった。
「大丈夫?」彼が言った。「今、外してあげよう」
彼が腕を伸ばして、彼女の腹部に引っ付いた金属片に触れる。触れただけでそれは地面に転がった。衣服は破れていたが、彼女も身体に傷はなかった。
腕が背後に回された。
沈黙。
彼女もなんとなく彼の背後へ腕を送る。
ふと視線を横にずらすと、彼の腕に巻かれた腕時計が目に入った。長針も、短針も、秒針も、すべて止まっている。
彼の頭ごしに顔を正面に向けると、灰色の大地が遙か向こうまで続いていた。
「もう、時間にも、空間にも縛られる必要はない」
彼が言った。
「ゆっくり、コーヒーを飲もう」
「私、誰?」彼女は尋ねる。
「知らないけど、誰か」
「有機? 無機?」
「どちらでも」
「そうか」
「そうだよ」
「私って、ぽんこつ?」
「全然」
「まだ、ぽんこつのまま?」
「まったく」
「生きてる?」
「生きてると、次々と変化していくんだ」
「変化していく?」
「矛盾も沢山生まれる」
「そう?」
「でもね、それは横に並べるからで、辺りに散らかせば、案外そんなこともないんだよ」
0
お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説
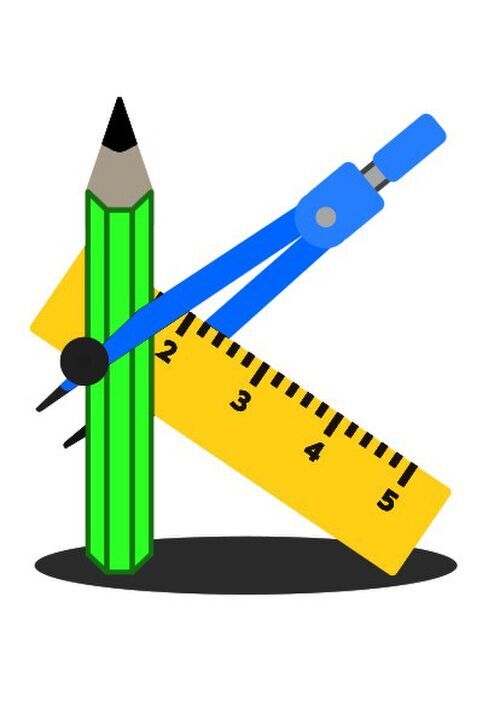
蜜柑製の死
羽上帆樽
現代文学
毎日500文字ずつ更新する詞です。その日の自分の状態が現れるだろうと予想します。上手くいく日もあれば、そうでない日もあるでしょう。どこから読んでも関係ありません。いつから知り合いになっても関係がないのと同じように。いつまで続くか未定です。続くまで続きます。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

可愛くて巨乳で幼馴染の彼女に耳かきしてもらうだけの話
湯島二雨
青春
大好きな彼女はとなりに住んでる幼馴染で、可愛いし巨乳。
そんな彼女と適当におしゃべりしたり、のんびりまったりと耳かきしてもらうだけのイチャラブライフ。
※小説家になろう、カクヨムでも公開しております。

Lily connect
加藤 忍
恋愛
学校でぼっちの四条遥華にはたった一人の親友がいた。どんな時もそばにいてくれた信頼できる友達。
ある日の放課後、ラブレターが下駄箱に入っていた。遥華はその相手に断りと言うつもりだった。
だけど指定された場所にいたのは親友の西野楓だった!?
高校生の同性愛を描いたラブストーリー
(性描写少なめ)

春を売る少年
凪司工房
現代文学
少年は男娼をして生計を立てていた。ある時、彼を買った紳士は少年に服と住処を与え、自分の屋敷に住まわせる。
何故そんなことをしたのか? 一体彼が買った「少年の春」とは何なのか? 疑問を抱いたまま日々を過ごし、やがて彼はある回答に至るのだが。
これは少年たちの春を巡る大人のファンタジー作品。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















