1 / 5
第1部 死にたいと思う心
しおりを挟む
朱色の木の葉。
金色の木の葉。
その上に、一人の少女が。
片腕を額の上に当てて、目を瞑ったまま微かに呼吸をしている。
正確には、それは少女ではなかったし、呼吸をしているのでもなかった。彼女はロボットだ。だから、見た目が人間に近いというだけだし、酸素と二酸化炭素の交換を行っていることに違いはないが、それは人間が行うのと異なるメカニズムによって成されていた。
辺り一帯は枯れ葉の絨毯。右を見ても、左を見ても、朱色と金色の地面がずっと続いている。頭の上には枝葉が生い茂り、もはや陽光は届かない。けれど、この場所はずっと暖かかった。暖かいから木の葉が生じるのか、それとも、木の葉の色が暖かさを生じさせるのか、判断はできない。する必要がないからと解釈するのが妥当だろうか。
僅かに、小鳥の声。
ぴ×3、と鳴いたかと思うと、またすぐに黙ってしまう。
時間の経過に従って、少女の身体の上に少しずつ木の葉が堆積していく。呼吸による胸部の上下動によって、葉のいくつかは地面に滑り落ちていく。木の葉は、もともと木々の枝に付随していたものだから、量に限りがあるはずだ。でも、それは延々と空から降ってくる。一見すると保存則を無視しているように思えるこの現象は、しかし、実はその法則のもとに成り立っている。つまりは、地面に落下した木の葉はやがて土に溶けて養分となり、一方で木は、その土から養分を吸い上げることでまた枝に葉を成らせる。ただし、この場所で生じるその一連のプロセスは、通常の場合に比べて進行速度が幾分速いようだった。
世界は、単純で、明快。
真理は、明快で、単純。
そこに書かれていることが本当に真理であるのなら、本のように分厚くなるはずがない。
一枚の紙に収まってしかるべき。
したがって、上の叙述は、きっと真理ではない。
では、真理はどこにあるのか?
それはもちろん、目の前で眠りに耽っている、その、少女に。
ピンポイントで瞼の上に落ちて来た木の葉に不快感を覚えて、少女は手でそれを払い退ける。良いタイミングだと、彼女はそこで目を開けた。彼女の目は、その中にもう一つ目があって、その中にもう一つ目があって、その中にもう一つ目があって、その中にもう一つ目がある、という構造をしている。たぶん、その中にももう一つ目があるに違いない。見ていると吸い込まれそうになる目だった。でも、見ていると吸い込みそうになる目ではない。彼女にそのつもりはなかった。
落ち葉の絨毯からゆっくりと身体を起こし、彼女は大きく伸びをする。途中で欠伸が零れ、伸ばしていた腕の一方を器用に屈めて、彼女は手で口を塞いだ。その間、瞼は閉じられていた。彼女がそのように典型的な動作しかできないのは、彼女がロボットだからではない。行動の趣向を自分で決定するくらいの能力は、ロボットの彼女にも備わっている。彼女がそんな動作しかできないのは、彼女がそんな動作しか知らないからだ。欠伸の仕方というものを誰にも倣ったことがないから。
衣服に付着していた葉を掌で払い、彼女は周囲を見渡す。首を動かすより先に目が動いた。何重にも重なっている彼女の目は、観察をスムーズに行うためにそうなっている。けれど、ほかの器官はその目についていけるほどのスペックを伴っていなかった。全体的に調整不足といえる。
彼女はぽんこつだった。
ぽんこつだから、この場所に捨てられた。
いや、自分で、自分の身を捨てた。
つまり、自分によって捨てられた自分。
死んだつもりだったが、また目を覚ましてしまった。
これも、またぽんこつのゆえ?
彼女は百年ほどそこにそうして横たわっていたが、そうする前と今とで、周囲の状況はほとんど変わっていなかった。木の葉の数は変わっているに違いない。しかし、木の葉で地面が覆われているという状態は変わらない。自分の姿もきっと変わらないだろう。
要するに、ぽんこつのまま。
落ち葉を掻き分ける音が背後から近づいてくる。高速で動く目で遠くを見ると、一人分の陰がこちらに向かってくるのが分かった。革でできた丈夫そうなコートを身に纏い、羊毛で編まれたマフラーを首からぶら下げている。片手に本を開き、ページに目を落としたままこちらに近づいてくる。一種のファッションのつもりかもしれない。
「やあ」彼女の前で立ち止まり、彼は本から顔を上げて言った。「随分と遅いお目覚めだね」
「おはよう」彼女は応える。「どのくらい眠ってたと思う?」
「百年」
「馬鹿みたいな数」
再び本に目を落とそうとした彼の意志を遮って、彼女は正面から彼に抱きつく。その影響で本の位置が高くなり、彼の目は文字を追えない状態になった。彼は人間だからだ。
「大好き」と彼女は言った。
「知ってる」と彼は応じる。
「どこへ行くところ?」
「どこって、君の所へ」彼は本を閉じた。「この先に洒落たカフェがあるんだ。一緒に行こう」
金色の木の葉。
その上に、一人の少女が。
片腕を額の上に当てて、目を瞑ったまま微かに呼吸をしている。
正確には、それは少女ではなかったし、呼吸をしているのでもなかった。彼女はロボットだ。だから、見た目が人間に近いというだけだし、酸素と二酸化炭素の交換を行っていることに違いはないが、それは人間が行うのと異なるメカニズムによって成されていた。
辺り一帯は枯れ葉の絨毯。右を見ても、左を見ても、朱色と金色の地面がずっと続いている。頭の上には枝葉が生い茂り、もはや陽光は届かない。けれど、この場所はずっと暖かかった。暖かいから木の葉が生じるのか、それとも、木の葉の色が暖かさを生じさせるのか、判断はできない。する必要がないからと解釈するのが妥当だろうか。
僅かに、小鳥の声。
ぴ×3、と鳴いたかと思うと、またすぐに黙ってしまう。
時間の経過に従って、少女の身体の上に少しずつ木の葉が堆積していく。呼吸による胸部の上下動によって、葉のいくつかは地面に滑り落ちていく。木の葉は、もともと木々の枝に付随していたものだから、量に限りがあるはずだ。でも、それは延々と空から降ってくる。一見すると保存則を無視しているように思えるこの現象は、しかし、実はその法則のもとに成り立っている。つまりは、地面に落下した木の葉はやがて土に溶けて養分となり、一方で木は、その土から養分を吸い上げることでまた枝に葉を成らせる。ただし、この場所で生じるその一連のプロセスは、通常の場合に比べて進行速度が幾分速いようだった。
世界は、単純で、明快。
真理は、明快で、単純。
そこに書かれていることが本当に真理であるのなら、本のように分厚くなるはずがない。
一枚の紙に収まってしかるべき。
したがって、上の叙述は、きっと真理ではない。
では、真理はどこにあるのか?
それはもちろん、目の前で眠りに耽っている、その、少女に。
ピンポイントで瞼の上に落ちて来た木の葉に不快感を覚えて、少女は手でそれを払い退ける。良いタイミングだと、彼女はそこで目を開けた。彼女の目は、その中にもう一つ目があって、その中にもう一つ目があって、その中にもう一つ目があって、その中にもう一つ目がある、という構造をしている。たぶん、その中にももう一つ目があるに違いない。見ていると吸い込まれそうになる目だった。でも、見ていると吸い込みそうになる目ではない。彼女にそのつもりはなかった。
落ち葉の絨毯からゆっくりと身体を起こし、彼女は大きく伸びをする。途中で欠伸が零れ、伸ばしていた腕の一方を器用に屈めて、彼女は手で口を塞いだ。その間、瞼は閉じられていた。彼女がそのように典型的な動作しかできないのは、彼女がロボットだからではない。行動の趣向を自分で決定するくらいの能力は、ロボットの彼女にも備わっている。彼女がそんな動作しかできないのは、彼女がそんな動作しか知らないからだ。欠伸の仕方というものを誰にも倣ったことがないから。
衣服に付着していた葉を掌で払い、彼女は周囲を見渡す。首を動かすより先に目が動いた。何重にも重なっている彼女の目は、観察をスムーズに行うためにそうなっている。けれど、ほかの器官はその目についていけるほどのスペックを伴っていなかった。全体的に調整不足といえる。
彼女はぽんこつだった。
ぽんこつだから、この場所に捨てられた。
いや、自分で、自分の身を捨てた。
つまり、自分によって捨てられた自分。
死んだつもりだったが、また目を覚ましてしまった。
これも、またぽんこつのゆえ?
彼女は百年ほどそこにそうして横たわっていたが、そうする前と今とで、周囲の状況はほとんど変わっていなかった。木の葉の数は変わっているに違いない。しかし、木の葉で地面が覆われているという状態は変わらない。自分の姿もきっと変わらないだろう。
要するに、ぽんこつのまま。
落ち葉を掻き分ける音が背後から近づいてくる。高速で動く目で遠くを見ると、一人分の陰がこちらに向かってくるのが分かった。革でできた丈夫そうなコートを身に纏い、羊毛で編まれたマフラーを首からぶら下げている。片手に本を開き、ページに目を落としたままこちらに近づいてくる。一種のファッションのつもりかもしれない。
「やあ」彼女の前で立ち止まり、彼は本から顔を上げて言った。「随分と遅いお目覚めだね」
「おはよう」彼女は応える。「どのくらい眠ってたと思う?」
「百年」
「馬鹿みたいな数」
再び本に目を落とそうとした彼の意志を遮って、彼女は正面から彼に抱きつく。その影響で本の位置が高くなり、彼の目は文字を追えない状態になった。彼は人間だからだ。
「大好き」と彼女は言った。
「知ってる」と彼は応じる。
「どこへ行くところ?」
「どこって、君の所へ」彼は本を閉じた。「この先に洒落たカフェがあるんだ。一緒に行こう」
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説
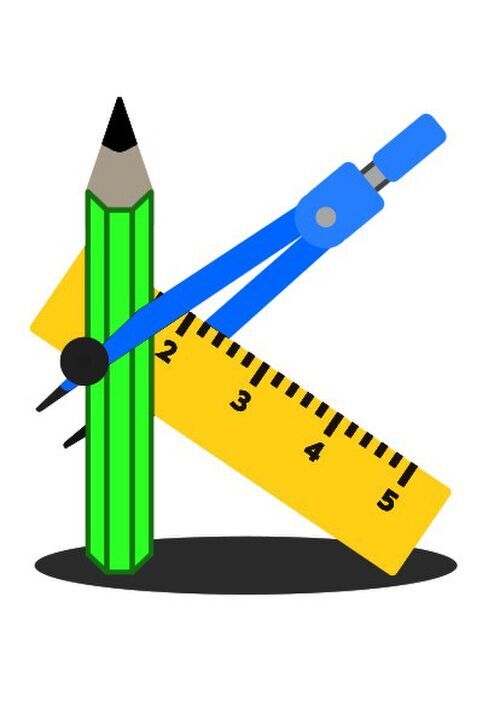
蜜柑製の死
羽上帆樽
現代文学
毎日500文字ずつ更新する詞です。その日の自分の状態が現れるだろうと予想します。上手くいく日もあれば、そうでない日もあるでしょう。どこから読んでも関係ありません。いつから知り合いになっても関係がないのと同じように。いつまで続くか未定です。続くまで続きます。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

Lily connect
加藤 忍
恋愛
学校でぼっちの四条遥華にはたった一人の親友がいた。どんな時もそばにいてくれた信頼できる友達。
ある日の放課後、ラブレターが下駄箱に入っていた。遥華はその相手に断りと言うつもりだった。
だけど指定された場所にいたのは親友の西野楓だった!?
高校生の同性愛を描いたラブストーリー
(性描写少なめ)

春を売る少年
凪司工房
現代文学
少年は男娼をして生計を立てていた。ある時、彼を買った紳士は少年に服と住処を与え、自分の屋敷に住まわせる。
何故そんなことをしたのか? 一体彼が買った「少年の春」とは何なのか? 疑問を抱いたまま日々を過ごし、やがて彼はある回答に至るのだが。
これは少年たちの春を巡る大人のファンタジー作品。

可愛くて巨乳で幼馴染の彼女に耳かきしてもらうだけの話
湯島二雨
青春
大好きな彼女はとなりに住んでる幼馴染で、可愛いし巨乳。
そんな彼女と適当におしゃべりしたり、のんびりまったりと耳かきしてもらうだけのイチャラブライフ。
※小説家になろう、カクヨムでも公開しております。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

台本保管所
赤羽根比呂
大衆娯楽
noteのマガジン『台本保管所』をこちらに引っ越し中です。
【明るめ・優しい感じ】【暗め・責める感じ】【朗読・呟く感じ】【恋文】【掛け合い・演じ分け】の大まかに五つのジャンルで構成してますので、好きな台本を読んでください。
※著作権は【赤羽根比呂】にありますがフリー台本なので、YouTubeやstand.fmなど音声投稿サイトなどでの公開は自由です!使用の際は、ご一報下されば聴きに行きます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















