7 / 11
7
しおりを挟む
「稲綱山の」
松井左馬丞が言った。
「子喰い猿を知っているか?」
「子喰い猿」
永吾は眉を上げた。
「よく大人が子供を怖がらせるあれか? 悪さをすると、稲綱山の子喰い猿が浚いにくるぞ、とかなんとか」
「そう、そいつだ。稲綱山の奥に昔から棲むと言われている」
「知っているぞ、俺も」
同輩の嶋東三郎が口をはさんだ。いつも笑っているような細い目をした丸顔の男だ。
「こんな話がある」
宿直のつれづれ、皆で詰め所の火鉢を囲んでのよもやま話だった。深まった秋の夜は、しんしんと冷えてきている。
「ある男が遠眼鏡を手に入れて、喜び勇んで稲綱山に登った。峰の高い所に立って、あちらこちらを眺め回していたそうだ。向こうの峰を見ると、一匹の猿がいる。そいつは両手で木の枝につかまって、楽しそうにぐるぐる回っていたというよ。やがて逆立ちしたり、宙返りしたり、曲芸じみたことをやりだした。男もおもしろくなって、ずっと猿を見ていたら、突然、遠眼鏡から猿が消えた」
「消えた?」
「ああ。男は遠眼鏡から目を離した。すると目の前に、たったいま遠眼鏡で眺めていた猿がにやりと牙をむきだして立っている。男と同じくらいの大きさで、金色の毛だ。男は悲鳴を上げて逃げ出した。あれは子喰い猿だったに違いないと、後になって人に話したそうだ。自分が子供だったら、取って喰われたところだったと」
「一瞬で峰を渡ったわけか」
永吾は半信半疑だった。
「子喰い猿はおそろしく俊足らしい」
うかない顔で左馬丞が言った。
「この頃は城下にまで下りて、子供を浚って行く」
「本当か? それは」
「嘘などつくものか。はじめは近在の村の子供が二人ばかりやられた。次は九軒町で、一昨日は田原町だ。田原町のは姉におぶわれた赤ん坊で、姉がはっきり大猿の姿を見ている」
左馬丞はさらに顔をしかめた。
「昔は二三年に一度、山里の子供が浚われたくらいだというが──困ったことだ」
左馬丞は小さな子供たちの父親だ。人ごとではないのだろう。永吾も頷いてやった。
「だが、なんでまたこんなしょっちゅう現れるようになったんだ?」
「わからん。町の子に味をしめたのか、人里近くに巣を変えたのか」
「昔とは違うやつかもしれんぞ」
東三郎が言った。
「昔はこう、なんというか愛嬌があったが、今のはただの人喰いだ」
永吾は腕組みしながら考えた。
矢兵衛は、この話を聞いているだろうか。
犬の矢兵衛は、今でもちょくちょく城下の夜に現れていた。永吾も矢兵衛の姿を求めてつい出歩いてしまう。
見かけても黙って遠目に眺めるだけにしていた。矢兵衛に卑屈な思いをさせたくなかったし、なにより悠然と夜気を裂いて駈ける白い獣は、一匹でいる時こそが美しい。
しかしまた、ともに戦えるかもしれない機会が訪れた。
矢兵衛と肩を並べて化けものに相対することは、とてつもない悦びだった。その時、永吾の命は矢兵衛と繋がっている。自分たちが、唯一ひとつになれる時なのだ。
くりかえす平凡な毎日に、矢兵衛の存在が耀きを与えてくれていた。たとえ死ぬことになろうとも、犬の矢兵衛が側にいてくれるなら満足だと思う。
評定橋の上で、永吾は矢兵衛と出会った。
永吾の姿を見ると矢兵衛は速歩をやめ、ゆっくりと近づいて来て永吾を見上げた。
「では、子喰い猿のことをご存じなのですね」
「矢兵衛もか?」
「店を開いていると様々な話が入ってきます」
「なるほど」
たしかに、町場の方が騒ぎが大きいにちがいない。
「隅倉さまがいらっしゃるころだとは思っていました」
永吾は笑みをこらえることができなかった。矢兵衛も同じく戦いを求め、自分を待っていてくれたのだ。
「で、どうする?」
「わたしなりに探ってみました。気になる場所がひとつ」
「どこだ?」
「稲綱山の入り口に、梅雲寺という廃寺があります。住職が死んだのはだいぶ前で、継ぐ者も無く荒れ果てたままになっているのですが、そこから新しい血の臭いがするのです」
「人間の?」
「はい」
「子喰い猿の塒なのだろうか」
「いかに子喰いが俊足でも、稲綱の山奥と城下では離れすぎていますから。そこを足場に、町に出入りしているのかもしれません」
「覗いてははみなかったのか」
「一人では危険かと」
「そうか」
永吾はゆっくりと頷いた。
「ならば、二人で行ってみるか」
「はい」
永吾と矢兵衛は顔を見合わせた。
互いのまなざしに、同じ渇望を見だした。
永吾は思わず矢兵衛の頭に手を伸ばしかけ、とどまって矢兵衛の脇にしゃがみ込んだ。目を同じ高さにして、
「よろしく頼む」
矢兵衛は頷き、軽く尾を動かした。
松井左馬丞が言った。
「子喰い猿を知っているか?」
「子喰い猿」
永吾は眉を上げた。
「よく大人が子供を怖がらせるあれか? 悪さをすると、稲綱山の子喰い猿が浚いにくるぞ、とかなんとか」
「そう、そいつだ。稲綱山の奥に昔から棲むと言われている」
「知っているぞ、俺も」
同輩の嶋東三郎が口をはさんだ。いつも笑っているような細い目をした丸顔の男だ。
「こんな話がある」
宿直のつれづれ、皆で詰め所の火鉢を囲んでのよもやま話だった。深まった秋の夜は、しんしんと冷えてきている。
「ある男が遠眼鏡を手に入れて、喜び勇んで稲綱山に登った。峰の高い所に立って、あちらこちらを眺め回していたそうだ。向こうの峰を見ると、一匹の猿がいる。そいつは両手で木の枝につかまって、楽しそうにぐるぐる回っていたというよ。やがて逆立ちしたり、宙返りしたり、曲芸じみたことをやりだした。男もおもしろくなって、ずっと猿を見ていたら、突然、遠眼鏡から猿が消えた」
「消えた?」
「ああ。男は遠眼鏡から目を離した。すると目の前に、たったいま遠眼鏡で眺めていた猿がにやりと牙をむきだして立っている。男と同じくらいの大きさで、金色の毛だ。男は悲鳴を上げて逃げ出した。あれは子喰い猿だったに違いないと、後になって人に話したそうだ。自分が子供だったら、取って喰われたところだったと」
「一瞬で峰を渡ったわけか」
永吾は半信半疑だった。
「子喰い猿はおそろしく俊足らしい」
うかない顔で左馬丞が言った。
「この頃は城下にまで下りて、子供を浚って行く」
「本当か? それは」
「嘘などつくものか。はじめは近在の村の子供が二人ばかりやられた。次は九軒町で、一昨日は田原町だ。田原町のは姉におぶわれた赤ん坊で、姉がはっきり大猿の姿を見ている」
左馬丞はさらに顔をしかめた。
「昔は二三年に一度、山里の子供が浚われたくらいだというが──困ったことだ」
左馬丞は小さな子供たちの父親だ。人ごとではないのだろう。永吾も頷いてやった。
「だが、なんでまたこんなしょっちゅう現れるようになったんだ?」
「わからん。町の子に味をしめたのか、人里近くに巣を変えたのか」
「昔とは違うやつかもしれんぞ」
東三郎が言った。
「昔はこう、なんというか愛嬌があったが、今のはただの人喰いだ」
永吾は腕組みしながら考えた。
矢兵衛は、この話を聞いているだろうか。
犬の矢兵衛は、今でもちょくちょく城下の夜に現れていた。永吾も矢兵衛の姿を求めてつい出歩いてしまう。
見かけても黙って遠目に眺めるだけにしていた。矢兵衛に卑屈な思いをさせたくなかったし、なにより悠然と夜気を裂いて駈ける白い獣は、一匹でいる時こそが美しい。
しかしまた、ともに戦えるかもしれない機会が訪れた。
矢兵衛と肩を並べて化けものに相対することは、とてつもない悦びだった。その時、永吾の命は矢兵衛と繋がっている。自分たちが、唯一ひとつになれる時なのだ。
くりかえす平凡な毎日に、矢兵衛の存在が耀きを与えてくれていた。たとえ死ぬことになろうとも、犬の矢兵衛が側にいてくれるなら満足だと思う。
評定橋の上で、永吾は矢兵衛と出会った。
永吾の姿を見ると矢兵衛は速歩をやめ、ゆっくりと近づいて来て永吾を見上げた。
「では、子喰い猿のことをご存じなのですね」
「矢兵衛もか?」
「店を開いていると様々な話が入ってきます」
「なるほど」
たしかに、町場の方が騒ぎが大きいにちがいない。
「隅倉さまがいらっしゃるころだとは思っていました」
永吾は笑みをこらえることができなかった。矢兵衛も同じく戦いを求め、自分を待っていてくれたのだ。
「で、どうする?」
「わたしなりに探ってみました。気になる場所がひとつ」
「どこだ?」
「稲綱山の入り口に、梅雲寺という廃寺があります。住職が死んだのはだいぶ前で、継ぐ者も無く荒れ果てたままになっているのですが、そこから新しい血の臭いがするのです」
「人間の?」
「はい」
「子喰い猿の塒なのだろうか」
「いかに子喰いが俊足でも、稲綱の山奥と城下では離れすぎていますから。そこを足場に、町に出入りしているのかもしれません」
「覗いてははみなかったのか」
「一人では危険かと」
「そうか」
永吾はゆっくりと頷いた。
「ならば、二人で行ってみるか」
「はい」
永吾と矢兵衛は顔を見合わせた。
互いのまなざしに、同じ渇望を見だした。
永吾は思わず矢兵衛の頭に手を伸ばしかけ、とどまって矢兵衛の脇にしゃがみ込んだ。目を同じ高さにして、
「よろしく頼む」
矢兵衛は頷き、軽く尾を動かした。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

慶安夜話
MIROKU
歴史・時代
慶安の江戸に現れた死者の行列。剣客の忍足数馬は死者の行列に挑むも、その魔性に引きこまれた。次いで死者の行列は遊女の店が並ぶ通りに現れた。そこには人斬りとあだ名される用心棒の蘭丸がいた…… 江戸を包む暗雲に蘭丸は挑む。かたわらの女が穏やかに眠れるように。

おとか伝説「戦国石田三成異聞」
水渕成分
歴史・時代
関東北部のある市に伝わる伝説を基に創作しました。
前半はその市に伝わる「おとか伝説」をですます調で、
後半は「小田原征伐」に参加した石田三成と「おとか伝説」の衝突について、
断定調で著述しています。
小説家になろうでは「おとか外伝『戦国石田三成異聞』」の題名で掲載されています。
完結済です。

人情落語家いろは節
朝賀 悠月
歴史・時代
浅草は浅草寺の程近くに、煮売茶屋がある。
そこの次男坊である弥平は、幼き頃より噺家になることを夢見ていた。
十五の歳、近くの神社で催された祭りに寄せ場が作られた。
素人寄席ながらも賑わいを見せるその中に、『鈴乃屋小蔵』と名乗る弥平が高座に上がる。
そこへ偶然居合わせた旗本の三男坊、田丸惣右衛門は鈴乃屋小蔵の人情噺をその目で見て、心の臓が打ち震えた。終演後に声を掛け、以来二人は友人関係を結ぶ。
半端物の弥平と惣右衛門。家柄は違えど互いを唯一無二と慕った。
しかし、惣右衛門にはどうしても解せないことがあった。
寄せ場に上がる弥平が、心の臓を射抜いた人情噺をやらなくなってしまったのだ……


名残雪に虹を待つ
小林一咲
歴史・時代
「虹は一瞬の美しさとともに消えゆくもの、名残雪は過去の余韻を残しながらもいずれ溶けていくもの」
雪の帳が静かに降り、時代の終わりを告げる。
信州松本藩の老侍・片桐早苗衛門は、幕府の影が薄れゆく中、江戸の喧騒を背に故郷へと踵を返した。
変わりゆく町の姿に、武士の魂が風に溶けるのを聴く。松本の雪深い里にたどり着けば、そこには未亡人となったかつての許嫁、お篠が、過ぎし日の幻のように佇んでいた。
二人は雪の丘に記憶を辿る。幼き日に虹を待ち、夢を語ったあの場所で、お篠の声が静かに響く——「まだあの虹を探しているのか」。早苗衛門は答えを飲み込み、過去と現在が雪片のように交錯する中で、自らの影を見失う。
町では新政府の風が吹き荒れ、藩士たちの誇りが軋む。早苗衛門は若者たちの剣音に耳を傾け、最後の役目を模索する。
やがて、幕府残党狩りの刃が早苗衛門を追い詰める。お篠の庇う手を振り切り、彼は名残雪の丘へ向かう——虹を待ったあの場所へ。
雪がやみ、空に淡い光が差し込むとき、追っ手の足音が近づく。
早苗衛門は剣を手に微笑み、お篠は遠くで呟く——「あなたは、まだ虹を待っていたのですね」
名残雪の中に虹がかすかに輝き、侍の魂は静かに最後の舞を舞った。

手児奈し思ほゆ
三谷銀屋
歴史・時代
万葉集にも詠われた伝説の美女「真間の手児奈」に題材をとった古代ファンタジー&バイオレンス小説。実らぬ初恋と復讐の物語。
下総国(今の千葉県)の国造(くにのみやつこ)の娘・手児奈と、手児奈に想いを寄せる墓守の男・阿止利……一度は引き裂かれた二人が再び出会う時、残酷な現実が二人の運命を飲み込んでいく。

魔斬
夢酔藤山
歴史・時代
深淵なる江戸の闇には、怨霊や妖魔の類が巣食い、昼と対なす穢土があった。
その魔を斬り払う闇の稼業、魔斬。
坊主や神主の手に負えぬ退魔を金銭で請け負う江戸の元締は関東長吏頭・浅草弾左衛門。忌むべき身分を統べる弾左衛門が最後に頼るのが、武家で唯一の魔斬人・山田浅右衛門である。昼は罪人の首を斬り、夜は怨霊を斬る因果の男。
幕末。
深い闇の奥に、今日もあやかしを斬る男がいる。
2023年オール讀物中間発表止まりの作品。その先の連作を含めて、いよいよ御開帳。
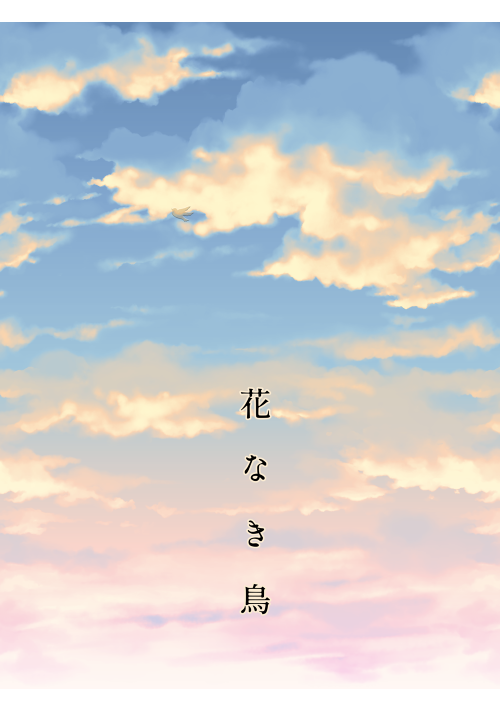
花なき鳥
紫乃森統子
歴史・時代
相添はん 雲のあはひの 彼方(をち)にても──
安政六年、小姓仕えのために城へ上がった大谷武次は、家督を継いで間もない若き主君の帰国に催された春の園遊会で、余興に弓を射ることになる。
武次の放った矢が的にある鳥を縫い留めてしまったことから、謹慎処分を言い渡されてしまうが──
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















