3 / 11
3
しおりを挟む
夜がしらみかけたころ、永吾は城下はずれの九軒町についた。
矢兵衛は、犬の姿で待っており、静かに永吾に近づいた。
永吾はあらためて矢兵衛を見つめた。
矢兵衛のもたげた頭は、永吾の腰のあたりまでとどく。
まったく、なんて見事な犬だろう。
冴えて冷たく光る二つの目は、黒曜石さながらだ。純白の毛色は燐光を放つかのよう、寸分の狂いなく均整のとれた肢体。
自分は魔であると矢兵衛は言ったが、たしかにこの世のものならぬ美しさだ。
手をのばし、やわらかな絹糸めいた毛並みに指を埋めたい衝動を、永吾はようやくこらえた。矢兵衛に申し訳ないような気がする。
「参りましょうか」
人の声で矢兵衛は言った。
「ああ」
永吾は、我にかえってうなずいた。
「行こう」
稲綱山の緑はいっそう深くなり、高い所ではほのかな色づきもあった。平地よりもずっと風が冷たくなっている。
永吾はハクを埋めた場所に寄って手を合わせた。
仇は必ずとってやると心に誓い、老婆の小屋に向かった。
矢兵衛は小屋が見える木陰で立ち止まった。老婆は外でなにやら仕事をしており、赤犬ものっそりと側にひかえている。
「あれでございますね」
矢兵衛は低く言った。
「ああ」
矢兵衛はしばらく一人と一匹を眺めていた。
やがて、鼻先に皺を寄せて永吾を見上げた。
「隅倉さま。あれを人だとお思いか?」
「なんだと」
「私と同じ、魔性の臭いがいたします。犬からも、老婆からも」
永吾は目を見ひらいた。どう見ても人間と犬なのだが、同類の矢兵衛が言うなら間違いあるまい。
「ハクは化けものに殺されたのか」
「赤犬は私だけでなんとかなると思います」
考え深げに矢兵衛は言った。
「しかし、二匹相手は難しい。婆の方をお願いできますか」
永吾は腰の刀に手を伸ばした。
「斬るか」
「相手は人間ではありません。簡単には斬れないかと」
「どうすればいい」
「喉笛を狙ってください。急所はそこしかありません。遅れを取っては反対に咬み殺されてしまいますから、ご注意を」
「わかった」
臆病者ではないつもりだ。永吾は大きくうなずいた。
「では」
矢兵衛は念を押すように永吾を見、一声吠えて、ためらいもなく木陰から飛び出した。
脇差しを抜き、永吾も後に続いた。
矢兵衛は一直線に赤犬に向かい、その首に噛みついた。
赤犬は大きく吠え、矢兵衛を振り払らう。二匹はもつれながら激しい咬み合いをはじめた。
驚いた老婆は、白髪を振り乱して、赤犬に加勢しようとした。永吾は老婆の腕をつかんで押し倒した。老婆はのけぞって、哀れっぽい声をたてた。
こんな年寄りを、とひるんでしまう。だが、矢兵衛の言葉を信じるしかなかった。これは、人間の姿をした化けものなのだ。
永吾は、思いきってその喉元に刃を突き刺した。
老婆は、ぎゃっと獣のような悲鳴をあげた。
のたうつ老婆の力は、もはや瀕死の年寄りのものではなかった。永吾をがむしゃらに押しのけようとする。永吾は夢中で老婆を抱え込んだ。
老婆の姿がみるみる毛深く、膨れあがっていった。
大きく口が裂け、むき出しになった牙が空を噛む。永吾はひるまず同じ場所を刺しつづけた。
と、弾けたような痙攣が走った。
それはぐったりと動かなくなった。
矢兵衛も、赤犬の喉を喰いちぎっていた。
永吾と矢兵衛は、肩で大きく息をして顔を見合わせた。
倒れているのは子牛ほどもある巨大な猫二匹だった。
血にそまった斑の毛は針金のように太く、尾が二つに割れている。何百年もの歳を経てきた猫又か。
ハクの命さえととらなければ、まだしばらくはこの山奥でぬくぬくと生きていられたものを。
永吾は猫又の前にどっかりと座り込んだ。
今回は忘れなかった火打ち袋を出し、煙管に火をつけた。
深々と煙を吐き出す。
矢兵衛に、さほどの怪我はないようだ。身体についた血糊をなめながら、うずくまって毛繕いをはじめた。
その目はうっとりと細められていた。
矢兵衛は、犬の姿で待っており、静かに永吾に近づいた。
永吾はあらためて矢兵衛を見つめた。
矢兵衛のもたげた頭は、永吾の腰のあたりまでとどく。
まったく、なんて見事な犬だろう。
冴えて冷たく光る二つの目は、黒曜石さながらだ。純白の毛色は燐光を放つかのよう、寸分の狂いなく均整のとれた肢体。
自分は魔であると矢兵衛は言ったが、たしかにこの世のものならぬ美しさだ。
手をのばし、やわらかな絹糸めいた毛並みに指を埋めたい衝動を、永吾はようやくこらえた。矢兵衛に申し訳ないような気がする。
「参りましょうか」
人の声で矢兵衛は言った。
「ああ」
永吾は、我にかえってうなずいた。
「行こう」
稲綱山の緑はいっそう深くなり、高い所ではほのかな色づきもあった。平地よりもずっと風が冷たくなっている。
永吾はハクを埋めた場所に寄って手を合わせた。
仇は必ずとってやると心に誓い、老婆の小屋に向かった。
矢兵衛は小屋が見える木陰で立ち止まった。老婆は外でなにやら仕事をしており、赤犬ものっそりと側にひかえている。
「あれでございますね」
矢兵衛は低く言った。
「ああ」
矢兵衛はしばらく一人と一匹を眺めていた。
やがて、鼻先に皺を寄せて永吾を見上げた。
「隅倉さま。あれを人だとお思いか?」
「なんだと」
「私と同じ、魔性の臭いがいたします。犬からも、老婆からも」
永吾は目を見ひらいた。どう見ても人間と犬なのだが、同類の矢兵衛が言うなら間違いあるまい。
「ハクは化けものに殺されたのか」
「赤犬は私だけでなんとかなると思います」
考え深げに矢兵衛は言った。
「しかし、二匹相手は難しい。婆の方をお願いできますか」
永吾は腰の刀に手を伸ばした。
「斬るか」
「相手は人間ではありません。簡単には斬れないかと」
「どうすればいい」
「喉笛を狙ってください。急所はそこしかありません。遅れを取っては反対に咬み殺されてしまいますから、ご注意を」
「わかった」
臆病者ではないつもりだ。永吾は大きくうなずいた。
「では」
矢兵衛は念を押すように永吾を見、一声吠えて、ためらいもなく木陰から飛び出した。
脇差しを抜き、永吾も後に続いた。
矢兵衛は一直線に赤犬に向かい、その首に噛みついた。
赤犬は大きく吠え、矢兵衛を振り払らう。二匹はもつれながら激しい咬み合いをはじめた。
驚いた老婆は、白髪を振り乱して、赤犬に加勢しようとした。永吾は老婆の腕をつかんで押し倒した。老婆はのけぞって、哀れっぽい声をたてた。
こんな年寄りを、とひるんでしまう。だが、矢兵衛の言葉を信じるしかなかった。これは、人間の姿をした化けものなのだ。
永吾は、思いきってその喉元に刃を突き刺した。
老婆は、ぎゃっと獣のような悲鳴をあげた。
のたうつ老婆の力は、もはや瀕死の年寄りのものではなかった。永吾をがむしゃらに押しのけようとする。永吾は夢中で老婆を抱え込んだ。
老婆の姿がみるみる毛深く、膨れあがっていった。
大きく口が裂け、むき出しになった牙が空を噛む。永吾はひるまず同じ場所を刺しつづけた。
と、弾けたような痙攣が走った。
それはぐったりと動かなくなった。
矢兵衛も、赤犬の喉を喰いちぎっていた。
永吾と矢兵衛は、肩で大きく息をして顔を見合わせた。
倒れているのは子牛ほどもある巨大な猫二匹だった。
血にそまった斑の毛は針金のように太く、尾が二つに割れている。何百年もの歳を経てきた猫又か。
ハクの命さえととらなければ、まだしばらくはこの山奥でぬくぬくと生きていられたものを。
永吾は猫又の前にどっかりと座り込んだ。
今回は忘れなかった火打ち袋を出し、煙管に火をつけた。
深々と煙を吐き出す。
矢兵衛に、さほどの怪我はないようだ。身体についた血糊をなめながら、うずくまって毛繕いをはじめた。
その目はうっとりと細められていた。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

慶安夜話
MIROKU
歴史・時代
慶安の江戸に現れた死者の行列。剣客の忍足数馬は死者の行列に挑むも、その魔性に引きこまれた。次いで死者の行列は遊女の店が並ぶ通りに現れた。そこには人斬りとあだ名される用心棒の蘭丸がいた…… 江戸を包む暗雲に蘭丸は挑む。かたわらの女が穏やかに眠れるように。
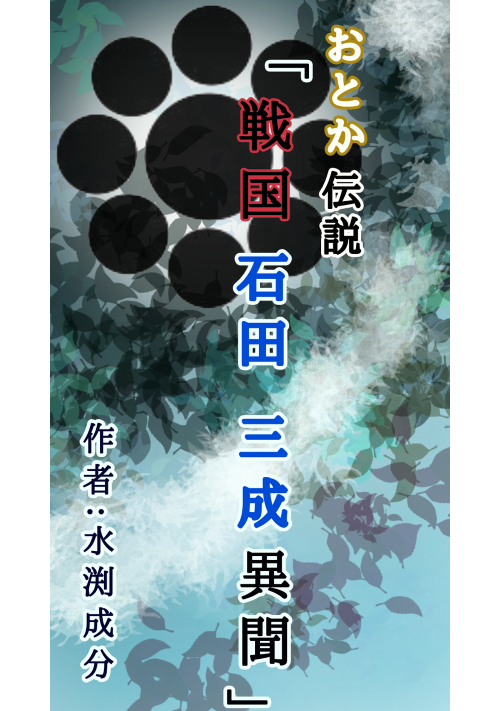
おとか伝説「戦国石田三成異聞」
水渕成分
歴史・時代
関東北部のある市に伝わる伝説を基に創作しました。
前半はその市に伝わる「おとか伝説」をですます調で、
後半は「小田原征伐」に参加した石田三成と「おとか伝説」の衝突について、
断定調で著述しています。
小説家になろうでは「おとか外伝『戦国石田三成異聞』」の題名で掲載されています。
完結済です。


人情落語家いろは節
朝賀 悠月
歴史・時代
浅草は浅草寺の程近くに、煮売茶屋がある。
そこの次男坊である弥平は、幼き頃より噺家になることを夢見ていた。
十五の歳、近くの神社で催された祭りに寄せ場が作られた。
素人寄席ながらも賑わいを見せるその中に、『鈴乃屋小蔵』と名乗る弥平が高座に上がる。
そこへ偶然居合わせた旗本の三男坊、田丸惣右衛門は鈴乃屋小蔵の人情噺をその目で見て、心の臓が打ち震えた。終演後に声を掛け、以来二人は友人関係を結ぶ。
半端物の弥平と惣右衛門。家柄は違えど互いを唯一無二と慕った。
しかし、惣右衛門にはどうしても解せないことがあった。
寄せ場に上がる弥平が、心の臓を射抜いた人情噺をやらなくなってしまったのだ……

名残雪に虹を待つ
小林一咲
歴史・時代
「虹は一瞬の美しさとともに消えゆくもの、名残雪は過去の余韻を残しながらもいずれ溶けていくもの」
雪の帳が静かに降り、時代の終わりを告げる。
信州松本藩の老侍・片桐早苗衛門は、幕府の影が薄れゆく中、江戸の喧騒を背に故郷へと踵を返した。
変わりゆく町の姿に、武士の魂が風に溶けるのを聴く。松本の雪深い里にたどり着けば、そこには未亡人となったかつての許嫁、お篠が、過ぎし日の幻のように佇んでいた。
二人は雪の丘に記憶を辿る。幼き日に虹を待ち、夢を語ったあの場所で、お篠の声が静かに響く——「まだあの虹を探しているのか」。早苗衛門は答えを飲み込み、過去と現在が雪片のように交錯する中で、自らの影を見失う。
町では新政府の風が吹き荒れ、藩士たちの誇りが軋む。早苗衛門は若者たちの剣音に耳を傾け、最後の役目を模索する。
やがて、幕府残党狩りの刃が早苗衛門を追い詰める。お篠の庇う手を振り切り、彼は名残雪の丘へ向かう——虹を待ったあの場所へ。
雪がやみ、空に淡い光が差し込むとき、追っ手の足音が近づく。
早苗衛門は剣を手に微笑み、お篠は遠くで呟く——「あなたは、まだ虹を待っていたのですね」
名残雪の中に虹がかすかに輝き、侍の魂は静かに最後の舞を舞った。

魔斬
夢酔藤山
歴史・時代
深淵なる江戸の闇には、怨霊や妖魔の類が巣食い、昼と対なす穢土があった。
その魔を斬り払う闇の稼業、魔斬。
坊主や神主の手に負えぬ退魔を金銭で請け負う江戸の元締は関東長吏頭・浅草弾左衛門。忌むべき身分を統べる弾左衛門が最後に頼るのが、武家で唯一の魔斬人・山田浅右衛門である。昼は罪人の首を斬り、夜は怨霊を斬る因果の男。
幕末。
深い闇の奥に、今日もあやかしを斬る男がいる。
2023年オール讀物中間発表止まりの作品。その先の連作を含めて、いよいよ御開帳。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め
七瀬京
歴史・時代
近藤勇の『首』が消えた……。
新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。
しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。
近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。
首はどこにあるのか。
そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。
※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

手児奈し思ほゆ
三谷銀屋
歴史・時代
万葉集にも詠われた伝説の美女「真間の手児奈」に題材をとった古代ファンタジー&バイオレンス小説。実らぬ初恋と復讐の物語。
下総国(今の千葉県)の国造(くにのみやつこ)の娘・手児奈と、手児奈に想いを寄せる墓守の男・阿止利……一度は引き裂かれた二人が再び出会う時、残酷な現実が二人の運命を飲み込んでいく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















