1 / 11
1
しおりを挟む
初夏の爽やかな気候に誘われて、隅倉永吾は稲綱山に向かった。麓近くに、よい渓流があると聞いたのだ。
お気に入りの釣り竿を持ち、愛犬ハクを従えた。
ハクは毛足の長い、白くたくましい犬だった。ころころした毛玉のような子犬の時分から飼っており、登城の時以外は永吾の行くところ、どこにでも付いてくる可愛いやつだ。
山は、まぶしいほどの緑に溢れていた。
新緑を縫って流れる渓流は雪解けで嵩を増し、突き出た岩々にぶつかって飛沫を上げている。水も風もまだ冷たくて、木の間から降りそそぐ強い陽射しをいい具合に和らげてくれる。目を上げると鳳連峰の高い稜線が残雪を際立たせて青空にくっきりと浮かび上がり、これもまた美しい。
永吾は手頃な岩場にのんびりと腰を落ち着けた。
永吾の隅倉家は、鷲杜藩の馬廻りを代々勤める士だったが、君主の側で颯爽と馬を駆っていたのも今は昔。この太平の世にあっては、仕事と言えば城内警備ぐらいなものだ。非番に日がな一日釣り糸を垂れていても、文句を言う者はだれもいない。
両親はとっくに亡くなっていた。二十五にもなって独り身はいかがなものかと、親戚連中はしきりと気をもんでいるけれど、永吾はどこ吹く風。濃い眉にきりりとした目鼻立ちの美丈夫で、嫁選びにも苦労すまいにとため息をつく家人たちをよそに、永吾はこの気ままな暮らしを充分楽しんでいる。
とはいうものの、魚はいっこうに釣れる気配がなかった。
聞いた場所を間違えたのか。
初めはおとなしく主を眺めていたハクもだんだんと飽きてきたとみえ、沢の斜面を上ったり、下りたりしている。
ハクを目で追っていると、みごとなみずの群生を見つけた。おひたしにすれば美味いだろう。何匹釣れるか分からない魚よりも、こっちの方が下女を喜ばせそうだった。
永吾は釣り竿をしまい、山菜摘みをはじめた。ハクも喜んでついてくる。
山の恵みは豊かだった。みずばかりではなく、ぜんまい、姫竹、こしあぶら。
魚籠につめこみ、気づいた時にはだいぶ山の奥に入っていた。
ハクが一声吠えた。見ると、木々の向こうに小屋らしきものがある。屋根から煙が立ち上っている。
こんな所にも人が住んでいるのか。
永吾は小屋に近づいた。うち捨てられた樵小屋といった粗末さだったが、前は日当たりのよい空き地になっていて、畑らしきものもある。
一人の老婆が顔をのぞかせた。七十は超えているだろう。日に焼けた顔は皺だらけで、頭頂の薄い白髪頭。小柄で腰が曲がっていた。白目の黄ばんだ目で永吾を見上げた。
「すまんが、煙草の火をもらえんだろうか。火打ち袋を忘れてきた」
「よござんすよ」
老婆は種火を持ってきてくれた。その礼に、永吾は摘んできた山菜を半分わけてやった。老婆はいそいそと小屋にひっこんだ。
空き地の隅に大きな石が転がっていて、永吾はそこに座って煙管をくわえた。足下で長々と寝そべっていたハクが、突然頭を上げた。
小屋の裏から、大きな赤犬がのそりと現れたのだ。
老婆の飼い犬らしい。ハクは起き上がり、前屈みになって歯をむきだした。赤犬は、昂然とハクを見下ろした。
ハクは低いうなり声を上げた。赤犬は動じることなく、鼻をならした。
ついにこらえきれなくなったように、ハクは激しく吠え始めた。永吾が止めようとした時、赤犬がハクに飛びかかった。
永吾は、あわてて赤犬を追い払おうとしたが、赤犬の攻撃は素早かった。ハクの首を噛んで振り回し、地面に叩きつけたのだ。
ハクは哀れな声で短く鳴き、身体をひくつかせた。赤犬は前足でハクを押さえつけ、容赦なくかみ続けた。白い毛がみるみる赤く染まり、ハクはついに動かなくなった。
永吾は呆然と立ち尽くした。
赤犬は、血のついた口のまわりを舐めながら永吾を一瞥した。
永吾は、思わず腰の刀に手をかけた。
「仕掛けてきたのは、そちらの犬でございますよ」
後ろから、老婆の冷たい声が聞こえた。
赤犬は勝ち誇るかのように身体をゆすり、林の奥に姿を消した。
老婆が、力任せに小屋の戸をしめた。
永吾は、やるせない思いでハクの亡骸を抱えた。
さっきまでふかふかとやわらかな温もりを伝えていた毛並みは、血にまみれごわついていた。硬直した身体が、たちまち冷たくなっていく。
子犬のころからの思い出が、とりとめもなく頭に浮かんだ。
あと数年は、共にいられるはずだったのに。それが一瞬で命を奪われてしまったのだ。
永吾は、絞り出すようなため息をついた。
ハクを山に埋め、家に帰った。
お気に入りの釣り竿を持ち、愛犬ハクを従えた。
ハクは毛足の長い、白くたくましい犬だった。ころころした毛玉のような子犬の時分から飼っており、登城の時以外は永吾の行くところ、どこにでも付いてくる可愛いやつだ。
山は、まぶしいほどの緑に溢れていた。
新緑を縫って流れる渓流は雪解けで嵩を増し、突き出た岩々にぶつかって飛沫を上げている。水も風もまだ冷たくて、木の間から降りそそぐ強い陽射しをいい具合に和らげてくれる。目を上げると鳳連峰の高い稜線が残雪を際立たせて青空にくっきりと浮かび上がり、これもまた美しい。
永吾は手頃な岩場にのんびりと腰を落ち着けた。
永吾の隅倉家は、鷲杜藩の馬廻りを代々勤める士だったが、君主の側で颯爽と馬を駆っていたのも今は昔。この太平の世にあっては、仕事と言えば城内警備ぐらいなものだ。非番に日がな一日釣り糸を垂れていても、文句を言う者はだれもいない。
両親はとっくに亡くなっていた。二十五にもなって独り身はいかがなものかと、親戚連中はしきりと気をもんでいるけれど、永吾はどこ吹く風。濃い眉にきりりとした目鼻立ちの美丈夫で、嫁選びにも苦労すまいにとため息をつく家人たちをよそに、永吾はこの気ままな暮らしを充分楽しんでいる。
とはいうものの、魚はいっこうに釣れる気配がなかった。
聞いた場所を間違えたのか。
初めはおとなしく主を眺めていたハクもだんだんと飽きてきたとみえ、沢の斜面を上ったり、下りたりしている。
ハクを目で追っていると、みごとなみずの群生を見つけた。おひたしにすれば美味いだろう。何匹釣れるか分からない魚よりも、こっちの方が下女を喜ばせそうだった。
永吾は釣り竿をしまい、山菜摘みをはじめた。ハクも喜んでついてくる。
山の恵みは豊かだった。みずばかりではなく、ぜんまい、姫竹、こしあぶら。
魚籠につめこみ、気づいた時にはだいぶ山の奥に入っていた。
ハクが一声吠えた。見ると、木々の向こうに小屋らしきものがある。屋根から煙が立ち上っている。
こんな所にも人が住んでいるのか。
永吾は小屋に近づいた。うち捨てられた樵小屋といった粗末さだったが、前は日当たりのよい空き地になっていて、畑らしきものもある。
一人の老婆が顔をのぞかせた。七十は超えているだろう。日に焼けた顔は皺だらけで、頭頂の薄い白髪頭。小柄で腰が曲がっていた。白目の黄ばんだ目で永吾を見上げた。
「すまんが、煙草の火をもらえんだろうか。火打ち袋を忘れてきた」
「よござんすよ」
老婆は種火を持ってきてくれた。その礼に、永吾は摘んできた山菜を半分わけてやった。老婆はいそいそと小屋にひっこんだ。
空き地の隅に大きな石が転がっていて、永吾はそこに座って煙管をくわえた。足下で長々と寝そべっていたハクが、突然頭を上げた。
小屋の裏から、大きな赤犬がのそりと現れたのだ。
老婆の飼い犬らしい。ハクは起き上がり、前屈みになって歯をむきだした。赤犬は、昂然とハクを見下ろした。
ハクは低いうなり声を上げた。赤犬は動じることなく、鼻をならした。
ついにこらえきれなくなったように、ハクは激しく吠え始めた。永吾が止めようとした時、赤犬がハクに飛びかかった。
永吾は、あわてて赤犬を追い払おうとしたが、赤犬の攻撃は素早かった。ハクの首を噛んで振り回し、地面に叩きつけたのだ。
ハクは哀れな声で短く鳴き、身体をひくつかせた。赤犬は前足でハクを押さえつけ、容赦なくかみ続けた。白い毛がみるみる赤く染まり、ハクはついに動かなくなった。
永吾は呆然と立ち尽くした。
赤犬は、血のついた口のまわりを舐めながら永吾を一瞥した。
永吾は、思わず腰の刀に手をかけた。
「仕掛けてきたのは、そちらの犬でございますよ」
後ろから、老婆の冷たい声が聞こえた。
赤犬は勝ち誇るかのように身体をゆすり、林の奥に姿を消した。
老婆が、力任せに小屋の戸をしめた。
永吾は、やるせない思いでハクの亡骸を抱えた。
さっきまでふかふかとやわらかな温もりを伝えていた毛並みは、血にまみれごわついていた。硬直した身体が、たちまち冷たくなっていく。
子犬のころからの思い出が、とりとめもなく頭に浮かんだ。
あと数年は、共にいられるはずだったのに。それが一瞬で命を奪われてしまったのだ。
永吾は、絞り出すようなため息をついた。
ハクを山に埋め、家に帰った。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

慶安夜話
MIROKU
歴史・時代
慶安の江戸に現れた死者の行列。剣客の忍足数馬は死者の行列に挑むも、その魔性に引きこまれた。次いで死者の行列は遊女の店が並ぶ通りに現れた。そこには人斬りとあだ名される用心棒の蘭丸がいた…… 江戸を包む暗雲に蘭丸は挑む。かたわらの女が穏やかに眠れるように。
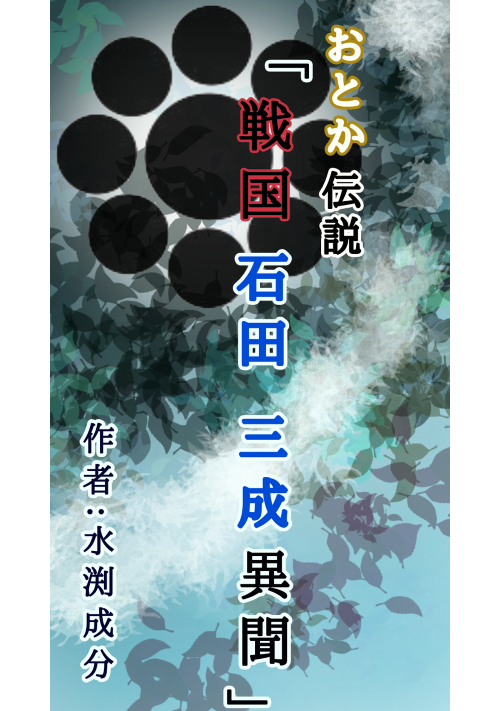
おとか伝説「戦国石田三成異聞」
水渕成分
歴史・時代
関東北部のある市に伝わる伝説を基に創作しました。
前半はその市に伝わる「おとか伝説」をですます調で、
後半は「小田原征伐」に参加した石田三成と「おとか伝説」の衝突について、
断定調で著述しています。
小説家になろうでは「おとか外伝『戦国石田三成異聞』」の題名で掲載されています。
完結済です。

人情落語家いろは節
朝賀 悠月
歴史・時代
浅草は浅草寺の程近くに、煮売茶屋がある。
そこの次男坊である弥平は、幼き頃より噺家になることを夢見ていた。
十五の歳、近くの神社で催された祭りに寄せ場が作られた。
素人寄席ながらも賑わいを見せるその中に、『鈴乃屋小蔵』と名乗る弥平が高座に上がる。
そこへ偶然居合わせた旗本の三男坊、田丸惣右衛門は鈴乃屋小蔵の人情噺をその目で見て、心の臓が打ち震えた。終演後に声を掛け、以来二人は友人関係を結ぶ。
半端物の弥平と惣右衛門。家柄は違えど互いを唯一無二と慕った。
しかし、惣右衛門にはどうしても解せないことがあった。
寄せ場に上がる弥平が、心の臓を射抜いた人情噺をやらなくなってしまったのだ……


名残雪に虹を待つ
小林一咲
歴史・時代
「虹は一瞬の美しさとともに消えゆくもの、名残雪は過去の余韻を残しながらもいずれ溶けていくもの」
雪の帳が静かに降り、時代の終わりを告げる。
信州松本藩の老侍・片桐早苗衛門は、幕府の影が薄れゆく中、江戸の喧騒を背に故郷へと踵を返した。
変わりゆく町の姿に、武士の魂が風に溶けるのを聴く。松本の雪深い里にたどり着けば、そこには未亡人となったかつての許嫁、お篠が、過ぎし日の幻のように佇んでいた。
二人は雪の丘に記憶を辿る。幼き日に虹を待ち、夢を語ったあの場所で、お篠の声が静かに響く——「まだあの虹を探しているのか」。早苗衛門は答えを飲み込み、過去と現在が雪片のように交錯する中で、自らの影を見失う。
町では新政府の風が吹き荒れ、藩士たちの誇りが軋む。早苗衛門は若者たちの剣音に耳を傾け、最後の役目を模索する。
やがて、幕府残党狩りの刃が早苗衛門を追い詰める。お篠の庇う手を振り切り、彼は名残雪の丘へ向かう——虹を待ったあの場所へ。
雪がやみ、空に淡い光が差し込むとき、追っ手の足音が近づく。
早苗衛門は剣を手に微笑み、お篠は遠くで呟く——「あなたは、まだ虹を待っていたのですね」
名残雪の中に虹がかすかに輝き、侍の魂は静かに最後の舞を舞った。

手児奈し思ほゆ
三谷銀屋
歴史・時代
万葉集にも詠われた伝説の美女「真間の手児奈」に題材をとった古代ファンタジー&バイオレンス小説。実らぬ初恋と復讐の物語。
下総国(今の千葉県)の国造(くにのみやつこ)の娘・手児奈と、手児奈に想いを寄せる墓守の男・阿止利……一度は引き裂かれた二人が再び出会う時、残酷な現実が二人の運命を飲み込んでいく。

魔斬
夢酔藤山
歴史・時代
深淵なる江戸の闇には、怨霊や妖魔の類が巣食い、昼と対なす穢土があった。
その魔を斬り払う闇の稼業、魔斬。
坊主や神主の手に負えぬ退魔を金銭で請け負う江戸の元締は関東長吏頭・浅草弾左衛門。忌むべき身分を統べる弾左衛門が最後に頼るのが、武家で唯一の魔斬人・山田浅右衛門である。昼は罪人の首を斬り、夜は怨霊を斬る因果の男。
幕末。
深い闇の奥に、今日もあやかしを斬る男がいる。
2023年オール讀物中間発表止まりの作品。その先の連作を含めて、いよいよ御開帳。

花なき鳥
紫乃森統子
歴史・時代
相添はん 雲のあはひの 彼方(をち)にても──
安政六年、小姓仕えのために城へ上がった大谷武次は、家督を継いで間もない若き主君の帰国に催された春の園遊会で、余興に弓を射ることになる。
武次の放った矢が的にある鳥を縫い留めてしまったことから、謹慎処分を言い渡されてしまうが──
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















