あなたにおすすめの小説


【短編】輿上(よじょう)の敵 ~ 私本 桶狭間 ~
四谷軒
歴史・時代
【あらすじ】
今川義元の大軍が尾張に迫る中、織田信長の家臣、簗田政綱は、輿(こし)が来るのを待ち構えていた。幕府により、尾張において輿に乗れるは斯波家の斯波義銀。かつて、信長が傀儡の国主として推戴していた男である。義元は、義銀を御輿にして、尾張の支配を目論んでいた。義銀を討ち、義元を止めるよう策す信長。が、義元が落馬し、義銀の輿に乗って進軍。それを知った信長は、義銀ではなく、輿上の敵・義元を討つべく出陣する。
【表紙画像】
English: Kano Soshu (1551-1601)日本語: 狩野元秀(1551〜1601年), Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

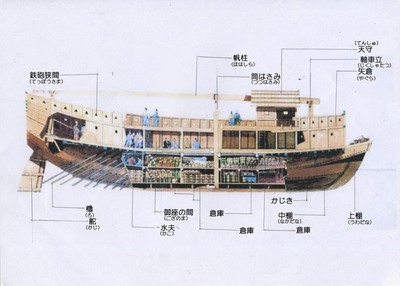

天正十年五月、安土にて
佐倉伸哉
歴史・時代
天正十年四月二十一日、織田“上総守”信長は甲州征伐を終えて安土に凱旋した。
長年苦しめられてきた宿敵を倒しての帰還であるはずなのに、信長の表情はどこか冴えない。
今、日ノ本で最も勢いのある織田家を率いる天下人である信長は、果たして何を思うのか?
※この作品は過去新人賞に応募した作品を大幅に加筆修正を加えて投稿しています。
<第6回歴史・時代小説大賞>にエントリーしています!
皆様の投票、よろしくお願い致します。
『小説家になろう(https://ncode.syosetu.com/n2184fu/ )』『カクヨム(https://kakuyomu.jp/works/1177354054891485907)』および私が運営するサイト『海の見える高台の家』でも同時掲載

織田信長 -尾州払暁-
藪から犬
歴史・時代
織田信長は、戦国の世における天下統一の先駆者として一般に強くイメージされますが、当然ながら、生まれついてそうであるわけはありません。
守護代・織田大和守家の家来(傍流)である弾正忠家の家督を継承してから、およそ14年間を尾張(現・愛知県西部)の平定に費やしています。そして、そのほとんどが一族間での骨肉の争いであり、一歩踏み外せば死に直結するような、四面楚歌の道のりでした。
織田信長という人間を考えるとき、この彼の青春時代というのは非常に色濃く映ります。
そこで、本作では、天文16年(1547年)~永禄3年(1560年)までの13年間の織田信長の足跡を小説としてじっくりとなぞってみようと思いたった次第です。
毎週の月曜日00:00に次話公開を目指しています。
スローペースの拙稿ではありますが、お付き合いいただければ嬉しいです。
(2022.04.04)
※信長公記を下地としていますが諸出来事の年次比定を含め随所に著者の創作および定説ではない解釈等がありますのでご承知置きください。
※アルファポリスの仕様上、「HOTランキング用ジャンル選択」欄を「男性向け」に設定していますが、区別する意図はとくにありません。


新視点、賤ヶ岳の戦い
いずもカリーシ
歴史・時代
日本史上有名な賤ヶ岳の戦いを、羽柴秀吉側で参加した堀秀政(ほりひでまさ)、柴田勝家側で参加した佐久間盛政(さくまもりまさ)の視点で描きます。
この戦いは勝家軍の敗北に終わり、秀吉の天下人を確定させたことで有名です。
定説では、佐久間盛政が勝家軍の迂回部隊を率いいくつか秀吉軍の砦を攻略したものの、勝家の命令を無視して留まり続けたことが敗因となっています。
果たして本当にそうなのでしょうか?
①秀吉軍、勝家軍の目的は何か?
②どうなれば秀吉の勝ち、勝家の負けなのか?
③どうなれば勝家の勝ち、秀吉の負けなのか?
④勝家軍はなぜ正面攻撃でなく迂回攻撃をしたのか?
⑤迂回攻撃するとして、なぜ参加したのが勝家軍の一部なのか? なぜ全軍で攻撃しなかったのか?
こういった疑問を解かない限り、戦いの真実は見えません。
ここでは定説を覆す、真の敗因を明らかにしたいと思います。
AIやテクノロジーの発展で、人の生活は改善し、歴史においても新しい事実が次々と分かってきています。
しかし、人は目的を持って生き、動くものです。
AIやテクノロジーは過去と今の事実を教えてはくれますが、それは目的を見付けるための手段に過ぎません。
過去の人が何の目的を持って生き、今の人が何を目的に生きればいいのか?
それは、人が考え、見付けなければならないのです。
戦いは、人と人がするものです。
実際の戦いはなくても、信念のために、未来のために、あるいはビジネスのために戦うこともあるでしょう。
過去の人が、何を目的に、何を考え、どう戦ったのか、事実が分かったとしても真実が見えるわけではないように……
もしかすると歴史の真実は、
よく考え、生きる目的を見付け、そのために戦おうとするとき、初めて見えてくるものなのかもしれません。
他、いずもカリーシの名前で投稿しています。


















