9 / 59
第9話
しおりを挟む
子供の頃に住んでいた埼玉の大宮は、東京のベッドタウンということもあり、子供の教育には熱心な地域だった。
英会話スクールにスパルタ式学習塾などに通うクラスメイトも多かった。
そして目指すは浦和高校。そんな時代だった。
私の小学校は生徒数がどんどん増えて行き、ひと学年が45人学級で15クラスもあった。
教室が間に合わず、臨時のプレハブ教室で急場を凌いでいた。
体育館などはなく、全校集会はいつも校庭で、雨の日は教室で校長先生たちの校内放送を聴いた。
会津の学校に転校して初めて体育館を見た。
水銀燈の眩しさに驚いた。
どうでもいい校長先生の長い訓話を「休め」の姿勢で立って聞いていると、バタバタと生徒が倒れ、中には失禁してしまう子もいた。
体育館の長時間の集会は、今も同じなんだろうか?
学区内には大きな低所得者向けの公営住宅があり、私はそこの「スラム街」で育った。
分譲マンションも多く、戸建てやマンションに住む子供たちは家にピアノやエアコンもあるような裕福な家庭だった。
「住む世界が違う」と、子供ながらにそう感じていた。
スラム街に住む子供と、恵まれた環境で暮らす子供が同じ教室で学ぶ矛盾。
私のクラスは公立の小学校でありながら、クラスの半分は帰国子女だった。
転校して来る子供もしょっちゅだった。
「ラオスから来ました」
「マレーシアから来ました」
ニューヨークから来た女の子はフランス人形のような子で、みんなから一目置かれていた。
話し掛けることも憚られた。
「おい、英語で何か話してみろよ」
だが彼女は何も話さなかった。
「大人だな?」と思った。
私は尊敬する父にそのことを話し、こうせがんだ。
「パパ、何か英語を書いてよ」
すると父は笑って、
This is a Pen
と広告の裏紙に書いて渡してくれた。
翌日、私はその父の書いてくれた英語の紙を、自信たっぷりにその女の子に見せた。
私は英語も出来る父を自慢したかったのだ。
「これってどういう意味だ?」
「これは「これはペンです」という意味よ」
英語なんて知らない私は、彼女と父を改めて尊敬した。
そして彼女はいつの間にかまた、ニューヨークへと帰って行った。
学力の差は歴然だった。
近くにはいくつか大学もあり、その当時は学生運動も盛んで、公安に追われた学生が、友人の家の庭に鉄パイプ爆弾を置いて逃げたこともあった。
大学教授の息子もいて、いつも弁舌さわやかに、理路整然と話しをする生徒だった。
男子でもピアノが弾ける子供もたくさんいた。
音楽の時間、先生が言った。
「馬場君、『トルコ行進曲』を弾いてみて」
すると彼はおもむろにピアノの蓋を開け、その曲を弾き始めた。
まだ小学校の2年生でモーツァルト。
私は彼が宇宙人なのではないかと思った。
そんな生徒がゴロゴロいた。
東京電力の社員寮に住んでいた女子に言われたことがある。
「アンタは黙っていなさいよ、馬鹿なんだから」
私もそうだと思っていたので気にならなかった。
勉強が出来ない私は軽蔑されていた。
クラスメイトの将来の夢は、野球選手や医者、外交官や大学教授が多い中で、私はただ、強くなりたかった。
スラム街の子供たちと取っ組み合いのケンカをすると、いつも泣かされていたからだ。
勉強は出来ない、ケンカも弱い。
いいところはなにもない小学生だった。
父も母も私の将来に期待をしてはいなかった。
子供は怪我や病気もせず、早く社会に出て自分で稼げるようになってくれればそれでいいと思っていた。
家に児童書といえば母親が内職をしていた会社の社長夫人がくれた、イソップ童話とグリム童話。
そしてジュール・ベルヌの『海底2万マイル』だけだった。
あと、いただき物の飛び出す絵本があったような気がする。
通信簿は1こそなかったが、2と3ばかりが並び、教師の記入欄には「落ち着きがない」といつも書かれていた。
学用品はいつも最低限の物しか買って貰えなかった。
色鉛筆は12色の紙の入れ物のやつだった。
みんなが28色の缶入りの色絵筆や48色の色鉛筆を自慢している時には惨めな思いをした。
だから年の離れた妹や、自分の子供たちにはなるべくいい物を買い与えた。
学校行事で自分が写っている写真も買ったことがない。
だから私には小学校時代の写真が殆どない。
母に「買って欲しい」とか「学校でお金が必要なんだけど」と言うのが苦痛だった。
宿題のプリントをしている時、消しゴムがなくなっていることに気づいた私は、指に唾をつけて間違った箇所を擦って消した。
給食費もそうだった。
「どうして毎月パパのお給料の前なのかしらねえ。
パパの給料日まで待ってもらいなさい」
そう言う母だった。
「菊池、給食費は?」
「忘れました・・・」
当時はたまに給食費がなくなることがあり、疑われるのはいつもスラム街の私たちだった。
「全員目を閉じて。間違えを犯した者は静かに手をあげなさい」
自分がやっていなくても、イヤだった。
お金がないということはそういうことなのかと悲しくなった。
その時私は思った。
結局人間は、「どの家に生まれるかで人生が決まるのだ」と。
私の家は借金もなく、僅かだが貯金もあったはずだが子供には無関心な親だった。
小学校3年生の頃だっただろうか? 団地の中に少年野球チームが出来ることになり、そこに入ることを勧めてくれたのは、意外にも母だった。
「野球やったら?」と。
並んでユニフォームをもらう時、なぜかみんな笑って並ぶ順番を変わったりしていた。
私は彼らがどうして度々並ぶ順番を変わるのか分からなかった。
何しろ100人近くいるチームだ。背番号も2桁代の後半になるのも当然である。
みんなジャイアンツの有名選手の背番号に憧れていた。
ユニフォームの入った箱には小さくボールペンで中に入っている背番号がわかるようになっていたのは私が知ったのは、その箱を手にした時だった。
私は間抜けな子供だったので、そのままユニフォームの入った箱を受け取った。
背番号「50」。
監督のような背番号だった。
私は母に頼んで「0」を剥がしてもらい、中央に「5」を付け替えてもらったが、背中には50の跡が残ってしまっていた。
隣に住んでいた、子供がまだいなかったご主人からバットをプレゼントしてもらった。
だが問題はグローブだった。
私のグローブは父の会社で昼休みにキャッチボールで使っていた、ベーブ・ルースが使っていたような代物で、野犬に齧られて中綿がはみ出た物だった。
コーチは当番制だったので、父も練習に参加した時もあった。
私がいつものようにチームメイトたちに囲まれて、
「何だお前のグローブ? 戦争中のやつじゃねえのか?」
と、みんなに笑われていた。
それを離れたところから見ていた父が、家で晩酌を始めると母に言った。
「昭仁にグローブを買ってやれ」
私はその時泣いたことを覚えている。
それは新しいグローブを買ってもらえるといううれしさの涙ではなく、みんなが持っている新しいグローブすら買って貰えなかった悔し涙だった。
私は翌日、母とスポーツ店に行き、いちばん安いグローブを買ってもらい、友だちに教えてもらいながら毎日新品のグローブに油を塗り、ボールを入れて形を整えた。
そのグローブだけは今も大切に捨てずに取ってある。
それから私は野球が好きになり、いつの間にかピッチャーで4番を打つ、大谷翔平のような二刀流としてレギュラーにまでなることが出来た。
だが本格的に野球をするにはカネがかかる。
私は会津に転校してからは水泳部に入り、平泳ぎでは会津若松市の大会で3位になり、当然中学でも水泳を続けるだろうと、同じ水泳をしていた友だちはそう思っていた。
水泳は海水パンツがあればそれで良かったからだ。
だが私は柔道部に入ってしまった。
水泳部に体験入部しに行く途中、体育館で柔道をしている先輩たちに、
「おいそこの1年生、柔道やらねえか? 柔道」
そしていつの間にか柔道着を着せられ、柔道部に入部させられた。
柔道を習うことでそれが自信となり、私は学年で一番強くなった。
私の将来の夢が実現された。
英会話スクールにスパルタ式学習塾などに通うクラスメイトも多かった。
そして目指すは浦和高校。そんな時代だった。
私の小学校は生徒数がどんどん増えて行き、ひと学年が45人学級で15クラスもあった。
教室が間に合わず、臨時のプレハブ教室で急場を凌いでいた。
体育館などはなく、全校集会はいつも校庭で、雨の日は教室で校長先生たちの校内放送を聴いた。
会津の学校に転校して初めて体育館を見た。
水銀燈の眩しさに驚いた。
どうでもいい校長先生の長い訓話を「休め」の姿勢で立って聞いていると、バタバタと生徒が倒れ、中には失禁してしまう子もいた。
体育館の長時間の集会は、今も同じなんだろうか?
学区内には大きな低所得者向けの公営住宅があり、私はそこの「スラム街」で育った。
分譲マンションも多く、戸建てやマンションに住む子供たちは家にピアノやエアコンもあるような裕福な家庭だった。
「住む世界が違う」と、子供ながらにそう感じていた。
スラム街に住む子供と、恵まれた環境で暮らす子供が同じ教室で学ぶ矛盾。
私のクラスは公立の小学校でありながら、クラスの半分は帰国子女だった。
転校して来る子供もしょっちゅだった。
「ラオスから来ました」
「マレーシアから来ました」
ニューヨークから来た女の子はフランス人形のような子で、みんなから一目置かれていた。
話し掛けることも憚られた。
「おい、英語で何か話してみろよ」
だが彼女は何も話さなかった。
「大人だな?」と思った。
私は尊敬する父にそのことを話し、こうせがんだ。
「パパ、何か英語を書いてよ」
すると父は笑って、
This is a Pen
と広告の裏紙に書いて渡してくれた。
翌日、私はその父の書いてくれた英語の紙を、自信たっぷりにその女の子に見せた。
私は英語も出来る父を自慢したかったのだ。
「これってどういう意味だ?」
「これは「これはペンです」という意味よ」
英語なんて知らない私は、彼女と父を改めて尊敬した。
そして彼女はいつの間にかまた、ニューヨークへと帰って行った。
学力の差は歴然だった。
近くにはいくつか大学もあり、その当時は学生運動も盛んで、公安に追われた学生が、友人の家の庭に鉄パイプ爆弾を置いて逃げたこともあった。
大学教授の息子もいて、いつも弁舌さわやかに、理路整然と話しをする生徒だった。
男子でもピアノが弾ける子供もたくさんいた。
音楽の時間、先生が言った。
「馬場君、『トルコ行進曲』を弾いてみて」
すると彼はおもむろにピアノの蓋を開け、その曲を弾き始めた。
まだ小学校の2年生でモーツァルト。
私は彼が宇宙人なのではないかと思った。
そんな生徒がゴロゴロいた。
東京電力の社員寮に住んでいた女子に言われたことがある。
「アンタは黙っていなさいよ、馬鹿なんだから」
私もそうだと思っていたので気にならなかった。
勉強が出来ない私は軽蔑されていた。
クラスメイトの将来の夢は、野球選手や医者、外交官や大学教授が多い中で、私はただ、強くなりたかった。
スラム街の子供たちと取っ組み合いのケンカをすると、いつも泣かされていたからだ。
勉強は出来ない、ケンカも弱い。
いいところはなにもない小学生だった。
父も母も私の将来に期待をしてはいなかった。
子供は怪我や病気もせず、早く社会に出て自分で稼げるようになってくれればそれでいいと思っていた。
家に児童書といえば母親が内職をしていた会社の社長夫人がくれた、イソップ童話とグリム童話。
そしてジュール・ベルヌの『海底2万マイル』だけだった。
あと、いただき物の飛び出す絵本があったような気がする。
通信簿は1こそなかったが、2と3ばかりが並び、教師の記入欄には「落ち着きがない」といつも書かれていた。
学用品はいつも最低限の物しか買って貰えなかった。
色鉛筆は12色の紙の入れ物のやつだった。
みんなが28色の缶入りの色絵筆や48色の色鉛筆を自慢している時には惨めな思いをした。
だから年の離れた妹や、自分の子供たちにはなるべくいい物を買い与えた。
学校行事で自分が写っている写真も買ったことがない。
だから私には小学校時代の写真が殆どない。
母に「買って欲しい」とか「学校でお金が必要なんだけど」と言うのが苦痛だった。
宿題のプリントをしている時、消しゴムがなくなっていることに気づいた私は、指に唾をつけて間違った箇所を擦って消した。
給食費もそうだった。
「どうして毎月パパのお給料の前なのかしらねえ。
パパの給料日まで待ってもらいなさい」
そう言う母だった。
「菊池、給食費は?」
「忘れました・・・」
当時はたまに給食費がなくなることがあり、疑われるのはいつもスラム街の私たちだった。
「全員目を閉じて。間違えを犯した者は静かに手をあげなさい」
自分がやっていなくても、イヤだった。
お金がないということはそういうことなのかと悲しくなった。
その時私は思った。
結局人間は、「どの家に生まれるかで人生が決まるのだ」と。
私の家は借金もなく、僅かだが貯金もあったはずだが子供には無関心な親だった。
小学校3年生の頃だっただろうか? 団地の中に少年野球チームが出来ることになり、そこに入ることを勧めてくれたのは、意外にも母だった。
「野球やったら?」と。
並んでユニフォームをもらう時、なぜかみんな笑って並ぶ順番を変わったりしていた。
私は彼らがどうして度々並ぶ順番を変わるのか分からなかった。
何しろ100人近くいるチームだ。背番号も2桁代の後半になるのも当然である。
みんなジャイアンツの有名選手の背番号に憧れていた。
ユニフォームの入った箱には小さくボールペンで中に入っている背番号がわかるようになっていたのは私が知ったのは、その箱を手にした時だった。
私は間抜けな子供だったので、そのままユニフォームの入った箱を受け取った。
背番号「50」。
監督のような背番号だった。
私は母に頼んで「0」を剥がしてもらい、中央に「5」を付け替えてもらったが、背中には50の跡が残ってしまっていた。
隣に住んでいた、子供がまだいなかったご主人からバットをプレゼントしてもらった。
だが問題はグローブだった。
私のグローブは父の会社で昼休みにキャッチボールで使っていた、ベーブ・ルースが使っていたような代物で、野犬に齧られて中綿がはみ出た物だった。
コーチは当番制だったので、父も練習に参加した時もあった。
私がいつものようにチームメイトたちに囲まれて、
「何だお前のグローブ? 戦争中のやつじゃねえのか?」
と、みんなに笑われていた。
それを離れたところから見ていた父が、家で晩酌を始めると母に言った。
「昭仁にグローブを買ってやれ」
私はその時泣いたことを覚えている。
それは新しいグローブを買ってもらえるといううれしさの涙ではなく、みんなが持っている新しいグローブすら買って貰えなかった悔し涙だった。
私は翌日、母とスポーツ店に行き、いちばん安いグローブを買ってもらい、友だちに教えてもらいながら毎日新品のグローブに油を塗り、ボールを入れて形を整えた。
そのグローブだけは今も大切に捨てずに取ってある。
それから私は野球が好きになり、いつの間にかピッチャーで4番を打つ、大谷翔平のような二刀流としてレギュラーにまでなることが出来た。
だが本格的に野球をするにはカネがかかる。
私は会津に転校してからは水泳部に入り、平泳ぎでは会津若松市の大会で3位になり、当然中学でも水泳を続けるだろうと、同じ水泳をしていた友だちはそう思っていた。
水泳は海水パンツがあればそれで良かったからだ。
だが私は柔道部に入ってしまった。
水泳部に体験入部しに行く途中、体育館で柔道をしている先輩たちに、
「おいそこの1年生、柔道やらねえか? 柔道」
そしていつの間にか柔道着を着せられ、柔道部に入部させられた。
柔道を習うことでそれが自信となり、私は学年で一番強くなった。
私の将来の夢が実現された。
11
あなたにおすすめの小説
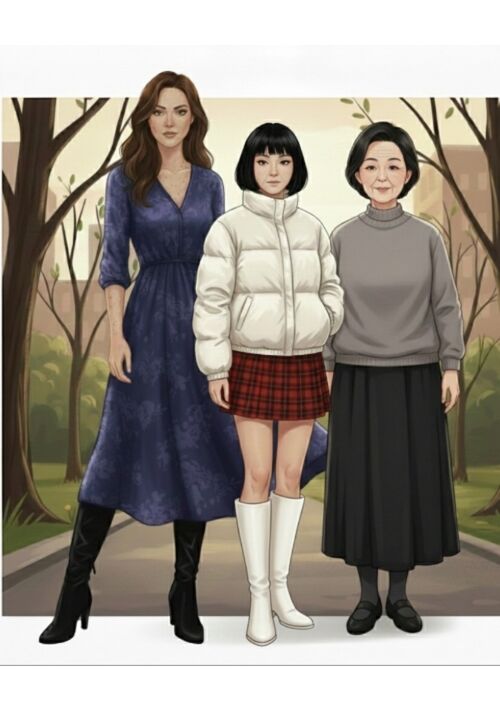
熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
恋愛
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。
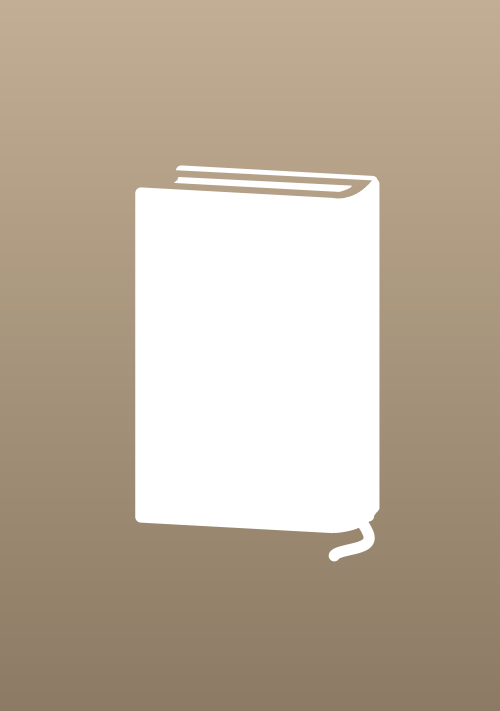

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
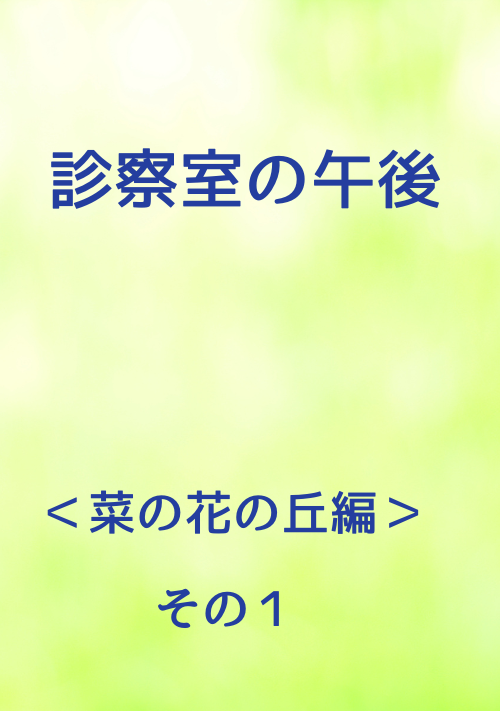
診察室の午後<菜の花の丘編>その1
スピカナ
恋愛
神的イケメン医師・北原春樹と、病弱で天才的なアーティストである妻・莉子。
そして二人を愛してしまったイケメン御曹司・浅田夏輝。
「菜の花クリニック」と「サテライトセンター」を舞台に、三人の愛と日常が描かれます。
時に泣けて、時に笑える――溺愛とBL要素を含む、ほのぼの愛の物語。
多くのスタッフの人生がここで楽しく花開いていきます。
この小説は「医師の兄が溺愛する病弱な義妹を毎日診察する甘~い愛の物語」の1000話以降の続編です。
※医学描写はすべて架空です。


屈辱と愛情
守 秀斗
恋愛
最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















