37 / 45
ユリエルの求婚
しおりを挟む
オルレリアン領は山の恵み溢れる豊かな土地だ。広い農地に鉱山、石切場や採石場、羊毛から絹まで産業は幅広い。
十歳の誕生日、初めて王都で父と母も揃って祝われた。社交シーズンの両親は毎年春から秋まで家にいることはなく、乳母が私たち兄弟の面倒を見ていた。貴族の中ではそれほど珍しいことではないが、最後の誕生日はやはりとても嬉しかったことを覚えている。
そう考えると、オルレリアン領に最後に足を踏み入れたのは二十年近く前のことらしい。馬車から見える景色は馴染みがなかった。
「ユリエル!戻ったか!」
「ユリエル様、お疲れでしょう」
兄と兄嫁の出迎えで家の門を潜ったが、そこが自らの家だと認識するのは難しかった。懐かしい面影はあるが、雪の残る庭は私の記憶とは異なって何体もの像が飾られていた。
「兄さん、本当にこれでいいのですか?」
「まぁ仕方ないだろう。お前がいるのに養子をとるなんて許されないのだから」
オルレリアン家は子供を儲けたものに継承される決まりだ。まだ直系子孫で子に恵まれなかったことはない。離縁か愛人との子を正妻の子として育てた歴史はある。正妻の子としなくても問題はないが、社交界での立場のことを考えれば避ける方が無難だろう。貴族として領地に不要な争いを生まないために求められるのが後継者を育てることだ。
「アン様も同じ考えなのですか?」
「あぁ。父は離縁しろと五月蠅かったが、馬鹿げた話だ。お前が継いでくれるならその方がいい」
神と聖女様のことだけを考えて生きていくのだと、疑いもせずにこの歳まで生きてきた私が、今度は領民のことを考えて生きていかなくてはならない。それは拷問のように苦痛に感じた。
私は貴族マナーの基本から学び直した。もちろん神殿でも学んだが、オルレリアン式の教育方法を知る必要があった。オルレリアンの立場での振る舞い、オルレリアンから見た近隣領や他国との関係、それを数年かけて学びながら婚姻相手を探すことを求められた。
だが、雪解けを待ってオルレリアン領へ来たので、幸いにもすぐに社交のために王都へと連れ出された。聖女様に会いたい。パーティでは一緒に踊る機会はあるだろうか。手を差し出せる立場であることは幸運なようにも思えたが、オルレリアンの後継者を求められる私では、聖女様の隣に立つことは決して許されない立場でもあった。
それでも、ただ会いたかった。そこに生きていてくれるなら、自分も生きていられると思えた。そんな自分が、他の誰かをこの腕に抱くことなんて出来るはずもない。
神殿で舞踏会が開かれていると聞いたのは、夕方、王都に着いて一呼吸置いた時だった。まだ荷を運び込んでいる最中で、公式的なパーティに行ける服はすぐには出てこない。兄の燕尾服を急遽借りて既に始まっている舞踏会の会場である神殿に急いだ。
「必ず会いにきてください」
聖女様との別れの際に言われた言葉が、今も耳元で囁かれているようだった。この腕に収まっていた小さな体を思い出して、神殿までの道が長く感じた。
会場では既にダンスタイムが始まっていた。ホールをゆっくりと回り、それでも心は落ち着かなかった。周りを見渡して、どこの誰とも分からない男と聖女様が踊っている姿を想像したら身震いがしそうなほどの嫌悪感で吐き気がした。いつか誰かと踊るためにエスコートした日が遠く昔のように思えた。
壇上でいつものように会場を見下ろす聖女様を見つけると、安堵のため息がでた。もう聖女様の後ろに控えるのは自分の役目ではなかった。
「聖女様、一曲ご一緒いただけませんか?」
天上人を見上げるように壇上を見上げると、いつか見た踊り出しそうなほどの笑顔を向けられていた。自分に向けられているのだと気付くまで時間がかかった。それから、ずっと夢を見ているようで、何も考えられなかった。
パーティは途中から参加したこともあり、あっという間に終わってしまった。まだ夢から覚めたくはなかった。聖女様の手を離したくはなかった。寝るその瞬間まで、聖女様の隣にいたかった。
「ユリエル、私は貴方と結婚したいと思っています。いつまで私を聖女様と呼ぶのですか?」
聖女様にそう言われても、都合のいい夢を見ているかと実感が湧かなかった。それ位、聖女様と私の間には大きな壁があった。どうにもならない壁があって、私は貴族としての責務を放棄出来なかった。
何も持たない平民なら…騎士団長のように大切なものを何も持たず、護りたいものをただ護れる立場なら…そう考えても貴族の家に生まれてしまったことから逃げると言う選択は出来なかった。
「侯爵はまだまだ若いです。アン様もまだ分かりませんし、私たちの子供が複数出来れば、一人をオルレリアンの後継者に養子に出すのもいいでしょう。それに、もしもの時は国は弟に任せて、ユリエルがオルレリアン家を継いだ後、血筋から養子をとる。ここまで言えば侯爵は頷くしかありませんよ。因みに、父は子供は出来ると言っているので、養子を取る必要はなさそうですよ?ユリエル」
そのどうにも出来ないと思っていた大きな壁は、私ではなく聖女様が崩した。
私ではどうにも出来なかった壁を、小さな身体の護るべき存在だった聖女様が、最も簡単に崩した。
「私で…いいのですか?」
私の口から出たのは、情けない言葉だった。その日、家に帰ると既に神殿からの求婚状が届いていた。社交のために早く王都に出された私は、その足で今日来た道を引き返して領地に帰った。父も母も、まだ領地にいたのだ。
神殿からの正式な求婚状に抗える家は存在しない。それが例えその家の後継者を奪い去るようなことでもだ。
オルレリアン家は神の忠実な僕だ。神託を賜るただ一人の人間を神殿が求めていることが分かると、父は喜んで承諾した。もし、後継者である兄に子どもができなくても、神の子孫がオルレリアンを継ぐ可能性がある。それはとても光栄なことだった。
オルレリアン家当主の受諾書を受け取るまでに三日、五日かかる距離を無理させた馬の疲労は限界に来ていた。それでも一刻でも早く王都に行きたいと馬に飛び乗った。
「聖女様は森にお出かけになられたようです」
各教会で休憩はしたが、ずっと仮眠程度しか取らず、馬も一度教会で乗り換えてきたが、その馬ももう限界だった。
「馬を借りられますか?」
「森に厩舎が出来たので、予備の馬しかないのですか……今は生憎騎士の演習中で…」
「儀式用の馬はどうですか?」
「あぁ!それなら…」
「ではそれを借ります」
神殿の厩舎へ向かうのも焦ったい。森には聖女様の婚約者だった王子いる。二人きりになることはないと言えど、聖女様が王子に心を開いているのは事実。婚約していた時よりも仲が縮まっている。今更馬車でのんびりと行く選択する余裕はなかった。
「わあー!白い馬だよ!」
「うぉー!カッコいいー」
森の細道をかけていると、遠くで子供が手を振るのが見えた。聖女様の馬車もまだ止まっていた。
子供の声を聞いたのか、小屋の前まで来た時には聖女様が小屋から顔を出す。
「聖女様!」
「ユリエル!?」
聖女様の驚いた顔を見るのも久しぶりだ。それが酷く嬉しい。
「聖女様の隣に立つ許可をもらってきました」
「早かったですね」
「聖女様に会いたくて少し無理をしました…」
「確かに、顔色が悪いです」
聖女様が目の前にいる。それはただの貴族にとっては奇跡のようなことだ。気軽に手を握られることも、抱きしめられることが許されることも、全てが奇跡だ。
「ユリエル?」
今思えば、今までの全てが奇跡の連続だった。私にとってのただ一人の女性と添い遂げられる権利を得られたのも奇跡だ。こんなに幸運なことはない。
「聖女様、愛しています。私と結婚していただけますか?」
聖女様はにっこりと笑ったまま返事せず、森にいる不安にかられた。
「……ユリエル、忘れたのですか?シャーリーです」
「シャーリー…」
「はい。ユリエル」
「シャーリー…好きです」
「私もユリエルが好きです」
「シャーリー…この世にある言葉では伝えられないくらい愛しています」
「ふふっ。この世で一番愛してます。私の唯一の王子様!」
どれだけ抱きしめても、手を握っても足りない。いっそ、溶けてグチャグチャになってしまいたかった。
「はいはい!ユリエル!子供の目の前でいつまでもイチャついてんじゃねぇ。聖女様も、人前で抱きつかない!帰りますよ!」
呆れたように騎士団長に止められても、もう離れたくはなかった。
「ユリエル、一緒に帰りましょう」
「はい」
聖女様を持ち抱えると、慣れたように聖女様は首に腕を回した。
「幸せですね。ユリエル」
そう言って聖女様は頬に唇を寄せた。
「私はシャーリーと出会ってからずっと幸せです」
子供達に見えないように背を向けながら、腕の中の聖女様に口付けた。今はエリアスと名乗る王子が、強く手を握りしめるのを片目に、聖女様と馬車に乗り込んだ。騎士団長はもう、一緒に同乗することはなかった。
十歳の誕生日、初めて王都で父と母も揃って祝われた。社交シーズンの両親は毎年春から秋まで家にいることはなく、乳母が私たち兄弟の面倒を見ていた。貴族の中ではそれほど珍しいことではないが、最後の誕生日はやはりとても嬉しかったことを覚えている。
そう考えると、オルレリアン領に最後に足を踏み入れたのは二十年近く前のことらしい。馬車から見える景色は馴染みがなかった。
「ユリエル!戻ったか!」
「ユリエル様、お疲れでしょう」
兄と兄嫁の出迎えで家の門を潜ったが、そこが自らの家だと認識するのは難しかった。懐かしい面影はあるが、雪の残る庭は私の記憶とは異なって何体もの像が飾られていた。
「兄さん、本当にこれでいいのですか?」
「まぁ仕方ないだろう。お前がいるのに養子をとるなんて許されないのだから」
オルレリアン家は子供を儲けたものに継承される決まりだ。まだ直系子孫で子に恵まれなかったことはない。離縁か愛人との子を正妻の子として育てた歴史はある。正妻の子としなくても問題はないが、社交界での立場のことを考えれば避ける方が無難だろう。貴族として領地に不要な争いを生まないために求められるのが後継者を育てることだ。
「アン様も同じ考えなのですか?」
「あぁ。父は離縁しろと五月蠅かったが、馬鹿げた話だ。お前が継いでくれるならその方がいい」
神と聖女様のことだけを考えて生きていくのだと、疑いもせずにこの歳まで生きてきた私が、今度は領民のことを考えて生きていかなくてはならない。それは拷問のように苦痛に感じた。
私は貴族マナーの基本から学び直した。もちろん神殿でも学んだが、オルレリアン式の教育方法を知る必要があった。オルレリアンの立場での振る舞い、オルレリアンから見た近隣領や他国との関係、それを数年かけて学びながら婚姻相手を探すことを求められた。
だが、雪解けを待ってオルレリアン領へ来たので、幸いにもすぐに社交のために王都へと連れ出された。聖女様に会いたい。パーティでは一緒に踊る機会はあるだろうか。手を差し出せる立場であることは幸運なようにも思えたが、オルレリアンの後継者を求められる私では、聖女様の隣に立つことは決して許されない立場でもあった。
それでも、ただ会いたかった。そこに生きていてくれるなら、自分も生きていられると思えた。そんな自分が、他の誰かをこの腕に抱くことなんて出来るはずもない。
神殿で舞踏会が開かれていると聞いたのは、夕方、王都に着いて一呼吸置いた時だった。まだ荷を運び込んでいる最中で、公式的なパーティに行ける服はすぐには出てこない。兄の燕尾服を急遽借りて既に始まっている舞踏会の会場である神殿に急いだ。
「必ず会いにきてください」
聖女様との別れの際に言われた言葉が、今も耳元で囁かれているようだった。この腕に収まっていた小さな体を思い出して、神殿までの道が長く感じた。
会場では既にダンスタイムが始まっていた。ホールをゆっくりと回り、それでも心は落ち着かなかった。周りを見渡して、どこの誰とも分からない男と聖女様が踊っている姿を想像したら身震いがしそうなほどの嫌悪感で吐き気がした。いつか誰かと踊るためにエスコートした日が遠く昔のように思えた。
壇上でいつものように会場を見下ろす聖女様を見つけると、安堵のため息がでた。もう聖女様の後ろに控えるのは自分の役目ではなかった。
「聖女様、一曲ご一緒いただけませんか?」
天上人を見上げるように壇上を見上げると、いつか見た踊り出しそうなほどの笑顔を向けられていた。自分に向けられているのだと気付くまで時間がかかった。それから、ずっと夢を見ているようで、何も考えられなかった。
パーティは途中から参加したこともあり、あっという間に終わってしまった。まだ夢から覚めたくはなかった。聖女様の手を離したくはなかった。寝るその瞬間まで、聖女様の隣にいたかった。
「ユリエル、私は貴方と結婚したいと思っています。いつまで私を聖女様と呼ぶのですか?」
聖女様にそう言われても、都合のいい夢を見ているかと実感が湧かなかった。それ位、聖女様と私の間には大きな壁があった。どうにもならない壁があって、私は貴族としての責務を放棄出来なかった。
何も持たない平民なら…騎士団長のように大切なものを何も持たず、護りたいものをただ護れる立場なら…そう考えても貴族の家に生まれてしまったことから逃げると言う選択は出来なかった。
「侯爵はまだまだ若いです。アン様もまだ分かりませんし、私たちの子供が複数出来れば、一人をオルレリアンの後継者に養子に出すのもいいでしょう。それに、もしもの時は国は弟に任せて、ユリエルがオルレリアン家を継いだ後、血筋から養子をとる。ここまで言えば侯爵は頷くしかありませんよ。因みに、父は子供は出来ると言っているので、養子を取る必要はなさそうですよ?ユリエル」
そのどうにも出来ないと思っていた大きな壁は、私ではなく聖女様が崩した。
私ではどうにも出来なかった壁を、小さな身体の護るべき存在だった聖女様が、最も簡単に崩した。
「私で…いいのですか?」
私の口から出たのは、情けない言葉だった。その日、家に帰ると既に神殿からの求婚状が届いていた。社交のために早く王都に出された私は、その足で今日来た道を引き返して領地に帰った。父も母も、まだ領地にいたのだ。
神殿からの正式な求婚状に抗える家は存在しない。それが例えその家の後継者を奪い去るようなことでもだ。
オルレリアン家は神の忠実な僕だ。神託を賜るただ一人の人間を神殿が求めていることが分かると、父は喜んで承諾した。もし、後継者である兄に子どもができなくても、神の子孫がオルレリアンを継ぐ可能性がある。それはとても光栄なことだった。
オルレリアン家当主の受諾書を受け取るまでに三日、五日かかる距離を無理させた馬の疲労は限界に来ていた。それでも一刻でも早く王都に行きたいと馬に飛び乗った。
「聖女様は森にお出かけになられたようです」
各教会で休憩はしたが、ずっと仮眠程度しか取らず、馬も一度教会で乗り換えてきたが、その馬ももう限界だった。
「馬を借りられますか?」
「森に厩舎が出来たので、予備の馬しかないのですか……今は生憎騎士の演習中で…」
「儀式用の馬はどうですか?」
「あぁ!それなら…」
「ではそれを借ります」
神殿の厩舎へ向かうのも焦ったい。森には聖女様の婚約者だった王子いる。二人きりになることはないと言えど、聖女様が王子に心を開いているのは事実。婚約していた時よりも仲が縮まっている。今更馬車でのんびりと行く選択する余裕はなかった。
「わあー!白い馬だよ!」
「うぉー!カッコいいー」
森の細道をかけていると、遠くで子供が手を振るのが見えた。聖女様の馬車もまだ止まっていた。
子供の声を聞いたのか、小屋の前まで来た時には聖女様が小屋から顔を出す。
「聖女様!」
「ユリエル!?」
聖女様の驚いた顔を見るのも久しぶりだ。それが酷く嬉しい。
「聖女様の隣に立つ許可をもらってきました」
「早かったですね」
「聖女様に会いたくて少し無理をしました…」
「確かに、顔色が悪いです」
聖女様が目の前にいる。それはただの貴族にとっては奇跡のようなことだ。気軽に手を握られることも、抱きしめられることが許されることも、全てが奇跡だ。
「ユリエル?」
今思えば、今までの全てが奇跡の連続だった。私にとってのただ一人の女性と添い遂げられる権利を得られたのも奇跡だ。こんなに幸運なことはない。
「聖女様、愛しています。私と結婚していただけますか?」
聖女様はにっこりと笑ったまま返事せず、森にいる不安にかられた。
「……ユリエル、忘れたのですか?シャーリーです」
「シャーリー…」
「はい。ユリエル」
「シャーリー…好きです」
「私もユリエルが好きです」
「シャーリー…この世にある言葉では伝えられないくらい愛しています」
「ふふっ。この世で一番愛してます。私の唯一の王子様!」
どれだけ抱きしめても、手を握っても足りない。いっそ、溶けてグチャグチャになってしまいたかった。
「はいはい!ユリエル!子供の目の前でいつまでもイチャついてんじゃねぇ。聖女様も、人前で抱きつかない!帰りますよ!」
呆れたように騎士団長に止められても、もう離れたくはなかった。
「ユリエル、一緒に帰りましょう」
「はい」
聖女様を持ち抱えると、慣れたように聖女様は首に腕を回した。
「幸せですね。ユリエル」
そう言って聖女様は頬に唇を寄せた。
「私はシャーリーと出会ってからずっと幸せです」
子供達に見えないように背を向けながら、腕の中の聖女様に口付けた。今はエリアスと名乗る王子が、強く手を握りしめるのを片目に、聖女様と馬車に乗り込んだ。騎士団長はもう、一緒に同乗することはなかった。
0
お気に入りに追加
603
あなたにおすすめの小説

本当の聖女は私です〜偽物聖女の結婚式のどさくさに紛れて逃げようと思います〜
桜町琴音
恋愛
「見て、マーガレット様とアーサー王太子様よ」
歓声が上がる。
今日はこの国の聖女と王太子の結婚式だ。
私はどさくさに紛れてこの国から去る。
本当の聖女が私だということは誰も知らない。
元々、父と妹が始めたことだった。
私の祖母が聖女だった。その能力を一番受け継いだ私が時期聖女候補だった。
家のもの以外は知らなかった。
しかし、父が「身長もデカく、気の強そうな顔のお前より小さく、可憐なマーガレットの方が聖女に向いている。お前はマーガレットの後ろに隠れ、聖力を使う時その能力を使え。分かったな。」
「そういうことなの。よろしくね。私の為にしっかり働いてね。お姉様。」
私は教会の柱の影に隠れ、マーガレットがタンタンと床を踏んだら、私は聖力を使うという生活をしていた。
そして、マーガレットは戦で傷を負った皇太子の傷を癒やした。
マーガレットに惚れ込んだ王太子は求婚をし結ばれた。
現在、結婚パレードの最中だ。
この後、二人はお城で式を挙げる。
逃げるなら今だ。
※間違えて皇太子って書いていましたが王太子です。
すみません

嫌われ聖女さんはとうとう怒る〜今更大切にするなんて言われても、もう知らない〜
𝓝𝓞𝓐
ファンタジー
13歳の時に聖女として認定されてから、身を粉にして人々のために頑張り続けたセレスティアさん。どんな人が相手だろうと、死にかけながらも癒し続けた。
だが、その結果は悲惨の一言に尽きた。
「もっと早く癒せよ! このグズが!」
「お前がもっと早く治療しないせいで、後遺症が残った! 死んで詫びろ!」
「お前が呪いを防いでいれば! 私はこんなに醜くならなかったのに! お前も呪われろ!」
また、日々大人も気絶するほどの魔力回復ポーションを飲み続けながら、国中に魔物を弱らせる結界を張っていたのだが……、
「もっと出力を上げんか! 貴様のせいで我が国の騎士が傷付いたではないか! とっとと癒せ! このウスノロが!」
「チッ。あの能無しのせいで……」
頑張っても頑張っても誰にも感謝されず、それどころか罵られるばかり。
もう我慢ならない!
聖女さんは、とうとう怒った。
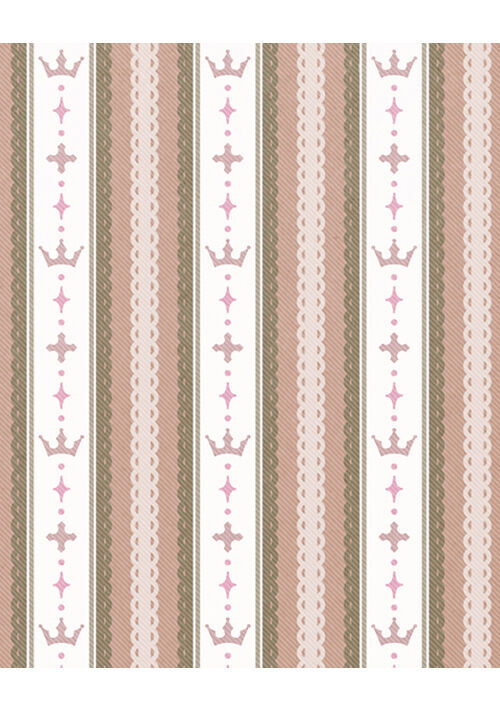
【完結】「神様、辞めました〜竜神の愛し子に冤罪を着せ投獄するような人間なんてもう知らない」
まほりろ
恋愛
王太子アビー・シュトースと聖女カーラ・ノルデン公爵令嬢の結婚式当日。二人が教会での誓いの儀式を終え、教会の扉を開け外に一歩踏み出したとき、国中の壁や窓に不吉な文字が浮かび上がった。
【本日付けで神を辞めることにした】
フラワーシャワーを巻き王太子と王太子妃の結婚を祝おうとしていた参列者は、突然現れた文字に驚きを隠せず固まっている。
国境に壁を築きモンスターの侵入を防ぎ、結界を張り国内にいるモンスターは弱体化させ、雨を降らせ大地を潤し、土地を豊かにし豊作をもたらし、人間の体を強化し、生活が便利になるように魔法の力を授けた、竜神ウィルペアトが消えた。
人々は三カ月前に冤罪を着せ、|罵詈雑言《ばりぞうごん》を浴びせ、石を投げつけ投獄した少女が、本物の【竜の愛し子】だと分かり|戦慄《せんりつ》した。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」
アルファポリスに先行投稿しています。
表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
2021/12/13、HOTランキング3位、12/14総合ランキング4位、恋愛3位に入りました! ありがとうございます!

【完結】ニセ聖女と追放されたので、神官長と駆け落ちします〜守護がなくなり魔物が襲来するので戻ってこい? では、ビジネスしましょう〜
禅
恋愛
婚約者の王太子からニセ聖女の烙印を押された私は喜んで神殿から出ていった。なぜか、神官長でエルフのシンも一緒に来ちゃったけど。
私がいなくなった国は守護していた結界がなくなり、城は魔物に襲来されていた。
是非とも話し合いを、という国王からの手紙に私は再び城へ。
そこで私はある条件と交換に、王を相手にビジネスをする。
※小説家になろうにも掲載

「お前は聖女ではない!」と妹に吹き込まれた王子に婚約破棄されました。はい、聖女ではなく、『大聖女』ですが何か?
つくも
恋愛
王国リンカーンの王女であるセシリア。セシリアは聖女として王国を支えてきました。しかし、腹違いの妹に「本当の聖女ではない」と吹き込まれた婚約者の王子に婚約破棄をされ、追放されてしまうのです。
そんな時、隣国の王宮にセシリアは『大聖女』としてスカウトされます。そう、セシリアはただの聖女を超えた存在『大聖女』だったのです。
王宮でセシリアは王子に溺愛され、『大聖女』として皆から慕われます。小国はセシリアの力によりどんどん発展していき、大国に成長するのです。
一方、その頃、聖女として代わりの仕事を担うはずだった妹は失敗の連続。彼女にセシリアの代わりは荷が重すぎたようです。次第に王国は衰えていき、婚約者の王子からは婚約破棄され、最後には滅亡していくのです。
これは聖女ではないと追放されたセシリアが、ホワイトな王宮で大聖女として皆から慕われ、幸せになるお話です。

虐げられた第一王女は隣国王室の至宝となる
珊瑚
恋愛
王族女性に聖なる力を持って産まれる者がいるイングステン王国。『聖女』と呼ばれるその王族女性は、『神獣』を操る事が出来るという。生まれた時から可愛がられる双子の妹とは違い、忌み嫌われてきた王女・セレナが追放された先は隣国・アバーヴェルド帝国。そこで彼女は才能を開花させ、大切に庇護される。一方、セレナを追放した後のイングステン王国では国土が荒れ始めて……
ゆっくり更新になるかと思います。
ですが、最後までプロットを完成させておりますので意地でも完結させますのでそこについては御安心下さいm(_ _)m

【ショートショート/完結】ふわふわした聖獣様とそのご家族と追放されかかっている聖女のわたし
雪野原よる
恋愛
聖獣さまを(文字通り)胸元に住まわせた私は、王子さまに婚約破棄されてしまいました。ですが、特に困ることは無いようなのです……
さらっと書いたもふもふネタです。

聖女に巻き込まれた、愛されなかった彼女の話
下菊みこと
恋愛
転生聖女に嵌められた現地主人公が幸せになるだけ。
主人公は誰にも愛されなかった。そんな彼女が幸せになるためには過去彼女を愛さなかった人々への制裁が必要なのである。
小説家になろう様でも投稿しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















