12 / 32
第十二話 国父
しおりを挟む
翌日、ルーカスは一睡もできないまま、昼過ぎまでぐずぐずとベッドの上にいた。
相変わらず靴磨きの道具を胸に抱きしめたままだ。彼の頭の中には家に帰りたいという気持ちが渦巻いている。
使用人たちは代わる代わるルーカスに声をかけた。
食事、風呂、菓子、遊び……。
ルーカスはどんな誘いにものらなかった。
彼は口をぎゅっとつぐんで「家に帰りたいです」という言葉以外何も発さない。
使用人のうち、何人かは頑迷なルーカスの態度に腹を立て、足音荒く部屋を出て行った。それでもルーカスは微動だにしない。
使用人のなかで一番年かさであるロイはそんなルーカスに根気よく話しかけ続けた。
「お着替えだけでも」
彼はそう言って粘り続けている。
彼の手にはシルクのガウンがある。ルーカスは昨日外出したときの服のままであった。
ルーカスは首を縦には振らない。そもそも、ルーカスは服をころころと変えるような生活を送っていなかった。そしてそのような生活をダン帝国人に与えられる理由もない。ルーカスは頑固だった。
しかし、それ以上にロイは粘り強かった。
何時間にも及ぶ交渉の末、彼はルーカスの髪をブラシで梳かす許可を得た。
「失礼します」
猪の毛で作られたブラシでルーカスの黒い髪を梳かす。ルーカスはベッドに横になったままであるが、使用人は器用にルーカスの髪を整えていく。
「せっかくきれいな髪ですから、手入れをしませんとね」
ロイはそう言った。ルーカスはそれは嘘だと思った。ルーカスの髪は日に焼け、毛先が茶色っぽくなっている。栄養も足りていないせいで、髪は細く、ともすれば簡単に抜け落ちることさえあるのだ。ルーカスは使用人の腕を払いのけた。
しかし使用人はルーカスの手を掴み、そのまま手の甲を撫でた。
「手も、クリームを塗っておきましょうか」
ルーカスの手は工廠での労働、畑仕事、靴磨きによって荒れていた。指先はひび割れ、皮がむけ、あかぎれている。使用人はその手にゆっくりとクリームを塗りこんだ。この邸宅に来てから、この使用人はルーカスの体の手入れを熱心に行っていた。彼の手つきはいつも通りだ。やさしく、丁寧。ルーカスは肉厚の使用人の手を今度は振り払えなかった。
ロイはひそかに息を吐いた。彼は、ルーカスのいかにも浮浪児といった様子の外見、特に髪と手についてきれいにしてあげたいと思って毎日手入れをしていた。
年かさの彼はバートンの子ども時代の面倒をみた使用人でもある。彼には名門ハヴォック家に仕える使用人としての矜持がある。その矜持ゆえにこの西のカントット国まではるばるバートンに随行したのだ。
彼にとって、ルーカスは待ちに待った主の子なのだ。バートンに「息子の世話はお前に頼みたい」と言われて、断るという選択肢などない。
ルーカスの外見は美しいバートンに似ていない。しかし、醜い外見をしているわけでもない。
きれいに手入れをすれば、主の隣に立っても見劣りしないくらいにはなるはずである。彼がルーカスにできるのはこれくらいしかない。ルーカスがその手入れを受け入れたことに安堵した。
ルーカスはずっと沈黙していた。彼は彼で、この使用人の気持ちなど知る由もないのだ。ルーカスはいま自分のことで精いっぱいだ。
しばらく経って、ルーカスの部屋に別の使用人が入ってきた。丸い眼鏡をかけて髪に油を塗ってかためている。いつもバートンの後ろについている使用人だ。
「バートン様から許可がでました。少しだけカルヴァの街をご覧になって、それから……船を用意しています。もしご覧になって、それでもお心が変わらないようでしたら、私どもがイレまでお送ります」
ルーカスはようやくベッドから起き上がった。
*
カルヴァは東西に細長いかたちをした都市である。主要部分は平野であり、西はカルヴァ湾に面している。西部は港を中心とする工業地帯、中心地に政治中枢機関、東部に財閥の本社群をもち、カントット国の人口の20パーセントが集中している。
バートンの邸宅は人工的につくられた小高い丘の上に位置しており、手入れされた林に囲まれている。その林を抜けるとすぐに政治の中枢機関となる建物が立ち並ぶ。
ルーカスは先日その光景を見たばかりである。議事堂、裁判所、そして掲げられたダン帝国の旗――しかし、今日、その光景は一変していた。
ルーカスは息を呑んだ。
――旗だ。
ダン帝国の黄色い旗と、カントット国の青い旗である。二つが並んで掲げられ、初夏の風に揺られている。
子どもたちは旗を見上げ、両手を伸ばす。煤けていたカルヴァの歴史的な建物たちも、誇りを取り戻したように輝いて見えた。
「あ……」
ルーカスは目を見開いた。自分が見ている景色が信じられなかった。
「これ……」
「バートン様がそうご指示なさったそうです。ダン帝国の意思を示す、と」
「バートンさんが……?」
ルーカスは首を振った。昨日が悪夢で、いまが現実なのか、それとも昨日が現実で、いまが夢なのだろうか。
しょせんただの旗だ。それはルーカスもわかっている。しかしそれが無数に掲げられたカルヴァは、夢の中の景色のようだった。
ルーカスは自分のことを愛国心があるほうではないと思っていた。しかし、翻る旗を見てこみあげるものがあった。昨日は確かに敗戦の意味を体現していた街が、いまは共生を示している。それは希望となってルーカスの胸をつきさした。
使用人は丸い眼鏡を一度直したあと「主は」と切り出した。
「ラジオ塔でお待ちです。会われますか?」
「……会います。会わせてください……」
*
ラジオ塔の展望台にバートンは立っていた。その塔はカルヴァの中でもっとも高い建造物である。そこからはカルヴァの街が一望できた。
ルーカスが近づくと、カルヴァの街を見ていたバートンは振り返った。
「……意外と、家の中に隠している人が多かったね」
「え?」
「旗だよ。カントット国の旗。一から作るとなると大仕事だと思っていたんだけれど、意外とみんな隠し持っていた」
バートンは笑った。
「ルーカスも持っていたりするかい?」
「……」
ルーカスは抱きかかえた靴磨きの道具箱の中から、一枚の布を取り出した。ぼろぼろになって擦り切れたそれは、父が出征するのを見送るときに振ったカントット国の旗である。
バートンはそれを見て、胸を押さえた。
「ああ、そうか……気が付いてやれなくて、すまなかった。旗は大切なものと結びつくものだ……」
バートンはルーカスを抱きしめた。
「私は、カントット国を愛している。滅ぼしたりしない。この景色に誓っていい」
ルーカスは自分の体が弛緩していくのがわかった。ここまで、ずっと緊張していたようだった。
涙があふれてきた。それから、ルーカスは子どものようにしゃくりあげて泣いた。自分の足元がようやく固まっていくような気がした。バートンはカントット国を愛してくれている。ルーカスはずっとバートンの庇護をうけることは祖国への裏切りであるように感じていた。庇護をうける自分が許せなかった。しかし、いまようやく庇護をうける自分を赦すことができた。
バートンはルーカスの頬を撫でて、それから言った。
「私も一枚持っているんだよ」
彼が差し出したのは古ぼけたダン帝国の旗であった。ルーカスの持っている旗よりひとまわり大きいそれをバートンは広げて見せた。
「昔、訓練兵時代に教官からもらったものなんだ。同期と寄せ書きしてね……若かった」
その言葉通り、旗にはいくつかの筆跡で文字が書かれていた。しかしそれらは滲み、ほとんど読み取れるものはなかった。それくらい、長年バートンと共にあった旗なのだ。
「ルーカス、交換しようか」
「え?」
「友好の印に」
「……」
ルーカスはためらったあと、頷いて了承の意思を示した。
最初は旗を交換することになんの意味があるのかわからなかったが、ルーカスの旗がバートンの手に渡り、反対にバートンの旗がルーカスの手にやってきた瞬間、その意味を理解した。
――尊重されている。
ルーカスはその旗をぎゅっと胸に抱きしめた。バートンに会ってから、カントット人としての自分を否定されているような気がしていた。それが、いまバートンはカントット人としてルーカスを認めてくれていることがよく伝わった。
バートンは言った。
「いますぐに、ルーカスが私を父と思えないのも仕方ない」
でも、と彼は続ける。
「私はカントット人全員を幸せにするのが目標だから、その手始めとしてカントット人の君を幸せにしてあげる、ということでどうだろう?」
バートンは優しく微笑んでいる。その笑みに、ルーカスの胸が跳ねた。美人のとろけるような笑顔は心臓に悪い。
頬が火照るのがわかった。誤魔化すために頷いて「ありがとうございます」と言うので精いっぱいだった。
相変わらず靴磨きの道具を胸に抱きしめたままだ。彼の頭の中には家に帰りたいという気持ちが渦巻いている。
使用人たちは代わる代わるルーカスに声をかけた。
食事、風呂、菓子、遊び……。
ルーカスはどんな誘いにものらなかった。
彼は口をぎゅっとつぐんで「家に帰りたいです」という言葉以外何も発さない。
使用人のうち、何人かは頑迷なルーカスの態度に腹を立て、足音荒く部屋を出て行った。それでもルーカスは微動だにしない。
使用人のなかで一番年かさであるロイはそんなルーカスに根気よく話しかけ続けた。
「お着替えだけでも」
彼はそう言って粘り続けている。
彼の手にはシルクのガウンがある。ルーカスは昨日外出したときの服のままであった。
ルーカスは首を縦には振らない。そもそも、ルーカスは服をころころと変えるような生活を送っていなかった。そしてそのような生活をダン帝国人に与えられる理由もない。ルーカスは頑固だった。
しかし、それ以上にロイは粘り強かった。
何時間にも及ぶ交渉の末、彼はルーカスの髪をブラシで梳かす許可を得た。
「失礼します」
猪の毛で作られたブラシでルーカスの黒い髪を梳かす。ルーカスはベッドに横になったままであるが、使用人は器用にルーカスの髪を整えていく。
「せっかくきれいな髪ですから、手入れをしませんとね」
ロイはそう言った。ルーカスはそれは嘘だと思った。ルーカスの髪は日に焼け、毛先が茶色っぽくなっている。栄養も足りていないせいで、髪は細く、ともすれば簡単に抜け落ちることさえあるのだ。ルーカスは使用人の腕を払いのけた。
しかし使用人はルーカスの手を掴み、そのまま手の甲を撫でた。
「手も、クリームを塗っておきましょうか」
ルーカスの手は工廠での労働、畑仕事、靴磨きによって荒れていた。指先はひび割れ、皮がむけ、あかぎれている。使用人はその手にゆっくりとクリームを塗りこんだ。この邸宅に来てから、この使用人はルーカスの体の手入れを熱心に行っていた。彼の手つきはいつも通りだ。やさしく、丁寧。ルーカスは肉厚の使用人の手を今度は振り払えなかった。
ロイはひそかに息を吐いた。彼は、ルーカスのいかにも浮浪児といった様子の外見、特に髪と手についてきれいにしてあげたいと思って毎日手入れをしていた。
年かさの彼はバートンの子ども時代の面倒をみた使用人でもある。彼には名門ハヴォック家に仕える使用人としての矜持がある。その矜持ゆえにこの西のカントット国まではるばるバートンに随行したのだ。
彼にとって、ルーカスは待ちに待った主の子なのだ。バートンに「息子の世話はお前に頼みたい」と言われて、断るという選択肢などない。
ルーカスの外見は美しいバートンに似ていない。しかし、醜い外見をしているわけでもない。
きれいに手入れをすれば、主の隣に立っても見劣りしないくらいにはなるはずである。彼がルーカスにできるのはこれくらいしかない。ルーカスがその手入れを受け入れたことに安堵した。
ルーカスはずっと沈黙していた。彼は彼で、この使用人の気持ちなど知る由もないのだ。ルーカスはいま自分のことで精いっぱいだ。
しばらく経って、ルーカスの部屋に別の使用人が入ってきた。丸い眼鏡をかけて髪に油を塗ってかためている。いつもバートンの後ろについている使用人だ。
「バートン様から許可がでました。少しだけカルヴァの街をご覧になって、それから……船を用意しています。もしご覧になって、それでもお心が変わらないようでしたら、私どもがイレまでお送ります」
ルーカスはようやくベッドから起き上がった。
*
カルヴァは東西に細長いかたちをした都市である。主要部分は平野であり、西はカルヴァ湾に面している。西部は港を中心とする工業地帯、中心地に政治中枢機関、東部に財閥の本社群をもち、カントット国の人口の20パーセントが集中している。
バートンの邸宅は人工的につくられた小高い丘の上に位置しており、手入れされた林に囲まれている。その林を抜けるとすぐに政治の中枢機関となる建物が立ち並ぶ。
ルーカスは先日その光景を見たばかりである。議事堂、裁判所、そして掲げられたダン帝国の旗――しかし、今日、その光景は一変していた。
ルーカスは息を呑んだ。
――旗だ。
ダン帝国の黄色い旗と、カントット国の青い旗である。二つが並んで掲げられ、初夏の風に揺られている。
子どもたちは旗を見上げ、両手を伸ばす。煤けていたカルヴァの歴史的な建物たちも、誇りを取り戻したように輝いて見えた。
「あ……」
ルーカスは目を見開いた。自分が見ている景色が信じられなかった。
「これ……」
「バートン様がそうご指示なさったそうです。ダン帝国の意思を示す、と」
「バートンさんが……?」
ルーカスは首を振った。昨日が悪夢で、いまが現実なのか、それとも昨日が現実で、いまが夢なのだろうか。
しょせんただの旗だ。それはルーカスもわかっている。しかしそれが無数に掲げられたカルヴァは、夢の中の景色のようだった。
ルーカスは自分のことを愛国心があるほうではないと思っていた。しかし、翻る旗を見てこみあげるものがあった。昨日は確かに敗戦の意味を体現していた街が、いまは共生を示している。それは希望となってルーカスの胸をつきさした。
使用人は丸い眼鏡を一度直したあと「主は」と切り出した。
「ラジオ塔でお待ちです。会われますか?」
「……会います。会わせてください……」
*
ラジオ塔の展望台にバートンは立っていた。その塔はカルヴァの中でもっとも高い建造物である。そこからはカルヴァの街が一望できた。
ルーカスが近づくと、カルヴァの街を見ていたバートンは振り返った。
「……意外と、家の中に隠している人が多かったね」
「え?」
「旗だよ。カントット国の旗。一から作るとなると大仕事だと思っていたんだけれど、意外とみんな隠し持っていた」
バートンは笑った。
「ルーカスも持っていたりするかい?」
「……」
ルーカスは抱きかかえた靴磨きの道具箱の中から、一枚の布を取り出した。ぼろぼろになって擦り切れたそれは、父が出征するのを見送るときに振ったカントット国の旗である。
バートンはそれを見て、胸を押さえた。
「ああ、そうか……気が付いてやれなくて、すまなかった。旗は大切なものと結びつくものだ……」
バートンはルーカスを抱きしめた。
「私は、カントット国を愛している。滅ぼしたりしない。この景色に誓っていい」
ルーカスは自分の体が弛緩していくのがわかった。ここまで、ずっと緊張していたようだった。
涙があふれてきた。それから、ルーカスは子どものようにしゃくりあげて泣いた。自分の足元がようやく固まっていくような気がした。バートンはカントット国を愛してくれている。ルーカスはずっとバートンの庇護をうけることは祖国への裏切りであるように感じていた。庇護をうける自分が許せなかった。しかし、いまようやく庇護をうける自分を赦すことができた。
バートンはルーカスの頬を撫でて、それから言った。
「私も一枚持っているんだよ」
彼が差し出したのは古ぼけたダン帝国の旗であった。ルーカスの持っている旗よりひとまわり大きいそれをバートンは広げて見せた。
「昔、訓練兵時代に教官からもらったものなんだ。同期と寄せ書きしてね……若かった」
その言葉通り、旗にはいくつかの筆跡で文字が書かれていた。しかしそれらは滲み、ほとんど読み取れるものはなかった。それくらい、長年バートンと共にあった旗なのだ。
「ルーカス、交換しようか」
「え?」
「友好の印に」
「……」
ルーカスはためらったあと、頷いて了承の意思を示した。
最初は旗を交換することになんの意味があるのかわからなかったが、ルーカスの旗がバートンの手に渡り、反対にバートンの旗がルーカスの手にやってきた瞬間、その意味を理解した。
――尊重されている。
ルーカスはその旗をぎゅっと胸に抱きしめた。バートンに会ってから、カントット人としての自分を否定されているような気がしていた。それが、いまバートンはカントット人としてルーカスを認めてくれていることがよく伝わった。
バートンは言った。
「いますぐに、ルーカスが私を父と思えないのも仕方ない」
でも、と彼は続ける。
「私はカントット人全員を幸せにするのが目標だから、その手始めとしてカントット人の君を幸せにしてあげる、ということでどうだろう?」
バートンは優しく微笑んでいる。その笑みに、ルーカスの胸が跳ねた。美人のとろけるような笑顔は心臓に悪い。
頬が火照るのがわかった。誤魔化すために頷いて「ありがとうございます」と言うので精いっぱいだった。
29
お気に入りに追加
82
あなたにおすすめの小説

悪役令息に転生して絶望していたら王国至宝のエルフ様にヨシヨシしてもらえるので、頑張って生きたいと思います!
梻メギ
BL
「あ…もう、駄目だ」プツリと糸が切れるように限界を迎え死に至ったブラック企業に勤める主人公は、目覚めると悪役令息になっていた。どのルートを辿っても断罪確定な悪役令息に生まれ変わったことに絶望した主人公は、頑張る意欲そして生きる気力を失い床に伏してしまう。そんな、人生の何もかもに絶望した主人公の元へ王国お抱えのエルフ様がやってきて───!?
【王国至宝のエルフ様×元社畜のお疲れ悪役令息】
▼この作品と出会ってくださり、ありがとうございます!初投稿になります、どうか温かい目で見守っていただけますと幸いです。
▼こちらの作品はムーンライトノベルズ様にも投稿しております。
▼毎日18時投稿予定

【完結】別れ……ますよね?
325号室の住人
BL
☆全3話、完結済
僕の恋人は、テレビドラマに数多く出演する俳優を生業としている。
ある朝、テレビから流れてきたニュースに、僕は恋人との別れを決意した。
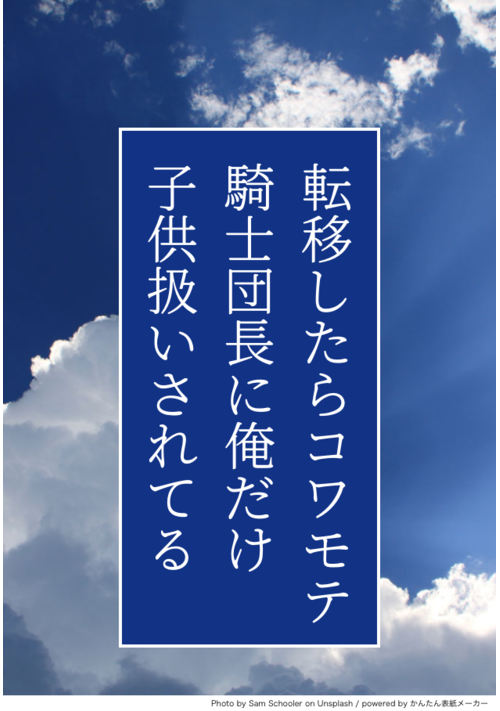
転移したらなぜかコワモテ騎士団長に俺だけ子供扱いされてる
塩チーズ
BL
平々凡々が似合うちょっと中性的で童顔なだけの成人男性。転移して拾ってもらった家の息子がコワモテ騎士団長だった!
特に何も無く平凡な日常を過ごすが、騎士団長の妙な噂を耳にしてある悩みが出来てしまう。


孕めないオメガでもいいですか?
月夜野レオン
BL
病院で子供を孕めない体といきなり診断された俺は、どうして良いのか判らず大好きな幼馴染の前から消える選択をした。不完全なオメガはお前に相応しくないから……
オメガバース作品です。

平凡なSubの俺はスパダリDomに愛されて幸せです
おもち
BL
スパダリDom(いつもの)× 平凡Sub(いつもの)
BDSM要素はほぼ無し。
甘やかすのが好きなDomが好きなので、安定にイチャイチャ溺愛しています。
順次スケベパートも追加していきます


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















