お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

平凡冒険者のスローライフ
上田なごむ
ファンタジー
26歳独身動物好きの主人公大和希は、神様によって魔物・魔法・獣人等ファンタジーな世界観の異世界に転移させられる。
平凡な能力値、野望など抱いていない彼は、冒険者としてスローライフを目標に日々を過ごしていく。
果たして、彼を待ち受ける出会いや試練は如何なるものか……
ファンタジー世界に向き合う、平凡な冒険者の物語。

異世界で演技スキルを駆使して運命を切り開く
井上いるは
ファンタジー
東京の夜、ネオンが輝く街を歩く中、主人公の桜井紗良(さくらい さら)は心地よい疲れを感じていた。彼女は人気ドラマの撮影を終えたばかりで、今夜は久しぶりの自由な時間だ。しかし、その自由も束の間、奇妙な感覚が彼女を襲った。突然、足元がふらつき、視界が暗転する。
目が覚めると、紗良は見知らぬ場所に立っていた。周りを見回すと、そこはまるで中世ヨーロッパのような街並み。石畳の道、木造の家々、そして遠くには壮麗な城が見える。「これは一体…」と呟く紗良。しかし、驚くべきことはそれだけではなかった。近くにいた人々の服装や言葉遣いが、まるで演劇の中にいるかのようだったのだ。

魔女の弟子ー童貞を捨てた三歳児、異世界と日本を行ったり来たりー
あに
ファンタジー
|風間小太郎《カザマコタロウ》は彼女にフラれた。公園でヤケ酒をし、美魔女と出会い一夜を共にする。
起きると三歳児になってしまってさぁ大変。しかも日本ではなく異世界?!
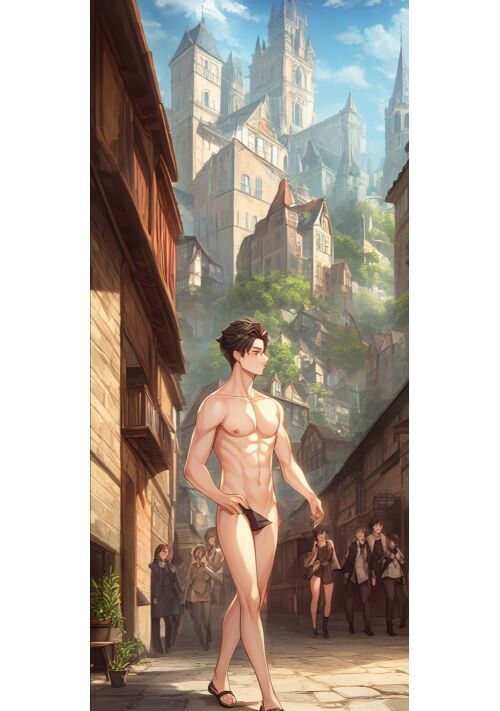
ゲームのモブに転生したと思ったら、チートスキルガン積みのバグキャラに!? 最強の勇者? 最凶の魔王? こっちは最驚の裸族だ、道を開けろ
阿弥陀乃トンマージ
ファンタジー
どこにでもいる平凡なサラリーマン「俺」は、長年勤めていたブラック企業をある日突然辞めた。
心は晴れやかだ。なんといってもその日は、昔から遊んでいる本格的ファンタジーRPGシリーズの新作、『レジェンドオブインフィニティ』の発売日であるからだ。
「俺」はゲームをプレイしようとするが、急に頭がふらついてゲーミングチェアから転げ落ちてしまう。目覚めた「俺」は驚く。自室の床ではなく、ゲームの世界の砂浜に倒れ込んでいたからである、全裸で。
「俺」のゲームの世界での快進撃が始まる……のだろうか⁉

一宿一飯の恩義で竜伯爵様に抱かれたら、なぜか監禁されちゃいました!
当麻月菜
恋愛
宮坂 朱音(みやさか あかね)は、電車に跳ねられる寸前に異世界転移した。そして異世界人を保護する役目を担う竜伯爵の元でお世話になることになった。
しかしある日の晩、竜伯爵当主であり、朱音の保護者であり、ひそかに恋心を抱いているデュアロスが瀕死の状態で屋敷に戻ってきた。
彼は強い媚薬を盛られて苦しんでいたのだ。
このまま一晩ナニをしなければ、死んでしまうと知って、朱音は一宿一飯の恩義と、淡い恋心からデュアロスにその身を捧げた。
しかしそこから、なぜだかわからないけれど監禁生活が始まってしまい……。
好きだからこそ身を捧げた異世界女性と、強い覚悟を持って異世界女性を抱いた男が異世界婚をするまでの、しょーもないアレコレですれ違う二人の恋のおはなし。
※いつもコメントありがとうございます!現在、返信が遅れて申し訳ありません(o*。_。)oペコッ 甘口も辛口もどれもありがたく読ませていただいてます(*´ω`*)
※他のサイトにも重複投稿しています。


マイナー18禁乙女ゲームのヒロインになりました
東 万里央(あずま まりお)
恋愛
十六歳になったその日の朝、私は鏡の前で思い出した。この世界はなんちゃってルネサンス時代を舞台とした、18禁乙女ゲーム「愛欲のボルジア」だと言うことに……。私はそのヒロイン・ルクレツィアに転生していたのだ。
攻略対象のイケメンは五人。ヤンデレ鬼畜兄貴のチェーザレに男の娘のジョバンニ。フェロモン侍従のペドロに影の薄いアルフォンソ。大穴の変人両刀のレオナルド……。ハハッ、ロクなヤツがいやしねえ! こうなれば修道女ルートを目指してやる!
そんな感じで涙目で爆走するルクレツィアたんのお話し。

魔界最強に転生した社畜は、イケメン王子に奪い合われることになりました
タタミ
BL
ブラック企業に務める社畜・佐藤流嘉。
クリスマスも残業確定の非リア人生は、トラックの激突により突然終了する。
死後目覚めると、目の前で見目麗しい天使が微笑んでいた。
「ここは天国ではなく魔界です」
天使に会えたと喜んだのもつかの間、そこは天国などではなく魔法が当たり前にある世界・魔界だと知らされる。そして流嘉は、魔界に君臨する最強の支配者『至上様』に転生していたのだった。
「至上様、私に接吻を」
「あっ。ああ、接吻か……って、接吻!?なんだそれ、まさかキスですか!?」
何が起こっているのかわからないうちに、流嘉の前に現れたのは美しい4人の王子。この4王子にキスをして、結婚相手を選ばなければならないと言われて──!?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















