13 / 25
雪嶺とアリストクラット
噂が好きな聖女様
しおりを挟む
~噂が好きな聖女様~
マツリが仲間になって早くも一週間が経った。
金華猫の血の混ざっていた猫達ほかサーカスから連れ出した魔獣達はカルマアラネ・アンダージャン公国に心良く受け入れられたのを見届けてから、俺達はとりあえず寄り道を交えつつ、マツリの故郷へと歩く。
因みに俺とマサリはその町に行ったことはあるが、余りにもボロボロで、しっかりと調べたことはない。マツリの案内で町の中心辺りまで足を踏み入れられれば宝玉の手がかりがあるかもしれない。宝玉があればなおよし。
そんな魂胆のもと、俺達はトートシティーへ向かっていた。
――猫達を預けたあと、初めはずっと猫達のことが気になって、小振りな耳をピンと立てしきりに後ろを向いたりしていたマツリだったが、マサリが一言「信頼出来る人に定期的に写真を送ってもらおうか」と提案し、翌日白黒の写真と短い手紙が同封された封筒がマツリの元に届いたのでマツリは安心して旅に集中するようになった。
……いや待て。
信頼出来る人って誰だ?ってか、どうやって深い森の中に手紙が届いたんだ?
そう聞いた俺だったが、マサリは飄々とした態度で「正確には、ピ…いや、知り合いの知り合い、もしくはそのまた知り合いが手伝ってくれてるんだけど」と答えになっていない答えを返してくる。ちょっとだけ目を泳がせる。どちらかというと溺れたような酷い動揺に呑まれた泳がせ方だった。
待て、またまた待てよ。
ピってなんだ。ピって。俺は昔彼氏のことを彼ピとかそう呼ぶと聞いたことがある気がするぞ。それは大分昔、うんと遠い世界で聞いたことだが、若い奴らの考えることはどこでも同じだろ。
え、彼氏いるの?いや、駄目って訳じゃないんだけど、え?
恐る恐る訊ねる。
「マサリお前、か、彼氏がいるのか」
「まさか、いるわけないじゃん。自分の彼氏はゴシップ紙だよ」
「待てせめて新聞紙くらいにしてくれ」
「マサ姉ー、ゴシップ氏って名字?名前?彼氏さんいるなんて大人だね!シンブン氏さんもあんまり聞かない名前だなぁ」
「マツリ、マサリは今読んでるやつを彼氏と言ったんだ」
「あ、そっち?」
「そっち」
俺はマツリを訂正しながら安堵する。俺が二十歳になる前からずっと一緒に旅してたんだ、まさかそんな大事な秘密をずっと気付かないわけないもんな。さすがにそんなに鈍くないよな…?俺。
と、そんなひと悶着も数日前のことで、俺達は今、今日野営するために比較的夜でも木陰にならずに明るくなる平地を探していた。もうじきに夕暮れはくるし、そうなれば夜も早い。かといって、今から間に合う町は無いしな。
そして俺が軽く準備をしている間、お年頃の二人は後ろで地面に誰かがへし折っただろう太めの落ちた枝で落書きかなにかをして遊んでいるらしい。
「で、これが町にあった聖女像…」
「聖女様か~。マサ姉は見たことあるの?」
「ないね。どこかにいるはずなんだけど、一度も見たことがない。世界にただ一人だけなんだから、見つけるのは難しいけど」
なるほど、町で見かけた聖女像の話のようだ。昔拝んだ時も綺麗だったけど、今回は手を合わせずに来てしまったな。
にしても聖女様か。確かに、俺も会ってみたいもんだな。
俺はナップサックから残り十本しかないサーカステント柄のマッチ箱と、牛と魔物の干し肉、そして道中生えていた木々からもぎったいくつか暖色系の果物を取り出すと、表面だけは綺麗にしているチェック柄のテーブルクロスをそのまま泥が乾いて間もない土の上に敷く。塩や粉末状の唐辛子や砂糖や最近手に入れた梅シロップなどをそばに配置する。くしゃみをしながら、集めていた枝達に火をつける。寒々しさが幾分か和らいだ。今日返り討ちにした魔物の肉や角や目玉を、少し離れたところで改めて整理する。
しかしいつもは火をつければ道端で遊んでいても一目散にご飯を食べに来る二人だが、今日は一向にやって来る気配がない。
「二人とも、食べてい…」
二人の方を振り向く。
「「サトリ様!」」
「うわっ!?」
振り向いた途端、二人はぐいっと俺に近づいてきた。瞳には輝きが見えて、二人の濁りない目をまばゆく装飾していた。俺はやや狼狽えながら応対する。
「な、なんだよ…」
「あのねあのね、ここ行こう!」
ばっと、マツリはマサリの紙製の大きな地図を広げる。
マサリはさっと地図の前に飛び出し、お気に入りの鉛筆でぐるりとひとつ、ずたぼろに抉れたどら焼きみたいな形の丸を描いた。
「ペナトルイン王国か。」
「そう!ここから近いし、マツリの故郷とはほんのちょっと離れるだけだし、寄り道には良くない!?」
まあ、別に急いだ旅路じゃないし、良いけど。
俺一人では行ったことがある国だし、国境は越えるがカルマアラネ・アンダージャン公国のようにすぐに越えられるだろうから、別に困ったこともないし。空気もうまく、穏和な国だ。
素直に承諾しようとして、俺はふと口をつぐむ。この国は確か、亜人排斥主義じゃなかったか?
「あー…」
とりあえず俺は二人に飯を食うよう促しながら、その国に行くメリットとデメリットをあげてみる。差別のあるこの国にマツリを連れて行くのは嫌だよな。
それからまた少し考えて、考え直す。
いや、違う。
たまたま、このベニートシティー…というか今いるこの大きな国全体の風潮的にはそういう主張がないわけだが、ほかの国にはだいたい差別主義が根っこの方から広まっている。なにもペナトルイン王国だけの話じゃないんだ。現に、王国の人達は皆気さくだった。
つまりは今、ここで避けていたとしても必ずそんな問題にはぶち当たるわけで。
だが、だからといって「この国はお前を良く思わないからフードでも買うか」とでも言えば良いのか?自衛と差別の境界はどこだ。
「…因みに、なんでお前らはそこに行きたいんだ?」
俺は干し肉に適当に塩を振りかけて食べる。料理?そんなもの俺が、俺達が出来るわけがない。
俺が訊ねれば、マツリとマサリは互いに端整な顔を付き合わせ、マツリは友人の棺の中に詰めてやった花を見たかのように慈愛を込めて笑い、マサリは冒険前日に背負ってみたリュックの重みに感動したような笑顔を見せた。
「聖女様がいるかもしれないって噂なんだ!一目でも見てみたい!」
そして汚れた地方新聞紙を見せる。どうやら森に、隠すように捨てられていたらしい。ペナトルイン王国のものだろうか。……R指定品じゃなくて良かった。
マツリはまた笑う。
「一目でも良いから話してみたいんだ」
「そうだよな」
「お姉様が会って話をしたいんだって。」
「へえ…」
「それで、だから、もし許されたら、お姉様を見つけたらもう一回一緒にお話ししに行きたいんだ」
「本物かどうかは、わからないぞ?」
「でも、可能性はあるじゃん?」
そう言ったのはマサリだった。
「マサリはなんで会いたいんだ?」
「有名人じゃん」
「ミーハーだな」
「サトリもでしょ」
まあ、そうだけど。
俺はまた本の少しだけ悩んで、グミや季節外れのクワの他にヒヨドリジョウゴの小さな実をもぎってしまってたことに気付いて慌ててそれらをテーブルクロスから放り出しながら、頷いた。
二人をペナトルイン王国に連れていこう。
「明日の昼にはペナトルイン王国に着く。だが、覚悟をしてもらう」
「覚悟?」
「ペナトルイン王国ってすごく良い国トップテンには含まれるところだよ」
「それでも色々あるんだよ、明日話す。」
マサリは深く首をかしげる。
俺はナップサックを引き寄せて、ここ数日換金用に貯めておいた魔物の素材を数個取り出し、空の小瓶を四つ取り出し、ラストに服の下に隠れたペティナイフの首飾りを取り出す。凝固してしまっているが、セリルガリルの血も抜き取っていて良かった。
よし、あれをつくろう。
これが正しいかはわからないが、少なくとも最悪ではないと思う。
「サト兄、どうしたの?」
「いや、昔作り方を教えて貰った薬がつくれると思ってな。時間かかるから、お前らは先に寝といてくれよ」
「トランプは?」
「二人でどうぞ」
それだけ告げると、俺は念のためもう一度赤い身に毒のあるものが混じっていないか、焚き火の近くで確認し、それからマサリやマサリからなるべく離れたところで薬の製造に取りかかる。マッチを一本取り出し、はなを押さえる。こっからは刺激臭がするからな。
翌朝までぶっ通しで薬物の製造に取りかかったお陰か、朝日が七時を指し示す辺りに輝く頃には薬は四つとも完成していた。
寝巻きのままのマツリが俺の背後に近づいているのに俺は十二歩先まで予測できず、瓶に蓋をすると同時に一度ため息を吐く。
「こう集中してる時なのに気配を感じなかった。勘がすげえ弱くなってる」
言い訳じみた独り言を呟いた。
「おはよう」
「ああ、おはよう。」
後ろを振り向くと、マサリは腰を低くして俺に気付かれないように近づいていたらしく、ニヤッと笑う。
「それは自分の冒険者の力が上がったからじゃあなくて?にゃーっははは!」
「…マサリが一番好きな動物は猫だっけ?可愛いのが好きだったよな」
「メガマウス」
「えっ鮫?」
「嘘、ロボロフスキーハム」
「ハムって……ハムスターか、猫に喰われる方だったか」
「食物連鎖に持っていかないで」
「先に食い物にしたのはそっちだろ」
良かった。
俺はほっとひと安心する。鮫だとちょっと困っていたが、ハムスターなら良かった。
俺はハムスターを飼いたいとの無茶を受け流しながら俺は軽く片付けを済ませて、四つの瓶をポケットに入れ俺達の寝床へ戻った。
「あ、おはようサト兄マサ姉」
「おはよう!」
「おはよう」
俺は寝癖の酷いマツリに思わず吹き出しながら、続いて昨日使ったテーブルクロスの上で胡座をかく。
「少し話したい。朝から悪いが、大丈夫か?」
マサリとマツリを交互に見ると、二人は俺の真剣な目に息を止め、黙って頷いた。
朝の準備を済ませてからの方が良かったか?でもすぐに終わらせるから…
二人がなぜか正座で座るのを見届け、俺は二人にそっと語りかける。なるべく、子供達が怖じけついてしまった幽霊から守る親のような感じで。
「お前らは知らないだろうが、俺達のすむこの世界の大半は差別意識の強い国だ。俺だって平等な思想じゃないし、そういう意識は生まれたときから近くにあって、個人だけじゃ中々気付けないと思う。だから、ええとなマサリ、マツ――」
「それくらい知ってるよ」
「え?」
「マツリにももう説明した」
「えっそうなの?」
拍子抜け。
俺は目を見開きながら、動揺を隠さない。
「え、それで、マツリお前は…」
「うん、まあ仕方ないかなって。亜人差別は知らなかったけど、歌ってた以上、歌に対しての批判も良くあったし。それに、差別意識はあっても危害を加えるような人たちじゃないんでしょ?」
マツリはあっけらかんとして言った。それは恐れを知らないことはないがその日暮らしの楽観主義を根本から肯定出来るタイプの人間によくある態度だった。
「それは…」
確かに、今からの国はそういう思想なだけで、亜人とわかった瞬間に奴隷にするようなどこかの帝国とは違う。俺はそこのゆべしを懐かしがりながら、本当に大丈夫かと聞こうとした口を閉じる。マサリが先にピースをしながらこう言ったのだ。
「もしも何かあれば、いや、何かある前に自分が何とかするからね」
そして昨日のあまりの木の実に梅シロップを少しかけて口にする。自信満々だった。
「でもな、必ずしも安全とは…」
「それにサトリだって、何とかするために昨日何かをつくってたんでしょ?」
「は!?いや、そんなそういうわけじゃなくて、たまたまみたいな!?冒険に、役に?たつ?だけだから!?」
咄嗟のことで、思わず否定しまう。ばれてたんだ。ぎりぎりまで隠そうとしてた分、余計に恥ずかしい。
「…二人とも、ごめんね」
マツリは頭を下げる。悲しそうな声で。そうだ、こいつは真面目なんだった。
「違う、お前のせいじゃないし、謝罪も感謝もなにもしなくて良い。それよりやっぱり、どうしたって差別がある以上危険ってのはぬぐえないんだ。だから俺は昨日、人種を一時的に変える薬を用意した。」
そう、それこそが俺の判断。
人種を変えてしまう。
これが一番穏便にいくはずだ。そうだろ?勇者時代ならいざ知らず、俺は全世界の意識的問題を変化するだけの声を持ち得ていないし、何かを変えることは、一日二日その国に滞在するだけの旅人が気軽になし得れることじゃない。俺達には俺達の果たすべきことがあるんだから。
マツリは単語を繰り返す。
「人種を?」
「ああ。セルキー族から昔教わったんだ。」
ひとつの瓶には七ミリリットル程の白と黒の液体がマーブルのように混じっている。
マツリは右手で自身の小さな子犬か猫くらいの大きさの耳に触れて数回撫で、恐る恐る俺へと手を伸ばす。
「ありがとう。飲めば良いのかな。」
「え?いや、違う」
「浴びる?」
「いやだから、違うって」
「目にさす…?」
「いやなんでそうなるんだ?」
俺は首をかしげる。するとマサリが俺の肩を叩いた。
「で、ハムハムの耳はあるの?」
「ああ、犬と猫と兎と鼠だからな」
「どれがハムスター?」
「これだ」
「ありがとっ!」
マサリは薬を飲み干す。
するとまもなく頭部全体が光に包まれ、そしてマサリの耳はハムスターのような小さな耳が頭についていた。
「わぁい、久しぶりだ、この耳!!」
マサリはすぐに茂みに入り、そして戻ってくる。
「うん、やっぱり音が聞きやすいねっ!サトリったらなーかなか作ってくれないんだから!」
「ある意味遺伝子操作だからな、多用は厳禁だ」
俺は犬の薬を飲み干す。ゴールデンレトリバーのような垂れ耳である。
マツリはそれら一連の行動を、口をパクパク動かして、目を見開きながら驚いていた。
そこで俺はある失態に、ようやく気付く。
「ごめん。マツリもどれか、別の耳になりたかったりしたのか?猫か兎ならあるけど…もしかして犬が良かった?」
そうならそうと早く言ってくれれば。いや、ちゃんとこいつは欲しがったのに、俺が無視した形になってしまったな。つい本物より勝るものはないんだから、と。うっかりしていた。
俺がとりあえず薬を渡そうとすれば、マツリは全力で拒絶する。
「そっ、そうじゃなくて…!話の流れ的に、僕が人の耳になるとか、そういう…」
「いやそんなわけないだろ」
そっちが良いというなら作ってやるけど、お前さっき嫌がってたしな。
「でっでもさ、さ、差別とか…」
「なに言ってんだ、俺は勇者サトリだぞ?…元だけど。要は俺こそが正義なんだよ。…元だけど。」
「このマサリちゃんは最強の魔導師だしね、文句がある人はこう、まずは霞っていう頭の部分を……やだな、二人とも冗談だよ、ジョーダン!約束があるしね!ナニモシナイヨッ!」
今の目は冗談に見えなかったぞ、マサリさん。
「ふっ、あはは!」
マサリに一抹の不安を覚えたところで、マツリは突然笑いだす。
「そうと決まれば早速行こう!僕だって独奏の覇者って呼ばれてたんだ。見た目なんか気にならない歌を歌ってみるよ」
俺とマサリは目を見合わせる。
なんだ。
なんだ!
俺が思うより、この二人はずっと勇気に満ちた奴らだった。
かくして、俺達はそれぞれ犬とハムスターと猫の耳で自然の木々や水の音を楽しみながら、ペナトルイン王国へ向かったのだった。
マツリが仲間になって早くも一週間が経った。
金華猫の血の混ざっていた猫達ほかサーカスから連れ出した魔獣達はカルマアラネ・アンダージャン公国に心良く受け入れられたのを見届けてから、俺達はとりあえず寄り道を交えつつ、マツリの故郷へと歩く。
因みに俺とマサリはその町に行ったことはあるが、余りにもボロボロで、しっかりと調べたことはない。マツリの案内で町の中心辺りまで足を踏み入れられれば宝玉の手がかりがあるかもしれない。宝玉があればなおよし。
そんな魂胆のもと、俺達はトートシティーへ向かっていた。
――猫達を預けたあと、初めはずっと猫達のことが気になって、小振りな耳をピンと立てしきりに後ろを向いたりしていたマツリだったが、マサリが一言「信頼出来る人に定期的に写真を送ってもらおうか」と提案し、翌日白黒の写真と短い手紙が同封された封筒がマツリの元に届いたのでマツリは安心して旅に集中するようになった。
……いや待て。
信頼出来る人って誰だ?ってか、どうやって深い森の中に手紙が届いたんだ?
そう聞いた俺だったが、マサリは飄々とした態度で「正確には、ピ…いや、知り合いの知り合い、もしくはそのまた知り合いが手伝ってくれてるんだけど」と答えになっていない答えを返してくる。ちょっとだけ目を泳がせる。どちらかというと溺れたような酷い動揺に呑まれた泳がせ方だった。
待て、またまた待てよ。
ピってなんだ。ピって。俺は昔彼氏のことを彼ピとかそう呼ぶと聞いたことがある気がするぞ。それは大分昔、うんと遠い世界で聞いたことだが、若い奴らの考えることはどこでも同じだろ。
え、彼氏いるの?いや、駄目って訳じゃないんだけど、え?
恐る恐る訊ねる。
「マサリお前、か、彼氏がいるのか」
「まさか、いるわけないじゃん。自分の彼氏はゴシップ紙だよ」
「待てせめて新聞紙くらいにしてくれ」
「マサ姉ー、ゴシップ氏って名字?名前?彼氏さんいるなんて大人だね!シンブン氏さんもあんまり聞かない名前だなぁ」
「マツリ、マサリは今読んでるやつを彼氏と言ったんだ」
「あ、そっち?」
「そっち」
俺はマツリを訂正しながら安堵する。俺が二十歳になる前からずっと一緒に旅してたんだ、まさかそんな大事な秘密をずっと気付かないわけないもんな。さすがにそんなに鈍くないよな…?俺。
と、そんなひと悶着も数日前のことで、俺達は今、今日野営するために比較的夜でも木陰にならずに明るくなる平地を探していた。もうじきに夕暮れはくるし、そうなれば夜も早い。かといって、今から間に合う町は無いしな。
そして俺が軽く準備をしている間、お年頃の二人は後ろで地面に誰かがへし折っただろう太めの落ちた枝で落書きかなにかをして遊んでいるらしい。
「で、これが町にあった聖女像…」
「聖女様か~。マサ姉は見たことあるの?」
「ないね。どこかにいるはずなんだけど、一度も見たことがない。世界にただ一人だけなんだから、見つけるのは難しいけど」
なるほど、町で見かけた聖女像の話のようだ。昔拝んだ時も綺麗だったけど、今回は手を合わせずに来てしまったな。
にしても聖女様か。確かに、俺も会ってみたいもんだな。
俺はナップサックから残り十本しかないサーカステント柄のマッチ箱と、牛と魔物の干し肉、そして道中生えていた木々からもぎったいくつか暖色系の果物を取り出すと、表面だけは綺麗にしているチェック柄のテーブルクロスをそのまま泥が乾いて間もない土の上に敷く。塩や粉末状の唐辛子や砂糖や最近手に入れた梅シロップなどをそばに配置する。くしゃみをしながら、集めていた枝達に火をつける。寒々しさが幾分か和らいだ。今日返り討ちにした魔物の肉や角や目玉を、少し離れたところで改めて整理する。
しかしいつもは火をつければ道端で遊んでいても一目散にご飯を食べに来る二人だが、今日は一向にやって来る気配がない。
「二人とも、食べてい…」
二人の方を振り向く。
「「サトリ様!」」
「うわっ!?」
振り向いた途端、二人はぐいっと俺に近づいてきた。瞳には輝きが見えて、二人の濁りない目をまばゆく装飾していた。俺はやや狼狽えながら応対する。
「な、なんだよ…」
「あのねあのね、ここ行こう!」
ばっと、マツリはマサリの紙製の大きな地図を広げる。
マサリはさっと地図の前に飛び出し、お気に入りの鉛筆でぐるりとひとつ、ずたぼろに抉れたどら焼きみたいな形の丸を描いた。
「ペナトルイン王国か。」
「そう!ここから近いし、マツリの故郷とはほんのちょっと離れるだけだし、寄り道には良くない!?」
まあ、別に急いだ旅路じゃないし、良いけど。
俺一人では行ったことがある国だし、国境は越えるがカルマアラネ・アンダージャン公国のようにすぐに越えられるだろうから、別に困ったこともないし。空気もうまく、穏和な国だ。
素直に承諾しようとして、俺はふと口をつぐむ。この国は確か、亜人排斥主義じゃなかったか?
「あー…」
とりあえず俺は二人に飯を食うよう促しながら、その国に行くメリットとデメリットをあげてみる。差別のあるこの国にマツリを連れて行くのは嫌だよな。
それからまた少し考えて、考え直す。
いや、違う。
たまたま、このベニートシティー…というか今いるこの大きな国全体の風潮的にはそういう主張がないわけだが、ほかの国にはだいたい差別主義が根っこの方から広まっている。なにもペナトルイン王国だけの話じゃないんだ。現に、王国の人達は皆気さくだった。
つまりは今、ここで避けていたとしても必ずそんな問題にはぶち当たるわけで。
だが、だからといって「この国はお前を良く思わないからフードでも買うか」とでも言えば良いのか?自衛と差別の境界はどこだ。
「…因みに、なんでお前らはそこに行きたいんだ?」
俺は干し肉に適当に塩を振りかけて食べる。料理?そんなもの俺が、俺達が出来るわけがない。
俺が訊ねれば、マツリとマサリは互いに端整な顔を付き合わせ、マツリは友人の棺の中に詰めてやった花を見たかのように慈愛を込めて笑い、マサリは冒険前日に背負ってみたリュックの重みに感動したような笑顔を見せた。
「聖女様がいるかもしれないって噂なんだ!一目でも見てみたい!」
そして汚れた地方新聞紙を見せる。どうやら森に、隠すように捨てられていたらしい。ペナトルイン王国のものだろうか。……R指定品じゃなくて良かった。
マツリはまた笑う。
「一目でも良いから話してみたいんだ」
「そうだよな」
「お姉様が会って話をしたいんだって。」
「へえ…」
「それで、だから、もし許されたら、お姉様を見つけたらもう一回一緒にお話ししに行きたいんだ」
「本物かどうかは、わからないぞ?」
「でも、可能性はあるじゃん?」
そう言ったのはマサリだった。
「マサリはなんで会いたいんだ?」
「有名人じゃん」
「ミーハーだな」
「サトリもでしょ」
まあ、そうだけど。
俺はまた本の少しだけ悩んで、グミや季節外れのクワの他にヒヨドリジョウゴの小さな実をもぎってしまってたことに気付いて慌ててそれらをテーブルクロスから放り出しながら、頷いた。
二人をペナトルイン王国に連れていこう。
「明日の昼にはペナトルイン王国に着く。だが、覚悟をしてもらう」
「覚悟?」
「ペナトルイン王国ってすごく良い国トップテンには含まれるところだよ」
「それでも色々あるんだよ、明日話す。」
マサリは深く首をかしげる。
俺はナップサックを引き寄せて、ここ数日換金用に貯めておいた魔物の素材を数個取り出し、空の小瓶を四つ取り出し、ラストに服の下に隠れたペティナイフの首飾りを取り出す。凝固してしまっているが、セリルガリルの血も抜き取っていて良かった。
よし、あれをつくろう。
これが正しいかはわからないが、少なくとも最悪ではないと思う。
「サト兄、どうしたの?」
「いや、昔作り方を教えて貰った薬がつくれると思ってな。時間かかるから、お前らは先に寝といてくれよ」
「トランプは?」
「二人でどうぞ」
それだけ告げると、俺は念のためもう一度赤い身に毒のあるものが混じっていないか、焚き火の近くで確認し、それからマサリやマサリからなるべく離れたところで薬の製造に取りかかる。マッチを一本取り出し、はなを押さえる。こっからは刺激臭がするからな。
翌朝までぶっ通しで薬物の製造に取りかかったお陰か、朝日が七時を指し示す辺りに輝く頃には薬は四つとも完成していた。
寝巻きのままのマツリが俺の背後に近づいているのに俺は十二歩先まで予測できず、瓶に蓋をすると同時に一度ため息を吐く。
「こう集中してる時なのに気配を感じなかった。勘がすげえ弱くなってる」
言い訳じみた独り言を呟いた。
「おはよう」
「ああ、おはよう。」
後ろを振り向くと、マサリは腰を低くして俺に気付かれないように近づいていたらしく、ニヤッと笑う。
「それは自分の冒険者の力が上がったからじゃあなくて?にゃーっははは!」
「…マサリが一番好きな動物は猫だっけ?可愛いのが好きだったよな」
「メガマウス」
「えっ鮫?」
「嘘、ロボロフスキーハム」
「ハムって……ハムスターか、猫に喰われる方だったか」
「食物連鎖に持っていかないで」
「先に食い物にしたのはそっちだろ」
良かった。
俺はほっとひと安心する。鮫だとちょっと困っていたが、ハムスターなら良かった。
俺はハムスターを飼いたいとの無茶を受け流しながら俺は軽く片付けを済ませて、四つの瓶をポケットに入れ俺達の寝床へ戻った。
「あ、おはようサト兄マサ姉」
「おはよう!」
「おはよう」
俺は寝癖の酷いマツリに思わず吹き出しながら、続いて昨日使ったテーブルクロスの上で胡座をかく。
「少し話したい。朝から悪いが、大丈夫か?」
マサリとマツリを交互に見ると、二人は俺の真剣な目に息を止め、黙って頷いた。
朝の準備を済ませてからの方が良かったか?でもすぐに終わらせるから…
二人がなぜか正座で座るのを見届け、俺は二人にそっと語りかける。なるべく、子供達が怖じけついてしまった幽霊から守る親のような感じで。
「お前らは知らないだろうが、俺達のすむこの世界の大半は差別意識の強い国だ。俺だって平等な思想じゃないし、そういう意識は生まれたときから近くにあって、個人だけじゃ中々気付けないと思う。だから、ええとなマサリ、マツ――」
「それくらい知ってるよ」
「え?」
「マツリにももう説明した」
「えっそうなの?」
拍子抜け。
俺は目を見開きながら、動揺を隠さない。
「え、それで、マツリお前は…」
「うん、まあ仕方ないかなって。亜人差別は知らなかったけど、歌ってた以上、歌に対しての批判も良くあったし。それに、差別意識はあっても危害を加えるような人たちじゃないんでしょ?」
マツリはあっけらかんとして言った。それは恐れを知らないことはないがその日暮らしの楽観主義を根本から肯定出来るタイプの人間によくある態度だった。
「それは…」
確かに、今からの国はそういう思想なだけで、亜人とわかった瞬間に奴隷にするようなどこかの帝国とは違う。俺はそこのゆべしを懐かしがりながら、本当に大丈夫かと聞こうとした口を閉じる。マサリが先にピースをしながらこう言ったのだ。
「もしも何かあれば、いや、何かある前に自分が何とかするからね」
そして昨日のあまりの木の実に梅シロップを少しかけて口にする。自信満々だった。
「でもな、必ずしも安全とは…」
「それにサトリだって、何とかするために昨日何かをつくってたんでしょ?」
「は!?いや、そんなそういうわけじゃなくて、たまたまみたいな!?冒険に、役に?たつ?だけだから!?」
咄嗟のことで、思わず否定しまう。ばれてたんだ。ぎりぎりまで隠そうとしてた分、余計に恥ずかしい。
「…二人とも、ごめんね」
マツリは頭を下げる。悲しそうな声で。そうだ、こいつは真面目なんだった。
「違う、お前のせいじゃないし、謝罪も感謝もなにもしなくて良い。それよりやっぱり、どうしたって差別がある以上危険ってのはぬぐえないんだ。だから俺は昨日、人種を一時的に変える薬を用意した。」
そう、それこそが俺の判断。
人種を変えてしまう。
これが一番穏便にいくはずだ。そうだろ?勇者時代ならいざ知らず、俺は全世界の意識的問題を変化するだけの声を持ち得ていないし、何かを変えることは、一日二日その国に滞在するだけの旅人が気軽になし得れることじゃない。俺達には俺達の果たすべきことがあるんだから。
マツリは単語を繰り返す。
「人種を?」
「ああ。セルキー族から昔教わったんだ。」
ひとつの瓶には七ミリリットル程の白と黒の液体がマーブルのように混じっている。
マツリは右手で自身の小さな子犬か猫くらいの大きさの耳に触れて数回撫で、恐る恐る俺へと手を伸ばす。
「ありがとう。飲めば良いのかな。」
「え?いや、違う」
「浴びる?」
「いやだから、違うって」
「目にさす…?」
「いやなんでそうなるんだ?」
俺は首をかしげる。するとマサリが俺の肩を叩いた。
「で、ハムハムの耳はあるの?」
「ああ、犬と猫と兎と鼠だからな」
「どれがハムスター?」
「これだ」
「ありがとっ!」
マサリは薬を飲み干す。
するとまもなく頭部全体が光に包まれ、そしてマサリの耳はハムスターのような小さな耳が頭についていた。
「わぁい、久しぶりだ、この耳!!」
マサリはすぐに茂みに入り、そして戻ってくる。
「うん、やっぱり音が聞きやすいねっ!サトリったらなーかなか作ってくれないんだから!」
「ある意味遺伝子操作だからな、多用は厳禁だ」
俺は犬の薬を飲み干す。ゴールデンレトリバーのような垂れ耳である。
マツリはそれら一連の行動を、口をパクパク動かして、目を見開きながら驚いていた。
そこで俺はある失態に、ようやく気付く。
「ごめん。マツリもどれか、別の耳になりたかったりしたのか?猫か兎ならあるけど…もしかして犬が良かった?」
そうならそうと早く言ってくれれば。いや、ちゃんとこいつは欲しがったのに、俺が無視した形になってしまったな。つい本物より勝るものはないんだから、と。うっかりしていた。
俺がとりあえず薬を渡そうとすれば、マツリは全力で拒絶する。
「そっ、そうじゃなくて…!話の流れ的に、僕が人の耳になるとか、そういう…」
「いやそんなわけないだろ」
そっちが良いというなら作ってやるけど、お前さっき嫌がってたしな。
「でっでもさ、さ、差別とか…」
「なに言ってんだ、俺は勇者サトリだぞ?…元だけど。要は俺こそが正義なんだよ。…元だけど。」
「このマサリちゃんは最強の魔導師だしね、文句がある人はこう、まずは霞っていう頭の部分を……やだな、二人とも冗談だよ、ジョーダン!約束があるしね!ナニモシナイヨッ!」
今の目は冗談に見えなかったぞ、マサリさん。
「ふっ、あはは!」
マサリに一抹の不安を覚えたところで、マツリは突然笑いだす。
「そうと決まれば早速行こう!僕だって独奏の覇者って呼ばれてたんだ。見た目なんか気にならない歌を歌ってみるよ」
俺とマサリは目を見合わせる。
なんだ。
なんだ!
俺が思うより、この二人はずっと勇気に満ちた奴らだった。
かくして、俺達はそれぞれ犬とハムスターと猫の耳で自然の木々や水の音を楽しみながら、ペナトルイン王国へ向かったのだった。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

1×∞(ワンバイエイト) 経験値1でレベルアップする俺は、最速で異世界最強になりました!
マツヤマユタカ
ファンタジー
23年5月22日にアルファポリス様より、拙著が出版されました!そのため改題しました。
今後ともよろしくお願いいたします!
トラックに轢かれ、気づくと異世界の自然豊かな場所に一人いた少年、カズマ・ナカミチ。彼は事情がわからないまま、仕方なくそこでサバイバル生活を開始する。だが、未経験だった釣りや狩りは妙に上手くいった。その秘密は、レベル上げに必要な経験値にあった。実はカズマは、あらゆるスキルが経験値1でレベルアップするのだ。おかげで、何をやっても簡単にこなせて――。異世界爆速成長系ファンタジー、堂々開幕!
タイトルの『1×∞』は『ワンバイエイト』と読みます。
男性向けHOTランキング1位!ファンタジー1位を獲得しました!【22/7/22】
そして『第15回ファンタジー小説大賞』において、奨励賞を受賞いたしました!【22/10/31】
アルファポリス様より出版されました!現在第四巻まで発売中です!
コミカライズされました!公式漫画タブから見られます!【24/8/28】
よろしくお願いいたします。
マツヤマユタカ名義でTwitterやってます。
見てください。

平凡冒険者のスローライフ
上田なごむ
ファンタジー
26歳独身動物好きの主人公大和希は、神様によって魔物・魔法・獣人等ファンタジーな世界観の異世界に転移させられる。
平凡な能力値、野望など抱いていない彼は、冒険者としてスローライフを目標に日々を過ごしていく。
果たして、彼を待ち受ける出会いや試練は如何なるものか……
ファンタジー世界に向き合う、平凡な冒険者の物語。

『購入無双』 復讐を誓う底辺冒険者は、やがてこの世界の邪悪なる王になる
チョーカ-
ファンタジー
底辺冒険者であるジェル・クロウは、ダンジョンの奥地で仲間たちに置き去りにされた。
暗闇の中、意識も薄れていく最中に声が聞こえた。
『力が欲しいか? 欲しいなら供物を捧げよ』
ジェルは最後の力を振り絞り、懐から財布を投げ込みと
『ご利用ありがとうございます。商品をお選びください』
それは、いにしえの魔道具『自動販売機』
推すめされる商品は、伝説の武器やチート能力だった。
力を得た少年は復讐……そして、さらなる闇へ堕ちていく
※本作は一部 Midjourneyにより制作したイラストを挿絵として使用しています。

田舎暮らしと思ったら、異世界暮らしだった。
けむし
ファンタジー
突然の異世界転移とともに魔法が使えるようになった青年の、ほぼ手に汗握らない物語。
日本と異世界を行き来する転移魔法、物を複製する魔法。
あらゆる魔法を使えるようになった主人公は異世界で、そして日本でチート能力を発揮・・・するの?
ゆる~くのんびり進む物語です。読者の皆様ものんびりお付き合いください。
感想などお待ちしております。
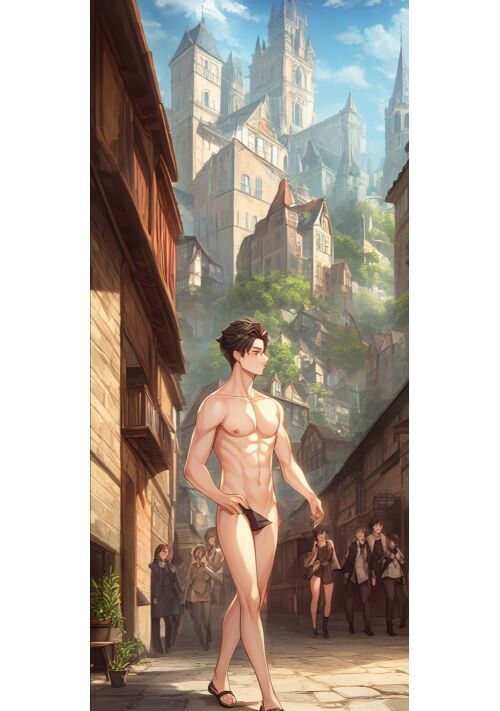
ゲームのモブに転生したと思ったら、チートスキルガン積みのバグキャラに!? 最強の勇者? 最凶の魔王? こっちは最驚の裸族だ、道を開けろ
阿弥陀乃トンマージ
ファンタジー
どこにでもいる平凡なサラリーマン「俺」は、長年勤めていたブラック企業をある日突然辞めた。
心は晴れやかだ。なんといってもその日は、昔から遊んでいる本格的ファンタジーRPGシリーズの新作、『レジェンドオブインフィニティ』の発売日であるからだ。
「俺」はゲームをプレイしようとするが、急に頭がふらついてゲーミングチェアから転げ落ちてしまう。目覚めた「俺」は驚く。自室の床ではなく、ゲームの世界の砂浜に倒れ込んでいたからである、全裸で。
「俺」のゲームの世界での快進撃が始まる……のだろうか⁉

一宿一飯の恩義で竜伯爵様に抱かれたら、なぜか監禁されちゃいました!
当麻月菜
恋愛
宮坂 朱音(みやさか あかね)は、電車に跳ねられる寸前に異世界転移した。そして異世界人を保護する役目を担う竜伯爵の元でお世話になることになった。
しかしある日の晩、竜伯爵当主であり、朱音の保護者であり、ひそかに恋心を抱いているデュアロスが瀕死の状態で屋敷に戻ってきた。
彼は強い媚薬を盛られて苦しんでいたのだ。
このまま一晩ナニをしなければ、死んでしまうと知って、朱音は一宿一飯の恩義と、淡い恋心からデュアロスにその身を捧げた。
しかしそこから、なぜだかわからないけれど監禁生活が始まってしまい……。
好きだからこそ身を捧げた異世界女性と、強い覚悟を持って異世界女性を抱いた男が異世界婚をするまでの、しょーもないアレコレですれ違う二人の恋のおはなし。
※いつもコメントありがとうございます!現在、返信が遅れて申し訳ありません(o*。_。)oペコッ 甘口も辛口もどれもありがたく読ませていただいてます(*´ω`*)
※他のサイトにも重複投稿しています。

マイナー18禁乙女ゲームのヒロインになりました
東 万里央(あずま まりお)
恋愛
十六歳になったその日の朝、私は鏡の前で思い出した。この世界はなんちゃってルネサンス時代を舞台とした、18禁乙女ゲーム「愛欲のボルジア」だと言うことに……。私はそのヒロイン・ルクレツィアに転生していたのだ。
攻略対象のイケメンは五人。ヤンデレ鬼畜兄貴のチェーザレに男の娘のジョバンニ。フェロモン侍従のペドロに影の薄いアルフォンソ。大穴の変人両刀のレオナルド……。ハハッ、ロクなヤツがいやしねえ! こうなれば修道女ルートを目指してやる!
そんな感じで涙目で爆走するルクレツィアたんのお話し。

魔界最強に転生した社畜は、イケメン王子に奪い合われることになりました
タタミ
BL
ブラック企業に務める社畜・佐藤流嘉。
クリスマスも残業確定の非リア人生は、トラックの激突により突然終了する。
死後目覚めると、目の前で見目麗しい天使が微笑んでいた。
「ここは天国ではなく魔界です」
天使に会えたと喜んだのもつかの間、そこは天国などではなく魔法が当たり前にある世界・魔界だと知らされる。そして流嘉は、魔界に君臨する最強の支配者『至上様』に転生していたのだった。
「至上様、私に接吻を」
「あっ。ああ、接吻か……って、接吻!?なんだそれ、まさかキスですか!?」
何が起こっているのかわからないうちに、流嘉の前に現れたのは美しい4人の王子。この4王子にキスをして、結婚相手を選ばなければならないと言われて──!?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















