149 / 178
交流編
ガレリア国代表選手たちの凱旋式
しおりを挟む
「英雄たちの凱旋だぞッ!」
ルイーダたち代表選手は学園に帰還するなり、出迎えに訪れた生徒たちからの歓声で出迎えられることになった。ルイーダたちは文字通り大手を振って出迎えられたのである。多くの生徒たちがガレリア国の国旗を振り、握手を求めていた。
大歓迎を受けたルイーダはすっかりと得意げな様子であったが、その様子を見て危機を感じたのかジードが小突いて彼女を現実へと引き戻させた。
それから抗議を行おうとするルイーダを他所に小声で忠告を行っていく。
「お前な、今の自分がどんな状況に置かれてるのかわかってるのか?」
「ガレリアの代表に選ばれたんだろ?名誉なことじゃあないか」
「名誉だけじゃないぞ、そこには責任も加わってくる」
「責任?」
忠告を聞いてもルイーダはいまいちピンとこなかったらしい。そのためジードは深刻な顔を浮かべて代表選手に選ばれることによってどのような責任が生じていくのかを説明していく。
まず、背負う責任というのはこの学園の生徒の期待ばかりではなく、ガレリア国全体の期待を背負うというものだった。
万が一にも大会で負けるようなことがあればルイーダたちには立つ瀬がない。
全校生徒のみならず街の人々たちの冷たい視線に晒されてしまう。それに耐えきれず、故郷に戻って世間が自分たちのことを忘れて引き篭もるしかないのだ。
下手をすれば自害にまで追い込まれてしまうかもしれない。それだけ国を背負って立つという責任は大きなものなのだ。
だが、そのことを語ってもルイーダは平然とした顔のままである。少なくともその飄々とした表情からはジードが先ほどまで語っていた最悪の結末など想像だにしていないことが感じられる。
あまりにも余裕な妻の態度にやり切れない思いを感じたジードであったが、ルイーダは腕を組みながら得意気な顔を浮かべて言った。
「案ずるな、我が夫よ。負けると思っているから負けるのだ。お前は今度の試合に負けてしまうのだと思っているのかもしれないが、私は違う。私は常に勝つことばかりを考えている。遥か遠くの昔、私は国王陛下の名を背負って馬上試合に出たが、その時も私は勝った。他国の勇敢な騎士を突き飛ばしてなッ!」
ルイーダの声はジードの声と比較して大きなものであった。ルイーダの声からはハッキリとした意思が感じられた。
ジードは妻の自信を聞いて、しばらくの間は半ば呆然としていた。
だが、すぐに口元に何かを悟ったような笑みを浮かべていく。
それから勢いよく妻の手を握り締めていく。
「そうだなッ!確かにお前の言うとおりだ。負けると思っていたら負けるに決まってるッ!勝とうぜッ!今度の試合にはッ!」
「それでこそ、我が夫だッ!」
ルイーダはジードの体を勢いよく抱き締めながら叫んだ。突然他の生徒たちの前で妻から抱きしめられたことによってジードはすっかりと顔を赤くしていた。茹でたばかりの蛸のように赤くなっていた。
自身を力強く抱き締めていたルイーダの背中を左手でパタパタと叩いて、
「ちょっと待てよ、周りに人がいるだろ!?」
ジードの指摘を聞いたルイーダは気不味そうに笑いながら慌ててジードを引き離した。
その日はこれだけで終わったのだと思ったが、先ほどの抱擁やルイーダの言葉は群衆の中に紛れていたエックハルトによってしっかりと記録されてしまったらしい。
廊下に抱擁した瞬間を収めた写真とルイーダの自信とを語った言葉を一面に押し出した一面が載った校内新聞が発行されたことには二人も驚きを隠せなかった。
「見ろ、お前があんなことを言ったせいだからだぞ」
「何を言う。元はといえばおめでたい場所で水を差すようなことを言ったお前のせいだ」
お互いに悪態を吐き、そのまま喧嘩を始めんばかりの勢いで睨み合っていたが、直後に生徒たちが大挙してきたために喧嘩は断念せざるを得なかった。
この時ルイーダは大言壮語というものには気を付けなければならないと感じた。
結局その日は多くの生徒たちに囲まれて過ごすことになったので、結果的に練習を始めるのは翌日からということになった。
自分たちと共に代表選手となったメンバーは自分たちと共に首都へと向かったメンバーだったので今更選抜する必要もなかった。
メンバーはルイーダにジード、コルネリア、コニーとケニー、ハンスといった見知ったメンバーの他にも新たに参加したメンバーもいる。
ザビーネ・リッケンドルフとルイーザ・ベルツの二名である。
ザビーネ・リッケンドルフは青色のボブショートヘアに小柄な体型、そして無口という特徴があった。
普段はルイーダの改革以来大抵の女子生徒が履いているズボンの制服を着用しており、男子から好意の対象として見られるようなことは少なかった。
事実学校の休み時間も友達や男子生徒と過ごすよりも一人で本を読んでいるということが多かった。
秀才かと問われると、成績はどちらかといえば平均的で可もなく不可もなくというのが彼女に対する教師からの評価であった。
ここまでの特徴を挙げていけば彼女はどこにでもいる目立たない女子生徒だという印象を受けるが、『人は見かけによらない』という言葉があるように彼女には意外な特徴が備わっていた。
まず、彼女は体術にかけては普段の印象とは全く別であった。それに加えて田舎に住む両親が牧場を経営しているということもあり、幼い頃から馬を操ってきたので馬術の達人でもあった。
無口な性格である故にそのことを敢えて語らないというので彼女はこれまでの人生を大きく損していたように思えた。
もう一人ルイーザ・ベルツは腰まで垂らした金髪、長く整った両眉、宝石のように美しいアイスブルーの瞳、長くて高い均整のとれた鼻、それらを収めた逆卵形の顔という見た目だけならばまるで古くから語られる御伽噺の挿絵に描かれるような高貴な姫君のように美しい人物であった。
見た目ばかりではない。現在の魔銃士育成学園においてスカート状の制服という珍しい姿をしていたこともお姫様を連想させることの一因となった。
そんな彼女は入学時から成績も良く、友人も多いという勝者の部類に属していた。容姿端麗で成績も良く人からも好かれる性格の彼女であったが、唯一運動の成績だけは人並みだった。それでもそんな欠点を補うかのように舞踏の達人で踊りにかけては右に出る者はいなかった。
エリザベトがこの大会に選出されたのは代表選手を探して辺りを練り歩いていたルイーダによって体育館の中で一人踊っている様子を認められたからだ。
スポーツばかりを重んじる大会において舞踏などは必要ないと思われるが、芸術部門が設けられており、そこにおける選手が一人必要だったのだ。
芸術部門というのは建築、彫刻、音楽、絵画、文学といった芸術作品を各国の代表たちが競う部門を指す言葉だ。
上記の芸術作品を競い合う大会以外にも各国の代表がソロでの踊りを披露し、最も美しい踊りを踊った人物に対して高い点を与えるという踊り部門が存在する。
彼女はその踊り部門における代表なのだ。そのため彼女はルイーダたちに同行していた。
他の芸術部門の選手たちは学園から大会委員に向けて個別に送って応募するということもあり、畑違いともいえるルイーダたちはどのような人物が出るのかということさえも知らなかった。
踊りの部門はルイーダたちの旅に同行していた観点からも例外のように思えるが、それでも練習は別だった。
ルイーダたちが仲間と共に木刀を打ち合っている横で一人、専属のコーチと共に踊っているのだ。自分たちとは引き離された場所で、たった二人コーチと踊っているということが妙に寂しい、気に掛けてやりたいという思う気持ちがルイーダの中にはあった。
これは他の芸術部門の生徒たちには芽生えなかった特殊な感情であった。
もしかすれば彼女の名前が『ルイーザ』なので自分と名前が似ていたということも大きかったかもしれない。
どんな理由であったのかはルイーダ自身にも分からなかったが、ルイーダをあまり接点のないルイーザの元へと突き動かしたのは事実であった。
その日たまたま練習を早く終えたルイーダがサロンで土産として包んでもらった菓子類を携えて待ち構えていた。
ルイーダが練習場所として使っているのは芝生が生えた校庭であり、ルイーザが使っているのは巨大な体育館だから距離はあった。そんな中でわざわざ手土産まで携えているのだからルイーダの入れ込みようは相当なものであった。
やはり予選に過ぎないとはいえ自身の手でその存在を見出し、僅かな時間とはいえ共に大会を戦った身であるということも大きかったのかもしれない。
練習を終えタオルで汗を拭いているルイーザの前にルイーダがサロンでもらった菓子を差し出しながら言った。
「お疲れ様、どうだ?よかったらこの後で私と一緒に休憩しないか?」
「休憩ですか?」
「あぁ、たまには休憩しないと体に毒だぞ」
「……せっかくのお誘いですが、今回は辞退させていただきます。この後も教室でコーチと相談する予定が入っていますので」
ルイーザはキッパリと言い放ったかと思うと、足早にルイーダの元を去っていったのである。
ここまであからさまに断られては仕方がない。サロンでもらった菓子は家に戻ってジードと共に食べよう。
そんなことを考えながら校舎の門を出ると、既に辺りの空間は暗闇が支配していた。宝石箱の宝石を散りばめたような星空に優しい光を放つ丸い月が輝いていた。
ルイーダは星と月のみが支配する汚れ一つないような綺麗な夜空を見上げていると、ふと背後から突然自分をつけている気配を感じた。
あとがき
本日は多忙のため執筆になかなか取り掛かれず、結果として日を跨ぐ結果になってしまったことを改めてお詫びさせていただきます。
用事を終えて完成したのが夜中だということもあり、皆様の睡眠を妨げてはいけないという思いから投稿は翌朝とさせていただきました。
ルイーダたち代表選手は学園に帰還するなり、出迎えに訪れた生徒たちからの歓声で出迎えられることになった。ルイーダたちは文字通り大手を振って出迎えられたのである。多くの生徒たちがガレリア国の国旗を振り、握手を求めていた。
大歓迎を受けたルイーダはすっかりと得意げな様子であったが、その様子を見て危機を感じたのかジードが小突いて彼女を現実へと引き戻させた。
それから抗議を行おうとするルイーダを他所に小声で忠告を行っていく。
「お前な、今の自分がどんな状況に置かれてるのかわかってるのか?」
「ガレリアの代表に選ばれたんだろ?名誉なことじゃあないか」
「名誉だけじゃないぞ、そこには責任も加わってくる」
「責任?」
忠告を聞いてもルイーダはいまいちピンとこなかったらしい。そのためジードは深刻な顔を浮かべて代表選手に選ばれることによってどのような責任が生じていくのかを説明していく。
まず、背負う責任というのはこの学園の生徒の期待ばかりではなく、ガレリア国全体の期待を背負うというものだった。
万が一にも大会で負けるようなことがあればルイーダたちには立つ瀬がない。
全校生徒のみならず街の人々たちの冷たい視線に晒されてしまう。それに耐えきれず、故郷に戻って世間が自分たちのことを忘れて引き篭もるしかないのだ。
下手をすれば自害にまで追い込まれてしまうかもしれない。それだけ国を背負って立つという責任は大きなものなのだ。
だが、そのことを語ってもルイーダは平然とした顔のままである。少なくともその飄々とした表情からはジードが先ほどまで語っていた最悪の結末など想像だにしていないことが感じられる。
あまりにも余裕な妻の態度にやり切れない思いを感じたジードであったが、ルイーダは腕を組みながら得意気な顔を浮かべて言った。
「案ずるな、我が夫よ。負けると思っているから負けるのだ。お前は今度の試合に負けてしまうのだと思っているのかもしれないが、私は違う。私は常に勝つことばかりを考えている。遥か遠くの昔、私は国王陛下の名を背負って馬上試合に出たが、その時も私は勝った。他国の勇敢な騎士を突き飛ばしてなッ!」
ルイーダの声はジードの声と比較して大きなものであった。ルイーダの声からはハッキリとした意思が感じられた。
ジードは妻の自信を聞いて、しばらくの間は半ば呆然としていた。
だが、すぐに口元に何かを悟ったような笑みを浮かべていく。
それから勢いよく妻の手を握り締めていく。
「そうだなッ!確かにお前の言うとおりだ。負けると思っていたら負けるに決まってるッ!勝とうぜッ!今度の試合にはッ!」
「それでこそ、我が夫だッ!」
ルイーダはジードの体を勢いよく抱き締めながら叫んだ。突然他の生徒たちの前で妻から抱きしめられたことによってジードはすっかりと顔を赤くしていた。茹でたばかりの蛸のように赤くなっていた。
自身を力強く抱き締めていたルイーダの背中を左手でパタパタと叩いて、
「ちょっと待てよ、周りに人がいるだろ!?」
ジードの指摘を聞いたルイーダは気不味そうに笑いながら慌ててジードを引き離した。
その日はこれだけで終わったのだと思ったが、先ほどの抱擁やルイーダの言葉は群衆の中に紛れていたエックハルトによってしっかりと記録されてしまったらしい。
廊下に抱擁した瞬間を収めた写真とルイーダの自信とを語った言葉を一面に押し出した一面が載った校内新聞が発行されたことには二人も驚きを隠せなかった。
「見ろ、お前があんなことを言ったせいだからだぞ」
「何を言う。元はといえばおめでたい場所で水を差すようなことを言ったお前のせいだ」
お互いに悪態を吐き、そのまま喧嘩を始めんばかりの勢いで睨み合っていたが、直後に生徒たちが大挙してきたために喧嘩は断念せざるを得なかった。
この時ルイーダは大言壮語というものには気を付けなければならないと感じた。
結局その日は多くの生徒たちに囲まれて過ごすことになったので、結果的に練習を始めるのは翌日からということになった。
自分たちと共に代表選手となったメンバーは自分たちと共に首都へと向かったメンバーだったので今更選抜する必要もなかった。
メンバーはルイーダにジード、コルネリア、コニーとケニー、ハンスといった見知ったメンバーの他にも新たに参加したメンバーもいる。
ザビーネ・リッケンドルフとルイーザ・ベルツの二名である。
ザビーネ・リッケンドルフは青色のボブショートヘアに小柄な体型、そして無口という特徴があった。
普段はルイーダの改革以来大抵の女子生徒が履いているズボンの制服を着用しており、男子から好意の対象として見られるようなことは少なかった。
事実学校の休み時間も友達や男子生徒と過ごすよりも一人で本を読んでいるということが多かった。
秀才かと問われると、成績はどちらかといえば平均的で可もなく不可もなくというのが彼女に対する教師からの評価であった。
ここまでの特徴を挙げていけば彼女はどこにでもいる目立たない女子生徒だという印象を受けるが、『人は見かけによらない』という言葉があるように彼女には意外な特徴が備わっていた。
まず、彼女は体術にかけては普段の印象とは全く別であった。それに加えて田舎に住む両親が牧場を経営しているということもあり、幼い頃から馬を操ってきたので馬術の達人でもあった。
無口な性格である故にそのことを敢えて語らないというので彼女はこれまでの人生を大きく損していたように思えた。
もう一人ルイーザ・ベルツは腰まで垂らした金髪、長く整った両眉、宝石のように美しいアイスブルーの瞳、長くて高い均整のとれた鼻、それらを収めた逆卵形の顔という見た目だけならばまるで古くから語られる御伽噺の挿絵に描かれるような高貴な姫君のように美しい人物であった。
見た目ばかりではない。現在の魔銃士育成学園においてスカート状の制服という珍しい姿をしていたこともお姫様を連想させることの一因となった。
そんな彼女は入学時から成績も良く、友人も多いという勝者の部類に属していた。容姿端麗で成績も良く人からも好かれる性格の彼女であったが、唯一運動の成績だけは人並みだった。それでもそんな欠点を補うかのように舞踏の達人で踊りにかけては右に出る者はいなかった。
エリザベトがこの大会に選出されたのは代表選手を探して辺りを練り歩いていたルイーダによって体育館の中で一人踊っている様子を認められたからだ。
スポーツばかりを重んじる大会において舞踏などは必要ないと思われるが、芸術部門が設けられており、そこにおける選手が一人必要だったのだ。
芸術部門というのは建築、彫刻、音楽、絵画、文学といった芸術作品を各国の代表たちが競う部門を指す言葉だ。
上記の芸術作品を競い合う大会以外にも各国の代表がソロでの踊りを披露し、最も美しい踊りを踊った人物に対して高い点を与えるという踊り部門が存在する。
彼女はその踊り部門における代表なのだ。そのため彼女はルイーダたちに同行していた。
他の芸術部門の選手たちは学園から大会委員に向けて個別に送って応募するということもあり、畑違いともいえるルイーダたちはどのような人物が出るのかということさえも知らなかった。
踊りの部門はルイーダたちの旅に同行していた観点からも例外のように思えるが、それでも練習は別だった。
ルイーダたちが仲間と共に木刀を打ち合っている横で一人、専属のコーチと共に踊っているのだ。自分たちとは引き離された場所で、たった二人コーチと踊っているということが妙に寂しい、気に掛けてやりたいという思う気持ちがルイーダの中にはあった。
これは他の芸術部門の生徒たちには芽生えなかった特殊な感情であった。
もしかすれば彼女の名前が『ルイーザ』なので自分と名前が似ていたということも大きかったかもしれない。
どんな理由であったのかはルイーダ自身にも分からなかったが、ルイーダをあまり接点のないルイーザの元へと突き動かしたのは事実であった。
その日たまたま練習を早く終えたルイーダがサロンで土産として包んでもらった菓子類を携えて待ち構えていた。
ルイーダが練習場所として使っているのは芝生が生えた校庭であり、ルイーザが使っているのは巨大な体育館だから距離はあった。そんな中でわざわざ手土産まで携えているのだからルイーダの入れ込みようは相当なものであった。
やはり予選に過ぎないとはいえ自身の手でその存在を見出し、僅かな時間とはいえ共に大会を戦った身であるということも大きかったのかもしれない。
練習を終えタオルで汗を拭いているルイーザの前にルイーダがサロンでもらった菓子を差し出しながら言った。
「お疲れ様、どうだ?よかったらこの後で私と一緒に休憩しないか?」
「休憩ですか?」
「あぁ、たまには休憩しないと体に毒だぞ」
「……せっかくのお誘いですが、今回は辞退させていただきます。この後も教室でコーチと相談する予定が入っていますので」
ルイーザはキッパリと言い放ったかと思うと、足早にルイーダの元を去っていったのである。
ここまであからさまに断られては仕方がない。サロンでもらった菓子は家に戻ってジードと共に食べよう。
そんなことを考えながら校舎の門を出ると、既に辺りの空間は暗闇が支配していた。宝石箱の宝石を散りばめたような星空に優しい光を放つ丸い月が輝いていた。
ルイーダは星と月のみが支配する汚れ一つないような綺麗な夜空を見上げていると、ふと背後から突然自分をつけている気配を感じた。
あとがき
本日は多忙のため執筆になかなか取り掛かれず、結果として日を跨ぐ結果になってしまったことを改めてお詫びさせていただきます。
用事を終えて完成したのが夜中だということもあり、皆様の睡眠を妨げてはいけないという思いから投稿は翌朝とさせていただきました。
0
お気に入りに追加
115
あなたにおすすめの小説

解呪の魔法しか使えないからとSランクパーティーから追放された俺は、呪いをかけられていた美少女ドラゴンを拾って最強へと至る
早見羽流
ファンタジー
「ロイ・クノール。お前はもう用無しだ」
解呪の魔法しか使えない初心者冒険者の俺は、呪いの宝箱を解呪した途端にSランクパーティーから追放され、ダンジョンの最深部へと蹴り落とされてしまう。
そこで出会ったのは封印された邪龍。解呪の能力を使って邪龍の封印を解くと、なんとそいつは美少女の姿になり、契約を結んで欲しいと頼んできた。
彼女は元は世界を守護する守護龍で、英雄や女神の陰謀によって邪龍に堕とされ封印されていたという。契約を結んだ俺は彼女を救うため、守護龍を封印し世界を牛耳っている女神や英雄の血を引く王家に立ち向かうことを誓ったのだった。
(1話2500字程度、1章まで完結保証です)

無能なので辞めさせていただきます!
サカキ カリイ
ファンタジー
ブラック商業ギルドにて、休みなく働き詰めだった自分。
マウントとる新人が入って来て、馬鹿にされだした。
えっ上司まで新人に同調してこちらに辞めろだって?
残業は無能の証拠、職務に時間が長くかかる分、
無駄に残業代払わせてるからお前を辞めさせたいって?
はいはいわかりました。
辞めますよ。
退職後、困ったんですかね?さあ、知りませんねえ。
自分無能なんで、なんにもわかりませんから。
カクヨム、なろうにも同内容のものを時差投稿しております。

【完結】あなたに知られたくなかった
ここ
ファンタジー
セレナの幸せな生活はあっという間に消え去った。新しい継母と異母妹によって。
5歳まで令嬢として生きてきたセレナは6歳の今は、小さな手足で必死に下女見習いをしている。もう自分が令嬢だということは忘れていた。
そんなセレナに起きた奇跡とは?

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。
黒ハット
ファンタジー
【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。
この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。
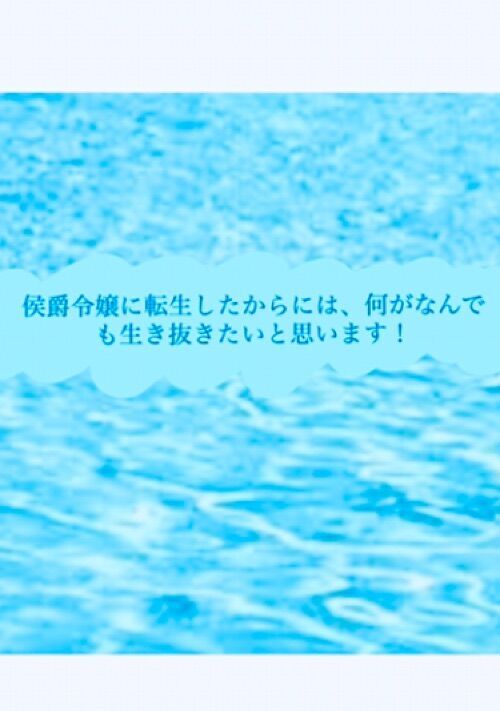
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

(完結)醜くなった花嫁の末路「どうぞ、お笑いください。元旦那様」
音爽(ネソウ)
ファンタジー
容姿が気に入らないと白い結婚を強いられた妻。
本邸から追い出されはしなかったが、夫は離れに愛人を囲い顔さえ見せない。
しかし、3年と待たず離縁が決定する事態に。そして元夫の家は……。
*6月18日HOTランキング入りしました、ありがとうございます。

S級騎士の俺が精鋭部隊の隊長に任命されたが、部下がみんな年上のS級女騎士だった
ミズノみすぎ
ファンタジー
「黒騎士ゼクード・フォルス。君を竜狩り精鋭部隊【ドラゴンキラー隊】の隊長に任命する」
15歳の春。
念願のS級騎士になった俺は、いきなり国王様からそんな命令を下された。
「隊長とか面倒くさいんですけど」
S級騎士はモテるって聞いたからなったけど、隊長とかそんな重いポジションは……
「部下は美女揃いだぞ?」
「やらせていただきます!」
こうして俺は仕方なく隊長となった。
渡された部隊名簿を見ると隊員は俺を含めた女騎士3人の計4人構成となっていた。
女騎士二人は17歳。
もう一人の女騎士は19歳(俺の担任の先生)。
「あの……みんな年上なんですが」
「だが美人揃いだぞ?」
「がんばります!」
とは言ったものの。
俺のような若輩者の部下にされて、彼女たちに文句はないのだろうか?
と思っていた翌日の朝。
実家の玄関を部下となる女騎士が叩いてきた!
★のマークがついた話数にはイラストや4コマなどが後書きに記載されています。
※2023年11月25日に書籍が発売しています!
イラストレーターはiltusa先生です!
※コミカライズも進行中!

最強令嬢とは、1%のひらめきと99%の努力である
megane-san
ファンタジー
私クロエは、生まれてすぐに傷を負った母に抱かれてブラウン辺境伯城に転移しましたが、母はそのまま亡くなり、辺境伯夫妻の養子として育てていただきました。3歳になる頃には闇と光魔法を発現し、さらに暗黒魔法と膨大な魔力まで持っている事が分かりました。そしてなんと私、前世の記憶まで思い出し、前世の知識で辺境伯領はかなり大儲けしてしまいました。私の力は陰謀を企てる者達に狙われましたが、必〇仕事人バリの方々のおかげで悪者は一層され、無事に修行を共にした兄弟子と婚姻することが出来ました。……が、なんと私、魔王に任命されてしまい……。そんな波乱万丈に日々を送る私のお話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















