6 / 11
東屋
しおりを挟む
数日後、宗厳は木津川沿いに設えられた東屋に赴いていた。
そこには先客がいた。数人の従者を従えた武士が、招かれざる訪問者をにらむ。従者の人数といで立ちを見るに、織田軍の中でも城主を任される高位にある者だろう。
宗厳が一礼して名乗ると場の緊張は解けたが、代わりに不審げな空気が流れた。
「失礼ながら、こちらで野点(屋外の茶会)をされると聞き及び、推参つかまつった。道意さまがこちらにお見えになっているとのことで」
宗厳が言うと、男たちの脇をすり抜けて老人が姿を現した。
「おお、宗厳か。わざわざ足労をかけたのう」
「なんのこれしき。道意さまこそ、先日はわれらの里まで足をお運びいただいたそうで」
「おぬしにその名で呼ばれるとしっくりこんな。昔の呼び方で構わぬぞ」
「では、霜台さまと」
老人は鷹揚にうなずいた。霜台とは弾正少弼の位を指す。この老人は法名の道意よりもずっと有名な名を持っている。松永弾正少弼久秀。主家乗っ取り、足利将軍弑逆、東大寺大仏殿の焼き討ちという三悪を為した梟雄として知られる人物である。
久秀は同席していた武士に、宗厳と少し話をしていきたいと伝えた。事情を知った武士は表情を和らげて承諾したものの、宗厳にはちらりと冷たい視線を投げてよこした。柳生家は織田家に臣従しているものの、当主の宗厳は里に篭って隠棲しており、表舞台に姿を見せることはなくなっている。それがこうして姿を現したのを怪訝に思っているのだろう。
二人は武士の一団がいる東屋から離れ、適当な木陰の河原で腰を下ろした。まずは宗厳が切り出す。
「先日のご用件をお伺いしてもよろしいですかな」
「澄ました顔でなにを言うか」
久秀が苦々しい顔で、扇で東屋を指した。武士の従者たちがちらちらと宗厳たちの様子を伺っていた。
「おぬしがここに現れたことで、わしの目論見はすでに潰えてしまったわい」
やはりそうか。宗厳はひそかに嘆息した。久秀が供も連れず密かに宗厳に会いに来たということは、織田家に知られたくない謀議があったということだ。あの日、天狗面の明音が現れたので、用心した久秀はしばらくその場から離れたのだろう。宗厳にとっては幸いだった。暗殺か、調略か、戦の助勢か。どのような謀議にせよ、宗厳は久秀に手を貸すつもりはなかった。先触れもなく自らここへ赴いたのは、織田軍に警戒を促し、久秀を牽制するためだった。
「かつての主従のよしみで、目障りな筒井の当主を始末してほしかったのだがな」
監視している従者たちに気取られぬよう、久秀は穏やかな微笑を浮かべたままそんなことを言った。宗厳も合わせて、素知らぬ顔で首を振った。
「拙者、戦国の世から身を引く所存にて」
久秀は苦笑いでうなずいた。
「ならばあの弟子は破門しておいたほうがよいのではないか。筒井の辰巳兄弟を討つつもりだぞ。いかに里の者ではないとはいえ、事と次第によっては追及を免れまい」
「仇討ちはさせませぬ」
予期していた返答の一つだったのだろう。久秀は意外そうな顔も見せず、楽し気に目を細めて言葉の先を促す。
「明音には才がありまする。ゆえに、おのずと彼我の力量差を悟っております。辰巳兄弟を超えるための研鑽はとても数年では終わりますまい。この乱世のこと。研鑽を積むうちに、あの兄弟はどこぞの戦場で果てることでしょう」
「それであの娘の気が済むのか。天狗の斬り方は教えてやらぬのか。あやつは一刀石の前でうっとりとその日が来るのを夢想していたぞ」
「いかに才があれども、そればかりは」
「教えてやらぬのではなく、教えてやれぬのではないか」
宗厳はしばし口を閉ざした。この老人の手に乗ってはいけない。言葉巧みに相手の心中を詳らかにしてしまう手管は、久秀の家来であったときに何度も目にしてきた。言葉を選び、仕切り直す。
「どの道、仇討ちを為そうが為すまいが、それが成ろうが成るまいが、あの者の姉は戻ってきませぬ。怨嗟の声を胸中に鎮め、明音は己の生を全うすべきなのです。それが亡き姉への供養ともなるはずです」
「ふん、わしより坊主臭いことを言うのう。だがおぬしは一つ忘れておる。あの娘は呪いにかかっておるぞ。姉を死なせたのは自分であるという思いに囚われているゆえ、兄弟の首を獲って姉に詫びねばどうにも収まらぬのだ。あの呪いを解かねば、己の生に立ち戻ることなど到底できまい」
恐るべきは久秀。一度会っただけの娘の思惑をどこまで見透かしているのか。
やはり、これ以上関わらせてはいけない。宗厳は立ち上がり、東屋に向かい一礼した。
「客人をこれ以上お待たせしては心苦しい。拙者はそろそろお暇しますが、その前に一つお願いの儀が。もう明音には会わないでいただけますか」
さりげなく言ったが、刀の柄に乗せた手には殺気を忍ばせた。筒井家を疎んでいる久秀が、明音を己の策に巻き込まぬとも限らない。
宗厳の殺気をそらすように、久秀はつるりと禿げ上がった頭を撫でて笑った。
「よっぽどあの娘を気に入ったと見える。ま、そこまで言うなら約束しよう。会いに行ったりはせぬよ」
そこには先客がいた。数人の従者を従えた武士が、招かれざる訪問者をにらむ。従者の人数といで立ちを見るに、織田軍の中でも城主を任される高位にある者だろう。
宗厳が一礼して名乗ると場の緊張は解けたが、代わりに不審げな空気が流れた。
「失礼ながら、こちらで野点(屋外の茶会)をされると聞き及び、推参つかまつった。道意さまがこちらにお見えになっているとのことで」
宗厳が言うと、男たちの脇をすり抜けて老人が姿を現した。
「おお、宗厳か。わざわざ足労をかけたのう」
「なんのこれしき。道意さまこそ、先日はわれらの里まで足をお運びいただいたそうで」
「おぬしにその名で呼ばれるとしっくりこんな。昔の呼び方で構わぬぞ」
「では、霜台さまと」
老人は鷹揚にうなずいた。霜台とは弾正少弼の位を指す。この老人は法名の道意よりもずっと有名な名を持っている。松永弾正少弼久秀。主家乗っ取り、足利将軍弑逆、東大寺大仏殿の焼き討ちという三悪を為した梟雄として知られる人物である。
久秀は同席していた武士に、宗厳と少し話をしていきたいと伝えた。事情を知った武士は表情を和らげて承諾したものの、宗厳にはちらりと冷たい視線を投げてよこした。柳生家は織田家に臣従しているものの、当主の宗厳は里に篭って隠棲しており、表舞台に姿を見せることはなくなっている。それがこうして姿を現したのを怪訝に思っているのだろう。
二人は武士の一団がいる東屋から離れ、適当な木陰の河原で腰を下ろした。まずは宗厳が切り出す。
「先日のご用件をお伺いしてもよろしいですかな」
「澄ました顔でなにを言うか」
久秀が苦々しい顔で、扇で東屋を指した。武士の従者たちがちらちらと宗厳たちの様子を伺っていた。
「おぬしがここに現れたことで、わしの目論見はすでに潰えてしまったわい」
やはりそうか。宗厳はひそかに嘆息した。久秀が供も連れず密かに宗厳に会いに来たということは、織田家に知られたくない謀議があったということだ。あの日、天狗面の明音が現れたので、用心した久秀はしばらくその場から離れたのだろう。宗厳にとっては幸いだった。暗殺か、調略か、戦の助勢か。どのような謀議にせよ、宗厳は久秀に手を貸すつもりはなかった。先触れもなく自らここへ赴いたのは、織田軍に警戒を促し、久秀を牽制するためだった。
「かつての主従のよしみで、目障りな筒井の当主を始末してほしかったのだがな」
監視している従者たちに気取られぬよう、久秀は穏やかな微笑を浮かべたままそんなことを言った。宗厳も合わせて、素知らぬ顔で首を振った。
「拙者、戦国の世から身を引く所存にて」
久秀は苦笑いでうなずいた。
「ならばあの弟子は破門しておいたほうがよいのではないか。筒井の辰巳兄弟を討つつもりだぞ。いかに里の者ではないとはいえ、事と次第によっては追及を免れまい」
「仇討ちはさせませぬ」
予期していた返答の一つだったのだろう。久秀は意外そうな顔も見せず、楽し気に目を細めて言葉の先を促す。
「明音には才がありまする。ゆえに、おのずと彼我の力量差を悟っております。辰巳兄弟を超えるための研鑽はとても数年では終わりますまい。この乱世のこと。研鑽を積むうちに、あの兄弟はどこぞの戦場で果てることでしょう」
「それであの娘の気が済むのか。天狗の斬り方は教えてやらぬのか。あやつは一刀石の前でうっとりとその日が来るのを夢想していたぞ」
「いかに才があれども、そればかりは」
「教えてやらぬのではなく、教えてやれぬのではないか」
宗厳はしばし口を閉ざした。この老人の手に乗ってはいけない。言葉巧みに相手の心中を詳らかにしてしまう手管は、久秀の家来であったときに何度も目にしてきた。言葉を選び、仕切り直す。
「どの道、仇討ちを為そうが為すまいが、それが成ろうが成るまいが、あの者の姉は戻ってきませぬ。怨嗟の声を胸中に鎮め、明音は己の生を全うすべきなのです。それが亡き姉への供養ともなるはずです」
「ふん、わしより坊主臭いことを言うのう。だがおぬしは一つ忘れておる。あの娘は呪いにかかっておるぞ。姉を死なせたのは自分であるという思いに囚われているゆえ、兄弟の首を獲って姉に詫びねばどうにも収まらぬのだ。あの呪いを解かねば、己の生に立ち戻ることなど到底できまい」
恐るべきは久秀。一度会っただけの娘の思惑をどこまで見透かしているのか。
やはり、これ以上関わらせてはいけない。宗厳は立ち上がり、東屋に向かい一礼した。
「客人をこれ以上お待たせしては心苦しい。拙者はそろそろお暇しますが、その前に一つお願いの儀が。もう明音には会わないでいただけますか」
さりげなく言ったが、刀の柄に乗せた手には殺気を忍ばせた。筒井家を疎んでいる久秀が、明音を己の策に巻き込まぬとも限らない。
宗厳の殺気をそらすように、久秀はつるりと禿げ上がった頭を撫でて笑った。
「よっぽどあの娘を気に入ったと見える。ま、そこまで言うなら約束しよう。会いに行ったりはせぬよ」
0
お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説

狂乱の桜(表紙イラスト・挿絵あり)
東郷しのぶ
歴史・時代
戦国の世。十六歳の少女、万は築山御前の侍女となる。
御前は、三河の太守である徳川家康の正妻。万は、気高い貴婦人の御前を一心に慕うようになるのだが……?
※表紙イラスト・挿絵7枚を、ますこ様より頂きました! ありがとうございます!(各ページに掲載しています)
他サイトにも投稿中。

鬼嫁物語
楠乃小玉
歴史・時代
織田信長家臣筆頭である佐久間信盛の弟、佐久間左京亮(さきょうのすけ)。
自由奔放な兄に加え、きっつい嫁に振り回され、
フラフラになりながらも必死に生き延びようとする彼にはたして
未来はあるのか?

土方歳三ら、西南戦争に参戦す
山家
歴史・時代
榎本艦隊北上せず。
それによって、戊辰戦争の流れが変わり、五稜郭の戦いは起こらず、土方歳三は戊辰戦争の戦野を生き延びることになった。
生き延びた土方歳三は、北の大地に屯田兵として赴き、明治初期を生き抜く。
また、五稜郭の戦い等で散った他の多くの男達も、史実と違えた人生を送ることになった。
そして、台湾出兵に土方歳三は赴いた後、西南戦争が勃発する。
土方歳三は屯田兵として、そして幕府歩兵隊の末裔といえる海兵隊の一員として、西南戦争に赴く。
そして、北の大地で再生された誠の旗を掲げる土方歳三の周囲には、かつての新選組の仲間、永倉新八、斎藤一、島田魁らが集い、共に戦おうとしており、他にも男達が集っていた。
(「小説家になろう」に投稿している「新選組、西南戦争へ」の加筆修正版です)

夢のまた夢~豊臣秀吉回顧録~
恩地玖
歴史・時代
位人臣を極めた豊臣秀吉も病には勝てず、只々豊臣家の行く末を案じるばかりだった。
一体、これまで成してきたことは何だったのか。
医師、施薬院との対話を通じて、己の人生を振り返る豊臣秀吉がそこにいた。
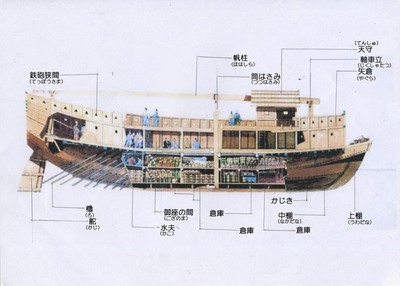

藤散華
水城真以
歴史・時代
――藤と梅の下に埋められた、禁忌と、恋と、呪い。
時は平安――左大臣の一の姫・彰子は、父・道長の命令で今上帝の女御となる。顔も知らない夫となった人に焦がれる彰子だが、既に帝には、定子という最愛の妃がいた。
やがて年月は過ぎ、定子の夭折により、帝と彰子の距離は必然的に近づいたように見えたが、彰子は新たな中宮となって数年が経っても懐妊の兆しはなかった。焦燥に駆られた左大臣に、妖しの影が忍び寄る。
非凡な運命に絡め取られた少女の命運は。


三国志「魏延」伝
久保カズヤ
歴史・時代
裏切者「魏延」
三国志演技において彼はそう呼ばれる。
しかし、正史三国志を記した陳寿は彼をこう評した。
「魏延の真意を察するに、北の魏へ向かわず、南へ帰ったのは、単に楊儀を除こうとしただけである。謀反を起こそうとしたものではない」と。
劉備に抜擢され、その武勇を愛された魏延の真意とは。それを書き記した短編です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















