15 / 34
浮上する影
しおりを挟む
『日々の記憶を編纂するために、日記をつけることにした。これがいつ遺書になってもおかしくない。』
書き出しはこんなもんだろうか。一文書いてガイはペンを止めた。さて何から書いたものか。そもそも誰が読むことを想定しているのかにもよるが、とりあえず自分の身に何かがあった場合を考えた。
『遭難からはや2か月ほど経って、皆の顔つきもどことなく変わってきた。』
「ダメですの~!レオナルドを置いていきたくありませんの~!」
「誰も置いていくとは言っとらんだろ!」
『例えば気の強そうなお嬢さんが、妙に駄々っ子になったり。』
港でひと悶着あった。曰く、レオナルドがデカすぎて船が重量オーバーになりかねないという。サウリアからこの大陸に来るまで乗っていた・・・正確には途中で難破した船は、もっと大きくてエンジンのついた近代的な船だったが、ここにあるのは帆船しかない。レオナルドを乗せれば最悪沈没、よくて文字通り亀の歩になってしまう。
「だからこうして筏を組んで別に乗せようって言うんだろ!
「何が悲しくて遭難したような準備をしなくちゃいけないのか。」
「竹がいっぱいあってよかったね。」
そういうわけで、レオナルドを乗せて帆船で引っ張っていける筏を用意している。全員工作のスキルが上がりつつある。
「大人しくしているんですよレオナルドー。」
『グゥ。』
「アイツも頭良くなってってるよな。」
「最近はオレらの言うことも聞いてくれてるし。」
推測の域を出ないが、体が大きい分脳もデカくて賢いのかもしれない。そういえば元は遺伝子改造を施された実験体だという事を考えると、そういう学習脳の処置を施されているとも考えられる。
まあ、従順なうちは問題ないだろう。
『グゥーグゥー。』
「それはイカダだから食べてはいけませんわよ!」
それとも考えすぎだったか?
「かわいい食いしん坊さんじゃないか。」
「かわいいか?」
「かわいいだろう。」
「かわいいですわ!」
「「ねー。」」
☆
そんなこんなで、無事に船は出航した。風に扇がれて、たっぷり1週間は潮の香りを堪能することになる。
「そんなにかかるのか。」
「ただの帆船だしな。食糧や水の問題はなさそうだけど。」
ビタミンは足りている。壊血症の心配はない。
「ぼぇええ・・・。」
「もう酔ったのか。」
必要なのは酔い止めの方だった。
「みんな情けないなー。」
「サリアは平気そうだな。」
「海運商の家やからね。」
「先生も平気そうだな。」
「密輸船に密航したときよりは穏やかなもんだ。」
「難破したとはいえ、サウリアからの船のほうが揺れは穏やかだったな。」
「波の強さも向こうの方が上だったと思うよ。」
やはり根本的な技術の差だろうか。むしろあの船の技術力の方が異常だったのだろう。壊れたけど。
(自然現象、不可視の電磁波の影響があったんだろうか。)
信仰の強い世界観なら、それを『天罰』と表現するだろうが、皆そういう風には捉えていないようだ。信仰に盲目ではないらしい。
「で、お前はなにをやっとるんだ。」
「この揺れの中なら、バランス感覚を鍛える訓練になるかもしれない。と、小遣い稼ぎ。」
「強かね。」
一方アキラは船員のアルバイトをしていた。大きな樽を運んだり、マストを整理したり、力仕事には事欠かない。
「アキラっていつもこういうのしてたの?」
「この世界来てこっち、大体そうだな。適当に仕事しながら旅してた。」
「定住しようとかは思わへんかったん?」
「こっちのが性に合ってる。」
家のタガから外れたアキラはとても生き生きとしていた。
「自由の身、ですのね。」
「あらシャロン、羨ましいのかしら?」
「べつにそういうわけではないわ。」
「たまに外で遊ぶぐらい許されるんじゃない?今が遊びの状況なのかは微妙だけど。」
「ははは、まあ気は抜けないわね。」
そうは言うが、ゴールにアテが見えてきたことで皆に余裕が生まれてきていた。余裕が生まれれば、旅を楽しむこともできる。
「おーい兄ちゃん、こっち手伝ってくれー。」
「はーい、じゃあまた後でな。」
「がんばってー。アタシたちも船室に戻るかしら。」
「そやね、みんなグロッキーになっとるけど。」
「シャロンも平気?」
「風に当たっていたらなんともないわ。うぇっぷ・・・。」
「やっぱダメじゃん。」
「あはは、もうちょっと外おろか。」
胃から空気が抜けてきた。シャロンはゲイルに背中をさすられながら、水平線に目をやった。陽の光を反射して、キラキラと輝いている。
「綺麗ですわね・・・。」
「せやなー、ん?」
サリアは、遥か遠方の海面がにわかに泡立つのが見えた。
「なんやろ、あれ?」
「海底からガスでも漏れてるんじゃないの?」
「ひょっとして、海底火山?」
「もう噴火はイヤですわよ?」
「そんなに近くも無いし、平気でしょう。こっちは動いているんだし。」
だから気にも留めないことにした。やがて泡が弾けるように、記憶からも霧散した。
船旅はまだまだ長い。その早々に出くわしたこれは、吉兆か凶兆かと言えば凶の方だった。
☆
「そういえば、この船って何を運んでるんだろ。」
3日目の昼食の席で、ふとガイが口にした。
「あれ、これってフェリーじゃないの?」
「ううん、貨物船やで。さっきも停泊して荷物積んどったやろ?あれトウモロコシや。」
「穀物か。今食べてるこれもトウモロコシの乾パンだな。」
「それに、このオレンジも。シロップ漬けの缶詰みたい。」
なんとも水が欲しくなる食事だが、副菜にバリエーションがあって飽きは来ない。
「人間というのは陸の生き物だとほとほと感じさせられるよ。」
「そう?」
「水中で息できないし、漂流したら溺れ死ぬし、海には危険が多い。」
「ひょっとしてガイ泳げない?」
「・・・決して泳げないわけではないぞ。」
「苦手なんだな。」
「そういえば、さっき停泊してた時の話なんだけど。」
「うん?」
「なんかここ最近、この辺の海で沈没事件が多発してるらしいよ。」
「事件?事故じゃなくて?」
「犯人がもうわかっとるからから事件なんやって。」
「マジ?」
「ゴホンゴホン。」
「お?なにアキラ。」
「お前ら、そういう話はせめて部屋戻ってからしろ。」
「なんで?」
「ここがその海の上だからだろ。」
食堂で食中毒の話なんかされたくないだろう?ともかく、場所を移して話は続けられる。
「で、何者なんだ?」
「噂によると、デビルフィッシュの仕業やってさ。」
「デビルフィッシュ?」
つまりタコである。
「なんでも、触手から毒を出して大きな獲物をも仕留めるんやて。だから悪魔の魚。」
「なるほど、そりゃ煮ても焼いても食えなさそうだ。」
「でもレオナルドなら構わず食べてしまいそうですわ。」
「あー、バカだからなアイツ。」
目の前にあるものにはなんでも噛みつくし、咀嚼できるならなんでも胃に収めてしまう。餌やりをするのもコツがいる。
「それにしても、そういうの話してると、高確率で巻き込まれるんだよなぁ。悪い予感ほどよくあたるっていうか。」
「そうそう、口は災いの門っていうか。」
「コトダマというやつですわね。」
「でもまさか俺たちが巻き込まれるわけないわな?」
「ですわよねー、そういえば初日に妙に海が泡立っていたのを見ましたが、きっと関係ありませんわよね!」
「ないない、今朝エサやりに行ったときもなんか海が泡立ってたのもきっと気のせいや。」
「「「ワーッハッハッハ!」」」
☆
半日後、船は傾いた状態で最寄りの港に到着した。
「悪い予感ほどよくあたるっていうか。」
「そうそう、口は災いの門っていうか。」
「コトダマというやつですわね。」
「「「一体何者の仕業なんだ???」」」
「お前らのせいだろ。」
「断じて違う、たぶん。」
無事に陸まで辿り着けたのは幸いとしか言いようがないだろう。積み荷はほとんど落としてしまったようだが、命には代えられない。
「でも大損やで。なんとかしてあげられへんかな。」
「サリアが気にすることじゃないだろ。」
「同じ商売人としては、こういう時こそ助け合いやで。」
「そんな聖人じゃあるまいし。」
「ちょっとガイ。」
「お前の言いたいことはわかる、が無理な話だぞ。」
「まだ何も言ってないぞ。」
「商売人でも聖人でもないけど、人として困ってる人は助けたい。」
アキラの言葉に裏はない。いたって善意から発せられている。
「そんなこと言ってる場合か?俺たちの命が優先されるべきだろ?」
「おおクリン生きてたか。」
「さっき点呼とったろ・・・ここからは陸路で行くって手はないのか?」
「ふむ、まあ無理ではない。ちょっと遠回りになるが、無理ではない。」
「なんで歯切れが悪いのセンセ?」
「ここからだと山道しかないからな。レオナルドの足も遅くなる。」
「山か・・・。」
むしろ、山を迂回するための海路だったというのに、これでは元の木阿弥だ。
(海の異変を解決しない限りは、海路は使えないか。)
(スペリオンならできないのか?)
(無理な話って言ったろ。)
そもそも範囲が『海』という時点で広すぎる。地点に目印も無い、上からじゃ海中の様子も見えないとあっては、骨が折れるどころか砕け散る。
せめて、何か手掛かりがあれば。
「よし、じゃあまずは壊れた船から調べていこうぜ。」
「調べるって、何を?」
「捜査の基本は足だ。」
「おっ、なんだなんだ。」
「探偵ですわね!」
「そういうわけで先生、何を調べたらいいと思う?」
「いきなり人に聞くなよ・・・そうだな、船を調べるものと、聞き込みをするものとで分けたらいいんじゃないか?アキラは船員をやっていたし船を調べて、サリアは商売人なら船員から話を聞けるかもしれない。」
「よし!じゃあ手分けしていこう!」
「・・・それって俺も行くのか?」
「山と海どっちがいい?」
「・・・海かな。」
☆
「ふーん、岩とかにぶつかって壊れたって感じじゃないなこれは。」
船体は外から奥の方へ、というよりは下方向に引っ張られて壊れたという風に見える。だが船体が沈む前に破られるだろうか?どうにも単純なパワー以外の力がかかったように見えるとアキラは踏んだ。
アキラと同行しているのは、ドロシーとゲイル、そしてシャロン。シャロンはレオナルドの様子を見に来ただけだが。
「たしか触手から毒が出るとか言ってなかったっけ。」
「なるほど、その毒のせいか。」
「あんまり直接触りたくないわね・・・。」
海にも毒を持った生物は多い。だが、毒というのは大抵弱い生物が自衛のために持つというパターンが多い。船を襲うために毒を使うというのは、相当頭がいい生物なんだろうか。
「噂通りデビルフィッシュがその正体なら、一体どんな奴なんだろう?」
「毒以外にどんな武器を持っているのかしら?」
「そもそも、一体何が目的だったんだ?」
必要な情報が増えてきた。そういうわけで船員に突撃インタビューを敢行した。
「デビルフィッシュ?ああ、『デクト』のことか。」
「『デクト』?」
「海底にすんでるタコの仲間さ。動くものにはなんだろうと咬み付く、毒のある狂暴なタコさ。」
「うーん、悪魔的。」
船を直す工員の1人が言った。
「でもデクトが船を沈めるなんてありえないぜ。10cmぐらいしかないんだぞ。」
「ちっちぇ。」
「被害と言えば漁の網にたまにかかったやつに、油断してたら噛みつかれるぐらいなもんだ。」
「つまり、どういうことだって?」
「ただのデビルフィッシュじゃないんだろう。」
「すんごいデカいんでしょうね。」
デビルフィッシュ以外の何者かの仕業とは考えない。
「もう少し探したら、シャロンを迎えに行きましょう。」
「レオナルドがなにか知っているかもしれない。」
そういえば、現場に一番近いところにいたのはレオナルドだった。
「ゲイルー!ゲイル来てー!」
「はいはい、なによ一体?」
「レオナルドの体に変なものがついてますのよー!」
「変なもの?」
それは、黒くて細い触手のようなもの。おそらくはデビルフィッシュ、デクトの脚だろう。それがレオナルドの口の周りについている。
「食ったなテメェ。」
『グゥ。』
「そんなものを食べたらお腹を壊しますわよ!」
「でもこれでハッキリしたわね。事件の傍には必ずデビルフィッシュがいる。」
毒を喰らったはずなのに、当の本人はケロリとしている。よっぽど人間なんかよりも強靭な胃袋を持っているらしい。
「他に何か変なもの食ってないだろうな?ちょっと口開けてみろ。」
「ええ、ほらレオナルド、アーンして。」
『グォッゴゴ。』
ガポッとレオナルドが口を開くと、アキラはその中を覗き込む。生臭いニオイがこもっている。口の中に怪しい物は・・・。
「あっ、なんだこれ・・・コーン?」
「トウモロコシ?積み荷の?」
「・・・まさか、お前。」
『グゥグゥ。』
「・・・いやいやそんなまさか!レオナルドにはちゃんとエサをあげていましたわよ!きっとたまたま流れてきたものが口に入っただけですわ!」
にわかに身内に犯人説が出てきてしまった。もっとも、沈没事件は以前から起きていたので、おそらくシャロンの言う通りたまたまだろうが。
「まあ、なんだ。このことは内密にしておこう。」
「レオナルドはコーンが好物なんですわね。今度用意してあげますわ。」
『グゥグゥ!』
「あ、喜んでる?」
「喜んでますわ!かわいいですわね!」
デビルフィッシュにもこれぐらいの聞き分けのよさと、可愛げがあればすみわけが出来たろうか。
☆
さて、街で聞き込みを始めたガイたちであったは、海鮮焼きの屋台に舌鼓をうっていた。
「うまい。」
「うまいなぁ。」
「って、食っとる場合やないやろ!」
何も食べ歩きがしたかったわけではない。聞き込みをしようとしたら屋台に引きずられてしまったのだ。元々船の乗客に向けた屋台をやっていたので、商魂に負けたといったところだ。
「海で獲れたものがそのまま焼かれてるから新鮮でうまい。」
「サザエのつぼ焼きがこんなに大きい・・・。」
「出荷されずに余った分をこっちに回してんねんな。」
どうもここ最近は、漁が大漁続きで屋台にも大物が回ってきて繁盛しているとのこと。
「それ海の異変と関係あるのか?」
「クリン何個食ってんだよ。」
「正直一番食文化をエンジョイしてるよな。」
「やーい文明人ー。」
「それは褒めてるのか貶してるのか。」
ここ最近というのが、海の異変と前後しているのなら無関係ではあるまい。
「疑問なのは、貨物船が何者かに襲われているのに、漁船は無事だという点かな?」
「お、パイル鋭いな。確かに、船は船でも、大型船ばかりが狙われてるってことか。」
「モグモグ、通航量というか、海にいる確率は漁船の方が多いよね?」
「まあ、この町は元々漁港の街だったのを、貨物船の中継地にしてるってところだし、漁船の方がまだ多いだろうね。」
「背の高い建物もそんなにないね。」
波止場近くに、貨物船の商会のものらしき建物ならある。中は事務所だった。
「漁船以外が被害を受けてるってことは、じゃあ漁師たちが犯人?」
「そういうの、街中で言うなよ。それに多分違う。商会のおかげで人の出入りがあって、村としてはむしろプラスのはずだからな。」
「どうだろう、実は恨み買ってたりとか?」
「今まさに喧嘩売ってるところなんだよなぁ、俺たちが。」
現在進行形で通りかかる人から変な目で見られている。
「おい兄ちゃんたち、オレたちの商売になんか文句あるのか?」
「いや、決してそんなつもりは。」
「まったく、ただでさえお上の締め付けがキツイっていうのに、外から来た連中は問題ばかり起こしやがる。」
「なんだ、ここってそんなに税金とられるの?」
「おうよ、特にここ数年上がりっぱなしだ。おかげでどんなに働いても全部吸い上げられちまう。」
「数年前ねぇ。ちなみに、貨物船が来るようになったのは?」
「数年前だな。さあ仕事だ仕事。」
まるでRPGのNPCのように情報だけよこして漁師のおじさんは去っていった。
「なんでどこもかしこも外の人間と軋轢を生んでるのかね。」
「これがホントの貿易摩擦っちゅーやつやな。」
「座布団一枚。」
国が金を集めてるということは、戦争準備でもしているのかという推測はさておき。
「税金と商会に、関係があるのかな?」
「商会が政府と繋がってるとかだろ。」
「利益が見込めるから、国があげて貿易をしていると考えれば筋は通るね。」
「なんや、国が指導しとんのか。あんま自由な貿易とちゃうねんな。」
「それで売るものがトウモロコシか。」
ウラが見えてきた。貿易で利益を上げて、富国強兵を図る、実にシンプルな実態だ。でもそれが今回の事件とどう関係しているのか?
「関係なくないか?」
「なくはなくないんじゃないかな?」
「俺も正直ないと思う。」
「ガイもそう思う?理由は?」
「・・・ない。勘だ。」
「考えたくなくなっただけだろ。」
「うん、そんなことより焼きトウモロコシが食べたい。」
「あっ、それサンセー。」
「結局食い意地かよ。」
「いいじゃん、一回食ってみようぜその・・・どこ産のトウモロコシだったっけ?」
「ゴルムやな、ジーナスより北で、もっと行くとウーシアに入るその手前。ノメルに負けず劣らずの農業大国やで。」
「そうか、じゃあそのゴルム産とやらを食してみようじゃないか。」
☆
「それでお前ら、散々食べ歩きだけしてきたのか。」
「センセたちの分もあるよ。」
「あら、甘いのね。」
「たしかにうまい・・・じゃなくて。」
集合場所の広場に、手土産を持ってガイたちは戻ってくると、デュランとカルマを丸め込んだ。
「昔旅をしていた頃に食べたものより、随分甘くなってるんだな。」
「糖度が高くて、生産性の高いように品種改良されてるんだな。」
「やはり、なにかの陰謀が?」
「陰謀?何の話?」
「ジーナスがゴルムを抱き込んで、産業革命を起こして世界を牛耳るんだろう、ってガイが。」
「そこまでは言ってない。」
「うっかり聞かれたら消されてしまいそうな話だな。」
あくまでシナリオのひとつとしてあり得そうというだけ。本筋には関わらない。
「ただいまー、って何食ってんだお前ら。焼きモロコシ?」
「あー、もう帰って来やがったか。」
「食いたきゃ自分で買ってこいってワケか。そっちは何か収穫あったか?」
「収穫というか味わったというか。」
「おい。」
全員合流し、情報交換を行った。
「品種改良されたトウモロコシに、未知の怪物、まさか!」
「どしたんアキラ?」
「品種改良されたトウモロコシを食べた生き物が、怪物に突然変異したとか!」
「遺伝子組み換え食品と、生物の突然変異には因果関係ねえよ。」
「でも、積み荷のトウモロコシが狙いってのは考えられるわね。それなら、貨物船ばかり狙われる理由になる。」
「じゃあそいつはナニモノなんだ?デビルフィッシュって呼ばれてるデクトってタコは、そんなに大きくないらしいし。」
「だからそいつが突然変異で!」
「突然変異便利すぎだろ。」
そんな食べただけで巨大化する食べ物があったら、この星は巨人の星になるっての。
「まあ、これだけ問題になっているなら、商会の方も何かしら手を打つだろうな。」
「明日大きな調査船が来るんだってさ。」
「じゃあ、もう任せちゃって休もうぜ。」
「そうだな、これ以上我々に出来ることはないだろうし。」
我々の力で解決するにしても、もう得られる情報はない。一晩じっくり寝かせて、明日考えてみるのがいいだろう。
「けど、ナンセンスですわね、突然変異なんて。」
「なにおう、ありえなくはないだろう。」
「せやせや、まさかまた恐竜みたいなんが出てくるとは思えへんで。」
「そう何回も遭遇してたまるか。いくら毒を持っていようと、個々の力は微々たるものだ。」
そうしてまたフラグを建てて夜を迎え、翌日の昼。腹の下に響く轟音、建物が崩れる振動の中でアキラは目が覚めた。
「なんだぁ!?」
「起きろみんなー!敵襲だぞ!」
「敵襲?!」
宿の外はまさに火事場のような騒ぎ。
「砲撃?!どこからだ!」
「海!」
騒動の元のひとつは海の上に浮かんでいる。そしてもうひとつが街を蹂躙している形になっている。
「タコ?いや、貝?」
大きな巻貝が、うにょうにょと動く足で蠢いている。
☆
時間は戻って朝。
港のすぐ沖には、でっかいお船が浮かんでいた。
「軍艦かあれ?」
船体に装甲が取り付けられ、大砲が並んでいる。
「あれはジーナスの船?」
「旗がそうだな。」
「あんなもの見せつけて、国際問題にならないのかな?」
「牽制の意味もあるんじゃないか。それと試運転と。」
「近くまでいってみようぜ!」
大げさな武装からは威圧感を醸し出す。一見したところ帆船でもない。ひとつ先のテクノロジーが使われているんだろう。それはまあさておき。
「なんかあの旗のマーク、見覚えがあるような?」
「見覚えがあるもなにも、ヴィクトール商社じゃないのかあれ。」
サウリア大陸から乗り合わせた船が沈んだ、あのヴィクトール商社である。あまりいい気分しないというか、嫌な予感がする。
「というか、国じゃなくて、商社の所属の軍艦?」
「ヴィクトールは商事だけやなくて、軍事や技術にも手を伸ばしてるから。」
「そのうち死の商人にでもなりそうだな。」
既にヴィクトール商会は、ジーナスだけにとどまらず、シアー大陸全体にまで手を広げているという。世界有数の一大勢力に王手がかかっている状態だ。一方、艦のブリッジでは、対策会議が行われていた。
「此度の貨物船難破事件、一刻も早い解決のため、我々も協力を惜しまないところだ。」
「ヴィクトール商社の、それもヴィクトール社長直々の支援、まことにありがたい。」
そこにいるのはそう、相も変わらずでっぷり腹に一物抱え、手にはネジを摘まんだ、カイゼル髭のおっさん。マシュー・ヴィクトール社長である。
「まさかヴィクトール商社から、こんな慈善事業の申し出があるとは夢にも思いませんでした。」
「いやいや、困った時は助け合いと相場が決まっておりますからな。」
(新しい船を売り込むチャンスだな。タダより高いものはない。サウリアだけでなく、地中海にも我が社の船を浮かせる時だ。)
情けは人のためならず、とはいうもののウラも下心もあるのが人間というもの。ただそれを表に出さないだけで、こうも丸く収まるのだ。
「では、どのように解決なさるおつもりで?」
「うむ、まずはだな・・・。」
「おっ、なんか始まったぞ。」
「すっかり見物人ムードだな。」
外では屋台がまた繁盛している。
「複数隻の船で、陣形を組んでいるのかしら?」
「陣形というには距離が開き過ぎだな。それよりも、あの網を使うんだろう。」
「なるほど、電気ショック漁か。それなら簡単に燻りだせるな。」
「でもそんな電源どっから用意するんだろ?」
「お抱えのゼノンがいるのか?」
「普通にジェネレーター使うんじゃね。発電機は積んでるようだし。」
メルカでは神秘とされている法術が、今まさに目の前で手軽な道具として扱われようとしている。
ここが未来の地球だとすると、どうすれば電気を使えるのかすぐに調べられたとしてもおかしい話ではないが、それでもガイには歪に映った。一つの大きな大陸なのに、なぜこうも思想に違いが出るのか。ヴィクトールがすごいのか、それとも、ゼノンが異常なのか。
(ヴィクトール商社によって、技術の目覚ましい発展が成されているとすると、それはつまり・・・。)
いずれにせよ、この件は大きな火種になりそうだ。下手に燃え広がらぬことを切に願う。
そうこうしている間に、船が動き出した。正体不明の敵を探しに行くらしい。
「じゃ、あとは任せて帰ろうぜ。」
「結局オレらが探索した意味無かったなー。」
「でも、これで解決ならそれに越したことはないわな。」
「そーねー、わたしたちはゆっくりお茶でも飲んで待ってましょう。」
「昼過ぎには帰ってくるかな。」
と、フラグを外野から散々建てまくって昼のシーンに繋がるのだ。
☆
先ほどまで海に浮かんでいた船が、今は町の瓦礫に横たわっている。火の手から濃い潮のニオイが漂ってくる。
「消火しろー!」
「バカ野郎逃げるぞ!」
さっきまで呑気な見物人だった町が、混沌の火事場となり果てた。対岸の火事、どこか他人事であった災厄が、文字通り降ってきたのだから。新式の軍艦から放たれる砲火が、容赦なく町を焼く。
「で、あれはなんだよ!」
「わからん!突然海からやってきた!」
勿論、連中はなにも戦争がしたくてそうしているわけではない。海から現れた災厄を討つためである。
タコだか貝だか、ようわからん。たとえるなら、アンモナイトのような巻貝から、アノマロカリスのような体が飛び出し、その顔の下からタコの触手が4本ずつ2対生えており、あたかも王様のヒゲのように見える。
「あれが海のおじさんの言ってた『デクト』の王様なら、『デクトキング』ってところか。」
「そのまんまだな。てかもっと小さいタコのはずだったろ。なんであんな姿の、それも巨大になってんだ!」
「きっと『突然変異』ですわ!」
「便利な言葉ねー、突然変異。」
だがデクトキングの姿は、到底自然から生まれるような『自然体』ではない。様々な古生物の合体したいような、ちぐはぐな恰好をしている。悪意ある何者かが、人為的に生み出したのでないとするならば、突然変異という他なかろう。それが何故巨大化しているのかは不明だが。
「とにかく、今はみんな合流するんだ。ここにいないやつらは?」
「港の方に行ったっきり!」
「えっと、ガイとサリアと、ドロシーとカルマと、あと先生?」
「レオナルドも放っておけませんわ!パイルがエサをあげに行ってますわ!」
「みんなバラけすぎだ。」
状況はよろしくない。散り散りになってこの混乱の中を探し回るのは愚行。特にアキラは、ガイと一刻も早く合流しなくてはならない。
「・・・よし、ゲイルはまた纏で避難指示を出してくれ。そこを合流地点とする。」
「わかったわ!」
「俺一人で全員を探しに行くのは厳しい・・・たぶんあっちも、レオナルドとパイルを迎えに分かれてると思う。」
「ならわたしがレオナルドの方に行きますわ!」
「危険だぞ?」
「忘れられているかもしれませんけど、わたしゼノンですわ!」
「そうか、じゃあクリンもついていってやってくれ。1人だけだと何かあった時困る。」
「ここに誰か戻ってくるかもしれないが、誰もいないと困るんじゃないか?」
「そうか、じゃあクリンはここで待機を頼む。シャロン、気を付けて。」
「平気ですわ!」
手際よく指示を飛ばせたところで、アキラもまた走り出す。
☆
「・・・ツマランな、祭りの花火というにはいささか派手さに欠ける。」
港町から外れた高台の上で、焼きトウモロコシを持って、目深にフードを被った男が呟く。目下ではデクトキングによる蹂躙が行われているが、それを見て心底つまらなさそうに、トウモロコシを一口齧って捨てた。
「あの男の貪欲さもなかなかだが、すべてを焼き尽くすほどの煩悩の炎には程遠いな。」
「いっそ自分を燃やしてみればいいんじゃないか『創造者』?」
クリエイターと呼ばれたその男が右手を掲げると、それが自身の頭を打ち抜こうとした弾丸を跳ね返した。そうすると、面白さ半分、呆れ半分といった具合にヘビのような目を攻撃の主に向ける。
「それならもう108度は試したかな。結果は御覧の通りだよ、『混沌の子供』、いやさケイよ。」
「なら109回目は俺の手で下してやる、ベノム。」
「遠慮しておく。今はもっと、人生を楽しみたい。」
「生きているとも死んでいるとも言えないやつが、そんな権利あると思う?」
「それはお互い様だろう?」
カッカッカと牙の生えた口が笑い、ペロリと細い舌を見せる。
「私に言わせてもらえば、あるかどうかすらわからないモノを探しているお前たちも大概だがな。」
「黙れ、少なくとも俺は誰にも迷惑かけてない。」
「私だってそうさ、哀れな人間の願いを叶えてあげているだけだ。私はその様子を見て楽しんでいるだけ。」
その瞬間、町の一角に閃光が迸る。
「そら、このショーを面白くしてくれるヒーローの登場だ。」
「スペリオン・・・。」
ベノムは拍手でもって迎え、ケイは苦々しい表情で見つめた。悔しいことに、この展開はベノムの望む通りのものだったから。
☆
「あっ、スペリオンだ!」
「来てくれたか!」
「ガイさんとアキラはどこに行きましたの?」
「あの2人なら大丈夫だろう、避難するぞ!」
多くの人間はその姿に目を奪われているが、すぐに現世に意識を取り戻すと避難が再開された。
『速攻で片づける!』
(無論だ、タコはあんまり好きじゃない)
『奇遇だな、俺もだ。』
首尾よくガイと合流できたアキラは、スペリオンへと合体変身を遂げた。今日も赤い体躯が燦燦と輝く。
『って、何やってんだアイツは?』
(どうやら倉庫を漁っているようだが。)
タコとヤドカリの相の子が、もぞもぞと建物の一つに執着している。なんだなんだとその背負った貝を引っ張ってみれば、何が目的だったのかは一目瞭然だった。
『この黄色いの・・・トウモロコシか?』
(どうやら粉末にして、バイオマスにするところのもののようだな。思ってるより進んでるんだな。)
『マス?魚、のエサ?』
(違う、バイオ燃料のことだ。)
炭水化物も組成が違えばエタノールになる。まさか化石燃料よりも先にバイオ燃料の研究が行われているとはガイも思わなんだ。
ともかく、どうやらデクトキングの狙いはコーンだとわかった。貨物船を襲っていたのも、やはり積み荷のコーンが狙いだったのだ。
『じゃあなにか、コイツはトウモロコシ食ってこんなにデカくなったのか?』
(ああ、だがただのデブとは違うぞ。)
コイツは動けるデブだ。触手を器用に使って体勢を立て直すと、殻の中から大きなハサミが飛び出してくる。
『今度はロブスターか!』
(挟まれると怖いな。)
『そんなにトロくねえ!いくぞ!』
左右非対称な歪な形の威圧感にも怯まず、スペリオンは大地を蹴って距離を詰める。図体がデカいだけでは、アキラには木偶の坊に過ぎない。関節部分を手刀で痛めつける。
『グボボボボボボ』
『うっ、邪魔な触手め!』
(切り払え、アームドフィンだ!)
『よぉし!』
腕から赤いクリスタルの刃が伸びると、纏わりつく触手を切り裂く。一歩引いて様子を窺うと、すぐさま触手は生え変わっていく。
『なんて再生力だ、キリがないぞ。』
(なら光波熱線で焼いてしまえばいい。)
『熱線の出し方なんてイメージできるかよ!』
(なら口から出してもいいんだぞ?)
『それはもっと嫌だな、ビジュアル的に。』
(柔軟性のないヤツめ。)
『タコには負けるわな。』
丹田で気力を練り込んで、呼吸と共に吐き出す。一緒に口から洩れてしまいそうなのを抑えて、掌に集中する。
『はぁああああああ・・・。』
(それ、名前は?)
『名前?えっと・・・気功・・・ブレイズ!気功ブレイズ!』
円を描いた両手を、胸の前で花の形にして押し出す。緩やかな勢いながら熱い炎が噴き出して、デクトキングの触手をこんがりと焼いていく。
(・・・いいんじゃない?)
『名前に意味あんのかよ!』
(まあ、あるっちゃあるよ。)
干物にしてもあまりおいしくなさそうな触手が、ぶすぶすと煙を上げ始めていた。
「よーし!いけいけー!!」
「熱気がすごいな・・・。」
「このままいけば・・・ってあれは!」
それまで静観していた戦艦が火を噴いた。だがその標的は、海獣ではない。
『グワーッ!な、なんだ?!』
(こっち撃ってきやがった!)
『なんでだよ!明らかにヒロイックな姿してるだろ!』
(彼らにはどっちも同じように見えてるんだろ。)
狙ってなのか、それとも流れ弾なのか、どちらにせよ思わぬ一撃を受けたスペリオンはたじろいで技を中断させられる。そうするとどうなるか。
『うぬっ、小癪な!』
(海へ引き込む気か!)
デクトキングは再び出したハサミでスペリオンを掴むと、勢いよく海へとダイブする。海はデクトキングのフィールドだ。
『ぐぉおおお・・・潰される・・・身動きできない・・・っ!』
(まずいな・・・。)
水中に骨が軋む音が響く。両腕ごと縛られている現状では、抵抗することもままならぬ。
『何か手はないのかよ!』
(髪を使え!)
『髪?!』
確かにマスクに収まりきらない髪が光を放っているが、そんなものを使えと言われても熱線を出すよりもイメージ出来ない。
(そのまま伸ばせばいいんだよ!)
『ええい、伸びろ!』
後頭部からレーザーが発せられ、ハサミの付け根を貫く。いきなりの奇襲に、デクトキングも狼狽える。
『ホントに出た・・・。』
(オプティックファイバーだ、覚えとけ。)
光のタテガミ。思ったよりも自在に動いてくれるが、使い過ぎるとハゲが心配になる。
ともあれ危機を脱したがのもつかの間、デクトキングは口から黒いもやを吐き出して目くらまししてきた。タコというからにはおそらくスミだろう。
『うっぷ!気色悪い!』
(だが今ので見失ったぞ。)
スペリオンはすかさず腕を大きく回して水流を作り、スミ洗い流したが、その隙にデクトキングの姿は消え失せていた。海底にあの巨体が隠れられる岩陰などはない。
(だがタコは岩に擬態する能力も持っている。岩のどれかに化けたのかもしれない。)
『アイツの背中も巻貝みたいで岩っぽかったからな。どれだ・・・?』
敵のホームグラウンドで長居はしたくないが、ここで逃がすわけにもいかない。
(・・・。)
『・・・。』
(・・・で?)
『なんか手立てはないのかよ?』
(ない。)
『とにかく、これじゃあ埒があかん。適当に目星をつけて吹き飛ばしてやる!そこだぁ!』
再び、気功ブレイズを放ち岩を砕く。目当ては外れたが、岩の一つが急速に逃げだした。デクトキングの背負っていた巻貝である。
『いやがったな、切り刻んでサシミにしてやるぞ!』
手に光の刃を出現させ、容赦なく突き立てる。しかしそれは意外なほどに手ごたえのない物だった。
『なにっ?!これは!』
(殻だけ?)
文字通りのもぬけの殻。返ってくるのは空虚な反響音だけ。直後、背中に嫌な予感を感じる。
(後ろだ!)
『なにっ!?うぉおお!』
誤算だった。タコは思いの外頭がいいが、まさか身代わりの術を使うとは思わなかった。背中にビッタリとくっつかれ、両肩にアノマロカリスのような口が突き刺さる。
『ぐっ・・・力が入らない・・・。』
(ぬぅん・・・毒か・・・。)
デクトキングの体重以上のものが伸し掛かる。
『どうにかならねえのか・・・。』
(生物毒なら、大抵タンパク質だ。タンパク質は熱で壊れる。)
『熱か・・・うぉおお・・・!』
再び、丹田に力を込める。今度は血液の巡りを良くし、発汗を促すように、体温を高めていく。
『ぬぅおおお・・・万力発散、スーパーデトックス!』
『ゴポンガァ!』
たちまち強熱が発生し、周囲を熱湯に変えていく。思わぬ反撃に、またデクトキングは離れる。が、今度は逃がさない!アノマロカリスの牙を引っ掴むと、ぐるんぐるんと思いっきり振り回す。
『へっ、折れちまったぜ。』
(貝は自分で捨てた、牙は折れた、なら残っているのは触手と・・・。)
ロブスターのような大きなハサミ。最後はこれを使ってくるだろう、自棄になったのか、海底を触手で駆けながら、スペリオンへと向かってくる。
『そっちが空蝉の術なら、こっちは畳返しの術!』
ハサミがふりかぶられるその瞬間、光の刃で海底の岩盤を切り、壁のように立てかける。粉々に砕かれる岩盤、その向こうにさらにハサミを振るうデクトキングだったが、その攻撃は空を切る。
『からのっ、土遁の術!』
体をドリルのように回転させて地中を潜り、デクトキングの虚と体を突く。
『ゴボボボボボボボボ』
『サシミじゃなくて串焼きになっちまいそうだな。』
(だが、こいつの再生能力は伊達じゃない。煮ても焼いても食えなさそうだ。)
『なら、干物にしたらどうだ!』
突き刺した手に回転エネルギーを纏わせる。するとデクトキングの体がプロペラのように回転を始める。
一方海面では。
「なんて渦だ!」
「巻き込まれたら沈むぞ!」
「社長、御無事ですか?」
「ああ、だがあの巨人・・・。」
戦艦の上で、ヴィクトールが呻く。恐るべき海獣を相手にしても沈むことが無かったことは、ヴィクトールも織り込み済みであった。しかし、あの巨人を見た途端に、ヴィクトールの顔色も変わった。
「あの」巨人はどこだ?」
「海です!あの海獣と戦っているでしょう。」
ようやっと現状を把握できたところだったが、現状というものは刻一刻と変化するもの。既にスペリオンのフィニッシュブローは始まっていた。
「渦の中から!」
「渦の中からなんだ!」
「海獣が!」
跳び出した。それもプロペラのように回転しながら、その下に巨人がぶら下がりながら、空へと向かっていく。
『遠心力で水分を全部飛ばす!』
(いい作戦だ!これなら再生も出来まい!)
デクトキングの体はスルメのようにどんどん乾いていく。
『あとは・・・燃えろぉ!気功ブレイズ!』
(やれええええええ!!)
すっかり元の体重の10分の1よりも軽くなり、回転力のままに打ち上げられた海獣の最後は、あまりにあっけないものだった。
『やった!』
(うむ。)
灰になったデクトキングが、海に落ちる。そこはかとなくいい香りがする。
「・・・撃て。」
「は?何が?」
「あの巨人を撃て!命令だ、今すぐ!」
「何故ですか?あれは海獣を倒してくれたではありませんか!」
「いいから撃て!次にあの力をこちらに向けないとも限らんのだぞ!」
(なにやら、穏やかじゃない雰囲気だな。)
『どうする、そっちがその気ならこっちも。』
(やめろ!人間に手を出すな。何があろうと。)
『冗談だよ。』
砲が向けられるよりも先に、スペリオンは光となって消えていった。
☆
「さっきは冗談に聞こえなかった。」
「まあ半分はマジで頭に来てたからな。」
先ほどまでの痛みは消え失せて、元のガイとアキラに戻った二人。港にも先ほどのデクトキングの灰が降り注いできている。
「おーい!ガイー!アキラー!」
「無事でしたのね!いなくなったって聞いて心配していましたわ!」
「せやから心配ないゆーたやん。この二人やったら平気やって。」
「すっかり二人組扱いか。」
「結局、あの大ダコはなんだったんだ?」
「少なくとも自然から生まれた生物ではない。手足や腹のそれぞれの機能が色んな生物のキメラのようだった。」
たしかに、タコも貝の仲間ではあるが、そこにアノマロカリスやロブスターが組み込まれているというのは不自然だ。タコを起点に、様々な形に先祖返りした、というケースも考えられなくもないが、あんな形質が必要になる環境など、ありはしない。よって自然から生まれる姿ではない。
「そんなことは火を見るより明らかだろ。問題は、誰がどんな目的を持ってやったのか、だろ?」
「いや、それも違う。」
「クリン?今までどこ行っとったん?」
「ずっと宿で待ってたんだよ!」
「そうだったな、悪い悪い。それで、なにが違うんだ?」
「俺たちの考えるべき問題は、どうやって帰るかって方法だろ?誰もオオダコの正体を突き止めろなんて頼んでないぞ。」
「確かに。」
困ったことに、ヴィクトール商社の船が沢山やってきて、ここら一帯を海上封鎖してしまった。これでは海路で帰る計画がパァだ。
「本来の予定なら、ここから西のサメルの街に着く予定だったんだな。」
「どうする?山道で西行くの?」
「・・・いっそ南に行って、そこからまた海に出るっていうのはどうだ?」
「また海?もう大タコに襲われるのは勘弁だよ!」
「さすがにあんな海獣はもういないと思うけど、海に出ていいことひとっつも無いよな現状。」
「・・・わかった、海はよそう。これからは陸路で西へ向かおう。」
どうにもこうにも、旅は上手くいかない。不安や災難にみまわれるが、旅が終われば思い出と土産話に変わる。
「まっ、これからだなこれから。」
「アキラ前向き。」
「前向いてなきゃ歩けないだろ。」
☆
「おのれ・・・まさかあの巨人が再び俺の前に現れるとは・・・。」
ところ変わって、ヴィクトール商社は社長の私室。ヴィクトール社長のこれまでの功績を称える品々や、大陸が一つと超大陸が一つ描かれた地球儀、高そうな調度品が揃えられたその部屋の中で、当の本人が椅子に腰かけて不満の言葉を宙に投げている。
「まさか・・・過ぎ去った悪夢とばかり思っていたが、なぜ今になってなのだ・・・。」
長く伸びた髭を指でさすりながら、厳しい表情で天井を見上げる。そして、『あの日』を思い出す。
「なにか、お困りのようだね?」
「! お前か、ベノム!」
ヴィクトール一人しかいないはずの部屋に、別の声が響く。見れば、その声の主は応接テーブルに座って勝手に酒を飲んでいた。その表情はフードに隠れて見えない。
「お前に会って、いやこの世界に来て20余年経った。おかげで俺のサクセスストーリーは順調だと言っていいものだった、はずなのに。」
「まさかの再会だな。ハルマゲドンの、その中心に立つ者の。」
「また、俺の人生を滅茶苦茶にするつもりなのなら、手を打たなければならない。どうか、手を貸してくれないか友よ。」
「勿論だ。今しばらくは様子を窺って、機を見て手を打とうではないか。」
「やってくれるか?」
「今そう言った。」
「そうか、そうか!なにか入用の物はないか?金か?なんでもいいぞ!」
「いや結構。自分でやるのが好きなんでね。なにかあったらまた来よう。それまでに、『あの準備』を進めておいてくれ。」
「ああわかった。感謝する、ベノム。」
決して歴史の表舞台に立たないもの、そういうものが、歴史のターニングポイントには現れる。目には見えない糸を操り、爪を研ぐ。そんな影が闇から浮上したことを知るものはいない。
「ん?」
「どうした、クリン?腹でも痛いのか?」
「違う、なんかこのクリスタルが・・・。」
「何それ、真っ黒だな。」
「・・・なんでもない。」
今はまだ、予兆を見せているだけ。
書き出しはこんなもんだろうか。一文書いてガイはペンを止めた。さて何から書いたものか。そもそも誰が読むことを想定しているのかにもよるが、とりあえず自分の身に何かがあった場合を考えた。
『遭難からはや2か月ほど経って、皆の顔つきもどことなく変わってきた。』
「ダメですの~!レオナルドを置いていきたくありませんの~!」
「誰も置いていくとは言っとらんだろ!」
『例えば気の強そうなお嬢さんが、妙に駄々っ子になったり。』
港でひと悶着あった。曰く、レオナルドがデカすぎて船が重量オーバーになりかねないという。サウリアからこの大陸に来るまで乗っていた・・・正確には途中で難破した船は、もっと大きくてエンジンのついた近代的な船だったが、ここにあるのは帆船しかない。レオナルドを乗せれば最悪沈没、よくて文字通り亀の歩になってしまう。
「だからこうして筏を組んで別に乗せようって言うんだろ!
「何が悲しくて遭難したような準備をしなくちゃいけないのか。」
「竹がいっぱいあってよかったね。」
そういうわけで、レオナルドを乗せて帆船で引っ張っていける筏を用意している。全員工作のスキルが上がりつつある。
「大人しくしているんですよレオナルドー。」
『グゥ。』
「アイツも頭良くなってってるよな。」
「最近はオレらの言うことも聞いてくれてるし。」
推測の域を出ないが、体が大きい分脳もデカくて賢いのかもしれない。そういえば元は遺伝子改造を施された実験体だという事を考えると、そういう学習脳の処置を施されているとも考えられる。
まあ、従順なうちは問題ないだろう。
『グゥーグゥー。』
「それはイカダだから食べてはいけませんわよ!」
それとも考えすぎだったか?
「かわいい食いしん坊さんじゃないか。」
「かわいいか?」
「かわいいだろう。」
「かわいいですわ!」
「「ねー。」」
☆
そんなこんなで、無事に船は出航した。風に扇がれて、たっぷり1週間は潮の香りを堪能することになる。
「そんなにかかるのか。」
「ただの帆船だしな。食糧や水の問題はなさそうだけど。」
ビタミンは足りている。壊血症の心配はない。
「ぼぇええ・・・。」
「もう酔ったのか。」
必要なのは酔い止めの方だった。
「みんな情けないなー。」
「サリアは平気そうだな。」
「海運商の家やからね。」
「先生も平気そうだな。」
「密輸船に密航したときよりは穏やかなもんだ。」
「難破したとはいえ、サウリアからの船のほうが揺れは穏やかだったな。」
「波の強さも向こうの方が上だったと思うよ。」
やはり根本的な技術の差だろうか。むしろあの船の技術力の方が異常だったのだろう。壊れたけど。
(自然現象、不可視の電磁波の影響があったんだろうか。)
信仰の強い世界観なら、それを『天罰』と表現するだろうが、皆そういう風には捉えていないようだ。信仰に盲目ではないらしい。
「で、お前はなにをやっとるんだ。」
「この揺れの中なら、バランス感覚を鍛える訓練になるかもしれない。と、小遣い稼ぎ。」
「強かね。」
一方アキラは船員のアルバイトをしていた。大きな樽を運んだり、マストを整理したり、力仕事には事欠かない。
「アキラっていつもこういうのしてたの?」
「この世界来てこっち、大体そうだな。適当に仕事しながら旅してた。」
「定住しようとかは思わへんかったん?」
「こっちのが性に合ってる。」
家のタガから外れたアキラはとても生き生きとしていた。
「自由の身、ですのね。」
「あらシャロン、羨ましいのかしら?」
「べつにそういうわけではないわ。」
「たまに外で遊ぶぐらい許されるんじゃない?今が遊びの状況なのかは微妙だけど。」
「ははは、まあ気は抜けないわね。」
そうは言うが、ゴールにアテが見えてきたことで皆に余裕が生まれてきていた。余裕が生まれれば、旅を楽しむこともできる。
「おーい兄ちゃん、こっち手伝ってくれー。」
「はーい、じゃあまた後でな。」
「がんばってー。アタシたちも船室に戻るかしら。」
「そやね、みんなグロッキーになっとるけど。」
「シャロンも平気?」
「風に当たっていたらなんともないわ。うぇっぷ・・・。」
「やっぱダメじゃん。」
「あはは、もうちょっと外おろか。」
胃から空気が抜けてきた。シャロンはゲイルに背中をさすられながら、水平線に目をやった。陽の光を反射して、キラキラと輝いている。
「綺麗ですわね・・・。」
「せやなー、ん?」
サリアは、遥か遠方の海面がにわかに泡立つのが見えた。
「なんやろ、あれ?」
「海底からガスでも漏れてるんじゃないの?」
「ひょっとして、海底火山?」
「もう噴火はイヤですわよ?」
「そんなに近くも無いし、平気でしょう。こっちは動いているんだし。」
だから気にも留めないことにした。やがて泡が弾けるように、記憶からも霧散した。
船旅はまだまだ長い。その早々に出くわしたこれは、吉兆か凶兆かと言えば凶の方だった。
☆
「そういえば、この船って何を運んでるんだろ。」
3日目の昼食の席で、ふとガイが口にした。
「あれ、これってフェリーじゃないの?」
「ううん、貨物船やで。さっきも停泊して荷物積んどったやろ?あれトウモロコシや。」
「穀物か。今食べてるこれもトウモロコシの乾パンだな。」
「それに、このオレンジも。シロップ漬けの缶詰みたい。」
なんとも水が欲しくなる食事だが、副菜にバリエーションがあって飽きは来ない。
「人間というのは陸の生き物だとほとほと感じさせられるよ。」
「そう?」
「水中で息できないし、漂流したら溺れ死ぬし、海には危険が多い。」
「ひょっとしてガイ泳げない?」
「・・・決して泳げないわけではないぞ。」
「苦手なんだな。」
「そういえば、さっき停泊してた時の話なんだけど。」
「うん?」
「なんかここ最近、この辺の海で沈没事件が多発してるらしいよ。」
「事件?事故じゃなくて?」
「犯人がもうわかっとるからから事件なんやって。」
「マジ?」
「ゴホンゴホン。」
「お?なにアキラ。」
「お前ら、そういう話はせめて部屋戻ってからしろ。」
「なんで?」
「ここがその海の上だからだろ。」
食堂で食中毒の話なんかされたくないだろう?ともかく、場所を移して話は続けられる。
「で、何者なんだ?」
「噂によると、デビルフィッシュの仕業やってさ。」
「デビルフィッシュ?」
つまりタコである。
「なんでも、触手から毒を出して大きな獲物をも仕留めるんやて。だから悪魔の魚。」
「なるほど、そりゃ煮ても焼いても食えなさそうだ。」
「でもレオナルドなら構わず食べてしまいそうですわ。」
「あー、バカだからなアイツ。」
目の前にあるものにはなんでも噛みつくし、咀嚼できるならなんでも胃に収めてしまう。餌やりをするのもコツがいる。
「それにしても、そういうの話してると、高確率で巻き込まれるんだよなぁ。悪い予感ほどよくあたるっていうか。」
「そうそう、口は災いの門っていうか。」
「コトダマというやつですわね。」
「でもまさか俺たちが巻き込まれるわけないわな?」
「ですわよねー、そういえば初日に妙に海が泡立っていたのを見ましたが、きっと関係ありませんわよね!」
「ないない、今朝エサやりに行ったときもなんか海が泡立ってたのもきっと気のせいや。」
「「「ワーッハッハッハ!」」」
☆
半日後、船は傾いた状態で最寄りの港に到着した。
「悪い予感ほどよくあたるっていうか。」
「そうそう、口は災いの門っていうか。」
「コトダマというやつですわね。」
「「「一体何者の仕業なんだ???」」」
「お前らのせいだろ。」
「断じて違う、たぶん。」
無事に陸まで辿り着けたのは幸いとしか言いようがないだろう。積み荷はほとんど落としてしまったようだが、命には代えられない。
「でも大損やで。なんとかしてあげられへんかな。」
「サリアが気にすることじゃないだろ。」
「同じ商売人としては、こういう時こそ助け合いやで。」
「そんな聖人じゃあるまいし。」
「ちょっとガイ。」
「お前の言いたいことはわかる、が無理な話だぞ。」
「まだ何も言ってないぞ。」
「商売人でも聖人でもないけど、人として困ってる人は助けたい。」
アキラの言葉に裏はない。いたって善意から発せられている。
「そんなこと言ってる場合か?俺たちの命が優先されるべきだろ?」
「おおクリン生きてたか。」
「さっき点呼とったろ・・・ここからは陸路で行くって手はないのか?」
「ふむ、まあ無理ではない。ちょっと遠回りになるが、無理ではない。」
「なんで歯切れが悪いのセンセ?」
「ここからだと山道しかないからな。レオナルドの足も遅くなる。」
「山か・・・。」
むしろ、山を迂回するための海路だったというのに、これでは元の木阿弥だ。
(海の異変を解決しない限りは、海路は使えないか。)
(スペリオンならできないのか?)
(無理な話って言ったろ。)
そもそも範囲が『海』という時点で広すぎる。地点に目印も無い、上からじゃ海中の様子も見えないとあっては、骨が折れるどころか砕け散る。
せめて、何か手掛かりがあれば。
「よし、じゃあまずは壊れた船から調べていこうぜ。」
「調べるって、何を?」
「捜査の基本は足だ。」
「おっ、なんだなんだ。」
「探偵ですわね!」
「そういうわけで先生、何を調べたらいいと思う?」
「いきなり人に聞くなよ・・・そうだな、船を調べるものと、聞き込みをするものとで分けたらいいんじゃないか?アキラは船員をやっていたし船を調べて、サリアは商売人なら船員から話を聞けるかもしれない。」
「よし!じゃあ手分けしていこう!」
「・・・それって俺も行くのか?」
「山と海どっちがいい?」
「・・・海かな。」
☆
「ふーん、岩とかにぶつかって壊れたって感じじゃないなこれは。」
船体は外から奥の方へ、というよりは下方向に引っ張られて壊れたという風に見える。だが船体が沈む前に破られるだろうか?どうにも単純なパワー以外の力がかかったように見えるとアキラは踏んだ。
アキラと同行しているのは、ドロシーとゲイル、そしてシャロン。シャロンはレオナルドの様子を見に来ただけだが。
「たしか触手から毒が出るとか言ってなかったっけ。」
「なるほど、その毒のせいか。」
「あんまり直接触りたくないわね・・・。」
海にも毒を持った生物は多い。だが、毒というのは大抵弱い生物が自衛のために持つというパターンが多い。船を襲うために毒を使うというのは、相当頭がいい生物なんだろうか。
「噂通りデビルフィッシュがその正体なら、一体どんな奴なんだろう?」
「毒以外にどんな武器を持っているのかしら?」
「そもそも、一体何が目的だったんだ?」
必要な情報が増えてきた。そういうわけで船員に突撃インタビューを敢行した。
「デビルフィッシュ?ああ、『デクト』のことか。」
「『デクト』?」
「海底にすんでるタコの仲間さ。動くものにはなんだろうと咬み付く、毒のある狂暴なタコさ。」
「うーん、悪魔的。」
船を直す工員の1人が言った。
「でもデクトが船を沈めるなんてありえないぜ。10cmぐらいしかないんだぞ。」
「ちっちぇ。」
「被害と言えば漁の網にたまにかかったやつに、油断してたら噛みつかれるぐらいなもんだ。」
「つまり、どういうことだって?」
「ただのデビルフィッシュじゃないんだろう。」
「すんごいデカいんでしょうね。」
デビルフィッシュ以外の何者かの仕業とは考えない。
「もう少し探したら、シャロンを迎えに行きましょう。」
「レオナルドがなにか知っているかもしれない。」
そういえば、現場に一番近いところにいたのはレオナルドだった。
「ゲイルー!ゲイル来てー!」
「はいはい、なによ一体?」
「レオナルドの体に変なものがついてますのよー!」
「変なもの?」
それは、黒くて細い触手のようなもの。おそらくはデビルフィッシュ、デクトの脚だろう。それがレオナルドの口の周りについている。
「食ったなテメェ。」
『グゥ。』
「そんなものを食べたらお腹を壊しますわよ!」
「でもこれでハッキリしたわね。事件の傍には必ずデビルフィッシュがいる。」
毒を喰らったはずなのに、当の本人はケロリとしている。よっぽど人間なんかよりも強靭な胃袋を持っているらしい。
「他に何か変なもの食ってないだろうな?ちょっと口開けてみろ。」
「ええ、ほらレオナルド、アーンして。」
『グォッゴゴ。』
ガポッとレオナルドが口を開くと、アキラはその中を覗き込む。生臭いニオイがこもっている。口の中に怪しい物は・・・。
「あっ、なんだこれ・・・コーン?」
「トウモロコシ?積み荷の?」
「・・・まさか、お前。」
『グゥグゥ。』
「・・・いやいやそんなまさか!レオナルドにはちゃんとエサをあげていましたわよ!きっとたまたま流れてきたものが口に入っただけですわ!」
にわかに身内に犯人説が出てきてしまった。もっとも、沈没事件は以前から起きていたので、おそらくシャロンの言う通りたまたまだろうが。
「まあ、なんだ。このことは内密にしておこう。」
「レオナルドはコーンが好物なんですわね。今度用意してあげますわ。」
『グゥグゥ!』
「あ、喜んでる?」
「喜んでますわ!かわいいですわね!」
デビルフィッシュにもこれぐらいの聞き分けのよさと、可愛げがあればすみわけが出来たろうか。
☆
さて、街で聞き込みを始めたガイたちであったは、海鮮焼きの屋台に舌鼓をうっていた。
「うまい。」
「うまいなぁ。」
「って、食っとる場合やないやろ!」
何も食べ歩きがしたかったわけではない。聞き込みをしようとしたら屋台に引きずられてしまったのだ。元々船の乗客に向けた屋台をやっていたので、商魂に負けたといったところだ。
「海で獲れたものがそのまま焼かれてるから新鮮でうまい。」
「サザエのつぼ焼きがこんなに大きい・・・。」
「出荷されずに余った分をこっちに回してんねんな。」
どうもここ最近は、漁が大漁続きで屋台にも大物が回ってきて繁盛しているとのこと。
「それ海の異変と関係あるのか?」
「クリン何個食ってんだよ。」
「正直一番食文化をエンジョイしてるよな。」
「やーい文明人ー。」
「それは褒めてるのか貶してるのか。」
ここ最近というのが、海の異変と前後しているのなら無関係ではあるまい。
「疑問なのは、貨物船が何者かに襲われているのに、漁船は無事だという点かな?」
「お、パイル鋭いな。確かに、船は船でも、大型船ばかりが狙われてるってことか。」
「モグモグ、通航量というか、海にいる確率は漁船の方が多いよね?」
「まあ、この町は元々漁港の街だったのを、貨物船の中継地にしてるってところだし、漁船の方がまだ多いだろうね。」
「背の高い建物もそんなにないね。」
波止場近くに、貨物船の商会のものらしき建物ならある。中は事務所だった。
「漁船以外が被害を受けてるってことは、じゃあ漁師たちが犯人?」
「そういうの、街中で言うなよ。それに多分違う。商会のおかげで人の出入りがあって、村としてはむしろプラスのはずだからな。」
「どうだろう、実は恨み買ってたりとか?」
「今まさに喧嘩売ってるところなんだよなぁ、俺たちが。」
現在進行形で通りかかる人から変な目で見られている。
「おい兄ちゃんたち、オレたちの商売になんか文句あるのか?」
「いや、決してそんなつもりは。」
「まったく、ただでさえお上の締め付けがキツイっていうのに、外から来た連中は問題ばかり起こしやがる。」
「なんだ、ここってそんなに税金とられるの?」
「おうよ、特にここ数年上がりっぱなしだ。おかげでどんなに働いても全部吸い上げられちまう。」
「数年前ねぇ。ちなみに、貨物船が来るようになったのは?」
「数年前だな。さあ仕事だ仕事。」
まるでRPGのNPCのように情報だけよこして漁師のおじさんは去っていった。
「なんでどこもかしこも外の人間と軋轢を生んでるのかね。」
「これがホントの貿易摩擦っちゅーやつやな。」
「座布団一枚。」
国が金を集めてるということは、戦争準備でもしているのかという推測はさておき。
「税金と商会に、関係があるのかな?」
「商会が政府と繋がってるとかだろ。」
「利益が見込めるから、国があげて貿易をしていると考えれば筋は通るね。」
「なんや、国が指導しとんのか。あんま自由な貿易とちゃうねんな。」
「それで売るものがトウモロコシか。」
ウラが見えてきた。貿易で利益を上げて、富国強兵を図る、実にシンプルな実態だ。でもそれが今回の事件とどう関係しているのか?
「関係なくないか?」
「なくはなくないんじゃないかな?」
「俺も正直ないと思う。」
「ガイもそう思う?理由は?」
「・・・ない。勘だ。」
「考えたくなくなっただけだろ。」
「うん、そんなことより焼きトウモロコシが食べたい。」
「あっ、それサンセー。」
「結局食い意地かよ。」
「いいじゃん、一回食ってみようぜその・・・どこ産のトウモロコシだったっけ?」
「ゴルムやな、ジーナスより北で、もっと行くとウーシアに入るその手前。ノメルに負けず劣らずの農業大国やで。」
「そうか、じゃあそのゴルム産とやらを食してみようじゃないか。」
☆
「それでお前ら、散々食べ歩きだけしてきたのか。」
「センセたちの分もあるよ。」
「あら、甘いのね。」
「たしかにうまい・・・じゃなくて。」
集合場所の広場に、手土産を持ってガイたちは戻ってくると、デュランとカルマを丸め込んだ。
「昔旅をしていた頃に食べたものより、随分甘くなってるんだな。」
「糖度が高くて、生産性の高いように品種改良されてるんだな。」
「やはり、なにかの陰謀が?」
「陰謀?何の話?」
「ジーナスがゴルムを抱き込んで、産業革命を起こして世界を牛耳るんだろう、ってガイが。」
「そこまでは言ってない。」
「うっかり聞かれたら消されてしまいそうな話だな。」
あくまでシナリオのひとつとしてあり得そうというだけ。本筋には関わらない。
「ただいまー、って何食ってんだお前ら。焼きモロコシ?」
「あー、もう帰って来やがったか。」
「食いたきゃ自分で買ってこいってワケか。そっちは何か収穫あったか?」
「収穫というか味わったというか。」
「おい。」
全員合流し、情報交換を行った。
「品種改良されたトウモロコシに、未知の怪物、まさか!」
「どしたんアキラ?」
「品種改良されたトウモロコシを食べた生き物が、怪物に突然変異したとか!」
「遺伝子組み換え食品と、生物の突然変異には因果関係ねえよ。」
「でも、積み荷のトウモロコシが狙いってのは考えられるわね。それなら、貨物船ばかり狙われる理由になる。」
「じゃあそいつはナニモノなんだ?デビルフィッシュって呼ばれてるデクトってタコは、そんなに大きくないらしいし。」
「だからそいつが突然変異で!」
「突然変異便利すぎだろ。」
そんな食べただけで巨大化する食べ物があったら、この星は巨人の星になるっての。
「まあ、これだけ問題になっているなら、商会の方も何かしら手を打つだろうな。」
「明日大きな調査船が来るんだってさ。」
「じゃあ、もう任せちゃって休もうぜ。」
「そうだな、これ以上我々に出来ることはないだろうし。」
我々の力で解決するにしても、もう得られる情報はない。一晩じっくり寝かせて、明日考えてみるのがいいだろう。
「けど、ナンセンスですわね、突然変異なんて。」
「なにおう、ありえなくはないだろう。」
「せやせや、まさかまた恐竜みたいなんが出てくるとは思えへんで。」
「そう何回も遭遇してたまるか。いくら毒を持っていようと、個々の力は微々たるものだ。」
そうしてまたフラグを建てて夜を迎え、翌日の昼。腹の下に響く轟音、建物が崩れる振動の中でアキラは目が覚めた。
「なんだぁ!?」
「起きろみんなー!敵襲だぞ!」
「敵襲?!」
宿の外はまさに火事場のような騒ぎ。
「砲撃?!どこからだ!」
「海!」
騒動の元のひとつは海の上に浮かんでいる。そしてもうひとつが街を蹂躙している形になっている。
「タコ?いや、貝?」
大きな巻貝が、うにょうにょと動く足で蠢いている。
☆
時間は戻って朝。
港のすぐ沖には、でっかいお船が浮かんでいた。
「軍艦かあれ?」
船体に装甲が取り付けられ、大砲が並んでいる。
「あれはジーナスの船?」
「旗がそうだな。」
「あんなもの見せつけて、国際問題にならないのかな?」
「牽制の意味もあるんじゃないか。それと試運転と。」
「近くまでいってみようぜ!」
大げさな武装からは威圧感を醸し出す。一見したところ帆船でもない。ひとつ先のテクノロジーが使われているんだろう。それはまあさておき。
「なんかあの旗のマーク、見覚えがあるような?」
「見覚えがあるもなにも、ヴィクトール商社じゃないのかあれ。」
サウリア大陸から乗り合わせた船が沈んだ、あのヴィクトール商社である。あまりいい気分しないというか、嫌な予感がする。
「というか、国じゃなくて、商社の所属の軍艦?」
「ヴィクトールは商事だけやなくて、軍事や技術にも手を伸ばしてるから。」
「そのうち死の商人にでもなりそうだな。」
既にヴィクトール商会は、ジーナスだけにとどまらず、シアー大陸全体にまで手を広げているという。世界有数の一大勢力に王手がかかっている状態だ。一方、艦のブリッジでは、対策会議が行われていた。
「此度の貨物船難破事件、一刻も早い解決のため、我々も協力を惜しまないところだ。」
「ヴィクトール商社の、それもヴィクトール社長直々の支援、まことにありがたい。」
そこにいるのはそう、相も変わらずでっぷり腹に一物抱え、手にはネジを摘まんだ、カイゼル髭のおっさん。マシュー・ヴィクトール社長である。
「まさかヴィクトール商社から、こんな慈善事業の申し出があるとは夢にも思いませんでした。」
「いやいや、困った時は助け合いと相場が決まっておりますからな。」
(新しい船を売り込むチャンスだな。タダより高いものはない。サウリアだけでなく、地中海にも我が社の船を浮かせる時だ。)
情けは人のためならず、とはいうもののウラも下心もあるのが人間というもの。ただそれを表に出さないだけで、こうも丸く収まるのだ。
「では、どのように解決なさるおつもりで?」
「うむ、まずはだな・・・。」
「おっ、なんか始まったぞ。」
「すっかり見物人ムードだな。」
外では屋台がまた繁盛している。
「複数隻の船で、陣形を組んでいるのかしら?」
「陣形というには距離が開き過ぎだな。それよりも、あの網を使うんだろう。」
「なるほど、電気ショック漁か。それなら簡単に燻りだせるな。」
「でもそんな電源どっから用意するんだろ?」
「お抱えのゼノンがいるのか?」
「普通にジェネレーター使うんじゃね。発電機は積んでるようだし。」
メルカでは神秘とされている法術が、今まさに目の前で手軽な道具として扱われようとしている。
ここが未来の地球だとすると、どうすれば電気を使えるのかすぐに調べられたとしてもおかしい話ではないが、それでもガイには歪に映った。一つの大きな大陸なのに、なぜこうも思想に違いが出るのか。ヴィクトールがすごいのか、それとも、ゼノンが異常なのか。
(ヴィクトール商社によって、技術の目覚ましい発展が成されているとすると、それはつまり・・・。)
いずれにせよ、この件は大きな火種になりそうだ。下手に燃え広がらぬことを切に願う。
そうこうしている間に、船が動き出した。正体不明の敵を探しに行くらしい。
「じゃ、あとは任せて帰ろうぜ。」
「結局オレらが探索した意味無かったなー。」
「でも、これで解決ならそれに越したことはないわな。」
「そーねー、わたしたちはゆっくりお茶でも飲んで待ってましょう。」
「昼過ぎには帰ってくるかな。」
と、フラグを外野から散々建てまくって昼のシーンに繋がるのだ。
☆
先ほどまで海に浮かんでいた船が、今は町の瓦礫に横たわっている。火の手から濃い潮のニオイが漂ってくる。
「消火しろー!」
「バカ野郎逃げるぞ!」
さっきまで呑気な見物人だった町が、混沌の火事場となり果てた。対岸の火事、どこか他人事であった災厄が、文字通り降ってきたのだから。新式の軍艦から放たれる砲火が、容赦なく町を焼く。
「で、あれはなんだよ!」
「わからん!突然海からやってきた!」
勿論、連中はなにも戦争がしたくてそうしているわけではない。海から現れた災厄を討つためである。
タコだか貝だか、ようわからん。たとえるなら、アンモナイトのような巻貝から、アノマロカリスのような体が飛び出し、その顔の下からタコの触手が4本ずつ2対生えており、あたかも王様のヒゲのように見える。
「あれが海のおじさんの言ってた『デクト』の王様なら、『デクトキング』ってところか。」
「そのまんまだな。てかもっと小さいタコのはずだったろ。なんであんな姿の、それも巨大になってんだ!」
「きっと『突然変異』ですわ!」
「便利な言葉ねー、突然変異。」
だがデクトキングの姿は、到底自然から生まれるような『自然体』ではない。様々な古生物の合体したいような、ちぐはぐな恰好をしている。悪意ある何者かが、人為的に生み出したのでないとするならば、突然変異という他なかろう。それが何故巨大化しているのかは不明だが。
「とにかく、今はみんな合流するんだ。ここにいないやつらは?」
「港の方に行ったっきり!」
「えっと、ガイとサリアと、ドロシーとカルマと、あと先生?」
「レオナルドも放っておけませんわ!パイルがエサをあげに行ってますわ!」
「みんなバラけすぎだ。」
状況はよろしくない。散り散りになってこの混乱の中を探し回るのは愚行。特にアキラは、ガイと一刻も早く合流しなくてはならない。
「・・・よし、ゲイルはまた纏で避難指示を出してくれ。そこを合流地点とする。」
「わかったわ!」
「俺一人で全員を探しに行くのは厳しい・・・たぶんあっちも、レオナルドとパイルを迎えに分かれてると思う。」
「ならわたしがレオナルドの方に行きますわ!」
「危険だぞ?」
「忘れられているかもしれませんけど、わたしゼノンですわ!」
「そうか、じゃあクリンもついていってやってくれ。1人だけだと何かあった時困る。」
「ここに誰か戻ってくるかもしれないが、誰もいないと困るんじゃないか?」
「そうか、じゃあクリンはここで待機を頼む。シャロン、気を付けて。」
「平気ですわ!」
手際よく指示を飛ばせたところで、アキラもまた走り出す。
☆
「・・・ツマランな、祭りの花火というにはいささか派手さに欠ける。」
港町から外れた高台の上で、焼きトウモロコシを持って、目深にフードを被った男が呟く。目下ではデクトキングによる蹂躙が行われているが、それを見て心底つまらなさそうに、トウモロコシを一口齧って捨てた。
「あの男の貪欲さもなかなかだが、すべてを焼き尽くすほどの煩悩の炎には程遠いな。」
「いっそ自分を燃やしてみればいいんじゃないか『創造者』?」
クリエイターと呼ばれたその男が右手を掲げると、それが自身の頭を打ち抜こうとした弾丸を跳ね返した。そうすると、面白さ半分、呆れ半分といった具合にヘビのような目を攻撃の主に向ける。
「それならもう108度は試したかな。結果は御覧の通りだよ、『混沌の子供』、いやさケイよ。」
「なら109回目は俺の手で下してやる、ベノム。」
「遠慮しておく。今はもっと、人生を楽しみたい。」
「生きているとも死んでいるとも言えないやつが、そんな権利あると思う?」
「それはお互い様だろう?」
カッカッカと牙の生えた口が笑い、ペロリと細い舌を見せる。
「私に言わせてもらえば、あるかどうかすらわからないモノを探しているお前たちも大概だがな。」
「黙れ、少なくとも俺は誰にも迷惑かけてない。」
「私だってそうさ、哀れな人間の願いを叶えてあげているだけだ。私はその様子を見て楽しんでいるだけ。」
その瞬間、町の一角に閃光が迸る。
「そら、このショーを面白くしてくれるヒーローの登場だ。」
「スペリオン・・・。」
ベノムは拍手でもって迎え、ケイは苦々しい表情で見つめた。悔しいことに、この展開はベノムの望む通りのものだったから。
☆
「あっ、スペリオンだ!」
「来てくれたか!」
「ガイさんとアキラはどこに行きましたの?」
「あの2人なら大丈夫だろう、避難するぞ!」
多くの人間はその姿に目を奪われているが、すぐに現世に意識を取り戻すと避難が再開された。
『速攻で片づける!』
(無論だ、タコはあんまり好きじゃない)
『奇遇だな、俺もだ。』
首尾よくガイと合流できたアキラは、スペリオンへと合体変身を遂げた。今日も赤い体躯が燦燦と輝く。
『って、何やってんだアイツは?』
(どうやら倉庫を漁っているようだが。)
タコとヤドカリの相の子が、もぞもぞと建物の一つに執着している。なんだなんだとその背負った貝を引っ張ってみれば、何が目的だったのかは一目瞭然だった。
『この黄色いの・・・トウモロコシか?』
(どうやら粉末にして、バイオマスにするところのもののようだな。思ってるより進んでるんだな。)
『マス?魚、のエサ?』
(違う、バイオ燃料のことだ。)
炭水化物も組成が違えばエタノールになる。まさか化石燃料よりも先にバイオ燃料の研究が行われているとはガイも思わなんだ。
ともかく、どうやらデクトキングの狙いはコーンだとわかった。貨物船を襲っていたのも、やはり積み荷のコーンが狙いだったのだ。
『じゃあなにか、コイツはトウモロコシ食ってこんなにデカくなったのか?』
(ああ、だがただのデブとは違うぞ。)
コイツは動けるデブだ。触手を器用に使って体勢を立て直すと、殻の中から大きなハサミが飛び出してくる。
『今度はロブスターか!』
(挟まれると怖いな。)
『そんなにトロくねえ!いくぞ!』
左右非対称な歪な形の威圧感にも怯まず、スペリオンは大地を蹴って距離を詰める。図体がデカいだけでは、アキラには木偶の坊に過ぎない。関節部分を手刀で痛めつける。
『グボボボボボボ』
『うっ、邪魔な触手め!』
(切り払え、アームドフィンだ!)
『よぉし!』
腕から赤いクリスタルの刃が伸びると、纏わりつく触手を切り裂く。一歩引いて様子を窺うと、すぐさま触手は生え変わっていく。
『なんて再生力だ、キリがないぞ。』
(なら光波熱線で焼いてしまえばいい。)
『熱線の出し方なんてイメージできるかよ!』
(なら口から出してもいいんだぞ?)
『それはもっと嫌だな、ビジュアル的に。』
(柔軟性のないヤツめ。)
『タコには負けるわな。』
丹田で気力を練り込んで、呼吸と共に吐き出す。一緒に口から洩れてしまいそうなのを抑えて、掌に集中する。
『はぁああああああ・・・。』
(それ、名前は?)
『名前?えっと・・・気功・・・ブレイズ!気功ブレイズ!』
円を描いた両手を、胸の前で花の形にして押し出す。緩やかな勢いながら熱い炎が噴き出して、デクトキングの触手をこんがりと焼いていく。
(・・・いいんじゃない?)
『名前に意味あんのかよ!』
(まあ、あるっちゃあるよ。)
干物にしてもあまりおいしくなさそうな触手が、ぶすぶすと煙を上げ始めていた。
「よーし!いけいけー!!」
「熱気がすごいな・・・。」
「このままいけば・・・ってあれは!」
それまで静観していた戦艦が火を噴いた。だがその標的は、海獣ではない。
『グワーッ!な、なんだ?!』
(こっち撃ってきやがった!)
『なんでだよ!明らかにヒロイックな姿してるだろ!』
(彼らにはどっちも同じように見えてるんだろ。)
狙ってなのか、それとも流れ弾なのか、どちらにせよ思わぬ一撃を受けたスペリオンはたじろいで技を中断させられる。そうするとどうなるか。
『うぬっ、小癪な!』
(海へ引き込む気か!)
デクトキングは再び出したハサミでスペリオンを掴むと、勢いよく海へとダイブする。海はデクトキングのフィールドだ。
『ぐぉおおお・・・潰される・・・身動きできない・・・っ!』
(まずいな・・・。)
水中に骨が軋む音が響く。両腕ごと縛られている現状では、抵抗することもままならぬ。
『何か手はないのかよ!』
(髪を使え!)
『髪?!』
確かにマスクに収まりきらない髪が光を放っているが、そんなものを使えと言われても熱線を出すよりもイメージ出来ない。
(そのまま伸ばせばいいんだよ!)
『ええい、伸びろ!』
後頭部からレーザーが発せられ、ハサミの付け根を貫く。いきなりの奇襲に、デクトキングも狼狽える。
『ホントに出た・・・。』
(オプティックファイバーだ、覚えとけ。)
光のタテガミ。思ったよりも自在に動いてくれるが、使い過ぎるとハゲが心配になる。
ともあれ危機を脱したがのもつかの間、デクトキングは口から黒いもやを吐き出して目くらまししてきた。タコというからにはおそらくスミだろう。
『うっぷ!気色悪い!』
(だが今ので見失ったぞ。)
スペリオンはすかさず腕を大きく回して水流を作り、スミ洗い流したが、その隙にデクトキングの姿は消え失せていた。海底にあの巨体が隠れられる岩陰などはない。
(だがタコは岩に擬態する能力も持っている。岩のどれかに化けたのかもしれない。)
『アイツの背中も巻貝みたいで岩っぽかったからな。どれだ・・・?』
敵のホームグラウンドで長居はしたくないが、ここで逃がすわけにもいかない。
(・・・。)
『・・・。』
(・・・で?)
『なんか手立てはないのかよ?』
(ない。)
『とにかく、これじゃあ埒があかん。適当に目星をつけて吹き飛ばしてやる!そこだぁ!』
再び、気功ブレイズを放ち岩を砕く。目当ては外れたが、岩の一つが急速に逃げだした。デクトキングの背負っていた巻貝である。
『いやがったな、切り刻んでサシミにしてやるぞ!』
手に光の刃を出現させ、容赦なく突き立てる。しかしそれは意外なほどに手ごたえのない物だった。
『なにっ?!これは!』
(殻だけ?)
文字通りのもぬけの殻。返ってくるのは空虚な反響音だけ。直後、背中に嫌な予感を感じる。
(後ろだ!)
『なにっ!?うぉおお!』
誤算だった。タコは思いの外頭がいいが、まさか身代わりの術を使うとは思わなかった。背中にビッタリとくっつかれ、両肩にアノマロカリスのような口が突き刺さる。
『ぐっ・・・力が入らない・・・。』
(ぬぅん・・・毒か・・・。)
デクトキングの体重以上のものが伸し掛かる。
『どうにかならねえのか・・・。』
(生物毒なら、大抵タンパク質だ。タンパク質は熱で壊れる。)
『熱か・・・うぉおお・・・!』
再び、丹田に力を込める。今度は血液の巡りを良くし、発汗を促すように、体温を高めていく。
『ぬぅおおお・・・万力発散、スーパーデトックス!』
『ゴポンガァ!』
たちまち強熱が発生し、周囲を熱湯に変えていく。思わぬ反撃に、またデクトキングは離れる。が、今度は逃がさない!アノマロカリスの牙を引っ掴むと、ぐるんぐるんと思いっきり振り回す。
『へっ、折れちまったぜ。』
(貝は自分で捨てた、牙は折れた、なら残っているのは触手と・・・。)
ロブスターのような大きなハサミ。最後はこれを使ってくるだろう、自棄になったのか、海底を触手で駆けながら、スペリオンへと向かってくる。
『そっちが空蝉の術なら、こっちは畳返しの術!』
ハサミがふりかぶられるその瞬間、光の刃で海底の岩盤を切り、壁のように立てかける。粉々に砕かれる岩盤、その向こうにさらにハサミを振るうデクトキングだったが、その攻撃は空を切る。
『からのっ、土遁の術!』
体をドリルのように回転させて地中を潜り、デクトキングの虚と体を突く。
『ゴボボボボボボボボ』
『サシミじゃなくて串焼きになっちまいそうだな。』
(だが、こいつの再生能力は伊達じゃない。煮ても焼いても食えなさそうだ。)
『なら、干物にしたらどうだ!』
突き刺した手に回転エネルギーを纏わせる。するとデクトキングの体がプロペラのように回転を始める。
一方海面では。
「なんて渦だ!」
「巻き込まれたら沈むぞ!」
「社長、御無事ですか?」
「ああ、だがあの巨人・・・。」
戦艦の上で、ヴィクトールが呻く。恐るべき海獣を相手にしても沈むことが無かったことは、ヴィクトールも織り込み済みであった。しかし、あの巨人を見た途端に、ヴィクトールの顔色も変わった。
「あの」巨人はどこだ?」
「海です!あの海獣と戦っているでしょう。」
ようやっと現状を把握できたところだったが、現状というものは刻一刻と変化するもの。既にスペリオンのフィニッシュブローは始まっていた。
「渦の中から!」
「渦の中からなんだ!」
「海獣が!」
跳び出した。それもプロペラのように回転しながら、その下に巨人がぶら下がりながら、空へと向かっていく。
『遠心力で水分を全部飛ばす!』
(いい作戦だ!これなら再生も出来まい!)
デクトキングの体はスルメのようにどんどん乾いていく。
『あとは・・・燃えろぉ!気功ブレイズ!』
(やれええええええ!!)
すっかり元の体重の10分の1よりも軽くなり、回転力のままに打ち上げられた海獣の最後は、あまりにあっけないものだった。
『やった!』
(うむ。)
灰になったデクトキングが、海に落ちる。そこはかとなくいい香りがする。
「・・・撃て。」
「は?何が?」
「あの巨人を撃て!命令だ、今すぐ!」
「何故ですか?あれは海獣を倒してくれたではありませんか!」
「いいから撃て!次にあの力をこちらに向けないとも限らんのだぞ!」
(なにやら、穏やかじゃない雰囲気だな。)
『どうする、そっちがその気ならこっちも。』
(やめろ!人間に手を出すな。何があろうと。)
『冗談だよ。』
砲が向けられるよりも先に、スペリオンは光となって消えていった。
☆
「さっきは冗談に聞こえなかった。」
「まあ半分はマジで頭に来てたからな。」
先ほどまでの痛みは消え失せて、元のガイとアキラに戻った二人。港にも先ほどのデクトキングの灰が降り注いできている。
「おーい!ガイー!アキラー!」
「無事でしたのね!いなくなったって聞いて心配していましたわ!」
「せやから心配ないゆーたやん。この二人やったら平気やって。」
「すっかり二人組扱いか。」
「結局、あの大ダコはなんだったんだ?」
「少なくとも自然から生まれた生物ではない。手足や腹のそれぞれの機能が色んな生物のキメラのようだった。」
たしかに、タコも貝の仲間ではあるが、そこにアノマロカリスやロブスターが組み込まれているというのは不自然だ。タコを起点に、様々な形に先祖返りした、というケースも考えられなくもないが、あんな形質が必要になる環境など、ありはしない。よって自然から生まれる姿ではない。
「そんなことは火を見るより明らかだろ。問題は、誰がどんな目的を持ってやったのか、だろ?」
「いや、それも違う。」
「クリン?今までどこ行っとったん?」
「ずっと宿で待ってたんだよ!」
「そうだったな、悪い悪い。それで、なにが違うんだ?」
「俺たちの考えるべき問題は、どうやって帰るかって方法だろ?誰もオオダコの正体を突き止めろなんて頼んでないぞ。」
「確かに。」
困ったことに、ヴィクトール商社の船が沢山やってきて、ここら一帯を海上封鎖してしまった。これでは海路で帰る計画がパァだ。
「本来の予定なら、ここから西のサメルの街に着く予定だったんだな。」
「どうする?山道で西行くの?」
「・・・いっそ南に行って、そこからまた海に出るっていうのはどうだ?」
「また海?もう大タコに襲われるのは勘弁だよ!」
「さすがにあんな海獣はもういないと思うけど、海に出ていいことひとっつも無いよな現状。」
「・・・わかった、海はよそう。これからは陸路で西へ向かおう。」
どうにもこうにも、旅は上手くいかない。不安や災難にみまわれるが、旅が終われば思い出と土産話に変わる。
「まっ、これからだなこれから。」
「アキラ前向き。」
「前向いてなきゃ歩けないだろ。」
☆
「おのれ・・・まさかあの巨人が再び俺の前に現れるとは・・・。」
ところ変わって、ヴィクトール商社は社長の私室。ヴィクトール社長のこれまでの功績を称える品々や、大陸が一つと超大陸が一つ描かれた地球儀、高そうな調度品が揃えられたその部屋の中で、当の本人が椅子に腰かけて不満の言葉を宙に投げている。
「まさか・・・過ぎ去った悪夢とばかり思っていたが、なぜ今になってなのだ・・・。」
長く伸びた髭を指でさすりながら、厳しい表情で天井を見上げる。そして、『あの日』を思い出す。
「なにか、お困りのようだね?」
「! お前か、ベノム!」
ヴィクトール一人しかいないはずの部屋に、別の声が響く。見れば、その声の主は応接テーブルに座って勝手に酒を飲んでいた。その表情はフードに隠れて見えない。
「お前に会って、いやこの世界に来て20余年経った。おかげで俺のサクセスストーリーは順調だと言っていいものだった、はずなのに。」
「まさかの再会だな。ハルマゲドンの、その中心に立つ者の。」
「また、俺の人生を滅茶苦茶にするつもりなのなら、手を打たなければならない。どうか、手を貸してくれないか友よ。」
「勿論だ。今しばらくは様子を窺って、機を見て手を打とうではないか。」
「やってくれるか?」
「今そう言った。」
「そうか、そうか!なにか入用の物はないか?金か?なんでもいいぞ!」
「いや結構。自分でやるのが好きなんでね。なにかあったらまた来よう。それまでに、『あの準備』を進めておいてくれ。」
「ああわかった。感謝する、ベノム。」
決して歴史の表舞台に立たないもの、そういうものが、歴史のターニングポイントには現れる。目には見えない糸を操り、爪を研ぐ。そんな影が闇から浮上したことを知るものはいない。
「ん?」
「どうした、クリン?腹でも痛いのか?」
「違う、なんかこのクリスタルが・・・。」
「何それ、真っ黒だな。」
「・・・なんでもない。」
今はまだ、予兆を見せているだけ。
0
お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説

超エンジェル戦士シャイニングカクウ
レールフルース
ライト文芸
何もかもがダメで、グータラだけどちょっとした正義感があるごく普通の中学生の佐東誠心(さとうまさむね)がある日メモリーパワーを受けてシャイニングカクウになってしまった!
シャイニングカクウに変身できるようになった誠心は大喜び。だけど周りの人には見えないから自慢ができない。
人間に密かに憑依して悪事を働くジェラサイドと言う悪の組織に立ち向かいながらも青春や恋愛に友情などを味わうヒーロー物語!
果たして佐東誠心はこの世界を守れるか!?

ま性戦隊シマパンダー
九情承太郎
キャラ文芸
魔性のオーパーツ「中二病プリンター」により、ノベルワナビー(小説家志望)の作品から次々に現れるアホ…個性的な敵キャラたちが、現実世界(特に関東地方)に被害を与えていた。
警察や軍隊で相手にしきれないアホ…個性的な敵キャラに対処するために、多くの民間戦隊が立ち上がった!
そんな戦隊の一つ、極秘戦隊スクリーマーズの一員ブルースクリーマー・入谷恐子は、迂闊な行動が重なり、シマパンの力で戦う戦士「シマパンダー」と勘違いされて悪目立ちしてしまう(笑)
誤解が解ける日は、果たして来るのであろうか?
たぶん、ない!
ま性(まぬけな性分)の戦士シマパンダーによるスーパー戦隊コメディの決定版。笑い死にを恐れぬならば、読むがいい!!
他の小説サイトでも公開しています。
表紙は、画像生成AIで出力したイラストです。
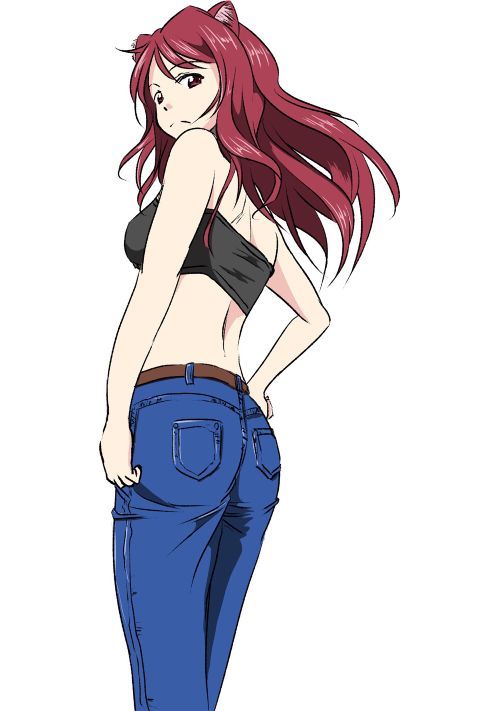
遥か
カリフォルニアデスロールの野良兎
キャラ文芸
鶴木援(ツルギタスケ)は、疲労状態で仕事から帰宅する。何も無い日常にトラウマを抱えた過去、何も起きなかったであろう未来を抱えたまま、何故か誤って監獄街に迷い込む。
生きることを問いかける薄暗いロー・ファンタジー。
表紙 @kafui_k_h

少年、その愛 〜愛する男に斬られるのもまた甘美か?〜
西浦夕緋
キャラ文芸
15歳の少年篤弘はある日、夏朗と名乗る17歳の少年と出会う。
彼は篤弘の初恋の少女が入信を望み続けた宗教団体・李凰国(りおうこく)の男だった。
亡くなった少女の想いを受け継ぎ篤弘は李凰国に入信するが、そこは想像を絶する世界である。
罪人の公開処刑、抗争する新興宗教団体に属する少女の殺害、
そして十数年前に親元から拉致され李凰国に迎え入れられた少年少女達の運命。
「愛する男に斬られるのもまた甘美か?」
李凰国に正義は存在しない。それでも彼は李凰国を愛した。
「おまえの愛の中に散りゆくことができるのを嬉しく思う。」
李凰国に生きる少年少女達の魂、信念、孤独、そして愛を描く。

化想操術師の日常
茶野森かのこ
キャラ文芸
たった一つの線で、世界が変わる。
化想操術師という仕事がある。
一般的には知られていないが、化想は誰にでも起きる可能性のある現象で、悲しみや苦しみが心に抱えきれなくなった時、人は無意識の内に化想と呼ばれるものを体の外に生み出してしまう。それは、空間や物や生き物と、その人の心を占めるものである為、様々だ。
化想操術師とは、頭の中に思い描いたものを、その指先を通して、現実に生み出す事が出来る力を持つ人達の事。本来なら無意識でしか出せない化想を、意識的に操る事が出来た。
クズミ化想社は、そんな化想に苦しむ人々に寄り添い、救う仕事をしている。
社長である九頭見志乃歩は、自身も化想を扱いながら、化想患者限定でカウンセラーをしている。
社員は自身を含めて四名。
九頭見野雪という少年は、化想を生み出す能力に長けていた。志乃歩の養子に入っている。
常に無表情であるが、それは感情を失わせるような過去があったからだ。それでも、志乃歩との出会いによって、その心はいつも誰かに寄り添おうとしている、優しい少年だ。
他に、志乃歩の秘書でもある黒兎、口は悪いが料理の腕前はピカイチの姫子、野雪が生み出した巨大な犬の化想のシロ。彼らは、山の中にある洋館で、賑やかに共同生活を送っていた。
その洋館に、新たな住人が加わった。
記憶を失った少女、たま子。化想が扱える彼女は、記憶が戻るまでの間、野雪達と共に過ごす事となった。
だが、記憶を失くしたたま子には、ある目的があった。
たま子はクズミ化想社の一人として、志乃歩や野雪と共に、化想を出してしまった人々の様々な思いに触れていく。
壊れた友情で海に閉じこもる少年、自分への後悔に復讐に走る女性、絵を描く度に化想を出してしまう少年。
化想操術の古い歴史を持つ、阿木之亥という家の人々、重ねた野雪の過去、初めて出来た好きなもの、焦がれた自由、犠牲にしても守らなきゃいけないもの。
野雪とたま子、化想を取り巻く彼らのお話です。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

クラスメイトの美少女と無人島に流された件
桜井正宗
青春
修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。
高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。
どうやら、漂流して流されていたようだった。
帰ろうにも島は『無人島』。
しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。
男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















