97 / 206
第3部 仇(あだ)
55:オトラル戦19:イディクート
しおりを挟む
「うるさいのう。鳥がおらぬようになってしまったではないか。そのせいで、最近うまい鳥肉が食えておらぬ」
ウイグル勢の首領たるイディクートがつぶやけば、
「まったくです」
と相対する者が応じる。
前者は30代、後者は一回りほど年長であり、オゲ(日本風に言えば家老職)の官職にあった。
かなりまばらになったとはいえ、投石が城壁に当たる轟音がここまで届いておったのである。炭火を焚くカマドのかたわらで、2人は盤面を挟んで座る。昔、ソグド人がマニ教と共にウイグルに持ち込んだチェスの1種であった。
その天幕は、オトラル城からだいぶ離れておった。ただ最初からではない。徐々に徐々に離れて行ったのだった。その居心地の悪さゆえと言って良い。といってオトラル攻めの指揮官たるチャアダイやオゴデイから文句が来ることもなかった。
「義兄上たちとて、我の姿を見れば、全く気をつかわぬという訳にも行かぬであろう。何せ、ウイグルのカンの血筋を引く我である。更には駙馬を約束された身である。我が近くにおらぬ方が気安いであろう」
などとイディクートは周囲に漏らしておった。
とはいえ、遊牧帝国の主と言い得たは遠き昔のことであった。また、この者も妻の尻にしかれており、というより、ひどく恐れるゆえに、チンギス・カンの娘との婚姻を先延ばしにしておった。ゆえに、この者が自負するほどであったかは、はなはだ疑わしい。
実際のところを言えば、この時、率いる騎馬兵は300そこそこ。これでは、戦力としては何の頼りにもならぬことは、誰の目にも、無論2人の王子にも明らかであった。
また、この者自身、なるべく戦というものに関わらずに、この遠征を終わり、故郷に帰りたい。そう願っておったゆえに、現況はある一点を除いてむしろ願ったり叶ったりではあった。
ただ、ウイグル勢がまったく役に立っておらなかった訳ではない。チャアダイとオゴデイ各々にビチェーチ(ここは狭義の書記官の意味)として派遣されておるは、このイディクートの配下であった。
ウイグル語はトルコ語の1種であり、それをウイグル文字にて表記しておった。この時、このウイグル文字をもって、モンゴル語を記録するようになっておったのだった。ところで、ウイグル文字も、やはりソグド人がもたらしたソグド文字にもとづく。
餅は餅屋に似た言葉がモンゴルにあったかは分からないが、まさにそういう格好になっておったのである。
互いの駒は手についた油のためにベトベトであった。羊肉が香ばしい匂いを上げ続けている。これは羊皮の中に肉と熱した石を入れ、更には外側からカマドの火であぶる――現代風に言えば、肉汁をたんまりと閉じ込めた料理であった。
この2人は、食べては一つの駒を動かし、動かしては食べるを繰り返しておった。
下ごしらえの手間に加え焼き上がるのに時間がかかる料理であるが、ウイグルの陣中は兵は少ないといえども、王族専用の料理人はおり、問題はない。またイディクート本人も、急いで何かをしなければならぬということは無論ない。むしろ料理人からそれを受け取った後は、自ら焼き加減を見ながらつまむという楽しみがあった。その点では、それもまた良しであった。
ただそれにありつけたのは、攻囲の始まりから少しの間に留まり、今はそれを夢想して垂涎するしかなかった。かたわらにあるは、干し肉を湯で戻したものであり、それで口寂しさをまぎらわすのみであった。冬ゆえということもあるが、王侯貴族たる彼らならば、必ずしもそれにしばられる必要は無いはずであった。
これまでに、生かしておった牡羊は、たびたび徴集されておったのだ。最前線の兵のためと言われれば拒めるはずもなかった。
それで鳥の不在を嘆くといったことになる訳である。配下の者に獲らせた鳥なら、誰はばかることなく――無論、まったく分けぬということは、自らの評判を悪くするだけなので避けるべきであるが――それでも優先的に自らが食べることはできるゆえに。
両人とも、この遠征に参加する前は太りじしと言って良い体つきであったが、今や、その面影はなかった。
(補足 1.西征の時にイディクートがどの程度の軍勢を率いたかは明らかではない。ただジュワイニーには、ナイマンのクチュルグ追討には300の兵を率いて参戦したとあるので、ここでも同数とした。少なすぎるかと想わぬでもないが、王侯貴族を除いてほとんどが農耕定住化したとすれば、こんなものかとも想う。
いずれにしろ、チンギスとしてはイディクートが参戦すれば、それで良しというか、最低限の義務は果たしたとみなしたのだろう。
2.イディクートのイディは『主』、クートはザルヌーク(第3部28話)のところで論じたクトルグと同意であり、ゆえに単純には『幸運の主』となる。これでは、なかなか様にならぬが、『天恵の主』、『天命の主』とすれば、日本語の語感にても悪くないとなろう。
3.家畜は冬が進み行くにつれ痩せて行くので、かつては冬の始まりに多少なりとも屠って冬に備えるのが一般的であった。干し肉にするか否かは、その地の気温などによる。モンゴルの如くの厳寒の地では保存目的では不要であるが、食味など他の理由で干し肉にすることもある)
ウイグル勢の首領たるイディクートがつぶやけば、
「まったくです」
と相対する者が応じる。
前者は30代、後者は一回りほど年長であり、オゲ(日本風に言えば家老職)の官職にあった。
かなりまばらになったとはいえ、投石が城壁に当たる轟音がここまで届いておったのである。炭火を焚くカマドのかたわらで、2人は盤面を挟んで座る。昔、ソグド人がマニ教と共にウイグルに持ち込んだチェスの1種であった。
その天幕は、オトラル城からだいぶ離れておった。ただ最初からではない。徐々に徐々に離れて行ったのだった。その居心地の悪さゆえと言って良い。といってオトラル攻めの指揮官たるチャアダイやオゴデイから文句が来ることもなかった。
「義兄上たちとて、我の姿を見れば、全く気をつかわぬという訳にも行かぬであろう。何せ、ウイグルのカンの血筋を引く我である。更には駙馬を約束された身である。我が近くにおらぬ方が気安いであろう」
などとイディクートは周囲に漏らしておった。
とはいえ、遊牧帝国の主と言い得たは遠き昔のことであった。また、この者も妻の尻にしかれており、というより、ひどく恐れるゆえに、チンギス・カンの娘との婚姻を先延ばしにしておった。ゆえに、この者が自負するほどであったかは、はなはだ疑わしい。
実際のところを言えば、この時、率いる騎馬兵は300そこそこ。これでは、戦力としては何の頼りにもならぬことは、誰の目にも、無論2人の王子にも明らかであった。
また、この者自身、なるべく戦というものに関わらずに、この遠征を終わり、故郷に帰りたい。そう願っておったゆえに、現況はある一点を除いてむしろ願ったり叶ったりではあった。
ただ、ウイグル勢がまったく役に立っておらなかった訳ではない。チャアダイとオゴデイ各々にビチェーチ(ここは狭義の書記官の意味)として派遣されておるは、このイディクートの配下であった。
ウイグル語はトルコ語の1種であり、それをウイグル文字にて表記しておった。この時、このウイグル文字をもって、モンゴル語を記録するようになっておったのだった。ところで、ウイグル文字も、やはりソグド人がもたらしたソグド文字にもとづく。
餅は餅屋に似た言葉がモンゴルにあったかは分からないが、まさにそういう格好になっておったのである。
互いの駒は手についた油のためにベトベトであった。羊肉が香ばしい匂いを上げ続けている。これは羊皮の中に肉と熱した石を入れ、更には外側からカマドの火であぶる――現代風に言えば、肉汁をたんまりと閉じ込めた料理であった。
この2人は、食べては一つの駒を動かし、動かしては食べるを繰り返しておった。
下ごしらえの手間に加え焼き上がるのに時間がかかる料理であるが、ウイグルの陣中は兵は少ないといえども、王族専用の料理人はおり、問題はない。またイディクート本人も、急いで何かをしなければならぬということは無論ない。むしろ料理人からそれを受け取った後は、自ら焼き加減を見ながらつまむという楽しみがあった。その点では、それもまた良しであった。
ただそれにありつけたのは、攻囲の始まりから少しの間に留まり、今はそれを夢想して垂涎するしかなかった。かたわらにあるは、干し肉を湯で戻したものであり、それで口寂しさをまぎらわすのみであった。冬ゆえということもあるが、王侯貴族たる彼らならば、必ずしもそれにしばられる必要は無いはずであった。
これまでに、生かしておった牡羊は、たびたび徴集されておったのだ。最前線の兵のためと言われれば拒めるはずもなかった。
それで鳥の不在を嘆くといったことになる訳である。配下の者に獲らせた鳥なら、誰はばかることなく――無論、まったく分けぬということは、自らの評判を悪くするだけなので避けるべきであるが――それでも優先的に自らが食べることはできるゆえに。
両人とも、この遠征に参加する前は太りじしと言って良い体つきであったが、今や、その面影はなかった。
(補足 1.西征の時にイディクートがどの程度の軍勢を率いたかは明らかではない。ただジュワイニーには、ナイマンのクチュルグ追討には300の兵を率いて参戦したとあるので、ここでも同数とした。少なすぎるかと想わぬでもないが、王侯貴族を除いてほとんどが農耕定住化したとすれば、こんなものかとも想う。
いずれにしろ、チンギスとしてはイディクートが参戦すれば、それで良しというか、最低限の義務は果たしたとみなしたのだろう。
2.イディクートのイディは『主』、クートはザルヌーク(第3部28話)のところで論じたクトルグと同意であり、ゆえに単純には『幸運の主』となる。これでは、なかなか様にならぬが、『天恵の主』、『天命の主』とすれば、日本語の語感にても悪くないとなろう。
3.家畜は冬が進み行くにつれ痩せて行くので、かつては冬の始まりに多少なりとも屠って冬に備えるのが一般的であった。干し肉にするか否かは、その地の気温などによる。モンゴルの如くの厳寒の地では保存目的では不要であるが、食味など他の理由で干し肉にすることもある)
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説

空母鳳炎奮戦記
ypaaaaaaa
歴史・時代
1942年、世界初の装甲空母である鳳炎はトラック泊地に停泊していた。すでに戦時下であり、鳳炎は南洋艦隊の要とされていた。この物語はそんな鳳炎の4年に及ぶ奮戦記である。
というわけで、今回は山本双六さんの帝国の海に登場する装甲空母鳳炎の物語です!二次創作のようなものになると思うので原作と違うところも出てくると思います。(極力、なくしたいですが…。)ともかく、皆さまが楽しめたら幸いです!

土方歳三ら、西南戦争に参戦す
山家
歴史・時代
榎本艦隊北上せず。
それによって、戊辰戦争の流れが変わり、五稜郭の戦いは起こらず、土方歳三は戊辰戦争の戦野を生き延びることになった。
生き延びた土方歳三は、北の大地に屯田兵として赴き、明治初期を生き抜く。
また、五稜郭の戦い等で散った他の多くの男達も、史実と違えた人生を送ることになった。
そして、台湾出兵に土方歳三は赴いた後、西南戦争が勃発する。
土方歳三は屯田兵として、そして幕府歩兵隊の末裔といえる海兵隊の一員として、西南戦争に赴く。
そして、北の大地で再生された誠の旗を掲げる土方歳三の周囲には、かつての新選組の仲間、永倉新八、斎藤一、島田魁らが集い、共に戦おうとしており、他にも男達が集っていた。
(「小説家になろう」に投稿している「新選組、西南戦争へ」の加筆修正版です)

いや、婿を選べって言われても。むしろ俺が立候補したいんだが。
SHO
歴史・時代
時は戦国末期。小田原北条氏が豊臣秀吉に敗れ、新たに徳川家康が関八州へ国替えとなった頃のお話。
伊豆国の離れ小島に、弥五郎という一人の身寄りのない少年がおりました。その少年は名刀ばかりを打つ事で有名な刀匠に拾われ、弟子として厳しく、それは厳しく、途轍もなく厳しく育てられました。
そんな少年も齢十五になりまして、師匠より独立するよう言い渡され、島を追い出されてしまいます。
さて、この先の少年の運命やいかに?
剣術、そして恋が融合した痛快エンタメ時代劇、今開幕にございます!
*この作品に出てくる人物は、一部実在した人物やエピソードをモチーフにしていますが、モチーフにしているだけで史実とは異なります。空想時代活劇ですから!
*この作品はノベルアップ+様に掲載中の、「いや、婿を選定しろって言われても。だが断る!」を改題、改稿を経たものです。
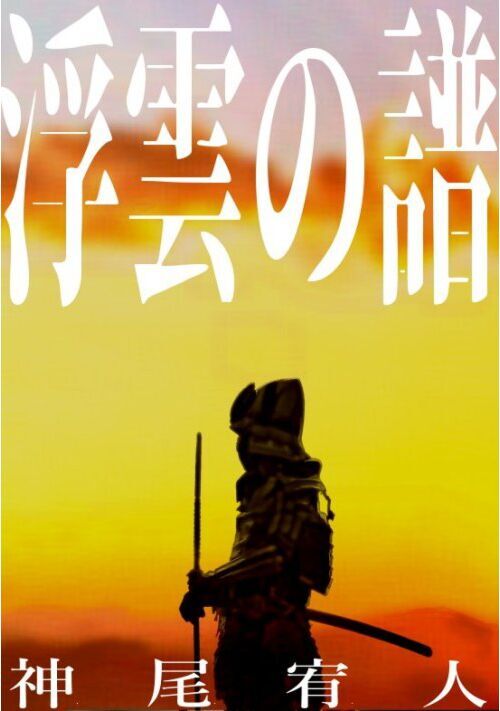
浮雲の譜
神尾 宥人
歴史・時代
時は天正。織田の侵攻によって落城した高遠城にて、武田家家臣・飯島善十郎は蔦と名乗る透波の手によって九死に一生を得る。主家を失って流浪の身となったふたりは、流れ着くように訪れた富山の城下で、ひょんなことから長瀬小太郎という若侍、そして尾上備前守氏綱という男と出会う。そして善十郎は氏綱の誘いにより、かの者の主家である飛州帰雲城主・内ヶ島兵庫頭氏理のもとに仕官することとする。
峻厳な山々に守られ、四代百二十年の歴史を築いてきた内ヶ島家。その元で善十郎は、若武者たちに槍を指南しながら、穏やかな日々を過ごす。しかしそんな辺境の小国にも、乱世の荒波はひたひたと忍び寄ってきていた……

帝国夜襲艦隊
ypaaaaaaa
歴史・時代
1921年。すべての始まりはこの会議だった。伏見宮博恭王軍事参議官が将来の日本海軍は夜襲を基本戦術とすべきであるという結論を出したのだ。ここを起点に日本海軍は徐々に変革していく…。
今回もいつものようにこんなことがあれば良いなぁと思いながら書いています。皆さまに楽しくお読みいただければ幸いです!

四代目 豊臣秀勝
克全
歴史・時代
アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。
読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。
史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。
秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。
小牧長久手で秀吉は勝てるのか?
朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?
朝鮮征伐は行われるのか?
秀頼は生まれるのか。
秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

改造空母機動艦隊
蒼 飛雲
歴史・時代
兵棋演習の結果、洋上航空戦における空母の大量損耗は避け得ないと悟った帝国海軍は高価な正規空母の新造をあきらめ、旧式戦艦や特務艦を改造することで数を揃える方向に舵を切る。
そして、昭和一六年一二月。
日本の前途に暗雲が立ち込める中、祖国防衛のために改造空母艦隊は出撃する。
「瑞鳳」「祥鳳」「龍鳳」が、さらに「千歳」「千代田」「瑞穂」がその数を頼みに太平洋艦隊を迎え撃つ。

札束艦隊
蒼 飛雲
歴史・時代
生まれついての勝負師。
あるいは、根っからのギャンブラー。
札田場敏太(さつたば・びんた)はそんな自身の本能に引きずられるようにして魑魅魍魎が跋扈する、世界のマーケットにその身を投じる。
時は流れ、世界はその混沌の度を増していく。
そのような中、敏太は将来の日米関係に危惧を抱くようになる。
亡国を回避すべく、彼は金の力で帝国海軍の強化に乗り出す。
戦艦の高速化、ついでに出来の悪い四姉妹は四一センチ砲搭載戦艦に改装。
マル三計画で「翔鶴」型空母三番艦それに四番艦の追加建造。
マル四計画では戦時急造型空母を三隻新造。
高オクタン価ガソリン製造プラントもまるごと買い取り。
科学技術の低さもそれに工業力の貧弱さも、金さえあればどうにか出来る!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















