31 / 51
六章『花、熱る 後編』
その二
しおりを挟む
鎧武者は執拗にナナヱばかりを狙って追いかけ、ナナヱはすばしっこく動き回り鎧武者の拘束を躱し続けている。ナナヱの体力に限界が来る前に、一刻も早く鎧武者の動きを封じたいおれとリツだが、攻撃範囲の広い槍を振るってくるのでなかなか思うようにならなかった。
「外へ出ます! 鎧を宿から引き離すのです!」
ナナヱは追いかけられてもなお、旅館の客の安全を気にしていたらしい。鎧武者の手をまたひらりと躱すと、旅館の裏口へ一気に駆けだした。
「あの子に従いましょ。建物の中だと動きにくいわ」
「そうくれば――」
おれたちは視線を交わして合図し合う。リツは鎧武者の前に回り込んで刀代わりの棒切れを振るい、おれは先をちょろちょろ動き回っていたナナヱを抱き上げて鎧武者から距離を取った。
「ナナヱ、このまま外に出れば良いんだな?」
「はい! 先日手合わせした空き地へ!」
「了解。リツ!」
足止めをしていたリツに合図を送ると、リツは受け止めていた槍をいなし、よろけた鎧武者の兜を踏み台にして飛び退いた。
「ぶにゃ~っ!」
リツが素早く鎧武者から離れたと同時に、全力疾走でやってきた寅松がさらに、鎧武者の背中を蹴って跳躍する。相変わらず丸い体型に似つかわしくない身体能力で寅松は駆け寄り、主人を呼ぶように鳴き声を上げた。
「寅松……! ナナヱを追ってきたのですか?」
「にゃ~ぅ!」
ナナヱの言葉に、ああそうだと言わんばかりに声を張り上げて鳴く寅松。ご主人様至上主義もここまで来ると、尊敬に値する。寅松は名犬ならぬ名猫だった。
さて、中身のない独りでに動く甲冑に追い回されるというこの奇怪な状況に、早急に手を打たねば。おれは宿の裏手へと続く夜道を、雨を突っ切って走りながら考える。
禁書の気配を感じないとはいえ、何らかの譚が絡んでいるのは間違いないだろう。そして、それは恐らく。
「ナナヱ。さっき『懲らしめに来た』って聞こえたけど、ありゃどういう意味だ?」
彼女のその台詞が鍵を握っていると踏んだおれは腕の中にいるナナヱに尋ねる。ナナヱはおれの寝間着の襟にしがみつきながら答えた。
「大祖母様から聞いたことがあるのです。あの鎧にはご先祖さまの魂が篭っていて、加峯家に仇なす者から守ってくださるのだと」
「じゃあまさか、本当に魂が宿っちゃってるなんて言うの?」
「そんなの知りません! でも、大祖母様から不思議な体験を聞いたことはあります。なんでも、子供の頃にあの鎧に悪戯をして、その夜、鎧に追いかけられる夢を見たとか。――だから、ナナヱのことも、もしかしたらお叱りに来たのでしょうか……?」
おれたちが会話をしながら逃げている間もずっと、金属製の騒がしい足音が後ろをぴったりと追跡してきていた。
小さな門をくぐり抜け、細い通路を一列になって走り、坂を一気に駆け下りても、足音が遠のくことはない。追いつかれるのも時間の問題だった。
「叱られるような悪戯をあの鎧にしたのか?」
「そんなことしてないのです! 大祖母様のお話を聞いたら、悪戯なんてできないのです。小さい頃のナナヱは怖くて、あの鎧が飾ってある表の玄関から宿に入れなかったくらいなんですから」
「あら、ずいぶん可愛らしいお譚じゃない」
「うるさいのですっ! 下穿きの下から大根が二本丸見えなのですよっ!」
「なんですって、この恩知らずの豆粒娘!」
「助けてなんて言ってないのです、山芋足!」
「ミジンコって呼び変えてもいいのよ!?」
「だぁーッ!! 喧嘩始めんじゃねえ、お前らァ!!」
この危機的状況下でも喧嘩を始めそうになった二人に怒ると、今回ばかりはさすがにそんな場合じゃないと理解したのか、二人とも大人しく黙った。
「けど、譚の観点から行けば、ナナヱが関係してる可能性は高いな」
あるいは加峯家の譚があの甲冑を動かしているのか――古くから加峯家が所有している物ともなれば、あれには加峯家代々の譚が内包されているのだろう。それはもう濃厚に染みついた、加峯家の譚――おっさんがいれば、すぐにご自慢の嗅覚でとらえていたに違いない。
「叱られるって言葉が出てくるっつーことはよ、ナナヱにもあの鎧から叱られるようなことに心当たりがあるんじゃねえのか。もしくは――ご先祖さまに叱られそうなことに」
「…………っ」
ナナヱがまた、くっくっと唇を噛んでいる。言い難いことを言おうとする時の癖なのだろうか。彼女はおれの襟に更にしがみつくと、やがて覚悟を決めたように告白した。
「……ナナヱが、加峯家を出て旅がしたいって、考えてしまったから」
「さっきの話か?」
ナナヱはこくりと頷く。
「あの時は勇気が出なくて言えなかったけれど、本当はナナヱも、世助様の言うように旅に出たいと思ったのです。……それをご先祖さまが止めに来た、のかもしれません。ナナヱが、悪い子だから……」
なるほど、理解した。譚本を扱う七本屋で働いたおれの直感はきちんと当たったようだ。
「リツ、やっぱりあいつは禁書じゃねえ。譚の断片だ!」
「どういうこと?」
「禁書みたいなやべえ危険性はねえが、ちっとばかし厄介な状態になってる!」
加峯家の譚。それは長きにわたり加峯家で繰り広げられてきた歴史――因習、因縁、偏った思想や価値観なども含んだ、譚。加峯家のためにならぬ、加峯家に仇なす存在を徹底的に責め立てる譚。あるいはそんな存在を迫害し、叱責し、縛り付ける――そういった行為が繰り返されてきた譚が、濃厚に染み付いた甲冑だ。
それがナナヱの心と結びついた結果、加峯家の方針に背こうとするナナヱを制裁する武者となって表れ、彼女を追いかけだした。――といったところだろう。
「禁書じゃないというのなら、どう対処すればいいの? 粉々に砕く?」
「なっ!? 加峯家の宝物になんてことを!」
甲冑を粉々に、というリツの豪快な発言に、ナナヱが目を剥く。
しかし、それをしたところで無駄だろう。ナナヱが右肩を破壊してもすぐに元通りに再生したのがその証拠だ。ただ闇雲に破壊しただけでは、あの鎧武者を止めることはできない。
「譚の断片は読み解きをして本に紡がなきゃならねえんだがな、あいにくこの場に専門家がいねえ。が……」
本当に、おっさんがこの場にいたら大喜びだっただろう。読み解きはおっさんの十八番だというのに、全く悔やまれるばかりだ。
だが、おれも譚の読み解きは一度だけ経験済みだ。草村堂という古本屋に住み着いた座敷童子の譚――それを、唯助と共に読み解いている。
「物は試しだ、ナナヱ次第でどうにかできるかもしれねえぜ」
「ナナヱちゃんが?」
「ナナヱが、ですか?」
おっさんの言葉を借りて言うならば、今のナナヱの状態は起承転結の転までが揃った状態だ。この鎧を動かした彼女の譚の歯車をさらに動かし、結まで導き出せば、あるいは。
「……! そろそろ空き地に着くのです!」
「ということは、そろそろ対決かしら」
昨日ナナヱと手合わせをした、開けた平地にたどり着く。鎧武者の足音もすぐ近くまで迫ってきている。あと数秒すれば、夜闇から姿を現すことだろう。
「リツ、時間を稼げるか?」
「やってみる。でも棒切れ一本だから、できるだけ早くお願い」
後方へ振り返ったリツが、棒切れの先を向ける。その切っ先が睨む夜闇の向こうから、ついに真っ赤な鎧武者が姿を現した。
ナナヱを庇うように立ち塞がるリツに、鎧武者もまた、槍の矛先を向ける。互いとの距離を測り合いながら、じりじりと歩み寄る双方。
――先に動いたのは鎧武者のほうだった。槍を突き出し、一気にリツに襲いかかる。リツは飛び出てきた槍の突きを躱し、鎧武者にひと太刀浴びせんと距離を詰めた。
リツが鎧武者に応戦して時間を稼いでいる間に、おれは抱えていたナナヱを下ろし、彼女に目線を合わせて問いかけた。
「ナナヱ、よく聞け。あの鎧はお前の譚だ。お前自身の心なんだ」
「はなし……心?」
「ああ、譚ってのは心だ。お前の中に根付いた不安や恐怖の心が、加峯家にお前を閉じ込めようとしてるんだ」
加峯家の娘として結婚し、縁を結ぶことが出来ないのであれば、お前は役立たずだ。穀潰しだ。
――あの鎧武者は、大人たちから繰り返しそう言われ続け、根深く植え付けられた彼女の価値観。自分は加峯家の娘として、家の方針に従わなければならないのだ、という彼女の強迫観念――そして、加峯家で繰り返されてきた譚の断片が結びついて動き出したものだ。
「あの鎧がお前を捕まえようとしているのは、加峯家に従わなきゃいけないんだって、もう一人のお前が止めてるからでもあるんだ」
「では、諦めれば良いのですか? ナナヱが、旅に出ることを諦めれば、あの鎧は止まるのですか?」
確かに、ナナヱが大人しく加峯家に留まるという選択肢を取れば、あの鎧武者を鎮めることはできるだろう。だが、それは抜本的な解決方法ではない。お家の歪んだ価値観や評価に雁字搦めにされたナナヱの、旅に出てみたいという心は、永遠に抑圧されたままだ。
「それだけが選択肢じゃねえさ。正面からあの鎧をぶっ壊して逃げ切るって手もあるぜ」
「え……」
おっさんならナナヱの譚を読み解いて本にするところだろうが、あいにくおれはそんな技術など持ち合わせていない。なので、こうするしかないのだ。
「ナナヱ、お前は加峯家に留まるか? それとも、このままあいつから逃げ切って旅に出るか?」
ナナヱがしきりに唇を噛む。おれから逸らされた目線は、今まさにリツと戦っている鎧武者に向けられていた。
「どっちにするかはお前次第だ。旅を我慢してでも加峯家にいるべきだと思うならそうすればいい。加峯家を出て旅がしてみたいなら、今ここで宣言しな」
「……ナ、ナヱは……」
ナナヱの視線は鎧武者とおれの間を行き来する。
おれはリツの様子を見る。彼女も剣技を使ってまだなんとか持ち堪えているが、腕力では相手の方が一枚上手だ。ここまで走ってきて体力も消耗しているし、時間稼ぎもそろそろ厳しい頃合いだろう。
「ナナヱ。お前が自分の心に決着をつけるんだ。できるかできないかじゃなくて、お前がどうしたいかで決めな」
「ナナヱが、どうしたいか……?」
「大丈夫だ、おれとリツがついてる。勇気を出しておれに話してくれたんだ、お前はもう一人じゃねえよ」
おれはナナヱにそっと握り拳を差し出す。彼女からも握り拳を突き合わせてもらえるだろうかと期待して。しかし、期待したのとは違うナナヱの戸惑う顔を見たあとで、『しまった、これは唯助にしか通じねえんだった』と気づいた。
「ぶにゃ~……」
迷うナナヱの足元で、特徴的な猫の鳴き声があがる。見下ろせば、寅松の緑色の双眸が彼女をどこか心配そうに見つめていた。
「寅松……」
寅松はナナヱの傍に寄ると、彼女の足にぴとりと体を添わせた。おれにはその仕草が、絶対離れないぞと宣言しているかのように見えた。
「――そう、ですね。ナナヱには、ずっと寅松がいてくれたのです」
ナナヱは寅松の丸々とした体を抱き上げると、その頭を愛おしげに撫でた。
「決められそうか?」
そう問いかけて、ナナヱがおれの方へ再度向き直った時。惑い、曇っていた彼女の水色の目に、もはやその翳りはなかった。
「はい。ナナヱは、旅に出て強くなるのです。加峯家のためにではなく、ナナヱのために。ナナヱは加峯家に反抗してやるのです!」
「ぶにゃ!」
おれの差し出した握り拳に、寅松がナナヱに代わって肉球をポンとのせてきた。
「よく言った!」
言い切ったナナヱと寅松の頭をわしわし撫でてから、おれはすっくと立ち上がる。
堅牢なリツの防壁を今にも破ろうとしていた鎧武者は、途端に動きを鈍らせた。勿論、リツはその隙を見逃さない。威勢の揺らいだ鎧武者の足取りへさらに追い打ちをかけるように、棒切れで一文字に薙ぎ払う。
「怯んだわ!」
鎧武者の勢いが明らかに削がれたのを見るに、おれの目論見は上手くいったようだ。まるで地震が起きて崩れかけている積み木のように、危なげにぐらぐら揺れている。
「ナナヱ。今からあれを壊すけど、いいよな?」
「どうぞ粉々にやっちゃえなのです!」
「にゃ~ぅ!」
ナナヱは完全に吹っ切れたのか、寅松と共におれとリツを応援しだした。どうぞ粉々に、という彼女の言い方に、思わず笑ってしまいそうになる。
「なら、よく見とけよ。お前の見たがってた、夏目の柔術だ」
動きを察したリツが一歩引いたのを確認し、おれは足を踏み込む。一瞬の間さえ要らない――今では口に出して数える必要もないほど染みついた基本的な歩法を、心の中で一、二、三、と数えて――刹那の間に赤い鎧武者の懐へ迫る。
ナナヱとの手合わせで使ったのと同じものを、今度は手加減なしで、相手を確実に倒すための技として放つ。
鎧によって守られていない両の脇から掌底を叩き込み、鎖帷子伝いに両腕の装備を破壊する。後ろへ傾きかけたその肩を掴み、膝蹴りで腰部の接合を撃ち抜く。手刀を兜に振り下ろす。前屈みになった胴部を目掛けて踵を撃ち込む。
「行け、リツ! 一発ぶち込んでやれ!」
一部の無駄なく衝撃を与えられヒビが入った鎧――起き上がりかけたその体の胸部へ、リツの繰り出した刀の突きが加わる。
ただの棒切れによる刺突は鎧武者の体を貫き、細かなヒビを伝って隅々まで破壊し尽くした。鎧武者は文字通り、粉々に破砕されたのだった。
「外へ出ます! 鎧を宿から引き離すのです!」
ナナヱは追いかけられてもなお、旅館の客の安全を気にしていたらしい。鎧武者の手をまたひらりと躱すと、旅館の裏口へ一気に駆けだした。
「あの子に従いましょ。建物の中だと動きにくいわ」
「そうくれば――」
おれたちは視線を交わして合図し合う。リツは鎧武者の前に回り込んで刀代わりの棒切れを振るい、おれは先をちょろちょろ動き回っていたナナヱを抱き上げて鎧武者から距離を取った。
「ナナヱ、このまま外に出れば良いんだな?」
「はい! 先日手合わせした空き地へ!」
「了解。リツ!」
足止めをしていたリツに合図を送ると、リツは受け止めていた槍をいなし、よろけた鎧武者の兜を踏み台にして飛び退いた。
「ぶにゃ~っ!」
リツが素早く鎧武者から離れたと同時に、全力疾走でやってきた寅松がさらに、鎧武者の背中を蹴って跳躍する。相変わらず丸い体型に似つかわしくない身体能力で寅松は駆け寄り、主人を呼ぶように鳴き声を上げた。
「寅松……! ナナヱを追ってきたのですか?」
「にゃ~ぅ!」
ナナヱの言葉に、ああそうだと言わんばかりに声を張り上げて鳴く寅松。ご主人様至上主義もここまで来ると、尊敬に値する。寅松は名犬ならぬ名猫だった。
さて、中身のない独りでに動く甲冑に追い回されるというこの奇怪な状況に、早急に手を打たねば。おれは宿の裏手へと続く夜道を、雨を突っ切って走りながら考える。
禁書の気配を感じないとはいえ、何らかの譚が絡んでいるのは間違いないだろう。そして、それは恐らく。
「ナナヱ。さっき『懲らしめに来た』って聞こえたけど、ありゃどういう意味だ?」
彼女のその台詞が鍵を握っていると踏んだおれは腕の中にいるナナヱに尋ねる。ナナヱはおれの寝間着の襟にしがみつきながら答えた。
「大祖母様から聞いたことがあるのです。あの鎧にはご先祖さまの魂が篭っていて、加峯家に仇なす者から守ってくださるのだと」
「じゃあまさか、本当に魂が宿っちゃってるなんて言うの?」
「そんなの知りません! でも、大祖母様から不思議な体験を聞いたことはあります。なんでも、子供の頃にあの鎧に悪戯をして、その夜、鎧に追いかけられる夢を見たとか。――だから、ナナヱのことも、もしかしたらお叱りに来たのでしょうか……?」
おれたちが会話をしながら逃げている間もずっと、金属製の騒がしい足音が後ろをぴったりと追跡してきていた。
小さな門をくぐり抜け、細い通路を一列になって走り、坂を一気に駆け下りても、足音が遠のくことはない。追いつかれるのも時間の問題だった。
「叱られるような悪戯をあの鎧にしたのか?」
「そんなことしてないのです! 大祖母様のお話を聞いたら、悪戯なんてできないのです。小さい頃のナナヱは怖くて、あの鎧が飾ってある表の玄関から宿に入れなかったくらいなんですから」
「あら、ずいぶん可愛らしいお譚じゃない」
「うるさいのですっ! 下穿きの下から大根が二本丸見えなのですよっ!」
「なんですって、この恩知らずの豆粒娘!」
「助けてなんて言ってないのです、山芋足!」
「ミジンコって呼び変えてもいいのよ!?」
「だぁーッ!! 喧嘩始めんじゃねえ、お前らァ!!」
この危機的状況下でも喧嘩を始めそうになった二人に怒ると、今回ばかりはさすがにそんな場合じゃないと理解したのか、二人とも大人しく黙った。
「けど、譚の観点から行けば、ナナヱが関係してる可能性は高いな」
あるいは加峯家の譚があの甲冑を動かしているのか――古くから加峯家が所有している物ともなれば、あれには加峯家代々の譚が内包されているのだろう。それはもう濃厚に染みついた、加峯家の譚――おっさんがいれば、すぐにご自慢の嗅覚でとらえていたに違いない。
「叱られるって言葉が出てくるっつーことはよ、ナナヱにもあの鎧から叱られるようなことに心当たりがあるんじゃねえのか。もしくは――ご先祖さまに叱られそうなことに」
「…………っ」
ナナヱがまた、くっくっと唇を噛んでいる。言い難いことを言おうとする時の癖なのだろうか。彼女はおれの襟に更にしがみつくと、やがて覚悟を決めたように告白した。
「……ナナヱが、加峯家を出て旅がしたいって、考えてしまったから」
「さっきの話か?」
ナナヱはこくりと頷く。
「あの時は勇気が出なくて言えなかったけれど、本当はナナヱも、世助様の言うように旅に出たいと思ったのです。……それをご先祖さまが止めに来た、のかもしれません。ナナヱが、悪い子だから……」
なるほど、理解した。譚本を扱う七本屋で働いたおれの直感はきちんと当たったようだ。
「リツ、やっぱりあいつは禁書じゃねえ。譚の断片だ!」
「どういうこと?」
「禁書みたいなやべえ危険性はねえが、ちっとばかし厄介な状態になってる!」
加峯家の譚。それは長きにわたり加峯家で繰り広げられてきた歴史――因習、因縁、偏った思想や価値観なども含んだ、譚。加峯家のためにならぬ、加峯家に仇なす存在を徹底的に責め立てる譚。あるいはそんな存在を迫害し、叱責し、縛り付ける――そういった行為が繰り返されてきた譚が、濃厚に染み付いた甲冑だ。
それがナナヱの心と結びついた結果、加峯家の方針に背こうとするナナヱを制裁する武者となって表れ、彼女を追いかけだした。――といったところだろう。
「禁書じゃないというのなら、どう対処すればいいの? 粉々に砕く?」
「なっ!? 加峯家の宝物になんてことを!」
甲冑を粉々に、というリツの豪快な発言に、ナナヱが目を剥く。
しかし、それをしたところで無駄だろう。ナナヱが右肩を破壊してもすぐに元通りに再生したのがその証拠だ。ただ闇雲に破壊しただけでは、あの鎧武者を止めることはできない。
「譚の断片は読み解きをして本に紡がなきゃならねえんだがな、あいにくこの場に専門家がいねえ。が……」
本当に、おっさんがこの場にいたら大喜びだっただろう。読み解きはおっさんの十八番だというのに、全く悔やまれるばかりだ。
だが、おれも譚の読み解きは一度だけ経験済みだ。草村堂という古本屋に住み着いた座敷童子の譚――それを、唯助と共に読み解いている。
「物は試しだ、ナナヱ次第でどうにかできるかもしれねえぜ」
「ナナヱちゃんが?」
「ナナヱが、ですか?」
おっさんの言葉を借りて言うならば、今のナナヱの状態は起承転結の転までが揃った状態だ。この鎧を動かした彼女の譚の歯車をさらに動かし、結まで導き出せば、あるいは。
「……! そろそろ空き地に着くのです!」
「ということは、そろそろ対決かしら」
昨日ナナヱと手合わせをした、開けた平地にたどり着く。鎧武者の足音もすぐ近くまで迫ってきている。あと数秒すれば、夜闇から姿を現すことだろう。
「リツ、時間を稼げるか?」
「やってみる。でも棒切れ一本だから、できるだけ早くお願い」
後方へ振り返ったリツが、棒切れの先を向ける。その切っ先が睨む夜闇の向こうから、ついに真っ赤な鎧武者が姿を現した。
ナナヱを庇うように立ち塞がるリツに、鎧武者もまた、槍の矛先を向ける。互いとの距離を測り合いながら、じりじりと歩み寄る双方。
――先に動いたのは鎧武者のほうだった。槍を突き出し、一気にリツに襲いかかる。リツは飛び出てきた槍の突きを躱し、鎧武者にひと太刀浴びせんと距離を詰めた。
リツが鎧武者に応戦して時間を稼いでいる間に、おれは抱えていたナナヱを下ろし、彼女に目線を合わせて問いかけた。
「ナナヱ、よく聞け。あの鎧はお前の譚だ。お前自身の心なんだ」
「はなし……心?」
「ああ、譚ってのは心だ。お前の中に根付いた不安や恐怖の心が、加峯家にお前を閉じ込めようとしてるんだ」
加峯家の娘として結婚し、縁を結ぶことが出来ないのであれば、お前は役立たずだ。穀潰しだ。
――あの鎧武者は、大人たちから繰り返しそう言われ続け、根深く植え付けられた彼女の価値観。自分は加峯家の娘として、家の方針に従わなければならないのだ、という彼女の強迫観念――そして、加峯家で繰り返されてきた譚の断片が結びついて動き出したものだ。
「あの鎧がお前を捕まえようとしているのは、加峯家に従わなきゃいけないんだって、もう一人のお前が止めてるからでもあるんだ」
「では、諦めれば良いのですか? ナナヱが、旅に出ることを諦めれば、あの鎧は止まるのですか?」
確かに、ナナヱが大人しく加峯家に留まるという選択肢を取れば、あの鎧武者を鎮めることはできるだろう。だが、それは抜本的な解決方法ではない。お家の歪んだ価値観や評価に雁字搦めにされたナナヱの、旅に出てみたいという心は、永遠に抑圧されたままだ。
「それだけが選択肢じゃねえさ。正面からあの鎧をぶっ壊して逃げ切るって手もあるぜ」
「え……」
おっさんならナナヱの譚を読み解いて本にするところだろうが、あいにくおれはそんな技術など持ち合わせていない。なので、こうするしかないのだ。
「ナナヱ、お前は加峯家に留まるか? それとも、このままあいつから逃げ切って旅に出るか?」
ナナヱがしきりに唇を噛む。おれから逸らされた目線は、今まさにリツと戦っている鎧武者に向けられていた。
「どっちにするかはお前次第だ。旅を我慢してでも加峯家にいるべきだと思うならそうすればいい。加峯家を出て旅がしてみたいなら、今ここで宣言しな」
「……ナ、ナヱは……」
ナナヱの視線は鎧武者とおれの間を行き来する。
おれはリツの様子を見る。彼女も剣技を使ってまだなんとか持ち堪えているが、腕力では相手の方が一枚上手だ。ここまで走ってきて体力も消耗しているし、時間稼ぎもそろそろ厳しい頃合いだろう。
「ナナヱ。お前が自分の心に決着をつけるんだ。できるかできないかじゃなくて、お前がどうしたいかで決めな」
「ナナヱが、どうしたいか……?」
「大丈夫だ、おれとリツがついてる。勇気を出しておれに話してくれたんだ、お前はもう一人じゃねえよ」
おれはナナヱにそっと握り拳を差し出す。彼女からも握り拳を突き合わせてもらえるだろうかと期待して。しかし、期待したのとは違うナナヱの戸惑う顔を見たあとで、『しまった、これは唯助にしか通じねえんだった』と気づいた。
「ぶにゃ~……」
迷うナナヱの足元で、特徴的な猫の鳴き声があがる。見下ろせば、寅松の緑色の双眸が彼女をどこか心配そうに見つめていた。
「寅松……」
寅松はナナヱの傍に寄ると、彼女の足にぴとりと体を添わせた。おれにはその仕草が、絶対離れないぞと宣言しているかのように見えた。
「――そう、ですね。ナナヱには、ずっと寅松がいてくれたのです」
ナナヱは寅松の丸々とした体を抱き上げると、その頭を愛おしげに撫でた。
「決められそうか?」
そう問いかけて、ナナヱがおれの方へ再度向き直った時。惑い、曇っていた彼女の水色の目に、もはやその翳りはなかった。
「はい。ナナヱは、旅に出て強くなるのです。加峯家のためにではなく、ナナヱのために。ナナヱは加峯家に反抗してやるのです!」
「ぶにゃ!」
おれの差し出した握り拳に、寅松がナナヱに代わって肉球をポンとのせてきた。
「よく言った!」
言い切ったナナヱと寅松の頭をわしわし撫でてから、おれはすっくと立ち上がる。
堅牢なリツの防壁を今にも破ろうとしていた鎧武者は、途端に動きを鈍らせた。勿論、リツはその隙を見逃さない。威勢の揺らいだ鎧武者の足取りへさらに追い打ちをかけるように、棒切れで一文字に薙ぎ払う。
「怯んだわ!」
鎧武者の勢いが明らかに削がれたのを見るに、おれの目論見は上手くいったようだ。まるで地震が起きて崩れかけている積み木のように、危なげにぐらぐら揺れている。
「ナナヱ。今からあれを壊すけど、いいよな?」
「どうぞ粉々にやっちゃえなのです!」
「にゃ~ぅ!」
ナナヱは完全に吹っ切れたのか、寅松と共におれとリツを応援しだした。どうぞ粉々に、という彼女の言い方に、思わず笑ってしまいそうになる。
「なら、よく見とけよ。お前の見たがってた、夏目の柔術だ」
動きを察したリツが一歩引いたのを確認し、おれは足を踏み込む。一瞬の間さえ要らない――今では口に出して数える必要もないほど染みついた基本的な歩法を、心の中で一、二、三、と数えて――刹那の間に赤い鎧武者の懐へ迫る。
ナナヱとの手合わせで使ったのと同じものを、今度は手加減なしで、相手を確実に倒すための技として放つ。
鎧によって守られていない両の脇から掌底を叩き込み、鎖帷子伝いに両腕の装備を破壊する。後ろへ傾きかけたその肩を掴み、膝蹴りで腰部の接合を撃ち抜く。手刀を兜に振り下ろす。前屈みになった胴部を目掛けて踵を撃ち込む。
「行け、リツ! 一発ぶち込んでやれ!」
一部の無駄なく衝撃を与えられヒビが入った鎧――起き上がりかけたその体の胸部へ、リツの繰り出した刀の突きが加わる。
ただの棒切れによる刺突は鎧武者の体を貫き、細かなヒビを伝って隅々まで破壊し尽くした。鎧武者は文字通り、粉々に破砕されたのだった。
0
お気に入りに追加
15
あなたにおすすめの小説

夫の色のドレスを着るのをやめた結果、夫が我慢をやめてしまいました
氷雨そら
恋愛
夫の色のドレスは私には似合わない。
ある夜会、夫と一緒にいたのは夫の愛人だという噂が流れている令嬢だった。彼女は夫の瞳の色のドレスを私とは違い完璧に着こなしていた。噂が事実なのだと確信した私は、もう夫の色のドレスは着ないことに決めた。
小説家になろう様にも掲載中です

【完結】王太子妃の初恋
ゴールデンフィッシュメダル
恋愛
カテリーナは王太子妃。しかし、政略のための結婚でアレクサンドル王太子からは嫌われている。
王太子が側妃を娶ったため、カテリーナはお役御免とばかりに王宮の外れにある森の中の宮殿に追いやられてしまう。
しかし、カテリーナはちょうど良かったと思っていた。婚約者時代からの激務で目が悪くなっていて、これ以上は公務も社交も難しいと考えていたからだ。
そんなカテリーナが湖畔で一人の男に出会い、恋をするまでとその後。
★ざまぁはありません。
全話予約投稿済。
携帯投稿のため誤字脱字多くて申し訳ありません。
報告ありがとうございます。

あなたの子ですが、内緒で育てます
椿蛍
恋愛
「本当にあなたの子ですか?」
突然現れた浮気相手、私の夫である国王陛下の子を身籠っているという。
夫、王妃の座、全て奪われ冷遇される日々――王宮から、追われた私のお腹には陛下の子が宿っていた。
私は強くなることを決意する。
「この子は私が育てます!」
お腹にいる子供は王の子。
王の子だけが不思議な力を持つ。
私は育った子供を連れて王宮へ戻る。
――そして、私を追い出したことを後悔してください。
※夫の後悔、浮気相手と虐げられからのざまあ
※他サイト様でも掲載しております。
※hotランキング1位&エールありがとうございます!

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

妻のち愛人。
ひろか
恋愛
五つ下のエンリは、幼馴染から夫になった。
「ねーねー、ロナぁー」
甘えん坊なエンリは子供の頃から私の後をついてまわり、結婚してからも後をついてまわり、無いはずの尻尾をブンブン振るワンコのような夫。
そんな結婚生活が四ヶ月たった私の誕生日、目の前に突きつけられたのは離縁書だった。

未亡人クローディアが夫を亡くした理由
臣桜
キャラ文芸
老齢の辺境伯、バフェット伯が亡くなった。
しかしその若き未亡人クローディアは、夫が亡くなったばかりだというのに、喪服とは色ばかりの艶やかな姿をして、毎晩舞踏会でダンスに興じる。
うら若き未亡人はなぜ老齢の辺境伯に嫁いだのか。なぜ彼女は夫が亡くなったばかりだというのに、楽しげに振る舞っているのか。
クローディアには、夫が亡くなった理由を知らなければならない理由があった――。
※ 表紙はニジジャーニーで生成しました
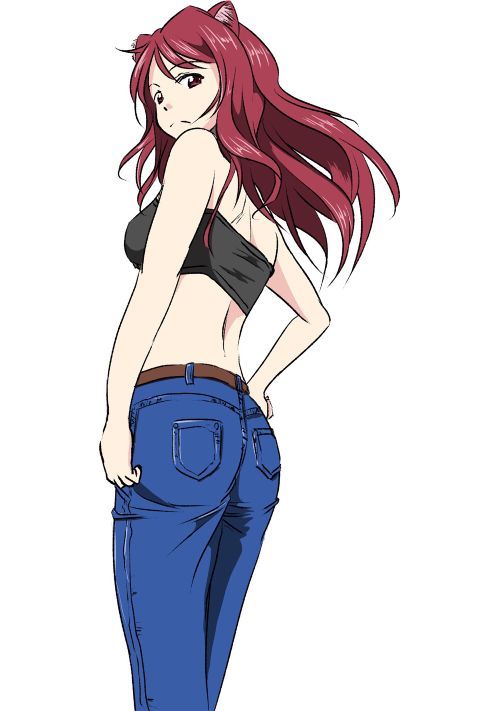
遥か
カリフォルニアデスロールの野良兎
キャラ文芸
鶴木援(ツルギタスケ)は、疲労状態で仕事から帰宅する。何も無い日常にトラウマを抱えた過去、何も起きなかったであろう未来を抱えたまま、何故か誤って監獄街に迷い込む。
生きることを問いかける薄暗いロー・ファンタジー。
表紙 @kafui_k_h

諦めて溺愛されてください~皇帝陛下の湯たんぽ係やってます~
七瀬京
キャラ文芸
庶民中の庶民、王宮の洗濯係のリリアは、ある日皇帝陛下の『湯たんぽ』係に任命される。
冷酷無比極まりないと評判の皇帝陛下と毎晩同衾するだけの簡単なお仕事だが、皇帝陛下は妙にリリアを気に入ってしまい……??
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















