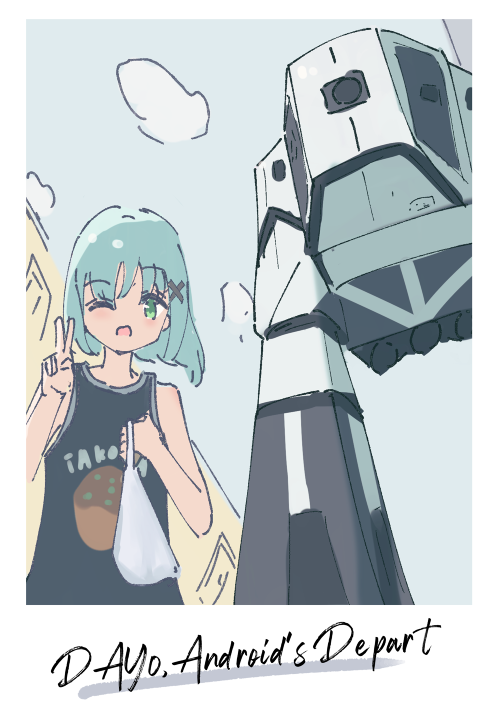18 / 63
八月『先生の匣庭』
その二
しおりを挟む
夏目世助。菜摘芽唯助と血を分けた唯一無二の双子の兄。弟と惚れた娘を取り合い、家の跡目争いに勝ち、結果的に唯助を奈落の底へ落とした張本人。
――そんなことを言って世助を咎めるのは、実は実にお門違いなことである。精神的に追い詰められた当時の唯助にしてみれば酷いいじめにあったと感じるのも無理はないが、状況を客観視すれば、世助は実力で弟に勝っただけにすぎない。惚れた娘に気に入られた弟に嫉妬したのは確かだが、だからといってそれと後継争いは関係ない。弟と競争するにあたって世助は不正など一切しておらず、並々ならぬ努力によって勝ったのだから、むしろ正攻法である。唯助は地力で追いつくことができなかった。それだけだ。
唯助とて四月の頃は世助を恨めしいと思うこともあったが、今となってはそんな筋合いもなかったのだと理解していた。やりたくなくても、いつかはしなければいけなかった跡継ぎ競争――それを、実は自分よりも強かった世助が先に仕掛けてきただけ。取り巻いていた状況が唯助にとって悪く作用しただけ。世助と仲違いしてしまったのは、今までずっと噛み合っていた歯車がいくつかの要因によって外れたせいだ。
――単純に事だけを見つめてしまえば、それだけの話なのだ。
*****
「紫色の浴衣のお兄ちゃんなら、あっちのほうに歩いてったよ」
「玩具とかお菓子とかいっぱい持ってて、いらないからあげるって配ってた」
子供たちが指をさすのは、やはりみな同じ方向だった。唯助にそっくりな少年は、町の北端に向かっているらしい。
「それにしても、本当にそっくりねぇ。着物の色が同じだったら分からなかったわぁ」
二人の子供と手を繋ぐ母親らしき女性が唯助を見て言う。このような反応も、ここに来るまでに何度もされた。
「皆さんが初見で勘違いしているということは、それだけ唯助さんとお兄さんは似ていらっしゃるのですね」
「似てるっつーか、同じ人間が二人いたようなもんだったんでしょう。子供の頃に悪戯で着物の色を入れ替えても、バレたことなんて一回もありませんでしたから」
柔術の実力差が浮き彫りになるまでは、夏目家の道場の誰もが彼らを見分けることができなかった。力の強さ、機動性、動きの癖までも似ていた二人は、試合を仕切る者たちを度々困らせていた。髪の毛を括る紐や腕輪などの色だけが彼らを区別する目印であった。
棚葉町の中心を貫く大通りを北へ進みながら、三八は先を歩く唯助に問う。
「本当に良いのか? 会ったとしても、まともに会話できん可能性もあるぞ」
「そうかもしれないですね。その時はそれでいいかなって思ってます」
唯助の受け答えは、驚くほどあっさりしていた。四ヶ月前、死にたいほどつらい気持ちで思い悩んでいたとは思えないほど、あっさりしすぎていた。あまりのあっさり加減に、音音も、三八でさえも目を丸くしている。否、三八の目は前髪で見えないのだけど。
「でも、このまま見て見ぬふりはしたくないです。ちゃんと道場の跡継ぎになってたなら、世助がこんなところにいられるわけない。きっと、世助にはなにかがあったんです」
唯助は何か目印でもあるように、世助を探すというよりは、世助に向かっていくように、迷うことなく歩く。
「嫌な予感がするんです」
ただの杞憂であればいいのだが。会話は続けながらも、唯助はひたすらに足を動かされるように歩く。
「唯助。分かった。気持ちは分かったから、少し歩く速さを緩めてはくれまいか」
「……あれ?」
唯助はてっきり、三八がすぐ後ろをついてきているものとばかり考えていた。しかし、後方を振り返れば、三八は十歩以上離れたところにいた。傍には少し息を弾ませているらしい音音もいる。
世助を探してもう長く歩き回った。音音が息を弾ませるのも無理はない。唯助は踵を返し、二人のもとへ戻る。
「すみません……少し、足の指が」
「……擦れているではないか! 我慢していたのか?」
音音が三八に促されながら道端の石の上に腰をかける。下駄を脱いだ足の指の間には確かに鼻緒で擦れた痕跡があった。
「すいません、姐さん! おれのせいで無理させちゃって……」
「大丈夫ですよ、少し擦れただけですから。お気になさらないでくださいまし」
しかし、鼻緒に付着した血が赤黒く乾いてこびりついているのを見ると、唯助は音音に対し申し訳なくなった。彼女のことだ、唯助に余計な気を遣わせまいと長く我慢していたのだろう。
「この程度なら術本で治せるだろうが……」
医者でもない三八では、術本を用いてもせいぜい応急処置しかできない。音音を歩かせれば、また擦れてしまう。三八は続きの台詞を引っ込めたようだが、恐らくはそう言おうとしたのだろう。これ以上音音に足を痛めさせてまで付き合わせるわけにもいくまいと思いつつ、しかし、どうしても兄が気になる唯助は
「じゃあ、旦那と姐さんは先に家に帰っていてください。おれもあとから遅くならないうちに帰りますから……」
と提案した。
「駄目だ」
間髪入れずに三八は提案を却下する。
「初めの頃に言っただろう。この町では、夜に何かが蠢くと。賑やかな夜に複数で出かけるならいい。だが、一人で歩くのは絶対に駄目だ」
常日頃からへらへらしている温厚な三八にしては珍しく真剣で、緊張感のある声だった。
「じゃあ、今夜は諦めて――」
「駄目です!」
今度は音音が、言い終わらないうちに声を上げる。常日頃から柔らかい口調で話す音音がこんなふうに声を大きく発するのも、同じくらい珍しいことであった。
「お兄さんに何かあったかもしれないのでしょう? 確かめなくてはいけないのでしょう? お兄さんの一大事かもしれないなら、わたくしの足の怪我など些細なことでございます。嫌な予感がするならなおのこと、そちらを優先させるべきですわ」
いつも柔らかく微笑んでいる音音が、今は微笑みのひと欠片も感じられない表情で訴えかけている。当事者の唯助よりも深刻な顔をしていた。
「でも、おれの思い過ごしかもしれませんし……」
「何もなかったならなかったで、それで良いではありませんか。無事を確認して、大いに安心すれば良いのです」
だから、行ってあげて。
と、音音が続けようとしたところで、三人の誰のものでもない声が突如割り込んだ。
「おい」
三人の誰でもない声ではあったが。三人の中の、唯助によく似た声であった。――否。よく似た、というよりも――全く同じ声だ。
声がした方を振り返れば、紫色の浴衣を着た、唯助と瓜二つの少年が立っていた。
見紛うはずもない、鏡写しの顔。
目立つ茶髪に、少しばかり赤く色づいた頬。
「世助!」
探し求めていた兄の姿を見て、唯助は二人を置いて一目散に駆け寄った。
「お前、どうしてここに!」
何があったんだ? と続けようとして、唯助は世助の肩を掴む前に立ち止まる。
「……? なあ、お前。おれの勘違いなら謝るけど」
違和。
幾度となく見て、幾度となく同じ空気を吸って、幾度となく同じ気配を感じてきた、双子の兄の姿から感じる――漠然としながら、確としてある、違和。
慣れすぎてしまったがゆえに、説明することができない双子の兄の感覚とは確かに異なる――匂い、気配。
「――本当に世助なのか?」
なんとなく感じただけの違和感から自然と発してしまった、唯助のそのひと言。しかし、それは決して唯助の勘違いなどではなかった。
「離れろ、唯助!! それは君の兄じゃない!!」
後方からの警鐘。緊迫感をまとって、今まで聞いたこともないような声で、三八が唯助に向かって叫んでいた。
それと同時に。
「うわっ!?」
がしり、と。唯助の腕を瓜二つの少年の手が掴む。掴んで、引きずり込む。
唯助が再び少年の方を見れば、そこには――にたりとした、真っ黒な悪意に満ちた笑顔があった。
「つかまえた」
鏡写しの少年の背後から――巨大な人間の歯が覗く。がっぱりと、白い歯が生え揃う顎を外れんばかりに大きく開けて、少年ごと唯助を喰おうとしていた。
「唯助ッ!!」
三八が駆けるが、並みの人間の速さでは既に三十歩ほども離れている両者に追いつかない。
唯助はにたりと笑う少年から逃れようとするが、しかし全力で抵抗することができない。兄の顔を、殴ることができないのだ。
(――喰われる)
唯助は、確信した。
「ボサッとしてんじゃねえ!!」
確信と同時に、さらに別の声が割り込んだ。
それはまたしても、唯助と全く同じ声。
唯助の腕を掴む少年とも瓜二つの――紫色の浴衣を着た、本物の少年だった。
「よす――」
名を呼びきるその前に、巨大な口は飲み込んだ。
唯助と、偽物の世助と、本物の世助。
全く同じ顔と声をした三者を、全て丸ごと、丸呑みにした。
「唯助ッ!」
残念ながら、三八が呼び出した黒い蛇――糜爛の処女は間に合わなかった。蛇の牙が到達する寸前で、口は全員を飲み込んで消えた。
「唯助さん!」
音音の声が虚空の闇に溶ける。建物の少ない開けた空間で、声は反射することなく溶ける。
「クソっ! 間に合わなかった!」
行き場のなくなった黒い蛇が、虚空をさまよっていた。見失ったのではない、双子を飲み込んだ口は、一瞬でそこからいなくなったのだ。
「そんな……あの子たちは?」
「唯助は大丈夫だ、まだ栞を通して気配を感じる。飛び込んだあの子も無事だろう」
黒い蛇が三八の腕に巻き付き、するすると肩まで登ってくる。三八はそれの喉を指で撫でた。
「しかし、あの世助という少年。禁書の毒に素手で干渉するとは」
「どういうことですか?」
「あの子、あの口をあろうことか素手でこじ開けてすべり込みおった」
唯助が呑まれようとした、その一瞬。三八は確かに見た。
結果的に呑まれはしたものの――割り込んだ本物の世助は、唯助の頭を噛み砕きそうだったその歯をしっかと掴み、一瞬こじ開けたのである。
禁書の毒に、人間の攻撃は通用しない。六月、禁書『ある女』に対して、柄田と三八が禁書の毒を武器にしたように、禁書の毒には同じ禁書の毒でしか干渉することができないのだ。
――一部の例外を除けぱ。
「間違いないよ。あの子は『先天干渉者』だ」
霊能力者といった飛び抜けた第六感を持つものが、霊や魂などと交信することができるように。禁書の毒を用いることなく、自らの身体のみで干渉することができる者も、この世界には稀にいる。それが『先天干渉者』。
職業柄『先天干渉者』を幾度か目にしていた三八は、世助がそれだったことにはさして驚いていない。三八が驚いていたのは、世助のその性質がさらに輪をかけて稀であったからだ。
「いくら『先天干渉者』とはいえ、訓練していない状態なら数秒触れただけでも上等と言われるのに。こじ開けるなんて、桁が違いすぎる。あんな逸材、帝国司書が見たら目ん玉ひん剥くぞ」
*****
「………け。 すけ。おい! 起きろ、唯助!」
怒号にも似た声で体が大きく揺さぶられる。うっすら視界に光がさしたところで、両の頬をバシバシと強く叩かれる。皮の硬くなった手による容赦ない平手打ちの痛みで、唯助はようやく意識を浮上させた。
「いてえ……」
「やっと起きたか」
徐々にハッキリしていく輪郭。焦げ茶色の丸い瞳。きゅっと結んだ口に、赤みのある頬。鏡を見ているような姿。
目を瞬かせ、唯助はもう一度その顔を見る。
「……世助?」
「そうだよ、世助だよ。早く目を覚ませ、寝ぼけっ面に水ぶっかけんぞ」
つってもねえけどな。と、世助は掴んでいた萌木色の襟を離す。辺りを見渡せば、そこは暗闇の中。世助も唯助も、お互いの姿しか見えていない。それでもなお、唯助はハッキリしなかった。ここは確かに現実だが、夢を見ているようだった。現実味がなかった。
「……なあ、世助だよな? 本当の本当に世助なんだよな?」
「あ? 寝ぼけすぎじゃねえか、お前」
面倒くさそうに舌打ちする世助。しかし、唯助に現実味がなかなか湧いてこないのも無理はない。
二度と会えないと思っていた双子の兄に再会し、再会したと思ったらそれは偽物で、さらに巨大な口にあーんと食われかけて、そこへ本物の双子の兄が突然飛び込んできて。
驚愕に次ぐ驚愕。雪崩のような、息つく間もない驚愕。目の前に世助が現れた時点で追いついていなかった思考に、次々と信じられない状況が重なってしまったため、唯助は混乱していたのである。
「あのなぁ。まだ寝ぼけてんなら、お前がガキの頃に言ってた変な寝言を古い順から言ってやろうか? 『おしりがくるー! う〇こー!』から」
「ぶっ」
それは唯助にとっては思い出すのも恥ずかしい、寝言集の序章である。いったい普段から何を見てどんな想像をすれば飛び出してくるのか分からないそれらを全て言われてはたまらぬと、唯助は慌てて脳を回転させた。
「うわ、世助だ。本当に世助なんだ」
「おう」
しかし、訣別から数ヶ月ぶりに再会した双子は、状況を十分に喜べない。巨大な口に呑まれたこの状況もそうだが、なにより。
「……逃げねえのかよ」
「逃げる気なんてねえよ」
四ヶ月前まで彼らを縛っていた、いくつものしがらみ。追い詰められていた元・夏目唯助と、追い詰めた張本人・夏目世助。もうなにも気にしていない唯助はともかく、弟を蹴落とした世助にとって、この状況は随分と居心地が悪いらしい。
「変なものを寄せつけがちなのは変わってねえんだな、お前」
「そういうお前は、またおれを助けてくれたんだな。……おれはもう、夏目家の人間じゃねえのに」
「別に、助けようなんて思ってもいねえよ。身体が勝手に動いただけだ」
しかし、状況が状況だけに、会話せざるを得ない二人はぎこちなく会話をする。目をそらし、ぶっきらぼうに振る舞う世助。いたたまれなさを感じている彼を刺激しないよう努める唯助。まるで目隠ししながらお互いを杖で探り合うような会話だ。
「でも、世助。なんでお前、おれのところに駆けつけて……」
「たまたまだ」
世助は目を合わせないまま、やや食い気味に答える。
「おかしいと思ったよ。おれは金魚屋なんて行ってねえのに、すれ違ったガキどもに下手くそだのへなちょこだの馬鹿にされた」
「うっ」
「そんで、金魚屋の前に通りかかって『七本さんとはぐれたのか?』って店のおやじに聞かれて気づいた。七本って、お前を雇ってる貸本屋のおっさんのことだろ」
「あ……知ってたんだ、旦那のこと」
「お前が夏目家と縁切るって話聞かされた時、名前だけ父上から聞いてた。で、適当にふらふらしてたら、なんかヤバそうなデカブツに食われかけてるお前を見つけたわけ」
世助は目をずっと合わせない。唯助が自分を嫌がらないのがさらにいたたまれないらしく、唯助から目をそらしたままだ。
「また変なもんに巻き込まれやがって。昔っから気をつけろっつってただろうが。おれが駆けつけてなかったら、今頃粉々に噛み砕かれてたぞ」
「うっ、ごめん……」
ツンケンしてるなぁと唯助は思いつつ、それには触れずにただ世助の乱暴な言葉を受け入れる。いらない刺激してしまっては、せっかく会えた兄との会話が打ち切られてしまうかもしれないと、刺々しい世助の言葉を受け入れていた。
「にしてもよ、ここはなんだ? あの馬鹿でかい口した化け物の腹の中には違いねえけどよ」
歩く。同じ歩幅で。同じ速度で。寸分違わず、双子は闇を歩く。二人に見えているのはお互いの姿のみだ。しかしそれも間近にいるから。一歩でも歩みがズレれば見失ってしまいそうな闇の中で、双子ははぐれないように手を繋いでいた。ちなみに、先にそれを提案したのは唯助である。
「けど、腹の中ってわりには妙だよな。外を歩いてるみてえだ。踵を落としてみても、うんともすんとも言わねえ。だだっ広くて、いくら歩いても壁に当たらねえ。一体全体どうなってやがんだ」
世助は度々、自分たちの足と接する地面の感触を探っているが、つま先でつついても踵で蹴っても変わらない。たまに砂利があるくらいの踏み固められた地面のようだが、そもそもこの暗闇で視界がはっきりしないので、本当に地面なのかも判然としない。
「さあ。でも、もしかしたら…これも、禁書の【毒】の仕業かもしんねえ」
「禁書の【毒】? なんだそれ」
これこれこうこうかくかくしかじか。唯助は三八に授けられた教えをそのまま世助に伝える。
「ふーん。人に危害を加える本ねえ。人間の生み出した本が人間を襲う、なんてどんな皮肉だ」
確かに。唯助はそれに頷く。なあ、と世助が唯助に投げかける。
「お前がたまに襲われてたのも、それだったんじゃねえのか」
実は唯助もそうだったのではないかと思っていたところである。
そう、六月に遭遇した禁書の毒・紫蔓に狙われたことといい、今回のことといい――唯助が異形に襲われることは、実はそう珍しいことではなかった。唯助の身のまわりでは、度々妙なことが起きていた。唯助のお化け嫌いはこれのせいである。
そして、唯助を襲う異形を退治していたのは、決まって世助であった。初めて出くわした時は、まさかお化けに拳での物理攻撃が通じるとは思わなかったが。
「おれを襲ってたのがもし本当に禁書の毒だったら、こうやって姿を似せて分散させなきゃ死んでたかもしれねえな」
彼らは双子であるから、自己同一性が生まれる前段階の時点では姿も性格も似ていて瓜二つだったが、自己同一性が生まれたこの歳になっても瓜二つなのは、あまりに不自然だ。いくら双子といえども違う人間。当然、性格にも微妙な違いが出てくるし、好みも異なる。双子だから姿も中身も全く同じ、というのは不自然なのであり、差異があることこそが自然なのだ。
不自然に似ているのは、彼らが意図的に似せていたからだ。理由のひとつは、唯助の身を守るために、二人が一緒になるよう揃えたから。唯助が狙われる確率を少しでも下げ、世助が間違って狙われる確率を少しでも上げるため。双子の彼らにしかとれない防御術だった。
「……でも待てよ? 禁書の毒には、禁書の毒でしか攻撃ができないって、旦那が言ってた。普通の攻撃は通用しないって、知り合いの帝国司書さんも言ってたし」
「は? んなバカな。おれは普通に触れるし、ぶん殴れるぜ。お前も殴れるだろ?」
「試したことねえし、試したくもねえよ。戦う以前におっかねえもん」
「弱腰だなぁ」
「世助が血気盛んなんだよ。普通、お化けだと思ったら咄嗟に殴れねえだろ」
「通用するって分かってたら反射で殴るから、お前の殴れねえって感覚の方がむしろ分かんねえ」
「喧嘩屋かよ」
「うっせえヘタレ」
二人になると決まって始まる軽口。両者の明らかな違いを孕んだ軽口。実は喧嘩っ早い世助と、実は穏健派の唯助による、兄弟ならではの軽口である。
「多分、旦那に聞けば分かるのかな」
「あの妙ちきりんなおっさんか? 胡散臭くねえか?」
「妙ちきりんなのも胡散臭いのもそうだけど、あの人はそれ以上に色んなことを知ってるよ。本のことにかけては何でも。帝国司書さんのお墨付きだぜ」
「ふーん」
「変な人だけど、基本的にはいい人だし。なんでも知ってる先生みたいな感じ」
「ふーん」
「姐さんもすごくいい人でさ、飯もめちゃくちゃうめえんだ」
「……ふーん」
最初の居心地悪さが少し和らいでいた世助は、ここでまたばつが悪そうな顔をする。
「すげえ仲が良くてさ、毎日暑っ苦しいくらいベタベタしてんの。おれがいるのにお構いなし」
「……そう」
胸が温まるまま、嬉々として現状を語る唯助に対し――世助の表情は深く、より深く沈んでいた。唯助がそんな世助に気づかないなか、世助はふう、とひとつため息を漏らす。
「楽しそうだな。お前」
「まあな。実際、ほんとに楽しい。師範の稽古は…正直つまんなかったけど、旦那に教わるのは結構すきだぜ」
「…………ふーん」
沈み、沈んで。ようやく気づいた唯助が怪訝そうな顔つきになるのとちょうど入れ替わるようにして――世助は、ここに来てようやく心から笑った。
「よかったな、幸せになれて」
――心からの、自嘲であった。
この場合は、さすが双子というべきか。さすが長く一緒にいた仲というべきか。いずれにしてもどちらにしても、唯助には世助の笑顔が『自嘲』だとすぐに分かった。
そして思い出した。とびきりの緊急事態が続いていたせいですっかり頭から吹っ飛んでいた、世助を探していた理由。
「……世助? お前、なにが――」
唯助はそれを問おうとしたが、折の悪いことに、先は阻まれた。
「お兄ちゃんたち、新入り?」
いつの間にか開けていた視界の数歩先に、二人を見つめる子供がいた。
――そんなことを言って世助を咎めるのは、実は実にお門違いなことである。精神的に追い詰められた当時の唯助にしてみれば酷いいじめにあったと感じるのも無理はないが、状況を客観視すれば、世助は実力で弟に勝っただけにすぎない。惚れた娘に気に入られた弟に嫉妬したのは確かだが、だからといってそれと後継争いは関係ない。弟と競争するにあたって世助は不正など一切しておらず、並々ならぬ努力によって勝ったのだから、むしろ正攻法である。唯助は地力で追いつくことができなかった。それだけだ。
唯助とて四月の頃は世助を恨めしいと思うこともあったが、今となってはそんな筋合いもなかったのだと理解していた。やりたくなくても、いつかはしなければいけなかった跡継ぎ競争――それを、実は自分よりも強かった世助が先に仕掛けてきただけ。取り巻いていた状況が唯助にとって悪く作用しただけ。世助と仲違いしてしまったのは、今までずっと噛み合っていた歯車がいくつかの要因によって外れたせいだ。
――単純に事だけを見つめてしまえば、それだけの話なのだ。
*****
「紫色の浴衣のお兄ちゃんなら、あっちのほうに歩いてったよ」
「玩具とかお菓子とかいっぱい持ってて、いらないからあげるって配ってた」
子供たちが指をさすのは、やはりみな同じ方向だった。唯助にそっくりな少年は、町の北端に向かっているらしい。
「それにしても、本当にそっくりねぇ。着物の色が同じだったら分からなかったわぁ」
二人の子供と手を繋ぐ母親らしき女性が唯助を見て言う。このような反応も、ここに来るまでに何度もされた。
「皆さんが初見で勘違いしているということは、それだけ唯助さんとお兄さんは似ていらっしゃるのですね」
「似てるっつーか、同じ人間が二人いたようなもんだったんでしょう。子供の頃に悪戯で着物の色を入れ替えても、バレたことなんて一回もありませんでしたから」
柔術の実力差が浮き彫りになるまでは、夏目家の道場の誰もが彼らを見分けることができなかった。力の強さ、機動性、動きの癖までも似ていた二人は、試合を仕切る者たちを度々困らせていた。髪の毛を括る紐や腕輪などの色だけが彼らを区別する目印であった。
棚葉町の中心を貫く大通りを北へ進みながら、三八は先を歩く唯助に問う。
「本当に良いのか? 会ったとしても、まともに会話できん可能性もあるぞ」
「そうかもしれないですね。その時はそれでいいかなって思ってます」
唯助の受け答えは、驚くほどあっさりしていた。四ヶ月前、死にたいほどつらい気持ちで思い悩んでいたとは思えないほど、あっさりしすぎていた。あまりのあっさり加減に、音音も、三八でさえも目を丸くしている。否、三八の目は前髪で見えないのだけど。
「でも、このまま見て見ぬふりはしたくないです。ちゃんと道場の跡継ぎになってたなら、世助がこんなところにいられるわけない。きっと、世助にはなにかがあったんです」
唯助は何か目印でもあるように、世助を探すというよりは、世助に向かっていくように、迷うことなく歩く。
「嫌な予感がするんです」
ただの杞憂であればいいのだが。会話は続けながらも、唯助はひたすらに足を動かされるように歩く。
「唯助。分かった。気持ちは分かったから、少し歩く速さを緩めてはくれまいか」
「……あれ?」
唯助はてっきり、三八がすぐ後ろをついてきているものとばかり考えていた。しかし、後方を振り返れば、三八は十歩以上離れたところにいた。傍には少し息を弾ませているらしい音音もいる。
世助を探してもう長く歩き回った。音音が息を弾ませるのも無理はない。唯助は踵を返し、二人のもとへ戻る。
「すみません……少し、足の指が」
「……擦れているではないか! 我慢していたのか?」
音音が三八に促されながら道端の石の上に腰をかける。下駄を脱いだ足の指の間には確かに鼻緒で擦れた痕跡があった。
「すいません、姐さん! おれのせいで無理させちゃって……」
「大丈夫ですよ、少し擦れただけですから。お気になさらないでくださいまし」
しかし、鼻緒に付着した血が赤黒く乾いてこびりついているのを見ると、唯助は音音に対し申し訳なくなった。彼女のことだ、唯助に余計な気を遣わせまいと長く我慢していたのだろう。
「この程度なら術本で治せるだろうが……」
医者でもない三八では、術本を用いてもせいぜい応急処置しかできない。音音を歩かせれば、また擦れてしまう。三八は続きの台詞を引っ込めたようだが、恐らくはそう言おうとしたのだろう。これ以上音音に足を痛めさせてまで付き合わせるわけにもいくまいと思いつつ、しかし、どうしても兄が気になる唯助は
「じゃあ、旦那と姐さんは先に家に帰っていてください。おれもあとから遅くならないうちに帰りますから……」
と提案した。
「駄目だ」
間髪入れずに三八は提案を却下する。
「初めの頃に言っただろう。この町では、夜に何かが蠢くと。賑やかな夜に複数で出かけるならいい。だが、一人で歩くのは絶対に駄目だ」
常日頃からへらへらしている温厚な三八にしては珍しく真剣で、緊張感のある声だった。
「じゃあ、今夜は諦めて――」
「駄目です!」
今度は音音が、言い終わらないうちに声を上げる。常日頃から柔らかい口調で話す音音がこんなふうに声を大きく発するのも、同じくらい珍しいことであった。
「お兄さんに何かあったかもしれないのでしょう? 確かめなくてはいけないのでしょう? お兄さんの一大事かもしれないなら、わたくしの足の怪我など些細なことでございます。嫌な予感がするならなおのこと、そちらを優先させるべきですわ」
いつも柔らかく微笑んでいる音音が、今は微笑みのひと欠片も感じられない表情で訴えかけている。当事者の唯助よりも深刻な顔をしていた。
「でも、おれの思い過ごしかもしれませんし……」
「何もなかったならなかったで、それで良いではありませんか。無事を確認して、大いに安心すれば良いのです」
だから、行ってあげて。
と、音音が続けようとしたところで、三人の誰のものでもない声が突如割り込んだ。
「おい」
三人の誰でもない声ではあったが。三人の中の、唯助によく似た声であった。――否。よく似た、というよりも――全く同じ声だ。
声がした方を振り返れば、紫色の浴衣を着た、唯助と瓜二つの少年が立っていた。
見紛うはずもない、鏡写しの顔。
目立つ茶髪に、少しばかり赤く色づいた頬。
「世助!」
探し求めていた兄の姿を見て、唯助は二人を置いて一目散に駆け寄った。
「お前、どうしてここに!」
何があったんだ? と続けようとして、唯助は世助の肩を掴む前に立ち止まる。
「……? なあ、お前。おれの勘違いなら謝るけど」
違和。
幾度となく見て、幾度となく同じ空気を吸って、幾度となく同じ気配を感じてきた、双子の兄の姿から感じる――漠然としながら、確としてある、違和。
慣れすぎてしまったがゆえに、説明することができない双子の兄の感覚とは確かに異なる――匂い、気配。
「――本当に世助なのか?」
なんとなく感じただけの違和感から自然と発してしまった、唯助のそのひと言。しかし、それは決して唯助の勘違いなどではなかった。
「離れろ、唯助!! それは君の兄じゃない!!」
後方からの警鐘。緊迫感をまとって、今まで聞いたこともないような声で、三八が唯助に向かって叫んでいた。
それと同時に。
「うわっ!?」
がしり、と。唯助の腕を瓜二つの少年の手が掴む。掴んで、引きずり込む。
唯助が再び少年の方を見れば、そこには――にたりとした、真っ黒な悪意に満ちた笑顔があった。
「つかまえた」
鏡写しの少年の背後から――巨大な人間の歯が覗く。がっぱりと、白い歯が生え揃う顎を外れんばかりに大きく開けて、少年ごと唯助を喰おうとしていた。
「唯助ッ!!」
三八が駆けるが、並みの人間の速さでは既に三十歩ほども離れている両者に追いつかない。
唯助はにたりと笑う少年から逃れようとするが、しかし全力で抵抗することができない。兄の顔を、殴ることができないのだ。
(――喰われる)
唯助は、確信した。
「ボサッとしてんじゃねえ!!」
確信と同時に、さらに別の声が割り込んだ。
それはまたしても、唯助と全く同じ声。
唯助の腕を掴む少年とも瓜二つの――紫色の浴衣を着た、本物の少年だった。
「よす――」
名を呼びきるその前に、巨大な口は飲み込んだ。
唯助と、偽物の世助と、本物の世助。
全く同じ顔と声をした三者を、全て丸ごと、丸呑みにした。
「唯助ッ!」
残念ながら、三八が呼び出した黒い蛇――糜爛の処女は間に合わなかった。蛇の牙が到達する寸前で、口は全員を飲み込んで消えた。
「唯助さん!」
音音の声が虚空の闇に溶ける。建物の少ない開けた空間で、声は反射することなく溶ける。
「クソっ! 間に合わなかった!」
行き場のなくなった黒い蛇が、虚空をさまよっていた。見失ったのではない、双子を飲み込んだ口は、一瞬でそこからいなくなったのだ。
「そんな……あの子たちは?」
「唯助は大丈夫だ、まだ栞を通して気配を感じる。飛び込んだあの子も無事だろう」
黒い蛇が三八の腕に巻き付き、するすると肩まで登ってくる。三八はそれの喉を指で撫でた。
「しかし、あの世助という少年。禁書の毒に素手で干渉するとは」
「どういうことですか?」
「あの子、あの口をあろうことか素手でこじ開けてすべり込みおった」
唯助が呑まれようとした、その一瞬。三八は確かに見た。
結果的に呑まれはしたものの――割り込んだ本物の世助は、唯助の頭を噛み砕きそうだったその歯をしっかと掴み、一瞬こじ開けたのである。
禁書の毒に、人間の攻撃は通用しない。六月、禁書『ある女』に対して、柄田と三八が禁書の毒を武器にしたように、禁書の毒には同じ禁書の毒でしか干渉することができないのだ。
――一部の例外を除けぱ。
「間違いないよ。あの子は『先天干渉者』だ」
霊能力者といった飛び抜けた第六感を持つものが、霊や魂などと交信することができるように。禁書の毒を用いることなく、自らの身体のみで干渉することができる者も、この世界には稀にいる。それが『先天干渉者』。
職業柄『先天干渉者』を幾度か目にしていた三八は、世助がそれだったことにはさして驚いていない。三八が驚いていたのは、世助のその性質がさらに輪をかけて稀であったからだ。
「いくら『先天干渉者』とはいえ、訓練していない状態なら数秒触れただけでも上等と言われるのに。こじ開けるなんて、桁が違いすぎる。あんな逸材、帝国司書が見たら目ん玉ひん剥くぞ」
*****
「………け。 すけ。おい! 起きろ、唯助!」
怒号にも似た声で体が大きく揺さぶられる。うっすら視界に光がさしたところで、両の頬をバシバシと強く叩かれる。皮の硬くなった手による容赦ない平手打ちの痛みで、唯助はようやく意識を浮上させた。
「いてえ……」
「やっと起きたか」
徐々にハッキリしていく輪郭。焦げ茶色の丸い瞳。きゅっと結んだ口に、赤みのある頬。鏡を見ているような姿。
目を瞬かせ、唯助はもう一度その顔を見る。
「……世助?」
「そうだよ、世助だよ。早く目を覚ませ、寝ぼけっ面に水ぶっかけんぞ」
つってもねえけどな。と、世助は掴んでいた萌木色の襟を離す。辺りを見渡せば、そこは暗闇の中。世助も唯助も、お互いの姿しか見えていない。それでもなお、唯助はハッキリしなかった。ここは確かに現実だが、夢を見ているようだった。現実味がなかった。
「……なあ、世助だよな? 本当の本当に世助なんだよな?」
「あ? 寝ぼけすぎじゃねえか、お前」
面倒くさそうに舌打ちする世助。しかし、唯助に現実味がなかなか湧いてこないのも無理はない。
二度と会えないと思っていた双子の兄に再会し、再会したと思ったらそれは偽物で、さらに巨大な口にあーんと食われかけて、そこへ本物の双子の兄が突然飛び込んできて。
驚愕に次ぐ驚愕。雪崩のような、息つく間もない驚愕。目の前に世助が現れた時点で追いついていなかった思考に、次々と信じられない状況が重なってしまったため、唯助は混乱していたのである。
「あのなぁ。まだ寝ぼけてんなら、お前がガキの頃に言ってた変な寝言を古い順から言ってやろうか? 『おしりがくるー! う〇こー!』から」
「ぶっ」
それは唯助にとっては思い出すのも恥ずかしい、寝言集の序章である。いったい普段から何を見てどんな想像をすれば飛び出してくるのか分からないそれらを全て言われてはたまらぬと、唯助は慌てて脳を回転させた。
「うわ、世助だ。本当に世助なんだ」
「おう」
しかし、訣別から数ヶ月ぶりに再会した双子は、状況を十分に喜べない。巨大な口に呑まれたこの状況もそうだが、なにより。
「……逃げねえのかよ」
「逃げる気なんてねえよ」
四ヶ月前まで彼らを縛っていた、いくつものしがらみ。追い詰められていた元・夏目唯助と、追い詰めた張本人・夏目世助。もうなにも気にしていない唯助はともかく、弟を蹴落とした世助にとって、この状況は随分と居心地が悪いらしい。
「変なものを寄せつけがちなのは変わってねえんだな、お前」
「そういうお前は、またおれを助けてくれたんだな。……おれはもう、夏目家の人間じゃねえのに」
「別に、助けようなんて思ってもいねえよ。身体が勝手に動いただけだ」
しかし、状況が状況だけに、会話せざるを得ない二人はぎこちなく会話をする。目をそらし、ぶっきらぼうに振る舞う世助。いたたまれなさを感じている彼を刺激しないよう努める唯助。まるで目隠ししながらお互いを杖で探り合うような会話だ。
「でも、世助。なんでお前、おれのところに駆けつけて……」
「たまたまだ」
世助は目を合わせないまま、やや食い気味に答える。
「おかしいと思ったよ。おれは金魚屋なんて行ってねえのに、すれ違ったガキどもに下手くそだのへなちょこだの馬鹿にされた」
「うっ」
「そんで、金魚屋の前に通りかかって『七本さんとはぐれたのか?』って店のおやじに聞かれて気づいた。七本って、お前を雇ってる貸本屋のおっさんのことだろ」
「あ……知ってたんだ、旦那のこと」
「お前が夏目家と縁切るって話聞かされた時、名前だけ父上から聞いてた。で、適当にふらふらしてたら、なんかヤバそうなデカブツに食われかけてるお前を見つけたわけ」
世助は目をずっと合わせない。唯助が自分を嫌がらないのがさらにいたたまれないらしく、唯助から目をそらしたままだ。
「また変なもんに巻き込まれやがって。昔っから気をつけろっつってただろうが。おれが駆けつけてなかったら、今頃粉々に噛み砕かれてたぞ」
「うっ、ごめん……」
ツンケンしてるなぁと唯助は思いつつ、それには触れずにただ世助の乱暴な言葉を受け入れる。いらない刺激してしまっては、せっかく会えた兄との会話が打ち切られてしまうかもしれないと、刺々しい世助の言葉を受け入れていた。
「にしてもよ、ここはなんだ? あの馬鹿でかい口した化け物の腹の中には違いねえけどよ」
歩く。同じ歩幅で。同じ速度で。寸分違わず、双子は闇を歩く。二人に見えているのはお互いの姿のみだ。しかしそれも間近にいるから。一歩でも歩みがズレれば見失ってしまいそうな闇の中で、双子ははぐれないように手を繋いでいた。ちなみに、先にそれを提案したのは唯助である。
「けど、腹の中ってわりには妙だよな。外を歩いてるみてえだ。踵を落としてみても、うんともすんとも言わねえ。だだっ広くて、いくら歩いても壁に当たらねえ。一体全体どうなってやがんだ」
世助は度々、自分たちの足と接する地面の感触を探っているが、つま先でつついても踵で蹴っても変わらない。たまに砂利があるくらいの踏み固められた地面のようだが、そもそもこの暗闇で視界がはっきりしないので、本当に地面なのかも判然としない。
「さあ。でも、もしかしたら…これも、禁書の【毒】の仕業かもしんねえ」
「禁書の【毒】? なんだそれ」
これこれこうこうかくかくしかじか。唯助は三八に授けられた教えをそのまま世助に伝える。
「ふーん。人に危害を加える本ねえ。人間の生み出した本が人間を襲う、なんてどんな皮肉だ」
確かに。唯助はそれに頷く。なあ、と世助が唯助に投げかける。
「お前がたまに襲われてたのも、それだったんじゃねえのか」
実は唯助もそうだったのではないかと思っていたところである。
そう、六月に遭遇した禁書の毒・紫蔓に狙われたことといい、今回のことといい――唯助が異形に襲われることは、実はそう珍しいことではなかった。唯助の身のまわりでは、度々妙なことが起きていた。唯助のお化け嫌いはこれのせいである。
そして、唯助を襲う異形を退治していたのは、決まって世助であった。初めて出くわした時は、まさかお化けに拳での物理攻撃が通じるとは思わなかったが。
「おれを襲ってたのがもし本当に禁書の毒だったら、こうやって姿を似せて分散させなきゃ死んでたかもしれねえな」
彼らは双子であるから、自己同一性が生まれる前段階の時点では姿も性格も似ていて瓜二つだったが、自己同一性が生まれたこの歳になっても瓜二つなのは、あまりに不自然だ。いくら双子といえども違う人間。当然、性格にも微妙な違いが出てくるし、好みも異なる。双子だから姿も中身も全く同じ、というのは不自然なのであり、差異があることこそが自然なのだ。
不自然に似ているのは、彼らが意図的に似せていたからだ。理由のひとつは、唯助の身を守るために、二人が一緒になるよう揃えたから。唯助が狙われる確率を少しでも下げ、世助が間違って狙われる確率を少しでも上げるため。双子の彼らにしかとれない防御術だった。
「……でも待てよ? 禁書の毒には、禁書の毒でしか攻撃ができないって、旦那が言ってた。普通の攻撃は通用しないって、知り合いの帝国司書さんも言ってたし」
「は? んなバカな。おれは普通に触れるし、ぶん殴れるぜ。お前も殴れるだろ?」
「試したことねえし、試したくもねえよ。戦う以前におっかねえもん」
「弱腰だなぁ」
「世助が血気盛んなんだよ。普通、お化けだと思ったら咄嗟に殴れねえだろ」
「通用するって分かってたら反射で殴るから、お前の殴れねえって感覚の方がむしろ分かんねえ」
「喧嘩屋かよ」
「うっせえヘタレ」
二人になると決まって始まる軽口。両者の明らかな違いを孕んだ軽口。実は喧嘩っ早い世助と、実は穏健派の唯助による、兄弟ならではの軽口である。
「多分、旦那に聞けば分かるのかな」
「あの妙ちきりんなおっさんか? 胡散臭くねえか?」
「妙ちきりんなのも胡散臭いのもそうだけど、あの人はそれ以上に色んなことを知ってるよ。本のことにかけては何でも。帝国司書さんのお墨付きだぜ」
「ふーん」
「変な人だけど、基本的にはいい人だし。なんでも知ってる先生みたいな感じ」
「ふーん」
「姐さんもすごくいい人でさ、飯もめちゃくちゃうめえんだ」
「……ふーん」
最初の居心地悪さが少し和らいでいた世助は、ここでまたばつが悪そうな顔をする。
「すげえ仲が良くてさ、毎日暑っ苦しいくらいベタベタしてんの。おれがいるのにお構いなし」
「……そう」
胸が温まるまま、嬉々として現状を語る唯助に対し――世助の表情は深く、より深く沈んでいた。唯助がそんな世助に気づかないなか、世助はふう、とひとつため息を漏らす。
「楽しそうだな。お前」
「まあな。実際、ほんとに楽しい。師範の稽古は…正直つまんなかったけど、旦那に教わるのは結構すきだぜ」
「…………ふーん」
沈み、沈んで。ようやく気づいた唯助が怪訝そうな顔つきになるのとちょうど入れ替わるようにして――世助は、ここに来てようやく心から笑った。
「よかったな、幸せになれて」
――心からの、自嘲であった。
この場合は、さすが双子というべきか。さすが長く一緒にいた仲というべきか。いずれにしてもどちらにしても、唯助には世助の笑顔が『自嘲』だとすぐに分かった。
そして思い出した。とびきりの緊急事態が続いていたせいですっかり頭から吹っ飛んでいた、世助を探していた理由。
「……世助? お前、なにが――」
唯助はそれを問おうとしたが、折の悪いことに、先は阻まれた。
「お兄ちゃんたち、新入り?」
いつの間にか開けていた視界の数歩先に、二人を見つめる子供がいた。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
387
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。