お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説
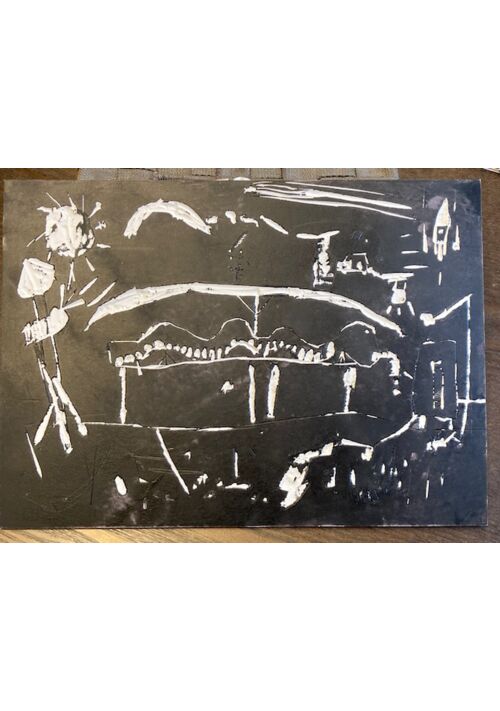
ミズルチと〈竜骨の化石〉
珠邑ミト
児童書・童話
カイトは家族とバラバラに暮らしている〈音読みの一族〉という〈族《うから》〉の少年。彼の一族は、数多ある〈族〉から魂の〈音〉を「読み」、なんの〈族〉か「読みわける」。彼は飛びぬけて「読め」る少年だ。十歳のある日、その力でイトミミズの姿をしている〈族〉を見つけ保護する。ばあちゃんによると、その子は〈出世ミミズ族〉という〈族《うから》〉で、四年かけてミミズから蛇、竜、人と進化し〈竜の一族〉になるという。カイトはこの子にミズルチと名づけ育てることになり……。
一方、世間では怨墨《えんぼく》と呼ばれる、人の負の感情から生まれる墨の化物が活発化していた。これは人に憑りつき操る。これを浄化する墨狩《すみが》りという存在がある。
ミズルチを保護してから三年半後、ミズルチは竜になり、カイトとミズルチは怨墨に知人が憑りつかれたところに遭遇する。これを墨狩りだったばあちゃんと、担任の湯葉《ゆば》先生が狩るのを見て怨墨を知ることに。
カイトとミズルチのルーツをたどる冒険がはじまる。

星読みの少女――ようこそ、ブルースターへ!
東山未怜
児童書・童話
ユーリ、11歳の誕生日の夜。
ミミズクがはこんできた、科学者だった亡き祖母からの手紙には「ミモザの丘のブルースターの、カルシャという星読みをたずねなさい」とある。
翌日、ミモザの丘を目ざしたユーリ。
ブルースターという占いカフェで最初にユーリが出会ったのは、カルシャの妹のサーシャだった。
サーシャはユーリに冷たく応対する。姉のカルシャを取られてしまったような寂しさからだった。
カルシャはユーリを快く迎え、星読みにしか読み解けない『星読みの書』を見せてくれる。
しかし、ユーリにはちゃんと読める。
ユーリは星読みとして、生まれついたのだった。
『星読みの書』をもとに、星を見るときの基本を教わるユーリ。
ある日、サーシャにせがまれ、『星読みの書』を勝手に開いてしまった。
中からは小さな星が現れ、ガーデンへと飛びだしてしまい……。
ひとりの少女と、彼女をとりまく人たちとの、星と愛情のストーリー。

"かくれんぼ"は、やっちゃダメ
みこと。
児童書・童話
"お城山"での"かくれんぼ"は、絶対禁止。昔、ご先祖さまが閉じ込めた"悪いヤツ"を、間違って見つけてしまったら大変だから。なのに、集まったイトコたちと"かくれんぼ"を始めることになってしまったミツキは...。
前半ホラー、後半ファンタジー。子どもにも読めるよう仕立てました。

あいつは悪魔王子!~悪魔王子召喚!?追いかけ鬼をやっつけろ!~
とらんぽりんまる
児童書・童話
【第15回絵本・児童書大賞、奨励賞受賞】ありがとうございました!
主人公の光は、小学校五年生の女の子。
光は魔術や不思議な事が大好きで友達と魔術クラブを作って活動していたが、ある日メンバーの三人がクラブをやめると言い出した。
その日はちょうど、召喚魔法をするのに一番の日だったのに!
一人で裏山に登り、光は召喚魔法を発動!
でも、なんにも出て来ない……その時、子ども達の間で噂になってる『追いかけ鬼』に襲われた!
それを助けてくれたのは、まさかの悪魔王子!?
人間界へ遊びに来たという悪魔王子は、人間のフリをして光の家から小学校へ!?
追いかけ鬼に命を狙われた光はどうなる!?
※稚拙ながら挿絵あり〼

【もふもふ手芸部】あみぐるみ作ってみる、だけのはずが勇者ってなんなの!?
釈 余白(しやく)
児童書・童話
網浜ナオは勉強もスポーツも中の下で無難にこなす平凡な少年だ。今年はいよいよ最高学年になったのだが過去5年間で100点を取ったことも運動会で1等を取ったこともない。もちろん習字や美術で賞をもらったこともなかった。
しかしそんなナオでも一つだけ特技を持っていた。それは編み物、それもあみぐるみを作らせたらおそらく学校で一番、もちろん家庭科の先生よりもうまく作れることだった。友達がいないわけではないが、人に合わせるのが苦手なナオにとっては一人でできる趣味としてもいい気晴らしになっていた。
そんなナオがあみぐるみのメイキング動画を動画サイトへ投稿したり動画配信を始めたりしているうちに奇妙な場所へ迷い込んだ夢を見る。それは現実とは思えないが夢と言うには不思議な感覚で、沢山のぬいぐるみが暮らす『もふもふの国』という場所だった。
そのもふもふの国で、元同級生の丸川亜矢と出会いもふもふの国が滅亡の危機にあると聞かされる。実はその国の王女だと言う亜美の願いにより、もふもふの国を救うべく、ナオは立ち上がった。

ヒョイラレ
如月芳美
児童書・童話
中学に入って関東デビューを果たした俺は、急いで帰宅しようとして階段で足を滑らせる。
階段から落下した俺が目を覚ますと、しましまのモフモフになっている!
しかも生きて歩いてる『俺』を目の当たりにすることに。
その『俺』はとんでもなく困り果てていて……。
どうやら転生した奴が俺の体を使ってる!?

【完】ことうの怪物いっか ~夏休みに親子で漂流したのは怪物島!? 吸血鬼と人造人間に育てられた女の子を救出せよ! ~
丹斗大巴
児童書・童話
どきどきヒヤヒヤの夏休み!小学生とその両親が流れ着いたのは、モンスターの住む孤島!?
*☆* *☆* *☆* *☆* *☆* *☆* *☆*
夏休み、家族で出掛けた先でクルーザーが転覆し、漂流した青山親子の3人。とある島に流れ着くと、古風で顔色の悪い外国人と、大怪我を負ったという気味の悪い執事、そしてあどけない少女が住んでいた。なんと、彼らの正体は吸血鬼と、その吸血鬼に作られた人造人間! 人間の少女を救い出し、無事に島から脱出できるのか……!?
*☆* *☆* *☆* *☆* *☆* *☆* *☆*
家族のきずなと種を超えた友情の物語。

極甘独占欲持ち王子様は、優しくて甘すぎて。
猫菜こん
児童書・童話
私は人より目立たずに、ひっそりと生きていたい。
だから大きな伊達眼鏡で、毎日を静かに過ごしていたのに――……。
「それじゃあこの子は、俺がもらうよ。」
優しく引き寄せられ、“王子様”の腕の中に閉じ込められ。
……これは一体どういう状況なんですか!?
静かな場所が好きで大人しめな地味子ちゃん
できるだけ目立たないように過ごしたい
湖宮結衣(こみやゆい)
×
文武両道な学園の王子様
実は、好きな子を誰よりも独り占めしたがり……?
氷堂秦斗(ひょうどうかなと)
最初は【仮】のはずだった。
「結衣さん……って呼んでもいい?
だから、俺のことも名前で呼んでほしいな。」
「さっきので嫉妬したから、ちょっとだけ抱きしめられてて。」
「俺は前から結衣さんのことが好きだったし、
今もどうしようもないくらい好きなんだ。」
……でもいつの間にか、どうしようもないくらい溺れていた。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















