お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説
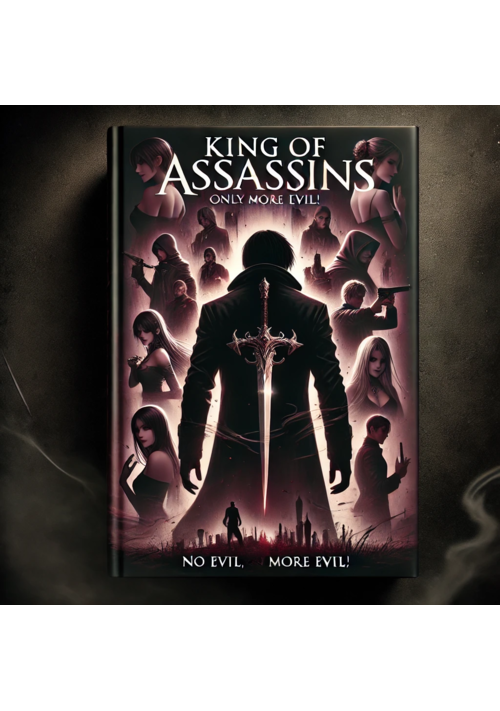

幻影のアリア
葉羽
ミステリー
天才高校生探偵の神藤葉羽は、幼馴染の望月彩由美と共に、とある古時計のある屋敷を訪れる。その屋敷では、不可解な事件が頻発しており、葉羽は事件の真相を解き明かすべく、推理を開始する。しかし、屋敷には奇妙な力が渦巻いており、葉羽は次第に現実と幻想の境目が曖昧になっていく。果たして、葉羽は事件の謎を解き明かし、屋敷から無事に脱出できるのか?

【毎日20時更新】アンメリー・オデッセイ
ユーレカ書房
ミステリー
からくり職人のドルトン氏が、何者かに殺害された。ドルトン氏の弟子のエドワードは、親方が生前大切にしていた本棚からとある本を見つける。表紙を宝石で飾り立てて中は手書きという、なにやらいわくありげなその本には、著名な作家アンソニー・ティリパットがドルトン氏とエドワードの父に宛てた中書きが記されていた。
【時と歯車の誠実な友、ウィリアム・ドルトンとアルフレッド・コーディに。 A・T】
なぜこんな本が店に置いてあったのか? 不思議に思うエドワードだったが、彼はすでにおかしな本とふたつの時計台を巡る危険な陰謀と冒険に巻き込まれていた……。
【登場人物】
エドワード・コーディ・・・・からくり職人見習い。十五歳。両親はすでに亡く、親方のドルトン氏とともに暮らしていた。ドルトン氏の死と不思議な本との関わりを探るうちに、とある陰謀の渦中に巻き込まれて町を出ることに。
ドルトン氏・・・・・・・・・エドワードの親方。優れた職人だったが、職人組合の会合に出かけた帰りに何者かによって射殺されてしまう。
マードック船長・・・・・・・商船〈アンメリー号〉の船長。町から逃げ出したエドワードを船にかくまい、船員として雇う。
アーシア・リンドローブ・・・マードック船長の親戚の少女。古書店を開くという夢を持っており、謎の本を持て余していたエドワードを助ける。
アンソニー・ティリパット・・著名な作家。エドワードが見つけた『セオとブラン・ダムのおはなし』の作者。実は、地方領主を務めてきたレイクフィールド家の元当主。故人。
クレイハー氏・・・・・・・・ティリパット氏の甥。とある目的のため、『セオとブラン・ダムのおはなし』を探している。

学園ミステリ~桐木純架
よなぷー
ミステリー
・絶世の美貌で探偵を自称する高校生、桐木純架。しかし彼は重度の奇行癖の持ち主だった! 相棒・朱雀楼路は彼に振り回されつつ毎日を過ごす。
そんな二人の前に立ち塞がる数々の謎。
血の涙を流す肖像画、何者かに折られるチョーク、喫茶店で奇怪な行動を示す老人……。
新感覚学園ミステリ風コメディ、ここに開幕。
『小説家になろう』でも公開されています――が、検索除外設定です。


孤島の洋館と死者の証言
葉羽
ミステリー
高校2年生の神藤葉羽は、学年トップの成績を誇る天才だが、恋愛には奥手な少年。彼の平穏な日常は、幼馴染の望月彩由美と過ごす時間によって色付けされていた。しかし、ある日、彼が大好きな推理小説のイベントに参加するため、二人は不気味な孤島にある古びた洋館に向かうことになる。
その洋館で、参加者の一人が不審死を遂げ、事件は急速に混沌と化す。葉羽は推理の腕を振るい、彩由美と共に事件の真相を追い求めるが、彼らは次第に精神的な恐怖に巻き込まれていく。死者の霊が語る過去の真実、参加者たちの隠された秘密、そして自らの心の中に潜む恐怖。果たして彼らは、事件の謎を解き明かし、無事にこの恐ろしい洋館から脱出できるのか?

友よ、お前は何故死んだのか?
河内三比呂
ミステリー
「僕は、近いうちに死ぬかもしれない」
幼い頃からの悪友であり親友である久川洋壱(くがわよういち)から突如告げられた不穏な言葉に、私立探偵を営む進藤識(しんどうしき)は困惑し嫌な予感を覚えつつもつい流してしまう。
だが……しばらく経った頃、仕事終わりの識のもとへ連絡が入る。
それは洋壱の死の報せであった。
朝倉康平(あさくらこうへい)刑事から事情を訊かれた識はそこで洋壱の死が不可解である事、そして自分宛の手紙が発見された事を伝えられる。
悲しみの最中、朝倉から提案をされる。
──それは、捜査協力の要請。
ただの民間人である自分に何ができるのか?悩みながらも承諾した識は、朝倉とともに洋壱の死の真相を探る事になる。
──果たして、洋壱の死の真相とは一体……?

【完結】湖に沈む怪~それは戦国時代からの贈り物
握夢(グーム)
ミステリー
諏訪湖の中央に、巨大な石箱が沈んでいることが発見された。その石箱の蓋には武田家の紋章が。
―――これは武田信玄の石櫃なのか?
石箱を引き上げたその夜に大惨劇が起きる。逃げ場のない得体のしれないものとの戦い。
頭脳派の時貞と、肉体派の源次と龍信が立ち向かう。
しかし、強靭な外皮をもつ不死身の悪魔の圧倒的な強さの前に、次々と倒されていく……。
それを目の当たりにして、ついに美人レポーターの碧がキレた!!
___________________________________________________
この物語は、以下の4部構成で、第1章の退屈なほどの『静』で始まり、第3章からは怒涛の『動』へと移ります。
映画やアニメが好きなので、情景や場面切り替えなどの映像を強く意識して創りました。
読んでいる方に、その場面の光景などが、多少でも頭の中に浮かんでもらえたら幸いです^^
■第一章 出逢い
『第1話 激情の眠れぬ女騎士』~『第5話 どうやって石箱を湖に沈めた!?』
■第二章 遭遇
『第6話 信長の鬼伝説と信玄死の謎』~『第8話 過去から来た未来刺客?』
■第三章 長い戦い
『第9話 貴公子の初陣』~『第15話 遅れて来た道化師』
■第四章 祭りの後に
『第16話 信玄の石棺だったのか!?』~『第19話 仲間たちの笑顔に』
※ごゆっくりお楽しみください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















