お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

淫らな蜜に狂わされ
歌龍吟伶
恋愛
普段と変わらない日々は思わぬ形で終わりを迎える…突然の出会い、そして体も心も開かれた少女の人生録。
全体的に性的表現・性行為あり。
他所で知人限定公開していましたが、こちらに移しました。
全3話完結済みです。
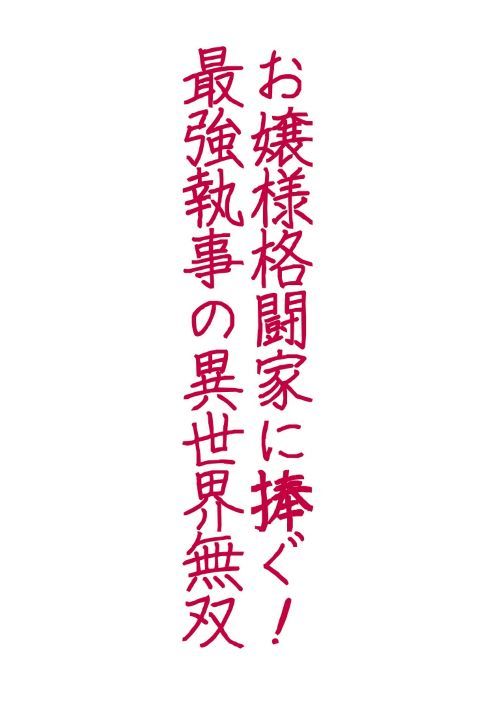
お嬢様格闘家に捧ぐ!最強執事の異世界無双
天宮暁
ファンタジー
霧ヶ峰敬斗(きりがみねけいと)は、名家の令嬢・鳳凰院紅華(ほうおういんべにか)に仕える執事の少年である。
紅華の趣味は格闘技。その実力は「趣味」の枠に収まるものではなく、若くして道場破りを繰り返し、高名な武術家をも破ってきた。
そんな紅華が、敬斗の読んでいた異世界転生小説を見て言った。
「異世界ねぇ……わたしも行ってみたいわ。こっちの世界より強い奴がいそうじゃない!」
そんな紅華の言葉を、執事長が拾い、冗談交じりに話を持ち出す。
「古より当家に伝わる『隔世(へだてよ)の門』というものがございます。その門は『波留解(はるげ)』なる異世界に通じているとかいないとか……」
「なにそれ、おもしろそう!」
冷やかし半分で門を見にいく紅華と敬斗。だが、その伝承はまぎれもなく事実だった。門をくぐり抜けた先には、未知の世界が広がっていた――!
興奮する紅華とは対照的に、敬斗は秘かに心配する。魔物が跋扈し、魔法が使える未知の世界。こんな世界で、お嬢様をどうやって守っていけばいいのだろうか――!?
やがて敬斗は、ひとつの結論へとたどり着く。
「僕が万難を排した上で、お嬢様が気持ちよく戦えるよう『演出』すればいいじゃないか」
と。
かくして、「超絶強いくせに心配性」「鉄橋を叩き割ってから自前の橋をかけ直す」最強執事が、全力でお嬢様の無双を「演出」する――ッ!
そう。
これは、異世界に紛れ込んだお嬢様格闘家が無双しまくる物語――
……を「演出」する、彼女の「執事」の物語であるッッ!

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします
文野多咲
恋愛
秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。
夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。
エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。
「ゲルハルトさま、愛しています」
ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。
「エレーヌ、俺はあなたが憎い」
エレーヌは凍り付いた。

【第一部】異世界を先に生きる ~先輩転移者先生との異世界生活記!~
月ノ輪
ファンタジー
―私達と共に来てくれないか? 帰る方法も必ず見つけ出そう。
平凡な中学生の雪谷さくらは、夏休みに入った帰り道に異世界に転移してしまう。
着いた先は見慣れない景色に囲まれたエルフや魔族達が暮らすファンタジーの世界。
言葉も通じず困り果てていたさくらの元に現れたのは、20年前に同じ世界からやってきた、そして今は『学園』で先生をしている男性“竜崎清人”だった。
さくら、竜崎、そして竜崎に憑りついている謎の霊体ニアロン。彼らを取り巻く教師陣や生徒達をも巻き込んだ異世界を巡る波瀾万丈な学園生活の幕が上がる!
※【第二部】、ゆっくりながら投稿開始しました。宜しければ!
【第二部URL】《https://www.alphapolis.co.jp/novel/333629063/270508092》
※他各サイトでも重複投稿をさせて頂いております。

チート幼女とSSSランク冒険者
紅 蓮也
ファンタジー
【更新休止中】
三十歳の誕生日に通り魔に刺され人生を終えた小鳥遊葵が
過去にも失敗しまくりの神様から異世界転生を頼まれる。
神様は自分が長々と語っていたからなのに、ある程度は魔法が使える体にしとく、無限収納もあげるといい、時間があまり無いからさっさと転生しちゃおっかと言いだし、転生のため光に包まれ意識が無くなる直前、神様から不安を感じさせる言葉が聞こえたが、どうする事もできない私はそのまま転生された。
目を開けると日本人の男女の顔があった。
転生から四年がたったある日、神様が現れ、異世界じゃなくて地球に転生させちゃったと・・・
他の人を新たに異世界に転生させるのは無理だからと本来行くはずだった異世界に転移することに・・・
転移するとそこは森の中でした。見たこともない魔獣に襲われているところを冒険者に助けられる。
そして転移により家族がいない葵は、冒険者になり助けてくれた冒険者たちと冒険したり、しなかったりする物語
※この作品は小説家になろう様、カクヨム様、ノベルバ様、エブリスタ様でも掲載しています。

転生したら貴族の息子の友人A(庶民)になりました。
襲
ファンタジー
〈あらすじ〉
信号無視で突っ込んできたトラックに轢かれそうになった子どもを助けて代わりに轢かれた俺。
目が覚めると、そこは異世界!?
あぁ、よくあるやつか。
食堂兼居酒屋を営む両親の元に転生した俺は、庶民なのに、領主の息子、つまりは貴族の坊ちゃんと関わることに……
面倒ごとは御免なんだが。
魔力量“だけ”チートな主人公が、店を手伝いながら、学校で学びながら、冒険もしながら、領主の息子をからかいつつ(オイ)、のんびり(できたらいいな)ライフを満喫するお話。
誤字脱字の訂正、感想、などなど、お待ちしております。
やんわり決まってるけど、大体行き当たりばったりです。

辺境伯家ののんびり発明家 ~異世界でマイペースに魔道具開発を楽しむ日々~
雪月 夜狐
ファンタジー
壮年まで生きた前世の記憶を持ちながら、気がつくと辺境伯家の三男坊として5歳の姿で異世界に転生していたエルヴィン。彼はもともと物作りが大好きな性格で、前世の知識とこの世界の魔道具技術を組み合わせて、次々とユニークな発明を生み出していく。
辺境の地で、家族や使用人たちに役立つ便利な道具や、妹のための可愛いおもちゃ、さらには人々の生活を豊かにする新しい魔道具を作り上げていくエルヴィン。やがてその才能は周囲の人々にも認められ、彼は王都や商会での取引を通じて新しい人々と出会い、仲間とともに成長していく。
しかし、彼の心にはただの「発明家」以上の夢があった。この世界で、誰も見たことがないような道具を作り、貴族としての責任を果たしながら、人々に笑顔と便利さを届けたい——そんな野望が、彼を新たな冒険へと誘う。
他作品の詳細はこちら:
『転生特典:錬金術師スキルを習得しました!』
【https://www.alphapolis.co.jp/novel/297545791/906915890】
『テイマーのんびり生活!スライムと始めるVRMMOスローライフ』 【https://www.alphapolis.co.jp/novel/297545791/515916186】
『ゆるり冒険VR日和 ~のんびり異世界と現実のあいだで~』
【https://www.alphapolis.co.jp/novel/297545791/166917524】

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















